自治体の広報とは?住民に届く効果的な情報発信と戦略的PR実践ガイド

共感を生む戦略的広報の重要性
単なる情報伝達ではなく、住民の関心・共感を引き出す「戦略的な広報」が求められている。
ターゲットと目的の明確化
誰に・何を伝えるかを明確にし、ストーリー性や発信のタイミングを工夫することが成功の鍵である。
広報は信頼と施策推進の基盤
効果的な広報は施策への理解を促進し、自治体への信頼を高める。自治体経営の中核を担う分野となりつつある。
自治体の広報活動は、今大きな転換期を迎えています。かつては広報誌を中心とした一方通行の情報発信が主流でしたが、現代ではSNSや動画コンテンツなど様々なデジタルメディアを活用し、市民との双方向コミュニケーションを重視した「戦略的広報」へと進化しています。効果的な広報活動は、地域住民に必要な情報を届けるだけでなく、住民の地域参画意識を高め、地域外にも魅力を発信することで移住促進や観光振興、企業誘致にもつながる重要な役割を担っています。
しかし多くの自治体では、限られた予算・人材・時間の中で、どのように効果的な広報活動を展開すべきか課題を抱えています。また、広報の目標が不明確だったり、住民のニーズを適切に把握できていなかったり、特定のメディアに偏った情報発信になっているといった問題も少なくありません。
この記事では、自治体広報の定義や目的から、効果的な広報手段の選択方法、住民ニーズの把握、デジタル時代の戦略的広報のあり方、AI活用の可能性まで幅広く解説します。さらに、全国の自治体による広報の成功事例を紹介し、あなたの自治体でも取り入れられる実践的なポイントをご紹介します。広報担当者の方だけでなく、自治体運営に関わるすべての方に役立つ内容となっています。

自治体広報の定義と重要性

自治体における広報活動は、単なる情報提供にとどまらない重要な役割を担っています。ここでは、広報の基本的な定義から自治体特有の役割、そして現代における広報の重要性について解説します。
広報の定義と自治体広報の役割
広報とは「Public Relations(PR)」の和訳で、組織と公衆(ステークホルダー)の間に相互理解と信頼関係を構築するための活動を指します。自治体における広報は、行政の方針や施策、サービスなどの情報を市民に伝えるとともに、市民からの声を聴き、行政に反映させる双方向のコミュニケーション活動です。
自治体広報の主な役割としては、以下のような点が挙げられます:
- 行政情報の周知と透明性の確保
- 住民サービスの利用促進
- 地域の魅力やブランド力の向上
- 市民参加・協働の促進
- 危機管理時の迅速な情報提供
特に自治体は、高齢者から若年層まで幅広い年代、多様なバックグラウンドを持つ住民に対して適切な情報を届ける必要があります。それぞれの属性やニーズに合わせた情報発信が求められる点が、企業などの広報活動とは異なる特徴といえるでしょう。
まちづくりに欠かせない自治体の広報
自治体がどんなに優れたまちづくり施策を実施していても、その取り組みが住民に理解されず、参加や協力が得られなければ、十分な効果は期待できません。広報活動は、行政と住民をつなぎ、協働のまちづくりを実現するための重要な架け橋となります。
具体的には、以下のような点でまちづくりに貢献します:
- 住民のまちづくりへの参画意識を高める
- 地域の課題や政策について理解を促進する
- 行政サービスの適切な活用を支援する
- 地域のアイデンティティや帰属意識を醸成する
- 地域外からの関心を集め、交流人口や移住者の増加につなげる
例えば、環境保全や防災などの取り組みでは、住民の理解と協力が不可欠です。適切な広報活動によって住民の意識を高め、主体的な参加を促すことができます。また、地域の魅力を効果的に発信することで、観光振興や企業誘致、移住促進など、地域の活性化にもつながります。
広報から「広聴」へ:双方向コミュニケーションの時代
従来の自治体広報は、行政からの一方的な情報発信(お知らせ広報)が中心でした。しかし、SNSなどの普及により、情報の受け手だった市民が情報発信者となる時代へと変化しています。現代の自治体広報には、情報を「伝える」だけでなく、市民の声を「聴く」姿勢が不可欠です。
このような「広報」から「広聴」への転換には、以下のようなメリットがあります:
- 住民ニーズの的確な把握による効果的な政策立案
- 住民との信頼関係の構築と行政への理解促進
- 地域課題の早期発見と迅速な対応
- 住民の満足度向上と地域への愛着形成
- 行政サービスの質の向上と効率化
例えば、SNSのコメント機能やアンケート機能を活用して住民の声を集めたり、ワークショップやタウンミーティングを開催して直接対話の機会を設けたりする自治体が増えています。こうした双方向コミュニケーションを通じて、より住民のニーズに合った行政サービスの提供や政策の立案が可能になります。
自治体の広報担当者には、情報を発信するスキルだけでなく、住民の声に耳を傾け、その声を行政運営に反映させるという「広聴」の視点を持った活動が求められています。双方向のコミュニケーションを重視した広報活動は、住民と行政の協働によるまちづくりの基盤となり、地域の持続的な発展に貢献するでしょう。
自治体広報の3つの目的
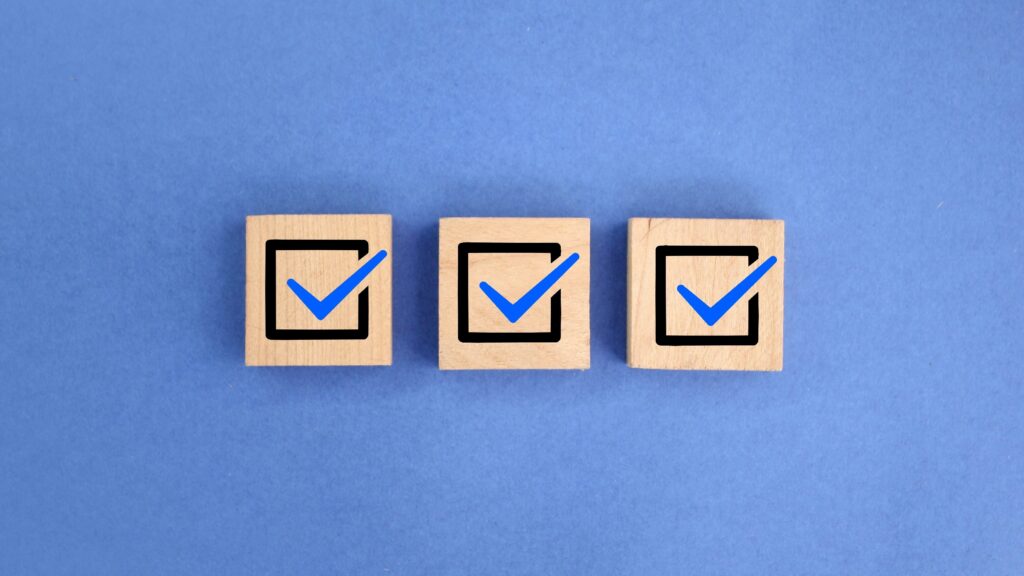
自治体が広報活動を行う目的は大きく分けて3つあります。それぞれの目的を理解し、バランスよく取り組むことで、効果的な広報活動につながります。
地域住民への正確な情報提供
自治体広報の最も基本的な目的は、地域住民に必要な情報を正確かつタイムリーに提供することです。住民の生活や安全に直結する情報は、確実に届けることが求められます。
住民が特に関心を持っている情報には、以下のようなものがあります:
- 健康・福祉・医療介護に関する情報:健康診断、予防接種、介護サービス、福祉制度など
- 防犯・防災に関する情報:災害時の避難場所、犯罪発生状況、防犯対策など
- 環境・ごみ・リサイクルに関する情報:ごみの分別方法、収集日、環境保全活動など
- 子育て・教育に関する情報:保育園・学校情報、子育て支援サービス、教育イベントなど
- 各種手続き・届出に関する情報:税金、戸籍、住民票などの手続き方法や期限など
これらの情報は、住民の日常生活や福祉に直結するため、わかりやすく、アクセスしやすい形で提供することが重要です。例えば、高齢者向けには紙媒体を重視し、若年層にはSNSや動画を活用するなど、情報の受け手に合わせた媒体選択が効果的です。
また、情報の信頼性も重要な要素です。特に災害時や緊急時には、正確な情報を迅速に提供することが住民の安全確保につながります。日頃から信頼性の高い情報源として認識されるよう、正確な情報発信を心がけることが大切です。
住民の地域参画意識の醸成
自治体広報の2つ目の目的は、住民の地域への関心を高め、まちづくりや政策への参画意識を醸成することです。地域の課題解決や発展には、住民の理解と協力が不可欠であり、広報はその基盤を作る役割を担っています。
住民参画を促進するための広報活動には、以下のようなアプローチがあります:
- 地域の課題や政策を分かりやすく伝える:専門用語を避け、図表や事例を用いた説明
- 住民が参加できる機会を積極的に紹介する:ワークショップ、パブリックコメント、ボランティア活動など
- 住民の活動や意見を取り上げる:市民インタビュー、活動報告、意見投稿の掲載など
- 地域の魅力や誇りを伝える:歴史、文化、自然環境、特産品など地域資源の紹介
- 対話の場を創出する:SNSでの意見交換、タウンミーティング、意見交換会の開催など
これらの活動を通じて、住民が「自分たちのまち」という当事者意識を持ち、地域の課題解決や魅力向上に主体的に関わるようになることが期待できます。特に近年では、「シビックテック」と呼ばれる市民と技術を活用した問題解決の取り組みも広がっており、こうした活動を広報で積極的に取り上げることも有効です。
住民参画を促進する広報では、一方的な情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションを重視することがポイントです。住民の声に耳を傾け、それを政策に反映していく姿勢を示すことで、住民の信頼と参画意欲を高めることができます。
地域外への魅力発信(移住・観光・企業誘致)
3つ目の目的は、地域外の人々や企業に対して地域の魅力をアピールし、移住促進、観光振興、企業誘致につなげることです。人口減少や地域経済の活性化が課題となる中、地域の外に向けた広報活動の重要性はますます高まっています。
地域外に向けた効果的な広報のポイントには、以下のようなものがあります:
- 地域の独自性や優位性を明確に打ち出す:他の地域にはない魅力や強みを強調
- ターゲットを明確にした情報発信:移住検討者、観光客、企業など対象ごとにカスタマイズ
- ビジュアルを重視したコンテンツ制作:写真、動画など視覚的に魅力を伝える素材の活用
- 実体験や口コミを活用する:移住者インタビュー、観光客の感想、進出企業の声など
- オンライン・オフラインの複合的なアプローチ:Webサイト、SNS、イベント出展など多様な接点の創出
例えば、移住促進のためには、自然環境や子育て環境の良さ、住宅取得支援制度などの情報に加え、実際に移住した人々の声や日常の様子を紹介することで具体的なイメージを持ってもらうことが効果的です。観光振興では、地域の観光資源や特産品、イベントなどの情報を魅力的な写真や動画とともに発信し、旅行者の興味を引くことが重要です。
企業誘致においては、交通アクセスの良さ、用地の状況、優遇制度などの基本情報に加え、すでに進出している企業の声や地域の産業構造、人材の特徴などを提供することで、進出検討企業の不安を解消し、メリットを具体的に伝えることができます。
地域外への広報では、インターネットの活用が特に重要です。オンライン上の情報は地理的制約なく拡散し、潜在的な移住者や観光客、進出企業に効率的にリーチすることができます。また、情報検索の入り口となるSEO対策も忘れてはならない要素です。
これら3つの目的はいずれも重要であり、バランスよく取り組むことで自治体広報の効果を最大化することができます。住民への適切な情報提供という基本的な役割を果たしながら、住民参画の促進と地域外への魅力発信にも力を入れることで、地域の持続的な発展につながる広報活動が実現します。
自治体における広報の手段と特徴
自治体が住民や地域外の人々に情報を届けるための広報手段は多様化しています。それぞれのメディアの特徴を理解し、目的に応じて適切に使い分けることが効果的な広報の鍵となります。
広報誌:基本にして今なお効果的な情報媒体
広報誌は、自治体広報の中でも最も歴史が長く、今なお重要な役割を果たしています。全戸配布や新聞折り込みにより、インターネットを利用しない高齢者層にも確実に情報を届けられる点が最大の強みです。
広報誌の主な特徴:
- 行政情報を網羅的かつ体系的に伝えることができる
- 情報の信頼性が高く、公式記録としての役割も果たす
- 保存性があり、後から参照することができる
- インターネット環境のない住民にも情報が届く
- デザインや紙質にこだわることで、読者の関心を高められる
埼玉県三芳町の『広報みよし』は、タイトルにローマ字表記を採用し若者にも親しみやすいデザインにするなど、従来の堅いイメージを払拭する工夫により「全国広報コンクール」で内閣総理大臣賞を受賞した例があります。
広報誌の課題としては、発行頻度が限られること(多くは月1回程度)、情報の即時性に欠けること、制作コストがかかることなどが挙げられます。また、若年層の活字離れにより読まれなくなる傾向もあります。こうした課題を克服するために、紙面のビジュアル化や特集記事の充実など、読者の関心を引くための工夫が求められています。
Webサイト:地域内外に届く情報プラットフォーム
自治体のWebサイトは、地域住民だけでなく地域外の人々にも情報を提供できる重要なプラットフォームです。24時間アクセス可能で、リアルタイムに情報を更新できる点が大きな利点です。
Webサイトの主な特徴:
- 情報量に制限がなく、詳細なデータや資料を掲載できる
- リアルタイムでの情報更新が可能
- 検索機能により必要な情報に素早くアクセスできる
- 多言語対応や文字拡大など、アクセシビリティへの対応が可能
- SNSやメルマガなど他のデジタルメディアとの連携が容易
一方で、情報が整理されていないと使いにくさを感じさせる、更新されていないと信頼性が低下する、セキュリティ対策が必要といった課題もあります。また、インターネットを利用しない住民には情報が届かないという限界もあります。
効果的なWebサイト運用のポイントとしては、ユーザーの視点に立った情報の整理、アクセシビリティへの配慮、定期的な情報更新、スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)、アクセス解析に基づく改善などが挙げられます。特に最近では、スマートフォンからの閲覧が増加していることから、モバイル対応は必須となっています。
SNS:即時性と拡散性を活かした情報発信
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、即時性と拡散性に優れ、住民との双方向コミュニケーションを可能にする広報ツールです。特に若年層へのリーチと緊急情報の発信に効果を発揮します。
主なSNSプラットフォームと特徴:
- X(旧Twitter):短文を即時に配信でき、災害時などの緊急情報発信に適している
- Facebook:イベント機能やコミュニティ機能があり、地域コミュニティの形成に役立つ
- Instagram:写真や動画を中心に、地域の魅力を視覚的に伝えることができる
- LINE:プッシュ型の通知機能があり、住民の日常に密着した情報提供に適している
- YouTube:動画による詳細な情報提供や、地域の魅力発信に効果的
神奈川県葉山町は、Instagramを活用した広報で成功している事例として知られています。フォロワー数約3.8万人を誇り、美しい海岸線や自然の写真を通じて地域の魅力を発信し、若い世代の移住促進につなげています。「#葉山歩き」というハッシュタグを活用し、住民や訪問者からの投稿も促進することで、多角的に町の魅力を伝えることに成功しています。
SNS運用の課題としては、継続的な更新が求められること、炎上リスクがあること、プラットフォームごとに特性が異なるため運用ノウハウが必要なこと、などが挙げられます。効果的なSNS運用のためには、ターゲット層の利用傾向に合わせたプラットフォーム選択、定期的な投稿計画、視覚的に魅力的なコンテンツ制作、コメントへの適切な対応などが重要です。
動画配信:魅力的なビジュアルコンテンツの活用
動画は文字や静止画以上に情報量が多く、視聴者の感情に訴えかける力を持っています。YouTubeなどの動画プラットフォームの普及により、自治体の動画配信も一般的になってきました。
動画配信の主な特徴:
- 複雑な情報を視覚的にわかりやすく伝えることができる
- 感情に訴えかけ、視聴者の共感や理解を得やすい
- 地域の雰囲気や魅力を臨場感をもって伝えられる
- スマートフォンの普及により、視聴者が拡大している
- 若年層の関心を引きやすい
茨城県は動画活用の先進事例として知られています。県運営の動画サイト「いばキラTV」では1万本以上の動画を公開し、YouTubeでは日本の自治体として初めてチャンネル登録者数10万人を突破しました。また、VTuber「茨ひより」を起用した情報発信も話題となり、従来の行政広報のイメージを覆す親しみやすいコンテンツ作りに成功しています。
動画配信の課題としては、制作に専門知識やスキル、機材が必要なこと、製作コストや時間がかかること、視聴環境によっては見られない場合があることなどが挙げられます。しかし、近年ではスマートフォンでも高品質な動画撮影が可能になり、編集ソフトやアプリも使いやすくなっているため、低コストでの動画制作も可能になってきています。
メールマガジン:プッシュ型の情報提供
メールマガジンは、登録者に直接情報を届けることができる「プッシュ型」の広報手段です。特定のテーマや対象に絞った情報提供に適しています。
メールマガジンの主な特徴:
- 必要な情報を必要な人に直接届けることができる
- 防犯・防災情報など速報性の高い情報提供に適している
- テーマ別に情報を分類し、ターゲットを絞った発信が可能
- 比較的低コストで運用できる
- 登録者データを分析することで、ニーズの把握にも役立つ
メールマガジンの課題は、登録してもらうためのハードルがあること、メール受信環境に依存すること、迷惑メールと誤認されるリスクがあることなどです。効果的なメールマガジン運用のポイントとしては、登録手続きの簡素化、カテゴリ分けによる受信設定の柔軟化、定期的な配信、簡潔でわかりやすい内容、適切な件名設定などが挙げられます。
近年では、メールに代わってLINE公式アカウントを利用した情報提供も増えています。福岡県福岡市はLINE公式アカウントの友だち登録者数が多く、広報課による日々のコンテンツチェックと改善により、質の高い情報提供を実現している好例です。スマートフォンの普及に伴い、メールよりもLINEの方が開封率が高く、若年層にもリーチしやすいというメリットがあります。
ターゲット別の最適メディア選択
効果的な広報活動を展開するためには、情報の内容や伝えたいターゲット層に応じて、最適なメディアを選択することが重要です。年齢層や生活スタイルによって利用するメディアは異なります。
年齢層別の主なメディア利用傾向:
- 高齢者層(65歳以上):広報誌、テレビ、ラジオなどの従来型メディア
- 中年層(40〜64歳):広報誌、Webサイト、テレビ、ラジオ、メールなど幅広いメディア
- 若年層(18〜39歳):SNS、動画、Webサイト、LINEなどのデジタルメディア
- 子ども・学生:SNS(特にInstagramやTikTokなど)、動画など
情報内容別の適したメディア:
- 日常的な行政情報:広報誌、Webサイト
- 緊急・防災情報:SNS(特にX)、LINE、メール、防災無線
- イベント情報:SNS、Webサイト、広報誌
- 観光・地域PR:Instagram、YouTube、Webサイト
- 政策や計画の詳細:Webサイト、広報誌、冊子
ひとつのメディアだけでは、すべての住民に情報を届けることは難しいため、複数のメディアを組み合わせたクロスメディア戦略が効果的です。例えば、広報誌に掲載した内容をSNSでも発信したり、詳細情報をWebサイトに掲載してQRコードで誘導したりするなどの工夫が考えられます。
メディア選択のポイントとしては以下のことが重要です:
- ターゲット層がよく利用するメディアを把握する
- 伝えたい情報の特性(緊急性、詳細さ、視覚的要素など)を考慮する
- 複数のメディアを連携させ、相互に補完し合うよう設計する
- 各メディアの特性を活かしたコンテンツを制作する
- 効果測定を行い、継続的に改善する
例えば、高齢者への福祉サービス情報は広報誌を中心に詳しく掲載し、若い子育て世帯向けのイベント情報はSNSでタイムリーに発信するといった使い分けが効果的です。また、災害情報など全住民に確実に届けるべき重要情報は、複数のメディアを通じて発信することが安全です。
自治体の広報担当者は、これらの多様なメディアの特性を理解し、限られた予算と人材の中で最適な組み合わせを選択することが求められています。また、技術やメディア環境の変化に合わせて、常に新しい手法を取り入れる柔軟性も必要です。メディアの多様化は一見すると業務の複雑化を招きますが、適切に活用することで、より効果的かつ効率的な広報活動が可能になるのです。
自治体の広報活動で発生しがちな問題点

自治体の広報活動において、しばしば発生する問題点を理解し、事前に対策を講じることで、より効果的な広報活動を展開することができます。ここでは、多くの自治体が直面する5つの主要な問題点について解説します。
目標が不明確で方向性が定まらない
自治体の広報活動において最も基本的かつ重要な問題点が、目標の不明確さです。「何のために広報するのか」という本質的な問いに対する答えが曖昧なまま、慣例的に情報発信を続けているケースが少なくありません。
具体的な問題例:
- 「広報を行うこと自体」が目的化し、その効果や成果を考慮していない
- 「何を伝えるべきか」ではなく「何を伝えられるか」が優先されている
- KPI(重要業績評価指標)が設定されておらず、効果測定ができない
- 担当者の交代により、広報の方針が頻繁に変わる
- 広報活動と自治体の政策や戦略との連携が不足している
目標が不明確であると、一貫した広報活動を展開することが難しく、予算や人的リソースを効果的に活用できません。また、効果測定の基準も曖昧になるため、改善のサイクルが回りにくくなります。
解決のポイント:
- 自治体の全体戦略や政策目標と連動した広報目標を設定する
- 具体的で測定可能なKPIを設定する(例:記事の閲覧数、イベント参加者数、サービス利用率など)
- 短期・中期・長期の広報計画を策定し、PDCAサイクルを回す
- 各広報施策の目的と期待する効果を明確にする
- 広報活動の優先順位を明確にし、リソースを効率的に配分する
情報の収集がうまくできない
広報部門は多くの場合、各部署から情報を集めて発信する役割を担いますが、庁内での情報収集がスムーズに行われないケースが多々あります。
具体的な問題例:
- 各部署が広報の重要性を理解しておらず、情報提供に消極的
- 情報収集のタイミングが遅く、発信までに時間がかかる
- 専門用語や行政特有の表現が多く、一般住民向けに加工するのが難しい
- 収集される情報に偏りがあり、住民が本当に必要としている情報が不足
- 情報収集の仕組みや体制が整備されていない
情報収集がうまくいかないと、発信される情報の質が低下し、広報活動の効果も限定的になってしまいます。特に緊急時には、迅速な情報収集と発信が求められるため、平時からの体制整備が重要です。
解決のポイント:
- 庁内の情報共有体制を確立し、広報担当者と各部署の連携を強化する
- 定期的な情報収集の仕組み(報告フォーマット、連絡会議など)を整備する
- 各部署に広報担当者を配置し、広報部門との連携窓口とする
- 首長や幹部職員から広報の重要性を発信し、組織全体の意識を高める
- 住民ニーズに関する情報を各部署に提供し、必要な情報の認識を共有する
広報の内容がステークホルダーのニーズと合致しない
自治体からの一方的な情報提供になりがちで、住民やその他のステークホルダー(利害関係者)が本当に必要としている情報と、提供される情報にギャップが生じる場合があります。
具体的な問題例:
- 行政視点の情報が多く、住民目線の情報が少ない
- 専門用語や難しい表現が多く、理解しづらい
- 年齢層や属性によって情報ニーズが異なることへの配慮が不足
- 住民のライフステージに応じた情報提供ができていない
- 住民の関心事よりも行政の伝えたいことが優先されている
ニーズと合致しない情報は住民に届いても読まれず、広報活動の効果は大きく減少します。特に若年層では行政情報への関心が低い傾向があり、ニーズを把握した上での情報発信が重要です。
解決のポイント:
- 住民アンケートやワークショップなどで定期的にニーズを調査する
- 広報誌やWebサイトのアクセス解析、SNSの反応などを分析する
- 年齢層や居住地域、ライフステージ別にターゲット分析を行う
- 専門用語を避け、わかりやすい表現を心がける
- 住民モニター制度を導入し、定期的なフィードバックを得る
自治体の魅力をアピールしきれていない
多くの自治体では、地域の魅力や強みを効果的にアピールできていないという課題があります。特に移住促進や観光振興、企業誘致など地域活性化を目指す上で、このことは大きな問題となります。
具体的な問題例:
- 地域の独自性や強みが明確に打ち出せていない
- 地域住民にとっては当たり前でも、外部の人にとっては魅力的な資源に気づいていない
- プロモーション的な発想や技術が不足している
- 写真や動画などビジュアル面での訴求力が弱い
- 地域ブランディングの視点が欠けている
地域間競争が激しくなる中、自地域の魅力を効果的にアピールすることは、人口減少対策や地域経済の活性化において不可欠な要素です。
解決のポイント:
- 地域資源の棚卸しを行い、独自の強みを再発見する
- 外部の視点(移住者、観光客、専門家など)からの評価を積極的に取り入れる
- プロフェッショナルな写真・動画の撮影や制作に投資する
- ストーリー性のある発信を心がけ、感情に訴えかける
- 民間企業のマーケティング手法を取り入れる
特定のメディアに偏った情報発信
自治体の広報活動が特定のメディア(例えば広報誌のみ)に偏り、多様な住民層にバランスよく情報が届いていないケースが見られます。
具体的な問題例:
- 広報誌中心で、デジタル媒体の活用が不十分
- SNSを始めたものの、効果的な運用ができていない
- 広報担当者のスキルや関心によって、使用するメディアに偏りがある
- 新しいメディアへの対応が遅れている
- メディア間の連携が不足し、情報が分断されている
特定のメディアに偏ると、そのメディアを利用していない層に情報が届かなくなります。例えば広報誌だけでは若年層に、SNSだけでは高齢者層に情報が届きにくいという問題が生じます。
解決のポイント:
- 各メディアの特性とターゲット層を理解し、複数のメディアを効果的に組み合わせる
- 広報担当者の研修やスキルアップを支援し、多様なメディア運用能力を高める
- 外部専門家や民間企業との連携により、不足するノウハウを補完する
- クロスメディア戦略を策定し、各メディアの役割を明確にする
- デジタルデバイドに配慮し、情報格差が生じないよう工夫する
これらの問題点の多くは互いに関連しており、根本的な解決には組織全体の広報への理解と協力、そして計画的な取り組みが不可欠です。広報は自治体の「顔」であり、住民との信頼関係を築く重要な活動です。問題点を認識し、継続的に改善していくことで、より効果的な広報活動が実現できるでしょう。
広報における住民ニーズの把握

効果的な自治体広報を行うためには、住民が本当に必要としている情報は何かを理解することが不可欠です。住民ニーズを適切に把握し、それを広報活動に反映させることで、情報の届きやすさと活用度が高まります。
住民が求める情報とは
住民が自治体から得たいと考えている情報には、様々な種類があります。公益社団法人日本広報協会の調査によると、特に関心が高いのは以下のような情報です。
住民が特に関心を持つ情報(優先度順):
- 健康・福祉・医療介護情報(76.4%):健康診断、予防接種、介護保険、福祉サービスなど
- 防犯・防災情報(47.8%):防災マップ、避難所情報、犯罪発生状況、詐欺対策など
- 環境・ごみ・リサイクル情報(45.7%):ごみ分別方法、収集日、リサイクル方法など
- 観光情報(33.4%):観光スポット、イベント情報、特産品など
- 各種証明・届出手続き(30.4%):税金、戸籍、住民票などの手続き方法
- 子育て・教育情報(30.3%):保育園・学校情報、子育て支援サービス、教育イベントなど
これらのデータからわかるように、住民が最も求めているのは日常生活や安心・安全に直結する実用的な情報です。特に健康・福祉・医療介護情報は、高齢化社会を反映して関心が非常に高くなっています。
ただし、このようなニーズは地域の特性や人口構成によって異なる場合もあります。例えば、若い子育て世代が多い地域では子育て・教育情報へのニーズが高く、観光地では観光情報への関心が高いなど、地域によって優先度が変わることがあります。
また、同じ住民でも、ライフステージによって求める情報は変化します。例えば、子育て世代は保育園・学校情報、中高年は健康・介護情報というように、年齢や家族構成によって関心事が異なります。時期によっても、選挙時期には投票情報、確定申告時期には税金情報など、季節や時期に応じたニーズがあります。
住民のニーズを適切に汲み上げる方法
住民のニーズを適切に把握するためには、様々な手法を組み合わせて多角的に情報を収集することが重要です。
住民ニーズを把握するための主な方法:
- アンケート調査:広報誌や自治体Webサイト、イベント会場などでアンケートを実施し、定量的なデータを収集する
- 住民モニター制度:一般住民から広報モニターを募集し、定期的にフィードバックを得る
- パブリックコメント:政策や計画の策定過程で広く意見を募集し、関心事を把握する
- 住民懇談会・ワークショップ:テーマを設定して意見交換を行い、深堀りした情報を収集する
- SNSやWebサイトの分析:コメント、いいね!、アクセス数などから関心の高いトピックを分析する
- 窓口や電話での問い合わせ分析:よくある質問や相談内容を整理し、情報ニーズを把握する
- 地域団体との連携:自治会、NPO、商工会など地域団体からの情報収集
これらの方法を組み合わせることで、より正確で多面的なニーズ把握が可能になります。特に重要なのは、「声なき声」を拾う努力をすることです。アンケートなどに積極的に回答する層の意見だけでなく、普段は意見を表明しない層のニーズも考慮する必要があります。
例えば、千葉県流山市では、マーケティング課が中心となり、子育て世代をターゲットにした詳細な市場調査を実施。「母になるなら、流山市。」というキャッチフレーズでプロモーションを展開し、大きな成果を上げています。このように、マーケティングの手法を取り入れた科学的なニーズ把握も効果的です。
ニーズ調査の実施と活用
ニーズ調査を効果的に実施し、その結果を広報活動に活かすためのステップを具体的に見ていきましょう。
効果的なニーズ調査の実施手順:
- 調査目的の明確化:何を知りたいのか、どう活用するのかを明確にする
- 調査方法の選定:目的に合った調査方法(アンケート、インタビュー、観察など)を選ぶ
- サンプリング計画:偏りのないデータを得るため、年齢、性別、地域などバランスの取れた対象者選定を行う
- 質問設計:答えやすく、かつ必要な情報が得られる質問を設計する
- 調査実施:オンライン、紙、対面など複数の手段を用意し、多くの住民が参加できるようにする
- データ分析:単純集計だけでなく、属性別のクロス分析なども行う
- 結果の共有・活用:結果を庁内で共有し、広報計画に反映させる
- 調査結果の公表:住民にフィードバックし、次回の参加意欲を高める
特に重要なのは、調査結果を実際の広報活動に反映させることです。せっかく集めたデータが活用されないままでは、調査の意義が失われてしまいます。
調査結果の活用例:
- ニーズの高いトピックを広報誌の特集記事として取り上げる
- 関心の高い情報をWebサイトのトップページに配置する
- よく質問される事項についてFAQを作成し、Webサイトに掲載する
- 特定の層から需要が高いテーマについて、ターゲットを絞ったメールマガジンを作成する
- 住民の情報取得経路に関する調査結果をもとに、メディアミックス戦略を見直す
定期的にニーズ調査を実施し、その結果に基づいて広報活動を見直すPDCAサイクルを回すことで、常に住民のニーズに応える広報が実現できます。
地域外の声も取り入れたバランスのとれた情報発信
自治体広報では地域住民のニーズ把握が中心となりますが、移住促進や観光振興、企業誘致などを目指す場合は、地域外の人々の視点やニーズも理解することが重要です。
地域外の声を把握する方法:
- 観光客アンケート:観光地や宿泊施設などで実施し、地域の印象や魅力を調査する
- 移住相談会での情報収集:移住検討者がどんな情報を求めているか直接聞く
- ふるさと納税寄付者の分析:寄付の理由や返礼品選択の傾向から関心事を探る
- SNSでの地域に関する投稿分析:外部の人が地域のどんな点に注目しているか分析する
- 専門家や有識者の意見収集:観光、移住、地域振興などの専門家からアドバイスを得る
地域住民にとっては当たり前の風景や習慣、特産品なども、外部の視点から見れば魅力的なコンテンツになり得ます。地域の「当たり前」を再発見し、価値化するためにも、外部の目線は非常に重要です。
神奈川県葉山町では、Instagram運用にあたり、地域外の人々からの反応を分析。地元の人には日常的な海辺の風景が、外部の人々にとって大きな魅力となっていることを再認識し、ビジュアル中心の発信を強化することで、移住促進につなげています。
また、沖縄県渡名喜島のFacebookページは人口に対してフォロワー数が非常に多く(人口約450人に対しフォロワー約9,800人)、島外の人々とのコミュニケーションを大切にしています。地域おこし協力隊のメンバーが地域の日常をこまめに投稿し、コメントへの丁寧な返信を行うことで、島外からの支持を集めています。
このように、住民ニーズと地域外の視点をバランスよく取り入れた情報発信を行うことで、地域内のコミュニケーション活性化と地域外からの関心獲得という二つの目的を同時に達成することができます。地域の持続的な発展のためには、内向きと外向きの広報のバランスを取ることが重要です。
自治体が広報戦略を策定する際のポイント

自治体の広報活動を効果的に展開するためには、明確な戦略に基づいた計画的なアプローチが必要です。ここでは、広報戦略を策定する際に押さえるべき5つの重要なポイントを解説します。
目標や計画を明確にする
広報活動の出発点となるのが、目標設定です。「何のために広報するのか」「どのような状態を目指すのか」を明確にすることで、効果的な広報戦略の土台が築かれます。
目標設定のポイント:
- 自治体の総合計画や政策目標との連動:広報活動は自治体全体の目標達成を支援するものであるべき
- SMART原則の活用:具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、現実的(Realistic)、期限付き(Time-bound)な目標設定
- 短期・中期・長期目標の設定:即効性のある取組みと、ブランディングなど長期的な視点の両方を持つ
- ターゲット別の目標設定:住民、移住検討者、観光客、企業など対象ごとに目指す状態を定義
- 定量・定性両面での目標設定:数値で測れる指標だけでなく、印象や満足度などの質的側面も考慮
例えば、「広報誌の認知度を1年以内に20%向上させる」「移住相談件数を半年で30%増加させる」「ホームページのアクセス数を月間1万PV増やす」といった具体的な目標を設定することで、取り組むべき施策が明確になります。
また、目標達成のための具体的な計画も重要です。「いつ」「誰が」「何を」「どのように」実施するのかを明記したアクションプランを作成し、定期的に進捗を確認する仕組みを整えましょう。計画には予算や人員などのリソース配分も含め、実行可能性を十分に検討することが大切です。
目的とマッチしたメディアを活用する
情報を届けたいターゲットと情報の性質に応じて、最適なメディア(伝達手段)を選択することが効果的な広報のカギとなります。
メディア選択のポイント:
- ターゲット層の利用メディア分析:年齢層や属性によって主に利用するメディアは異なる
- 情報の性質に合わせた選択:緊急性の高い情報はSNSやメール、詳細な制度説明はWebサイトや広報誌など
- 複数メディアの連携活用:一つのメディアだけでなく、相互に補完し合うメディアミックス戦略
- 費用対効果の検討:予算制約の中で最大の効果を上げるメディア選択
- 運用体制の現実性:人的リソースや技術的なハードルを考慮したメディア選択
例えば、高齢者向けの健康情報を発信する場合は、インターネット利用率が低い層もあるため、広報誌や回覧板、地域の集会などのアナログな手段が効果的です。一方、若い子育て世代向けの情報は、SNSやLINE、子育て支援アプリなどのデジタルツールを活用するのが適しています。
また、情報の性質によっても最適なメディアは異なります。例えば、災害情報などの緊急性の高い情報は、SNS(特にX)やLINE、防災メールなど即時性のあるメディアが適しています。一方、詳細な制度説明や長期的な計画などは、広報誌やWebサイトのような情報量の多いメディアが向いています。
メディア選択の際には、住民の情報取得経路に関する調査データを活用し、科学的な根拠に基づいた判断をすることが重要です。
ユニークな観点で広報を考える
他の自治体との差別化を図り、印象に残る広報を行うためには、地域の独自性を活かしたユニークな観点からの情報発信が効果的です。
ユニークな広報のポイント:
- 地域資源の再発見と価値化:当たり前と思われている地元の自然、文化、産業、人材などの魅力を掘り起こす
- 外部視点の活用:地域外の人々や専門家の視点から、地域の「当たり前」の中にある価値を発見する
- ストーリーテリング:地域の歴史や人々の物語を通じて感情に訴えかける広報
- ユーモアや意外性の活用:堅いイメージの行政情報も、親しみやすく記憶に残る表現で伝える
- 地域キャラクターや著名人の活用:親しみやすさや認知度を高めるための象徴的存在の活用
例えば、茨城県が「日本一不人気な県」という逆境をバネに展開した「茨城県PRプロジェクト」では、VTuber「茨ひより」の起用や自虐的なキャッチコピーなど斬新なアプローチで注目を集め、県のイメージ向上に貢献しました。
千葉県流山市の「母になるなら、流山市。」というキャッチフレーズも、ターゲットを絞った明確なメッセージで差別化に成功した好例です。こうしたキャッチーなフレーズは、地域ブランディングの核となり、継続的な情報発信の一貫性を保つ役割も果たします。
ユニークな広報を考える際には、地域住民のアイデアを取り入れるワークショップの開催や、学生や若手クリエイターとのコラボレーションなど、多様な視点を集める工夫も有効です。
広報の効果測定と改善サイクル
広報活動の効果を定期的に測定し、その結果に基づいて改善を図るPDCAサイクルは、広報戦略の質を高める上で不可欠なプロセスです。
効果測定と改善のポイント:
- 適切なKPI(重要業績評価指標)の設定:目標達成度を測るための具体的な指標を定める
- 定量・定性両面での評価:数値データだけでなく、住民の反応や意見も重視する
- 各メディアの特性に合わせた測定方法:Webサイトのアクセス解析、SNSのエンゲージメント率、アンケート調査など
- 定期的な効果測定の仕組み化:月次、四半期、年次など、定期的な振り返りの機会を設ける
- 分析結果の共有と活用:測定結果を庁内で共有し、次の施策に反映させる
主な効果測定指標の例:
- Webサイト:ページビュー数、訪問者数、滞在時間、直帰率など
- SNS:フォロワー数、いいね!数、コメント数、シェア数、エンゲージメント率など
- 広報誌:認知度、閲読率、満足度、役立ち度など(アンケート調査による)
- メールマガジン:開封率、クリック率、登録者数、解除率など
- イベント:参加者数、満足度、問い合わせ数、関連サービスの利用率など
効果測定の結果、期待した成果が得られなかった場合は、その原因を分析し、改善策を検討することが重要です。例えば、Webサイトの特定ページへのアクセスが少ない場合、コンテンツの内容、見つけやすさ、デザイン、導線など様々な観点から問題点を洗い出し、改善を図ります。
改善サイクルを継続的に回すことで、住民のニーズや行動の変化に柔軟に対応し、常に効果的な広報活動を展開することができます。特に、デジタルメディアは比較的容易に修正・改善が可能なため、小さな改善を積み重ねる「カイゼン」の考え方が有効です。
外部人材・専門家の登用
広報活動の質を高めるためには、組織内のリソースだけでなく、外部の専門知識や技術を積極的に取り入れることも重要な戦略です。
外部人材活用のポイント:
- 不足するスキルの補完:デザイン、写真・動画撮影、SNS運用、Webサイト構築など専門性の高い分野
- 客観的な視点の導入:組織内では気づきにくい課題や改善点の発見
- 最新トレンドやノウハウの取り入れ:民間企業や他地域の成功事例の導入
- 多様な雇用形態の検討:正規職員、任期付職員、業務委託、兼業・副業人材など柔軟な活用
- 内部人材の育成と連携:外部人材のノウハウを組織内に蓄積・展開する仕組み
兵庫県三木市では「複業人材登用による情報発信強化に向けた実証実験」を実施し、民間企業で広報・マーケティングを担当するプロフェッショナルを「複業」の形で採用。情報発信力の強化と職員のスキルアップを同時に進める取り組みを行っています。
また、千葉県流山市では、日本の自治体で初めて「マーケティング課」を設置し、民間から専門人材を登用することで、戦略的なシティプロモーションを展開しています。「母になるなら、流山市。」というキャッチフレーズを核にした一貫性のある施策により、子育て世代の移住促進に成功しています。
外部人材を活用する際のポイントとしては、単に業務を委託するだけでなく、内部の職員と外部人材が協働する体制を作り、ノウハウ移転や人材育成も視野に入れたパートナーシップを構築することが重要です。また、外部人材が自治体の組織文化や地域特性を理解し、それに合った提案ができるよう、十分なコミュニケーションを取ることも欠かせません。
このように、明確な目標設定、適切なメディア選択、ユニークな視点の導入、効果測定と改善の仕組み化、そして外部人材の活用という5つのポイントを押さえることで、自治体の広報活動は大きく進化します。これらのポイントを踏まえた戦略的な広報活動は、住民サービスの向上や地域の活性化に大きく貢献するでしょう。
デジタル時代の自治体広報戦略

デジタル技術の急速な進化により、自治体の広報活動も大きく変化しています。特にSNSや動画配信などのデジタルメディアは、若い世代を中心に情報収集の主要チャネルとなっており、これらを効果的に活用することが自治体広報の成否を左右します。ここでは、デジタル時代における自治体広報戦略のポイントを解説します。
SNS運用の実践ポイント
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、即時性、拡散性、双方向性に優れており、自治体広報に新たな可能性をもたらしています。しかし、やみくもに始めるのではなく、戦略的な運用が必要です。
SNS運用の基本戦略:
- 目的とターゲットの明確化:各SNSでどんな目的を達成し、誰に情報を届けたいのかを明確にする
- プラットフォーム選択:目的とターゲットに合わせてSNSを選択する(例:若年層向け→Instagram、幅広い層→Facebook)
- 一貫性のあるアカウント設計:プロフィール、アイコン、カバー画像などの統一感を持たせる
- 運用ポリシーの策定:投稿内容、頻度、返信方針、危機管理対応などのルールを定める
- 担当者・権限の明確化:誰が投稿・チェック・承認を行うかの体制を整える
効果的な投稿コンテンツ作成のポイント:
- ビジュアル重視:写真や動画を効果的に活用し、視覚的に訴求する
- 簡潔で分かりやすい文章:行政特有の難しい表現を避け、親しみやすい言葉で伝える
- ハッシュタグの活用:適切なハッシュタグをつけることで検索性と拡散性を高める
- 地域の日常や魅力の発信:地域の自然、文化、食、人々の活動など、身近で親しみやすい題材
- 時事性・季節性の考慮:旬の話題や季節のイベントと連動した投稿
神奈川県葉山町のInstagramは、美しい海岸線や自然の写真を中心に、地域の日常を魅力的に切り取った投稿で約3.8万人のフォロワーを獲得しています。特に「#葉山歩き」というハッシュタグを活用し、住民や訪問者からの投稿も促進することで、多様な視点から町の魅力を発信しています。
フォロワー獲得・エンゲージメント向上のコツ:
- 定期的な投稿:一定のリズムで継続的に情報を発信する
- コメントへの返信:フォロワーとの対話を大切にし、コミュニティを形成する
- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用:フォロワーの投稿を紹介し、参加意識を高める
- 他アカウントとの連携:地域の企業、団体、インフルエンサーなどとのコラボレーション
- 投稿データの分析と改善:どんな内容が反応を得ているかを分析し、継続的に改善する
沖縄県渡名喜島のFacebookページは人口約450人に対してフォロワー約9,800人を誇り、島の日常を丁寧に発信しながらコメントへの返信を大切にすることで、島外からも多くの支持を集めています。
SNS運用では、「炎上」リスクも考慮する必要があります。事前に危機管理マニュアルを作成しておき、不適切なコメントへの対応方針や、誤った情報を投稿した場合の訂正方法などを明確にしておくことが重要です。また、複数の担当者によるチェック体制を構築し、投稿前に内容の正確性や適切性を確認することも大切です。
動画コンテンツの効果的な活用法
YouTubeなどの動画プラットフォームの普及により、動画は自治体広報において重要な位置を占めるようになりました。特に若年層へのリーチや複雑な情報の視覚的な説明に効果を発揮します。
自治体広報における動画活用の目的:
- 地域の魅力発信:観光資源、特産品、文化、自然などを視覚的に紹介
- 行政サービスの説明:制度やサービスの内容をわかりやすく解説
- イベント・取り組みの記録:地域の活動やイベントを記録し、アーカイブ化
- 防災・安全情報の提供:避難方法や防犯対策などを具体的に示す
- 首長や職員からのメッセージ:親しみやすく、直接的なコミュニケーション
効果的な動画制作のポイント:
- 冒頭で視聴者の興味を引く:最初の数秒で内容の魅力を伝え、視聴継続を促す
- 適切な長さ:内容に応じた最適な尺を設定(概要紹介は2〜3分、詳細解説は5〜10分程度)
- 明確なメッセージ:伝えたいことを絞り込み、簡潔に表現する
- 字幕・テロップの活用:音声なしでも理解できるよう、テキスト情報を適切に配置
- アクセシビリティへの配慮:字幕、明瞭な音声、十分なコントラストなど
茨城県の動画サイト「いばキラTV」は日本の自治体動画サイトとして先駆的な存在で、1万本以上の動画を公開し、YouTubeでは日本の自治体として初めてチャンネル登録者数10万人を突破しました。地域の魅力を伝える高品質な動画制作に加え、「ガールズ&パンツァー」などの人気コンテンツとのコラボレーションも話題を呼びました。
茨城県は更に、VTuber(バーチャルYouTuber)「茨ひより」による情報発信も行っています。アニメキャラクターを用いることで若い世代の興味を引き、従来の行政広報では届きにくい層にリーチすることに成功しています。
低予算でも実現できる動画制作のヒント:
- スマートフォンでの撮影:最新のスマートフォンは高画質な撮影が可能
- 無料・低コストの編集ツール活用:iMovie、DaVinci Resolveなど初心者でも使いやすいソフトの利用
- 著作権フリーの音楽・素材の活用:YouTube Audio Libraryなどの無料素材サイトの利用
- 地域の学生やクリエイターとの協働:地元の映像関係者や学生との連携
- シンプルな構成・演出:凝った演出より、内容の充実と伝わりやすさを重視
動画は制作に時間とコストがかかりがちですが、内容や目的に応じて制作レベルを使い分けることも重要です。例えば、観光プロモーション動画は高品質な映像制作に投資し、日常的な情報発信はスマートフォンでの簡易撮影でも十分という使い分けも効果的です。
地域住民の目線に立った情報の配信
デジタル時代においても、広報の基本は受け手のニーズに合わせた情報提供です。特に地域住民向けの情報発信では、住民目線に立ったコンテンツ設計と配信方法の工夫が重要です。
住民目線の情報配信のポイント:
- ライフイベントに沿った情報整理:出生、入学、就職、結婚、子育て、介護など人生の節目に必要な情報を体系化
- Q&A形式の情報提供:よくある質問に対する回答をわかりやすく提示
- 専門用語の言い換え:行政特有の難解な用語を平易な表現に置き換える
- 視覚的な情報整理:フローチャート、インフォグラフィックスなどを活用した情報の可視化
- パーソナライズされた情報提供:居住地域、家族構成、年齢などに応じた情報のカスタマイズ
神奈川県川崎市では、ラジオを活用した広報活動を継続的に展開し、地域住民との距離を縮める工夫をしています。週1回の番組で市内の最新情報やイベントを紹介するだけでなく、ゲストとのトークや現地リポートを通じて、親しみやすい形で行政情報を届けています。
緊急時・災害時の情報発信の留意点:
- 迅速性と正確性のバランス:速報性を重視しつつも、誤情報を流さない慎重さ
- 複数メディアの活用:SNS、メール、防災無線、Webサイトなど多角的な情報発信
- 情報の優先順位付け:生命・安全に関わる情報を最優先に
- 定期的な更新と進捗報告:「現在も調査中」など状況が変わらなくても定期的な情報提供
- 多言語・やさしい日本語対応:多様な住民に確実に情報が届くよう配慮
福岡県福岡市では、LINE公式アカウントを活用した情報発信を積極的に行っており、友だち登録者数が多い自治体として知られています。特に防災情報や緊急お知らせなど、迅速に伝える必要がある情報をプッシュ型で届けることで、住民の安心・安全に貢献しています。
地域のブランド力を地域外にアピールする技術
デジタルメディアの普及により、地域の魅力を全国・全世界に発信することが容易になりました。特に観光振興や移住促進、企業誘致などを目指す自治体にとって、地域ブランディングとそのアピールは重要な戦略です。
地域ブランディングの基本ステップ:
- 地域資源の棚卸しと分析:自然、歴史、文化、産業、人材など地域の資源を客観的に評価
- ターゲット設定:観光客、移住者、企業など、誰に対してアピールするかを明確化
- コンセプト・メッセージの策定:地域の強みと独自性を凝縮したキャッチフレーズや物語の作成
- ビジュアルアイデンティティの確立:ロゴ、カラー、写真などのデザイン要素の統一
- 多様なチャネルでの一貫した発信:Webサイト、SNS、パンフレット、イベントなど様々な接点での統一感
千葉県流山市の「母になるなら、流山市。」は、ターゲットを子育て世代に絞り込み、一貫したメッセージで地域ブランディングに成功した好例です。単にキャッチフレーズを作るだけでなく、駅前送迎保育ステーションの設置など実際の子育て支援策と連動させることで、移住者の増加につなげています。
デジタルを活用した地域外へのアピール手法:
- SEO対策:検索エンジンで上位表示されるようWebサイトを最適化
- ターゲティング広告:年齢、居住地、興味関心などに基づいた広告配信
- インフルエンサーマーケティング:影響力のある人物による地域の魅力発信
- デジタルパンフレット・電子書籍:印刷物をデジタル化し、より広範囲に配布
- バーチャルツアー・VR体験:実際に訪れていない人にも地域の魅力を体感してもらう
特に、Google検索で「移住 子育て」「観光 温泉」などの関連キーワードで上位表示されることは、地域の認知度を高める上で重要です。検索エンジン最適化(SEO)の基本的な対策としては、適切なキーワードの使用、質の高いコンテンツの提供、適切なメタタグの設定、モバイル対応などが挙げられます。
また、ターゲティング広告は費用対効果の高いプロモーション手段です。例えば、30代子育て世代で移住に関心がある層に絞った広告配信や、特定の趣味(アウトドア、グルメなど)を持つ人々をターゲットにした観光プロモーションなどが可能です。
宮城県では農産品のブランド化に成功した例があります。「ぷれ宮夢みやぎ」というサイトを通じて、県産品の魅力や生産者の思いをSNSも活用しながら発信することで、地域外への認知度向上に貢献しています。
地域外へのアピールにおいては、「Webプロモーションを支援するプラットフォーム」の活用も効果的です。行政向けに特化した広告配信サービスを利用することで、専門的なノウハウがなくても効率的な情報発信が可能になります。
デジタル時代の自治体広報では、従来の一方通行の情報提供から脱却し、住民や地域外の人々との対話や共創を重視したアプローチが求められています。SNSや動画などのデジタルツールは、その双方向性を活かすことで、より効果的な広報活動を展開するための強力な手段となります。
また、コロナ禍を経て、オンラインでの情報収集や交流が一般化した今、デジタル広報の重要性はますます高まっています。各自治体の特性や目的に合わせて、適切なデジタル戦略を立案・実行していくことが、これからの自治体広報の鍵となるでしょう。
自治体広報のDXとAI活用の可能性

デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は自治体広報にも押し寄せており、単なるデジタル化にとどまらない業務の抜本的な変革と、AI(人工知能)などの先端技術の活用により、より効率的かつ効果的な広報活動が可能になっています。ここでは、自治体広報における DX の推進と AI 活用の具体的な方法について解説します。
広報業務のデジタルトランスフォーメーション
広報のデジタルトランスフォーメーション(DX)とは、単にアナログな業務をデジタル化するだけでなく、デジタル技術を活用して広報業務のプロセスや住民とのコミュニケーション方法を根本から変革することを指します。
広報DXの主な領域:
- コンテンツ制作のデジタル化:紙媒体中心からデジタルファースト制作への転換
- 情報発信のデジタル化:紙媒体とデジタルメディアの最適な組み合わせ
- ワークフローのデジタル化:企画から承認、公開までの業務プロセスの効率化
- データの活用:広報効果の測定・分析と改善サイクルの確立
- 住民とのコミュニケーション改革:双方向・パーソナライズされた情報提供
広報DXの推進ステップ:
- 現状分析と課題の洗い出し:現在の広報業務の流れやボトルネックを特定
- デジタル化の目標設定:何のためにDXを推進するのか、達成したい状態を明確化
- システム・ツールの選定:目標達成に必要なデジタルツールの選択
- 人材育成・体制整備:デジタルスキルの習得とDX推進体制の構築
- 段階的な実装と改善:小さな成功を積み重ね、継続的に改善
具体的な取り組み例としては、「コンテンツハブ」の構築が挙げられます。これは、一度作成したコンテンツを広報誌、Web、SNS、メルマガなど様々なメディアで再利用できる形で管理するシステムです。例えば、イベント情報を一か所で作成・管理し、各メディアに最適な形で配信することで、作業の重複を防ぎ、効率化を図ることができます。
また、承認ワークフローのデジタル化も重要です。従来の紙の決裁や対面での確認ではなく、クラウド上で原稿の共有、編集、承認を行うことで、リモートワーク環境でも滞りなく業務を進められるようになります。
広報業務のDXを進める際の注意点としては、単にデジタルツールを導入するだけでなく、業務プロセス全体の見直しや組織文化の変革も併せて行うことが重要です。また、職員のデジタルリテラシーにばらつきがある場合は、研修や勉強会を通じてスキルの底上げを図ることも欠かせません。
AI技術を活用した効率的な広報活動
AI(人工知能)技術の進化により、自治体広報においても様々な業務の効率化や高度化が可能になっています。特に生成AI(Generative AI)の急速な発展は、コンテンツ制作や分析などの領域に大きな変革をもたらしています。
自治体広報におけるAI活用の主な場面:
- コンテンツ制作支援:記事の下書き作成、要約、多言語翻訳など
- 画像・動画制作支援:イラスト生成、動画編集の効率化など
- チャットボット活用:住民からの問い合わせに自動応答
- データ分析・予測:広報効果の分析や住民ニーズの予測
- ターゲティング最適化:個々の住民に最適な情報提供
生成AIを活用したコンテンツ制作の例:
- 広報記事の下書き作成:基本情報を入力することで、記事の原案を自動生成
- 専門用語のやさしい言葉への言い換え:行政特有の難解な表現を平易な日本語に変換
- 多言語対応:日本語コンテンツを英語、中国語、やさしい日本語などに翻訳
- 画像生成:説明用のイラストや図表の作成
- 文章の要約・箇条書き化:長文情報をSNS用に簡潔にまとめる
自治体におけるAI活用の先進事例として、横浜市のAIチャットボット「AIChatbot(R Powered by IBM Watson)」が挙げられます。市民からのよくある質問に自動応答し、24時間365日の問い合わせ対応を実現して市民サービスの向上と業務効率化の両方を達成しています。
また、生成AI技術を活用したコンテンツ制作支援も広がりつつあります。例えば、イベント案内や制度説明などの定型的な文章の下書き作成をAIに任せ、人間はその内容確認や微調整に集中することで、作業効率を高めることができます。
AI活用のポイントと注意点:
- 人間による監修の徹底:AIの出力はあくまで案であり、最終確認は人間が行う
- 著作権・肖像権への配慮:AI生成コンテンツの権利関係を理解し適切に対応
- 倫理的・法的側面の考慮:個人情報保護やバイアスなどに配慮
- 段階的な導入:リスクの低い業務から試験的に導入し、徐々に範囲を拡大
- スキル向上と役割再定義:AIを使いこなす能力の育成と、人間の役割の再定義
AIの活用は業務効率化の強力なツールですが、最終的な判断や創造的な企画立案は人間が担うべき役割です。AIと人間がそれぞれの強みを活かして協働することで、広報活動の質の向上と効率化の両立が可能になります。
データ分析に基づく効果測定と継続的改善
デジタル広報の大きな利点の一つは、様々なデータを収集・分析し、効果測定と改善に活かせる点です。データに基づく意思決定(データドリブン)により、より効果的な広報活動が実現します。
収集・分析すべき主なデータ:
- Webサイトアクセス解析:PV数、訪問者数、滞在時間、流入経路、離脱率など
- SNS分析:フォロワー数、エンゲージメント率、リーチ数、シェア数など
- メール配信分析:開封率、クリック率、登録解除率など
- 検索キーワード分析:サイト内検索や検索エンジンでの検索キーワード
- ユーザー行動分析:ヒートマップ、クリックパス、スクロール深度など
データ分析ツールの例:
- Google Analytics:Webサイトのアクセス解析
- SNS分析ツール:各SNSプラットフォームの分析機能
- メール配信システム:配信結果の分析機能
- ヒートマップツール:ユーザーの行動可視化
- アンケート分析ツール:住民調査結果の分析
これらのデータを定期的に収集・分析することで、広報活動の効果を客観的に評価し、改善につなげることができます。例えば、Webサイトの特定ページへのアクセスが少ない場合、そのページの内容、見つけやすさ、デザインなどを見直すことができます。また、SNS投稿の中でエンゲージメント率が高いものの特徴を分析し、今後の投稿に活かすことも可能です。
データ分析と改善のPDCAサイクル:
- Plan(計画):目標と指標(KPI)の設定
- Do(実行):広報活動の実施とデータ収集
- Check(評価):データ分析と目標達成度の評価
- Act(改善):分析結果に基づく改善策の実施
データ分析に基づく改善の具体例として、ある自治体では、Webサイトのアクセス解析により、移住情報ページへの訪問者の多くがスマートフォンからアクセスしていることが判明。それを受けてモバイル表示を最適化した結果、ページの閲覧時間と問い合わせ数が増加したという事例があります。
また、SNS投稿の分析により、写真付きの投稿や朝の時間帯の投稿がエンゲージメント率が高いことがわかり、投稿戦略を調整したケースもあります。
データ活用の高度化ステップ:
- 基本的な分析:各メディアごとの基本指標の収集と傾向分析
- クロスメディア分析:複数メディア間の相関関係の分析
- セグメント分析:年齢、地域、興味関心などの属性別の分析
- 予測分析:過去のデータから未来のトレンドを予測
- AI活用分析:機械学習などによる高度なパターン認識
データに基づく効果測定と改善サイクルを回すことで、広報担当者の「感覚」や「経験」だけに頼らない、科学的な広報活動が可能になります。ただし、数値に表れない定性的な価値も重要であることを忘れず、データとヒューマンインサイトをバランスよく活用することが成功の鍵です。
自治体広報におけるDXやAI活用はまだ発展途上ですが、今後ますます重要性が高まるでしょう。特に人口減少や職員の減少が進む中、限られたリソースで効果的な広報活動を展開するためには、これらの技術を適切に取り入れていくことが不可欠です。重要なのは、技術そのものを目的化するのではなく、住民サービスの向上や地域活性化という本来の目的のための手段として活用することです。
広報に行き詰まりを感じたときの打開策

多くの自治体広報担当者は、「情報が住民に届いていない」「関心を持ってもらえない」「効果がわからない」などの課題に直面することがあります。ここでは、広報活動に行き詰まりを感じたときの具体的な打開策を紹介します。これらの方法を試すことで、マンネリ化した広報活動に新たな風を吹き込み、効果的な情報発信を実現できるでしょう。
新たな広報手段への挑戦
長年同じメディアや手法で広報活動を続けていると、住民側も慣れてしまい、情報が目に留まりにくくなることがあります。新たな広報手段に挑戦することで、住民の注目を集め直すことができます。
新たな広報手段を導入するステップ:
- 現状分析:既存の広報手段の効果と課題を整理
- ターゲット再確認:情報を届けたい層が利用するメディアを調査
- 新メディアの研究:他自治体の成功事例や最新トレンドを調査
- 小規模試行:リスクを抑えて新しい手段を試験的に導入
- 効果測定と改善:結果を分析し、本格導入または別手段の検討
比較的導入しやすい新たな広報手段:
- 既存の広報誌のデジタル化:紙の広報誌をPDF化してWebサイトで公開
- メールマガジンやLINE配信:定期的な情報をプッシュ型で届けるサービス
- 無料で始められるSNS:X、Instagram、Facebookなど目的に合わせて選択
- 動画コンテンツ:スマートフォンでも撮影・編集可能な簡易動画
- ポッドキャスト:音声による情報発信(通勤中や家事中にも聴取可能)
例えば、従来は広報誌だけで情報発信していた自治体が、Webサイト上で広報誌のPDFを公開するのは比較的ハードルの低い第一歩です。さらに、メールマガジンやLINEなどのプッシュ型メディアを活用すれば、住民が能動的にチェックしなくても情報が届く仕組みを作ることができます。
新たなメディア導入の際は、必ずしも最初から完璧を目指す必要はありません。例えば、SNS運用を始める場合、最初は週1回の定期投稿から始め、徐々に頻度や内容の幅を広げていくというステップを踏むことで、担当者の負担を抑えながら着実に展開することができます。
また、新しい広報手段を導入する際は、既存の広報活動との連携も重要です。例えば、広報誌でSNSアカウントを紹介したり、SNSで広報誌の特集記事を短く要約して紹介したりするなど、相互に誘導する仕組みを作ることで、それぞれのメディアの効果を高めることができます。
住民の声を積極的に取り入れる
広報活動の行き詰まりを打開するには、情報の受け手である住民の声に耳を傾けることが非常に効果的です。住民の関心やニーズを理解することで、より響く広報内容を企画することができます。
住民の声を集める方法:
- 広報モニター制度:一般住民から広報モニターを募集し、定期的にフィードバックを得る
- アンケート調査:広報誌やWebサイト、イベント会場などでアンケートを実施
- 住民座談会・ワークショップ:テーマを設定して意見交換を行う場を設ける
- SNSのコメント分析:投稿へのコメントや反応から関心事を把握
- 窓口担当者からの情報収集:住民と直接接する職員からよくある質問や要望を収集
広報モニター制度は、継続的に住民の意見を取り入れる効果的な方法です。例えば、年齢や居住地域、職業などを考慮して10〜20名程度のモニターを募集し、広報誌やWebサイトについての感想や改善点を定期的に聞くことで、住民目線の課題発見につながります。
また、「何を知りたいですか?」という漠然とした質問ではなく、「子育て情報で最も知りたいことは何ですか?」「防災情報はどのような形式で提供されると役立ちますか?」など、具体的なテーマに絞った質問をすることで、より実用的な意見を集めることができます。
住民の声を広報に活かすポイント:
- 意見の可視化:集めた意見を整理し、傾向や優先度を明確化
- 迅速な改善:すぐに対応できる点は速やかに改善し、成果を示す
- フィードバックの共有:どのような意見があり、どう対応したかを公表
- 継続的な対話:一度きりでなく、改善後の評価も含めた継続的なプロセス
- 組織内共有:住民の声を関連部署と共有し、全庁的な改善につなげる
住民の声を取り入れる際に重要なのは、単に意見を聞くだけでなく、それに基づいて実際に広報活動を改善し、その結果をフィードバックすることです。「あなたの声を聴きました」「こう変わりました」という循環を作ることで、住民の参画意識が高まり、広報活動への関心も高まります。
地域外の視点を活用する
地域内だけの視点では気づきにくい魅力や課題を発見するために、地域外の人々の視点を積極的に取り入れることも有効な打開策です。「当たり前」と思っていることが、実は特別な魅力である場合も少なくありません。
地域外の視点を取り入れる方法:
- 観光客や来訪者へのインタビュー:地域の第一印象や魅力的に感じた点を聞く
- 移住者からの意見収集:移住の決め手や地域の良さを再評価
- ふるさと納税の寄付者アンケート:地域の魅力や期待することを調査
- 他自治体との交流・比較:類似自治体との情報交換や相互評価
- 外部専門家の招聘:広報やマーケティングの専門家による客観的評価
例えば、移住者は「移住前に知りたかった情報」や「移住後に発見した魅力」など、移住検討者に届けるべき情報について貴重な意見を持っています。移住者座談会や個別インタビューを通じて、外部から見た地域の魅力を掘り起こし、広報内容に反映させることができます。
また、SNSなどでの地域に関する投稿を分析することも有効です。特に観光客や来訪者が投稿する写真や感想には、地元の人が気づかない視点から捉えた地域の魅力が表れていることがあります。これらの「外部の目」で発見された魅力を、広報コンテンツとして活用することで、新鮮な情報発信が可能になります。
地域外の視点を活かす際のポイント:
- 固定観念を捨てる:「その程度のことは当たり前」という思い込みを排除
- 多様な意見の収集:年齢、性別、出身地などが異なる多様な人々の視点を集める
- 否定的意見も活用:批判的な意見も改善のチャンスとして前向きに捉える
- 地域資源の再評価:当たり前と思っていた風景、食文化、習慣などを見直す
- 地域内外の「ギャップ」に注目:認識の違いがある点に広報のヒントがある
地域外の視点を活用する際は、単に「良いところ」だけでなく、「改善すべき点」や「わかりにくかった点」なども積極的に聞くことが重要です。例えば、「自治体のWebサイトで情報が見つけにくかった」という指摘は、情報設計の改善につながる貴重なフィードバックとなります。
Webプロモーションを支援するツールの活用
限られた人員や予算の中で効果的なWebプロモーションを展開するには、専門的なツールやプラットフォームの活用が有効です。特に移住促進や観光振興、企業誘致などを目的とした広域的な情報発信には、デジタル広告やマーケティングツールが力を発揮します。
活用できる主なWebプロモーションツール:
- 広告配信プラットフォーム:Google広告、SNS広告など特定のターゲットに情報を届ける
- アクセス解析ツール:Google Analyticsなどサイト訪問者の行動を分析
- SEO(検索エンジン最適化)ツール:検索順位向上のための分析と対策
- コンテンツ管理システム(CMS):Webサイトのコンテンツ更新を効率化
- ソーシャルメディア管理ツール:複数のSNSアカウントを一元管理
例えば、「まちあげ」のような自治体向けWebプロモーション支援プラットフォームは、自治体が取り組む各事業に興味関心を持つユーザーに対して、効果的な広告を配信する仕組みを提供しています。マイクロアドのデータプラットフォーム「UNIVERSE」が保有するWeb上の行動履歴や位置情報データを分析し、より親和性の高い層を捉えることで、最適化された広告配信を実現します。
このようなツールを活用することで、「移住に関心がある30代子育て世代」「特定の趣味を持つ観光客」など、従来の広報では届きにくかった特定のターゲット層に効率的にアプローチすることが可能になります。
ツール活用のポイント:
- 目的の明確化:何を達成したいのか、どんなターゲットにリーチしたいのかを明確に
- 費用対効果の検討:予算に見合ったツールの選択と期待効果の設定
- 段階的な導入:小規模な試行から始め、効果を確認しながら拡大
- 内部人材の育成:外注だけに頼らず、操作やデータ分析のスキルを習得
- 結果分析と改善:単なる数値だけでなく、具体的な成果につながったかを評価
Webプロモーションツールを活用する際は、単に「導入した」ことで満足せず、その結果を細かく分析し、継続的に改善していくプロセスが重要です。例えば、どのような広告表現や訴求ポイントが反応を得たか、どの時間帯にアクセスが多かったかなどのデータを分析し、次のプロモーション施策に活かすことで、効果を最大化することができます。
また、こうしたデジタルマーケティングの知見は、Webだけでなく従来の広報媒体にも応用可能です。例えば、Webでの反応が良かったコンテンツを広報誌でも取り上げる、人気のあったキャッチコピーをポスターにも使用するなど、オンラインとオフラインの連携により、より効果的な広報活動を展開することができます。
広報活動に行き詰まりを感じたときこそ、従来の方法や考え方にとらわれず、新たな視点や手法を積極的に取り入れるチャンスです。住民の声に耳を傾け、地域外の視点を取り入れ、新しい広報手段やツールを活用することで、より効果的な情報発信が可能になります。重要なのは、小さな一歩から始め、継続的に改善していく姿勢です。
多様な住民に届ける広報の工夫

自治体の住民は年齢、性別、国籍、障がいの有無など多様な属性を持ち、情報の受け取り方や必要とする内容も異なります。効果的な広報活動を展開するためには、この多様性を考慮した情報発信が求められます。ここでは、様々な住民層に情報を届けるための具体的な工夫について解説します。
高齢者と若者両方に効果的な情報発信
年齢層によって情報の入手経路や内容の理解度が大きく異なるため、世代を超えて効果的に情報を届けるには工夫が必要です。特に、デジタルネイティブの若者とデジタルデバイドの課題を抱える高齢者の両方にリーチすることは大きな課題です。
高齢者に情報を届けるポイント:
- 紙媒体の重視:広報誌や回覧板、紙のお知らせなど伝統的なメディアの活用
- 文字の大きさと読みやすさ:12ポイント以上の文字サイズ、明確なコントラスト
- 平易な言葉遣い:専門用語や横文字、デジタル用語などを避ける
- 地域コミュニティとの連携:自治会や老人クラブなど既存のネットワークの活用
- 対面・電話での情報提供:デジタルでは補完できない直接的なコミュニケーション
若者に情報を届けるポイント:
- SNSや動画の活用:Instagram、X、TikTokなど若者が日常的に利用するプラットフォーム
- ビジュアル重視:文字より画像・動画を中心としたビジュアルコミュニケーション
- 簡潔で要点を絞った内容:長文より短く的確なメッセージ
- 若者の関心事に合わせた切り口:環境問題、キャリア、趣味など若年層の興味を引くトピック
- インフルエンサーやコミュニティとの連携:地元の学生団体や若手クリエイターとのコラボレーション
世代を超えて情報を届けるための工夫:
- クロスメディア戦略:複数のメディアを組み合わせ、同じ情報を様々な形で発信
- 世代間交流の促進:若者と高齢者が情報を共有する場や機会の創出
- デジタルデバイド解消の取り組み:高齢者向けのスマホ教室やデジタル活用支援
- ユニバーサルデザインの導入:年齢を問わず理解しやすいデザインや言葉遣い
- 多層的なコンテンツ設計:概要は簡潔に、詳細は必要に応じて提供できる構成
例えば、市の重要な政策変更を伝える場合、広報誌での詳細な解説、Webサイトでの要点まとめ、SNSでの簡潔な告知、地域の集会での説明会など、複数のチャネルを通じて情報を発信することで、様々な年齢層にリーチすることができます。
また、QRコードを活用して紙媒体からデジタルコンテンツへの誘導を図るなど、世代間のギャップを埋める工夫も有効です。高齢者と若者の両方をターゲットにする場合、使用するメディアだけでなく、内容の表現方法や提供する情報の詳細度も考慮する必要があります。
多言語対応による多文化共生の推進
近年、在留外国人の増加や訪日観光客の回復により、多言語での情報提供の重要性が高まっています。言語の壁を越えて情報を届けることは、多文化共生社会の実現とともに、地域の国際化や観光振興にも寄与します。
多言語対応のポイント:
- 地域の外国人構成を把握:どの国・地域出身者が多いかを調査し、優先言語を決定
- 重要情報の優先対応:防災、医療、教育など生活に直結する情報を優先的に多言語化
- 「やさしい日本語」の活用:難しい日本語を避け、簡潔で理解しやすい表現を用いる
- ピクトグラム(絵文字)の活用:言語に頼らない視覚的な情報伝達
- 外国人コミュニティとの連携:翻訳の品質チェックや情報拡散への協力依頼
多言語情報提供の方法:
- 多言語版広報誌・パンフレット:主要外国語での紙媒体の作成
- 多言語対応Webサイト:言語切替機能を備えたWebサイトの構築
- 翻訳アプリとの連携:QRコードから翻訳アプリへ誘導
- 自動翻訳ツールの活用:AI翻訳技術を用いたリアルタイム翻訳
- 多言語対応の防災アプリ:緊急時の多言語情報提供
「やさしい日本語」は、外国人にもわかりやすい簡易な日本語表現のことで、多言語対応の補完として効果的です。例えば、「避難準備・高齢者等避難開始」を「危険かもしれません。逃げる準備をしてください。お年寄りは今すぐ逃げてください」といった具体的でわかりやすい表現に言い換えることで、日本語学習者でも理解しやすくなります。
多言語対応を進める際の課題として、翻訳コストや正確性の確保が挙げられます。これに対処するため、機械翻訳と人による確認を組み合わせる、地域の外国人住民や語学ボランティアとの協力体制を構築する、国際交流協会などの外部機関と連携するなどの方法が有効です。
また、多言語対応は単なる翻訳にとどまらず、外国人住民のニーズに合わせた情報提供という視点も重要です。例えば、母国とは異なる日本の行政システムや生活ルールについての解説、外国人が特に関心を持つ文化イベントや交流機会の案内など、情報の内容にも配慮が必要です。
アクセシビリティに配慮した広報
障がいのある方や高齢者など、様々な制約を持つ人々にも等しく情報が届くようにするためには、アクセシビリティ(情報やサービスへのアクセスのしやすさ)への配慮が不可欠です。
アクセシビリティ向上のポイント:
- 視覚障がい者への配慮:点字資料、音声読み上げ対応、文字拡大機能
- 聴覚障がい者への配慮:手話動画、字幕付き映像、文字による情報提供
- 知的・発達障がい者への配慮:わかりやすい言葉遣い、図解の活用
- 身体障がい者への配慮:操作しやすいWebデザイン、情報入手手段の多様化
- 高齢者への配慮:見やすいフォントや色使い、直感的な操作性
Webアクセシビリティの向上策:
- JIS X 8341-3準拠:ウェブアクセシビリティの日本工業規格に準拠したサイト設計
- 代替テキストの提供:画像に対する説明文の付与(スクリーンリーダー対応)
- キーボード操作の対応:マウスを使わなくても全ての機能が利用可能
- 十分なコントラスト:背景と文字の色のコントラストを確保
- 文字サイズ変更機能:閲覧者が文字サイズを調整できる機能
紙媒体でのアクセシビリティ向上策:
- ユニバーサルデザインフォント:識別しやすい書体の採用
- 適切な文字サイズとコントラスト:読みやすさを優先したデザイン
- 音声コード(SPコード)の導入:専用機器で読み取り可能な音声情報の埋め込み
- 点字版・拡大版の作成:視覚障がい者向けの代替媒体の提供
- 図表への説明文付与:視覚的情報を言葉でも理解できるよう配慮
アクセシビリティに配慮した広報活動の好例として、東京都の「声の広報」があります。これは広報誌の内容を音声化したもので、視覚障がい者や高齢者が電話やインターネットで聴くことができます。また、多くの自治体では広報誌の点字版や拡大文字版を発行しており、希望者に配布しています。
Webサイトのアクセシビリティについては、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を参考に、定期的な診断と改善を行うことが推奨されています。また、公式サイトだけでなく、SNSでの投稿や動画コンテンツにおいても、代替テキストや字幕の提供などアクセシビリティへの配慮が重要です。
障がい者団体や当事者との定期的な意見交換や、アクセシビリティ診断のための外部専門家の活用なども効果的です。実際に利用する立場からのフィードバックを得ることで、当事者にとって本当に使いやすい情報提供が可能になります。
多様な住民に広報情報を届けるためには、「誰一人取り残さない」という視点が重要です。年齢や言語、障がいの有無にかかわらず、すべての住民が必要な情報にアクセスできる環境を整えることは、自治体の基本的な責務と言えるでしょう。多様性を考慮した広報活動は手間やコストがかかることもありますが、それは地域社会の包摂性を高め、すべての住民が安心して暮らせるまちづくりにつながる重要な投資です。
危機管理時の効果的な広報

自然災害やパンデミック、大規模事故など危機的状況においては、通常時とは異なる広報活動が求められます。適切な情報を迅速かつ正確に提供することは、住民の生命や財産を守るために不可欠です。ここでは、危機管理時における効果的な広報のあり方について解説します。
災害時に求められる広報のあり方
災害時の広報は、住民の安全確保と不安解消を最優先に考えた情報提供が基本となります。通常の広報活動とは異なる優先順位や方法で情報を発信する必要があります。
災害時広報の基本原則:
- 迅速性:できるだけ早く情報を提供する
- 正確性:確認された事実に基づいた情報を提供する
- 明瞭性:専門用語を避け、わかりやすく伝える
- 一貫性:情報元を一本化し、矛盾した情報を出さない
- 多様性:様々な手段を用いて情報を届ける
災害時に提供すべき主な情報:
- 被害状況:災害の規模や影響範囲、人的・物的被害の状況
- 避難情報:避難指示、避難所の開設状況や場所、避難経路
- ライフライン情報:電気・ガス・水道・通信の状況と復旧見込み
- 交通情報:道路・鉄道・バスなどの運行状況と復旧見込み
- 医療情報:診療可能な医療機関、救護所の設置状況
- 物資・支援情報:食料・水・物資の配給場所や時間、支援制度
災害時は情報の錯綜や誤情報の拡散が起こりやすいため、公式情報として自治体が発信する情報の信頼性を確保することが重要です。情報の出所を明確にし、確認済みの情報と未確認の情報を区別して伝えることで、混乱を防ぐことができます。
また、情報が更新されない場合でも「現在も状況確認中です」「前回の情報から変更はありません」など定期的に発信することで、住民に安心感を与えることが大切です。
災害時に活用すべき広報手段:
- 防災行政無線:広範囲に一斉に情報を伝達できる
- 緊急速報メール:エリア内の携帯電話に一斉配信できる
- SNS:リアルタイムでの情報更新が可能
- 公式Webサイト:詳細情報を掲載できる
- 災害FM放送:臨時災害放送局を開設して情報提供
- 広報車:電源がなくても情報伝達が可能
- 掲示板:避難所や公共施設での情報掲示
災害時には停電や通信障害が発生する可能性があるため、電源や通信に依存しない手段も含めた多重的な情報伝達体制を構築しておくことが重要です。また、高齢者や障がい者、外国人など情報弱者と呼ばれる方々への配慮も不可欠です。
緊急時の情報発信ガイドライン
緊急時に迅速かつ適切な情報発信ができるよう、あらかじめガイドラインを策定しておくことが重要です。事前に判断基準や手順を明確にしておくことで、危機発生時の混乱を最小限に抑えることができます。
緊急時情報発信ガイドラインに含めるべき要素:
- 情報収集体制:誰がどのような情報を収集するか
- 情報発信の判断基準:どのレベルの情報をいつ発信するか
- 発信内容のテンプレート:状況別の定型文を事前に用意
- 発信権限と承認フロー:誰が発信を決定・承認するか
- 情報発信ツールの優先順位:状況に応じた最適なツールの選択
- 外部機関との連携方法:警察、消防、医療機関などとの情報共有
- 多言語対応・アクセシビリティ対応:あらゆる住民に情報を届ける方法
情報発信のテンプレートを用意しておくことは、緊急時の迅速な対応に大いに役立ちます。例えば、警戒レベルごとの避難情報や、ライフライン被害報告、避難所開設のお知らせなど、状況別に文案を事前に作成しておき、必要に応じて具体的な情報を埋め込むだけで発信できるようにしておくと良いでしょう。
緊急時の情報発信で心がけるべきこと:
- 「5W1H」を明確に:いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように
- 優先順位をつける:命に関わる情報を最優先に
- 簡潔明瞭に伝える:重要情報を先に、詳細は後で
- 行動指示を具体的に:「注意してください」ではなく「〇〇してください」
- 誤情報への迅速な対応:デマや誤報に対する正確な情報提供
緊急時には情報の受け手の心理状態も通常とは異なります。不安や恐怖で冷静な判断が難しい状況であることを考慮し、シンプルで明確なメッセージを心がけることが大切です。また、何をすべきか、何をしてはいけないかという行動指示を具体的に伝えることで、住民の適切な行動を促すことができます。
例えば、「危険ですので注意してください」という抽象的な表現よりも、「急な増水の恐れがあります。河川には近づかないでください」といった具体的な表現の方が効果的です。
平常時からの備え
効果的な危機管理広報を実現するためには、危機が発生する前からの準備が不可欠です。平常時からの取り組みが、緊急時の情報発信の質を大きく左右します。
平常時に準備しておくべきこと:
- 危機管理広報計画の策定:想定される危機ごとの対応方針を文書化
- 情報発信ツールの整備:多様な媒体を活用できる環境づくり
- 定期的な訓練の実施:広報担当者の危機対応能力向上
- バックアップ体制の構築:機材や人員の代替手段の確保
- 関係機関とのネットワーク形成:警察、消防、医療機関、メディアとの連携
特に重要なのが、住民の情報入手経路の把握です。どのような媒体を通じて情報を得ているのか、日常的に調査しておくことで、緊急時に効果的な情報発信が可能になります。例えば、高齢者が多い地域では防災行政無線や広報車の活用が、若年層が多い地域ではSNSや緊急速報メールの活用が効果的かもしれません。
平常時の防災広報活動:
- ハザードマップの配布と説明:地域の災害リスクと避難方法の周知
- 避難所・避難経路の定期的な広報:住民の認知度を高める
- 防災訓練の実施と広報:参加を促し、実践的な知識を普及
- 災害時の情報入手方法の周知:緊急速報メールの設定方法、防災アプリの紹介など
- 防災意識啓発キャンペーン:定期的な注意喚起と準備の促進
平常時から防災に関する情報を定期的に発信することで、住民の防災意識を高め、いざというときの適切な行動につなげることができます。特に転入者や若年層など防災知識が不足しがちな層に向けた継続的な情報提供が重要です。
また、SNSのフォロワー数を増やしたり、災害情報アプリのダウンロードを促進したりするなど、緊急時の情報発信チャネルを平常時から整備しておくことも効果的です。例えば、イベント情報や生活情報など普段から役立つ情報を発信することで、公式アカウントのフォロワー獲得につなげる自治体も増えています。
災害時の広報体制整備:
- 広報担当者の役割分担:情報収集、発信、メディア対応などの明確化
- 代替要員の確保と育成:担当者不在時や長期対応のための体制
- 広報拠点のバックアップ:庁舎被災時の代替広報拠点の確保
- 非常用電源・通信手段の確保:停電や通信障害時の対応準備
- 多言語対応・要配慮者対応の準備:翻訳体制や専門的支援体制の構築
東日本大震災や熊本地震など過去の災害では、自治体自身が被災して広報機能が麻痺するケースもありました。こうした事態に備え、代替拠点や代替手段を確保しておくことが重要です。
災害対応は自治体単独ではなく、周辺自治体や都道府県、国などと連携して行われます。平常時から相互応援協定を結んだり、共同訓練を実施したりすることで、災害時の広報連携をスムーズに行える体制を構築しておくことも大切です。
危機管理広報は、住民の命を守るための最も重要な役割の一つです。平常時からの準備と訓練、そして実際の危機発生時の適切な情報発信により、住民の安全確保と被害軽減に大きく貢献することができます。自治体の広報担当者は、こうした危機管理広報の重要性を認識し、継続的な体制整備と能力向上に取り組むことが求められています。
まとめ:効果的な自治体広報の実現に向けて

これまで見てきたように、自治体広報は単なる情報提供にとどまらず、住民との信頼関係構築や地域の活性化、危機管理など、多岐にわたる役割を担っています。デジタル技術の急速な進化や社会環境の変化により、自治体広報のあり方も大きく変わりつつあります。本記事のポイントを振り返りながら、効果的な自治体広報の実現に向けた道筋を考えてみましょう。
本記事の主要ポイントの振り返り
広報の定義と目的を再認識する
自治体広報は、行政からの一方的な「お知らせ」ではなく、住民と行政をつなぐ双方向コミュニケーションであり、「地域住民への情報提供」「住民の地域参画意識醸成」「地域外への魅力発信」という3つの目的を持っています。効果的な広報活動を展開するためには、この原点に立ち返ることが大切です。
メディアの特性を理解し、目的に合わせた選択をする
広報誌、Webサイト、SNS、動画、メールマガジンなど、それぞれのメディアには固有の特性があります。ターゲットとなる層や伝えたい情報の性質に合わせて最適なメディアを選択し、複数のメディアを組み合わせた「クロスメディア戦略」を展開することが効果的です。
住民ニーズを把握し、ターゲットを明確にする
効果的な広報活動のためには、住民が本当に必要としている情報は何かを理解し、情報の受け手を明確にイメージすることが重要です。アンケート調査やモニター制度などを通じて住民の声を集め、広報内容に反映させることで、より価値のある情報発信が可能になります。
広報戦略を明確に定め、PDCAサイクルを回す
「何のために」「誰に対して」「どのような情報を」「どのように伝えるか」を明確にした戦略を立て、その効果を測定し、改善するサイクルを確立することが重要です。データに基づく分析と継続的な改善が、広報活動の質を高めていきます。
デジタル技術とAIを活用し、効率的かつ効果的な広報を実現する
デジタルトランスフォーメーション(DX)やAI技術の活用により、広報業務の効率化と高度化が可能になっています。新しい技術を適切に取り入れながら、人間にしかできない創造的な企画立案や住民との対話に注力することで、より効果的な広報活動が実現できます。
多様性とアクセシビリティに配慮する
年齢、性別、国籍、障がいの有無など、多様な属性を持つ住民に情報が届くよう、多言語対応やアクセシビリティ向上に取り組むことが重要です。「誰一人取り残さない」という視点で広報活動を見直し、すべての住民に必要な情報が届く環境を整えることが求められています。
危機管理広報の体制を整備する
災害やパンデミックなどの危機的状況では、正確かつ迅速な情報提供が住民の生命を守る鍵となります。平常時から危機管理広報の体制を整備し、訓練を重ねることで、いざというときに効果的な広報活動を展開できるようにしておくことが重要です。
これからの自治体広報に求められること
今後の自治体広報には、以下のような姿勢や取り組みがますます重要になってくるでしょう。
変化への柔軟な対応
技術の進化やメディア環境の変化、住民のライフスタイルや価値観の多様化など、広報を取り巻く環境は絶えず変化しています。こうした変化に柔軟に対応し、常に最適な広報のあり方を模索する姿勢が求められます。
広報の専門性の向上
効果的な広報活動を展開するためには、専門的な知識やスキルが不可欠です。広報担当者の育成や外部専門家との連携を通じて、組織全体の広報力を高めていくことが重要です。
住民との協働による広報
住民自身が情報発信者となる時代において、自治体だけが情報を独占するのではなく、住民と協働で地域の魅力や情報を発信していく姿勢が大切です。住民参加型の広報企画や、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用など、新しい形の広報活動を模索することが求められています。
持続可能な広報体制の構築
限られた予算や人員の中で継続的に質の高い広報活動を展開するためには、業務の効率化や優先順位の明確化、外部リソースの活用など、持続可能な広報体制の構築が必要です。
おわりに
自治体広報は、行政と住民をつなぐ重要な架け橋です。適切な情報を適切なタイミングで適切な方法で届けることで、住民の生活の質の向上に貢献し、地域の活性化を促進することができます。
本記事で紹介した様々なポイントや事例を参考に、それぞれの自治体の特性や課題に合わせた広報戦略を構築し、実践していくことで、より効果的な広報活動が実現できるでしょう。
重要なのは、広報活動を単なる「やるべき業務」としてではなく、地域づくりの重要な一翼を担う戦略的な活動として位置づけ、継続的に改善していく姿勢です。広報のプロフェッショナルとしての誇りと責任を持ち、住民に寄り添い、地域の未来を共に創る広報活動を展開していきましょう。
自治体広報の可能性は無限大です。これからも新しい発想と技術を取り入れながら、より良い地域社会の実現に向けて、広報活動を進化させていくことを期待しています。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















