自治体DX推進計画とは?7つの重点項目と段階的な進め方

住民中心のサービス改革と業務効率化の両立
自治体DXは単なるデジタル化ではなく、住民の利便性向上と行政業務の効率化・高度化を両立させるための本質的な変革。マイナンバー活用やオンライン手続きなどで「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す。
7つの重点取組と段階的アプローチ
フロントヤード改革、システム標準化、eLTAX活用、マイナンバー普及、セキュリティ強化、AI・RPA導入、テレワーク推進の7分野に取り組むとともに、段階的(気運醸成→方針策定→体制整備→施策実行)に推進することが成功の鍵となる。
課題克服と地域社会全体のデジタル化
アナログ文化、人材不足、財源制約、住民理解の不足といった課題を乗り越えるためには、トップのリーダーシップ、外部人材の活用、住民との対話などが不可欠。また、条例見直しや地域企業支援など、地域全体のデジタル化も併せて推進する必要がある。
政府が積極的に推進するデジタル化の波は、民間企業だけでなく地方自治体にも及んでいます。「自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、単なるデジタル技術の導入ではなく、行政サービスの質を高め、住民の生活をより豊かにするための重要な取り組みです。
2020年に総務省が策定した「自治体DX推進計画」は、自治体が重点的に取り組むべき事項や国による支援策を示した指針であり、2024年には第3.0版へと更新されました。昨今の人口減少や高齢化といった社会課題に対応するため、多くの自治体がDXによる業務効率化と住民サービスの向上を目指しています。
本記事では、自治体DX推進計画の概要から、7つの重点取組事項、推進するための段階的なステップ、先進事例まで、2024年最新の情報を踏まえて分かりやすく解説します。自治体職員の方はもちろん、自治体のデジタル化に関心をお持ちの方にも役立つ内容となっています。

自治体DXとは

「自治体DX」とは、地方自治体がデジタル技術を活用して行政サービスの提供方法や業務プロセスを変革し、住民の利便性や満足度を向上させることを目指す取り組みです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質
DXとは「Digital Transformation」の略称で、単にアナログな業務をデジタル化するだけではありません。デジタル技術を活用して業務やサービスを根本から変革し、新たな価値を創出することを指します。つまり、紙の申請書をPDF化するだけではなく、オンライン申請によって住民が24時間どこからでも手続きできるようにするなど、住民目線でのサービス改善を実現することが本質です。
自治体DXと一般的なDXの違い
民間企業におけるDXが主に企業価値や利益の向上を目的としているのに対し、自治体DXは「住民の利便性向上」「行政サービスの質の向上」「誰一人取り残さないデジタル社会の実現」といった公共的価値の創出を目指しています。
また、自治体DXでは、マイナンバーカードの活用や行政手続きのオンライン化など、国の政策と歩調を合わせた取り組みが求められるという特徴もあります。民間企業の独自性を重視したDXとは異なり、標準化や共通化を進めることで全国どこでも同じレベルのサービスを提供することを目指しています。
自治体DXに求められる視点
自治体DXを進めるにあたっては、以下の3つの視点が重要です:
- 住民中心の発想:住民のニーズや課題を起点にサービスを設計する
- バックオフィス改革:内部業務の効率化により職員の負担を軽減する
- データ活用:行政データを分析・活用して新たな価値を創出する
2024年6月時点での総務省の見解では、これらの視点に加えて「デジタルデバイド対策」の重要性も強調されています。DXの恩恵がすべての住民に行き渡るよう、高齢者や障がい者など、デジタル技術の活用が困難な方々への支援も自治体DXの重要な柱となっています。
自治体DX推進の目的と意義

自治体DXの推進には明確な目的と大きな意義があります。人口減少や高齢化が進む中で、限られた人的リソースで質の高い行政サービスを提供し続けるためには、デジタル技術の活用が不可欠です。
デジタル社会実現に向けた基本方針
政府が策定した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、目指すべきデジタル社会のビジョンとして、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化~」が示されています。
自治体には、このビジョンを実現するための具体的な取り組みが求められており、総務省が策定した自治体DX推進計画はその行動指針となっています。
自治体DX推進の3つの主要目的
1. 住民の利便性向上
自治体DXの最も重要な目的は、住民サービスの利便性を高めることです。従来は役所の窓口に出向く必要があった各種手続きをオンライン化することで、24時間365日どこからでも行政サービスを利用できるようになります。また、マイナンバーカードの活用により、複数の書類や手続きを一元化することで、住民の手続き負担を大幅に軽減できます。
2. 行政サービスの効率化・高度化
もう一つの重要な目的は、行政サービスの効率化と高度化です。AIやRPAなどのデジタル技術を活用することで、定型的な業務の自動化や効率化が可能になります。これにより、職員は複雑な判断を要する業務や住民との対話など、より価値の高い業務に注力できるようになります。また、テレワークの導入により、災害時や感染症流行時でも行政サービスを継続できる体制を構築できます。
3. データ活用による新たな価値創出
自治体が保有するデータを適切に分析・活用することで、地域課題の解決や新たな行政サービスの創出が可能になります。例えば、人口動態データと公共交通の利用データを組み合わせて分析することで、より効率的なバス路線の再編が可能になります。また、健康データと医療費データの分析により、効果的な健康増進施策の立案も可能になります。
自治体DX推進の社会的意義
自治体DXを推進する社会的意義としては、以下の点が挙げられます:
- 持続可能な行政運営:人口減少・高齢化が進む中でも、質の高い行政サービスを維持できる
- 地域活性化:デジタル技術の活用により、地域の産業振興や新たな雇用創出が期待できる
- 地域間格差の是正:標準化・共通化により、全国どこでも一定水準の行政サービスを享受できる
- 災害対応力の強化:デジタル技術を活用した防災情報の収集・分析・共有により、災害対応力が高まる
- 誰一人取り残さない社会の実現:デジタルデバイド対策を通じて、すべての住民がデジタル化の恩恵を受けられる
このように、自治体DXは単なる業務効率化の手段ではなく、より豊かで持続可能な地域社会を実現するための重要な取り組みと言えます。
自治体DX推進計画の概要
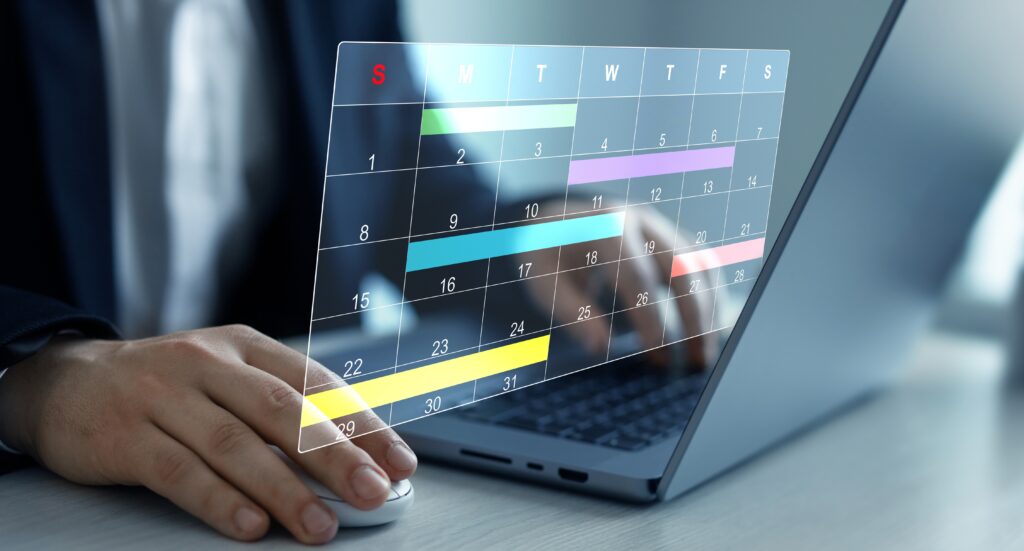
自治体DX推進計画は、総務省が2020年12月に策定し、その後も定期的に更新している計画書です。この計画は、自治体が重点的に取り組むべき事項や国による支援策を明確に示し、自治体のデジタル化を加速させることを目的としています。
推進計画の目的と変遷
自治体DX推進計画は、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」に基づき、自治体が住民サービスの向上と業務効率化を実現するための具体的な行動指針として作成されました。
当初は6つの重点取組事項が定められていましたが、2024年2月には第2.3版に更新され、「公金収納におけるeLTAXの活用」が追加されて7つになりました。さらに、2024年6月には第3.0版として、これらの取組事項の詳細な進め方や最新の成功事例が追加されています。
総務省が示す7つの重点取組事項
1. 自治体フロントヤード改革の推進
住民と行政との接点(フロントヤード)の改革です。「書かせない、待たせない、迷わせない、行かせない」をモットーに、住民サービスの利便性向上や業務効率化を図ります。これにより、定型業務から職員を解放し、企画立案や相談対応など、より付加価値の高い業務に人材をシフトさせることが可能になります。
2. 自治体の情報システムの標準化・共通化
2025年度までに、基幹系17業務(住民基本台帳、固定資産税、介護保険など)のシステムを国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行する取り組みです。これにより、カスタマイズコストの削減や自治体間の互換性向上、ベンダーロックインの防止などのメリットが期待されています。また、ガバメントクラウド(Gov-Cloud)の活用も推進されています。
3. 公金収納におけるeLTAXの活用
eLTAX(地方税ポータルシステム)を活用して、地方税や各種公金の収納業務を効率化する取り組みです。2024年から新たに追加された項目で、納税者の利便性向上と自治体の事務負担軽減を目指しています。オンラインでの税金納付が24時間可能になり、自治体側でもリアルタイムでの収納状況確認が可能になります。
4. マイナンバーカードの普及促進・利用推進
マイナンバーカードを活用したデジタル社会の基盤整備を目指します。カードの交付促進だけでなく、行政手続きのオンライン化やカードの多目的利用(図書館カードや健康保険証など)を推進し、住民の利便性向上を図ります。2022年末に全国民の交付を目指していましたが、現在も普及促進の取り組みが続けられています。
5. セキュリティ対策の徹底
デジタル化を進める上で不可欠なセキュリティ対策の強化です。「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき、自治体のセキュリティ体制を整備します。具体的には、最高情報セキュリティ責任者(CISO)の任命、セキュリティインシデント対応チーム(CSIRT)の設置、有事の対応策(ICT-BCP)の整備などが求められています。
6. 自治体のAI・RPAの利用推進
AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などのデジタル技術を活用して、定型業務の自動化や効率化を図る取り組みです。窓口での住民対応を支援するAIチャットボットの導入や、申請書処理を自動化するRPAの活用などにより、業務の効率化と住民サービスの向上を目指します。
7. テレワークの推進
ICTを活用して、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現する取り組みです。災害時や感染症流行時の業務継続性の確保だけでなく、働き方改革や優秀な人材確保の観点からも重要視されています。セキュリティを確保しつつ、どこからでも行政業務を遂行できる環境の整備が求められています。
自治体DX推進計画の実施体制
これらの重点取組事項を効果的に推進するために、自治体には以下のような体制整備が求められています:
- 首長によるリーダーシップと強いコミットメント
- CIO(最高情報責任者)の設置(多くの場合、副市区町村長などが兼任)
- 専門知識を持つCIO補佐官の任用(外部人材の活用も推奨)
- 情報政策部門と業務改革部門の連携
- デジタル人材の確保・育成
2024年4月の調査では、CIOを任命している地方自治体は半数以上に達しているものの、その多くは副知事や副市長などの兼任であり、専門性を持ったCIO補佐官の配置はまだ十分とは言えない状況です。
総務省は、自治体DXを成功させるために必要な体制やスキル、取り組み手順を詳細に示した「自治体DX全体手順書」を公開し、自治体の取り組みを支援しています。
自治体DXに取り組むメリット
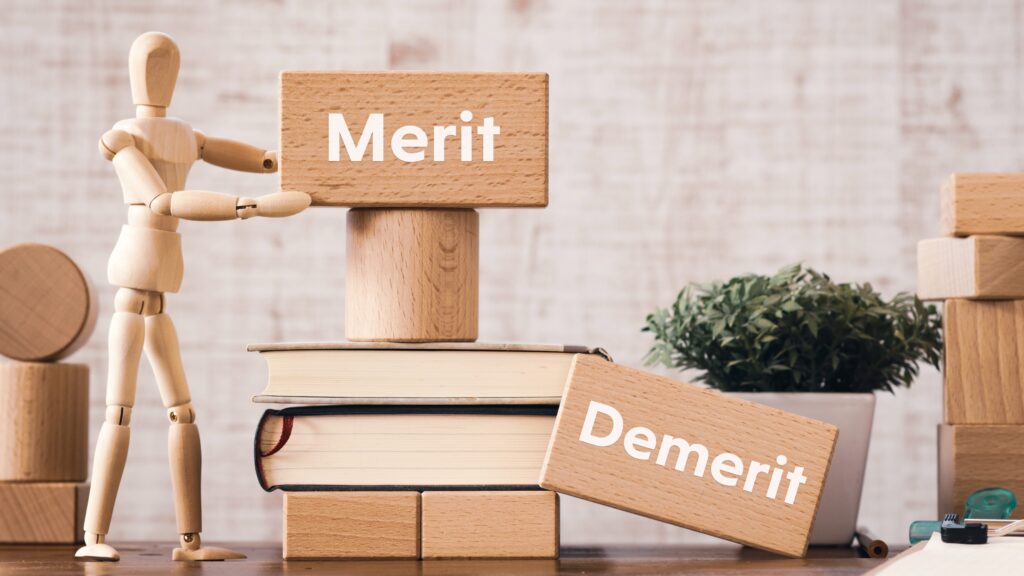
自治体がDXに取り組むことで、自治体自身はもちろん、住民や地域社会全体に多くのメリットがもたらされます。具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
役所内の業務効率化
自治体DXの大きなメリットの一つが、行政業務の効率化です。これにより、人的リソースを効果的に活用し、より質の高いサービスを提供することが可能になります。
定型業務の自動化
AI・RPAを活用することで、これまで手作業で行っていた定型的な業務を自動化できます。例えば、申請書の内容チェックや情報の転記作業、単純な問い合わせ対応などを自動化することで、業務時間の短縮と人的ミスの削減が実現します。あるデータによれば、RPA導入により対象業務の作業時間が平均で約70%削減されたという結果も報告されています。
ペーパーレス化による業務改善
紙の書類をデジタル化することで、保管スペースの削減だけでなく、検索性の向上や情報共有の円滑化が図れます。また、テレワーク環境下でも必要な情報にアクセスできるようになり、業務の継続性が高まります。さらに、紙の使用量や印刷コストの削減にもつながり、環境負荷の軽減と経費削減の両方を実現できます。
業務プロセスの見直しと最適化
DXを進める際には、既存の業務プロセスを見直し、最適化することが不可欠です。これにより、不要な作業の削減や業務の標準化が進み、業務全体の効率が大幅に向上します。福島県昭和村の事例では、電子決裁システムの導入により、わずか8ヶ月で全庁的な業務改革を実現し、決裁にかかる時間を大幅に短縮することに成功しています。
住民サービスの利便性向上
自治体DXの最大の受益者は住民です。デジタル技術を活用することで、より便利で質の高い行政サービスを提供することができます。
24時間365日のサービス提供
行政手続きのオンライン化により、役所の開庁時間に関係なく、いつでもどこからでも各種申請や届出が可能になります。仕事や家事、育児などで平日に役所に行くことが難しい住民にとって、この時間的制約からの解放は大きなメリットです。
ワンストップサービスの実現
マイナンバーカードの活用や各種システムの連携により、複数の手続きを一度に完了できるワンストップサービスが実現します。例えば、引っ越し時に必要な各種住所変更手続きを一括して行えるようになれば、住民の手続き負担が大幅に軽減されます。
行政サービスの質の向上
AIやデータ分析技術を活用することで、住民一人ひとりのニーズに合ったパーソナライズされたサービスの提供が可能になります。また、チャットボットなどを活用した24時間対応の問い合わせ窓口の設置により、住民の疑問にすぐに答えられる体制を構築できます。熊本県小国町では、災害時の被災状況報告アプリを作成し、被災状況の迅速な把握と対応が可能になり、住民サービスの質が向上しました。
地域社会全体のDX促進
自治体がDXに積極的に取り組むことで、地域社会全体のデジタル化が進み、様々な波及効果が期待できます。
地域産業のデジタル化支援
自治体が率先してDXに取り組むことで、地元の中小企業や商店などもデジタル化に取り組みやすい環境が整います。自治体が提供するオープンデータを活用した新ビジネスの創出や、デジタル技術を活用した地域課題解決の取り組みが活性化するでしょう。
デジタル人材の育成・確保
自治体DXを推進する過程で、職員のデジタルリテラシーが向上し、地域におけるデジタル人材の層が厚くなります。また、外部人材の登用や民間企業との連携を通じて、地域内のデジタル人材の循環が促進されます。
地域コミュニティの活性化
デジタル技術を活用した住民参加の仕組みにより、地域課題の発見・解決に住民が積極的に関わる機会が増えます。SNSやアプリを活用した情報共有や意見交換により、地域コミュニティの活性化につながります。福島県会津若松市では、住基台帳と地理情報システムを連携させた統合GISを活用し、防災や地域施策に役立てる取り組みを行っています。
財務効果と持続可能な行政運営
自治体DXは、長期的には財政面でもプラスの効果をもたらし、持続可能な行政運営を支えます。
コスト削減
業務の効率化やシステムの標準化・共通化により、人件費や維持管理費の削減が期待できます。紙の使用量削減、施設の維持管理費削減なども含め、中長期的には大きなコスト削減効果が見込まれます。
予算配分の最適化
データに基づく政策立案(EBPM:Evidence-Based Policy Making)により、効果的な施策に予算を重点配分することが可能になります。限られた予算を最大限に活用し、住民ニーズに合った政策を展開できるようになります。
新たな財源の創出
オープンデータの活用促進や官民連携の取り組みにより、新たな経済活動が生まれ、税収増加につながる可能性があります。また、未利用の公共施設や遊休地の有効活用などにより、新たな財源を確保することも可能になります。
情報セキュリティの強化
適切に計画された自治体DXは、情報セキュリティの強化にもつながります。
セキュリティ対策の体系化
DXを進める過程で、情報セキュリティポリシーの見直しや体制整備が行われ、より体系的なセキュリティ対策が実現します。CISOの任命やCSIRTの設置により、セキュリティ事故への対応力も向上します。
個人情報保護の強化
紙の書類の紛失や誤送付などのリスクが軽減され、適切なアクセス制御やログ管理により、個人情報の適切な取り扱いが徹底されます。これにより、個人情報漏洩のリスクが大幅に低減します。
災害時の業務継続性確保
クラウドサービスの活用やデータのバックアップ体制の整備により、災害時でも業務を継続できる環境が構築されます。住民情報や重要な行政データが安全に保管され、災害からの迅速な復旧が可能になります。
このように、自治体DXに取り組むことで、業務効率化や住民サービスの向上だけでなく、地域全体の発展や持続可能な行政運営にもつながるのです。長期的な視点で見れば、DXへの投資は必ず自治体と住民に大きなリターンをもたらすでしょう。
自治体DXが進まない現状と課題

自治体DXの重要性は広く認識されているものの、実際の導入や推進においては様々な障壁が存在します。ここでは、自治体DXが進まない主な要因と、それらの課題に対する対策について考察します。
総務省の自治体DX推進計画でも、DXの導入・推進における様々な障壁が指摘されています。多くの自治体がこれらの課題に直面しており、解決に向けた取り組みが進められています。
アナログ文化の根強さ
紙文化とハンコ文化
多くの自治体では、依然として紙の書類や押印による業務プロセスが主流となっています。長年の慣習により形成された「紙文化」「ハンコ文化」は、職員にとって安心感があり、変更への抵抗が大きいのが現状です。例えば、電子決裁システムが導入されていても、念のために紙の決裁も並行して行う「二重決裁」が行われているケースも少なくありません。
対面主義
「重要な手続きや相談は対面で行うべき」という考え方も根強く、オンライン手続きへの移行に慎重な姿勢が見られます。特に高齢者の多い地域では、対面でのサービス提供を求める声が強く、全面的なオンライン化に踏み切れない自治体も多いです。
対策
アナログ文化を変革するためには、トップのリーダーシップによる意識改革と、段階的な移行が効果的です。例えば、まずは内部の簡易な決裁から電子化を始め、成功体験を積み重ねていくアプローチや、紙とデジタルの併用期間を設けて徐々に移行していく方法などが考えられます。また、「デジタル・デイ」のような特定の日にはデジタルツールのみを使用するイベントを実施し、職員のデジタル活用を促進する取り組みも有効です。
DXに対する理解不足
DXの本質的理解の欠如
DXは単なるデジタル化ではなく、デジタル技術を活用した業務やサービスの変革です。しかし、多くの自治体では「システム導入=DX」という誤った認識があり、既存の業務プロセスを見直すことなく、単にデジタルツールを導入するだけにとどまっているケースが見られます。
住民視点の欠如
自治体DXの目的は最終的に住民サービスの向上にあります。しかし、内部業務の効率化に焦点を当てるあまり、住民にとってのメリットや使いやすさを考慮せずにシステムを導入してしまうケースも少なくありません。
対策
DXの本質を理解するための研修や勉強会を実施し、先進事例の視察や外部専門家との交流を通じて知見を深めることが重要です。また、住民参加型のワークショップやモニター制度を導入し、住民の視点を取り入れたサービス設計を行うことも効果的です。特に福島県昭和村のように、内製アプリを短期間で導入し、具体的な成果を上げている事例を参考にすることで、DXの実践的な理解が進むでしょう。
デジタル人材の不足
専門人材の確保難
DXを推進するためには、ITやデジタル技術に精通した人材が不可欠ですが、多くの自治体ではそうした専門人材の確保に苦労しています。民間企業との人材獲得競争や、地方自治体の給与水準の問題などが影響しています。2024年4月の調査では、CIOを設置している自治体は増加しているものの、その多くは副知事や副市長などの兼任であり、専門知識を持つCIO補佐官の配置は十分に進んでいません。
一般職員のデジタルリテラシー不足
DX推進には、一部の専門家だけでなく、全職員のデジタルリテラシー向上が必要です。しかし、特に中高年層の職員を中心に、デジタルツール活用への苦手意識や抵抗感が根強く残っています。
対策
デジタル人材の確保については、外部人材の活用(任期付職員、地域おこし協力隊など)や、複数の自治体での人材共有、民間企業との人材交流などの方法が考えられます。また、既存職員のスキルアップのため、実践的な研修プログラムの実施やOJTの充実、デジタル活用に積極的な職員への評価や処遇の工夫も有効です。福島県磐梯町のように、副町長直下にデジタル変革戦略室を設置し、CDOやCDO補佐官などの外部人材を積極的に登用している事例は参考になります。
行政と住民とのコミュニケーション不足
DX推進の意義や効果の伝達不足
自治体DXの恩恵を住民が実感するためには、その意義や効果を分かりやすく伝える必要がありますが、多くの自治体ではその説明や広報が不十分です。例えば、マイナンバーカードの普及促進においても、その具体的なメリットが住民に十分理解されていないケースが多く見られます。
住民からのフィードバック不足
自治体が導入したデジタルサービスの使い勝手や問題点について、住民からのフィードバックを収集し、改善に活かす仕組みが不十分なケースが多いです。住民のニーズや課題に合致していないサービスは、結果的に利用率が低くなり、DX投資の効果を最大化できません。
対策
行政と住民のコミュニケーションを強化するために、オープンなデジタル施策の説明会の開催や、SNSを活用した情報発信、デジタルサービスの体験会などを実施することが有効です。また、住民参加型のデジタルサービス開発プロセスの導入や、アンケートやフィードバックを収集する仕組みの構築も重要です。宮城県仙台市の「デジタル化ファストチャレンジ」のように、小さな成功事例を積み重ねながら住民の理解と参加を促す取り組みは参考になります。
財源確保の難しさ
初期投資の負担
自治体DXには、システム導入や設備更新、人材育成など、初期段階で相当な投資が必要です。特に小規模自治体では、限られた予算の中でDX投資の優先順位付けに苦慮しています。また、DX投資の費用対効果が不確実なケースも多く、予算確保の説明責任に悩む担当者も少なくありません。
持続的な財源の確保
DXは一度システムを導入して終わりではなく、継続的なメンテナンスや更新、人材育成が必要です。この持続的な財源をどのように確保していくかが課題となっています。
対策
財源確保のためには、国の補助金や交付金(デジタル田園都市国家構想推進交付金など)の積極的な活用や、複数の自治体による共同調達によるコスト削減などが考えられます。また、クラウドサービスやサブスクリプションモデルの活用による初期投資の抑制、民間企業との連携による費用分担なども有効です。さらに、DX投資の費用対効果を明確にするための評価指標の設定や、成功事例の横展開による効率的な投資も重要です。
総合的な対応策
これらの課題に対処するためには、個別の対策に加えて、総合的なアプローチが必要です。具体的には以下のような取り組みが効果的でしょう。
- 段階的な推進:DXの全てを一度に実現しようとせず、優先順位を付けて段階的に進める
- 小さな成功体験の積み重ね:まずは小規模なプロジェクトで成功体験を積み、組織全体の理解と協力を得る
- トップのコミットメント:首長や幹部職員のリーダーシップとコミットメントを明確に示す
- 外部知見の積極的活用:コンサルタントや専門家、先進自治体の知見を積極的に取り入れる
- デジタルデバイド対策の徹底:誰一人取り残さないための支援策を充実させる
- 自治体間の連携強化:単独では難しい取り組みも、自治体間の連携により実現可能にする
自治体DXの課題は一朝一夕に解決できるものではありませんが、これらの対策を地道に実行していくことで、着実な進展が期待できます。重要なのは、DXを単なる「デジタル化」ではなく、行政サービスや組織文化の根本的な変革と捉え、長期的な視点で取り組むことでしょう。
自治体DXとあわせて取り組むべき事項

自治体DX推進計画では、7つの重点取組事項に加えて、並行して取り組むべき重要な3つの事項が示されています。これらは自治体DXの効果を最大化し、真に住民目線に立ったデジタル社会を実現するために不可欠な要素です。
1. 地域社会のデジタル化
自治体DXの効果を最大化するためには、行政内部のデジタル化だけでなく、地域社会全体のデジタル化を進めることが重要です。
デジタル田園都市国家構想の推進
岸田内閣が提唱する「デジタル田園都市国家構想」では、デジタル技術の活用によって地方の社会課題を解決し、地方と都市の格差をなくすことを目指しています。具体的には、次の4つの重点的な取り組みが求められています。
- デジタルの力を活用した地方の社会課題解決:介護・医療・教育などの分野でデジタル技術を活用し、地方特有の課題を解決する
- ハード・ソフトのデジタル基盤整備:5G基地局の整備、ローカル5Gの導入など、デジタル化に必要なインフラを整備する
- デジタル人材の育成・確保:地域におけるデジタル人材を育成し、都市部からの人材誘致も推進する
- 誰一人取り残されないための取組:高齢者や障がい者など、すべての住民がデジタル化の恩恵を受けられるよう支援する
官民データ活用の推進
官民データ活用推進基本法に基づき、自治体が保有するデータをオープンデータとして公開し、民間企業や住民による活用を促進することも重要です。例えば、公共交通の運行情報や防災情報、統計データなどをオープンデータ化することで、民間企業による新たなサービス開発や住民主体の地域課題解決が促進されます。
地域企業のデジタル化支援
地域の中小企業や商店のデジタル化を支援することも、地域社会のデジタル化において重要な役割です。自治体による補助金やセミナーの開催、専門家派遣などを通じて、地域企業のDX推進を後押しすることで、地域経済の活性化につながります。また、地域企業と連携したデジタルサービスの開発や実証実験を行うことで、地域全体のデジタル化を加速させることができます。
2. デジタルデバイド対策
デジタル化が進む中で、年齢、地理的条件、経済状況、障がいの有無などによって生じる「デジタルデバイド(情報格差)」の解消は喫緊の課題です。「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現のためには、積極的な対策が必要です。
高齢者等へのデジタル活用支援
総務省は「デジタル活用支援推進事業」を通じて、高齢者等のデジタル活用をサポートしています。地域の携帯ショップやパソコン教室、公民館などで、スマートフォンの基本的な操作やマイナンバーカードの申請方法、行政手続きのオンライン利用方法などの講習会を実施しています。自治体はこうした国の支援策と連携しながら、地域の実情に合わせた支援体制を構築することが重要です。
アクセシビリティの確保
行政のデジタルサービスを提供する際には、障がい者や高齢者など、様々な利用者が使いやすいようアクセシビリティを確保することが重要です。ウェブサイトやアプリの設計段階から、色覚特性に配慮した配色や文字の拡大機能、音声読み上げ機能などを取り入れることで、誰もが利用しやすいサービスの提供が可能になります。
地理的デジタルデバイドの解消
山間部や離島など、ブロードバンド環境が整っていない地域では、デジタルサービスを十分に利用できないという課題があります。こうした地域に対しては、通信基盤の整備支援や、モバイル回線を活用したサービス提供、公共施設における無料Wi-Fi環境の整備などの対策が必要です。
対面サービスの維持・充実
デジタル化を進める一方で、デジタルサービスを利用できない、または利用したくない住民のために、対面でのサービス提供も継続することが重要です。特に福祉や税務など、複雑な相談が必要な場合には、デジタルと対面の両方のチャネルを提供し、住民が自分に合った方法を選択できるようにすることが求められます。
2024年6月の総務省の見解では、デジタルデバイド対策の徹底が改めて強調されており、自治体に対してさらなる取り組みの強化を求めています。デジタル化の恩恵がすべての住民に行き渡るよう、きめ細かな対策が必要です。
3. デジタル原則に基づく条例等の規制の点検・見直し
デジタル化を推進するためには、現行の法令や条例に含まれる「アナログ規制」を見直し、デジタル技術の活用を阻害する要因を取り除くことが重要です。
構造改革のためのデジタル原則
デジタル臨時行政調査会では、「構造改革のためのデジタル原則」として、デジタル技術を前提とした規制・制度に見直すべき5つの原則を定めています。
- デジタル完結・自動化原則:書面・目視等を規定する手続・ルールについて、デジタル処理を基本とする
- アジャイルガバナンス原則:アジャイル型の規制・制度へ見直す
- 官民連携原則:官民が連携してデジタル化を進める
- 相互運用性確保原則:システム間の相互運用性を確保する
- 共通基盤利用原則:共通的な基盤サービスを利用する
見直しが必要な代表的なアナログ規制
自治体の条例や規則には、以下のような代表的なアナログ規制が含まれており、これらを見直すことが求められています。
- 目視規制:人による目視での確認を義務付ける規制
- 定期検査・点検規制:定期的な検査や点検を義務付ける規制
- 実地監査規制:現地に赴いての監査を義務付ける規制
- 常駐・専任規制:特定の業務に常駐・専任の人員配置を義務付ける規制
- 書面掲示規制:紙の書面での掲示を義務付ける規制
- 対面講習規制:対面での講習を義務付ける規制
- 往訪閲覧・縦覧規制:特定の場所に赴いての書類閲覧を義務付ける規制
条例等の見直しプロセス
条例等の規制を点検・見直しする際には、以下のようなプロセスで進めることが効果的です。
- 現状把握:デジタル化の障壁となる条例・規則等を洗い出す
- 優先順位付け:住民の利便性向上に大きく寄与する項目から着手する
- 代替手段の検討:目視や書面に代わるデジタル技術による代替手段を検討する
- 条例等の改正:議会での審議や住民への説明を経て条例等を改正する
- 効果検証:改正後の効果を検証し、必要に応じて更なる見直しを行う
デジタル臨時行政調査会では、2025年までに全ての法令におけるアナログ規制の見直しを目指しており、自治体においても同様のスピード感で取り組むことが求められています。
これらの取り組みの相互関係
地域社会のデジタル化、デジタルデバイド対策、デジタル原則に基づく規制の見直しは、互いに密接に関連しています。例えば、規制の見直しにより新たなデジタルサービスが生まれても、デジタルデバイド対策が不十分であれば、そのサービスを利用できない住民が生じてしまいます。
そのため、これらの取り組みをバランスよく推進し、住民目線での総合的なデジタル化を進めることが重要です。自治体DXの7つの重点取組事項と併せて、これらの3つの事項にも積極的に取り組むことで、真に住民に寄り添ったデジタル社会の実現が可能になるでしょう。
自治体DX推進の手順とステップ

自治体DXを効果的に推進するためには、体系的なアプローチが不可欠です。総務省が公表している「自治体DX全体手順書」では、自治体DXを進めるための段階的なステップが示されています。ここでは、その手順と各ステップにおけるポイントを解説します。
自治体DX推進の4つのステップ
自治体DX推進は、以下の4つのステップに分けて進めることが推奨されています。
ステップ0:DXの認識共有・気運醸成
最初のステップは、組織全体でDXの意義や必要性について共通理解を形成し、DX推進への機運を高めることです。特にDXに着手したばかりの自治体にとって、このステップは極めて重要です。
主な取り組み内容
- 首長や幹部職員向けのDX勉強会・研修の実施
- 全職員を対象としたDXへの理解促進のための情報提供
- 庁内外に向けたDX推進への意気込みの表明(宣言など)
- 他自治体の先進事例の視察や情報収集
成功のポイント
- トップのリーダーシップによる積極的な姿勢の表明
- DXを「単なるシステム化」ではなく「業務やサービスの変革」として捉える視点の醸成
- 身近な成功事例を通じたDXのメリットの可視化
先進事例
大阪府豊中市では、市長自ら「とよなかデジタル・ガバメント宣言」を発出し、庁内外に向けてDXへの強い意気込みを表明しました。さらに、地域情報化アドバイザー派遣制度を活用して「DXセミナー」を開催し、職員の意識改革と業務改革を行う人材の育成に力を入れています。また、ITベンダーと包括連携協定を締結し、「ICTよろず相談会」をビデオ会議で多数開催することで、各部署のICT活用を推進しています。
ステップ1:全体方針の決定
DXの認識共有ができたら、次は自治体全体としてのDX推進の方針を定めるステップです。現状分析を行い、目指すべきビジョンと具体的な取り組み内容、スケジュールを明確にします。
主な取り組み内容
- 自治体の現状と課題の分析(SWOT分析等)
- DXによって目指す将来像(ビジョン)の設定
- 重点的に取り組む施策の選定と優先順位付け
- 年度別の具体的な工程表の作成
- DX推進計画の策定と公表
成功のポイント
- 住民目線での課題設定と将来像の描出
- 国の自治体DX推進計画との整合性確保
- 実現可能で具体的な工程表の作成
- 「できることはすぐ実行」の姿勢
先進事例
宮城県仙台市では、「できることはすぐ実行」の考えのもと、「デジタル化ファストチャレンジ」として以下の3つの取り組みを実施しています。①「窓口手続のデジタル化」(押印の廃止、添付書類の簡素化、キャッシュレス決済の導入等)、②「デジタルでつながる市役所」(オンラインでの子育て相談、市民対応にモバイル端末の活用等)、③「デジタル化で市役所業務の改善」(WEB会議システムの活用、AI・RPAの活用等)。また、DX推進計画において、DXを「単なる新しいデジタル技術の導入ではなく、制度や政策、組織の在り方等を新技術に合わせて変革し、地域課題の解決や社会経済活動の発展を促すこと」と定義し、施策を構築しています。
ステップ2:推進体制の整備
全体方針が決まったら、それを実行するための体制を整備します。このステップでは、DX推進の司令塔となる組織や人材の配置、役割分担を明確にします。
主な取り組み内容
- DX推進担当部門の設置(CIO、CIO補佐官の任命)
- 部門横断的な推進体制の構築(DX推進会議等)
- デジタル人材の確保・育成(外部人材の登用、研修の実施等)
- 庁内のデジタルリテラシー向上のための取り組み
成功のポイント
- DX推進部門への十分な権限付与
- 専門知識を持つ外部人材の効果的な活用
- 各部門のDX推進担当者(デジタル化推進委員等)の配置
- 計画的な人材育成と配置
先進事例
福島県磐梯町では、「仕組みを変えず全庁一丸となってデジタル変革に取り組むことは極めて困難」との考えから、副町長直下に全庁横断的なDX推進担当組織として「デジタル変革戦略室」を設置しました。CDO、CDO補佐官(ICT・セキュリティ担当、デザイン担当)、地域プロジェクトマネージャー、地域活性化起業人及び地域おこし協力隊として外部人材を積極的に登用し、DXを強力に推進しています。また、外部人材とも円滑に業務を行えるよう、完全オンライン、ペーパーレス、リモートを前提とした組織づくりを進めています。
ステップ3:DX施策の実行
推進体制が整ったら、いよいよ具体的なDX施策を実行するステップです。推進計画に基づき、優先順位の高い施策から順次実施していきます。
主な取り組み内容
- 情報システムの標準化・共通化の推進
- 行政手続きのオンライン化
- AI・RPAの導入による業務効率化
- テレワーク環境の整備
- セキュリティ対策の強化
- データ活用基盤の構築
成功のポイント
- PDCAサイクルによる進捗管理と継続的な改善
- OODAループ(Observe:観察、Orient:方向づけ、Decide:判断、Act:行動)を活用した迅速な意思決定
- 小さな成功体験の積み重ねと横展開
- 住民や職員からのフィードバックの収集と反映
先進事例
東京都港区では、行政手続きのオンライン化に積極的に取り組んでいます。令和3年度以降、申請数が多い手続きから順次電子申請を拡充し、各種証明書をオンラインで交付請求できる電子申請サービスを開始しました。また、区民等が自宅で必要手続きを確認できるとともに、来庁時に複数の申請書を一括で作成できる窓口総合支援システムの導入も進めています。
推進時のポイント
自治体DXを成功させるためには、以下のようなポイントに留意することが重要です。
1. 住民中心の発想
DXの目的は最終的に住民サービスの向上にあります。技術ありきではなく、住民の課題やニーズを起点に考え、「何のためのDXか」を常に意識することが大切です。
2. 全庁的な取り組み
DXは特定の部署だけの取り組みではなく、全庁的な協力が不可欠です。情報システム部門と業務部門の連携、部門間の壁を越えた協力体制の構築が重要です。
3. PDCAとOODAの適切な使い分け
計画的に進めるべき施策はPDCAサイクルで、状況の変化に迅速に対応すべき施策はOODAループを活用するなど、施策の特性に応じた進め方を選択することが効果的です。
4. スモールスタート、スケールアップ
一度に大規模な改革を目指すのではなく、小規模なプロジェクトから始め、成功体験を積み重ねながら段階的に拡大していくアプローチが、リスクを最小化しながら確実に成果を上げる方法です。
5. 柔軟性と継続性のバランス
変化の激しいデジタル技術に対応するための柔軟性と、長期的な視点で施策を継続する粘り強さのバランスを取ることが重要です。
推進計画と工程表の作成
自治体DXを計画的に進めるためには、具体的な推進計画と工程表の作成が必要です。推進計画には、以下の要素を盛り込むことが推奨されています。
- 現状分析:自治体の強み・弱み、機会・脅威の分析
- ビジョン:DXによって目指す将来像
- 重点取組事項:特に注力する施策と目標
- 推進体制:組織体制と役割分担
- 工程表:年度別の実施計画と目標
- 評価指標:進捗を測定する具体的な指標
- 予算計画:必要となる経費の見積もりと確保方法
このような計画を策定し、定期的に進捗状況を評価・見直しながら、着実に自治体DXを推進していくことが重要です。
都道府県による市区町村の支援
特に小規模な市区町村では、単独でDXを推進するのが難しいケースもあります。そのため、都道府県による市区町村への支援が重要な役割を果たします。
主な支援内容
- 情報やノウハウの共有(勉強会、研修会の開催等)
- デジタル人材の派遣や共同確保の支援
- 共同調達や広域連携の調整
- 財政的支援(補助金等の提供)
- 先進事例の収集・展開
こうした都道府県の支援を効果的に活用することで、小規模自治体でもDXを着実に推進することが可能になります。
自治体DXは一朝一夕で実現するものではなく、中長期的な視点で計画的に進めていく必要があります。しかし、「できることから始める」というスモールスタートの精神で、着実に一歩ずつ前進することが重要です。段階的なステップを踏みながら、住民目線でのサービス改革を進めていきましょう。
自治体DXの先進事例紹介

全国の自治体では、DXの実現に向けた様々な取り組みが進められています。ここでは、特に参考になる先進事例を、重点取組事項ごとに紹介します。これらの事例を自治体の規模や特性に合わせて参考にすることで、効果的なDX推進が可能になるでしょう。
1. フロントヤード改革の事例
東京都港区:窓口総合支援システムの導入
港区では、区民の窓口体験を改善するための「窓口総合支援システム」を導入しました。このシステムには以下の特徴があります。
- 区民がウェブサイト上で必要な手続きを事前に確認できる
- 来庁時に複数の申請書を一括で作成できる
- 手続きガイドと連携し、必要書類や手数料の案内を自動化
- 来庁前の事前準備を促すことで、窓口での待ち時間を短縮
このシステム導入により、区民の手続き負担が大幅に軽減されるとともに、窓口職員の業務効率も向上しました。特に複数の手続きを一度に行う場合の効果が大きく、区民からの評価も高いです。
東京都新宿区:マルチクラウド利活用での行政サービス向上
新宿区では、異なるクラウドサービスを連携させる「マルチクラウド」の考え方を取り入れ、住民サービスの向上と業務の効率化を実現しています。
- 複数のクラウドサービスを用途に応じて使い分け、最適なシステム構成を実現
- ガバメントクラウドとLGWAN接続系の統合によるシームレスな情報連携
- セキュリティを確保しつつ、柔軟なデータ活用を可能に
このアプローチにより、住民向けサービスのスピードと質が向上するとともに、業務の効率化も実現しています。特に、データの二重入力や情報連携の手間が大幅に削減されました。
2. 情報システム標準化・共通化の事例
栃木県:県と市町村の共同利用型システムの構築
栃木県では、県と県内市町村が共同でクラウド型の情報システムを利用する「とちぎ共同利用型システム」を構築しています。このシステムには以下の特徴があります。
- 県内25市町の半数以上が参加し、基幹系17業務のシステムを共同利用
- 共同調達によるコスト削減効果(約40%の削減を実現)
- 標準準拠システムへの移行を見据えた段階的な整備計画
- 県が中心となり、市町村の規模や状況に応じたきめ細かな支援
この取り組みにより、各市町村は単独での標準化・共通化対応の負担が軽減され、限られた資源を有効活用できるようになりました。特に小規模自治体にとっては、専門人材やノウハウの共有という点でも大きなメリットとなっています。
兵庫県神戸市:ガバメントクラウドへの早期移行の取り組み
神戸市では、基幹系17業務のシステムについて、2025年度の期限を待たずにガバメントクラウドへの移行を進めています。先行的な取り組みとして注目されています。
- 移行計画の早期策定と段階的な移行スケジュールの設定
- 移行に伴う業務プロセスの見直しと標準化
- 新旧システムの並行運用期間を設けての段階的移行
- 職員向けの研修プログラムの充実
早期移行によって得られた知見を他業務のシステム移行にも活かすとともに、他自治体とも積極的に共有することで、全国的な標準化・共通化の動きを加速させています。
3. AIやRPA活用の事例
愛知県豊橋市:AI・RPAを活用した業務効率化
豊橋市では、AIとRPAを積極的に活用して業務の効率化と市民サービスの向上を図っています。特に以下の取り組みが注目されています。
- AI-OCR+RPAによる申請書処理の自動化:児童手当や国民健康保険の申請書をAI-OCRで読み取り、RPAで自動入力することで、作業時間を約70%削減
- AIチャットボットの導入:市民からの問い合わせに24時間365日対応するAIチャットボットを導入し、窓口や電話での問い合わせ負担を軽減
- AI議事録作成支援システム:会議の音声を自動でテキスト化し、議事録作成業務を効率化
これらの取り組みにより、定型業務の効率化が進み、職員はより付加価値の高い業務に集中できるようになっています。また、AIチャットボットの導入により、市民は時間や場所を問わず必要な情報を入手できるようになりました。
福島県会津若松市:データ連携基盤を活用した統合GIS
会津若松市では、住民基本台帳と地理情報システム(GIS)を連携させた「統合GIS」を構築し、防災や地域施策に活用しています。
- 住民情報と地理情報を統合することで、災害時の避難支援が効率化
- 要支援者の位置情報をリアルタイムで把握し、適切な支援計画を策定
- バス路線再編など公共交通計画の検討にも活用
- 人口分布と公共施設の位置関係を分析し、最適な施設配置を検討
データ連携基盤の構築により、従来は別々に管理されていた情報を統合的に活用できるようになり、より効果的な政策立案と住民サービスの向上が実現しています。
4. テレワーク推進の事例
福島県昭和村:ローコード開発による全庁的電子決裁の実現
人口約1,200人の小規模自治体である昭和村では、ローコード開発ツールを活用して、わずか8ヶ月で全庁的な電子決裁システムを導入しました。
- コロナ禍でのリモートワーク環境整備を契機に電子決裁システムを内製
- 専門的なプログラミング知識がなくても開発可能なローコードツールを活用
- 庁内の実情に合わせてカスタマイズした使いやすいシステムを実現
- 紙ベースの決裁と比較して、決裁時間を約60%短縮
小規模自治体ならではの機動力と柔軟性を活かし、限られた予算と人材でDXを実現した好例です。このシステムにより、職員が場所を問わず業務を遂行できる環境が整備され、テレワークの推進に大きく寄与しています。
神奈川県横浜市:デジタル職の新設によるテレワーク環境整備
横浜市では、テレワーク環境の整備を加速させるため、新卒および中途採用において「デジタル職」を新設し、ICTスキルを持つ人材の確保に努めています。
- 受験資格として情報処理技術者試験等の合格を条件に設定
- 採用後はICTの利活用やデジタル関連業務に従事
- 専門人材の確保により、テレワーク環境の整備や運用が円滑に
- 職員のテレワークスキル向上のための研修プログラムも充実
専門人材の確保により、テレワーク環境の整備だけでなく、デジタルツールを活用した業務効率化や新たなサービス開発も進み、自治体DX全体が加速しています。
5. セキュリティ対策の事例
長野県:県と市町村が共同したセキュリティ対策
長野県では、県と県内77市町村が共同で「自治体情報セキュリティクラウド」を構築し、効率的かつ高度なセキュリティ対策を実現しています。
- 共同によるスケールメリットを活かした高度なセキュリティ対策
- 24時間365日の監視体制による迅速なインシデント対応
- 県によるCSIRT(サイバーセキュリティインシデント対応チーム)の設置と市町村への支援
- 小規模自治体でも導入可能な費用負担の仕組み
この取り組みにより、専門人材が不足する小規模自治体でも高度なセキュリティ対策が可能になり、安全なDX推進の基盤が整備されました。
北海道:自治体向けICT-BCP作成支援
北海道では、道内市町村のICT-BCP(ICT部門の業務継続計画)作成を支援するため、ガイドラインの策定やテンプレートの提供を行っています。
- 道内市町村の特性に合わせたICT-BCP作成ガイドラインの策定
- 小規模自治体でも容易に作成できるテンプレートの提供
- 計画作成のためのワークショップや研修会の開催
- 計画の実効性を高めるための訓練シナリオの提供
これらの支援により、道内市町村のICT-BCPの策定率が大幅に向上し、災害や情報セキュリティインシデント発生時の対応力が強化されました。
6. 公金収納におけるeLTAX活用の事例
大阪府:eLTAXを活用した公金収納の効率化
大阪府では、2024年の新たな重点取組事項である「公金収納におけるeLTAXの活用」を先進的に実施し、納税者の利便性向上と業務効率化を実現しています。
- 地方税以外の各種公金についてもeLTAXを活用した電子納付を可能に
- 24時間365日、いつでもどこからでも納付可能な環境を整備
- 納付情報と収納情報の自動連携による業務効率化
- 入金確認作業の自動化による人為的ミスの削減
この取り組みにより、納税者の利便性が向上するとともに、窓口対応や入金確認業務が大幅に軽減され、人的リソースを他の業務に振り向けることが可能になりました。
7. 地域社会のデジタル化の事例
熊本県小国町:無償アプリを活用した被災状況報告システム
熊本県小国町では、当初は感染症対策のために無償提供された検温レポートアプリを活用して、被災状況報告アプリを独自に開発しました。
- 既存の無償アプリを応用し、低コストで迅速にシステムを構築
- スマートフォンで撮影した被災箇所の写真と位置情報を即時に報告可能
- 報告データをリアルタイムで集約し、被災状況を速やかに把握
- 被災状況報告書の作成業務を大幅に効率化
このシステムにより、災害時の初動対応が迅速化され、限られた人員で効果的な対応が可能になりました。また、平時からの防災訓練にも活用されており、住民の防災意識の向上にも寄与しています。
北海道旭川市:デジタルデバイド対策としてのシニア向けICT教室
旭川市では、高齢者のデジタルデバイド解消を目指し、「シニアのためのICT活用講座」を継続的に開催しています。
- 年齢や経験に応じたレベル別の講座設計(初心者向け、ステップアップ向け等)
- 現役の高校生や大学生がサポーターとして参加する世代間交流型の学習環境
- 行政手続きのオンライン化に合わせた実践的な内容(マイナポータルの使い方等)
- 地域のICT企業との連携による最新技術の紹介
この取り組みにより、参加高齢者のICTリテラシーが向上し、行政のデジタル化による恩恵を広く享受できる環境が整備されています。また、若い世代との交流による高齢者の生きがいづくりにも貢献しています。
先進事例から学ぶ成功のポイント
これらの先進事例から、自治体DXを成功させるための共通するポイントが見えてきます。
- トップのリーダーシップと明確なビジョン:首長や幹部のコミットメントと、目指すべき姿の明確化
- 住民目線のサービス設計:行政の論理ではなく、住民の視点に立ったサービス設計
- 段階的アプローチ:小さな成功を積み重ねながら段階的に進める方法
- 既存リソースの有効活用:既存のツールやサービスを創意工夫で活用
- 部署間・自治体間の連携:組織の壁を越えた協力体制の構築
- 専門人材の確保と活用:内部人材の育成と外部人材の効果的な活用
- 効果測定と継続的改善:定量的な効果測定と改善の繰り返し
これらのポイントを押さえながら、各自治体の特性や課題に合わせたDX推進策を検討することが重要です。先進事例のそのままの模倣ではなく、「なぜ成功したのか」という本質を理解し、自らの状況に合わせて応用することが求められます。
自治体DX推進で確認すべき参考資料
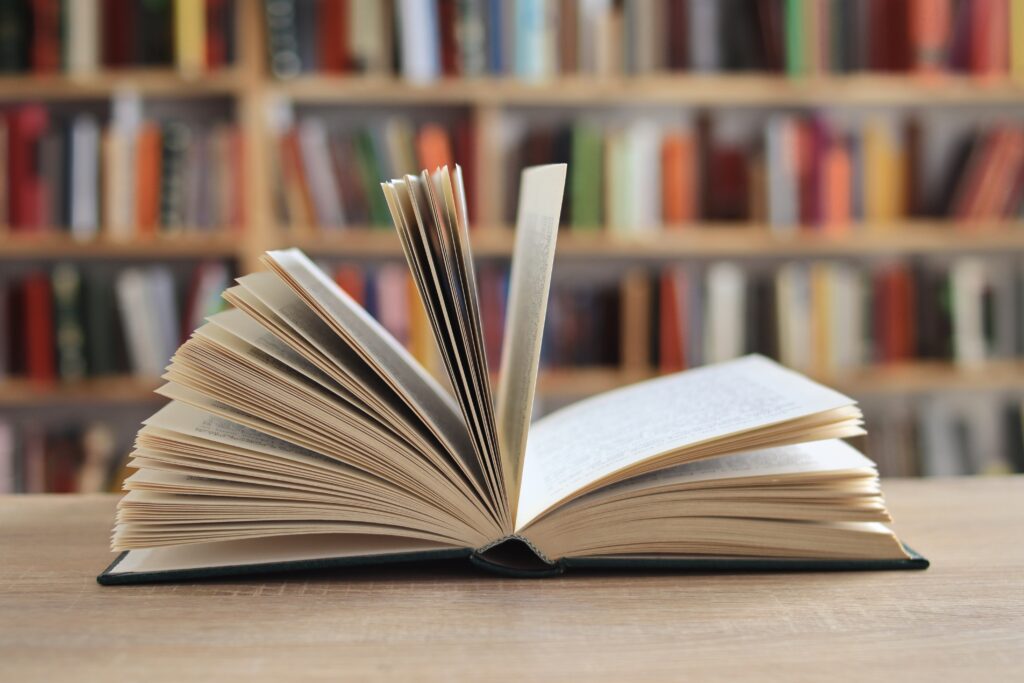
自治体DXを効果的に推進するためには、国が提供する様々な参考資料を活用することが有効です。これらの資料は、DX推進の具体的な手順や先進事例、注意点などを詳細に解説しており、自治体が計画を立てる際の貴重な指針となります。ここでは、特に確認しておくべき重要な参考資料を紹介します。
1. 自治体DX推進計画関連資料
自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画【第3.0版】
総務省が策定した自治体DX推進の基本計画です。2020年12月に初版が発表され、2024年6月には第3.0版に改訂されました。この計画書には、自治体が重点的に取り組むべき7つの事項や、国による支援策などが明記されています。
主な内容:
- 自治体DX推進の背景と目的
- 7つの重点取組事項の詳細
- 自治体DXとあわせて取り組むべき事項
- 推進体制のあり方
- 国による支援策
この計画は、自治体DX推進の基本方針を示すものであり、まずは必ず確認すべき資料です。
自治体DX・情報化推進概要
総務省が毎年実施している自治体のデジタル化の進捗状況調査の結果をまとめた資料です。全国の自治体におけるDX推進状況や取り組み事例が紹介されており、他自治体との比較や先進事例の参考にできます。
主な内容:
- 全国の自治体のDX推進状況(グラフや統計データ)
- 各重点取組事項ごとの進捗状況
- 自治体規模別の取り組み状況
- 先進的な取り組み事例の紹介
2024年4月に最新版が公表されており、現在の全国的な傾向を把握するのに役立ちます。
2. 自治体DX全体手順書
自治体DX推進計画を実行に移すための具体的な手順を解説した資料です。DXを進めるための一連の流れを段階的に示しており、実践的なガイドとして活用できます。
手順書は以下の4つから構成されています:
自治体DX全体手順書【第2.0版】
DX推進の全体像と推進手順を解説しています。ステップ0からステップ3までの各段階での取り組み内容や、推進体制の整備方法、人材確保・育成の進め方などが詳細に説明されています。
主な内容:
- 自治体DX推進の4ステップの詳細
- 推進体制の整備方法
- デジタル人材の確保・育成方法
- DX推進計画の策定方法
- 効果的な進捗管理の方法
自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第1.0版】
基幹系17業務のシステムを標準化・共通化するための具体的な手順を解説しています。2025年度までに対応が必要な重要事項であり、計画的な移行が求められます。
主な内容:
- 標準化・共通化の意義と効果
- 対象となる17業務の詳細
- 標準準拠システムへの移行手順
- データ移行のポイント
- ガバメントクラウド活用の方法
自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【第1.1版】
行政手続きのオンライン化を進めるための具体的な手順を解説しています。マイナポータルを活用したオンライン手続きの導入方法や、業務プロセスの見直し方法などが説明されています。
主な内容:
- オンライン化の対象となる手続きの選定方法
- マイナポータルとの連携方法
- 業務プロセスの見直し(BPR)の進め方
- システム導入・運用のポイント
- 効果測定の方法
自治体DX推進手順書参考事例集【第1.0版】
全国の自治体における先進的なDX推進事例を集めた資料です。様々な規模・特性の自治体の取り組みが紹介されており、自団体の状況に合った参考事例を見つけることができます。
主な内容:
- 推進体制構築の事例
- 人材確保・育成の事例
- 各重点取組事項の実践事例
- DXとあわせて取り組むべき事項の事例
- 小規模自治体の工夫事例
3. 自治体DXダッシュボード
総務省が2023年に公開を開始した、全国の自治体のDX推進状況を一覧で確認できるウェブツールです。重点取組事項ごとの進捗状況が地図上でビジュアル化されており、他自治体との比較や全国的な傾向を簡単に把握することができます。
主な機能:
- 都道府県・市区町村別のDX推進状況の地図表示
- 重点取組事項ごとの進捗状況のグラフ表示
- 人口規模別の比較機能
- 時系列での変化の確認
- CSV形式でのデータダウンロード機能
自団体の位置づけを客観的に把握し、今後の推進計画に活かすことができる便利なツールです。総務省のウェブサイトから無料で利用できます。
4. 地域社会のデジタル化に係る参考事例集
自治体DXとあわせて取り組むべき「地域社会のデジタル化」に関する先進事例をまとめた資料です。地域の特性に合わせたデジタル技術の活用事例が、写真やイラストとともに分かりやすく紹介されています。
主な内容:
- 医療・福祉分野のデジタル化事例
- 教育分野のデジタル化事例
- 防災・減災分野のデジタル化事例
- 交通・観光分野のデジタル化事例
- 農林水産業分野のデジタル化事例
事業の概要だけでなく、企画の背景や工夫点、効果と課題も記載されており、実践的な参考となります。
5. デジタル社会実現のための構造改革のためのデジタル原則
デジタル臨時行政調査会が策定した、デジタル社会の実現に向けた規制・制度の見直しの指針となる原則です。自治体の条例や規則の見直しを行う際の参考となります。
5つのデジタル原則:
- デジタル完結・自動化原則
- アジャイルガバナンス原則
- 官民連携原則
- 相互運用性確保原則
- 共通基盤利用原則
これらの原則に基づいて、自治体の条例・規則等に含まれる「アナログ規制」を点検・見直すための具体的な方法も解説されています。
6. 自治体DX推進のためのデジタル人材確保の手引き
自治体DX推進の鍵となるデジタル人材を確保・育成するための指針を示した資料です。CIO補佐官などの外部人材の任用方法や、内部人材の育成方法などが解説されています。
主な内容:
- デジタル人材に求められるスキル標準
- 外部人材の効果的な活用方法
- デジタル人材の確保に向けた採用戦略
- 内部人材の育成プログラム
- デジタル人材の処遇やキャリアパス
特に、CIO補佐官等の外部人材任用に対する特別交付税措置の活用方法も詳細に説明されており、財政面での支援策としても参考になります。
7. 情報セキュリティポリシーに関するガイドライン
自治体のセキュリティ対策の指針となるガイドラインです。DXを推進する上で不可欠なセキュリティ確保のための具体的な方策が詳細に解説されています。
主な内容:
- 情報セキュリティポリシーの策定・見直し方法
- 情報セキュリティ管理体制の整備
- 情報資産の分類と管理
- 物理的・技術的・人的セキュリティ対策
- インシデント対応の方法
2022年3月に改訂版が公表されており、クラウドサービスの利用やテレワークの実施など、最新の動向に対応したセキュリティ対策が盛り込まれています。
資料の入手方法と活用のポイント
これらの参考資料は、総務省のウェブサイト「自治体DX」のページからダウンロードすることができます。また、デジタル庁のウェブサイトにも関連資料が掲載されています。
資料の効果的な活用のポイントとしては、以下の点に留意することをおすすめします:
- 目的に合わせた資料の選択:DX推進の段階や課題に応じて、適切な資料を選択する
- 自団体の特性に応じた読み解き:人口規模や地域特性が似た自治体の事例を重点的に参考にする
- 最新版の確認:定期的に更新される資料もあるため、最新版をチェックする
- 関連資料の横断的活用:複数の資料を横断的に参照し、総合的な理解を深める
- 庁内での共有と学習会の実施:資料の内容を庁内で広く共有し、理解を促進する
これらの参考資料は、国が蓄積してきた知見や先進自治体の経験が詰まった貴重なリソースです。自治体DXを進める際には、是非とも活用して、効率的かつ効果的な推進を目指しましょう。
まとめ

本記事では、自治体DX推進計画について、その概要から重点取組事項、推進方法、先進事例まで幅広く解説してきました。2024年最新の情報に基づき、自治体がデジタル社会の実現に向けて取り組むべき内容を整理しました。
自治体DX推進の重要性と意義
人口減少や高齢化が進む中、限られた人的リソースで質の高い行政サービスを提供し続けるためには、自治体DXの推進が不可欠です。単なる業務の効率化にとどまらず、住民サービスの質の向上、データを活用した新たな価値創出など、DXには多様な意義があります。
デジタル技術を活用して「誰一人取り残さない」社会を実現するという理念のもと、総務省が示す7つの重点取組事項と3つの併せて取り組むべき事項に計画的に取り組むことが求められています。
自治体DX推進のポイント
自治体DXを成功させるためのポイントは以下の通りです。
- トップのリーダーシップと全庁的な推進体制:首長や幹部のコミットメントと、部門を超えた協力体制の構築
- 住民目線のサービス設計:デジタル技術ありきではなく、住民ニーズに基づくサービス設計
- デジタル人材の確保・育成:外部人材の登用と内部人材の計画的な育成
- 段階的アプローチ:小さな成功を積み重ねながら、着実に前進する方法
- デジタルデバイド対策の徹底:誰もがデジタル化の恩恵を受けられるための支援
これらのポイントを押さえながら、自治体の規模や特性に合わせた独自のDX推進計画を策定・実行することが重要です。
自治体DXの今後の展望
2025年度までに基幹系17業務のシステム標準化・共通化が求められるなど、自治体DXは重要な節目を迎えています。これを単なる「対応すべき課題」ではなく、行政サービスや組織文化を根本から変革する機会と捉え、積極的に取り組むことが求められます。
今後は、AI・データ活用の高度化、デジタル人材の本格的な育成・確保、官民連携の深化など、より高度なDXへと進化していくことが予想されます。常に最新の動向を把握しながら、柔軟に対応していくことが重要です。
住民と行政の協働の重要性
最後に強調したいのは、自治体DXは行政だけで完結するものではないということです。住民や地域企業との協働、デジタル化に関する対話の場の創出など、多様なステークホルダーを巻き込んだ取り組みが欠かせません。
「デジタル技術の活用によって、どのような地域社会を実現したいのか」という共通のビジョンのもと、住民と行政が一体となってデジタル社会の実現に向けて歩みを進めることが、真の意味での自治体DXの成功につながるでしょう。
自治体DXは目的ではなく手段です。デジタル技術を活用して「住民の幸せ」や「地域の持続可能性」を高めることが最終的なゴールであることを常に意識し、一歩一歩着実に前進していきましょう。
- 自治体DXとは単なるデジタル化ではなく、デジタル技術を活用して行政サービスや業務を根本から変革し、住民の利便性向上と行政の効率化・高度化を実現する取り組みです。
- 7つの重点取組事項(自治体フロントヤード改革、情報システムの標準化・共通化、公金収納におけるeLTAXの活用、マイナンバーカードの普及促進、セキュリティ対策の徹底、AI・RPAの利用推進、テレワークの推進)に計画的に取り組むことが必要です。
- 自治体DXを段階的に推進する4ステップ(ステップ0:認識共有・気運醸成、ステップ1:全体方針の決定、ステップ2:推進体制の整備、ステップ3:DX施策の実行)に沿って着実に進めることが成功の鍵です。
- 課題解決には総合的アプローチが必要で、アナログ文化の変革、DXへの理解促進、デジタル人材の確保・育成、行政と住民のコミュニケーション強化などの取り組みを進めることが重要です。
- 最新の参考資料や先進事例を活用して、自団体の特性に合わせた効果的なDX推進計画を策定・実行することが、デジタル社会実現への近道となります。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















