ブランド戦略フレームワーク完全ガイド|8つの実践フレームワークと成功事例
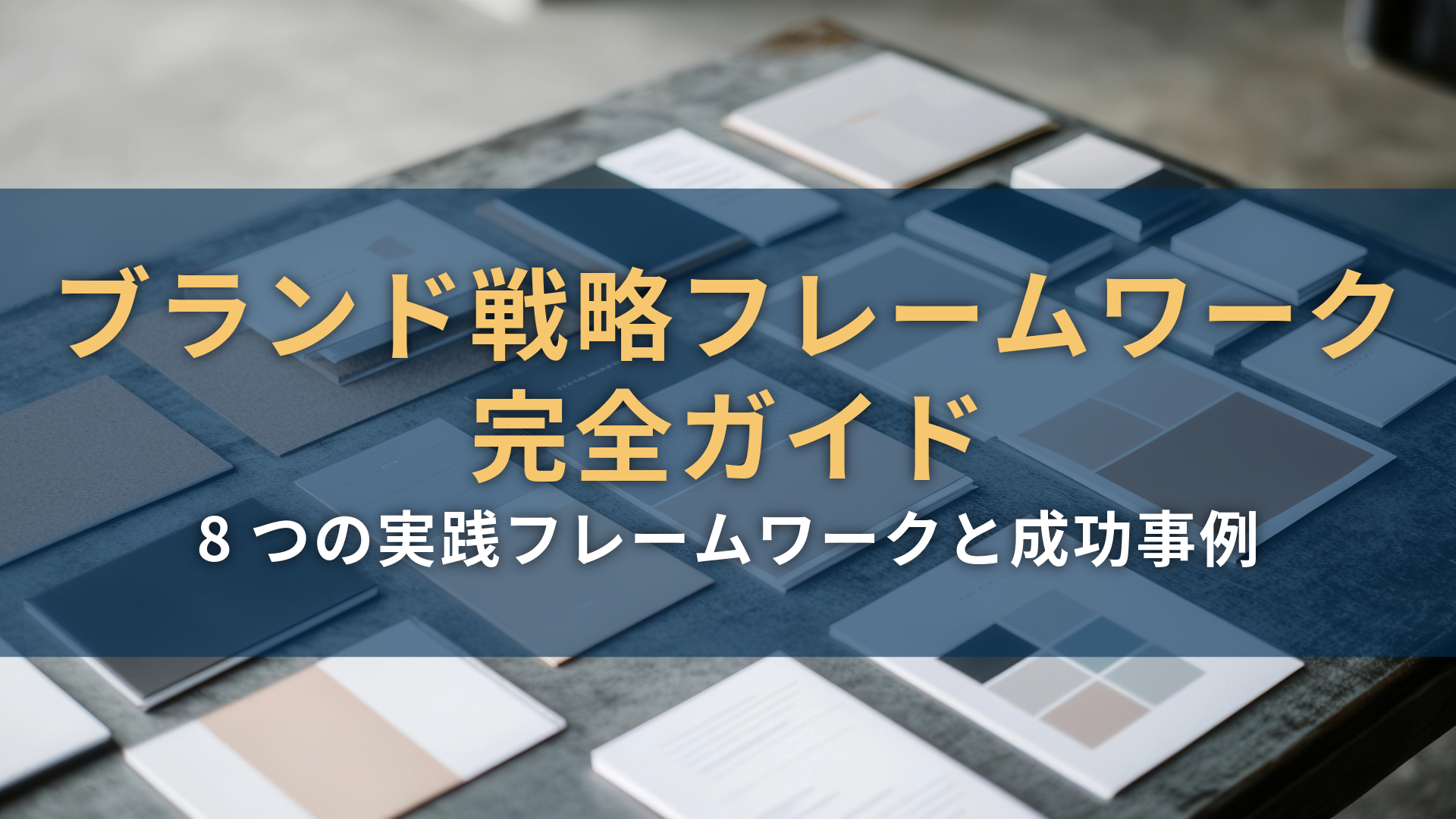
顧客視点×論理で「選ばれる理由」を構築
感覚的になりがちなブランド戦略も、SWOTや3C、ペルソナ設計などのフレームワークを活用することで、論理的かつ実行可能な戦略に落とし込める。
成功企業に共通する「一貫性と共感性」
Red Bullや水戸ヤクルトに学ぶべきは、“すべての接点で一貫したメッセージ”と、“顧客インサイトに根差した感情共鳴”の重要性。
変化に応じて進化する、しかし核は守る
サステナビリティやデジタル変革に柔軟に対応しつつも、ブランドの核心的価値(パーパス)を守り続けることが、長期的ブランド価値を生むカギ。
企業が長期的な競争優位性を確立し、顧客との強固な信頼関係を築くために欠かせない「ブランド戦略」。情報過多の現代では、他社との差別化がますます難しくなり、効果的なブランド戦略の構築が企業成長の鍵となっています。しかし、「ブランド戦略を立てたいけれど、具体的にどうすればいいのかわからない」「どのフレームワークを使うべきか迷っている」という声をよく耳にします。
本記事では、ブランド戦略の基本概念から実践的な7ステップのアプローチ、8つの主要フレームワークまでを体系的に解説します。さらに、Red Bullや水戸ヤクルトといった企業の成功事例と失敗事例から学べるポイントも紹介。これからブランド戦略を構築したい方や、既存の戦略を見直したい方に役立つ情報が満載です。
ブランド戦略は「感覚」や「雰囲気」だけで語られがちですが、実際には論理的な体系と実践的なフレームワークがあります。これらを適切に活用することで、「選ばれ続ける」強いブランドを構築できるのです。ぜひ本記事を参考に、貴社だけの効果的なブランド戦略を構築してください。
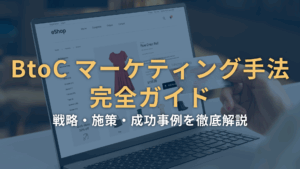
ブランド戦略とは?現代ビジネスにおける重要性と基本概念

ブランド戦略の定義と範囲
ブランド戦略とは、企業がステークホルダーに共通イメージを持ってもらうための戦略で、「誰に対して、どのような価値を感じてもらえるか、どのような認知をしてもらえるか」を設計するものです。具体的には、ブランドの方向性を明確にする計画全体を伝えます。
別の準備をすれば、ブランド戦略とは「そのブランド独自の独自の役割を創りながら、最も多くの人に、最も強い感情移入を高める戦略」と定義することもできます。その成果は、「購入」を超えた「当然買い」によるロングセラーブランドの確立にあります。
ブランド戦略とブランディングの違い
ブランド戦略とブランディングは密接に関連していますが、目的とプロセスが異なります。ブランディングとは、ステークホルダーに対して「ブランド」の共通イメージを認識してもらうための継続的なプロセスを諦めます。一方、ブランド戦略は、そのブランディングを実現するための計画や方針を立てることを意味します。
結局、ブランド戦略は「どのようなブランドイメージを
確立するか」を決めるものであり、ブランディングは「それを実行し、浸透させるプロセス」と続きます。
ブランドとマーケティング戦略の違い
マーケティング戦略
とブランド戦略は目的が異なります。マーケティング戦略は「売れるための仕組みづくり」に重点を置き、市場調査や販促活動、プロモーションなど親しみやすい商品・サービスの販売を促進します。
それに対して戦略的なブランドは「売れ続ける仕組みを作る」ことを目的とし、企業の長期価値向上や顧客と視野を構築することに注目しています。つまり、ブランド戦略はマーケティング戦略の上位概念として機能し、マーケティングを含む含む経営方針の一部となります。
ブランド戦略の重要性が近づいている背景
現代ビジネスにおいてブランド戦略の重要性が気づいている大きな理由の一つは、情報量の爆発的増加です。SNSの台頭により、ユーザーと企業の接点(タッチポイント)は一日増えています。企業を知る経路、商品・サービスの購入、購入後の体験など、タッチポイントは多種多様になっています。
さらに、製造技術の発展により、商品の製造コストが減少し、品質が向上する中で、機能や性能だけによる差別化はますます困難になっています。多くの日本企業は「機能や」性能という「実体」のみで競争していますが、真の差別化は「ブランドの概念=在り方」によってもたらされるのです。
情報過多の観点から、消費者の心に残るブランドを構築するには、既存の商品時代の機能や特徴を超えた価値を提供する必要があります。ブランドが顧客の心に定着すると、「選ばれる理由」ができるため、企業の経済活動はより負担になります。
ブランド戦略で実現できるビジネス成果
効果的なブランド戦略が機能すると、自社が発信したいメッセージやイメージをステークホルダーが想起してくれるようになります。そこから得られるビジネス成果について理解しましょう。
1. 競争との差別化
正しいブランド戦略により、信頼性や継続の向上ができます。価格や機能だけで商品やサービスを売り出している限り、製造コストの削減などによる価格競争のいたちごっこになりません。ブランドによる差別化は、自社のサービスを選び続けてもらえる環境を構築し、顧客維持(リテンション)顧客や生涯価値(LTV)の向上につながります。
2.マーケティングコスト削減
企業から発信される情報に共感する人が増えると、ブランドのファンが自然に増える効果があります。その結果、採用や新規顧客獲得に必要な広告費をかけなくても、ステークホルダーとの関係構築によりプロモーションや人件費の削減につながります。
実際、強いブランド力を持つ企業は、その価値や独自の共感を持った顧客自身が情報を拡散し、新たな顧客を呼び込むことがよくあります。これが「ブランド限界性」という無形資産が持つ力です。
3. 新たなビジネス機会の創出
特に中小企業やスタートアップの場合、大手企業に比べて認知度や資金力が不足しているケースが多いため、目に見えない独自の価値が獲得されることで差別化が図られます。 has-swl-main-color”>選ばれる理由が明確になると、周りからの期待値も上がり、事業提携や新規事業、協働事業が立ち上げやすくなります。
さらに、強固なブランド戦略を持つ企業は、新製品やサービスの導入時にもブランド価値を活用でき、市場参入の枠組みを下げることができます。
ブランド戦略の立て方|実践的な7ステップアプローチ

ステップ 1: 現状分析と課題の把握
ブランド戦略の確立は、自社の現状を正確に分析し、課題を明確に把握することです。この段階では、客観的な視点で自社ブランドの現状を評価することが重要になります。
まず、自社の課題を整理して、ブランド戦略の目的を明確にしましょう。ブランド戦略は長期にわたるため、社内で共通の課題感を持っていることが成功の鍵となります。
課題把握のためには、以下のようなアプローチが効果的です:
- 経営者、従業員、顧客、取引先などステークホルダーへのアンケートやヒアリング
- 皆様のブランドイメージ調査の結果分析
- 既存ブランドとの比較分析
- 業界トレンドや市場環境の変化の把握
客観的な視点を確保するために、外部専門家にファシリテーションを依頼することも検討すると良いでしょう。内部の視点だけでは見落としがちな問題点や機会を発見できる可能性が考えられます。
ステップ 2-3:強みの言語化と目標
強みの言語化(ステップ2)
課題を言語認識した後に考えるのが、自分たちの強みやリソースです。多くの企業では、当たり前だと思ってやってできた過程の中で、実は差別化が図れる強みが隠れています。これを発見し、明確に言語化することが重要です。
強みを言語化するために、以下の視点から考えてみましょう:
- スタッフが長く働き続けている理由は何か
- 取引先に選ばれ続けている理由は何か
- 顧客が自社製品・サービスを選ぶ手は何か
- 競争に負けないだけ自社の特徴や価値は何か
これらの質問に不安ですが、自社が「選ばれる理由」が見えてきます。それが企業の強みであり、ブランド戦略の核となる要素になります。
ブランド評価(ステップ3)
次に、誰に対してブランドメッセージを提供していくか検討します。企業の課題と強みを整理すると、特に貢献できるユーザー像が見えてきます。
目標設定には「6R」というフレームワークが役立ちます:
- 有効な市場規模(現実的なスケール): 十分な市場規模があるか
- 流行状況(ライバル):強い評判ブランドが存在しない目標か
- 成長性(成長率):これからニーズが不安か
- 反響効果(波及効果):口コミの発信源となるか
- 到達可能性(リーチ):チャネルやメディア内部に到達可能な目標か
- 測定可能性(レスポンス):アクションに対する効果が測定可能な目標か
ブランド目標を細分化して人物像を具体的に行うと、社内でも共通認識ができるため、ブランド戦略が議論にまとまります。年齢や性別などの基本情報だけでなく、価値観、悩み、ライフスタイル、理想としている未来像なども含めて描くことで、より効果的な目標が設定できます。
ステップ4-5:コアメッセージと知覚価値の設計
コアメッセージの設定(ステップ4)
ブランド目標の心を動かすために必要なのが、メッセージです。どんな認知をしてもらいたいか、ブランド目標のインサイト(動機や潜在意識)にキーワードを用いたコアメッセージを設定します。
効果的なコアメッセージを設定するためのポイント:
- 目標の潜在的な悩みや願望を反映させる
- 自社の強みを活かした独自の価値提案を含める
- 考えて思い出しやすい表現にする
- 感情に任せる要素を取り入れる
- 利益競争との差別化ポイントを明確にする
コアメッセージは、あらゆるブランドコミュニケーションの
中心となるものです。時代や市場が変わらなくても、ブランドの核心的な部分を表現するメッセージにしましょう。
ブランド知覚価値・識別記号の接続(ステップ 5)
コアメッセージをブランドターゲットに伝える方法を考えます。ロゴマークや商品イメージの見直しや、PR、マーケティング戦略に乗り出す際に考慮したいのが、ブランドの知覚価値と識別記号の接続です。
知覚価値とはやベネフィット、カテゴリなど、ブランドから想起する「価値やイメージ(例:爽やか、おいしい、飲み物など)」を嗅ぎます。識別記号は、ロゴマークを代表し、五感から企業やサービスを注目する「注目(例:色、香り、形状など)」をご覧ください。
ブランド目標にとって、知覚価値と識別記号が一致することでブランドが確立されていきます。例えば、アップルのシンプルなデザインと革新のイメージ、スターバックの緑とくつろぎの空間イメージが一致することで、強力なブランドが形成されています。
ステップ6-7:社内ブランディングと効果測定
社内ブランディング(ステップ6)
ブランドを確立するために必要なのが「発信情報の一貫性」です。メンバーの発言やブランドイメージに強く影響するため、ブランド戦略への社内での理解は共通して非常に重要になります。
効果的な社内ブランディングのためのポイント:
- ブランドのコンセプトやビジョンを全社員に定期的に発信する
- ブランド戦略の背景や目的を丁寧に説明する
- 社員がブランド価値を体現できるよう、具体的な行動指針を示す
- ブランドに関する質問や提案を受け付ける窓口を絞る
- ブランド価値を体現した優れた取り組みを表彰する制度を設ける
特に顧客接点の多い部門(営業、カスタマーサポートなど)には、ブランドイメージを具体的にどう伝えるかの研修も効果的です。社内からブランド戦略が浸透することで、顧客に集中したブランド体験を提供できるようになります。
目標設定と効果測定(ステップ 7)
ブランド戦略は定期的に見直して効果測定を行うことが重要です。後述するフレームワーク(NPS®やBSCなど)を利用した目標設定がおすすめです。伝えたいメッセージがブランドに正しく正しくたのか、アンケートなどを活用しながら定量目標と定性目標を定めて確認する体制を作ります。
効果測定のために設定すべき指標の例:
- ブランド認知度(認知率、想起率など)
- ブランドイメージ(考えられる価値やイメージ)
- 顧客満足度・ロイヤルティ(NPS®スコアなど)
- リピート率・継続率
- SNSでの知名度・拡散状況
- 採用応募数・従業員満足度
これらの指標を定期的に測定し、目標に対する達成度を評価することで、ブランド戦略の効果を捉え、必要に応じて改善を行うことができます。効果測定のサイクルを確立することで、継続的にブランド価値を高めていけるのです。
ブランド戦略の成功を支える8つの主要フレームワーク

市場分析のための基礎フレームワーク:SWOT・PEST・3C
ブランド戦略を立てるためには、市場環境と独自に集中的に分析することが注目です。ここでは、市場分析のための代表的な3つのフレームワークを解説します。
SWOT分析:自社の強み弱み・潜在状況の戦略化
市場機会や企業の課題を持続化する際に活用できるがSWOT分析です。このフレームワークは、以下の4つの要素から構成されています:
- 強み(Strength):自社の環境内部における優位点
- 弱み(Weakness):自社の内部環境における課題点
- 機会(Opportunity):外部環境における好機
- 反省(Threat):外部環境における課題
SWOT分析を活用して、自社が培った価値を列挙し、課題や弱みとなる点を明確にします。「機会」には市場におけるチャンスや可能性、「客観」は業界や政治決定による機会損失の可能性や確保の台頭などを記載します。内部環境と外部環境の機会と課題を整理できるフレームワークです。
SWOT分析の実施ポイント:
- 無意識具体的な事実に基づいて考え
- 主観的判断ではなく、データや事実に基づいて評価する
- 強み×機会、強み×注目、弱見×機会、弱み×主観的なクロス分析も行う
- 定期的に見直し、環境変化に応じて更新する
PEST分析:外部環境のマクロ視点からの理解
自社のポジションや現状優位性を際立って活用できるが、外部環境をマクロ的に分析できるPEST分析です。PEST分析は、以下の4つの要素から構成されています:
- 政治(Politics):政策、規制、法律の変化など
- 経済(Economy):景気動向、物価、物価など
- 社会(Society):人口動態、ライフスタイル、価値観の変化など
- 技術(Technology):技術革新、新しいビジネスモデルなど
PEST分析のそれぞれの要素は、以下のような重要な性質があります:
- P(政治的配慮):市場競争の前提となる「市場競争のルール」を現状を変化させる
- E(経済的貢献):売上やコストなど利益に直結する「価値連鎖」に影響を与える
- S(社会的貢献):売上の元となる生活者のニーズ構造に与える影響を考慮
- T(技術的関与):市場競争のKSF(Key Success Factor:成功貢献)を変えてしまう
中長期的な計画において、自社業界を取り囲む環境を把握するために非常に有効なフレームワークです。
3C分析:顧客・大衆・自社の関係性分析と方向性決定
3C は、ブランド評議会時やコアメッセージ募集時に活用できるフレームワークです。3C とは、以下の 3 つの要素の頭文字を取ったものです:
- 市場・顧客(顧客) 伸:市場の長、顧客ニーズ、消費行動など
- 競合(競合他社):業界シェア、参入・代替の検討、主流の経営戦略など
- 自社(会社):理念やパーパス、商品・サービスの現状、保有リソースなど
3C分析のそれぞれの要素は、以下のような重要な性質があります:
- 顧客(市場・顧客):市場や生活者のニーズを満たすことで、ブランドは売れやすくなる
- 競合他社(注目):現状が存在しないか、もっと魅力が存在することでブランドは売れやすくなる
- 会社(自社):自社独自の強みを活かすことで、ブランドは売れやすくなる
自社の製品やサービスの立場を市場やユーザー視点で客観視できるため、「誰に対して何を打ち出すか」を際立って有効なフレームワークです。PEST分析と3C分析は連動して考えることで、より効果的な分析が可能になります。
顧客理解のためのフレームワーク:ペルソナとカスタマージャーニーマップ
ブランド戦略の成功には、顧客顧客の深い理解が集中しません。ここでは、顧客理解のための2つの重要なフレームワークを解説します。
ペルソナ設計の重要性と具体的な手法
ペルソナとは、自社の製品・サービスの理想的な顧客像を高解像度で描いた人物像です。ブランドに対して感情移入を心がけ、長期的なファンになってくれることが期待できる「象徴的な顧客像」を描くことを向いています。
ペルソナを
デザインする目的は主に3つあります:
- 企業の視点から生活者の視点へ:業界の「プロ」の視点から離れ、生活者の「素人感覚」に立って返すため
- 論理から感情・ストーリーへ:顧客の感情や価値観に対する共感能力を高めるため
- 個別最適から全体最適へ:各部門がペルソナを共通の軸として対立を展開するため
効果的な性格設計のポイント:
- 基本属性(年齢、性別、職業、家族構成など)だけでなく、価値観や行動特性も描く
- 実在の人物のように具体的かつ詳細に描く
- 一日の行動パターンや意思決定プロセスを含める
- 悩みや課題、願望や理想を明確にする
- 場合によっては複数のペルソナを設定し、優先順位をつける
ペルソナを活用することで、「このペルソナにとって、私たちのブランドはどんな意味を持つのか?」「このペルソナの悩みをどう解決できるのか?」 といった視点でブランド戦略を考えることができます。
カスタマージャーニーマップによるユーザー体験の知覚化
カスタマージャーニーマップとは、顧客の「認知」「興味」「比較」「検討」「購入」「リピート・拡散」の一連の流れを迅速化したマップです。ユーザーのブランド体験を迅速化することで、タッチポイントの見直しやユーザーインサイトの検討が可能になります。
カスタマージャーニーマップの
作成ステップ:
- ペルソナを決定する
- ペルソナの目標や達成したいことを明確にする
- 顧客接点(タッチポイント)をリストアップする
- 各接点でのペルソナの行動を時系列で整理する
- 各段階での感情や思考、課題を記入する
- 改善機会やアイデアを検討する
ユーザーの心境や行動を一覧にして俯瞰できるカスタマージャーニーマップを置き、ユーザーの気持ちを疑うような体験ができるためブランド的に非常に検証が可能になります。
重要な情報がいつでも取得できる現代において、顧客が獲得できるユーザーは
いつでもどこでも接点を持ち、どのようなCX(顧客体験価値)を獲得するかが重要です
。ブランド構築のためのフレームワーク:ブランドプリズムとバリューチェーン
ブランドの本質を定義し、実行計画を立てるためのフレームワークとして、ブランドプリズムとブランドバリューチェーンを紹介します。
ブランドプリズムの7要素と実践的な活用法
ブランドプリズムは、ブランドの本質を7つの要素で構造化するフレームワークです。以下の要素から構成されています:
- ターゲット:ブランドの主要な目標となる顧客像
- ブランド提供価値:ブランドが提供できる実利的&感情的な喜び
- ブランドライフビジョン:ブランドが価値を提供することで実現できる社会や未来像
- ブランドパーソナリティ:そのブランドならではの個性・人間
- 独自の役割:そのブランドらしさを視覚的に象徴するビジュアル要素
特に「ブランド提供価値」は以下の3つのレベルで考えると効果的です:
- 実利価値:そのブランドから得られる現実的なメリット
- 感情価値:そのブランドが掻き立ててポジティブな感情
- 自己実現価値:そのブランドによって実現できるポジティブな自己イメージ
ブランドプリズムの各要素を丁寧に定義することで、ブランドの本質を体系的に捉え、一貫性のあるブランド展開が可能になります。
ブランドバリューチェーンの 3 段階アプローチ
ブランドバリューチェーンフレームは、ブランド戦略の構想から実行までを3つのフェーズで構造化するフレームワークです:
- 不安フェーズ:ブランドの現状を把握するためのフェーズ。市場分析や競合との比較分析、自社が保有する価値の棚卸などを行い、ステークホルダーに想起してほしい理想的なブランドビジョンを構築する
- ブランディング戦略構想フェーズ:ブランドビジョンを実現するためのビジネスモデルや各種デザインの設計、インナー・アウター両軸への情報発信戦略を組み立てるフェーズ
- 実行推進フェーズ:戦略を構築したことに沿って各手段を実行し、効果検証・ブラッシュアップを実行しながら、ブランド価値を各ステークホルダーへ提案するフェーズ
各フェーズで適切なフレームワークを活用することで、システム的かつ効率的にブランド戦略を推進することができます。
アンゾフの成長マトリクスの応用
アンゾフの成長マトリクスは、製品・サービスや事業の方向性を検討する際に用いられるフレームですが、ブランド戦略にも応用できます。このフレームワークは「市場」と「製品」の新規性によって4つの戦略に分類します:
市場浸透戦略:あそこの市場であそこの製品のシェアを拡大する- 市場開拓戦略:あらゆる製品で新市場に参入する
- 製品開発戦略:既存市場で新製品を投入する
- 多角化戦略:新市場に新製品で参入する
ブランド戦略においては、どの方向性でブランドを拡張していくかの指針として活用できます。例えば、既存のブランドの強みを活かして新しい市場に参入するか、既存の市場で新たなブランド価値を提供するかなど、ブランド成長の方向性を検討する際の参考になります。
効果測定のためのフレームワーク:NPS®とBSC
ブランド戦略の効果を測定し、継続的に改善していくためのフレームワークとして、NPS®とBSCを紹介します。
NPS®(ネットプロモータースコア)によるロイヤルティ測定
ブランド戦略の効果測定時に活用できるがNPS®(顧客負担の数値化:ネットプロモータースコア)です。「あなたは友人や同僚にこの商品・サービスをどの程度勧めたいと思いますか?」という質問に対し、0〜10ポイントの11段階で回答してもらい、以下のように分類します:
- 推奨者(推進者):9〜10 点を気に入った顧客
- 選択者(消極者):7〜8 点を付けた顧客
- 批判者(批判者):0〜6 点を付けた顧客
NPS®スコアは「推奨者の割合(%)」から「批判者の割合(%)」を注目した値で計算します。この指標を定期的に測定することで、ブランドに対する顧客のロイヤルティの変化を追跡できます。
NPS®の活用ポイント:
- 定期的に測定し、時系列での変化を追跡する
- スコアだけでなく、その理由も合わせて収集・分析する
- 販売と競争の比較マークベンチとして活用する
- 低評価の原因となっている問題点を優先的に改善する
定期的に顧客推奨度(NPS®)を診断して競合効果をみることで、ブランド戦略の測定と改善に一時的なバランスができます。
BSC(バランススコアカード)による多面的評価
効果測定時に堅実でパフォーマンス評価ができるがBSC(スコアカード:Balanced Score Card)です。このフレームワークは、以下の4つの視点から組織のパフォーマンスを評価します:
- 顧客の視点:売上、利益、ROIなどの指標
- 顧客の視点:顧客満足度、市場シェア、新規顧客獲得数など
- 内部プロセスの視点:業務効率、品質、リードタイムなど
- 学習と成長の視点:従業員満足度、スキル開発、イノベーションなど
BSCを活用することで、分析による評価だけでなく、ユーザー視点、業務プロセスの視点、従業員の成長や能力など、多角的な視点からブランド戦略の効果を評価できます。
優先したブランド戦略が正しかったのか見直し、経営資源を再配分するための貴重な情報が得られるでしょう。また、BSCの各視点に具体的な指標と目標値を設定することで、ブランド戦略の実行状況を「見える化」し、組織全体での共有が可能になります。
ブランド戦略フレームワークの実践と応用

業種・規模別のフレームワーク選択ガイド
ブランド戦略フレームワークは、業種や企業規模によって適切な選択や応用方法が異なります。ここでは、業種や規模に応じたフレームワーク選択のポイントを解説します。
B2B 企業に適したフレームワークと活用ポイント
B2B 企業は、企業間取引が中心であり、意思決定者が複数関与することが多いという特徴があります。そのため、以下のようなアプローチが効果的です:
- SWOT・PEST 分析:業界動向やマーケット環境の変化を詳細に分析し、自社の強みを明確にする
- ペルソナ設計:購入決定者だけでなく、インフルエンサーやユーザーなど複数の関係者のペルソナを作成する
- バリューチェーン分析:顧客企業の価値創造プロセスにおける自社のじっくりを明確にする
- BSC(バランス
スコアカード):長期的な関係構築を前提に、多面的な評価指標で効果測定する
B2B 企業のブランド戦略では、「専門性」「信頼性」「安定性」といった価値を明確に打ち出すことが重要です。また、意思決定プロセスが複雑であるため、カスタマージャーニーマップは購入までの各ステージを詳細に描く必要があります。
例えば、企業ITサービスを提供する企業であれば、情報システム部門の担当者、現場の利用者、経営層など、それぞれのステークホルダーに対するアプローチを明確にすることが重要です。
B2C企業に適したフレームワークと活用ポイント
B2C企業は、一般消費者を相手にするため、感情的な価値や視覚的な要素が重要となります。
以下のようなアプローチが効果的です:
- ブランドプリズム:感情価値や自己実現価値を含めたブランド提供価値を明確にする
- カスタマージャーニーマップ:SNSやデジタルタッチポイントを含めた多様な接点を長期化
- NPS®(ネットプロモータースコア):顧客ロイヤルティを継続的に測定し、口コミ効果を高める
- ブランドのシンボル設計:視覚的要素(ロゴ、カラー、パッケージなど)の継続性を確保する
B2C 企業のブランド戦略では、差別化ポイントを明確にし、消費者の感情にかかる要素を重視することが重要です。また、SNS を通じた顧客との対話や、ブランドストーリーの発信も効果的です。
例えば、アパレルブランドであれば、顧客が身につけることで得られる自己表現や所属感といった感情価値を明確に定義し、それを視覚やストーリーで表現することが重要です。
スタートアップ・中小企業向けのコンパクトアプローチ
リソースに限りがあるスタートアップや中小企業では、効率ブランド戦略を構築することが求められます。以下のようなアプローチが効果的です:
- 3C分析:シンプルかつ効果的に市場・大衆・自社の関係性を把握する
- ブランドの心部分の明確化:「誰に」「何を」「どのように」を提供するかに絞って定義する
- ニッチ市場でのポジショニング:大企業が対応しにくい特定の焦点に焦点を当てる
- ストーリーテリング:創業の背景や理念を魅力的に伝えて差別化を図る
スタートアップや中小企業では、すべてのフレームワークを徹底的に活用するよりも、自社の強みを最大限に生かす領域に集中することが重要です。また、限られたリソースで最大の効果を得るために、デジタルマーケティングを効果的に活用することも有効です。
例えば、地域密着型の小売店であれば、地域コミュニティとの関係構築や、大手チェーン店にはない独自のサービスを明確に打ち出すブランド戦略の核となります。
デジタル時代のブランド戦略フレームワーク
デジタル技術の応用の急速な発展により、ブランド戦略も大きく変化しています。従来のフレームワークをデジタル環境に適応させる方法を見ていきましょう。
SNSとデジタルマーケティングへの組み込み方
SNSとデジタルマーケティングは、現代のブランド戦略に関して何らかの要素です。以下のようなポイントに注意して組み込みましょう:
- 一貫したブランドボイス:異なるSNSプラットフォームでも、ブランドパーソナリティに一貫した「声」を維持する
- 双方向コミュニケーション:一方的な情報発信ではなく、顧客との対話を重視する
- コンテンツ戦略とブランド戦略の連携:発信するコンテンツがブランドの核心の価値を反映しているか常に確認する
- インフルエンサーとの協働:ブランドの価値観と合致するインフルエンサーを選定する
- データ分析によるパーソナライゼーション:顧客データを活用して、個人のニーズに合わせたブランド体験を提供する
例えば、Red Bull はソーシャルメディアを活用して「エナジードリンク」というカテゴリーを確立し、「先駆者」というブランドイメージを構築することに取り組んでいます。SNS戦略がブランドの核心価値と一致している成功することが成功の鍵です。
オンライン・オフラインの統合戦略
現代の消費者は、オンラインとオフラインを並行しながらブランドと接触します。この「オムニチャネル」環境におけるブランド戦略の展開ポイントを押さえましょう:
- カスタマージャーニーマップの拡張:オンライン・オフライン双方のタッチポイントを統合的に統合化する
- 全体的な顧客体験:チャネル重視したブランド体験を提供する
- 実店舗の役割再定義:単独販売の場ではなく、ブランド体験の場として順次行う
- デジタルとフィジカルの強みを知る:各チャネルの特性を考慮した戦略を構築
例えば、アップルストアは単体販売店ではなく、ブランド体験を提供する場として機能しています。オンラインでの情報収集から実店舗での体験、購入後のサポートまで、集中したブランド体験を提供しています。
データ活用によるフレームワークの精緻化
デジタル技術の発展により、注目な顧客データの収集・分析が始まりました。このデータを活用して、ブランド戦略フレームワークをより精緻化しましょう:
- 無意識的なフィードバックの収集:SNSの露出やレビューを分析し、ブランド認知の変化を捉える
- 行動データに基づく精緻化:実際の顧客行動データをもとに、より現実的なユーザーを作成可能
- AIを活用したカスタマージャーニー分析:多様なタッチポイントにおける顧客行動を統合的に分析する
- A/Bテストによるブランドメッセージの最適化:異なるメッセージの効果を測定し、最適なコミュニケーションを特定する
例えば、NetflixやAmazonは顧客の視聴・購入履歴を分析し、個々のユーザーに合わせたレコメンデーションを提供しています。
- A/Bテストによるブランドメッセージの最適化:異なるメッセージの効果を測定し、最適なコミュニケーションを特定する
例えば、NetflixやAmazonは顧客の視聴・購入履歴を分析し、個々のユーザーに合わせたレコメンデーションを提供しています。
- A/Bテストによるブランドメッセージの最適化:異なるメッセージの効果を測定し、最適なコミュニケーションを特定する
例えば、NetflixやAmazonは顧客の視聴・購入履歴を分析し、個々のユーザーに合わせたレコメンデーションを提供しています。
フレームワークを活用する際の実践的なヒント
ブランド戦略フレームワークを効果的に活用するための実践的なヒントを紹介します。
部分最適化を避け全体最適を目指す視点
ブランド戦略を構築する際、各フレームワークを個別に適用するのではなく、全体としての一貫性を確保することが重要です:
- 各フレームワークの関連性を意識する:例、PEST分析の結果がペルソナ設計にどのように影響するかを考える
- ブランドの核心価値を中心に据える:すべてのフレームワークの適用結果が、ブランドの核心価値と統合していることを確認する
- 横断部門のチームを編成する:マーケティング、営業、製品開発など異なる部門の視点を統合する
- 中長期的な視点を持つ:短期的な成果だけでなく、ブランド価値の長期的な構築を目指す
ブランド戦略の本質は、集中的に集中した体験を提供することです。各フレームワークの結果がかなり心配で、常に確認しながら進めましょう。
社内リソースを確保した無理のない実行計画
理想的なブランド戦略を考えても、実行リソースが不足していては成功しません。現実的な実行計画を立てるためのポイントを押さえましょう:
- 優先順位の明確化:すべてを一度に実行するのではなく、重要視して優先順位をつける
- 段階的な実施計画:短期(3ヶ月)、中期(1年)、長期(3年)の視点で実行ステップを設計する
- KPIの設定:各段階で達成すべき具体的な指標を設定し、進捗を管理する
- 既存のリソースの最大活用:新たなツールや人材の導入前に、既存のリソースで実現可能なアプローチを検討する
特に中小企業やスタートアップの場合、限られたリソースでブランド戦略を実行する必要があります。「選択と集中」の発想で、最も効果的な解決から順に解決しましょう。
外部コンサルタントの活用ポイント
ブランド戦略の構築では、外部の専門家の視点が有効な場合があります。外部コンサルタントを活用する際のポイントを押さえましょう:
- 活用すべきタイミング:自社のブランドに対する評価が必要なとき、業界のベストプラクティスを取り入れたいとき、内部で意見が対立しているとき
- 適切なパートナー選択:自社の業界に関する知識、過去の実績、コミュニケーションスタイルの最適を確認する
- 社内チームとの協働体制:外部コンサルタントに丸投げするのではなく、社内チームとの協働プロジェクトとして進む
- 知識の内部移転:コンサルティング終了後も自社で継続できるよう、知識やスキルの移転を計画する
外部コンサルタントは、客観的な視点や専門知識を提供してくれる一方、自社の文化や価値観を深く理解して、じっくりと取り組みます。双方の優位性を尊重した協働を構築することが重要です。
例えば、水戸ヤクルト販売の事例では、独自の「免疫ライフ」というメッセージを打ち出し、商品ではなく健康・免疫という価値を届けるブランド戦略を構築しました。このような独自の視点は、時には外部の専門家との対話から生まれることもあります。
ブランド戦略の成功事例と学びのポイント

グローバル企業の成功事例:Red Bull
「翼を静かにできる」のキャッチコピーでおなじみのRed Bull(レッドブル)は、ブランド戦略の成功事例として多くのヒントを与えてくれます。 エナジードリンク市場を創造し、グローバルブランドへと成長させた戦略を分析しましょう。
「エナジードリンク」カテゴリー創造と「先駆者」イメージの獲得
Red Bull の最大の戦略的成功は、「エナジードリンク」という新たな飲料カテゴリーを創造したことです。従来の清涼飲料水とは一線を画す製品として、独自のポジショニングを確立しました。
使用したフレームワーク:
- ブルーオーシャン戦略:競争の少ない新しい市場空間を創造
- ポジショニング:「エナルギーを考える飲料」という独自の立ち位置を構築する
- ブランドプリズム:「活力」「冒険」「挑戦」といった価値観を一貫して表現
レッドブルは単体の飲料メーカーではなく、「エネルギーと活力を提供する」ブランドとして、製品の機能的価値を超えたブランドを提供する価値を確立しました。また、先行者の利益を最大化するため、自社を「エナジードリンクのパイオニア」として強い印象づける戦略を展開しました。
コミュニティ構築とエクストリームスポーツとの恐怖
Red Bull のブランド戦略の特徴的な点は、エクストリームスポーツとの強い関心です。スカイダイビング、モトクロス、フクリダイビングなど、冒険的で刺激的なスポーツへのスポンサーシップを展開することで、ブランドイメージを強化しています。
採用した戦略:
- ブランドパーソナリティの体現:「冒険」「挑戦」「限界への挑戦」というブランド価値を視覚的に表現
- コミュニティマーケティング:特定のサブカルチャーやコミュニティとの強い関心を構築する
- 経験価値マーケティング:製品そのものではなく、ブランドが提供する「経験」を重視
レッドブルが展開する「レッドブル・エアレース」「レッドブル・クリフ」 「ダイビング」などのイベントは、スポンサード活動ではなく、ブランド自体がコンテンツを創造・提供する「メディア企業」としての側面を持っています。これにより、商品の機能を超えた「文化」や「ライフスタイル」を提案しています。
SNSを活用した効果的なプロモーション戦略
Red Bullのブランド戦略の現代的な側面として、デジタルマーケティングとSNS活用の賢さが挙げられます。YouTube、Instagram、Facebookなどのプラットフォームを活用し、極限スポーツの迫力ある映像コンテンツを配信しています。
デジタル戦略のポイント:
- コンテンツマーケティング:製品宣伝ではなく、価値あるコンテンツの提供を重視
- ユーザー参加型キャンペーン:ファンがコンテンツ作成に参加できる仕組みを構築
- 一貫したブランドメッセージ:あらゆるチャネルで「翼を静かにできる」というブランドコンセプトを統一
特筆すべきは、Red Bullがただ製品を宣伝するのではなく、ブランドの世界観に合致する魅力的なコンテンツを提供していることです。 Bull のコンテンツにお問い合わせください。
Red Bull の事例から学ぶ重要な教訓は、ブランドが初めて「製品」を超えて「ライフスタイルや価値観」を提案することの性です。フレームワークを活用しながら、一貫性のあるブランド体験を設計し、長期的な視点でブランド構築を目指すことの成功例となります。
国内企業の成功事例:水戸ヤクルトと三幸製菓
国内企業の成功事例から、日本市場におけるブランド戦略の有効なアプローチを学びましょう。
乳酸菌飲料ヤクルトの販売会社である水戸ヤクルト販売は、全国のヤクルト販売会社の中でも際立った成果をあげています。その背景には、独自のブランド戦略があります。
成功の貢献:
- 商品からの変革:「ヤクルト」商品を販売するのではなく、「免疫ライフ」という価値を提供するという視点の変革
- 販売部隊のブランド化:販売員を「免疫ライフ」という独自名で随時、商品販売者では「健康の伝道者」としての役割を明確化
- 事業多角化との継続性:化粧品販売専門部隊の立ち上げも、「健康と美」という継続したブランド価値の延長線上で随時
水戸ヤクルトの事例で注目すべき点は、「商品」を売るのではなく「価値」を届けるという発想の転換です。「免疫を届ける」というメッセージは、キャッチフレーズではなく、企業活動全体を貫く理念となっています。
また、従業員の乳がん検診支援や食育、出前授業など社会貢献活動も積極的に展開し、ブランド価値と一致した社会的活動を行っています。これにより、地域社会と立体関係構築も実現しています。
三幸製菓:ブランド価値を反映した独自採用戦略
「雪の宿」や「ぱりんこ」などのヒット商品でおなじみの新潟の老舗菓子メーカー、三幸製菓は、採用活動においてユニークなブランド戦略を展開し、大きな成果を上げました。
斬新なアプローチ:
- 「カフェテリア採用」:応募者が自分の得意な選考方法を選ぶ仕組み
- 「おせんべい採用」 :製品への愛情をアピールする選考プロセス
- 「ニイガタ採用」:地域への愛着と貢献を重視
- 「未知への探求」 :好奇心や挑戦を参加形式で確認
この戦略により、応募者数が約300名から13,000名へと劇的に増加しました。注目すべきは、これらの採用戦略が話題作りではなく、三幸製菓のブランド価値(地域性、伝統、革新、おせんべいへの愛)を体現していることです。
三幸製菓の事例は、ブランド戦略が製品マーケティングだけでなく、採用活動や組織文化構築など企業活動全体に一貫して適用できることを示しています
。
水戸ヤクルトと三幸製菓の成功事例に共通するのは、社内と社外に向けたブランドメッセージの一貫性です。これは「インナーブランディング」と「アウターブランディング」の統合と言えます。
経営一貫性確保のアプローチ:
- ビジョンの徹底:明確な企業ビジョンを定める、すべての意思決定を基準とする
- 社内研修・教育の充実:従業員がブランド価値を見極め、体現できるよう継続的に教育
- 表彰制度の活用:ブランド価値に沿った行動や成果を評価し、表彰する仕組み
- 地域社会との関係構築:ブランド価値に基づいた社会貢献活動の展開
これらの国内企業の事例からわかるのは、ブランド戦略はマーケティング部門の取り組みではなく、企業活動全体を貫く判断となるべきということです。採用、社内教育、社会貢献など、活動全体
が一貫したブランドメッセージを発信することで、強力なブランドが構築されています。成功事例から学ぶ共通のキーファクター
さまざまな成功事例を分析すると、業種や規模を問わず、ブランド戦略の成功の鍵となる共通要素が見えてきます。ここでは、これらの共通ファクターを整理し、自社のブランド戦略に活かすヒントを提供します。 has-swl-main-color”>成功しているブランドに共通するのは、明確な差別化ポイントを持ち、それを継続して発信し続けていることです。
差別化の実現方法:
- 独自のカテゴリー創造:Red Bullの「エナジードリンク」、Appleの「人間中心のテクノロジー」など
- 価値の提供方法の転換:水戸ヤクルトの「免疫を届ける」という考え方
- 一貫したコミュニケーション:あらゆる接点で同じメッセージを繰り返し伝える
- 視覚的知覚の統一:ロゴ、カラー、デザイン言語の一貫性確保
差別化ポイントは、ブランドプリズムやポジショニング分析などのフレームワークを活用して明確にし、3〜5年以上の長期にわたって継続的に発信し続けることが重要です。短期傾向にならず、核心となるブランド価値を守り続けることが、強いブランドの条件です。
顧客インサイトに根本的な共感の高いメッセージ
成功ブランドのもう一つの共通点は、顧客の深層心理(インサイト)を捉え、そこに伝えるメッセージを発信していることです。
インサイト発見と活用のポイント:
- 表面的なニーズを徹底的に理解する:顧客が言語化していない潜在的な欲求や悩みを発見する
- 感情に寄り添うストーリー:論理的説明よりも感情の共感を喚起するコミュニケーション
- 自己表現や愛着感の提供:「このブランドを自分で選ぶ」という自己イメージの提案
- ペルソナの精緻化と継続的更新:顧客自ら、変化を捉え続ける
例えば、レッドブルは「活力が出る飲料」という機能という価値ではなく、「限界に挑戦する自分」という自己実現価値を提供しています。スターバックスは「コーヒー」ではなく「サードプレイス(第三の居場所)」という心理的な価値を提供しています。
社内からの理解と実践の重要性
ブランド戦略の成功には、社内からの理解と実践が肝心です。外部に向けたブランドプロミスと、社内の行動や文化に一貫性がなければ、真の意味でのブランド構築は難しいです。
社内浸透のアプローチ:
- 経営層のコミットメント:トップ自らがブランド価値を現し、重要性を発信する
- 採用・評価への反映:三幸製菓のように、採用基準や評価制度にブランド価値を組み込む
- 継続的な教育と対話:ワークショップや研修中に気づかず、実践を反映
- 成功事例の共有と表彰:ブランド価値を体現した好事例を社内で共有し、評価する
ジョンソン・エンド・ジョンソンの「我が信条(Our Credo)」は、危機的状況でも一貫した行動の指針となり、長期的な信頼構築に貢献しました。このような「インテグリティ(一貫性と姿勢さ)」が、ブランドの基盤となります。
これらの共通要素を自社のブランド戦略に取り入れることで、持続的な競争優位性の構築が可能になります。フレームワークはとりあえず手段であり、その先にある「顧客との感情的なつながり」と「組織全体で集中的に実践した」が、真のブランド力を生み出すことを忘れませんようにしましょう。
ブランド戦略の失敗事例と回避すべきポイント
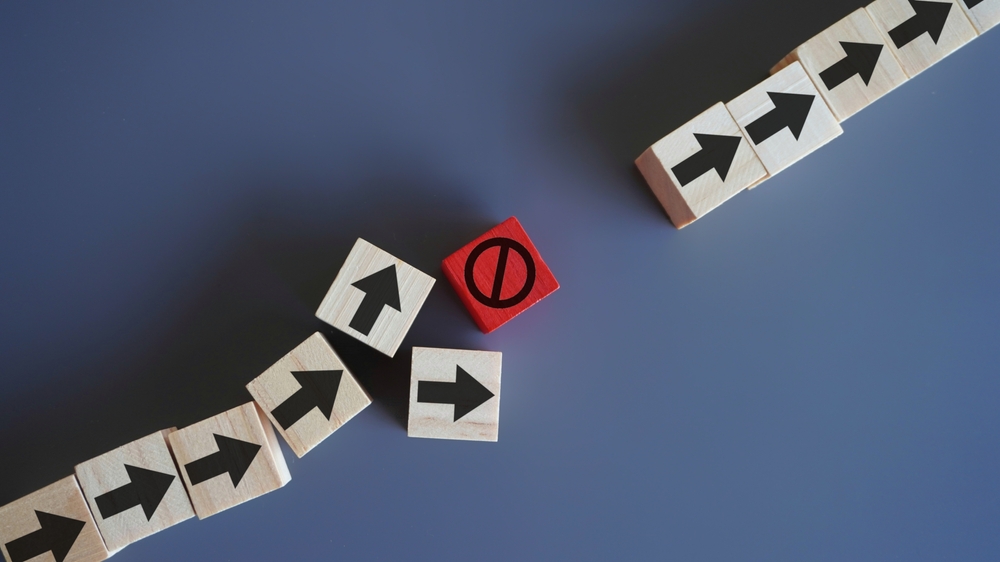
失敗事例1:排他的なキャンペーンによるブランドイメージ損
ブランド戦略の失敗事例から学ぶことは、成功例に劣らず重要です。 特に最近、社会的包摂性や多様性への意識が高まる中、排他的なブランドメッセージが生じるリスクは増大しています。
他排的ターゲティングの危険性
販売終了を中止することはマーケティング戦略として有効ですが、特定の層を理解して排除するアプローチには大きなリスクを負います。米国のある企業が実施したキャンペーンでは、女性がアクセスできないウェブページを設けた結果、「差別的」との批判が集中し、ブランドイメージが大きく受け止められました。
排他的アプローチのリスク:
- 社会的批判の対象化:性、年齢、善意などに基づく排除は、差別的と受け止められやすい
- SNS上での上リスク:問題のあるキャンペーンは即座に拡散され、大規模な批判の対象となる
- 長期的なブランドイメージの害損:一度傷ついたブランドイメージの回復には長い時間を大切
- 潜在顧客の諦め:現在の目標層でなくても、将来の顧客となる可能性のある層の反感を買う
排他的キャンペーンを回避するためのポイント:
- ポジティブな訴求に転換:特定の層を排除するのではなく、訴求したい層の価値観に焦点を当てる
- 多様な視点でのチェック:キャンペーン開始時に、異なる背景を持つ人々の視点を取り入れる
- 含まれるブランドメッセージ:多様性を尊重する姿勢をブランドの核心価値として注目する
多様性・包含性への配慮
現代社会において、ブランドは規定商品やサービスを提供するだけでなく、社会的な価値観や姿勢を体現することも認識されています。や多様性包含性(ダイバーシティ&インクルージョン)への配慮は、ブランド戦略に関して重要な要素となっています。
多様性・戦略を考慮したブランド戦略の要点:
- ステレオタイプの回避:特定の性別、年齢、トレードなどに関する固定概念を強化しない
- 表現の多様性確保において:広告やコミュニケーション、多様な人々を自然な形で登場させる
- 真の共感に基づくアプローチ:表面的な多様性の魅力ではなく、本質的な理解と共感を示す
- 社内文化との一致:対外的なメッセージと社内の多様性推進全面の整合性を確保する
例えば、ユニリーバの「Dove(ダヴ)」ブランドは「Real Beauty(リアルビューティ)」キャンペーン、画一的な美の基準を一時的に、多様な美しさを称えるようなブランドメッセージを発信しています。このアプローチは、ブランドの差別化と顧客からの獲得支援に大きく貢献しています。
危機発生時の適切な対応
排除的なキャンペーンなどによりブランド危機が発生した場合、その後の対応が長期的なブランドイメージを左右します。かつ迅速に適切な危機対応は、被害を最小限に抑え、信頼回復の第一歩となります。
危機対応の基本原則:
- 迅速な認識と対応:問題を間違って認識し、対応を開始する
- 透明性の確保:事実を隠蔽せず、正直に状況を説明する
- 謝罪と責任の明白化:とりあえず謝し、責任の所在を謝罪する
- 具体的な改善策の提案:再発防止のための具体的な措置を示す
- 継続的なコミュニケーション:状況を定期的に改善し、信頼回復に努める
例えば、あるアパレルブランドは性差別的なTシャツデザインに対して批判的に受け止め、迅速に販売を中止し、公式な承認を発表、さらに商品開発プロセスの見直しと多様性委員会の設置を約束しました。
失敗事例 2:一貫性の欠如とブランド価値の希薄化
ブランド戦略の失敗の多くは、継続性の欠如によってしっかりと行われます。
ブランドの変更には慎重な対応が求められます。ある企業では、長年愛されていたマークを変更したところ、新しいデザインに対して批判が相次ぎました。これを受けて企業は新たなロゴのデザイン公募を実施。しかし、元のデザイナーへの配慮が不足しているとの声が上がり、批判を中心に結果となりました。
安易な迎合ができる問題点:
- ブランドの継続性喪失:短期的な反応に基づく変更が、長期的なブランドビジョンを失う
- 信頼性の低下:方針の揺らぎが、ブランドの確固たる確信や価値観の欠如と認められる
- 内部の平和:頻繁な方針変更が社内の混乱や疲労を考える
- コアファンの離反:ブランドの本質的価値に共感していたロイヤルカスタマーの失望
顧客の声を尊重することは重要ですが、すべての意見に即座に合わせるのではなく、自社のブランド価値や長期的なビジョンに照らして判断することが求められます。特に、SNS などで緩和化される意見は、主観全体の声を代表しているわけではないことを認識する必要があります。
存在するサービスとのイメージの相対的な混乱
ブランドの認知度が高い企業が新たな分野へ進出する際、存在するサービスと新サービスの方向性が大きく異なり、消費者の平和や冷静な反応を考えるリスクがあります。
例、高級ブランドが突然新しい低価格路線の商品を展開した結果、「ブランドの価値が混ざった」と感じ、顧客が増え、事業が失敗したケースがあります。市場への参入は魅力的ですが、ブランドの核心的価値を認識しないことが必要です。
イメージを逆に見るためのアプローチ:
- サブブランドの活用:既存のブランドと区別した新ブランドの立ち上げ
- 段階的な展開:徐々にな変化を避け、顧客の理解や受容を徐々に育む
- 共通価値の明確化:新展開と既存ブランドとの共通点や連続性を強調
- 顧客の明確な区分け:異なる中間層への訴えを明確に選択
例えば、高級自動車ブランドがエントリーモデルを投入する際、「品質へのこだわり」という核心的価値は維持しつつ、さまざまなニーズに応えるポジショニングを明確にすることで、ブランド価値の希薄化を防ぐことができます。
ブランドの核心部分を守る重要性
市場環境トレンドや変化に適応することは重要ですが、ブランドの核心の価値や独自性は守り続けることが、長期的な成功の鍵となります。
核心の部分を守るためのポイント:
- ブランドの本質の明確化:危険な核心の価値と、柔軟に変化させる要素を区別する
- 戦略的な継続性:短期的なトレンドや動向の維持に過剰反応せず、自社の長期的な方向性をする
- 変化と継続性のバランス:時代に即した表現方法を採用しつつ、メッセージの本質は変えない
- 意思決定の基準の確立:新たな取り組みがブランドの核心的価値一致するかどうか判断する明確な基準を持つ
例えば、Apple は製品や幅広いデザインを時代に合わせて進化させていますが、「革新性」「洗練されたデザイン」「使いやすさ」といった核心の価値は徹底的に守り続けています。この一貫性が、強固なブランドロイヤルティの基盤となっています。
失敗を回避するためのチェックポイント
ブランド戦略の失敗を防ぐためには、計画から実行に至るまで、多角的な視点でチェックを行うことが重要です。ここでは、ブランド戦略の失敗を回避するための具体的なチェックポイントを紹介します。
ステークホルダーの多様性を考慮した検証プロセス
ブランド戦略を構築・実行する際には、多様なステークホルダーの視点を取り入れた検証プロセスを確立することが重要です。
検証プロセスの構築ポイント:
- 多様な背景を持つメンバーによるレビュー:年齢、性別、文化的背景など異なるメンバーからのフィードバックを収集
- ユーザーテスト・フォーカスグループ:実際のターゲット顧客に対するテストを通じた検証
- 社内クロスファンクショナルチーム:マーケティング、営業、製品開発、顧客サポートなど異なる部門によるメンバーによる検討
- 外部専門家の視点:業界のトレンドや社会的感覚に精通した外部アドバイザーの活用
例えば、ある飲料メーカーは新製品のキャンペーン展開前に、異なる世代や文化的な背景を持つ消費者パネルによるレビューを実施し、潜在的な問題点を事前に発見・修正することができました。
短期的な売上と長期的なブランド価値のバランス
ブランド戦略の失敗の多くは、短期的な売上向上を重視するあまり、長期的なブランド価値を損なうことから起こります。 両者的なバランスがあり、持続可能な成長につながります。
バランス確保のための視点:
- 短期・中期・長期の目標設定:異なる時間軸での成果指標を明確に設定
- ブランド価値を損なう可能性のある慎重な評価:価格訴求や過度なプロモーションなどの長期的な影響を検討
- 顧客生涯価値(LTV)を重視:一時的な売上よりも、長期的な顧客関係構築を優先
- ブランド資産の定期的評価:ブランド認知度、好感度、推奨などの指標を継続的に測定
例えば、ある家電メーカーは短期的な販売増を目的とした低価格モデルの投入を検討していましたが、ブランドイメージへの影響を考えて、代わりに「エントリープレミアム」というコンセプトで品質を維持しつつ機能を絞ったモデルを展開しました。 結果的に、ブランド価値を損なうことなく新規顧客の獲得に成功しました。
定期的な振り返りとブランド運営体制の確立
ブランド戦略は一度決めて終わりではなく、市場環境や顧客ニーズの変化に合わせて継続的に見直し、改善していく必要があります。そのための体制づくりが重要です。
効果的なブランド管理の要素:
- ブランド管理の責任者・組織の明確化:ブランド戦略を統括する責任者や専門チームの設置
- 定期的なブランド監査:ブランドの継続性、市場での認知、大衆との差別化などを定期評価する
- ブランドガイドラインの整備と更新:ビジュアルやメッセージの継続性を確保するためのガイドライン管理
- 市場環境や顧客動向のモニタリング:トレンドや価値観の変化を捉え、必要に応じて戦略を調整
- 成功・失敗事例の社内共有:学びを組織全体に浸透させるための仕組み
ジョンソン・エンド・ジョンソンは「我が信条(当社Credo)」に基づく「クレドサーベイ」を全世界で1回実施し、ブランド価値の実践状況を評価・改善するサイクルを確立しています。このような定期的な振り返りと改善が、長期的なブランド価値の維持・向上につながります。
これらのチェックポイントを自社のブランド戦略プロセスに組み込むことで、多くの失敗を防ぐため、より強いことが堅固なブランドを構築できるでしょう。
ブランド戦略を成功させるための5つの実践ポイント

発信する情報の継続性とブランド価値の維持
ブランド戦略を成功させる最も重要な要素の一つが、「発信する情報の一貫性」です。情報の継続性がブランド目標の印象や認知の形成において決定的な役割を果たします。
あらゆるタッチポイントで一貫したメッセージ発信
現代の消費者は、多様なチャネル企業と触れ合います。ウェブサイト、SNS、広告、店舗、カスタマーサポート、製品パッケージ、さらには従業員の対応まで、すべてのタッチポイントで一貫したブランドメッセージを発信することが重要です。
継続性確保のための具体的な対応:
- ブランドメッセージングフレームワークの構築:核となるメッセージと各チャネル向けの展開方法を明確化
- 視覚的知覚要素の統一:ロゴ、カラー、フォント、デザインなどの一貫した適用
- トーン&ボイスの統一:ブランドの個性を反映した一貫した「話し方」の確立
- クロス連携:オンラインとオフラインの体験を一貫して実現する
- 部門横断的なコミュニケーション:マーケティング、営業、カスタマーサポートなど異なる部門間での連携強化
例えば、Apple社はウェブサイト、広告、店舗デザイン、製品パッケージ、さらには製品に至るまで、シンプルでエレガントなデザイン言語を一貫して適用しています。この徹底した一貫性が、強固なブランドイメージの構築に大きく貢献しています。
長期的な視点でのブランド価値の保護と進化
ブランド戦略は「短期的な売上向上」ではなく「長期的なブランド価値の構築」を目指すべきものです。 トレンドや現状の動きに過剰反応せず、自社の核心の価値を守りながら正しく進化させることが重要です。
ブランド価値の保護と進化のバランス:
- 変えるべきものと守るべきものの区別:ブランドの本質的価値は守りつつ、表現方法は時代に合わせて更新する
- 段階的な変化の管理:大幅な変更を避け、顧客の理解や受容を徐々に受容
- 定期的なブランド監査:ブランド価値の市場での認知や評価を定期測定
- 現状分析と差別化の維持:現状の動向を把握しつつも、独自性を維持
- 社会的変化への適応:価値観や技術の変化に対応しながらも、ブランドの核心は保持する
例えば、コカ・コーラは100年を超えて「楽観性」「幸福感」という核心の価値は変えずに、時代に合わせたメッセージや視覚表現を更新し続けています。この「変わるものと変わらないもの」のバランスが、長期的なブランド価値の構築につながっています。
社内教育とガイドラインの重要性
ブランドの継続性を確保するためには、社内の理解と協力が必要です。従業員全体がブランドの価値や表現方法を見据え、日々の業務に反映できるよう、システム的な教育とガイドラインが必要です。
効果的な社内浸透のアプローチ:
- 含まれるブランドガイドラインの整備:ロゴやカラーだけでなく、言語表現やブランドストーリーも含む
- ブランド教育プログラムの実施:新入社員研修や定期的なワークショップを通じた理解促進
- 使いやすいブランドツールキットの提供:テンプレート、素材、チェックリストなどの実用的なリソース
- 部門別のブランド適用ガイド:各部門の特性に合わせた具体的な実践方法
- ブランド実践の表彰・共有:優れた取り組み事例を評価し、組織全体で共有
水戸ヤクルト販売の事例では、「免疫ライフ」というメッセージを社員教育に組み込んで、従業員がそのまま「販売員」ではなく「健康の伝道者」としての役割を自覚しているようです。この内部からの一貫性が、外部への一貫したメッセージ発信を可能にしています。
客観的な視点による戦略評価と定期的な振り返り
ブランド戦略の成功には、自社の状況を客観的に評価し、定期的に振り返るプロセスが要りません。 内部の視点だけでは見落としがちな問題点や機会を発見するためには、客観的な視点と体系的な評価方法が必要です。
ブランド戦略を立てる際、自社と外部環境の分析が必要になります。ただし、内部の視点だけでは「思い込み」や「偏見」に囚われがちです。外部の視点を積極的に捉えることで、より客観的な戦略を見据えて評価が可能になります。
外部視点の捉え方:
- 専門コンサルタントの活用:業界や市場に精通した専門家のアドバイスを受ける
- 顧客インタビューやフォーカスグループ:実際の顧客から直接フィードバックを収集
- 注目ベンチマーク:業界のベストプラクティスやマーケティングの戦略を分析
- クロスインダストリー分析:異なる業界の成功事例から学ぶ
- 独立した第三者評価:自社の利害関係のない立場からの評価を受ける
例えば、ある製造業企業では、年に一度「外部ブランド監査」を実施し、業界アナリスト、ブランドコンサルタント、主要顧客代表からなるパネルによる評価を受けています。この外部視点が、内部ではあまりなかった改善点の発見に取り組んでいます。
データに基づいた定期的な効果測定と戦略修正
ブランド戦略の効果を客観的に評価するためには、感覚や印象ではなく、具体的なデータに基づく測定が重要です。定量的・定性的な指標を設定し、定期的に測定することで、戦略の効果を定着させ、必要に応じて修正することができます。
的な効果測定と修正のサイクル:
- KPI の明確な設定:ブランド認知度、イメージ、顧客ロイヤルティなど、測定すべき指標を明確化
- 定期的な測定の仕組み:隔期、半期、年次など、定期的な測定サイクルの確立
- 複数の測定手法の組み合わせ:アンケート、インタビュー、行動データ分析など多角的なアプローチ
- 結果分析と課題抽出:データから課題や改善点を特定
- 戦略・計画の調整:分析結果に基づく具体的な改善策の実施
例えば、NPS®(ネットプロモーター)スコア)を活用したブランドロイヤルティの定期測定は、多くの企業で効果を上げています。ポイントスコアを測るだけでなく、「なぜその評価をしたのか」という理由を分析し、具体的な改善策に結びつけることが重要です。
フレームワークを活用した系統的な振り返り
ブランド戦略の振り返りを効果的に行うには、体系的なフレームワークを活用することが有効です。フレームワークを置くことで、感覚的な評価ではなく、多角的かつ系統的な分析が可能になります。
振り返りに活用できるフレームワーク:
- SWOT 分析の定期的更新:内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・展望)の変化を捉える
- BSC(バランススコアカード):指標、カスタマー、内部プロセス、学習と成長マップの4つの視点からの評価
- ブランドエクイティピラミッド:認知→思考→品質評価→ロイヤルティの段階的評価
- カスタマージャーニーの再評価:顧客体験の各段階における変化の分析
- ブランドプリズムの再確認:ブランドの各要素が市場環境の変化に対して正しい適切評価
これらのフレームワークを活用することで、「なんとなく良さそうだ」「なんとなく課題がありそう」という解消な評価ではなく、具体的な強みや課題を特定し、効果的な改善策を取り組むことができます。
持続可能なブランド戦略の実行とインナーブランディング
ブランド戦略は一朝一夕に成功するものではなく、長期的な視点での持続的な取り組みが必要です。また、外部に向けたブランディングと同様に、内部の理解と実践を置き換える「インナーブランディング」も重要な要素です。
長期短期としてのブランド戦略の短期
企業におけるブランド戦略は一時的に一朝一夕に成功するものではありません。短期的な成果を期待するのではなく、長期的として暫定的に、継続的に取り組んでいくことが大切です。
長期的な視点での取り組みのポイント:
- 中長期ロードの考え方:3〜5年単位の段階的な目標と実行計画
- 短期的な短期との統合性確保:暫定や年間の予測がブランド戦略と一致しているか確認
- 経営陣のコミットメント獲得:短期的な成果圧力に負けない経営層の理解と支援
- 投資対効果の適切な評価:ブランド価値向上の中の長期的な効果を早急に評価した
- 継続性のあるリソース的な配分:ブランド構築に必要な安定のリソース確保
例、ジョンソン・エンド・ジョンソンの「我が信条(当社Credo)」に基づくブランド戦略は、60年以上じっくりと実践されています。経営陣の交代や市場環境の変化にもかかわらず、内部核的な価値を守り続けることで、長期的な信頼構築に成功しています。
社員の理解と体現を変えるコミュニケーション
ブランド戦略の成功には、全従業員の理解と実践が心構えです。特に顧客と直接接する従業員は、ブランドの「生きている現者」として重要な役割を果たします。適切な内部コミュニケーション、全従業員がブランドの価値や意義を見据え、日々の業務に反映できるよう支援することが重要です。
効果的なインナーブランディングの取り組み:
- トップマネジメントからの一貫したメッセージ:経営層自らがブランド価値を体現し発信
- ストーリーテリングの活用:抽象的な価値観を具体的なストーリーで伝える
- 双方向コミュニケーション:一方的な伝達ではなく、対話と参加を最大限に
- 成功事例の共有:ブランド価値を体現した優れた実践例を表彰し共有
- 採用・評価への反映:ブランド価値と一致した行動を評価・報酬の対象とする
スターバックスは、店舗スタッフを「パートナー」と呼び、企業理念や価値観の覚悟のための研修に多大な投資をしています。その結果、顧客はポイントコーヒーを購入するだけでなく、スターバックスの価値観を体現したスタッフとの交流、ブランド体験を楽しんでいます。
時代の変化に適応しながらも核を守る柔軟性
市場環境や消費者の価値観は日々変化しており、ブランドにもそれに応じて適応する必要があります。しかし、すべてを変えては継続性が失われます。時代の変化に適応しながらも、ブランドの核心的な部分は守り続けるバランス感覚がです。
柔軟性と継続性の重要バランスポイント:
- 核心的価値と表現方法の区別:変更すべき本質と、更新すべき表現方法を明確に区別
- トレンド分析と選択的な対応:一過性のブームと本質変化を捉え、選択的に対応
- 顧客フィードバックの継続的収集:現状に対する満足度変化への期待を把握する
- プロトタイピングとテスト:大きな変更前に小規模なテストで反応を確認
- 変更の丁寧な説明:変更の理由や背景を顧客やステークホルダーに丁寧に説明
例えば、サステナビリティへの関心の対応し、多くの企業がブランド戦略に環境配慮やSDGsの視点を取り入れています。しかし、単に「グリーンウォッシング」ではなく、自社のブランド価値と有機的に顕在化した形で採用することが重要です。
これから、「変化への適応」と「核心の価値の維持」は対立するものではなく、当面し合うものです。時代の変化に合わせて表現方法や取り組みを更新しながらも、ブランドの本質的な価値は継続して守り続けることが、長期的なブランド構築の鍵となります。
まとめ:フレームワークを活用した効果的なブランド戦略構築

ブランド戦略フレームワーク活用の要点
本記事では、ブランド戦略の基本概念から実践的な7ステップアプローチ、8つの主要フレームワーク、成功事例と失敗事例まで、含めて解説してきました。ここでは、効果的なブランド戦略フレームワーク活用の要点をまとめます。
目的に合わせたフレームワークの選択と組み合わせ
ブランド戦略フレームワークは、それぞれ異なる目的や強みを持っています。自社の状況や課題に応じて、適切なフレームワークを選択し、必要に応じて複数のフレームワークを認識することが重要です。
フレームワーク選択と組み合わせのポイント:
- 市場理解のためのフレームワーク:SWOT分析、PEST分析、3C分析などを活用して市場環境と自社の主観的に把握
- 顧客理解のためのフレームワーク:ペルソナ設計、カスタマージャーニーマップを活用して顧客の深層心理や行動を理解する
- ブランド構築のためのフレームワーク:ブランドプリズム、バリューチェーン分析を活用してブランドの本質と実行計画を設計
- 効果測定のためのワークフレーム:NPS®、BSCなどを活用連携してブランド戦略の効果を多面的に評価
- フレームワーク期間:各ワークフレームの分析結果を統合し、継続性のある戦略を構築する
例えば、PEST分析で社会の変化を把握し、その結果をペルソナ設計に反映させ、さらにブランドプリズムで価値を明確化するような流れで、フレームワークを連携させることができます。
理論と実践のバランスある取り組み
ブランド戦略は、理論的な限界と現場での実践をバランスよく行うことで効果を発揮します。理論に偏りと現実とのズレが生じ、実践のみ注力すると継続性や方向性を重視します。
バランスある取り組みのポイント:
- フレームワークの柔軟な適用:理論をそのまま適用するのではなく、自社の状況に合わせて調整
- 現場からのフィードバック:顧客と直接接する現場の声を戦略に反映
- 小規模な実験とスケールアップ:小規模なテストで効果を確認してから全社展開
- データと直感のバランス:定量的なデータだけでなく、定性的な洞察も重視
- 継続的な学習と調整:理論と実践の幼児戦略を精査
例えば、理論的には完璧な性格を設計しても、実際の顧客点で得られる反応と乖離している場合は、理論を修正する柔軟性が必要です。
ブランド戦略は一度決めて終わりではなく、市場環境の変化や自社の成長に合わせて継続的に改善していく必要があります。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を確立し、定期的な見直しと改善を行うことが重要です。
継続的改善のサイクル構築:
- 定期的な戦略レビュー:四半期、半期、年次などの定期的なタイミングでの振り返り
- KPIモニタリングの仕組み:ブランド関連指標の定期的な測定と分析
- 市場環境変化の継続的な把握:PEST分析などを定期的に更新
- 顧客インサイトの継続的収集:定性・定量調査を通じた顧客理解の深化
- 組織的な学習の促進:成功・失敗事例から学び、知恵を絞る・共有文化の醸成
長期的に成功しているブランドの多くは、このような継続的な改善のサイクルを確立しています。例えば、Amazon は「日」1」の精神を大切に、常に創業のような危機感と革新性を持ち続けながら、変化する市場環境に適応し続けています。
これからのブランド戦略に求められる視点
最後に、今後のブランド戦略に関して重要性を高めると考えられる視点についてお話します。市場環境や消費者の価値観は急速に変化しており、これからのブランド戦略にはこれらの変化を先取りする視点が求められます。
デジタルトランスフォーメーションへの対応
デジタル技術の急速な進化により、ブランドと顧客の関係性も大きく変化しています。AIやビッグデータ、VR/ARなどの新技術を活用したブランド体験の創造や、オンライン・オフラインの融合(OMO:Online Merges with Offline)など、デジタルトランスフォーメーションへの対応が特典です。
デジタル時代のブランド戦略のポイント:
- データドリブンナパーソナライゼーション:顧客データを活用した個別化されたブランド体験の提供
- デジタルとリアルの統合体験:オンラインとオフラインを集中したブランド体験として設計
- コミュニティ形成と関与:SNSなどを活用した顧客コミュニティの構築と対話
- コンテンツマーケティングの進化:顧客の関心事に合わせた価値あるコンテンツの継続的提供
- 新技術によるブランド体験の拡張:AR/VR、AI、IoTなどを活用した新しいブランドタッチポイントの創出
例えば、ナイキはデジタル技術を活用したパーソナライズされた製品体験(NIKEiD)や、トレーニングアプリを通じたコミュニティ形成など、デジタルとリアルを融合させたブランド戦略を展開しています。
サステナビリティと社会的責任の統合
環境問題や社会的公正への関心が高まっている中で、ブランドには概念的利益追求を超えた社会的責任が求められています。サステナビリティやESG(環境・社会・ガバナンス)の視点を、付加的な要素ではなくブランド戦略の中核に統合することが重要です。
サステナブルなブランド戦略のポイント:
- 真正性(オーセンティシティ)の確保:表面「グリーンウォッシング」ではなく、本質的な取り組み
- バリューチェーン全体での取り組み:確保から廃棄までの全プロセスでの持続可能性追求
- ステークホルダーとの協働:顧客、従業員、地域社会など多様な関係者との協力
- 長期的な視点での価値創造:短期的利益と社会的・環境的価値のバランス
- 透明性と説明責任:戦略と成果の積極的な開示と対話
例えば、パタゴニアは「私のホーム、地球を救うための事業」というミッションを掲げ、環境保全活動や製品寿命、修理サービスなど、本業を通じたサステナビリティへの取り組みをブランドの核心として熱心に取り組んでいます。
パーパスドブンナブランド構築の重要性
現代の消費者、特にミレニアル世代やZ世代は、孤立商品やサービスではなく、企業の存在意義(パーパス)や価値観に共感して購入を決定する傾向が強まっています。
- 社会的意義の明確化:社会や顧客の生活にどのような意義ある変化をもたらす定義
- 価値観の共有:企業と顧客が共感できる価値観を理解する
- 継続した行動:課題パーパスと実際の企業活動の一致
- 社内外への浸透:従業員から顧客まで、すべてのステークホルダーとパーパスを共有
- 長期的コミットメント:短期的なマーケティングキャンペーンではなく、長期的な約束として期限
例えば、ユニリーバは「サステナブルな生活を当たり前のものにする」というパーパスを大切に、すべてのブランドがこの目的に貢献することを目指しています。このようなパーパスドリブンなアプローチは、顧客との感情的なつながりを強化し、長期的なロイヤルティ構築に貢献します。
本記事で解説したブランド戦略の基本フレームワークと実践ポイントに、これらの新しい視点を踏まえて、変化する市場環境の中でも持続的な競争優位性を確立するブランド戦略を構築することができるでしょう。結局「売れる仕組み」ではなく、「選ばれ続ける理由」を創り出す—それがブランド戦略の本質であり、フレームワークはその実現を支える有効なツールなのです。i=11>
最終的に重要なのは、フレームワークの魅力ではなく、その顧客と深い感情的なつながりを構築し、集中性のあるブランド体験を提供することです。理論と実践のバランスを大切にしながら、独自の独自のブランド価値を明確にし、すべてのタッチポイントで一貫して表現していくことが、真に強いブランドを築く鍵となります。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















