ウェビナー集客の手法12選|申し込みを増やすための実践ガイド
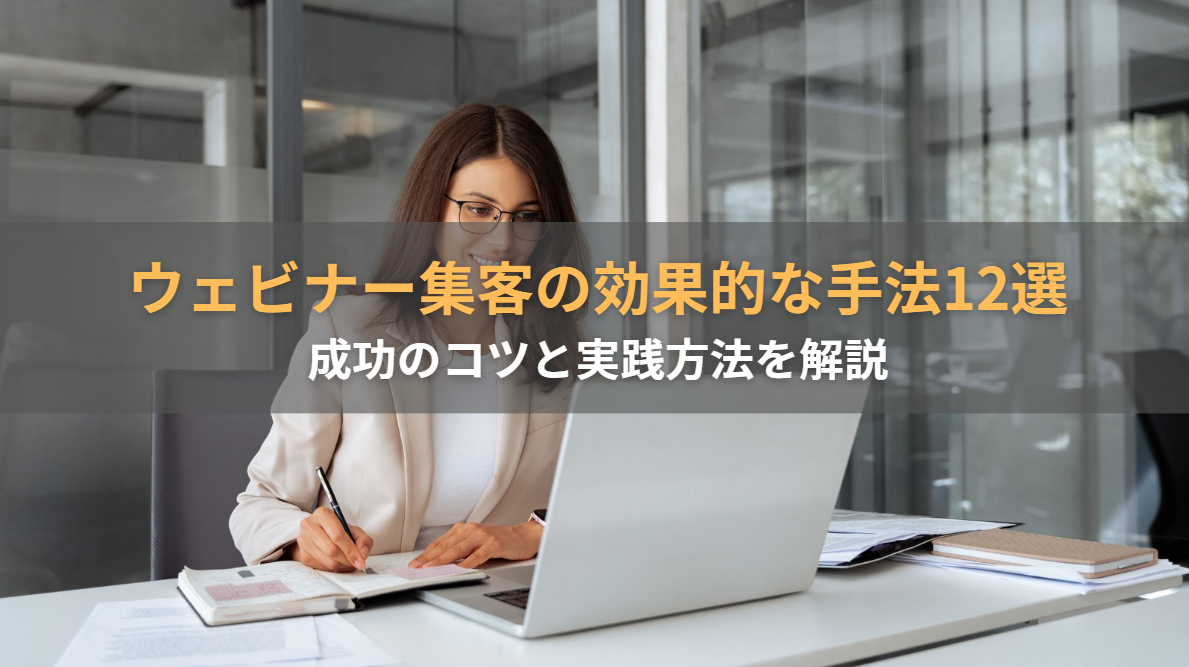
- 多様な集客チャネルの戦略的活用:SNS、メール、Web広告、セミナーポータルサイトなど12の手法を組み合わせることで、幅広い層にアプローチし、リスク分散を図りながら効果的な集客を実現
- 明確なターゲット設定とペルソナの策定:具体的な人物像を設定し、その課題や情報収集行動に合わせた集客戦略を構築することで、より質の高い参加者を効率的に獲得
- 継続的な効果測定と改善:申し込み数、参加率、満足度、商談化率などの包括的なKPIを設定し、PDCAサイクルによる継続的な改善で集客効果を最大化
- 業界別・規模別の最適化戦略:BtoB企業ではLinkedIn広告の活用、BtoC企業ではSNSマーケティング、スタートアップでは無料チャネルの最大活用など、企業特性に応じた戦略的アプローチ
- 参加率向上のための実践的テクニック:複数回配信、告知型・Tips型メールの使い分け、効果的なリマインド配信、魅力的な参加特典の設計により、申し込みから参加までの歩留まりを向上
ウェビナーの申し込みが伸び悩む原因の多くは、コンテンツではなく集客設計にあります。どれだけ質の高い登壇者を立てても、告知チャネルの選択を誤れば参加者は集まりません。
この記事では、オンライン・オフライン合わせて12の集客手法を、BtoBマーケターがすぐに使える形で解説します。SNSやメール配信の具体的な運用方法から、参加率を上げるリマインド設計、業界別のチャネル選定の違いまで、施策の全体像をカバーしています。
「どの手法から着手すればいいか」を判断できる内容を目指しましたので、集客に課題を感じている担当者の方はぜひ最後までご覧ください。

ウェビナー集客の基本知識
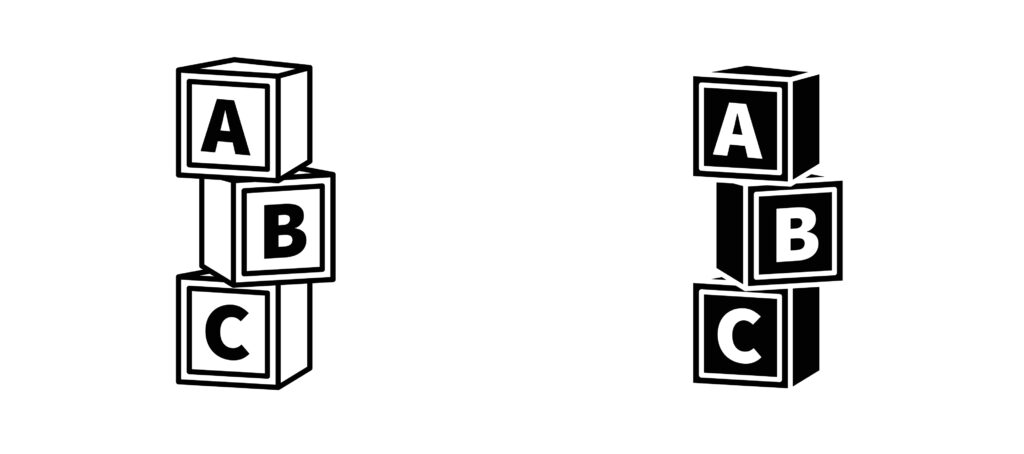
ウェビナーとは「Web」と「Seminar」を掛け合わせた造語で、インターネット経由で配信するオンラインセミナーを指します。参加者は場所を問わず参加でき、企業側も会場費や移動コストを抑えられます。BtoBマーケティングでは、見込み顧客との接点づくりやリード育成の手段として、すでに多くの企業が継続的に活用しています。
Content Marketing Instituteの調査によると、BtoB企業の55%がウェビナーをコンテンツ配信手法として活用しており、対面イベントとほぼ並ぶ評価を受けています(2024年)。規模を問わず取り組みやすく、開催後の録画を営業資料として再利用できる点も、費用対効果を高める理由の一つです。
ウェビナー集客の特徴とメリット
対面セミナーと比べてウェビナーが集客しやすい最大の理由は、参加者の行動コストが低いことです。交通費も移動時間も不要なため、遠方の見込み顧客や多忙な役職者にもリーチできます。
一方で、気軽に申し込める分、当日キャンセルも発生しやすいという側面があります。業種を問わない平均参加率は申込者の46%前後とされており(99Firms調べ)、申し込みを集めるだけでなく、当日参加まで誘導する設計が欠かせません。録画・アーカイブ配信を用意することで、この歩留まりをカバーする施策にもなります。
効果的なウェビナー集客の全体像
集客を一つのチャネルに頼ると、配信エラーや想定外のリーチ不足が起きたとき回復できません。メール・SNS・Web広告・ポータルサイトなど、複数のチャネルを組み合わせることがリスク分散の基本です。
各チャネルには役割の違いがあります。メール配信は既存リストへのリーチに強く、SNSは新規層への拡散に向きます。有料広告は即効性がありますが単価が上がります。この特性を踏まえてチャネルを組み合わせ、開催3〜4週間前から告知を開始するのが標準的な進め方です。
ウェビナー集客の準備段階

ターゲット設定とペルソナの明確化
集客がうまくいかないウェビナーの多くは、ターゲット設定が曖昧なまま告知を始めています。「マーケティング担当者向け」では広すぎます。業界・役職・抱えている課題・情報収集の行動パターンまで絞って初めて、チャネル選定と訴求メッセージが決まります。
たとえば「SaaS企業のマーケティング担当者で、リード獲得数の改善を上長から求められているが、広告予算は限られている」という人物像を設定すれば、LinkedIn広告でのターゲティング条件も、メールの件名も、ランディングページの訴求軸もすべて変わってきます。参加者の数ではなく質を上げるには、ペルソナの粒度を上げることが先決です。
意思決定者と実務担当者を同時に集めようとすると、どちらにも刺さらないウェビナーになりがちです。テーマによって対象を分け、複数回開催する方が商談化率は上がりやすくなります。
魅力的なタイトルとコンテンツ設計
ウェビナーのタイトルは、申し込みページに到達する前に判断される最初のフィルターです。「デジタルマーケティングについて学ぶ」という概念訴求より、「リード獲得数を3ヶ月で1.5倍にした施策を公開」という成果訴求の方が申し込み率は上がります。タイトルに入れるべき要素は、誰向けか・何が得られるか・なぜ今なのか、の三点です。
コンテンツ設計では、参加者が当日持ち帰れる「使える知識」を軸に組み立ててください。概論に終始せず、具体的な事例・数値・手順を盛り込みます。登壇者のネームバリューや実績も集客力に直結します。業界の専門家や実績ある実務家を起用することで、告知の段階から注目度が上がります。
集客目標の設定と予算配分
目標は「参加者○名」だけを設定しがちですが、最終的な目的が商談獲得であれば、参加者数→商談化率→受注数の逆算で集客目標を決めるべきです。BtoBウェビナーの商談化率は業種・テーマによって差がありますが、ターゲット精度が高いウェビナーでは10〜20%程度が一つの目安になります。
予算配分の一例として、有料広告40%・コンテンツ制作費30%・ツール・プラットフォーム費用20%・予備費10%という構成があります。ただし、この比率は既存リストの有無や認知度によって大きく変わります。ハウスリストが充実している企業ならメール中心で広告費を抑えられますし、新規開拓が目的なら広告比率を引き上げる必要があります。どのチャネルが費用対効果を出しているかを毎回記録しておくことが、次回以降の精度を上げることにつながります。
オンライン施策によるウェビナー集客方法

自社メディア(Webサイト・ブログ)の活用
自社サイトは既存の見込み顧客が訪れる場所です。トップページの目立つ位置にバナーを設置し、ウェビナー専用のランディングページへ誘導します。LPには登壇者の顔写真・肩書・アジェンダ・申し込みフォームを一画面に収め、余計な離脱を防ぐ構成が基本です。
ブログ記事からの誘導も効果的です。ウェビナーテーマに関連する記事の末尾にCTAを置くことで、検索流入からの申し込みも期待できます。「デジタルマーケティング戦略」についてのウェビナーであれば、関連キーワードで書かれた複数の記事からランディングページへ誘導する設計にすると、集客効率が上がります。
SNSマーケティングの効果的な活用法
SNSは新規層へのリーチに強く、既存リストに届かない層を獲得する手段として機能します。
X(旧Twitter)は拡散力が高く、ハッシュタグを使った投稿がウェビナーに関心を持つユーザーに届きやすい媒体です。Facebookはイベント機能を使ってウェビナーページを作成でき、参加表明がそのまま告知の拡散につながります。LinkedInはBtoBに限定すれば職種・業界での絞り込み精度が最も高く、意思決定者層に届けたいウェビナーでは優先的に活用すべき媒体です。
投稿のタイミングは開催2〜3週間前から段階的に始め、最初は概要告知、1週間前からは登壇者情報や申し込み締め切りを加えて告知を強化していきます。
メールマーケティングの戦略的運用
GoToWebinarの調査では、ウェビナーの集客経路として最も多いのがメール配信です。既存のハウスリストを持つBtoB企業にとって、メールは最も費用対効果の高い集客手段といえます。
告知メールには「告知型」と「Tips型」の2種類があります。告知型は200〜300文字でウェビナーの開催情報だけを伝えるシンプルな構成で、テンプレートを用意しておけば数分で作成できます。一方のTips型は、ウェビナーテーマに関連するノウハウを500文字程度で届けつつ、その延長でウェビナーへの参加を促します。普段の告知メールに反応しない層にも届くため、両方を使い分けることで集客の間口が広がります。
2種類を組み合わせた配信スケジュールの例として、開催4週間前に告知型、3週間前にTips型、2週間前に告知型、1週間前にTips型を送る方法があります。件名には「残席〇名」「開催まで〇日」など具体性と緊急性を持たせると開封率が上がります。
配信リストをセグメント化し、業種・役職・過去のウェビナー参加履歴に応じてメッセージを変えると、申し込み率はさらに高まります。
セミナーポータルサイトの活用法
セミナーポータルサイトに掲載する最大のメリットは、セミナーを探して訪れているユーザーにリーチできることです。既存リストの外にいる参加意欲の高い新規層を獲得できます。
主要なサービスとして、こくちーずPro・Peatix(840万人以上が利用)・connpass・TECH PLAYがあります。TECH PLAYはIT・技術系に特化しており、エンジニアやIT担当者向けのウェビナーに向いています。Peatixは業種を問わず幅広い参加者にリーチできます。
無料で掲載できるサービスが多く、まず試しやすい選択肢です。掲載時には、視覚的に目を引くサムネイル画像と、参加して何が得られるかを明確に書いた説明文が申し込み率を左右します。
有料広告を活用したウェビナー集客

Web広告(Google・Facebook・LinkedIn)の活用
有料広告の強みは即効性です。告知開始から短期間で申し込みを集められる反面、CPAは他チャネルより高くなる傾向があります。既存リストが少ない企業や、新規層へのリーチを広げたいウェビナーで特に力を発揮します。
Google広告の検索連動型は、「ウェビナー 集客 方法」「オンラインセミナー マーケティング」などのキーワードで検索しているユーザーに表示されます。すでに課題を認識して情報を探している能動的な層へのアプローチになるため、コンバージョン率が高くなりやすいです。ディスプレイ広告は認知拡大に向いています。
Facebook広告は年齢・性別・興味関心・行動履歴での詳細なターゲティングが可能で、類似オーディエンス機能を使えば既存顧客と属性が近いユーザーにアプローチできます。
LinkedIn広告はBtoBウェビナーで投資対効果が出やすい媒体です。企業規模・業界・職種・役職レベルでの絞り込みが効くため、意思決定者や特定の職種に直接届けられます。クリック単価は高めですが、ターゲット精度が高い分、申し込みの質を維持しやすいという特長があります。
プレスリリースの戦略的活用
プレスリリースは、有料広告では届かないメディア読者層にリーチできる手法です。業界紙や専門メディアに掲載されると、そのメディアの読者層ごとウェビナーへの集客につながります。
メディアに取り上げてもらいやすいプレスリリースには、「業界初の事例」「著名な登壇者の起用」「最新調査データの発表」といったニュース性が必要です。開催2〜3週間前に配信し、掲載されたメディアの反響を次回以降のPR計画に反映させていきます。
外部メディアとの連携
業界メディアへの記事寄稿や、インフルエンサーとの共同告知は、自社の発信力を超えた集客につながります。記事寄稿ではウェビナーテーマに関連する専門コラムを提供し、記事末尾でウェビナーへ誘導します。読者との接点が自然な形で生まれます。
インフルエンサーへの協力依頼では、フォロワーの属性がウェビナーのターゲット層と重なるかどうかを最初に確認してください。フォロワー数より属性の一致度が重要で、業界の専門家や実務家のアカウントの方が、汎用的なビジネス系インフルエンサーより高い申し込み率につながることが多いです。
オフライン施策によるウェビナー集客

チラシ・ポスターの効果的な活用
デジタル施策が主流の今でも、特定の業界や地域に根ざしたウェビナーではオフライン媒体が機能することがあります。製造業・建設業・医療など、業界団体や商工会議所との接点が深い業種では、チラシの掲示や郵送が有効な集客経路になります。
作成時のポイントは、ウェビナーで得られる成果をタイトルと一文で表現することです。QRコードで申し込みフォームに直接誘導する設計にすれば、オフライン媒体からオンライン申し込みへのスムーズな導線が作れます。
ダイレクトメールの戦略的活用
DMは、重要顧客や意思決定者層への案内に特化した使い方が向いています。メールと違って物理的に手元に届く分、開封される可能性が高いのが特長です。
宛名に個人名を入れ、業界・企業規模に応じた内容にカスタマイズします。製造業向けのウェビナーであれば、製造業特有の課題を前面に出すことで反応率が上がります。「先着〇名限定」など緊急性を感じさせる要素も有効です。
口コミ・紹介システムの構築
過去のウェビナー参加者からの紹介は、新規集客の中でもコンバージョン率が高い経路の一つです。すでに自社への信頼がある参加者が「良かった」と知人に伝えることで、広告では作れない信頼が転移します。
紹介を促す仕掛けとしては、アンケート高評価者への個別フォローと紹介依頼、SNS投稿の促進、紹介者へのお礼特典(次回ウェビナーの優先案内・限定資料の提供など)が機能します。前提として、紹介したいと思われるクオリティのウェビナーを開催することが必要です。
参加率を上げる実践ポイント

複数回配信による機会損失の防止
日程が1つだけのウェビナーは、タイミングが合わない見込み顧客をそのまま逃してしまいます。同一内容を2〜3回配信するだけで集客数は大きく変わります。才流の実績データでは、3回配信した場合の集客比率は1回目に集中し、2回目・3回目で残りを分け合う形になります。4回以上に増やしても集客数はほぼ増えないため、2〜3回が現実的な上限です。
配信方法は毎回ライブか、初回録画を使った疑似ライブかの2択になります。外部講師や共催パートナーがいる場合は疑似ライブが現実的で、内製で完結する場合はライブを重ねることで登壇クオリティが毎回上がっていきます。
告知型とTips型メールの使い分け
メールの告知型とTips型については前述しましたが、配信スケジュールの設計が特に重要です。開催4週間前から告知型・Tips型を交互に送ることで、異なる動機を持つ読者それぞれに刺さる接点が作れます。
申し込みは開催1週間前に集中する傾向があり、GoToWebinarのデータでも申し込み者の59%が開催1週間以内に申し込むとされています。告知期間の後半に配信頻度を上げることで、このタイミングに合わせた集客ができます。
アンケートを活用した継続集客
ウェビナー終了直後のアンケートは、次回の集客チャネルになります。満足度が高かった参加者は次回ウェビナーへの関心も高く、アンケート内で次回の概要を伝えて申し込みの意向を確認することで、次回の初期集客を確保できます。
この手法が機能する条件は、誘導元と誘導先のテーマに関連性があること、満足度が5段階評価で平均4.0以上であること、次回の開催時期が1〜2週間後程度であることの三点です。
参加特典の設計と活用方法
申し込みを増やしたいなら、特典はウェビナーテーマに直結するコンテンツにします。ROI計算テンプレートや施策チェックリストなど、参加者が翌日の業務で使えるものが最も反応を得やすいです。割引クーポンより実務ツールの方が、BtoBターゲットには刺さりやすい傾向があります。
特典を申し込み完了後に即時送付すれば早期申し込みを促せます。アンケート回答後に渡す構成にすれば回答率が上がります。目的に応じて提供タイミングを変える設計にするとよいでしょう。
申し込みフォームの最適化
入力項目の数は申し込み完了率に直結します。氏名・メールアドレス・会社名の3項目を必須として、それ以外は任意に設定することをお勧めします。項目が増えるほど離脱率は上がります。
モバイルからの申し込みが多い現状では、タップしやすいボタンサイズと縦スクロール対応のレイアウトは欠かせません。送信ボタンのテキストは「登録する」より「無料で参加する」「今すぐ申し込む」の方がクリック率が上がりやすいです。
リマインドメールの効果的な配信
申し込んだウェビナーを当日に忘れている参加者は少なくありません。リマインドを4回送るだけで参加率は大きく変わります。開催1週間前・3日前・前日・当日朝の4タイミングが基本です。
1週間前のメールでは参加メリットを再確認し、3日前には登壇者の情報やアジェンダを補足します。前日と当日は接続URLと参加手順を明記します。各メールにカレンダー登録ファイルを添付しておくと、見落としによるキャンセルを減らすことができます。度であることの三点です。
ウェビナー集客の効果測定と改善

KPI設定と効果測定の重要指標
測定すべき指標を増やしすぎると、何を改善すべきか分からなくなります。商談創出を目的とするBtoBウェビナーに絞れば、優先すべき指標は集客数・参加率・商談化率の三つです。
参加率の目安として、国内での運用経験に基づくと対策なしで60〜65%、リマインド設計が整っているウェビナーでは70%前後になることが多いとされています。海外データでは平均46%と低く出ますが(99Firms調べ)、これは時差による影響も大きいため、国内ウェビナーの目標値とは切り分けて考えることをお勧めします。
満足度は5段階評価で4.0以上を最低ラインとして設定します。4.3以上が続くようであれば、アンケート経由の次回集客にも活用しやすい水準になります。
集客チャネル別の効果分析
チャネルごとに何名の申し込みが来て、その中から何名が参加し、何件が商談になったかを記録します。このデータの蓄積なしには予算配分の最適化はできません。
一般的な傾向として、メール配信からの参加者は関心度が高く商談化率が上がりやすいです。SNSからは多様な新規層が来る反面、温度感はバラつきます。有料広告はターゲティング精度が商談化率を左右します。
チャネルの評価では短期ROIだけを見ないことが大切です。初回接触のコストが高くても、長期的に顧客になる可能性が高いチャネルであれば継続投資の価値があります。
ROI最適化のための予算配分見直し
予算配分の見直しは四半期ごとに実施します。全チャネルのデータが揃ったタイミングで、費用対効果が低いチャネルを削るか手法を変え、成果が出ているチャネルに再配分します。
新しい集客チャネルのテストには全体予算の10〜15%を確保しておくと、既存手法に縛られずに改善が続けられます。実験と記録を繰り返すことが、集客精度を上げる基本的な取り組みです。
業界別・規模別のウェビナー集客戦略

BtoB企業のウェビナー集客戦略
BtoBウェビナーの集客で効果が出やすい媒体は、LinkedIn広告と既存ハウスリストへのメール配信です。LinkedInは企業規模・業界・役職での絞り込みが効くため、「従業員300名以上の製造業のIT部門責任者」のような粒度でターゲティングできます。
コンテンツ戦略では「業務がどう変わるか」を具体的に示すことが参加動機を高めます。「生成AIで月20時間の業務を削減した事例」のような定量的な成果の提示が、「デジタルトランスフォーメーションの重要性について考える」という概念訴求より反応を得やすいです。
業界専門メディアへの記事掲載とウェビナーの組み合わせも有効です。読者が専門家として認識しているメディアに記事が掲載されることで、ウェビナー告知の信頼性が上がります。
BtoC企業のウェビナー集客戦略
BtoCウェビナーの集客はInstagram・X・Facebookなどのビジュアルコンテンツが軸になります。参加者個人の課題や願望に直接訴えるコンテンツが有効で、「3ヶ月で体重を10kg落とした食事管理の方法」「副業で月10万円を達成した手順」のような具体性のあるタイトルが申し込み率に直結します。
インフルエンサーとの協力を検討する際は、フォロワーの属性をウェビナーターゲットと照合してから判断することをお勧めします。フォロワー数より属性の一致度を優先することが大切です。
スタートアップ企業の効率的集客法
予算が限られているスタートアップは、創業者・経営者の個人SNSアカウントを最大限に活用します。法人アカウントより個人アカウントの方が拡散されやすく、創業者自身が登壇することでウェビナーの信頼性も上がります。
共催ウェビナーは初期に特に効果的です。顧客層が重なる非競合企業と共催することで、相手のハウスリストにリーチできます。単独では難しい集客数を、費用をかけずに実現できる手段として積極的に活用したい施策です。
業界のオンラインコミュニティやSlackグループへの告知、専門ブログへのゲスト投稿も、認知が広がっていない初期段階では費用対効果が高い選択肢です。
集客代行サービスと外部リソースの活用

集客代行会社の選び方
ウェビナー集客の専門知識がなく、人員も足りない場合は代行サービスの活用が現実的な選択肢になります。選定時に確認すべきポイントは三つです。自社と同業界または近い業界での集客実績があるか、申し込み数だけでなく参加率・商談化率まで報告・改善提案する体制があるか、担当者が自社のサービスを理解してメッセージを作れるか、を確認してください。
費用対効果の評価は、代行費用に対して実際に発生した商談・受注額で測ります。集客代行の費用は申し込み獲得単価換算で他チャネルと比較すると判断しやすくなります。
内製化と外注化の判断基準
外注化が向いているのは、継続的なウェビナー開催の予定がなく、マーケティング人材が不足していて、早期に成果が必要な状況です。内製化に切り替えるタイミングは、ウェビナーを四半期に2回以上継続する見通しが立ち、担当者が集客プロセスを学ぶ時間を確保できるようになってからが現実的です。
どちらを選ぶ場合も、チャネル別の集客数・参加率・商談化率のデータを蓄積することだけは始めておきましょう。このデータなしには内製化も外注評価も機能しません。
ウェビナー集客の成功事例と失敗例

成功事例から学ぶベストプラクティス
集客に成功したウェビナーに共通するのは、ターゲットの絞り込みが徹底されていること、複数チャネルを組み合わせていること、当日参加までのリマインド設計があることです。
アナグラム社が実施した「Google広告のP-MAXに関するセミナー」では、業界トレンドを押さえたテーマ設定と、ネームバリューのある実務家を登壇者に起用したことで約300名の集客を達成しました。「見せ方、タイトル次第でCPAや集客数も大きく変わる。ウェビナーは企画勝負」という同社の見解は、集客の本質を示しています。テーマ選定と登壇者の組み合わせが、広告運用の前に決まるべき最重要事項です。
よくある失敗パターンと対策
失敗パターンの筆頭は、ターゲット設定が広すぎて誰にも刺さらないケースです。「ビジネスパーソン全般向け」という設定では、チャネル選定も訴求メッセージも薄まります。ターゲットを絞ることで参加者数は減っても、商談化率が上がれば結果的に成果は増えます。
単一チャネル依存も失敗しやすいパターンです。メール配信だけに頼ると、スパムフィルタや配信エラーで想定していた告知が届かないリスクがあります。SNSやポータルサイトとの組み合わせで分散させておくことが基本です。
効果測定を参加者数だけで終わらせることも問題です。申し込み数が多くても商談にならなければ、集客チャネルと参加者の質が合っていない可能性があります。チャネル別の商談化率まで記録することで、次回の集客設計が改善されていきます。
業界別成功事例の分析
製造業では、業界専門誌との連携と導入事例の数値化が高い集客効果を生んでいます。技術者向けのウェビナーは、課題解決の具体性と実績数値が申し込みを左右します。
金融業界では、法制度の改正・規制変更といった緊急性のあるテーマが高い集客力を持ちます。「対応しなければ困る」という参加動機があるため、告知から申し込みまでの期間が短くなりやすい傾向があります。
IT業界では、新技術の導入事例と具体的なROI提示が効きます。参加者の多くが情報収集段階にある管理職層であるため、ウェビナー後の迅速なフォローが商談化率を決めます。
まとめ:継続的なウェビナー集客を実現するために

長期的な集客戦略の構築
単発のウェビナーで成果を出すことより、継続することの方が難しいです。毎回ゼロから集客を設計するのではなく、ウェビナーシリーズとして全体のコンテンツ構成を設計し、参加者が次のウェビナーにも来たいと思う流れを作ることが、長期的な集客コストを下げることにつながります。
各回の参加者データとアンケートを蓄積し、どのテーマで誰が申し込み、どのチャネルから来た人が商談になったかを記録してください。この蓄積が、次回以降の集客精度を高める資産になります。
継続改善のためのPDCAサイクル
ウェビナー終了後に振り返るべきことは、集客数・参加率・満足度・商談化率の四指標です。このデータを翌週中にまとめ、次回の改善計画に落とし込むサイクルを作れるかどうかが、継続できるチームとそうでないチームを分けます。
改善は小さくて構いません。タイトルを変えた、リマインドを1回増やした、特典を変えた。そういった単一変数の変更を記録し続けることで、自社のターゲットに何が効くかが分かってきます。
次世代のウェビナー集客トレンド
AIを活用した参加者行動の分析と、リマインドメールのパーソナライズ化が普及しつつあります。参加者の視聴行動データをもとに、フォローメールの内容や商談アプローチのタイミングを自動で変えられるツールが増えており、限られた人員での運用をカバーできるようになってきました。
ハイブリッド形式(会場参加とオンライン参加の同時開催)は、オフラインの熱量を持ちながらウェビナーの地理的利便性も提供できます。規模の大きなカンファレンスや年次イベントでは、この形式が集客の幅を広げる選択肢になります。
ウェビナーの申し込みを増やしたいなら、告知チャネルを増やす前に、タイトル・ターゲット・登壇者の組み合わせを見直すことが先決です。集客設計が整ったうえで、メール・SNS・広告の各チャネルを役割分担させていきます。どのチャネルからどの参加者が商談になったかを記録し、改善を繰り返す。そのサイクルを回せている企業が、ウェビナー集客で着実に成果を出しています。
デボノでは、ウェビナーをはじめとするBtoBマーケティング施策の設計・実行を支援しています。集客に使うコンテンツ・資料の制作から、データに基づいた施策の見直しまで、マーケティングの課題があればお気軽にご相談ください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















