中小企業のDX推進に関する調査~最新データから読み解く現状と成功への道筋~


- 中小企業のDX理解度は49.2%と約半数にとどまり、「知らない」企業が15.2%に増加するなど二極化が進行している。一方で、DXに取り組んでいる企業の約8割が成果を実感しており、適切なアプローチを取れば中小企業でも確実に成果を出せることが調査で明らかになった。
- 従業員規模によって課題が大きく異なり、20人以下の小規模企業では「何から始めてよいかわからない」が27.7%と最大の課題である一方、21人以上の企業ではIT人材不足32.9%、DX推進人材不足33.5%と人材面の課題が深刻化している。それぞれの規模に応じた戦略が必要である。
- 成果を出している中小企業には4つの共通点がある。経営層・IT部門・業務部門の協調体制(成果ありの企業では約6割が実施)、外部企業や大学との連携による人材不足の補完、小規模から始める段階的アプローチ、そしてアナログデータのデジタル化による基本的成果の獲得である。
- 地域別では東京が「予算面」、地方が「人材不足と企画立案」という異なる課題を抱えており、地方では企画立案の課題が東京の約4倍に達している。しかし、今後のDX推進意欲は地方の方が25.5ポイントも高く、適切な支援があれば地方企業のDX推進が加速する可能性がある。
- 補助金・助成金の活用が鍵となり、49.3%の企業が期待する最大の支援策である。IT導入補助金や地方自治体の独自支援、専門家派遣制度などを組み合わせて活用することで、予算制約や人材不足という課題を克服しながらDX推進を進めることができる。今日から始められる5つのステップ(現状把握→課題特定→支援策活用→人材育成→段階的推進)に沿って取り組むことで、中小企業でも確実にDX推進を成功させることが可能である。
中小企業のDX推進は、企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。しかし、中小企業基盤整備機構が実施した最新調査によると、DXに既に取り組んでいる企業はわずか18.5%に留まり、理解度も49.2%と約半数という実態が明らかになりました。
本記事では、1,000社を対象とした「中小企業のDX推進に関する調査」の最新データをもとに、従業員規模20人以下と21人以上で異なる課題、東京と地方の地域差、そして人材不足30%超という深刻な現状を詳しく解説します。さらに、補助金活用や外部連携など、限られたリソースでも実践できる具体的な解決策と、成果を出している企業の共通点もご紹介します。
中小企業のDX推進に関する調査とは|最新版の概要と調査目的

中小企業基盤整備機構による最新調査の背景
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業のDX推進状況を継続的に把握するため、定期的に全国規模の調査を実施しています。最新の調査は、大企業を中心にDXへの取り組みが進む一方で、中小企業においては認知度は高まっているものの、大半の企業が依然としてデジタル化の途上にあるという前回調査の結果を受けて行われました。
この調査の背景には、日本企業の99%以上を占める中小企業のDX推進が日本経済全体の競争力に直結するという認識があります。人口減少や少子高齢化が進む中、中小企業がデジタル技術を活用して業務効率化や生産性向上を実現することは、企業の持続的成長だけでなく、日本全体の労働生産性向上にも不可欠な要素となっているのです。
調査対象と実施方法|1,000社から見る実態
最新の調査は、全国の中小企業経営者および経営幹部(個人事業主を除く)1,000社を対象に、Webアンケート形式で実施されました。調査期間は10月から11月にかけて行われ、株式会社ネオマーケティングと一般社団法人中小企業産学官連携センターが協力機関として参加しています。
調査内容は、DXへの理解度、取り組み状況、進捗段階、直面している課題、期待する支援策など、多岐にわたる項目で構成されています。また、従業員規模別や取り組み状況別など、複数の切り口からクロス分析を行うことで、中小企業の置かれている状況をより詳細に把握できる設計となっています。
特に注目すべき点は、従業員規模を20人以下と21人以上に分けて分析していることです。これにより、小規模企業と比較的規模の大きな中小企業では直面する課題が異なることが明確になり、それぞれの企業規模に応じた支援策の検討が可能になっています。
前回調査との比較で見えてきた変化
今回の調査では、前回(2023年8月実施)との比較分析も行われており、中小企業のDX推進がどのように進展しているかを時系列で把握できます。前回調査では、DXの認知度は高まっているものの、実際の取り組みは限定的であることが明らかになっていました。
最新調査では、「既に取り組んでいる」「取り組みを検討している」企業が42.0%と、前回調査から10.8ポイント増加しています。一方で、「取り組む予定はない」企業も30.9%存在しており、DXに積極的な企業とそうでない企業の二極化が進んでいる傾向も見られます。
また、DXに取り組んでいる企業の中でも、デジタイゼーション(アナログデータのデジタル化)段階に留まる企業が35.7%と最も多く、より高度なデジタルトランスフォーメーション段階まで到達している企業は28.1%に留まっています。この数値は前回調査から2.1ポイント増加しているものの、依然として初期段階の取り組みが中心であることが分かります。
こうした調査結果の変化を追うことで、中小企業のDX推進における進展と課題の両方が浮き彫りになり、各支援機関や中小企業者が今後の対応方針を検討するための貴重な基礎データとなっています。調査の目的は、単にデータを提供するだけでなく、中小企業のDX推進を実効性あるものにするための施策立案に貢献することにあるのです。
DX理解度は49.2%|中小企業の認知状況と二極化の実態
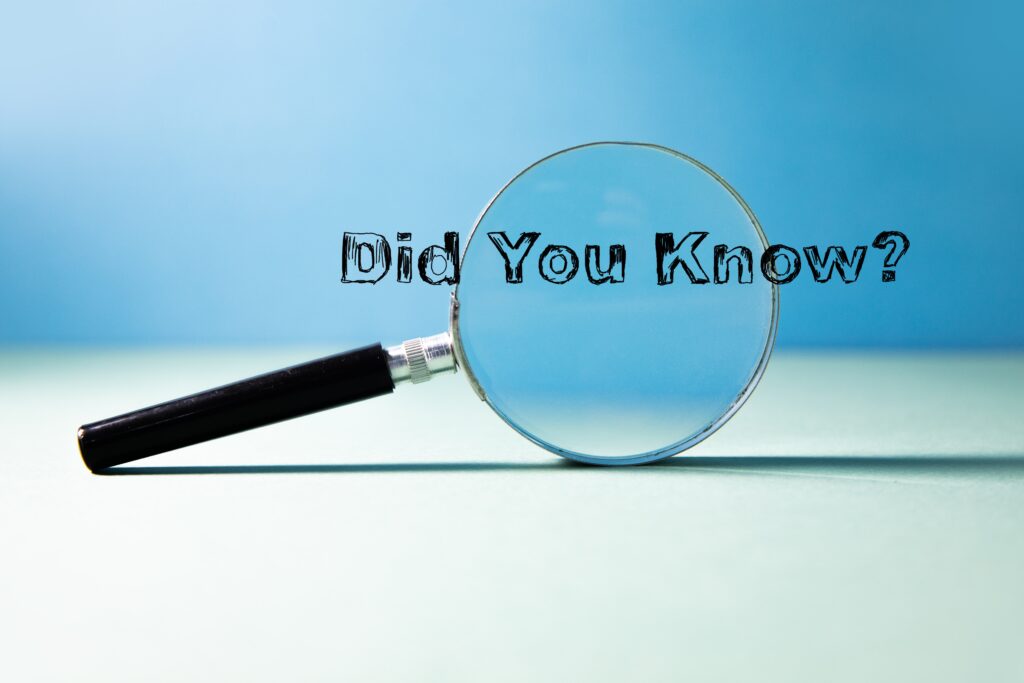
「理解している」企業は約半数|前回調査との比較
中小企業基盤整備機構の最新調査によると、DXについて「理解している」または「ある程度理解している」と回答した企業は49.2%と、全体のほぼ半数に達しました。これは中小企業においてもDXという言葉が浸透し、その重要性が認識され始めていることを示しています。一方で、残りの約半数は「あまり理解していない」または「理解していない」と回答しており、理解度には大きなばらつきがあることが明らかになっています。
前回調査と比較すると、DXの理解度は徐々に向上しているものの、その伸び率は緩やかです。デジタル庁設立から数年が経過し、各種メディアでDXが取り上げられる機会も増えたことで、言葉自体の認知度は高まっています。しかし、「DXとは何か」「自社にとってDXとは何を意味するのか」という本質的な理解までには至っていない企業が多いのが実情です。
特に注目すべきは、従業員規模によって理解度に差が見られる点です。従業員数が多い企業ほど理解度が高い傾向にあり、これは社内に情報収集や学習の機会が多いことや、経営層がDXに関する情報に触れる機会が多いことが影響していると考えられます。一方、小規模企業では日々の業務に追われ、DXについて学ぶ時間や機会が限られているという課題も浮き彫りになっています。
「知らない」企業が15.2%に増加|二極化が進む背景
興味深いのは、DXを「知らない」と回答した企業の割合が前回調査の6.7%から15.2%へと大幅に増加している点です。DXの認知度が全体として高まる中で、逆に「知らない」企業が増えるという一見矛盾した結果が出ています。この現象は、DXに積極的に取り組む企業とまったく関心を持たない企業との二極化が急速に進んでいることを示唆しています。
この二極化の背景には、複数の要因が考えられます。まず、DXに取り組む企業が増えることで、業界内での格差が顕在化し、デジタル化に遅れをとる企業が取り残される構図が生まれています。また、DXという言葉が多様な意味で使われるようになり、情報に触れる機会がない企業にとってはますます理解が難しくなっているという側面もあります。さらに、経営資源が限られる中小企業では、DXへの投資を後回しにせざるを得ない状況も少なくありません。
また、地域による情報格差も二極化を加速させる要因の一つです。都市部では行政や金融機関によるDX支援セミナーなどの機会が多い一方、地方では情報やサポートへのアクセスが限られています。この結果、DXに関する情報に日常的に触れる企業と、まったく触れない企業との間で認知度の差が拡大し、「知っている企業」と「知らない企業」の二極化が進行していると考えられます。
理解度向上のために必要な取り組み
中小企業のDX理解度を向上させるためには、段階的かつ実践的なアプローチが必要です。まず重要なのは、DXを抽象的な概念としてではなく、自社の業務に即した具体的な取り組みとして理解できるような支援です。例えば、同業種や同規模の企業の成功事例を紹介することで、「自社でもできる」という実感を持ってもらうことが効果的です。
また、経営者層へのアプローチも欠かせません。中小企業では経営者の意思決定が組織全体に大きな影響を与えるため、経営者自身がDXの必要性と可能性を理解することが重要です。そのためには、経営者向けの分かりやすいセミナーやワークショップの開催、業界団体や商工会議所を通じた情報提供など、経営者が気軽に学べる機会を増やす必要があります。
さらに、「知らない」企業を減らすためには、積極的な情報発信とアウトリーチが求められます。企業が自ら情報を取りに行くことを待つのではなく、行政や支援機関が地域の企業に直接働きかけ、DXの基本的な知識を提供していく必要があります。特に地方の小規模企業に対しては、訪問型の相談会や、地域金融機関との連携による情報提供など、企業に寄り添った支援が効果的です。デジタル化が進む社会において取り残される企業を減らすことは、地域経済全体の活性化にもつながる重要な取り組みといえるでしょう。
取り組み状況は18.5%|中小企業のDX推進の進捗実態
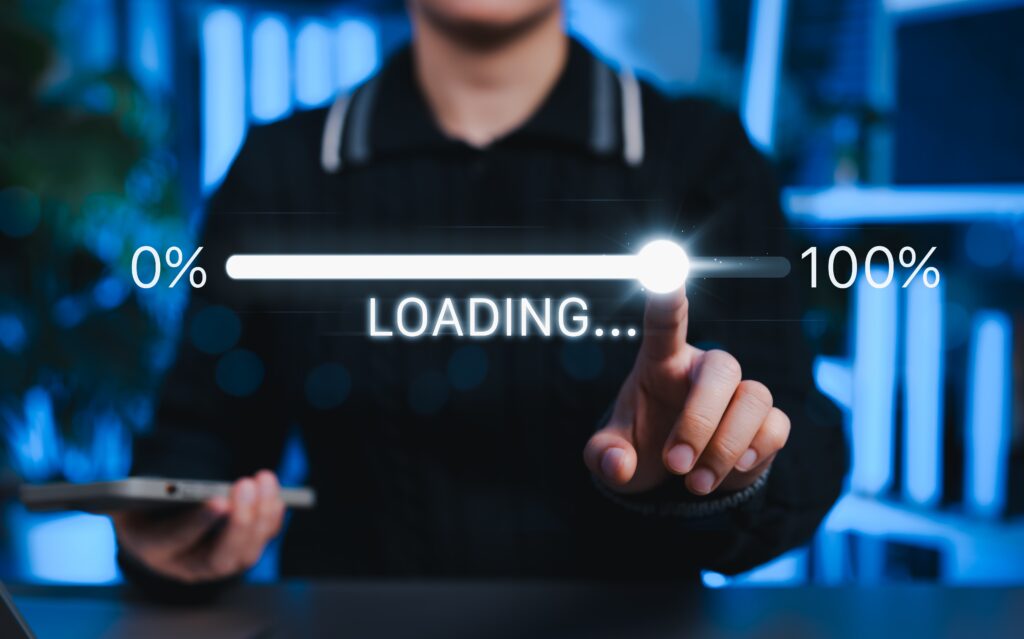
既に取り組んでいる企業は2割未満という現実
調査結果によると、DXに「既に取り組んでいる」と回答した中小企業はわずか18.5%に留まりました。前回調査の14.6%からは3.9ポイント上昇しているものの、依然として2割に満たない状況です。この数字は、理解度が約半数に達している一方で、実際の行動に移せている企業は限定的であることを示しています。理解と実践の間には大きなギャップが存在しているのです。
「取り組みを検討している」企業を加えると42.0%となり、何らかの形でDXに関心を持つ企業は増加傾向にあります。しかし、検討段階から実行段階への移行が大きな壁となっていることが浮き彫りになっています。多くの企業が「取り組みたい」「必要性は感じている」と考えながらも、具体的な一歩を踏み出せずにいる状況が続いているのです。
業種別に見ると、情報サービス業など元々デジタル技術に親和性の高い業種では取り組み率が高い一方、製造業や建設業、小売業などの伝統的な業種では取り組みが遅れている傾向があります。また、BtoB企業よりもBtoC企業の方が、顧客接点のデジタル化というニーズから取り組みが進んでいる傾向も見られます。このように業種特性によって取り組み状況に差が生じており、一律の支援策では十分な効果が得られない可能性が示唆されています。
「取り組む予定はない」が2割|その理由とは
一方で、「取り組む予定はない」と回答した企業は30.9%存在しています。前回調査の37.2%からは6.3ポイント減少しているものの、依然として3割の企業がDXに消極的な姿勢を示しています。これらの企業がDXに取り組まない理由を詳しく見ると、「具体的な効果や成果が見えない」が23.9%で最多となり、次いで「予算が不足している」が23.6%と続いています。
「何から始めてよいかわからない」という回答も27.2%に上り、情報や知識の不足が取り組みを阻んでいる実態が明らかになっています。特に小規模企業では、社内にITやデジタルに詳しい人材がおらず、相談できる相手も見つからないという状況が少なくありません。また、「推進できる人材がいない」が18.1%、「開発できる人材がいない」が14.6%と、人材面の課題も深刻です。
興味深いのは、取り組む予定がない企業と既に取り組んでいる企業を比較すると、「経営者の意識・理解が足りない」という回答の割合に大きな差がある点です。経営者がDXの必要性を理解し、積極的に推進する姿勢を示すかどうかが、企業全体の取り組みを左右する重要な要素となっています。中小企業では経営者の判断が組織の方向性を決定するため、経営層へのアプローチが特に重要であることが、このデータからも裏付けられています。
デジタイゼーション段階で停滞する7割の企業
DXに取り組んでいる企業の進捗状況を詳しく見ると、デジタイゼーション段階(アナログで行っていた作業やデータのデジタル化)に留まっている企業が35.7%と最も多く、全体の3分の1以上を占めています。これは、紙の書類を電子化したり、手作業をツール化したりという初期段階の取り組みが中心であることを示しています。
デジタライゼーション段階(個別の業務プロセスのデジタル化)まで進んでいる企業は28.6%、デジタルトランスフォーメーション段階(ビジネスモデルや企業文化の変革)まで到達している企業は28.1%です。前回調査と比較すると、それぞれ3.9ポイント、2.1ポイント増加しており、徐々に高度な段階へ進む企業が増えているものの、その伸びは緩やかです。
この停滞の背景には、初期段階の取り組みだけでも一定の効果が得られるため、それ以上の投資に踏み切れないという事情があります。実際に、DXに取り組んでいる企業の81.6%が「成果が出ている」または「ある程度成果が出ている」と回答しており、デジタイゼーション段階でも業務効率化やコスト削減といった効果は実感できています。しかし、真の意味でのビジネス変革や競争優位の確立といったDXの本質的な目標に到達するには、さらなる投資と継続的な取り組みが必要です。多くの中小企業にとって、限られたリソースの中で次のステップに進むことが大きな課題となっているのです。
従業員規模20人以下の企業が抱える3つの特有課題

「何から始めてよいかわからない」が27.7%
従業員規模20人以下の小規模企業では、「何から始めてよいかわからない」という回答が27.7%に達しており、これが最も大きな課題となっています。前回調査の18.7%から大幅に減少したものの、依然として約3割の企業が最初の一歩を踏み出せずにいる状況です。この背景には、社内にITやデジタルに関する知識を持つ人材が不足していることに加え、情報収集や学習に割ける時間や人員が限られているという実態があります。
小規模企業では、経営者自身が営業や製造など実務の最前線に立っていることが多く、DXについて学んだり計画を立てたりする時間を確保することが困難です。また、相談できる相手や情報源が見つからないという孤立した状況も少なくありません。大企業であれば社内のIT部門や外部のコンサルタントに相談できますが、小規模企業ではそうした選択肢が限られており、どこに相談すればよいかわからないまま時間が経過してしまうケースが多いのです。
この課題に対しては、自社の業種や規模に近い企業の具体的な事例を知ることが有効です。同じような課題を抱えていた企業がどのようにDXに取り組み、どんな成果を得たのかを知ることで、自社でも実現可能だという実感を持つことができます。また、商工会議所や地域の金融機関など、身近な相談窓口を活用することで、最初の一歩を踏み出すハードルを下げることができます。
予算確保の困難さ|小規模企業特有の資金問題
従業員規模20人以下の企業では、「予算の確保が難しい」という課題も深刻です。DX投資への予算が500万円未満の企業が約4割を占めており、限られた資金の中でどこまで投資するかが大きな悩みとなっています。小規模企業にとって、数十万円から数百万円の投資でも経営に大きな影響を与えるため、確実な効果が見込めない限り投資判断ができないのが実情です。
特に厳しいのは、初期投資だけでなく継続的なコストが発生するという点です。システムやツールの導入には初期費用だけでなく、月額利用料や保守費用、従業員の教育コストなども必要になります。さらに、導入後に期待した効果が得られなかった場合のリスクも大きく、慎重にならざるを得ません。このため、多くの小規模企業がDXへの投資に踏み切れずにいます。
この資金面の課題に対しては、IT導入補助金やDX投資促進税制などの公的支援制度の活用が重要です。実際に調査でも、小規模企業ほど「補助金・助成金」への期待が高いことが示されています。また、クラウドサービスの活用により初期投資を抑え、小規模から始めて段階的に拡大していくアプローチも有効です。まずは低コストで導入できるツールから始め、効果を確認しながら徐々に投資を拡大していくことで、リスクを最小限に抑えながらDXを進めることができます。
具体的な効果が見えないことへの不安
従業員規模20人以下の企業では、「具体的な効果や成果が見えない」という回答が22.2%に達しており、前回調査の19.8%から2.4ポイント上昇しています。限られたリソースで経営している小規模企業にとって、投資対効果が不明確なものに資金や時間を投入することは大きなリスクです。このため、DXの必要性は理解していても、具体的にどのような効果が得られるのかが見えないことが、取り組みを躊躇させる大きな要因となっています。
この不安の背景には、DXという言葉が抽象的で、自社にとって何を意味するのかが分かりにくいという問題があります。「業務効率化」「生産性向上」といった言葉は耳にするものの、自社の日々の業務でどう変わるのかが具体的にイメージできないのです。また、大企業の成功事例は目にするものの、自社とは規模や業種が異なるため参考にしにくいという声も多く聞かれます。
この課題を克服するには、同規模・同業種の具体的な成果事例を知ることが最も効果的です。例えば、「請求書作成にかかる時間が半分になった」「在庫管理のミスがなくなった」「顧客対応のスピードが2倍になった」といった、数値で示される具体的な改善例を知ることで、自社での効果もイメージしやすくなります。また、小さな取り組みから始めて短期間で効果を確認し、成功体験を積み重ねていくアプローチも重要です。まずは部分的にデジタル化を進め、その効果を実感してから次のステップに進むことで、不安を軽減しながらDXを推進することができます。
従業員規模21人以上の企業における人材不足の深刻化

IT人材不足が32.9%|採用の困難さ
従業員規模21人以上の中小企業においては、DX推進を阻む最大の課題として人材不足が深刻化しています。中小企業基盤整備機構による2024年の調査によると、従業員規模21人以上の企業では「ITに関わる人材が足りない」と回答した企業が32.9%に達しており、前回調査の41.7%から8.8ポイント減少したものの、依然として3社に1社が人材不足に悩んでいる状況が明らかになりました。
この数字は、従業員規模20人以下の企業における同様の課題(15.3%)と比較すると約2倍以上の高さとなっており、企業規模が大きくなるにつれて専門的なIT人材の必要性が高まることを示しています。IT人材不足の背景には、日本全体でのデジタル人材の絶対的な不足があります。経済産業省の推計では、2030年には約79万人のIT人材が不足するとされており、中小企業が優秀なIT人材を採用することは極めて困難な状況となっています。
従業員規模21人以上の企業では、業務のデジタル化が進むにつれて、システムの運用管理やデータ分析、セキュリティ対策など、より高度な技術スキルを持つ人材が求められます。しかし、大企業と比較して給与水準や福利厚生面で見劣りすることが多く、IT人材の獲得競争において不利な立場に置かれているのが実情です。採用活動に多くの時間とコストをかけても、期待するスキルを持つ人材を確保できない企業が後を絶ちません。
DX推進人材不足が33.5%|社内育成の必要性
IT人材不足に加えて、従業員規模21人以上の企業では「DX推進に関わる人材が足りない」と回答した企業が33.5%となっており、前回調査の42.2%から8.7ポイント減少したものの、IT人材不足と同程度の深刻な課題となっています。DX推進人材は単なるIT技術者とは異なり、デジタル技術の知識に加えて、ビジネス戦略の立案能力や組織を巻き込むリーダーシップ、変革を推進するマネジメントスキルなど、複合的な能力が求められます。
このような多様なスキルを持つDX推進人材を外部から採用することは、IT人材以上に困難です。そのため、多くの企業が社内人材の育成に注力する方向にシフトしています。独立行政法人情報処理推進機構の「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の獲得・確保方法として、「社内人材の育成」が54.9%で最も高く、「社内人材(人事異動を含む)の活用」が47.7%と続いています。外部採用よりも社内での人材育成を重視する企業が過半数を占めているのです。
社内育成のメリットは、自社のビジネスモデルや組織文化を深く理解している人材を活用できる点にあります。外部から採用したDX人材が、企業の実情に合わない施策を提案してしまうリスクを回避できます。また、中長期的な視点でDXを推進するためには、継続的に社内にノウハウを蓄積していく必要があり、そのためにも社内人材の育成が不可欠となっています。具体的には、DX研修プログラムの導入やeラーニングの活用、外部専門家によるコンサルティングの受講などを通じて、段階的にDX推進人材を育成する取り組みが広がっています。
情報セキュリティ確保の課題が3.4ポイント上昇
従業員規模21人以上の企業において、新たに顕著化している課題が情報セキュリティの確保です。2024年の調査では「情報セキュリティの確保が難しい」と回答した企業が14.0%となり、前回調査の10.6%から3.4ポイント上昇しました。これは、DX推進に伴うデジタル化の進展によってサイバー攻撃のリスクが高まっていることを反映しています。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2024年度に実施した「中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」によると、約7割の中小企業において組織的なセキュリティ体制が整備されていないという実態が明らかになりました。さらに、過去3年間にサイバー攻撃の被害に遭った中小企業のうち約7割が取引先にも影響が及んだという、いわゆる「サイバードミノ」が発生しています。中小企業のセキュリティの脆弱性が、取引先を含めたサプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼす事態となっているのです。
情報セキュリティ対策が進まない背景には、専門知識を持つ人材の不足があります。2024年12月にキヤノンマーケティングジャパンが実施した調査では、中小企業がセキュリティ対策を実施・運用する上で直面している課題として、「社内に専門知識を持った人材がいない」が44.7%、「専任のセキュリティ人材を確保できていない」が40.4%と、いずれも上位を占めました。セキュリティ対策には継続的な投資と専門性が必要であり、限られたリソースの中で十分な対策を講じることが困難な状況にあります。
従業員規模21人以上の企業では、業務システムの導入やクラウドサービスの利用が進んでおり、それに伴って管理すべきセキュリティ領域も拡大しています。しかし、セキュリティ専門人材の確保が難しい中で、既存の社員がセキュリティ業務を兼務せざるを得ないケースが多く、十分な対策が取れていないのが実情です。このような状況を改善するためには、社内でのセキュリティ教育の強化や、外部の専門サービスの活用、中小企業向けのセキュリティ対策支援制度の利用など、複合的なアプローチが求められています。
中小企業のDX推進における5大課題と解決の方向性

人材不足|IT人材28.1%、DX推進人材27.2%の深刻な状況
中小企業基盤整備機構の2024年調査によると、DX推進における最大の課題として「DXに関わる人材が足りない」が全体の28.1%、「ITに関わる人材が足りない」が27.2%となっており、合計すると過半数以上の企業が人材不足を最重要課題として認識しています。この数字は前回調査と比較してわずかに改善しているものの、依然として中小企業のDX推進を阻む最大の障壁となっています。
人材不足が深刻化している背景には、日本全体でのデジタル人材の絶対的な不足があります。経済産業省の推計では、2030年には約79万人のIT人材が不足するとされており、大企業との人材獲得競争において、給与水準や福利厚生面で不利な立場にある中小企業は、より深刻な状況に直面しています。DX推進人材には、IT技術の知識だけでなく、ビジネス戦略の立案能力、組織を巻き込むリーダーシップ、変革を推進するマネジメントスキルなど、複合的な能力が求められるため、外部からの採用は極めて困難です。
この課題に対する解決の方向性として、多くの企業が社内人材の育成にシフトしています。独立行政法人情報処理推進機構の「DX白書2023」によると、DX人材の獲得・確保方法として「社内人材の育成」が54.9%で最も高く、外部採用よりも社内育成を重視する傾向が明確になっています。具体的には、DX研修プログラムの導入、eラーニングの活用、外部専門家によるコンサルティングの受講などを通じて、段階的にDX人材を育成する取り組みが広がっています。また、外部の専門家派遣サービスを活用して、社内人材の育成をサポートする方法も注目されており、2024年調査では専門家派遣への期待が前回から3.4ポイント上昇しています。
予算確保の難しさ|費用対効果への懸念を解消する方法
DX推進における二つ目の大きな課題が予算確保です。2024年調査では「予算の確保が難しい」と回答した企業が24.9%に達し、特に従業員規模20人以下の企業では28.9%と、より深刻な状況となっています。また、DXに取り組む予定がない企業のうち23.6%が予算不足を理由に挙げており、予算面の制約がDX推進の大きな障壁となっていることが明らかになりました。
予算確保が難しい背景には、DX推進への初期投資の大きさと、費用対効果の見えにくさがあります。システムの導入費用、人材育成のコスト、業務プロセスの見直しに伴う一時的な生産性低下など、DX推進には多額の投資が必要となります。しかし、その効果が短期間で明確に現れるとは限らず、投資判断が難しいのが実情です。特に中小企業では、日々の経営に必要な資金を確保することが優先され、中長期的な投資であるDXに予算を割くことが困難なケースが多く見られます。
この課題に対する解決策として、第一に政府や自治体が提供する補助金・助成金の活用が挙げられます。2024年調査では、DX推進に向けて期待する支援策として「補助金・助成金」が49.3%で最も高い割合を占めており、多くの企業が公的支援を求めています。IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金など、DX関連の取り組みに活用できる補助金制度は充実しており、申請要件を満たせば導入費用の半分以上が補助されるケースも少なくありません。第二に、小さく始めて段階的に拡大する「スモールスタート」のアプローチが有効です。すべての業務を一度にデジタル化するのではなく、効果が出やすい特定の業務から始め、その成果を確認しながら徐々に範囲を広げていくことで、リスクを抑えながら投資対効果を高めることができます。
推進方法の不明確さ|何から始めるべきかのロードマップ
三つ目の課題は、DX推進の具体的な方法がわからないという点です。2024年調査では、DXに取り組む予定がない企業のうち27.2%が「何から始めてよいかわからない」と回答しており、従業員規模20人以下の企業では前回調査の27.7%から9.0ポイント改善したものの、依然として4社に1社以上が推進方法に悩んでいる状況です。DXという言葉の抽象性や、各企業で取り組むべき内容が異なることが、具体的なアクションプランの策定を困難にしている要因となっています。
この課題の背景には、DXが単なるIT導入ではなく、業務プロセスの変革やビジネスモデルの転換を含む包括的な取り組みであることが、十分に理解されていない点があります。また、専門的な知識を持つ人材が社内にいない中で、自社にとって最適なDX戦略を描くことは容易ではありません。さらに、DX推進の担当者が専任ではなく、日常業務と並行して取り組まなければならないケースが多く、十分な時間とリソースを割けないことも、推進方法の明確化を妨げています。
解決の方向性としては、まず経済産業省や中小企業庁が提供する「DX推進指針」や「デジタルガバナンス・コード実践の手引き」などのガイドラインを活用することが有効です。これらの資料には、DX推進のステップや考慮すべき事項が具体的に示されており、自社の状況に合わせて参考にすることができます。また、同業他社や類似規模の企業の成功事例を研究することで、自社でも実現可能な取り組みのヒントを得ることができます。中小企業白書や各種調査報告書には、業種別・規模別の具体的な事例が豊富に掲載されています。さらに、商工会議所や中小企業支援機関が提供する無料相談サービスや専門家派遣制度を活用することで、外部の専門家から具体的なアドバイスを受けることができます。実際に、2024年調査では専門家派遣への期待が16.4%と、前回調査から3.4ポイント上昇しており、外部支援へのニーズが高まっています。
経営者の意識改革|トップのコミットメントの重要性
四つ目の課題は、経営者の意識と理解の不足です。2024年調査では、DXに「必要だと思うが取り組めていない」企業や「取り組む予定はない」企業において、「経営者の意識・理解が足りない」と回答した割合が、すでにDXに取り組んでいる企業や検討している企業と比較して顕著に高くなっています。経営トップのコミットメントがないままでは、組織全体でのDX推進は極めて困難となります。
経営者の意識不足の背景には、DXの必要性や効果についての理解が十分でないことがあります。特に、長年にわたって成功してきた既存のビジネスモデルがある場合、わざわざ変革に取り組む必要性を感じにくいという心理的な障壁があります。また、DXは中長期的な取り組みであり、短期的な成果が見えにくいため、他の経営課題と比較して優先順位が下がってしまうケースも少なくありません。さらに、経営者自身がデジタル技術に対して苦手意識を持っている場合、DX推進に対して消極的になる傾向があります。
この課題を解決するためには、まず経営者自身がDXの重要性と具体的な効果について学ぶ機会を持つことが重要です。経営者向けのDXセミナーやシンポジウムに参加することで、他社の成功事例や最新のデジタル技術動向を知ることができます。実際に、2024年調査でDX推進のために期待する支援策として「セミナーの開催」が14.0%の企業から挙げられています。また、外部の専門家やコンサルタントから、自社の現状分析と具体的なDX戦略について助言を受けることも効果的です。経営者が率先してDXの重要性を社内に発信し、具体的な目標と方針を示すことで、組織全体の意識が変わり、DX推進が加速します。経営トップのリーダーシップがあってこそ、部門間の壁を越えた全社的な取り組みが可能となるのです。
具体的成果の可視化|効果測定の仕組みづくり
五つ目の課題は、DX推進による具体的な効果や成果が見えにくいという点です。2024年調査では「具体的な効果や成果が見えない」と回答した企業が23.0%に達し、特に従業員規模20人以下の企業では22.2%と、前回調査から2.4ポイント上昇しています。また、DXに取り組む予定がない企業の理由としても23.9%が効果の不透明さを挙げており、成果の可視化が大きな課題となっています。
効果が見えにくい背景には、DXの成果が多岐にわたり、定量的に測定しにくい側面があることが挙げられます。業務効率化によるコスト削減は比較的測定しやすいものの、顧客満足度の向上や従業員の働き方改善、新規ビジネス機会の創出といった効果は、短期的には数値化が難しいケースが多くあります。また、DX推進の初期段階では、システム導入やプロセス変更に伴う一時的な混乱が生じることもあり、すぐに成果が現れないことも、効果を実感しにくい要因となっています。
この課題に対する解決策として、まずDX推進の開始時点で具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。例えば、「特定業務の処理時間を30%削減」「紙の使用量を50%削減」「顧客対応時間を20%短縮」など、測定可能な目標を設定します。そして、定期的にこれらの指標を測定し、進捗状況を可視化することで、DXの効果を客観的に評価できるようになります。また、スモールスタートで小さな成功体験を積み重ねることも効果的です。限定的な範囲でDXに取り組み、その成果を社内で共有することで、DXの有効性を実感しやすくなり、次のステップへの推進力となります。さらに、DXに成功している他社の事例を参考にすることで、自社でも期待できる効果のイメージを具体化することができます。中小企業白書や各種調査報告書には、具体的な成果とともに事例が紹介されており、これらを活用することで、自社のDX推進における成果の可視化方法を学ぶことができます。
DX推進で期待される効果|調査から見る中小企業の目的トップ5

業務効率化による生産性向上|7割以上の企業が期待
中小企業白書2024年版によると、中小企業がDXに取り組む際に期待する効果・メリットとして、「業務効率化による負担軽減」が最も多く挙げられており、7割以上の企業がこの効果を期待しています。これは、紙や口頭による業務をデジタルツールに置き換えることで、手作業の時間を大幅に削減できることが大きな理由です。具体的には、ペーパーレス化による書類管理の効率化、データ入力作業の自動化、情報検索時間の短縮などが実現されています。
業務効率化は、従業員一人ひとりの生産性向上に直結します。デジタル化によって定型業務にかかる時間が削減されれば、その分を付加価値の高い業務に振り向けることができます。例えば、経理部門では会計ソフトの導入により月次決算の処理時間が大幅に短縮され、経営分析により多くの時間を割けるようになったという事例が数多く報告されています。また、営業部門では顧客管理システム(CRM)の導入により、顧客情報の一元管理が可能となり、営業活動の効率が向上しています。
中小企業白書では、DXに早期から取り組んでいる企業ほど、付加価値額が高い傾向にあることが報告されています。2019年以前からDXに取り組んでいる企業は、2020年以降に開始した企業と比較して、2022年時点での付加価値額が明確に高くなっています。これは、業務効率化の積み重ねが長期的には企業の高付加価値化につながることを示しており、早期にDXに取り組むことの重要性を裏付けています。また、人口減少・少子高齢化が進む日本において、人手不足が深刻化する中で、DXによる業務効率化は企業活動を維持するために不可欠な取り組みとなっています。
データ活用による意思決定の高度化
二つ目の期待効果は、データ活用による意思決定の質の向上です。これまで多くの中小企業では、経営者の経験や勘に基づいた意思決定が中心でしたが、DX推進によってデータに基づく客観的な判断が可能になります。売上データ、顧客データ、在庫データなどを一元管理し、分析することで、市場動向や顧客ニーズを的確に把握できるようになります。
データ活用の具体例として、顧客データの分析による販売戦略の最適化があります。顧客の購買履歴や属性情報を分析することで、どの商品がどの顧客層に人気があるのか、どのタイミングで購入される傾向があるのかといった情報が明確になります。これにより、効果的な販促施策の立案や、在庫の適正化が可能となります。また、業務プロセスのデータを可視化することで、ボトルネックとなっている工程を特定し、改善策を講じることもできます。
中小企業白書では、DXの取組段階が進んでいる企業ほど、「顧客データの一元管理・データ利活用」に取り組んでいる割合が高いことが報告されています。段階3(業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態)以上の企業では、データを経営判断の根拠として活用する文化が定着しており、これが企業の競争力強化につながっています。データに基づく意思決定は、不確実性の高い経営環境において、リスクを最小化しながら適切な判断を下すために極めて重要です。
人手不足解消への貢献
三つ目の期待効果は、深刻化する人手不足問題への対応です。日本では生産年齢人口が減少し続けており、女性や高齢者の就業率向上によってこれまで人手不足を補ってきましたが、すでに女性の就業率は7割超、高齢者も5割超に達し、これ以上の就業率向上は限界に近づいています。こうした状況下で、DXによる業務の自動化・効率化は、限られた人員で業務を回すための有効な手段となります。
具体的には、RPAツール(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、定型的な事務作業を自動化することで、人手をかけずに処理できる業務が増えています。請求書の作成、データ入力、メールの自動返信など、繰り返し発生する作業を自動化することで、従業員は本来注力すべきコア業務に集中できるようになります。また、オンライン会議システムやビジネスチャットの導入により、移動時間の削減や情報共有の迅速化が実現され、実質的な労働時間の有効活用が可能となっています。
さらに、DXは採用活動の効率化にも貢献します。採用管理システムの導入により、応募者情報の一元管理や選考プロセスの可視化が可能となり、採用担当者の業務負担が軽減されます。また、テレワークやリモートワークを可能にするデジタル環境の整備により、地理的制約を超えた人材採用も可能となり、人材確保の選択肢が広がります。中小企業白書では、DXに取り組む効果として人手不足の解消が期待されていることが明記されており、持続可能な企業活動の維持に不可欠な取り組みとして位置づけられています。
新規顧客開拓とビジネスモデル変革
四つ目の期待効果は、新規顧客の開拓とビジネスモデルの変革です。DXによってオンラインでの販売チャネルを構築したり、Webマーケティングを展開したりすることで、これまでアプローチできなかった地域や顧客層にリーチすることが可能になります。特に、地方の中小企業にとって、ECサイトの開設やSNSの活用は、商圏を全国さらには海外にまで拡大する機会となります。
中小企業白書では、DXの取組によって期待する効果として「新製品・サービスの創出」や「既存製品・サービスの価値向上」を挙げる企業は少数派であるものの、実際にDXの取組段階が進んでいる企業(段階4:DXによるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態)では、こうした効果を実感している企業が存在します。デジタル技術を活用した新しいサービスの提供や、既存サービスのオンライン化により、顧客との新しい接点を創出し、収益機会を拡大している事例が報告されています。
具体的な事例として、製造業でのIoT活用による予防保全サービスの提供や、小売業でのオムニチャネル戦略の展開などがあります。従来の製品販売だけでなく、デジタル技術を組み合わせたサービス提供により、顧客への提供価値を高め、差別化を図ることができます。また、顧客との接点がデジタル化されることで、顧客の行動データや嗜好データを収集・分析することが可能となり、これを新商品開発やサービス改善に活用することで、継続的な価値創造のサイクルを構築できます。
競争力強化と持続的成長の実現
五つ目の期待効果は、企業の競争力強化と持続的成長の実現です。DXは単なる業務効率化にとどまらず、企業の根本的な競争優位性を高める手段となります。デジタル技術を活用することで、顧客対応のスピードアップ、サービス品質の向上、コスト競争力の強化など、多面的な競争力の向上が期待できます。
中小企業白書では、DXに取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業と比較して、労働生産性や売上高が大きく向上していることが示されています。具体的には、DXの取組を早期から開始している企業ほど、付加価値額が高い傾向にあり、長期的な企業成長につながっていることが確認されています。これは、DXによる業務効率化やデータ活用が、単年度の効果にとどまらず、蓄積的に企業の競争力を高めていくことを示しています。
また、経済産業省が策定した「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」では、中堅・中小企業は経営規模が小さく経営者の判断が迅速であるため、大企業よりも変革のスピードが速く、効果も出やすいという特性が指摘されています。つまり、中小企業はDXを推進する上で大きなアドバンテージを持っており、適切に取り組めば、大企業に対抗できる競争力を獲得できる可能性があるのです。DXは単なる流行やトレンドではなく、企業を存続させ、持続的に成長させるために必要不可欠な取り組みであり、同時に大きな企業成長の余地を秘めたチャンスでもあります。感染症の流行、地政学リスク、市場の不確実性など、急激に変化する経営環境において、デジタル技術を活用して柔軟に対応できる企業体質を構築することが、長期的な競争力の源泉となるのです。
補助金・助成金が41.6%|中小企業が求めるDX推進支援策

中小企業のDX推進において、資金面の課題は最も深刻な障壁の一つです。中小企業基盤整備機構の2024年調査によると、DX推進に向けて期待する支援策として「補助金・助成金」を挙げた企業は41.6%にのぼり、最もニーズの高い支援策となっています。前回2023年調査の49.3%からは7.7ポイント減少したものの、依然として4割以上の企業が資金面での支援を強く求めている現状が明らかになりました。
DX推進には、ITツールの導入費用やシステム開発費用、人材育成のための研修費用など、多額の初期投資が必要となります。特に中小企業にとって、こうした投資は経営に大きな負担となるため、補助金や助成金の活用が実質的なDX推進の鍵を握っています。本セクションでは、中小企業が活用できる具体的な支援策と、その効果的な活用方法について詳しく解説します。
最もニーズの高い補助金・助成金の具体的活用方法
中小企業がDX推進で活用できる主な補助金・助成金には、「IT導入補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「中小企業省力化投資補助金」「人材開発支援助成金」などがあります。これらの制度は、それぞれ異なる目的と対象経費を持っているため、自社のDX推進計画に最も適した制度を選択することが重要です。
IT導入補助金の活用ポイント
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)を導入する際の費用を支援する制度です。2025年度も継続実施が決定しており、補助額は最大450万円、補助率は1/2〜4/5となっています。通常枠に加えて、インボイス枠やセキュリティ対策推進枠など、特定の目的に応じた申請枠が設けられています。
この補助金の特徴は、経済産業省に登録されたITツールから選択する必要があることです。そのため、まず自社の課題を明確にし、登録されているツールの中から最適なものを選定するプロセスが求められます。また、IT導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請する必要があるため、信頼できる支援事業者の選定も成功の鍵となります。
ものづくり補助金でのDX投資
ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上や新製品・新サービス開発のための設備投資を支援する制度です。2025年から再開されたこの補助金では、従業員数に応じて補助上限額が区分され、最大7,000万円まで支援を受けることが可能です。DX関連では、AI・デジタル化による業務革新やシステム構築が対象となります。
特に革新的なデジタル技術の導入や、業務プロセスの抜本的な改善を伴うDX投資に適しており、大規模な設備投資が必要な製造業やサービス業での活用事例が多く報告されています。ただし、審査基準が厳しく、事業計画書の作成には専門的な知識が必要となるため、コンサルタントや支援機関の活用も検討すべきでしょう。
事業再構築補助金の後継制度
2024年度まで人気を集めた事業再構築補助金は、2025年度からは「中小企業新事業進出促進事業」として生まれ変わりました。新規事業への進出やビジネスモデルの転換を図る企業を対象に、生成AIによる新サービス開発やDX化と新サービスを組み合わせたシステム開発などが補助対象となります。既存事業の改修には使えないものの、新たな事業展開を考えている企業にとっては魅力的な選択肢です。
DX推進指針が22.6%から20.7%へ|公的ガイドラインへの期待
補助金・助成金に次いで期待されている支援策が「中小企業のためのDX推進指針の策定・公表」で、2024年調査では20.7%の企業がこれを挙げています。前回調査の22.6%から1.9ポイント減少しましたが、依然として2割以上の企業が何から始めればよいか分からない状況にあることを示しています。
経済産業省は「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」や「デジタルスキル標準」など、DX推進のための各種ガイドラインを公表しています。これらの指針は、DXの全体像を理解し、自社に必要な取り組みを段階的に進めるためのロードマップとして活用できます。特に、デジタルスキル標準では、経営層を含むすべてのビジネスパーソンが身につけるべき「DXリテラシー標準」と、専門性を持った人材向けの「DX推進スキル標準」が明確に定義されており、人材育成の指針としても有効です。
専門家派遣が13.0%から16.4%へ上昇|外部人材活用の増加
注目すべき変化として、「専門家の派遣」を期待する企業が前回調査の13.0%から16.4%へと3.4ポイント上昇したことが挙げられます。この傾向は、中小企業が社内のみでDXを推進することの困難さを実感し、外部の専門知識や経験を積極的に取り入れようとする姿勢の表れと言えるでしょう。
専門家派遣制度の活用メリット
各自治体や支援機関では、DX推進のための専門家派遣制度を提供しています。例えば、東京都の「DX推進支援事業」では、アドバイザーが現地訪問を行い、2年間で最大24回まで無料で支援を受けることができます。大阪産業創造館でも「コンサル出前一丁」として期間限定でDX推進に関する無料専門家派遣を実施しており、業務のデジタル化から新規ビジネスモデルによる事業改革まで幅広く対応しています。
専門家派遣の最大のメリットは、自社の状況に合わせたオーダーメイドの支援が受けられることです。画一的なソリューションではなく、企業の規模、業種、経営課題に応じた具体的なアドバイスを受けることで、無駄な投資を避け、効果的なDX推進が可能になります。また、DX戦略の策定から実行、効果測定まで一貫した支援を受けられるため、中長期的な視点でのDX推進が実現できます。
地域金融機関の伴走支援
東京商工リサーチの調査によると、DXに取り組む中小企業の42.6%が支援機関として「金融機関」を挙げています。地域金融機関は、融資業務だけでなく、伴走支援の一環としてDX支援に積極的に取り組むようになっており、企業側もその必要性を強く感じています。金融機関は企業の財務状況を熟知しているため、投資効果を意識した実践的なアドバイスが期待できる点が特徴です。
セミナー・研修による人材育成支援の活用
DX推進において、資金面の支援と同様に重要なのが人材育成です。多くの自治体や支援機関では、中小企業向けのDXセミナーや研修プログラムを無料または低価格で提供しています。埼玉県では「DX推進講座」として、デジタルツールを活用した営業活動や業務効率化など、実務に直結するスキルを基礎から応用まで体系的に学べる全36講座をオンラインで提供しています。
これらの研修プログラムの特徴は、自社の課題や従業員のスキルレベルに応じて必要な講座だけを選択できる点にあります。また、オンライン形式であれば、業務の合間や移動時間を活用して学習することも可能です。DX推進指針の理解から具体的なツールの使い方、データ分析の基礎まで、幅広いテーマがカバーされており、社内人材の底上げに効果的です。
経済産業省のDX人材育成支援
「人材開発支援助成金」は、中小企業が従業員の研修費用を支援するための助成金です。DX関連の研修にも活用でき、外部研修の受講料や社内でのOJTにかかる経費の一部が助成されます。この制度を活用することで、限られた予算の中でも計画的な人材育成が可能になります。
補助金・助成金活用時の注意点と成功のポイント
補助金・助成金は返済不要な資金であるため、DX推進の強力な後押しとなりますが、活用にあたってはいくつかの注意点があります。最も重要なのは、補助金の多くが後払い制度であることです。つまり、まず自己資金で投資を行い、その後に申請・審査を経て補助金が交付される仕組みとなっています。
資金計画の重要性
後払い制度のため、DX投資に必要な初期資金を一時的に自社で負担する必要があります。資金繰りが厳しい場合は、金融機関からの融資を検討することも必要でしょう。融資の審査には3週間から1カ月半程度かかるため、補助金の申請期日から逆算して早めに準備を始めることが重要です。
申請書類の作成と採択率の向上
補助金の採択には厳しい審査があり、事業計画書の質が採択の可否を大きく左右します。特に、DXによってどのような経営課題を解決し、どのような成果を達成するのかを具体的に示すことが求められます。必要に応じて、補助金申請の実績がある専門家やコンサルタントのサポートを受けることも検討すべきでしょう。実際、補助金申請支援サービスを活用した企業では、採択率が90%を超えるケースも報告されています。
複数の支援策の組み合わせ
補助金・助成金、専門家派遣、セミナー・研修といった支援策は、単独で活用するよりも組み合わせることで相乗効果が期待できます。例えば、まずセミナーでDXの基礎知識を習得し、専門家派遣で自社に最適なDX戦略を策定した上で、補助金を活用してITツールを導入する、といった段階的なアプローチが効果的です。
東京商工リサーチの調査では、中小企業の約4割がDX投資予算を「500万円未満」としていますが、補助金を活用することで、この限られた予算でも効果的なDX推進が可能になります。補助率が1/2から2/3の制度が多いため、実質的な負担を大幅に軽減できるのです。
中小企業にとって、DX推進は避けては通れない経営課題となっています。補助金・助成金をはじめとする各種支援策を戦略的に活用することで、限られた経営資源の中でも着実にDXを進めることができます。まずは自社の課題を明確にし、利用可能な支援策を調査することから始めてみましょう。
成果を出す中小企業の共通点|8割が効果を実感する取り組み

中小企業基盤整備機構の調査では、DXに取り組んでいる中小企業の約8割が何らかの成果を実感しています。この高い成功率は、単なる偶然ではありません。成果を出している企業には、明確な共通点が存在します。本セクションでは、調査データと実際の成功事例から見えてきた、中小企業がDX推進で成果を出すための4つの重要な要素について詳しく解説していきます。
経営層・IT部門・業務部門の協調体制
DX推進で成果を出している中小企業の最大の特徴は、経営層がリーダーシップを発揮し、IT部門と業務部門が密接に連携している点です。独立行政法人情報処理推進機構の調査によれば、DX成果ありの企業では「経営者・IT部門・業務部門の協調」を実施している割合が約6割に達しています。一方で、DX取組なしの企業では2割前後にとどまっており、この協調体制の有無が成果を大きく左右することが明らかになっています。
経営層の役割は、DXの必要性を社内に明確に示し、全社的な変革のビジョンを提示することです。多くの成功事例では、経営者自らがDX推進の旗振り役となり、必要な予算や人員を確保しています。また、IT部門と業務部門の橋渡し役として、両者の視点を統合した戦略を策定することで、現場の実務に即したDX推進が可能になります。
IT部門は技術的な専門知識を持ちながらも、業務部門の課題を深く理解する必要があります。一方、業務部門は日々の業務で感じている課題や改善点を具体的にIT部門に伝えることが求められます。この相互理解と協力関係が、実効性のあるDX施策につながっているのです。実際の成功事例では、定期的な合同会議の開催や、プロジェクトチームへの各部門からの人員配置など、組織的な連携の仕組みを構築している企業が多く見られます。
外部企業や大学との連携による人材不足の補完
中小企業では、社内にDX推進に必要な専門人材が不足しているケースが一般的です。しかし、成果を出している企業は、この課題を外部との連携によって解決しています。IT分野に見識がある役員や専門部署が存在しない場合でも、外部のシステム開発会社、大学、他企業の人材を活用することで成果を出している事例が多数報告されています。
具体的な連携方法としては、ITベンダーやコンサルティング会社との協業、大学の研究室との共同プロジェクト、業界団体を通じた他社との情報共有などがあります。特に、中小企業への導入経験が豊富な専門家やベンダーに相談することで、自社の状況に合わせた適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
外部人材の活用で重要なのは、単に技術を導入するだけでなく、社内にノウハウを蓄積することです。成功している企業では、外部専門家と社内スタッフが密接に協働し、知識移転を図りながらプロジェクトを進めています。これにより、将来的には内製化を進められる体制を整えることが可能になります。また、外部との連携を通じて、最新のデジタル技術やトレンドに関する情報を継続的に入手できることも、大きなメリットとなっています。
小規模から始める段階的アプローチ
成果を出している中小企業に共通するもう一つの特徴は、スモールスタートによる段階的なDX推進です。限られた予算と人材の中で、いきなり大規模なシステム導入を行うのではなく、効果が見えやすい小規模な取り組みから始めることで、早期に成果を実感し、社内の理解と支持を得ています。
調査結果からも、中小企業では成果を実感できるスピードが、その後の全社展開の成否を決める重要な要素であることが分かっています。そのため、モデル部門やラインを絞って実装を進める「超着手小局」のアプローチが効果的です。例えば、特定の部署での業務効率化ツールの導入や、一部の製品ラインでのデータ活用など、限定的な範囲で始めることで、リスクを抑えながら確実に成果を積み上げることができます。
小規模な成功体験を積み重ねることには、複数のメリットがあります。第一に、初期投資を抑えられるため、経営層の承認を得やすくなります。第二に、実際の効果を数値で示すことで、次の段階への投資判断が容易になります。第三に、従業員が段階的に新しい技術やツールに慣れていくことができるため、変革への抵抗感が少なくなります。成功している企業では、このサイクルを繰り返しながら、徐々に取り組みの範囲を拡大していく戦略を採用しています。
アナログデータのデジタル化で基本的成果を獲得
中小企業のDX推進において、最も基本的かつ効果的な取り組みが、アナログ・物理データのデジタル化です。調査によると、従業員100人以下の中小企業では、この基本的なDX施策について「既に十分な成果が出ている」という回答が企業全体平均を上回っています。これは、中小企業の規模だからこそ、デジタル化の効果が実感しやすいことを示しています。
具体的には、紙の書類や帳票をデジタル化してクラウド上で管理することで、情報共有が迅速化し、必要な資料を素早く検索できるようになります。また、手作業で行っていたデータ入力を自動化することで、人的ミスを減らし、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。このような基本的なデジタル化だけでも、業務効率化による生産性向上という明確な成果を得ることができるのです。
デジタル化の取り組みは、比較的低コストで始められることも魅力です。現在では、中小企業でも導入しやすい価格設定のクラウドサービスや業務効率化ツールが数多く提供されています。例えば、会計ソフトや受発注システム、決済ソフト、ECプラットフォームなど、幅広い選択肢があります。また、IT導入補助金などの支援制度を活用することで、初期投資の負担をさらに軽減することも可能です。
重要なのは、デジタル化を単なる効率化で終わらせないことです。デジタル化によって蓄積されたデータを分析し、業務改善や意思決定に活用することで、次のステップである真のDX推進につなげることができます。成功している企業では、基本的なデジタル化で得られた成果を土台として、段階的により高度なデータ利活用やビジネスモデルの変革へと進化させています。
地域別DX推進状況|東京と地方の課題の違いと対応策

中小企業のDX推進状況は、企業が立地する地域によって大きな差が生じています。東京と地方では、直面する課題や期待する効果が異なり、それぞれの地域特性に応じた戦略が必要です。総務省の調査によれば、東京23区の大企業では5割を超える実施率に対し、中小企業では2割強にとどまり、さらに地方の中小企業ではより一層DX推進が遅れている実態が明らかになっています。本セクションでは、地域別のDX推進状況の違いと、それぞれに適した対応策について詳しく解説します。
東京の中小企業|予算面の課題が中心
東京の中小企業がDX推進で最も大きな課題として挙げるのは「予算」です。複数の調査結果から、東京の中小企業では「予算が割けない」という回答が上位に位置しています。これは、東京という大都市圏での事業展開には家賃や人件費などの固定費が高く、新たなデジタル投資に回す余裕が限られていることが背景にあります。
東京の中小企業の多くは、DXの必要性自体は理解しており、人材面での課題も認識しています。しかし、限られた予算の中で「どこにどれだけ投資すべきか」という優先順位付けに悩んでいるケースが多く見られます。特に、既存のITシステムの維持管理にコストがかかっている企業では、新たなDX投資のための予算確保がさらに困難になっています。
東京の中小企業がこの課題を克服するためには、段階的な投資計画の策定が重要です。全社的な大規模投資ではなく、効果が見込める業務から小規模に始めることで、初期投資を抑えながら成果を確認できます。また、IT導入補助金や東京都が提供する中小企業DX推進助成金など、最大300万円から500万円規模の支援制度を活用することで、予算面の負担を軽減することが可能です。さらに、クラウドサービスなど初期費用を抑えられるツールを選択することも、予算制約の中でDXを進める有効な手段となります。
地方の中小企業|人材不足と企画立案の困難さが4倍
地方の中小企業が直面する課題は、東京とは大きく異なります。地方都市版のDX実態調査によると、DX推進が滞っている理由として「DX推進のための人材が不足しているから」が36.2%、「DX推進のアイデアや企画・戦略立案が難しいから」が32.5%と、人材面と企画面の課題が上位を占めています。特に注目すべきは、「アイデアや企画」に関する課題が東京版と比べて24ポイントも多く、約4倍という結果になっている点です。
地方の中小企業では、DXに精通した人材の採用自体が非常に困難です。都市部に比べてIT人材の絶対数が少なく、また優秀な人材は大都市圏に流出する傾向があります。そのため、社内にDXを推進できる知識や経験を持つ人材がおらず、「何から始めればよいかわからない」という状態に陥りやすいのです。この人材不足は単なる実務担当者の不足だけでなく、DX戦略を立案できる企画人材の不足も意味しています。
地方の中小企業がこの課題に対応するためには、外部リソースの積極的な活用が鍵となります。地域の金融機関や商工会議所、よろず支援拠点などが提供するDX支援サービスを利用することで、専門知識を補完できます。実際、調査では地方中小企業の42.6%が支援機関として「金融機関」を活用しており、伴走型の支援を受けながらDXを進めています。また、近隣の大学や研究機関との連携、ITベンダーとの協業なども有効な手段です。人材育成の面では、経済産業省が提供する「みらデジ」などのオンラインプラットフォームを活用し、社内人材のスキルアップを図ることも重要です。
商圏拡大への期待|東京と地方で大きな差
DXに期待する効果についても、東京と地方では顕著な違いが見られます。両地域とも「業務効率化」や「生産性向上」が上位に挙げられる点は共通していますが、「商圏の拡大」に関しては大きな差が生じています。地方都市版の調査では、商圏拡大への期待が東京版の約4分の1にとどまる結果となっています。
この差が生じる背景には、地方中小企業のDX推進段階の違いがあります。調査結果から、地方企業の多くはDXの初期段階にあり、まずは内部業務の効率化に取り組んでいる状況が読み取れます。商圏拡大のようなビジネス拡大につながるDXは、業務効率化の次のフェーズとして位置づけられるため、まだそこまで視野に入っていない企業が多いのです。
しかし、地方中小企業にとって、DXによる商圏拡大は大きな可能性を秘めています。ECサイトの構築やオンライン商談ツールの活用により、地理的制約を超えて全国や海外に顧客基盤を広げることができます。実際、地方の特産品や伝統工芸品をオンラインで販売し、全国規模のビジネスに成長させた事例も数多く存在します。地方企業がDXを進める際には、業務効率化で得られた成果を土台として、次のステップとして商圏拡大を視野に入れた戦略を描くことが重要です。
地域特性を踏まえたDX推進戦略の立て方
東京と地方の課題の違いを踏まえた、それぞれに適したDX推進戦略が必要です。まず共通して重要なのは、自社が立地する地域のデジタル化環境を正しく理解することです。中小企業白書によれば、人口規模が大きい市区町村に立地する企業ほど、デジタル化の取組に関わる環境が整っていると感じている傾向があります。自社の周辺環境を把握し、利用可能な支援策や連携可能な機関を確認することが第一歩となります。
東京の中小企業は、予算制約の中でも成果を出すために、ROI(投資対効果)を重視した選択的投資を行うべきです。すべての業務を一度にデジタル化するのではなく、最も効果が高い業務から優先的に取り組むことで、限られた予算を効果的に活用できます。また、同業他社や異業種企業との情報交換を通じて、コストを抑えた成功事例を参考にすることも有効です。
地方の中小企業は、人材不足を補うために地域内外のネットワークを積極的に活用すべきです。新潟県DX推進プラットフォームのような産学官金の連携組織や、地域の支援機関が提供する専門家派遣制度を利用することで、社内に不足している知識やスキルを補完できます。また、DXの企画立案が難しい場合は、まず他社の成功事例を参考にしながら、自社に適用できる部分から始めることが推奨されます。経済産業省が公表している「DXセレクション」などの事例集を活用し、同規模・同業種の企業の取り組みを学ぶことで、具体的な推進イメージを描きやすくなります。
興味深いのは、今後のDX推進意欲については地方の方が高いという調査結果です。DX予算を増加すると回答した地方中小企業の数は東京よりも10.1ポイント高く、「今後推進したい」という回答も25.5ポイント多くなっています。これは、地方企業が現状の課題を認識し、DXの必要性を強く感じていることの表れです。この意欲を具体的な成果につなげるために、地域特性に応じた適切な支援と戦略が求められています。
中小企業が今日から始められるDX推進5ステップ
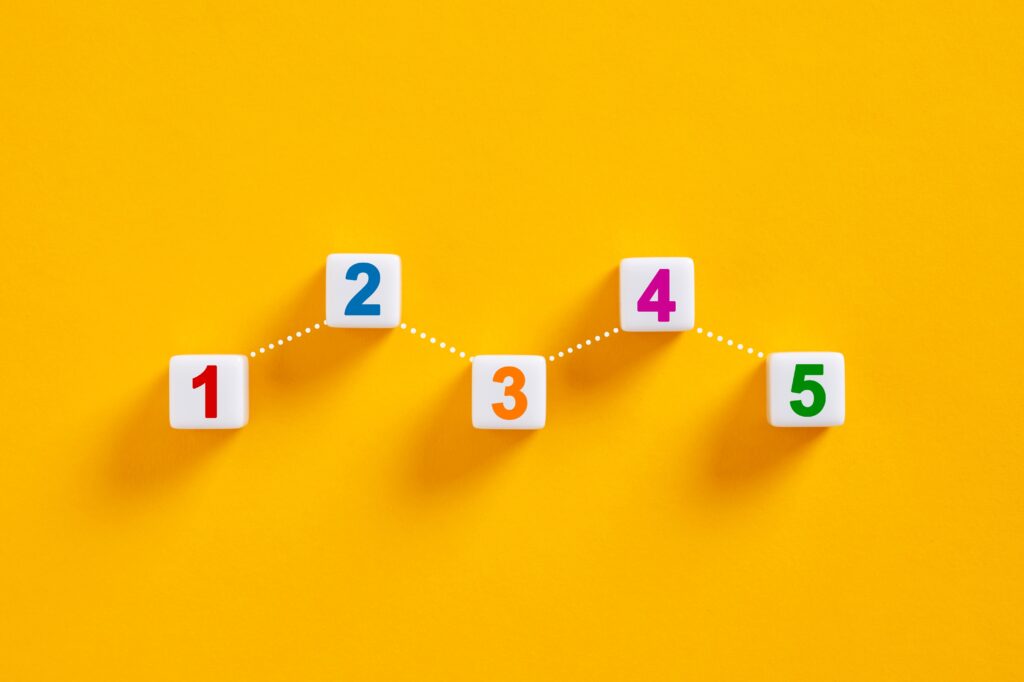
これまで見てきた調査データや課題を踏まえ、中小企業が実際にDX推進を始めるための具体的なステップを解説します。経済産業省が公表している「中堅・中小企業等向けデジタルガバナンス・コード実践の手引き」をベースに、中小企業の実情に合わせた実践的な進め方を5つのステップに整理しました。この手順に沿って取り組むことで、「何から始めればよいかわからない」という課題を克服し、着実にDX推進を前に進めることができます。
ステップ1|自社のDX理解度と現状を正確に把握する
DX推進の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。調査によれば、DXを理解している企業は49.2%と約半数にとどまり、さらに「知らない」企業が15.2%に増加しています。まず経営層が「DXとは何か」を正しく理解することが不可欠です。DXは単なるIT導入やデジタル化ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、競争優位性を確立することを指します。
自社の現状把握では、以下の項目を確認します。まず、業務プロセスの現状を洗い出し、どの業務がアナログで行われているか、どこに非効率が存在するかを明確にします。紙ベースの承認フローや手作業でのデータ入力、FAXでのやり取りなど、デジタル化できる業務を特定することが重要です。次に、社内のIT環境を確認します。現在使用しているシステムやツール、その利用状況、課題点を整理します。さらに、従業員のITリテラシーレベルも把握しておく必要があります。
現状把握の際には、経営層だけでなく現場の従業員からも意見を集めることが重要です。日々の業務で感じている課題や改善したい点は、現場が最もよく理解しています。アンケートやヒアリングを通じて、部門ごと、業務ごとの課題を可視化しましょう。また、自社がDX推進の4段階(デジタイゼーション、デジタライゼーション、DX推進、DX実現)のどの段階にいるのかを把握することで、次に取るべきアクションが明確になります。この段階では完璧を目指す必要はありません。まずは現状を客観的に把握し、課題を明確にすることが目的です。
ステップ2|従業員規模に応じた優先課題を特定する
現状把握ができたら、自社の従業員規模に応じた優先課題を特定します。調査結果から明らかなように、従業員規模20人以下の企業では「何から始めてよいかわからない」が27.7%と最大の課題であり、一方で従業員規模21人以上の企業では「IT人材不足」が32.9%、「DX推進人材不足」が33.5%と人材面の課題が深刻化しています。
小規模企業(20人以下)では、まず取り組みやすい業務から始めることが重要です。例えば、紙の請求書や契約書をPDF化してクラウドに保存する、承認フローをメールやチャットツールで行う、顧客情報を表計算ソフトからクラウド型の顧客管理システムに移行するなど、比較的低コストで始められる施策から着手します。重要なのは、小さくても確実に成果が見える取り組みを選ぶことです。成功体験を積むことで、次のステップへの意欲が高まります。
中規模企業(21人以上)では、人材育成と並行してDX推進を進める戦略が必要です。社内から推進リーダーを選定し、その人材に対して研修や外部セミナーへの参加機会を提供します。同時に、外部の専門家やITベンダーとの協業体制を構築することで、社内に不足している知識やスキルを補完します。優先課題を特定する際には、「効果が高く、実現が容易な施策」から着手するのが鉄則です。すべての業務を一度に変革しようとすると、現場の混乱を招き、DX推進自体が頓挫するリスクがあります。
ステップ3|補助金・助成金などの支援策を調査し活用する
DX推進における予算確保は、多くの中小企業にとって大きな課題です。調査でも、DX推進に向けて期待する支援策として「補助金・助成金」が49.3%と最も高い割合を示しています。幸いなことに、国や地方自治体は中小企業のDX推進を支援するために、さまざまな制度を用意しています。これらを積極的に活用することで、予算面の制約を軽減できます。
代表的な支援策としては、まずIT導入補助金があります。これは中小企業・小規模事業者が業務効率化や生産性向上のためにITツールを導入する際に、その経費の一部を補助する制度です。会計ソフトや受発注システム、決済ソフト、ECソフトなど幅広いツールが対象となり、クラウド利用料も補助対象に含まれる場合があります。申請には事前の計画策定や認定支援機関との連携が必要ですが、最大で数百万円の補助を受けられる可能性があります。
地方自治体も独自のDX支援策を展開しています。例えば東京都では「中小企業DX推進助成金」、大阪府では「DXモデル創出促進事業」など、最大300万円から500万円規模の助成を受けられる制度があります。地域により内容は異なるため、自社の所在する自治体の最新情報を必ず確認しましょう。また、「よろず支援拠点」や「IT経営サポートセンター」では、無料で専門家に相談できるサービスも提供されています。どの補助金・助成金が自社に適しているか分からない場合は、これらの相談窓口を活用することで、適切なアドバイスを受けることができます。
ステップ4|外部の専門家や研修を活用して人材を育成する
人材不足はDX推進における最大の課題の一つです。しかし、調査結果から明らかなように、成果を出している企業の多くは外部リソースを積極的に活用しています。中小企業が社内だけでDX人材をゼロから育成しようとすると、膨大な時間とコストがかかります。効率的に進めるためには、外部の専門家や研修サービスを戦略的に活用することが重要です。
外部専門家の活用方法としては、まずITベンダーやコンサルティング会社との協業があります。中小企業への導入経験が豊富な専門家を選ぶことで、自社の状況に合わせた適切なアドバイスやサポートを受けることができます。重要なのは、外部専門家に丸投げするのではなく、社内の担当者と密接に協働し、知識やノウハウを社内に蓄積することです。将来的な内製化を見据えた体制を構築しましょう。
人材育成の面では、経済産業省が提供する「みらデジ」などのオンラインプラットフォームを活用できます。これは中小企業のデジタル化を支援するポータルサイトで、自社の状況診断や、他社の事例、各種支援策の情報を得ることができます。また、地域の金融機関や商工会議所が主催するDX研修やセミナーに参加することで、基礎知識を習得しながらネットワークも構築できます。さらに、eラーニングサービスを導入することで、従業員が各自のペースで学習を進めることも可能です。調査では「DX推進指針の策定・公表」へのニーズが22.6%、「専門家の派遣」へのニーズが16.4%と増加傾向にあることから、これらの支援策を組み合わせて活用することが効果的です。
ステップ5|小さな成果を積み重ね段階的に推進する
最後のステップは、小さな成果を積み重ねながら段階的にDX推進を進めることです。成功している中小企業に共通するのは、スモールスタートで始め、成功体験を積み重ねながら徐々に取り組みの範囲を拡大している点です。中小企業では、成果が実感できるまでのスピードが、その後の全社展開の成否を決める重要な要素となります。
具体的な進め方としては、まずモデル部門や特定の業務を選定し、そこでDX施策を試験的に実施します。例えば、営業部門での顧客管理システムの導入、経理部門での電子帳簿保存システムの導入など、明確に効果が測定できる領域から始めます。3ヶ月から6ヶ月程度の期間で成果を確認し、課題があれば改善します。成功した施策は、他の部門や業務に横展開していきます。この段階的アプローチにより、リスクを最小限に抑えながら確実に前進できます。
重要なのは、PDCAサイクルを回し続けることです。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを短期間で回すことで、素早く課題を発見し、対応できます。また、小さな成功でも全社に共有し、従業員のモチベーションを高めることが大切です。社内報や定例会議で進捗状況や成果を報告し、DX推進の機運を醸成します。経営層がDX推進の重要性を繰り返し発信し、従業員の取り組みを評価・表彰することで、組織全体でDXに取り組む文化が育ちます。
これら5つのステップは、一度実施したら終わりではありません。ステップ5で得られた成果と学びをもとに、再びステップ1に戻って現状を把握し、次の優先課題を特定します。この循環を繰り返すことで、中小企業のDX推進は着実に進化していきます。調査データが示すように、DXに取り組んでいる中小企業の約8割が何らかの成果を実感しています。適切なステップを踏んで取り組めば、中小企業でも確実にDX推進を成功させることができるのです。
まとめ|調査データから見る中小企業DX推進の現在地と未来への道筋

中小企業基盤整備機構が実施した「中小企業のDX推進に関する調査(2024年)」は、日本の中小企業が直面するDX推進の現状と課題を浮き彫りにしました。本記事では、この最新調査データを詳細に分析し、中小企業がDX推進で成果を出すための実践的な道筋を示してきました。ここでは、調査から見えてきた重要なポイントを整理し、中小企業が今後DX推進を成功させるための指針をまとめます。
中小企業DX推進の現在地|二極化が進む実態
調査結果から明らかになったのは、中小企業のDX推進における「二極化」の進行です。DXを理解している企業は49.2%と約半数に達した一方で、「知らない」と回答した企業が15.2%に増加しています。また、既にDXに取り組んでいる企業は18.5%にとどまり、7割以上の企業がデジタイゼーション段階で停滞しています。しかし注目すべきは、DXに取り組んでいる企業の約8割が何らかの成果を実感しているという事実です。この高い成功率は、適切なアプローチを取れば中小企業でも確実にDX推進で成果を出せることを示しています。
従業員規模による課題の違いも重要な発見でした。20人以下の小規模企業では「何から始めてよいかわからない」が27.7%と最大の課題であり、21人以上の企業では人材不足(IT人材32.9%、DX推進人材33.5%)が深刻化しています。さらに、地域別では東京が「予算面」、地方が「人材不足と企画立案」という異なる課題を抱えていることも明らかになりました。これらの違いを理解し、自社の状況に応じた戦略を立てることが、DX推進成功の鍵となります。
成果を出すための4つの重要要素
調査データと成功事例の分析から、中小企業がDX推進で成果を出すための4つの共通要素が浮かび上がりました。第一に、経営層・IT部門・業務部門の協調体制です。DX成果ありの企業では、この協調を実施している割合が約6割に達しており、部門間の連携がDX推進の成否を大きく左右することが分かっています。第二に、外部企業や大学との連携による人材不足の補完です。社内にDX人材がいなくても、外部リソースを戦略的に活用することで成果を出している企業が多数存在します。
第三に、小規模から始める段階的アプローチです。モデル部門を絞って実装を進め、早期に成果を実感することで、その後の全社展開につなげています。第四に、アナログデータのデジタル化による基本的成果の獲得です。特に従業員100人以下の中小企業では、この基本的なDX施策で「既に十分な成果が出ている」という回答が企業全体平均を上回っており、まずは基礎的なデジタル化から始めることの有効性が実証されています。
支援策の活用が鍵|49.3%が補助金を期待
予算確保が課題となる中小企業にとって、補助金・助成金などの支援策の活用は極めて重要です。調査では、DX推進に向けて期待する支援策として「補助金・助成金」が49.3%と最も高い割合を示しました。IT導入補助金、地方自治体の独自支援策、専門家派遣制度など、中小企業が活用できる支援策は年々充実しています。これらの制度を積極的に活用することで、限られた予算の中でもDX推進を前に進めることが可能です。
また、「DX推進指針の策定・公表」へのニーズが22.6%、「専門家の派遣」へのニーズが16.4%と、知識やノウハウ面での支援も求められています。経済産業省の「みらデジ」や「よろず支援拠点」、地域の金融機関が提供する伴走支援など、無料で利用できる相談窓口も整備されています。これらの支援策を組み合わせて活用することで、中小企業は人材不足や予算制約という課題を克服しながらDX推進を進めることができます。
今日から始める5つのステップ
本記事では、中小企業が今日から実践できるDX推進の5つのステップを提示しました。ステップ1は自社のDX理解度と現状を正確に把握すること、ステップ2は従業員規模に応じた優先課題を特定すること、ステップ3は補助金・助成金などの支援策を調査し活用すること、ステップ4は外部の専門家や研修を活用して人材を育成すること、そしてステップ5は小さな成果を積み重ね段階的に推進することです。
これらのステップは一度実施して終わりではなく、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことが重要です。小さな成功体験を積み重ね、徐々に取り組みの範囲を拡大していくことで、中小企業でも確実にDX推進を前に進めることができます。完璧を目指して動けなくなるよりも、できることから一歩ずつ着実に進めることが、中小企業におけるDX成功の秘訣です。
未来への道筋|DXは中小企業の生き残り戦略
2024年の調査データが示すのは、DX推進が一部の先進企業だけの取り組みではなく、すべての中小企業にとって避けて通れない経営課題になっているという現実です。人材不足の深刻化、グローバル競争の激化、デジタル化が前提となる法制度改正など、中小企業を取り巻く環境は急速に変化しています。この変化に対応できなければ、企業の存続自体が危ぶまれる時代になっています。
しかし、本記事で見てきたように、中小企業だからこそのDX推進のアドバンテージも存在します。意思決定のスピードが速いこと、全社での足並みを揃えやすいこと、小規模から試行錯誤できることなど、規模が小さいからこそ柔軟に変革を進められる強みがあります。実際に、地方の中小企業の方が今後のDX推進意欲が高いという調査結果も、この可能性を示唆しています。
中小企業のDX推進は、単なるデジタル化にとどまらず、業務効率化による生産性向上、データ活用による意思決定の高度化、新規顧客開拓とビジネスモデル変革、そして持続的成長の実現という価値を生み出します。調査データが示す7割以上の企業が期待する「業務効率化」から始まり、段階的により高度なデータ利活用やビジネス変革へと進化させることで、中小企業は市場での競争優位性を確立できるのです。
最後に|一歩を踏み出す勇気を
本記事で紹介した調査データ、成功事例、具体的なステップは、すべて実際のデータと事例に基づいた実践的な内容です。「何から始めればよいかわからない」「予算が足りない」「人材がいない」という課題を抱える中小企業でも、適切なアプローチを取れば必ずDX推進を前に進めることができます。重要なのは、完璧な計画を立てることではなく、今できることから一歩を踏み出す勇気です。
DXに取り組んでいる中小企業の8割が成果を実感しているという事実は、行動を起こした企業が確実に報われることを示しています。自社の状況に合わせて、小さくても確実に成果が見える取り組みから始めましょう。補助金や専門家支援などの制度を活用し、外部の知見も取り入れながら、段階的に推進していくことで、中小企業のDXは必ず成功します。
2024年の調査が示す現在地を理解し、本記事で提示した道筋に沿って一歩ずつ前進することで、あなたの企業もDX推進で成果を出すことができます。未来は、今日の小さな一歩から始まります。中小企業のDX推進の成功を心より願っています。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















