自治体広報誌の作り方ガイド|住民に愛される効果的な情報発信術

・住民目線の企画と文章表現では、読者の関心に寄り添ったテーマ選びと、専門用語を避けたわかりやすい言葉づかいが重要。
・視認性の高いデザインと構成では、高齢者にも読みやすいフォントサイズ、適切な余白、親しみやすい色使いで誌面の魅力を向上。
・デジタルとの連携でリーチ拡大のために、紙とSNS・ウェブを組み合わせて、各世代に合わせた情報発信を実現。QRコードやティーザー戦略も有効。
「広報誌を作っているのに住民に読まれていない」「情報を伝えたいのに関心を持ってもらえない」そんな悩みを抱える自治体広報担当者は少なくありません。
実際に、多くの自治体で発行される広報誌が一方的な情報発信にとどまり、住民との双方向コミュニケーションが実現できていないのが現状です。しかし、適切な戦略と手法を用いることで、住民に愛され、地域活性化にも貢献する効果的な広報誌を作ることは十分可能です。
本記事では、内閣総理大臣賞を連続受賞した「広報うちこ」や、SNS活用で注目を集める葉山町の事例を参考に、住民に読まれる広報誌の作り方を基礎から応用まで体系的に解説します。限られた予算でも実践できる具体的な改善手法をマスターし、地域住民との信頼関係構築を実現しましょう。

自治体広報誌の基本知識と現状課題

自治体広報誌の定義と役割
自治体広報誌は、地方自治体が住民に向けて発行する定期刊行物であり、行政情報の伝達だけでなく、地域コミュニティの結束を深める重要な役割を担っています。従来の「お知らせ」中心の一方的な情報発信から、住民との双方向コミュニケーションを実現するツールへと進化が求められています。
広報誌の本来の目的は、パブリックリレーションズ(PR)の理念に基づき、自治体と住民の良好な関係を構築することです。単なる行政の告知媒体ではなく、住民の生活に寄り添い、地域への愛着と参加意識を育むコミュニケーションプラットフォームとして機能することが理想的です。
また、広報誌は地域外の人々に向けた魅力発信媒体としても重要性が高まっています。移住促進や観光誘致、企業誘致など、自治体のブランディング戦略において広報誌が果たす役割は拡大し続けています。
現代の広報誌が直面する3つの課題
多くの自治体広報誌が抱える最大の課題は、住民に読まれていない現実です。公益財団法人日本広告協会の調査によると、広報誌を「毎回必ず読む」と答えた住民の割合は全体の3割程度にとどまっており、多くの住民が広報誌を手に取っても詳細まで読み込んでいないことが明らかになっています。
この背景には、情報発信の一方通行化という構造的問題があります。自治体側が伝えたい情報と住民が知りたい情報との間にギャップが生じており、住民の実際のニーズや関心事に応えきれていないケースが散見されます。特に、専門的な行政用語を多用した文章や、住民の日常生活との関連性が見えにくい内容構成が、読者離れの要因となっています。
さらに、デジタル時代における紙媒体の存在意義についても見直しが求められています。SNSやウェブサイトなどの即効性の高いデジタルメディアが普及する中で、月1回発行の広報誌が果たすべき役割の明確化が急務となっています。単純な情報伝達であればデジタル媒体が優位であるため、紙媒体ならではの価値を提供できなければ、広報誌の必要性そのものが問われることになります。
効果的な広報誌がもたらす3つのメリット
一方で、質の高い広報誌を発行することで得られるメリットは計り知れません。第一に、住民参加意識の向上と地域活性化の実現があります。神奈川県葉山町の事例では、Instagram連携による若年層向け広報活動により、町のイベントへの若者参加が大幅に増加し、地域コミュニティの活性化につながりました。
第二のメリットは、自治体への信頼度向上と行政透明性の確保です。住民が求める情報を適切に提供し、政策決定プロセスを分かりやすく説明することで、行政に対する理解と信頼が深まります。これにより、住民と行政の協働による街づくりが実現しやすくなります。
第三に、移住促進・企業誘致への貢献効果も見逃せません。質の高い広報誌は自治体の魅力を効果的に発信し、地域ブランディングの重要な要素として機能します。千葉県流山市の「DEWKS」(共働き子育て世代)をターゲットにした戦略的広報活動は、人口増加という具体的な成果を生み出しています。これらの効果を最大化するためには、住民目線に立った広報誌づくりが不可欠です。
住民に愛される広報誌の4つの基本要素

読みやすいデザインとレイアウトの基本原則
広報誌の成功を左右する最重要要素の一つが、視認性を高めるデザイン設計です。全国広報コンクールの受賞作品を分析すると、読みやすい広報誌には共通の特徴があります。
まず、色使いについては、やわらかなパステルカラーを基調とした配色が効果的です。青森県「県民だよりあおもり」や静岡市「広報しずおか」などの受賞作品では、どの年代の読者が手に取っても親しみを感じられる優しい色調を採用しています。特に重要なのは、文字と背景のコントラスト比を4.5:1以上に設定し、高齢者でも読みやすい視認性を確保することです。
文字サイズについては、本文は最低でも10ポイント以上、見出しは14ポイント以上を推奨します。また、行間(行送り)は文字サイズの1.5倍程度に設定することで、文章の可読性が大幅に向上します。情報の優先順位に基づく効果的なページ構成では、重要度の高い情報を紙面の上部と左側に配置し、読者の視線の流れに沿ったZ型レイアウトを基本とします。
余白の活用も重要な要素です。情報を詰め込みすぎず、適度な余白を設けることで、読者の目の疲労を軽減し、重要な情報に注意を向けやすくなります。1ページあたりの情報量は、読者が5分以内で読み切れる程度に調整することが理想的です。
住民ニーズに応える記事企画の作り方
効果的な広報誌制作の出発点は、住民の真のニーズを把握することです。アンケート調査を活用したニーズ把握方法として、以下のアプローチが有効です。
まず、定期的な住民アンケートの実施により、関心の高い分野を特定します。公益財団法人日本広告協会の調査では、住民が最も求める情報として「健康・福祉・医療介護」(76.4%)、「防犯・防災」(47.8%)、「環境・ごみ・リサイクル」(45.7%)が上位に挙げられています。
年代別・属性別に響く企画立案では、ターゲット層の生活パターンと関心事を詳細に分析することが重要です。例えば、子育て世代には保育園情報や子育て支援制度、高齢者には健康づくりや生涯学習機会、働く世代には行政手続きのデジタル化情報など、それぞれのライフステージに応じた情報提供が求められます。
さらに、住民参加型の企画開発も効果的です。読者からの投稿コーナーや市民記者制度の導入により、住民自身が情報発信者となる仕組みを構築することで、当事者意識を高めることができます。静岡県吉田町の「広報よしだ」では、多数の町民が実名・顔写真付きで登場し、手書き風のコメントを掲載することで、親近感のある誌面を実現しています。
親しみやすい文章表現のコツ
行政文書特有の硬い表現を避け、分かりやすい表現術を身につけることは、広報誌の読みやすさを格段に向上させます。具体的には、専門用語や役所用語を使用する際は、必ず分かりやすい説明を併記します。
例えば、「施策」→「取り組み」、「実施」→「行う」、「周知」→「お知らせ」といった言い換えを積極的に行います。また、一文の長さは50文字以内を目安とし、複雑な内容は箇条書きや図表を活用して整理します。
住民目線でのストーリー構成法では、行政の取り組みを紹介する際に、それが住民の生活にどのような具体的なメリットをもたらすのかを明確に示します。愛媛県内子町の「広報うちこ」では、地域の高齢女性たちの活動を通じて、「郷土料理が廃れることは地域文化が廃れること」という独自の視点を提示し、読者に新しい気づきを与えています。
また、読者との距離感を縮めるために、担当職員の顔が見えるコラムや、市長・町長からの親しみやすいメッセージなどを定期的に掲載することで、人間味のある広報誌を実現できます。
写真・イラストの効果的な活用法
視覚的要素は、広報誌の印象を大きく左右する重要な要素です。全国広報コンクール受賞作品の分析から、笑顔の住民写真が読者に与える親近感効果は絶大であることが分かります。
写真撮影の際は、自然な表情を引き出すために、撮影対象者との事前コミュニケーションを十分に行います。また、住民が日常的に利用する場所(公園、商店街、公共施設など)での撮影を心がけることで、読者にとって身近で親しみやすい印象を与えることができます。
イラストの活用では、パステルカラーを多用した温かみのあるデザインが効果的です。特に、行政手続きの説明や制度の紹介など、文字だけでは理解が困難な内容については、フローチャートやインフォグラフィックスを活用することで、視覚的な理解を促進できます。
写真・イラストの配置については、文章との関連性を明確にし、説明的な役割を持たせることが重要です。単なる装飾ではなく、情報伝達の補完ツールとして機能するよう、計画的に配置することで、全体の情報伝達効果を最大化できます。
広報媒体の効果的な使い分け戦略

広報誌とデジタル媒体の連携手法
現代の効果的な広報活動では、紙媒体とデジタル媒体の特性を活かしたクロスメディア戦略が不可欠です。広報誌は詳細で体系的な情報提供に優れ、SNSは即効性と拡散力に長けているため、両者の相乗効果を最大化する連携設計が重要となります。
具体的な連携手法として、広報誌の特集記事をSNSで事前告知し、読者の関心を高める「ティーザー戦略」が効果的です。神奈川県葉山町では、Instagram上で「#葉山歩き」というハッシュタグを活用し、広報誌で紹介する地域スポットの写真を事前投稿することで、広報誌への関心度を大幅に向上させています。
また、広報誌に掲載しきれない詳細情報やリアルタイム更新が必要な内容については、QRコードを活用してウェブサイトへ誘導する手法も有効です。ウェブサイト・アプリとの情報連携による利便性向上では、広報誌で概要を紹介し、詳細な申請方法や最新の受付状況はデジタル媒体で確認できる構造を構築することで、利用者の利便性を大幅に向上させることができます。
さらに、広報誌のデジタル版を同時配信することで、若年層やスマートフォンユーザーにもリーチを拡大できます。ただし、単純なPDF配信ではなく、スマートフォンでの閲覧に最適化されたレスポンシブデザインの採用が必要です。
ターゲット層に応じた媒体選択の原則
効果的な情報発信を実現するためには、ターゲット層の情報取得習慣に合わせた媒体選択が欠かせません。高齢者層に対しては、紙媒体を中心とした情報提供アプローチが最も効果的です。60歳以上の住民の約8割が広報誌を主要な情報源としており、デジタル媒体よりも信頼性が高いと認識している調査結果があります。
高齢者向けの広報誌では、文字サイズを大きくし、コントラストを明確にすることで視認性を向上させます。また、健康・福祉・医療情報を重点的に掲載し、生活に直結する実用的な内容を中心に構成することが重要です。
一方、若年層に対してはデジタルファーストの情報発信戦略が有効です。18歳から39歳の住民の約7割がSNSを主要な情報源としており、Instagram、Twitter、LINEなどのプラットフォームを活用した視覚的で魅力的なコンテンツ配信が求められます。
千葉県流山市では、YouTubeチャンネルとLINE公式アカウントを連携させ、子育て支援情報や市の魅力を動画とテキストの両方で発信することで、DEWKS世代(共働き子育て世代)の関心を効果的に集めています。また、働く世代(30歳~50歳)に対しては、メールマガジンやプッシュ通知機能を活用し、必要な情報をタイムリーに届けるプル型配信が効果的です。
予算規模別の最適な媒体ミックス
限られた予算で最大効果を生む媒体組み合わせ術では、自治体の規模と予算に応じた戦略的な媒体選択が重要です。小規模自治体(人口1万人以下)では、広報誌を核とした情報発信に、無料で利用できるSNSプラットフォームを組み合わせる手法が最もコストパフォーマンスに優れています。
中規模自治体(人口1万人~10万人)では、広報誌・ウェブサイト・SNS・メールマガジンの4媒体を連携させた統合的なアプローチが推奨されます。この規模では、専任の広報担当者を配置し、各媒体の特性を活かした役割分担を明確化することで、効率的な情報発信体制を構築できます。
大規模自治体(人口10万人以上)では、上記に加えてYouTubeチャンネル、LINE公式アカウント、アプリ開発などの多様な媒体を組み合わせることで、より幅広い住民層にリーチできます。茨城県の「いばキラTV」のように、独自の動画コンテンツプラットフォームを構築することで、他自治体との差別化を図ることも可能です。
費用対効果を高める制作・配布方法の選択指針としては、印刷コストを抑制するため、ページ数の最適化と用紙の選択を検討します。また、配布方法についても、全戸配布から希望者配布への転換や、デジタル版の普及により印刷部数を段階的に削減するなど、持続可能な広報活動の実現を目指すことが重要です。
成功事例に学ぶ広報誌改革の実践方法

話題の自治体広報誌ベストプラクティス
全国の自治体で注目を集める広報活動の成功事例から、実践的な手法を学ぶことができます。神奈川県葉山町のInstagram連携による若年層取り込み成功例は、従来の広報誌の概念を大きく変革した画期的な取り組みです。
葉山町では、公式Instagramアカウントを開設し、町の女性職員が「#葉山歩き」のハッシュタグとカジュアルなコメントで町内の風景・グルメ・イベントの様子を毎日発信しました。この取り組みにより、フォロワー数は開始1年余りで9千人を超え、「#葉山歩き」の投稿数と「いいね」の獲得数では全自治体中1位を獲得しています。
特に注目すべきは、SNS投稿と広報誌の連携による相乗効果です。Instagram上で話題になった地域スポットやイベントを広報誌で詳細に特集し、逆に広報誌の企画をSNSで事前告知することで、両媒体の価値を高め合う循環を生み出しました。また、「オフ会」と呼ばれる住民参加型のイベントを開催することで、デジタル上の交流を実際の地域参加につなげることに成功しています。
茨城県の動画活用戦略「いばキラTV」も、広報活動の新しい可能性を示した成功例です。民放の県域テレビ局を持たない茨城県では、YouTubeを活用した動画サイトで観光スポットやグルメ、行政ニュースなどを精力的に発信し、1万本以上の動画を作成しました。その結果、動画掲載本数・総再生回数・チャンネル登録者数の3冠を達成し、都道府県運営の動画サイトとして国内トップの地位を獲得しています。
内閣総理大臣賞受賞「広報うちこ」の成功要因
愛媛県内子町の「広報うちこ」は、2018年と2019年に連続して内閣総理大臣賞を受賞した、まさに日本最高水準の自治体広報誌です。その成功要因を詳細に分析することで、他自治体でも応用可能な実践的な手法を抽出できます。
第一の成功要因は、地域密着型コンテンツの企画・取材手法にあります。2018年受賞号「地域づくりの源泉」では、約300人が住む石畳地区の町づくりにフォーカスし、広報担当職員が長期間にわたって地域に通い続け、住民との信頼関係を築きながら取材を進めました。
2019年受賞号「ふるさとの味をつなぐ20年の活動 おばあちゃんのみのり」では、地元農産物の加工・生産に携わる5人の高齢女性たちの活動を、単なる紹介にとどまらず、「郷土料理が廃れることは地域文化が廃れること」という独自の視点で再構築しています。この視点設定により、読者に新しい気づきと地域への愛着を同時に提供することに成功しました。
第二の成功要因は、住民を主役にした記事作成のポイントです。「広報うちこ」では、行政の取り組みを紹介する際も、必ず住民の顔と声を前面に出し、行政と住民が協働する姿を丁寧に描写しています。コンクールの講評でも「人と地域が織りなすまちづくりのドラマがうまく表現されている」と高く評価されており、住民主体の情報発信が成功の核心であることが分かります。
中小規模自治体でも実践可能な改善アイデア
大規模な予算や専門スタッフがいない中小規模自治体でも、工夫次第で広報誌の品質を大幅に向上させることが可能です。低予算でできるデザイン改善テクニックとして、以下の具体的な手法が効果的です。
まず、無料で利用できるデザインツールの活用があります。CanvaやGIMPなどのツールを使用することで、専門的なデザインソフトがなくても視覚的に魅力的な誌面を制作できます。テンプレートを活用すれば、デザインの知識がない職員でも一定水準以上の誌面を作成することが可能です。
写真撮影については、スマートフォンでも十分に質の高い写真を撮影できます。重要なのは、自然な表情を引き出すコミュニケーション技術と、構図や光の使い方などの基本的な撮影技術を身につけることです。住民の笑顔を効果的に撮影することで、親しみやすい誌面を実現できます。
職員のスキルアップによる内製化のコツとしては、まず広報担当職員が基本的な編集・デザインスキルを習得することが重要です。公益社団法人日本広報協会が開催する研修会への参加や、成功事例の分析を通じて、実践的なノウハウを蓄積していきます。
また、地域の人材リソースの活用も効果的です。美術教師、デザイン関係者、カメラマンなど、地域に埋もれている専門的スキルを持つ住民との協働により、地域参加型の広報誌づくりを実現できます。この手法は、制作費の削減だけでなく、住民の参加意識向上という副次効果も期待できます。
広報誌の効果測定と改善サイクル
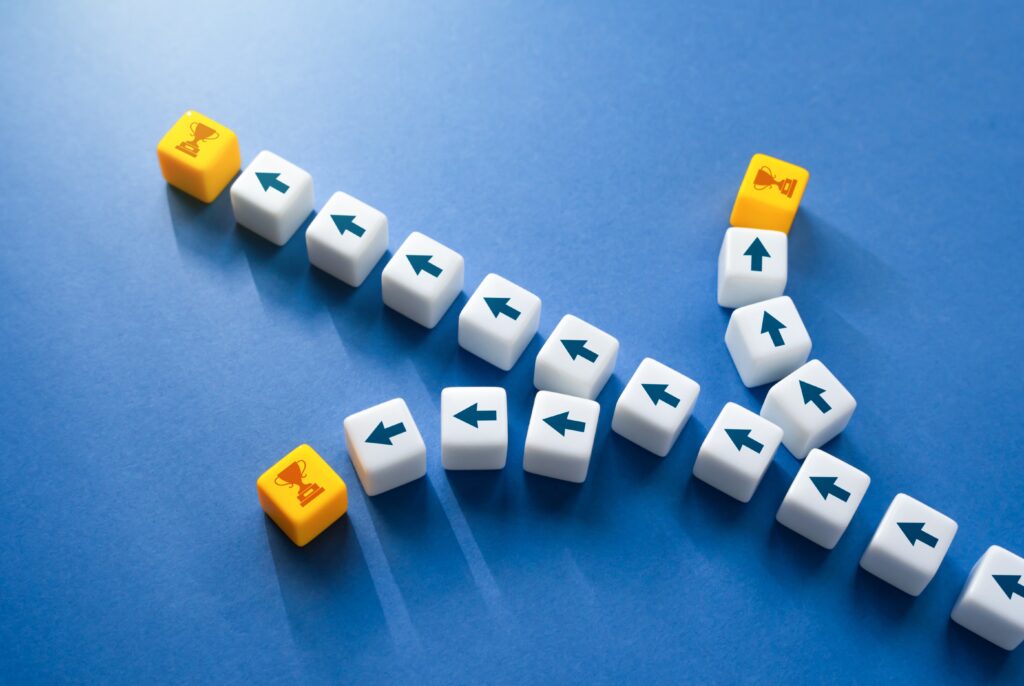
広報誌の効果を測る指標設定
広報誌の効果的な運営には、客観的な評価指標に基づく定期的な効果測定が不可欠です。読書率・認知度調査の効果的な実施方法として、年1回から2回の頻度で住民アンケートを実施し、以下の項目を継続的に追跡することが推奨されます。
基本指標としては、まず「読書率」があります。これは「毎回必ず読む」「時々読む」「ほとんど読まない」の3段階で測定し、経年変化を追跡します。次に「認知度」として、主要な行政施策や地域イベントについて、広報誌を通じて知ったかどうかを確認します。さらに「理解度」として、掲載された情報が住民にとって分かりやすかったかを5段階評価で測定します。
定性的な指標も同様に重要です。「親しみやすさ」「信頼性」「有用性」などの印象評価を定期的に調査することで、広報誌の方向性を適切に修正していくことができます。また、「最も印象に残った記事」「今後取り上げてほしいテーマ」などの自由記述回答により、住民ニーズの変化を敏感に察知することが可能です。
デジタル版の閲覧数・滞在時間分析では、Google AnalyticsやSNSのインサイト機能を活用し、オンライン上での読者行動を詳細に把握します。ページビュー数、平均滞在時間、直帰率、SNSでのシェア数などを継続的に監視することで、読者の関心度をリアルタイムで測定できます。特に、記事別の閲覧時間を分析することで、どのような内容が読者に支持されているかを客観的に把握できます。
PDCAサイクルによる継続改善
効果測定で得られたデータを基に、継続的な改善を実施するためのPDCAサイクルの構築が重要です。住民フィードバックの収集・活用システムでは、複数のチャネルを通じて住民の声を集約する体制を整備します。
Plan(計画)フェーズでは、前回の効果測定結果を基に改善目標を設定します。例えば、「20代の読書率を現在の15%から25%に向上させる」「健康・福祉関連記事の理解度を4.0から4.5に改善する」など、具体的で測定可能な目標を設定します。
Do(実行)フェーズでは、設定した改善策を実際に実施します。デザインの改善、記事構成の変更、新しい企画の導入など、仮説に基づいた施策を順次展開していきます。重要なのは、一度に多くの要素を変更せず、効果を正確に測定できるよう段階的に実施することです。
Check(評価)フェーズでは、実施した改善策の効果を客観的に検証します。アンケート調査の結果、デジタル版のアクセス解析、住民からの直接的なフィードバックなどを総合的に分析し、改善策の有効性を判断します。
Action(改善)フェーズでは、評価結果を基に次のサイクルの計画を策定します。効果が確認された取り組みは継続・拡大し、効果が不十分だった取り組みは修正または中止を検討します。このサイクルを継続することで、データ駆動型の広報改善を実現できます。
長期的な広報戦略の立案
広報誌の効果測定と改善は、単発の活動ではなく、長期的な視点での戦略的取り組みとして位置づける必要があります。地域ブランディングと連携した広報計画では、自治体の将来像と照らし合わせながら、5年から10年のスパンで広報活動の方向性を設定します。
まず、自治体の総合計画や地方創生戦略との整合性を確保し、広報誌が目指すべき役割を明確化します。人口減少対策、産業振興、観光振興、移住促進など、重点的に取り組む政策分野に応じて、広報誌の位置づけと期待される効果を具体的に設定します。
次に、住民の年齢構成や世帯構成の将来予測を踏まえ、ターゲット層の変化に対応した戦略を策定します。高齢化の進行、若年人口の減少、外国人住民の増加など、地域の人口動態の変化を見据えた情報発信手法の転換が必要です。
技術的な環境変化への対応も重要な要素です。デジタル化の進展、AIやIoT技術の普及、情報アクセス手段の多様化など、情報通信技術の発展を見据えた広報手法の進化を計画的に進めます。特に、個人の関心や属性に応じたパーソナライズ配信技術の活用により、より効果的な情報発信が可能になることが期待されます。
さらに、持続可能性の観点から、環境負荷の軽減、予算の最適配分、職員のスキル向上など、長期的に維持可能な広報活動の体制構築を進めます。これにより、一時的な改善にとどまらず、継続的に質の高い広報誌を発行し続けることが可能になります。
多様なニーズに対応する広報誌の工夫

アクセシビリティに配慮した誌面づくり
すべての住民が等しく情報にアクセスできる広報誌を実現するためには、高齢者・視覚障害者にも優しいデザインへの配慮が不可欠です。ユニバーサルデザインの原則に基づいた誌面設計により、年齢や身体的な制約にかかわらず、すべての住民にとって読みやすい広報誌を実現できます。
具体的な配慮事項として、まず文字サイズについては、本文を最低12ポイント以上、見出しを16ポイント以上に設定することで、加齢による視力低下があっても読みやすさを確保できます。また、文字と背景のコントラスト比を4.5:1以上に設定し、文字の視認性を最大化します。
色覚に障害がある方への配慮として、色だけで情報を区別せず、形状や模様、数字などの他の手段も併用します。例えば、重要度を示す際に、色分けだけでなく「★★★(重要)」「★★(注意)」などのマークを併用することで、色の識別が困難な方でも情報を正確に受け取ることができます。
音声読み上げソフトに対応するため、デジタル版ではテキストデータを適切に埋め込み、画像には代替テキストを設定します。また、多言語対応による外国人住民への配慮として、重要な情報についてはやさしい日本語での表記や、主要な外国語での要約を併記することが効果的です。
災害時・緊急時の情報発信体制
平時の広報誌と災害時の情報発信は、それぞれ異なる特性と要求に応える必要があります。平常時広報誌と緊急時広報の使い分けでは、メディアの特性を最大限に活用した効率的な情報伝達体制の構築が重要です。
災害発生直後の緊急情報については、即効性の高いSNSや緊急速報メール、防災行政無線などのデジタル媒体を優先的に活用します。一方、復旧・復興期における詳細な支援情報や手続き案内については、広報誌の臨時号発行により、体系的で正確な情報を住民に提供します。
SNSとの連携による迅速な情報伝達では、平時から公式アカウントのフォロワー数を増やし、住民との関係性を構築しておくことが重要です。福岡市の事例では、LINE公式アカウントを通じて防災情報、避難所情報、生活支援情報をリアルタイムで配信し、災害時の情報格差解消に大きな成果を上げています。
また、停電やインターネット障害が発生した場合に備え、紙媒体による情報発信体制も整備しておく必要があります。避難所での掲示用ポスターや、戸別配布用のチラシなど、アナログ手段による情報伝達も重要な補完機能として位置づけます。
環境に配慮した広報誌の制作・配布
持続可能な社会の実現に向けて、広報誌の制作・配布においても環境負荷の軽減が求められています。デジタル化推進による紙資源の節約は、最も効果的な環境配慮策の一つです。
具体的な取り組みとして、まず希望者へのデジタル版提供を積極的に推進し、紙版の発行部数を段階的に削減していきます。スマートフォンやタブレットでの閲覧に最適化されたデジタル版を制作し、QRコードや専用アプリを通じて簡単にアクセスできる環境を整備します。
紙版については、環境に優しい用紙の選択と印刷方法の見直しを行います。再生紙の使用率向上、植物性インクの採用、印刷時の化学物質使用量の削減など、制作プロセス全体での環境負荷軽減に取り組みます。
配布方法の改善では、従来の全戸配布から希望者配布への段階的な移行を検討します。住民アンケートによりデジタル版利用意向を把握し、紙版を必要とする世帯にのみ配布することで、無駄な印刷を大幅に削減できます。
また、広報誌の回収・リサイクルシステムの構築により、使用後の用紙を有効活用する循環型の取り組みも効果的です。公共施設に回収ボックスを設置し、回収した広報誌を地域の福祉施設や教育機関での工作材料として再利用するなど、地域循環型のリサイクル活動を推進することで、住民の環境意識向上にも貢献できます。
これらの環境配慮策は、単なるコスト削減効果だけでなく、自治体の環境政策への取り組み姿勢を住民に示すメッセージとしても機能します。広報誌自体が環境配慮の実践例となることで、住民の環境意識向上と行政への信頼度向上という二重の効果を期待できます。
これからの自治体広報に求められる視点

デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応
自治体広報の分野においても、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は避けて通れません。オンライン申請連携など利便性向上の工夫により、広報誌は単なる情報発信媒体から、住民サービスのゲートウェイとしての機能を担うようになっています。
具体的な取り組みとして、広報誌に掲載された制度紹介記事から、QRコードを介してオンライン申請画面に直接アクセスできる仕組みの構築があります。例えば、子育て支援制度の紹介記事に、該当する申請フォームへの直接リンクを設置することで、「知る」から「利用する」までのプロセスを大幅に短縮できます。
また、マイナンバーカードと連携した個人認証システムにより、広報誌で紹介された制度について、読者個人の利用資格や申請状況をリアルタイムで確認できるサービスの導入も進んでいます。これにより、一般的な制度説明から個人に最適化された情報提供への転換が可能になります。
AIを活用した個別最適化コンテンツの可能性も注目されています。住民の年齢、家族構成、居住地域、過去の行政サービス利用履歴などのデータを分析し、個人の関心や必要性に応じてカスタマイズされた広報コンテンツを自動生成する技術の実用化が進んでいます。これにより、すべての住民にとってより関連性の高い情報を効率的に届けることが可能になります。
住民参加型広報への転換
従来の行政主導型の情報発信から、住民が主体的に参加する双方向型の広報活動への転換が求められています。市民記者制度など住民主体の情報発信により、より身近で親しみやすい広報コンテンツの制作が可能になります。
市民記者制度では、地域住民の中から広報活動に関心のある方を募集し、簡単な研修を実施した後、地域イベントや施設紹介、住民インタビューなどの取材・執筆を担当してもらいます。行政職員では気づきにくい住民目線での発見や、地域の隠れた魅力を発掘することができ、広報誌の内容に多様性と親近感をもたらします。
住民投稿コーナーの充実も効果的な手法です。写真コンテスト、川柳・俳句の募集、地域の思い出エピソードの投稿など、住民が気軽に参加できる企画を定期的に実施することで、広報誌への関心度と地域への愛着を同時に高めることができます。
双方向コミュニケーションの実現方法では、広報誌に掲載された記事に対する読者からのフィードバックや質問を積極的に収集し、次号で回答や関連情報を掲載する「読者との対話コーナー」の設置が有効です。また、SNS上での住民からの質問や要望に対して、広報誌で詳細に回答することで、デジタルと紙媒体の連携による双方向性を実現できます。
地域間連携による広報力強化
限られた資源を有効活用し、広報活動の質を向上させるためには、近隣自治体との連携による効率化とノウハウ共有が重要です。近隣自治体とのノウハウ共有システムにより、成功事例や失敗事例を相互に学び合う体制を構築することで、個別の自治体では得られない知見を蓄積できます。
具体的な連携方法として、定期的な広報担当者交流会の開催により、制作技術、企画アイデア、効果測定手法などの情報交換を行います。また、共通の課題(人口減少、高齢化、産業振興など)を抱える自治体同士で、合同での調査研究や先進地視察を実施することで、より効率的な学習機会を創出できます。
広域圏での統一的な情報発信戦略では、観光振興や災害対応など、単独の自治体では対応困難な広域的な課題について、連携して情報発信することで相乗効果を生み出すことができます。例えば、複数の自治体で構成される観光圏において、それぞれの広報誌で他自治体の観光資源を紹介し合うことで、地域全体の魅力発信力を向上させることが可能です。
制作面での連携では、印刷業者との一括契約による制作コストの削減、デザイナーや写真家などの専門人材の共同活用、制作技術研修の合同開催など、スケールメリットを活かした効率化が期待できます。
さらに、成功事例のデータベース化と共有により、全国の優秀な広報事例を参考にした改善活動を効率的に進めることができます。内閣総理大臣賞受賞作品の分析結果や、各種コンクールの入賞事例の詳細な解析情報を共有することで、全体的なレベルアップを実現できます。これにより、個別の自治体の努力だけでは到達困難な高い水準の広報活動を、地域全体で実現することが可能になります。
まとめ|住民に愛される自治体広報誌を目指して

継続的改善こそが成功の鍵
本記事で解説してきた様々な手法や事例から明らかなように、効果的な自治体広報誌の実現には特別な予算や技術は必要ありません。最も重要なのは、住民目線を忘れずにPDCAサイクルを継続的に回し続ける姿勢です。
内閣総理大臣賞を連続受賞した「広報うちこ」も、葉山町のSNS活用成功事例も、一朝一夕に生まれたものではありません。住民のニーズを丁寧に把握し、効果測定に基づいた改善を繰り返すことで、現在の高い評価を獲得しています。特に重要なのは、失敗を恐れず新しい取り組みにチャレンジし、その結果を客観的に分析して次の改善につなげる継続的な学習姿勢です。
効果測定においては、読書率や認知度などの定量的指標だけでなく、住民からの直接的なフィードバックや職員の気づきなど、定性的な情報も同様に重要です。数値には表れない住民の満足度や地域への愛着度の変化を敏感に察知し、広報活動の方向性を適切に調整していくことが求められます。
また、デジタル技術の急速な発展により、広報活動を取り巻く環境は絶えず変化しています。新しい技術やプラットフォームの登場に対して、積極的に学習し、自治体の実情に合わせて適切に導入していく柔軟性も、長期的な成功には欠かせない要素です。
地域の特性を活かした独自性のある広報誌づくり
成功する広報誌に共通するもう一つの特徴は、その地域ならではの独自性と魅力を効果的に発信していることです。全国一律の手法を模倣するのではなく、地域の歴史、文化、産業、人材などの固有の資源を最大限に活用したオリジナリティのある企画こそが、住民の心に響く広報誌を生み出します。
茨城県の「いばキラTV」は、民放テレビ局がないという地域特性をむしろ強みに転換し、YouTube を活用した独自の情報発信で全国トップレベルの成果を上げました。内子町の「広報うちこ」は、地域の高齢女性たちの素朴な活動に光を当て、「郷土料理が廃れることは地域文化が廃れること」という独自の視点で地域の価値を再発見しています。
このように、他地域との差別化を図りながら、住民が誇りを持てる地域アイデンティティを育む広報誌づくりが重要です。地域の隠れた魅力や価値を発掘し、住民自身が気づいていなかった地域の素晴らしさを再認識してもらうことで、地域への愛着と参加意識を高めることができます。
限られた予算や人員でも、工夫次第で質の高い広報誌は制作可能です。重要なのは最新の技術や高額な制作費ではなく、住民に寄り添う姿勢と継続的な改善への取り組みです。無料のデザインツールの活用、地域人材との協働、近隣自治体との連携など、創意工夫により多くの課題は解決できます。
また、環境への配慮やアクセシビリティの向上など、社会的な要請に応える広報活動は、自治体の先進性をアピールする機会でもあります。デジタル化推進による環境負荷軽減、多言語対応による多様性の受容、ユニバーサルデザインによる共生社会の実現など、広報誌自体が自治体の政策姿勢を体現するメディアとして機能させることが可能です。
住民に愛される広報誌は、単なる情報伝達手段を超えて、地域コミュニティの結束を深め、住民参加を促進し、地域の魅力を内外に発信する総合的なプラットフォームとして機能します。本記事で紹介した手法と事例を参考に、あなたの自治体ならではの魅力的な広報誌の実現に向けて、ぜひ積極的に取り組んでください。住民との信頼関係を築き、地域の発展に貢献する広報活動の成功を心より応援しています。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















