行政調達の未来を切り開くDMP:効率化と透明性の実現
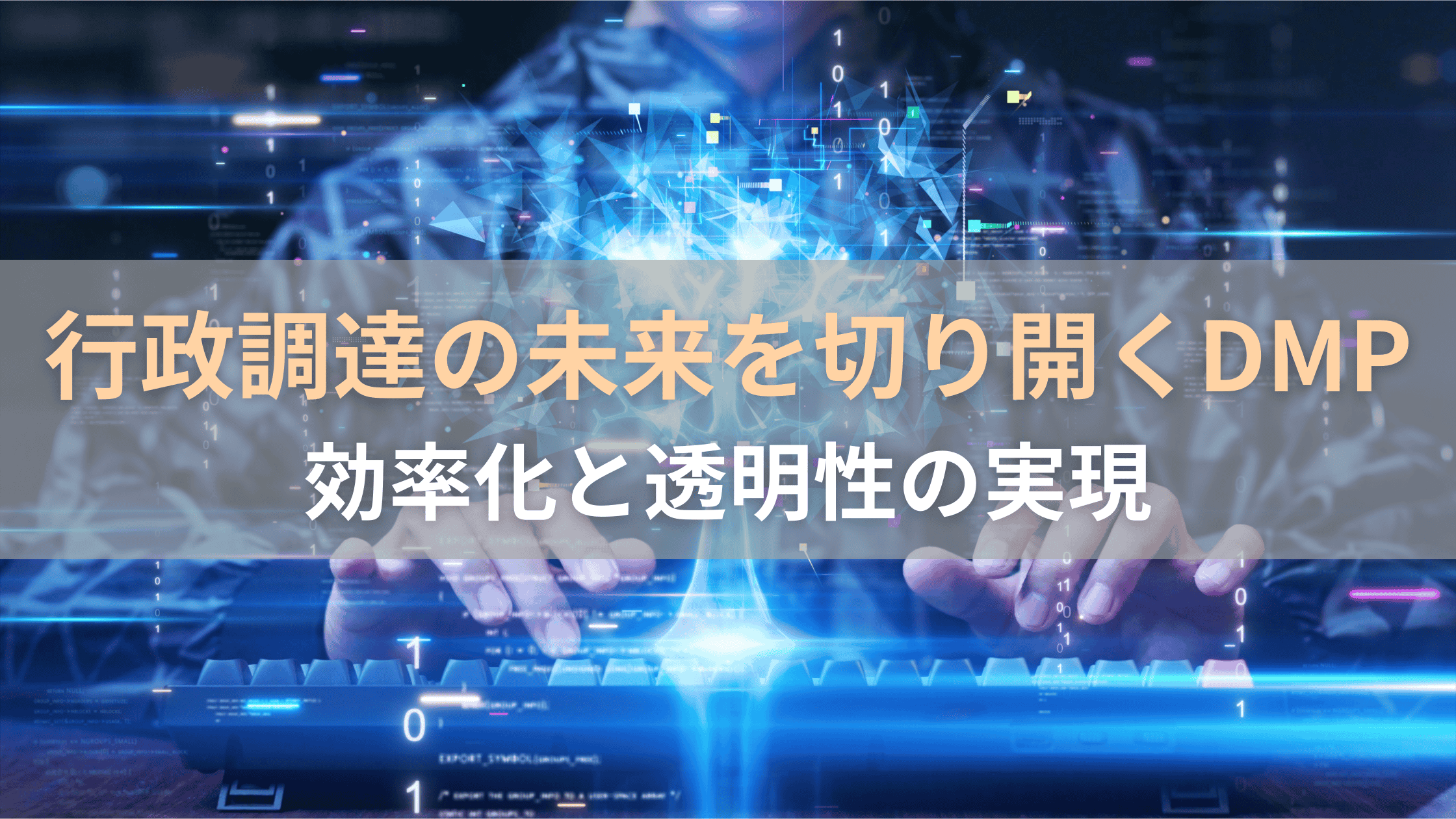
・デジタルマーケットプレイス(DMP)の基本と特徴
DMPは行政機関が迅速にITサービスを調達できるデジタル庁運営のプラットフォームで、事前登録された情報から直接サービスを選択可能で、調達期間を大幅に短縮する。
・従来の調達方式との違いとメリット
従来の方式と異なり、仕様書作成や評価の負担を軽減し、調達プロセスの透明性と効率性を向上。行政機関は調達の簡素化、中小企業は参入障壁の低下と営業コスト削減が期待できる。
・DMPの展望と課題
全国展開に向けた正式版のリリースが予定され、AI推奨機能や地方自治体向けカテゴリーの追加などが計画されていますが、導入効果の最大化にはユーザビリティ向上や市場活性化が課題となる。
行政機関のIT調達を効率化する新しい仕組み「デジタルマーケットプレイス(DMP)」が注目を集めています。デジタル庁が推進するこのプラットフォームは、クラウドサービスの調達を迅速かつ透明性高く実現し、行政のデジタル化を加速させる重要な役割を担っています。従来3〜6ヶ月かかっていた調達期間を約2週間まで短縮可能とし、本格運用にまでに、270以上の事業者が参加していました。本記事では、DMPの基本概念から具体的な活用方法まで詳しく解説します。
デジタルマーケットプレイス(DMP)の基本概念

デジタルマーケットプレイス(DMP)は、行政機関がITサービスやソリューションをオンライン上で迅速に調達できるプラットフォームです。デジタル庁が運営するこのシステムは、クラウドソフトウェア(SaaS)とその導入支援サービスを主な対象としています。
DMPの特徴と基本構造
DMPの核となるのは、デジタル庁と事業者間で締結される基本契約です。この契約に基づき、事業者は自社のサービスをプラットフォームに登録し、価格表、サービス仕様、利用規約などの情報を公開します。行政機関はこれらの情報を参照し、ニーズに合った最適なサービスを選択できます。
システムの特徴として、オープンなカタログ形式を採用していることが挙げられます。2024年4月時点で270以上の事業者が参加し、300を超えるソフトウェアが登録されており、行政機関は豊富な選択肢の中から最適なサービスを見つけることが可能です。
従来の調達方式との違い
従来の行政機関におけるIT調達は、総合評価方式が一般的でした。この方式では、調達の都度、複数の事業者から提案と価格を募り、総合的な評価を行って事業者を選定していました。一方、DMPでは事前に登録された情報から直接サービスを選択できるため、調達期間が大幅に短縮されます。従来の3〜6ヶ月程度かかっていた調達期間が、DMPでは約2週間程度まで短縮可能となります。
さらに、従来方式では調達仕様書の作成や提案書の評価など、官民双方に大きな負担がありましたが、DMPではこれらの手続きが大幅に簡素化されます。また、情報がオープンに公開されることで、調達プロセスの透明性も向上します。
DMPがもたらす具体的なメリット

行政機関側の利点
DMPの導入により、行政機関は調達プロセスを大幅に効率化できます。カタログサイト上で必要なサービスを検索・比較することで、最適なソリューションを素早く見つけることが可能になります。また、政策タグ機能により、「デジタル田園都市国家構想」や「マイナンバーカード対応」といった政策目標に沿ったサービスを効率的に探すことができます。
調達手続きの簡素化も大きなメリットです。基本契約がデジタル庁と事業者間で締結済みのため、個別契約の手続きが簡略化されます。さらに、検索結果をエビデンスとして保存できることで、調達の透明性と公平性も確保できます。
IT事業者側の利点
事業者にとって最大のメリットは、行政機関への営業機会の拡大です。DMPに一度登録すれば、全国の行政機関に向けて自社サービスをアピールすることができます。従来のような個別の営業活動が不要となり、営業コストの削減にもつながります。
特に中小企業やスタートアップにとっては、参入障壁が大きく下がることが重要です。実績や知名度に関係なく、優れたサービスがあれば行政機関の目に留まる可能性が高まります。英国のDMPでは、中小企業の参加率が約90%に達しており、日本でも同様の効果が期待されています。
社会全体への波及効果
DMPの導入は、行政のデジタル化を加速させる重要な役割を果たします。調達の効率化により、行政サービスのデジタル化がスピーディーに進み、市民サービスの向上につながります。また、多様な事業者の参入により市場が活性化し、革新的なソリューションの創出も期待できます。
さらに、調達コストの最適化も重要な効果です。英国では、DMPの導入により政府のIT調達額を160億ユーロから90億ユーロまで削減することに成功しています。日本においても、同様のコスト最適化効果が期待されています。
DMPの具体的な利用方法と活用事例

基本的な利用手順
DMPの利用は、行政機関にとってシンプルなプロセスで進められます。まず、カタログサイトで必要なサービスの検索を行います。検索の際は、キーワードだけでなく、政策タグや予算規模、導入実績などの条件で絞り込むことができます。目的に合ったサービスが見つかったら、サービスの詳細情報や価格、利用規約を確認します。
選定したサービスについては、検索結果をエビデンスとして保存し、内部での決裁手続きを進めます。その後、事業者との個別契約を締結することで、サービスの利用を開始できます。従来の調達手続きと比べて、大幅に簡素化されたプロセスとなっています。
効果的な活用のポイント
DMPを効果的に活用するためには、まず明確な要件定義が重要です。必要な機能や予算規模、導入スケジュールなどを事前に整理することで、最適なサービスを効率的に見つけることができます。また、政策タグを活用することで、特定の政策目標に沿ったソリューションを見つけやすくなります。
少額随意契約の場合は、DMPに登録されているサービスの価格情報を参考に、市場価格の把握や予算の適正化を図ることができます。また、複数の行政機関で同じサービスを利用する場合は、スケールメリットを活かした価格交渉も可能です。
実際の導入事例
2023年11月のα版公開以降、様々な行政機関がDMPを活用したIT調達を試験的に実施しています。特に、クラウドサービスの導入においては、従来の調達方式と比べて大幅な時間短縮を実現しています。例えば、文書管理システムや会議予約システムなどの基本的なSaaSの導入では、検討開始から契約締結まで2週間程度で完了するケースも出てきています。
また、自治体におけるDX推進の文脈でも、DMPの活用が進んでいます。デジタル田園都市国家構想に関連するサービスの調達や、マイナンバーカード関連システムの導入など、政策的な要請に基づくIT調達においても、DMPが効果的に活用されています。
DMPの期待される効果と課題

導入スケジュール
デジタル庁は2024年10月31日にDMP正式版Webサイトをリリースしました。2025年度以降は、DMPの全国展開を本格化させる計画です。特に地方自治体向けの専用カテゴリーの追加や、国際標準との相互運用性の確保など、より幅広い利用者のニーズに対応した機能拡充が予定されています。
期待される効果
DMPの本格導入により、行政のデジタル化が大きく加速することが期待されています。特に注目されるのは、中小企業やスタートアップの参入促進効果です。英国の事例では、DMPの導入により政府のIT調達における中小企業の比率が大幅に上昇し、イノベーションの促進とコスト削減の両立を実現しています。
また、行政サービスの質の向上も期待されます。迅速な調達が可能になることで、最新のテクノロジーやサービスを柔軟に導入できるようになり、市民サービスの向上につながります。さらに、調達プロセスの透明性向上により、税金の効率的な使用も促進されます。
今後の発展可能性
将来的には、DMPの機能をさらに拡張し、より包括的なデジタル調達プラットフォームへと進化させることが検討されています。例えば、AIによる最適サービス推奨機能の強化や、導入実績に基づく詳細な評価システムの構築など、より高度な機能の実装が期待されています。
また、民間セクターへの展開も検討課題の一つです。行政機関での成功事例を基に、大企業や中小企業向けの調達プラットフォームとしての活用も視野に入れられています。これにより、日本全体のデジタル調達の効率化と、デジタルトランスフォーメーションの加速が期待されます。
まとめ

デジタルマーケットプレイス(DMP)は、行政機関のIT調達に革新をもたらす画期的なプラットフォームです。従来の複雑な調達プロセスを大幅に簡素化し、調達期間を約2週間まで短縮することで、行政のデジタル化を加速させる原動力となっています。
2024年度秋の正式版リリースまでに、270以上の事業者が参加し、300を超えるソフトウェアが登録されており、着実に実績を積み重ねました。 英国での成功事例が示すように、DMPは中小企業やスタートアップの参入を促進し、行政IT調達の市場を活性化させる効果を持ちます。実際に英国では、DMPの導入により政府のIT調達額を160億ユーロから90億ユーロまで削減することに成功し、中小企業の参加率も約90%まで上昇しています。
日本でも同様の効果が見込まれ、今後は地方自治体向けの専用カテゴリー追加や、AI推奨システムの実装など、さらなる機能拡充が予定されています。また、将来的には民間セクターへの展開も視野に入れられており、日本全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させる重要な基盤として成長していくでしょう。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















