戸籍法改正による自治体の実務対応と外部委託の需要を徹底解説
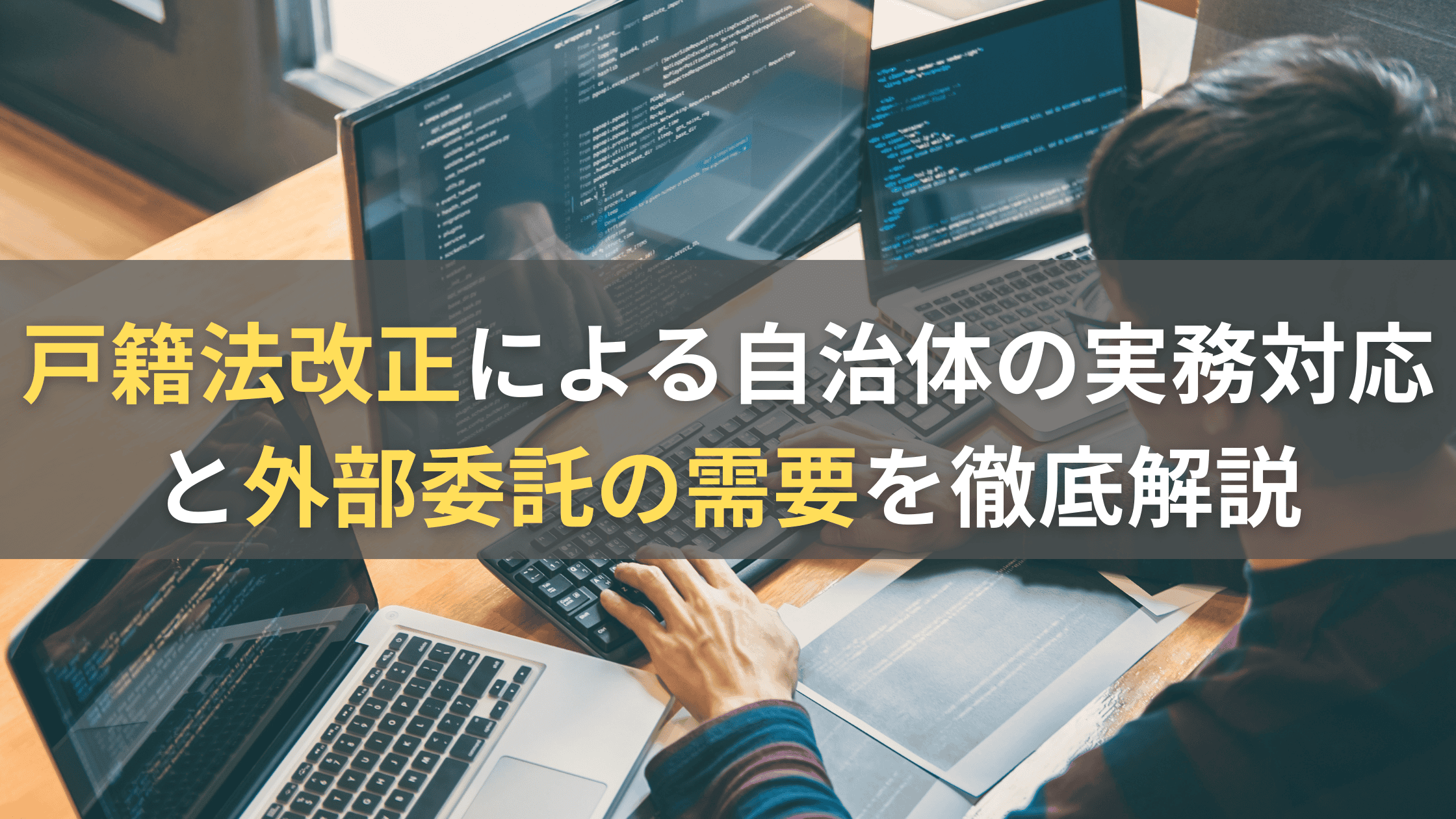
戸籍法改正の概要と影響
- 2024年3月の改正により戸籍謄抄本の添付省略や広域交付制度が導入され、2025年5月にはふりがなの記載が義務化されることで自治体の業務負担が増加する。
自治体の課題と対応策
- ふりがな法制化に伴う住民対応やデータ入力の負担増に対し、高齢者や外国籍住民への対応強化やITツールの活用が求められる。
外部委託の活用と円滑な移行の進め方
- 通知書の発送やデータ入力をBPO事業者に委託し、計画的なスケジュール管理や住民への周知を徹底することで、自治体の業務負担を軽減できる。
2024年3月に施行された戸籍法改正により、行政手続きの効率化が進められる一方、自治体では新たな業務対応に追われています。特に2025年5月から始まるふりがな法制化への準備は、多くの自治体で課題となっています。
本記事では、戸籍法改正に伴う実務対応のポイントと、増加する業務負担を軽減するための外部委託の活用方法について解説します。自治体職員の負担軽減と住民サービスの質の維持を両立させるための具体的な施策をご紹介しますので、戸籍事務や住民対応でお悩みの自治体職員の方々はぜひご参考にしてください。
自治体の外部委託については以下の記事もご参考にしてください。

戸籍法改正の概要と主要な変更点

2024年3月施行の主要改正内容
2024年3月より施行された戸籍法改正は、行政手続きの効率化と住民の利便性向上を主な目的としています。改正の中核となる変更点は、行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略です。
これにより、児童扶養手当の受給手続きや国民年金の被保険者資格確認など、各種社会保障の申請時にマイナンバーを提示するだけで、戸籍謄抄本の添付が不要となりました。これは法務省の新システムと行政機関の情報提供ネットワークシステムの連携により実現されています。
また、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付も不要となり、婚姻届や養子縁組などの手続きが簡素化されました。さらに、本籍地以外での戸籍謄本取得が可能となる「広域交付制度」が導入され、住民は最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できるようになっています。
2025年5月施行のふりがな法制化への対応
2025年5月から施行されるふりがな法制化は、自治体にとって特に重要な改正点となります。この改正により、戸籍の氏名にふりがなの記載が必須となり、新規登録分はもちろん、既存の戸籍についても1年以内にふりがなの登録が必要となります。
ふりがなには「一般的な読み方として認められているもの」という基準が設けられ、いわゆる特殊な読み方には一定の制限が課されることになります。
行政手続きの電子化とデジタル対応
今回の戸籍法改正は、政府が推進する「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の一環として位置づけられています。マイナンバー制度との連携強化や戸籍の電子証明書発行など、行政手続きのデジタル化を促進する内容となっています。これにより、自治体では従来の紙ベースの管理から電子的な処理への移行が進められ、業務効率の向上が期待される一方で、システム対応や職員教育など新たな課題への対応も必要となっています。
戸籍法改正に伴う自治体への影響

戸籍システムの更新と新規データ整備
戸籍法改正により、自治体では既存の戸籍システムの大幅な更新が必要となります。特に2025年5月から始まるふりがな法制化への対応では、従来の戸籍システムにないふりがなデータの新規作成が求められます。一部の自治体では住民基本台帳の電子化の際に便宜的にふりがなを付与していますが、マイナンバーカードの申請開始時に誤ったふりがなが登録されているケースも報告されており、データの精査と修正が必要です。
また、法務省の新システムとの連携に向けたシステム改修や、広域交付制度への対応も必要となります。これらのシステム更新には、適切な予算確保とともに、移行期間中の業務継続計画の策定が不可欠です。
住民対応業務の増加と課題
自治体職員の業務量は、特にふりがな法制化に関連して大幅に増加することが予想されます。まず、全住民に対してふりがな確認通知の発送が必要となり、その後の申請受付や問い合わせ対応など、一連の業務が新たに発生します。ふりがなの届出期間は改正法施行後1年以内と定められているため、この期間中は通常業務に加えて集中的な対応が求められます。
特に注意が必要なのは、高齢者などデジタル機器の操作に不慣れな住民への対応です。マイナポータルでのオンライン申請に加えて、従来型の窓口での申請にも適切に対応できる体制づくりが求められます。また、外国籍住民など、特別な配慮が必要なケースへの対応方針も整備する必要があります。
データ入力と精度管理の重要性
ふりがな登録における最も重要な課題の一つが、データ入力の正確性確保です。市区町村での入力ミスは、法務局の許可を得て訂正する必要があり、場合によっては家庭裁判所での申し立てが必要となるなど、住民に多大な影響を及ぼす可能性があります。そのため、入力時の二重チェック体制の構築や、入力ミスを防止するためのITツールの導入など、精度管理のための仕組みづくりが不可欠です。
また、一般的な読み方として認められる基準に基づくふりがなの審査も必要となり、特殊な読み方が申請された場合の判断基準や対応手順も整備しなければなりません。これらの業務を適切に実施するための職員教育や、業務マニュアルの整備も重要な課題となります。
外部委託活用のメリットと効果的な導入方法

外部委託による業務効率化の実現
戸籍法改正に伴う業務増加に対して、外部委託の活用は効果的な解決策となります。特にBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)事業者への委託は、専門的なノウハウと効率的な業務遂行体制を活用できる点で優れています。
通知書の作成・発送から、申請受付、データ入力まで一連の業務を一括して委託することで、自治体職員は本来の業務に注力できます。
また、BPO事業者の持つコールセンター機能を活用することで、住民からの問い合わせ対応も効率的に行えます。電話やWebを活用した届出促進も可能となり、申請期間内での確実な処理が期待できます。さらに、大量のデータ処理に関する専門的なノウハウを持つ事業者であれば、入力ミスの防止や効率的なチェック体制の構築も可能です。
委託可能な具体的業務内容
戸籍法改正に関連して外部委託が可能な業務は多岐にわたります。まず、ふりがな確認通知書の作成から発送業務があります。大量印刷・発送設備を持つ事業者への委託により、コスト削減と迅速な処理が可能です。
また、申請受付業務では、書面での申請受付からオンライン申請のサポートまで、包括的な対応が可能です。特に、マイナポータルでの申請に不慣れな住民向けのサポートデスク設置なども、委託業務として効果的です。
データ入力業務においては、OCR技術を活用した効率的な処理や、二重チェック体制による精度管理など、専門事業者のノウハウを活用できます。さらに、期限内に申請のない住民への督促業務や、特殊なふりがな申請の際の資料確認業務なども、外部委託の対象となります。
効果的な委託先選定のポイント
委託先の選定にあたっては、セキュリティ対策が最も重要な判断基準となります。個人情報を扱う業務であるため、プライバシーマークやISMS認証の取得は必須条件です。また、自治体業務の委託実績、特に戸籍関連業務の取扱実績も重要な選定基準となります。デジタル化への対応力も重要で、マイナンバー関連システムの対応実績なども確認が必要です。
さらに、業務の継続性や安定性を確保するため、受託事業者の財務状況や業務実施体制も精査する必要があります。特に人員体制については、繁忙期に適切な対応が可能か、また緊急時のバックアップ体制が整っているかなどを確認することが重要です。委託後のモニタリング体制や、トラブル発生時の対応体制についても、事前に明確な取り決めを行うことが推奨されます。
円滑な移行のための準備と対策

実施スケジュールの策定と管理
2025年5月のふりがな法制化に向けて、計画的な準備が不可欠です。まず、システム更新やデータ整備から、住民への通知発送、申請受付開始までの詳細なスケジュールを策定する必要があります。特に重要なのは、システム改修期間の確保です。法務省の新システムとの連携テストや、既存データの移行作業には十分な時間を見込む必要があります。
また、外部委託を活用する場合は、委託先の選定から契約締結、業務引継ぎまでの期間も考慮が必要です。特に、年度替わりの繁忙期と重なることを避けるため、2024年度内での準備完了を目指すことが推奨されます。マイルストーンを設定し、進捗管理を徹底することで、スムーズな移行を実現できます。
効果的な体制整備の方法
戸籍法改正への対応には、複数の部署が関係するため、横断的なプロジェクトチームの設置が有効です。システム担当、戸籍担当、住民対応担当など、各部門からメンバーを選出し、定期的な進捗確認と課題解決を行う体制を構築します。特に、外部委託を活用する場合は、委託事業者との連携窓口を一本化し、明確な指示系統を確立することが重要です。
また、職員向けの研修体制も整備が必要です。新システムの操作方法はもちろん、ふりがな登録における判断基準や、住民対応の留意点など、実務に即した内容での研修を計画的に実施します。特に窓口担当者には、高齢者や外国人住民への対応など、きめ細かな研修が求められます。
効果的な住民周知の実施方法
住民への周知は、混乱を防ぎ、スムーズな移行を実現するための重要な要素です。広報誌やホームページでの告知に加え、自治体のSNSなど多様な媒体を活用した情報発信が効果的です。特に、申請期限や必要書類、オンライン申請の方法など、具体的な手続き方法については、わかりやすい説明資料の作成が重要です。
また、高齢者や外国人など、情報が届きにくい層への配慮も必要です。自治会や町内会との連携、多言語での案内作成、福祉施設への説明会実施など、きめ細かな周知活動を計画します。特に、マイナポータルでのオンライン申請については、操作方法の説明会や相談窓口の設置など、具体的なサポート体制の整備が求められます。各種問い合わせに対する想定問答集(FAQ)の作成も、効率的な対応には有効です。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















