特命随意契約とは?意味・条件・実務ポイントをわかりやすく解説
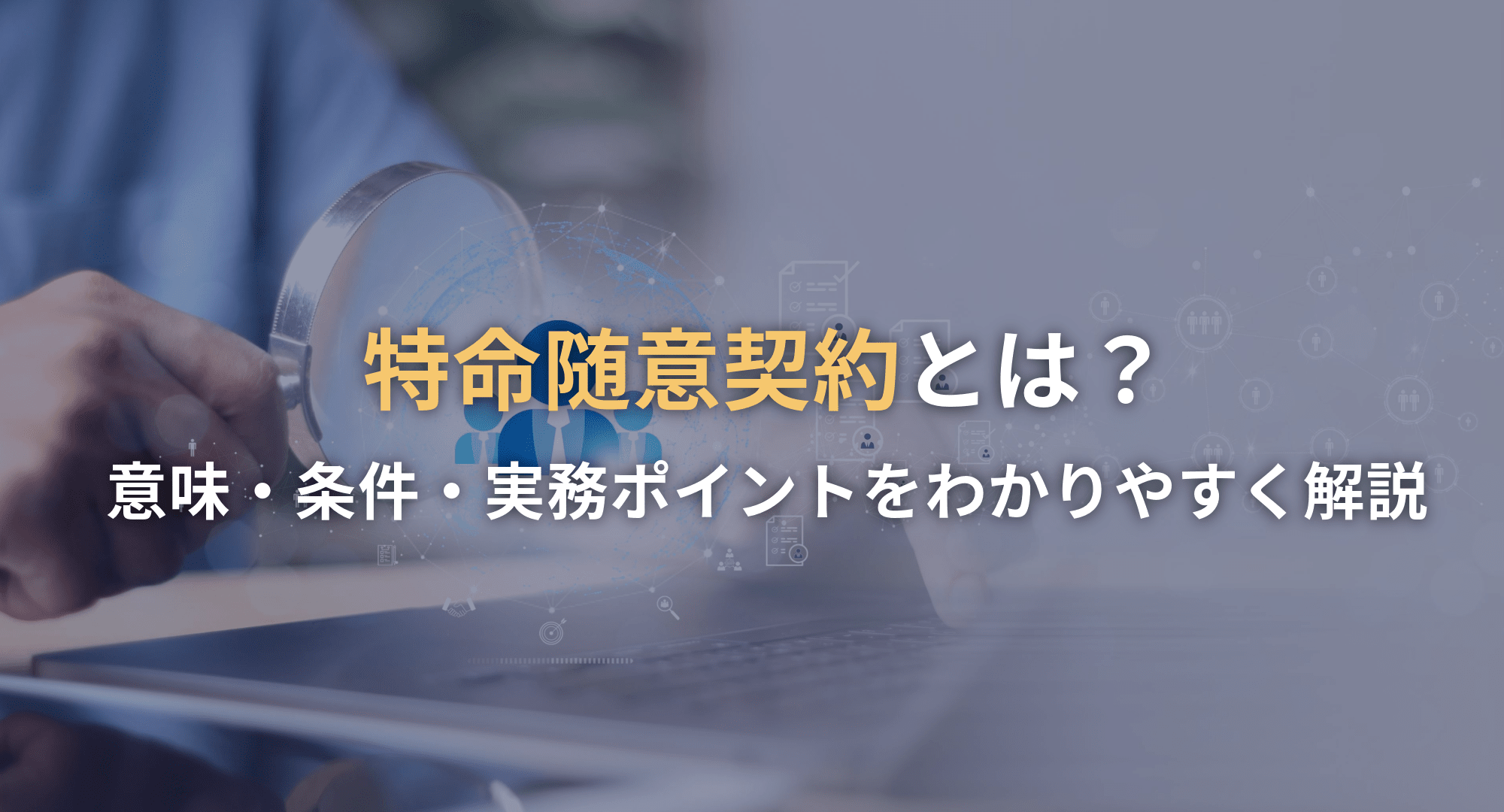
■特命随意契約は緊急時や専門性が高い案件で使われる
災害対応、特殊技術が必要な工事、特許製品の購入など、通常の入札が難しい場面で使われる。
■「随意契約理由書」の作成が必須
なぜ入札しないのか、なぜその業者を選んだのかなど、法的根拠に基づいた文書で明確にする必要がある。
■透明性・記録・監査対応が重要
不正防止のため、契約理由・金額の検討性・業者選定の根拠を記録し、情報公開や費用に備えることが求められる。
公共事業や物品調達において、通常は競争入札が原則とされていますが、特定の条件を満たす場合には「特命随意契約」という方法が認められています。この契約方式は、競争なしに特定の業者と直接契約を結ぶものであり、行政機関にとっても事業者にとっても重要な意味を持ちます。
しかし、特命随意契約は例外的な契約方式であるため、その法的根拠や適用条件、実務上の注意点を正しく理解していなければ、後々問題が生じる可能性があります。特に、透明性の確保や公平性の担保は常に重要な課題となっています。
本記事では、特命随意契約の基本概念から法的根拠、そして実務担当者が押さえるべきポイントまで解説します。災害対応や専門技術が必要なケース、理由書の作成方法など、具体的な事例も交えながら、特命随意契約を正しく理解し、適切に運用するために役立つ情報をご紹介します。
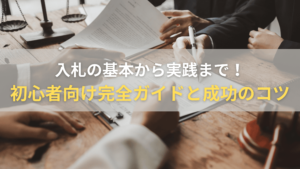
特命随意契約とは

特命随意契約の基本的な意味と仕組み
特命随意契約とは、国や地方自治体が公共工事や物品調達などを行う際に、競争入札を行わずに特定の業者を指名して直接契約を締結する方式です。随意契約には「特命随意契約」「少額随意契約」「不落随意契約」という3つの種類がありますが、単に「随意契約」と言う場合は、多くの場合「特命随意契約」を指します。
特命随意契約の基本的な仕組みは以下の通りです
1. 発注者側の判断:発注者(国や自治体など)が、ある条件に基づいて競争入札ではなく特命随意契約を選択します。
2. 業者の特定:発注者は特定の業者を選定します。この選定には合理的な理由が必要です。
3. 随意契約理由書の作成:発注者は、なぜ競争入札ではなく随意契約を選択したのか、なぜその特定の業者を選んだのかという理由を文書化します。
4. 直接交渉と契約締結:選定された業者と直接交渉を行い、契約内容を決定します。
5. 契約情報の公開:透明性を確保するため、多くの場合、契約情報は後日公開されます。
特命随意契約は、法令に定められた特定の条件を満たす場合にのみ認められる例外的な契約方式であり、公共調達の原則である競争性、透明性、公平性を部分的に制限するものです。そのため、その運用には十分な注意が必要とされています。
一般競争入札との違い
特命随意契約と一般競争入札は、公共調達における主要な契約方式ですが、その性質や手続きには大きな違いがあります。
| 比較項目 | 一般競争入札 | 特命随意契約 |
|---|---|---|
| 基本原則 | 競争性、公開性、透明性を重視 | 特定条件下での例外的措置 |
| 参加者 | 参加資格を満たす不特定多数の業者 | 発注者が特定した1社のみ |
| 手続きの流れ | 公告→入札→開札→落札者決定→契約 | 業者選定→理由書作成→直接交渉→契約 |
| 契約相手の決定方法 | 最低価格(または総合評価)による競争 | 特定の理由による指名 |
| 手続きの時間 | 比較的長期間を要する | 比較的短期間で完了可能 |
| 透明性 | 高い(公開の場での入札) | 相対的に低い(事後的な情報公開が重要) |
| 適した状況 | 標準的な調達、十分な準備期間がある場合 | 緊急時や特殊技術が必要な場合など |
一般競争入札は「公正な競争による最適な調達」を目指すのに対し、特命随意契約は「特定の条件下での合理的な調達」を可能にする手段と言えます。どちらが適切かは、調達の内容や状況によって判断する必要があります。
特命随意契約が使われる主なケース(災害対応・専門技術など)
特命随意契約は、以下のようなケースで主に活用されています。
1. 緊急対応が必要な場合
災害発生時の復旧工事や感染症対策など、緊急性が高く、通常の入札手続きを行う時間的余裕がない場合に用いられます。例えば、大規模地震後のインフラ復旧工事や、新型コロナウイルス対応のための医療物資調達などが該当します。
2. 特殊な技術や専門知識が必要な場合
高度な専門技術や特殊な知識を持つ業者が限られている場合、競争入札が実質的に機能しないケースがあります。例えば、特定のシステム開発の継続案件や、特殊な文化財の修復工事などが挙げられます。
3. 特許や著作権が関与する場合
調達する製品やサービスが特許権や著作権で保護されており、特定の業者しか提供できない場合に適用されます。既存システムの保守・拡張や、特定のソフトウェアライセンスの追加購入などがこれに該当します。
4. 互換性や一貫性の確保が必要な場合
既存の設備や仕組みとの互換性や一貫性を確保するために、特定の業者と契約する必要がある場合です。例えば、既存システムの拡張や、特定メーカーの設備の追加導入などが挙げられます。
5. 競争入札を行っても応札者がいない場合
競争入札を実施したにもかかわらず、応札者がいない、または条件を満たす応札がなかった場合に、随意契約に移行するケースがあります。これは厳密には「不落随意契約」に分類されますが、結果として特定業者との随意契約となります。
これらのケースにおいて特命随意契約を選択する際は、その理由を明確に説明できることが重要です。また、可能な限り複数の選択肢を検討し、透明性の確保に努めることが求められます。

特命随意契約の法的根拠と条件
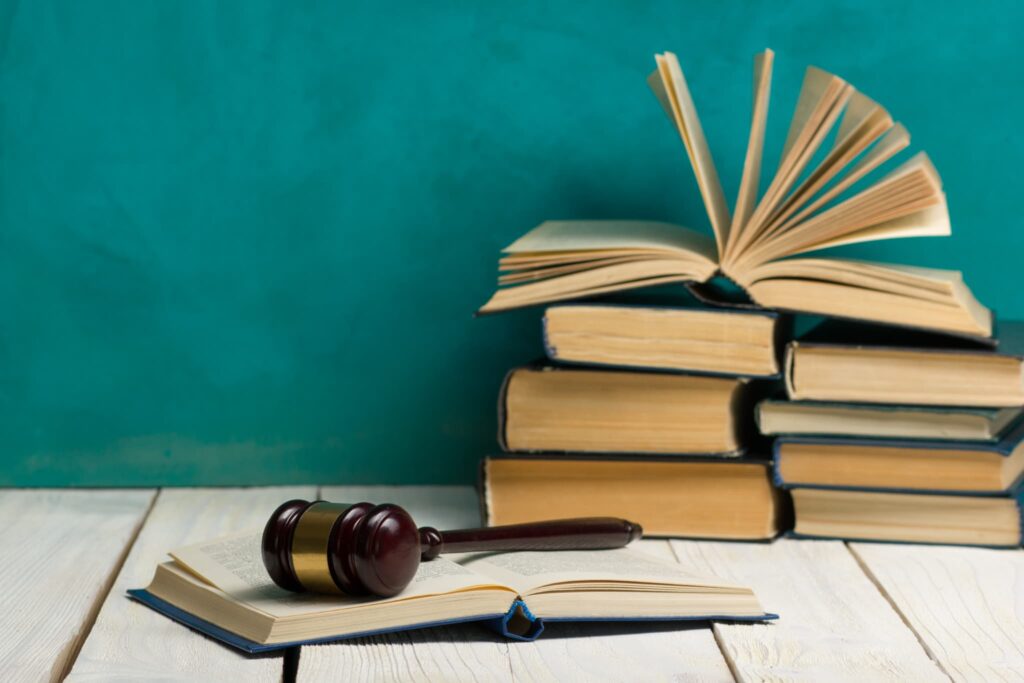
会計法や予算決算及び会計令における根拠
特命随意契約の法的根拠は、国の機関が契約を行う場合と地方自治体が契約を行う場合で、それぞれ異なる法令に基づいています。
国の機関が契約を行う場合の法的根拠
国の機関が特命随意契約を行う場合、主に以下の法令が根拠となります:
1. 会計法第29条の3第4項
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。」
2. 予算決算及び会計令(予決令)第99条
この政令では、会計法に基づき随意契約が認められる詳細な条件が規定されています。具体的には以下のような場合に随意契約が認められます:
- 国の行為を秘密にする必要がある場合
- 予定価格が一定金額以下の場合(工事は250万円以下、物品購入は160万円以下など)
- 特定の施設から物品を買い入れる場合
- 特定の販売業者以外では販売していない物品を買い入れる場合
- 緊急の必要により競争に付することができない場合
- 競争に付することが不利と認められる場合
地方自治体が契約を行う場合の法的根拠
地方自治体が特命随意契約を行う場合は、以下の法令が根拠となります:
1. 地方自治法第234条第2項
「前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によることができる。」
2. 地方自治法施行令第167条の2第1項
この施行令では、地方自治法に基づき随意契約が認められる詳細な条件が規定されています。主な条件として:
- 予定価格が一定金額以下の場合(都道府県・指定都市の工事は250万円以下、市町村の工事は130万円以下など)
- その性質又は目的が競争入札に適しない契約をする場合
- 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
- 競争入札に付することが不利と認められる場合
- 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある場合
- 競争入札に付しても入札者がない場合または再度の入札に付しても落札者がない場合
これらの法的根拠に基づき、国や地方自治体は例外的に特命随意契約を行うことができますが、いずれの場合も「例外的な措置」であることを認識し、適正な運用が求められます。
特命随意契約が認められる主な条件(緊急性・専門性・独占権など)
法的根拠を踏まえ、特命随意契約が具体的に認められる主な条件を詳しく見ていきましょう。
1. 契約の性質や目的による条件
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」とは、競争入札を実施しても実質的な競争が成立しないか、または競争に付すること自体が不適当である場合を指します。具体的には、以下のような場合があります。
- 特殊な技術や設備を要する場合:特定の技術や設備を持つ業者が限られている場合
- 特許権等の排他的権利を有する場合:特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権により、特定の者しか契約の相手方になり得ない場合
- 互換性の確保が必要な場合:既存のシステムや設備との互換性を確保するために、特定の業者と契約する必要がある場合
- 信頼関係や秘密保持が特に重要な場合:契約の性質上、特定の相手方との信頼関係や秘密保持が不可欠な場合
2. 緊急性による条件
「緊急の必要により競争に付することができない場合」とは、競争入札の手続きを行っている時間的余裕がなく、直ちに契約を締結する必要がある場合を指します。
- 災害復旧工事:地震、台風、洪水などの自然災害後の緊急復旧工事
- 公衆衛生上の緊急対応:感染症の流行時における医療物資の調達など
- システム障害の緊急対応:重要なシステムの障害による業務停止を回避するための緊急修理
- 安全確保のための緊急措置:公共施設等の危険箇所を緊急に修繕する必要がある場合
3. 競争入札が不利となる条件
「競争に付することが不利と認められる場合」とは、競争入札を行うことで、かえって経済的・時間的・質的な面で不利益が生じる場合を指します。
- 既契約の追加・補完工事:すでに契約している工事や業務の追加・補完が必要になった場合
- 発注準備に著しい費用がかかる場合:競争入札のための仕様書作成等に著しい費用や時間がかかる場合
- 特殊な実績や経験が必要な場合:特殊な実績や経験を持つ業者が限られており、競争の実益がない場合
4. その他の条件
上記以外にも、以下のような場合に特命随意契約が認められることがあります。
- 不落随意契約:競争入札を実施したが、入札者がいない、または落札者がいない場合
- 再度の入札が不調:再度の入札を行っても落札者が決まらない場合
- 著しく有利な条件での契約が可能:特定の者と契約することで、時価に比して著しく有利な条件で契約できる場合
これらの条件のいずれかに該当する場合でも、その適用は厳格に判断され、随意契約理由書等で明確に説明できることが求められます。また、多くの自治体では、独自のガイドラインを設けて、さらに詳細な条件や運用基準を定めています。
特命随意契約のメリット・デメリット
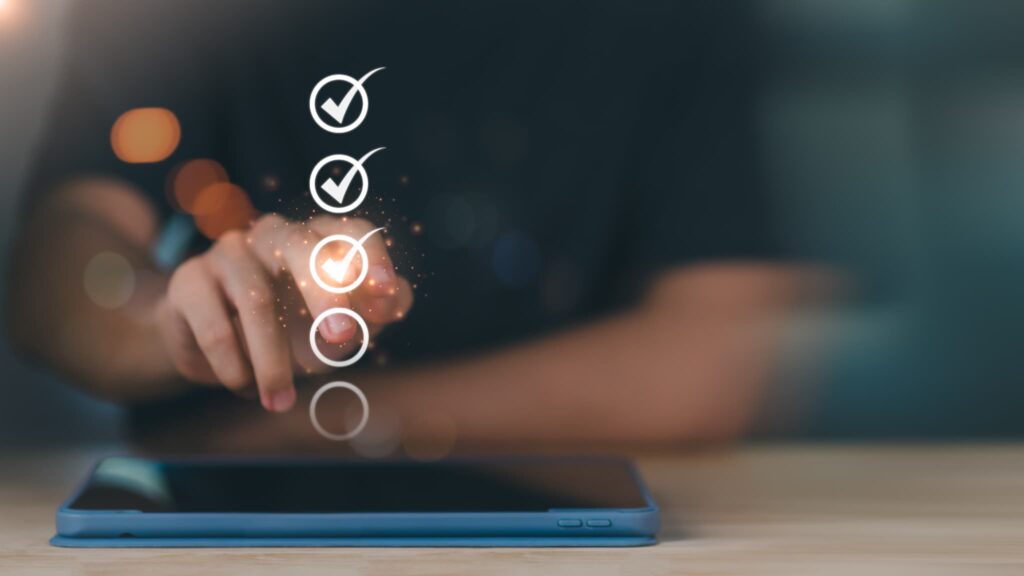
発注側(行政)と受注側(事業者)のメリット
特命随意契約は、発注側と受注側の双方にいくつかのメリットをもたらします。それぞれの立場からのメリットを詳しく見ていきましょう。
発注側(行政機関)のメリット
1. 迅速な契約締結が可能
競争入札のように公告期間や入札手続きを必要としないため、緊急性の高い案件に対して素早く対応できます。災害復旧や感染症対策など、時間的猶予がない状況で特に重要なメリットとなります。
2. 専門性・特殊性を重視した選定
価格だけでなく、業者の専門性、実績、技術力などを総合的に考慮して契約相手を選定できます。特に高度な専門知識や特殊な技術が必要なプロジェクトでは、最適な業者を柔軟に選べることが大きな利点です。
3. 既存システムとの互換性確保
既存のシステムや設備の拡張・更新を行う場合、同一業者と契約することで互換性の問題を回避できます。これにより、安定したサービス提供や運用が可能になります。
4. 事務手続きの簡素化
入札公告、入札説明書の作成、入札会の開催など、競争入札に伴う煩雑な手続きが不要となり、事務負担が軽減されます。特に小規模な案件では、調達コストの削減につながることもあります。
受注側(事業者)のメリット
1. 安定した受注機会
特殊な技術やノウハウを持つ事業者にとって、その強みを活かした受注機会が得られます。特に、特許や独自技術を持つ企業は、競争なしに契約を獲得できる可能性があります。
2. 入札コストの削減
競争入札への参加には、入札書類の準備や入札会への出席など、相応のコストと労力がかかります。特命随意契約ではこれらの負担が軽減されます。
3. 柔軟な契約条件の交渉
発注者と直接交渉できるため、プロジェクトの特性に応じた柔軟な契約条件を設定できる場合があります。これにより、より効果的・効率的な業務遂行が可能になることもあります。
4. 長期的な関係構築
一度特命随意契約で信頼関係を築くと、関連する後続業務や保守・運用業務などを継続的に受注できる可能性が高まります。これにより、安定した事業計画を立てやすくなります。
これらのメリットは、特命随意契約が適切に活用される場合に発揮されます。しかし、不適切な運用は様々な問題を引き起こす可能性もあるため、次に説明するデメリットや注意点も十分に理解しておく必要があります。
注意すべきリスクと透明性の確保
特命随意契約には多くのメリットがある一方で、その特性ゆえに注意すべきリスクも存在します。これらのリスクを認識し、適切な対策を講じることが重要です。
1. 特命随意契約の主なリスク
① 透明性・公平性の欠如
競争入札と異なり、契約プロセスが公開されないため、なぜその業者が選ばれたのか、契約金額は適正かといった点が不透明になりがちです。これにより、不正や癒着の疑いを招く可能性があります。
② 価格の適正性の問題
競争原理が働かないため、契約金額が市場価格より高くなる傾向があります。これは税金の効率的な使用という観点から問題となりえます。
③ 特定業者への依存
同じ業者と継続的に契約を結ぶことで、その業者への依存度が高まり、将来的に競争環境が損なわれる可能性があります。また、業者の変更が困難になるというリスクも生じます。
④ 監査や情報公開請求への対応
特命随意契約は例外的な契約方式であるため、監査や情報公開請求の際に厳しく審査される可能性が高く、十分な説明責任が果たせない場合は問題となります。
2. 透明性確保のための対策
これらのリスクを軽減し、特命随意契約の透明性を確保するためには、以下のような対策が重要です。
① 随意契約理由の明確化と文書化
特命随意契約を選択した理由と、特定の業者を選定した理由を明確に文書化することが必須です。具体的かつ合理的な理由を「随意契約理由書」などの形で残すことで、後日の説明責任に備えます。
② 価格の妥当性検証
市場調査や過去の類似契約との比較など、複数の方法で契約金額の妥当性を検証し、その過程を記録に残すことが重要です。可能であれば、複数の見積もりを取得することも有効です。
③ 契約情報の公開
契約の相手方、契約金額、契約内容、随意契約理由などの情報を積極的に公開することで、透明性を高めます。多くの自治体では、一定金額以上の随意契約について情報公開を義務付けています。
④ 内部チェック体制の強化
特命随意契約の判断を複数の担当者や部門で検証する体制を整え、恣意的な判断を防止します。特に高額な契約については、審査委員会などによる事前承認プロセスを設けることも効果的です。
⑤ ガイドラインの整備と遵守
特命随意契約の運用に関する明確なガイドラインを整備し、それに基づいた運用を徹底することで、一貫性と透明性を確保します。多くの自治体では独自のガイドラインを策定しています。
これらの対策を適切に実施することで、特命随意契約のメリットを活かしつつ、透明性と公平性を確保することが可能になります。特に公金を使用する公共調達においては、説明責任を果たすための取り組みが不可欠です。
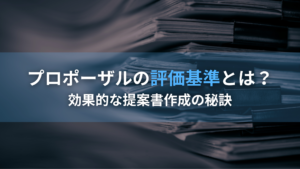
実務で押さえておきたいポイント

随意契約理由書作成の基本
特命随意契約を行う際に最も重要な書類の一つが「随意契約理由書」です。この書類は、なぜ競争入札ではなく随意契約を選択したのか、そしてなぜその特定の業者を選定したのかを明確に説明するものです。適切な理由書の作成は、契約の適法性を担保し、後日の監査や情報公開請求にも対応できるよう準備するために不可欠です。
随意契約理由書の基本構成
随意契約理由書の名称や様式は組織によって異なりますが、一般的に以下の項目を含むことが多いです。
- 契約の概要:件名、契約内容、予定金額、契約期間など
- 契約の相手方:業者名、所在地、代表者名
- 随意契約の法的根拠:適用する法令の条項(会計法第29条の3第4項、地方自治法施行令第167条の2第1項第○号など)
- 随意契約とする理由:なぜ競争入札ではなく随意契約を選択したのか
- 契約の相手方を選定した理由:なぜその特定の業者を選んだのか
- 契約金額の妥当性:金額が適正であることの説明
- 添付資料:必要に応じて性能比較表、見積書、カタログなど
効果的な理由書作成のポイント
随意契約理由書を作成する際の重要なポイントは以下の通りです。
1. 具体的かつ客観的な記述
「〇〇のため」「〇〇が必要だから」といった抽象的な表現ではなく、具体的な事実や数値に基づいた客観的な記述を心がけましょう。第三者が読んでも納得できる内容であることが重要です。
2. 法的根拠との整合性
適用する法令の条項と、記載する理由の内容が整合していることを確認しましょう。例えば「緊急の必要」を根拠とする場合は、本当に緊急性があったことを具体的に説明する必要があります。
3. 専門用語の適切な使用
専門的な内容を説明する場合でも、可能な限り分かりやすい言葉を使用し、必要に応じて専門用語の説明を加えることで、非専門家でも理解できるよう配慮しましょう。
4. 比較検討の過程を記述
可能であれば、他の選択肢(他の業者や他の調達方法)を検討したことを示し、なぜそれらではなくこの方法・この業者を選んだのかの比較検討過程を記載すると説得力が増します。
5. 実績や専門性の具体的な記述
「実績がある」「専門性が高い」といった抽象的な表現ではなく、「過去3年間で類似の開発案件を○件受注し、全て期限内に完了している」など、具体的な実績や専門性を記述しましょう。
随意契約理由書の種類と特徴
随意契約理由書には、主に以下のような種類があります。
1. 機種選定理由書
特定の機械や設備、システムなどを選定する理由を説明する書類です。主に以下の項目を記載します:
- 使用目的:なぜその機器が必要なのか
- 求められる性能や条件:具体的にどのような性能が必要か
- 選定理由:なぜその機種を選んだのか(性能比較表などを添付)
2. 業者選定理由書
特定の業者を選定する理由を説明する書類です。主に以下の項目を記載します:
- 業者の専門性や実績:なぜその業者が適しているのか
- 独占性や排他性:その業者しか提供できない理由(特許、独占販売権など)
- 継続性や互換性:既存のシステムや業務との関連性
3. 性能比較表
複数の機種や製品を比較検討した結果を示す表です。必要とする性能を項目として列挙し、各機種がその性能を満たしているかどうかを一覧にします。選定した機種が最も要件に合致していることを客観的に示すために有効です。
随意契約理由書の作成は、単なる形式的な手続きではなく、公共調達の透明性と説明責任を確保するための重要な手段です。丁寧かつ詳細な理由書の作成を心がけましょう。
監査や情報公開に備えた記録と対応
特命随意契約は、その性質上、競争性や透明性の面で疑問を持たれやすく、監査や情報公開請求の対象となる可能性が高いものです。そのため、適切な記録の保持と監査対応の準備が欠かせません。
1. 適切な記録の保持
特命随意契約に関連して、以下のような記録を適切に保持しましょう:
① 決裁文書一式
契約方式の決定から契約締結までの決裁文書一式を保管します。特に、随意契約を選択した理由や契約の相手方を選定した理由が明確に記載されていることが重要です。
② 見積書・価格検討資料
契約金額の妥当性を示す資料として、見積書だけでなく、市場調査結果や過去の類似契約との比較資料なども保管します。可能であれば、複数業者からの見積もりを取得しておくことも有効です。
③ 業者の選定に関する資料
業者の技術力、実績、専門性などを示す資料(パンフレット、過去の実績一覧、特許証の写しなど)を保管します。業者が唯一の供給者である場合は、そのことを証明する資料も重要です。
④ 打合せ記録
業者との打合せ内容を記録した議事録などを作成・保管します。契約条件の交渉過程や技術的な確認事項などを記録することで、後日の説明に役立ちます。
⑤ 成果物や履行確認資料
契約の履行状況や成果を確認できる資料(成果物、検査調書、写真など)を保管します。契約金額に見合った成果が得られたことを示す証拠となります。
2. 監査対応の準備
監査に備えた準備として、以下のポイントを押さえておきましょう:
① 法令やガイドラインの理解
随意契約に関する法令や自組織のガイドラインを十分に理解し、それに則った運用を行っていることを説明できるようにしておきます。
② 組織的な決定プロセスの確保
特命随意契約の判断が個人の恣意的な判断ではなく、組織的な検討と決定に基づいていることを示せるよう、適切な決裁手続きを経ていることが重要です。
③ 説明の一貫性確保
随意契約理由書の内容と、監査時の説明内容に齟齬が生じないよう、関係者間で認識を共有しておきます。理由書の内容を十分に理解し、補足説明ができるよう準備しておくことが大切です。
3. 情報公開請求への対応
特命随意契約に関する情報公開請求に備えて、以下の点に注意しましょう:
① 公開可能な情報と非公開情報の区分
情報公開法や各自治体の条例に基づき、どの情報が公開可能でどの情報が非公開となるのかを事前に整理しておきます。特に、企業の営業秘密や個人情報については、慎重な取り扱いが必要です。
② 文書の整理と索引作成
関連文書を体系的に整理し、必要に応じて索引を作成しておくことで、情報公開請求があった際に迅速かつ適切に対応できます。
③ 非公開部分のマスキング準備
公開文書中に非公開情報が含まれる場合のマスキング(黒塗り)の方法や範囲について、事前に検討しておくことも有効です。
監査や情報公開請求は、ネガティブなものとして捉えるのではなく、公共調達の透明性と説明責任を確保するための重要な仕組みとして前向きに対応することが大切です。日頃から適切な記録を保持し、説明責任を果たせる体制を整えておきましょう。
事例で学ぶ特命随意契約

災害復旧やデジタル分野での例
特命随意契約は様々な分野で活用されていますが、特に災害復旧とデジタル・IT分野では特徴的な事例が見られます。具体的な事例を通じて、特命随意契約の実務的な適用を理解しましょう。
災害復旧における特命随意契約の事例
事例1:大規模地震後の緊急道路復旧工事
契約概要:
大規模地震により市内の主要道路が損壊し、緊急車両の通行が困難になった状況で、迅速な復旧工事を特命随意契約で発注。
随意契約とした理由:
• 被災者救助や物資輸送のため、道路の早急な復旧が必要
• 通常の入札手続きでは復旧に数週間を要するため、緊急性の観点から随意契約を選択
• 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき)を適用
業者選定理由:
• 当該地域での道路工事の実績が豊富
• 被災地近隣に資材や重機を保有しており、即時動員が可能
• 過去の災害復旧工事での実績と信頼性
ポイント:
この事例では「緊急性」が特命随意契約の最大の根拠となっています。特に人命救助や二次災害防止に関わる場合、迅速な対応が最優先されます。ただし、緊急性を理由とする場合でも、業者選定には一定の合理性が求められ、単に「近くにいたから」というだけでは不十分です。
事例2:台風被害後の排水ポンプ緊急修繕
契約概要:
台風による大雨で市の主要排水ポンプが故障。浸水被害拡大防止のため、製造メーカーに緊急修繕を特命随意契約で発注。
随意契約とした理由:
• 排水機能の停止により周辺地域の浸水被害拡大のおそれがあり、緊急復旧が必要
• 特殊な設備であり、製造メーカー以外では部品調達や適切な修理が困難
業者選定理由:
• 当該ポンプの製造メーカーであり、構造を熟知している
• 専用部品の即時調達が可能
• 24時間対応の緊急修理体制を有している
ポイント:
この事例では「緊急性」と「専門性」の両面から特命随意契約の妥当性が説明されています。特に製造メーカーでなければ対応できない専門性の高い修理であることが重要なポイントです。
デジタル分野における特命随意契約の事例
事例3:基幹システムの保守・運用契約
契約概要:
自治体の住民情報システムの保守・運用業務を、システム開発業者と特命随意契約で締結。
随意契約とした理由:
• システムの安定稼働のためには、開発業者による専門的知識を活かした保守・運用が不可欠
• システムのソースコードや詳細設計書は開発業者のみが保有
• 他社に切り替えた場合、引継ぎや習熟に時間を要し、安定稼働に支障が生じるリスクがある
業者選定理由:
• システムの開発業者であり、プログラム構造を熟知している
• 過去のトラブル対応実績があり、迅速な障害対応が可能
• システム固有の技術情報を保有している唯一の業者である
ポイント:
この事例では「競争を許さない」という観点から特命随意契約の妥当性が説明されています。特に知的財産権や専門知識の排他性が重要な根拠となっています。ただし、こうした状況を避けるために、システム調達時にソースコードの権利帰属や保守・運用の競争性確保について検討しておくことも重要です。
事例4:既存システムの緊急セキュリティ対応
契約概要:
自治体のネットワークシステムに重大なセキュリティ脆弱性が発見され、現行システム保守業者に緊急対応を特命随意契約で発注。
随意契約とした理由:
• 個人情報漏洩や行政サービス停止のリスクがあり、即時対応が必要
• システム構成の複雑性から、現行保守業者以外では迅速な対応が困難
• 通常の入札手続きでは対応が間に合わない緊急性がある
業者選定理由:
• 現行システムの構成と設定を熟知している
• 既存保守契約により、システムへのアクセス権限と責任範囲が明確
• 24時間365日の緊急対応体制を有している
ポイント:
この事例では「緊急性」と「専門性」の両面から特命随意契約の妥当性が説明されています。情報セキュリティ上の脅威は対応の遅れが大きなリスクとなるため、迅速性が重視されます。
よくあるケースと実務上の工夫
特命随意契約はさまざまな状況で利用されますが、いくつかの典型的なケースがあります。ここでは、よくあるケースとその実務上の工夫について解説します。
ケース①:知的財産権が関係する契約(特許・著作権など)
状況例
- 特許技術を使った製品の購入
- ソフトウェアライセンス契約など、提供元が制限される場合
実務上の工夫
- 権利の証明:特許証などのコピーを取得し、対象製品との関連性を明確にする
- 代替手段の検討記録:他の手段を調査した記録を残すことで「競争性がない理由」を強調
- 価格交渉と妥当性検証:比較への販売実績や過去価格を調べ、値引き交渉と記録を実施
ケース②:既存システムの拡張・改修
状況例
- 導入済みシステムのバージョンアップや、法改正への対応
- 元の開発ベンダー以外では対応が難しい場合
実務上の工夫
- 互換性・一体性の明確化:システムの互換性・専用性を明確にし、競合では対応できない根拠を示唆
- 分離調達の検討:システム全体ではなく、分離して調達可能な部分がないか検討する
- 将来的な改善策の検討:将来的に競争性を確保するための方策(仕様の標準化、ソースコードの権利帰属明確化など)を検討し、次回の調達に向けた取り組みを記録
③:緊急対応が求められる場合(災害・事故など)
状況例
- 自然災害による設備破損、ライフラインのトラブルなど、時間に余裕のない状況
実務上の工夫
- 緊急性の証明:被害写真や報告書を添付し、「いつまでも対応が必要か」を明確化
- 必要最低限の範囲設定絞っ契約:恒久対策と分けて、緊急対応に絞った契約範囲とする
- 選定過程の透明化:業者選定の経緯や合理的な理由を記録し、監査や説明責任に備える
実務全般に共通する工夫ポイント
最後に、ケース命特別契約を進めていくために国際的に意識したい共通ポイントをご紹介します。
①情報収集と準備の徹底
- 他自治体の契約事例を調べて参考にする
- 市場調査を実施、対応可能業者の所在を確認
- 専門家の意見を取り入れ、判断の客観性を確保
②透明性を高める工夫
- 随意契約予定の事前公表(可能であれば)
- 第三者にも納得される 詳細な理由書作成
- 複数配備や外部委員による事前審査の実施(特に高額契約時)
③ 契約後の振り返り
- 履行状況を確認し、品質と費用の評価性を検証
- 事後評価で改善点を洗い出し、ナレッジとして組織に共有
特命随意契約は「例外的な契約手法」だからこそ、慎重な判断と記録が求められます。事例ごとの工夫と全体に共通する実務対応を冷静に、透明性と適正性を確保することが重要です。
実務担当者のための簡易チェックリスト

特命随意契約を検討・実施する際に、実務担当者がチェックすべきポイントを簡易なリスト形式でまとめました。このチェックリストを活用することで、適切な特命随意契約の実施と、後々の問題発生防止に役立てることができます。
特命随意契約前のチェックポイント
- 法的根拠の確認
- 適用する法令・条項を明確にしていますか?
- その法令・条項の要件を満たしていますか?
- 自組織のガイドラインに準拠していますか?
- 随意契約の必要性
- 競争入札ではなく随意契約とする明確な理由がありますか?
- その理由は客観的な事実や証拠に基づいていますか?
- 緊急性を理由とする場合、本当に緊急対応が必要ですか?
- 業者選定の妥当性
- 特定の業者を選定する合理的な理由がありますか?
- 他の業者では対応できない理由が明確ですか?
- 可能な限り複数の業者を検討しましたか?
- 契約金額の妥当性
- 契約金額の積算根拠は明確ですか?
- 過去の類似契約や市場価格と比較して適正ですか?
- 可能な限り値引き交渉を行いましたか?
- 組織的な意思決定
- 個人の判断ではなく、組織的な検討と決定を経ていますか?
- 適切な決裁手続きを踏んでいますか?
- 必要に応じて専門家の意見を聴取していますか?
随意契約理由書作成のチェックポイント
- 基本情報の記載
- 契約件名、契約内容、予定金額、契約期間は明記されていますか?
- 契約の相手方(業者名、所在地等)は明記されていますか?
- 法的根拠(適用条項)は明記されていますか?
- 随意契約理由の説明
- なぜ競争入札ではなく随意契約を選択したのか、具体的に説明していますか?
- 抽象的な表現ではなく、具体的な事実や数値に基づいた説明になっていますか?
- 適用条項の要件に沿った説明になっていますか?
- 業者選定理由の説明
- なぜその特定の業者を選んだのか、具体的に説明していますか?
- 業者の専門性、実績、独自性などを具体的に説明していますか?
- 他の業者では対応できない理由を明確に説明していますか?
- 添付資料の確認
- 理由を裏付ける資料(カタログ、性能比較表、特許証の写しなど)を添付していますか?
- 契約金額の妥当性を示す資料(見積書、過去の実績など)を添付していますか?
- 必要に応じて専門家の意見書などを添付していますか?
契約締結後のチェックポイント
- 記録の保持
- 決裁文書一式を適切に保管していますか?
- 業者との打合せ記録を作成・保管していますか?
- 契約の履行状況や成果を確認できる資料を保管していますか?
- 契約の履行確認
- 契約内容に沿った履行がなされているか確認していますか?
- 成果物の品質や数量は契約通りですか?
- 履行確認の結果を文書化していますか?
- 情報公開への備え
- 公開可能な情報と非公開情報を区分していますか?
- 情報公開請求があった場合の対応手順を確認していますか?
- 必要に応じて非公開部分のマスキング準備をしていますか?
- 次回調達への反映
- 随意契約の結果と課題を評価していますか?
- 次回の調達に向けた改善点を洗い出していますか?
- 可能であれば、次回は競争性を確保する方策を検討していますか?
このチェックリストは、すべての状況に完全に対応するものではありませんが、特命随意契約を適切に実施するための基本的な指針として活用してください。案件の特性や組織の規則に応じて、必要な項目を追加・調整することをお勧めします。
特命随意契約は、適切に運用すれば公共調達の有効なツールとなりますが、不適切な運用は様々な問題を引き起こす可能性があります。このチェックリストを参考に、常に適法かつ透明性の高い契約実務を心がけましょう。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















