DX推進指標の使い方|自己診断からKPI設計・実行まで

DX推進指標の概要:経産省の自己診断ツール(2019)。全35項目を6段階で評価し、〈経営のあり方〉×〈ITシステム〉の二軸、9つのキークエスチョン+26のサブで現状と課題を可視化。IPA提出で業界ベンチマークも取得可能。
活用法の要点:経営陣主導で部門横断的にガイダンス→自己診断→IPA提出→ベンチマーク確認→具体アクション設定。定量KPIを自社目的に合わせて設計し、PDCAで年次継続。業種・規模に応じて重点領域をカスタマイズ。
失敗回避のポイント:高スコア目的化や“手段の目的化(AI導入ありき)”を避ける。経営だけ・ITだけに丸投げしない。診断で終わらせず実行・検証を反復し、2025年の崖を意識してレガシー刷新と企業価値向上に直結させる。
「自社のDX推進は本当に正しい方向に進んでいるのだろうか」「何から手をつければよいのかわからない」そう悩んでいる経営者や DX担当者の方は少なくありません。
DX推進指標は、経済産業省が2019年に策定した自己診断ツールで、企業のDX推進状況を客観的に評価し、次に取るべきアクションを明確にするための指標です。35の診断項目と6段階の成熟度評価により、自社の現状と課題を正確に把握できます。
本記事では、DX推進指標の基本から実践的な活用方法、KPI設定のポイント、そして失敗を避けるための注意点まで徹底的に解説します。この記事を読めば、DX推進指標を効果的に活用し、自社のDXを着実に前進させることができるでしょう。

DX推進指標とは何か
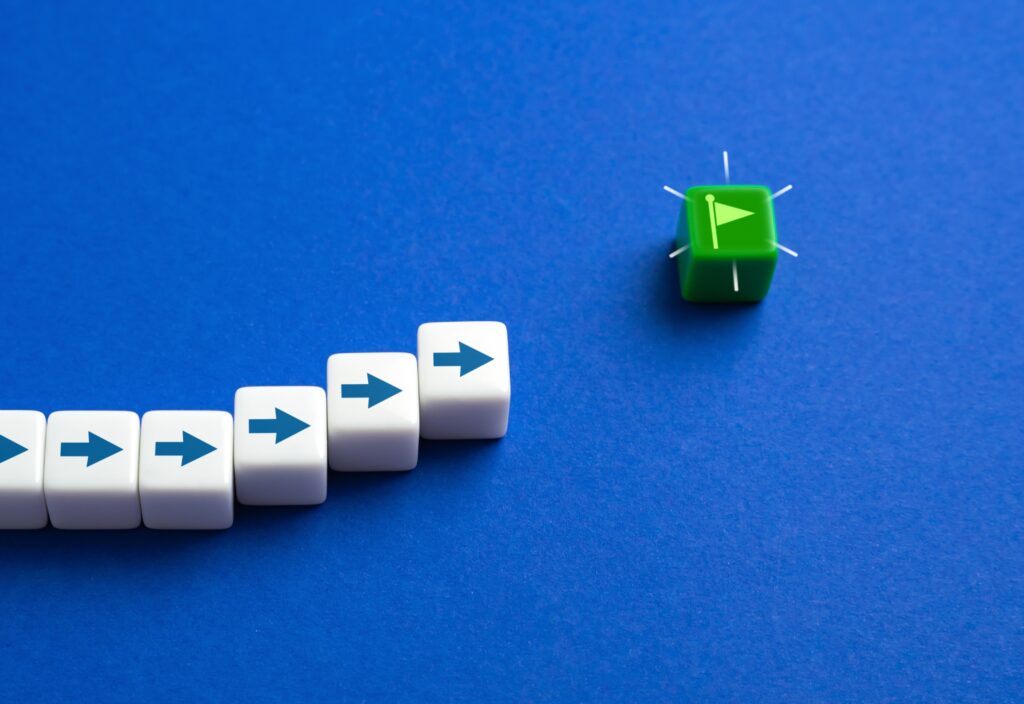
DX推進指標の定義と役割
DX推進指標とは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する際の現状と課題を正確に把握するための自己診断ツールです。2019年7月に経済産業省が策定・公開したもので、正式名称は「DX推進指標(デジタル経営改革のための評価指標)」といいます。
この指標は、単なるチェックリストではありません。経営者や社内の関係者がDX推進に向けた認識を共有し、具体的なアクションにつなげるための「気づきの機会」を提供することを目的としています。企業がDXを実現するには、部分的なデジタル化ではなく、経営方針の策定から基盤となるITシステムの構築まで、経営層を巻き込んだ全社的な取り組みが不可欠です。
DX推進指標は、全35項目の診断項目から構成されており、経営面とITシステム面の両軸からDXの進捗状況を評価します。各項目について0から5までの6段階で成熟度を自己評価することで、自社がDXのどの段階にあるのか、次に何をすべきかが明確になります。また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に診断結果を提出することで、他社や業界全体との比較が可能なベンチマークレポートを入手できる点も大きな特徴です。
策定された背景と2025年の崖
経済産業省がDX推進指標を策定した背景には、日本企業のDX推進が世界的に見て大きく遅れているという深刻な現状認識があります。国際経営開発研究所(IMD)が2020年に発表した世界デジタル競争力ランキングでは、日本は63の先進国中27位と低位に位置しており、デジタル変革の遅れが顕著でした。
さらに重大な問題として、経済産業省が2018年9月に公表した「DXレポート」では「2025年の崖」という概念が提示されました。これは、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存のレガシーシステムが残存し続けた場合、2025年以降に国内全体で最大年間12兆円の経済損失が発生する可能性があるというものです。具体的には、システムを理解する人材の高齢化と退職、製品サポートの終了、運用・メンテナンスコストの増大といったリスクが指摘されています。
多くの日本企業では、DXに取り組む意欲はあっても「どんな価値を創出するかではなく、AIを使って何かできないか」といった手段先行の発想に陥りがちです。また、経営層が号令をかけるだけで実際の仕組み変革が伴わない、部門間での認識のギャップが大きいといった課題も山積していました。DX推進指標は、こうした状況を打破し、企業が正しい方向でDXに取り組めるよう支援するために策定されたのです。
DX推進指標で実現できること
DX推進指標を活用することで、企業は具体的に三つの重要な成果を得ることができます。
第一に、自社のDX推進に関する課題の明確化です。35項目の診断を通じて、経営のあり方、組織体制、ITシステムの状況など、多角的な視点から自社の現状を客観的に把握できます。漠然としていたDXへの取り組みが、具体的な評価項目によって可視化され、どの領域が強みでどこに弱点があるのかが明らかになります。
第二に、組織全体での認識の統一と共有です。DXは技術の固有名称ではなく考え方を指す言葉であるため、個人によって認識が異なりがちです。しかし、DX推進指標では経営者がキークエスチョンに回答し、さらに経営幹部や事業部門、DX部門、IT部門の担当者が議論しながらサブクエスチョンに答える仕組みになっています。この過程で、部門を越えた対話が生まれ、全社的にDXに対する共通認識が醸成されます。
第三に、具体的なアクションへの道筋が見えることです。自己診断の結果とベンチマークレポートを照らし合わせることで、業界内での自社の位置づけが把握でき、次に優先的に取り組むべき施策が明確になります。単なる現状把握で終わらず、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくための基準として機能するのです。
DX推進指標の構成を理解する

定性指標と定量指標の違い
DX推進指標は、定性指標と定量指標という二つの評価軸で構成されています。この二つの指標を組み合わせることで、企業のDX推進状況を多面的かつ正確に評価できる仕組みになっています。
定性指標は、数値では表しにくいDX推進の質的な側面を評価するものです。具体的には、経営のビジョンが明確か、組織文化がDXに適しているか、推進体制が整っているかといった、企業の方針や姿勢、仕組みに関する項目が含まれます。定性指標は全35項目から構成され、各項目について0から5までの6段階で成熟度を自己評価します。評価にあたっては、なぜそのレベルと判断したのか根拠や証拠を示すことが推奨されており、これにより評価の客観性と説得力が高まります。
一方、定量指標は、DX推進の進捗や成果を具体的な数値で測定するものです。ただし、DXの目的は企業ごとに異なるため、定量指標については経済産業省が一律の基準を設定しているわけではありません。各企業が自社の状況やニーズに合わせて、意思決定のスピード向上率、新規顧客獲得数の増加、デジタル人材の育成数、システム刷新の進捗率といった指標を独自に設定します。重要なのは、自社がDXによって達成したい目標に直結する定量指標を選択し、定期的に測定しながら進捗管理を行うことです。
キークエスチョンとサブクエスチョンの詳細
定性指標の35項目は、キークエスチョン9項目とサブクエスチョン26項目に分類されています。この区分は、誰が中心となって回答すべきかという役割分担を明確にするためのものです。
キークエスチョンは、経営者自らが回答することが強く推奨される項目です。全9項目は「ビジョン」「経営トップのコミットメント」「マインドセット・企業文化」「推進・サポート体制」「人材育成・確保」「事業への落とし込み」「ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築」「ガバナンス・体制」から構成されます。これらは、DX推進において経営層の主導と意思決定が不可欠な領域であり、経営者が自ら現状を認識し、コミットメントを示すことが求められます。
サブクエスチョンは、経営者が経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門などの関係者と議論しながら回答する項目です。全26項目は、キークエスチョンをさらに具体化したものや、実務レベルでの取り組み状況を問うものが含まれます。例えば、「挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行するKPIを設定できているか」「データを迅速に利活用できる環境が整備されているか」といった項目があります。
重要なのは、ITシステムに関する項目であってもIT部門だけで回答するのではなく、経営層や事業部門も交えて議論することです。これにより、システム刷新がもたらす経営価値を全社で共有し、部門間の認識のずれを防ぐことができます。
6段階で評価する成熟度レベル
定性指標の各項目は、レベル0からレベル5までの6段階でDX推進の成熟度を評価します。この成熟度レベルは、企業が現在どの段階にあり、次にどのステップを目指すべきかを明確にするための指標です。
レベル0は「未着手」の状態で、DXに取り組むほどの関心がない、または興味はあっても具体的な取り組みに至っていない段階です。レベル1は「一部での散発的実施」で、具体的な施策がまとまっておらず、一部の部門や担当者のみが試行的に取り組んでいる状態を指します。レベル2は「一部での戦略的実施」で、DXに向けた方針と施策がまとまり、特定の部門から戦略的に取り組み始めている段階です。
レベル3は「全社戦略に基づく部門横断的推進」で、具体的な施策と方針が全社的にまとまり、各部門で横断的にDXが推進されている状態です。レベル4は「全社戦略に基づく持続的実施」で、定性・定量指標を用いてPDCAサイクルを回しながら、継続的かつ組織的にDXに取り組んでいる段階を示します。そして最高レベルのレベル5は「グローバル市場におけるデジタル企業」で、国内外の先進企業と遜色ないデジタル競争力を有し、グローバル市場で勝ち抜ける状態です。
重要な点は、すべての項目でレベル5を目指す必要はないということです。自社の事業戦略や経営資源に応じて、重点的に強化すべき領域とそうでない領域を見極め、現実的な目標設定をすることが推奨されています。
経営視点とITシステム視点の二軸評価
DX推進指標は、「DX推進のための経営のあり方・仕組み」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」という二つのカテゴリーで企業を評価します。この二軸評価により、経営面とシステム面の両方からバランス良くDXを推進できるようになります。
経営のあり方・仕組みに関する指標では、DXによってどのような価値を創出するかというビジョンが明確か、経営トップがコミットメントを示しているか、変革を促す企業文化が醸成されているか、推進体制やサポート体制が整備されているか、DX人材の育成と確保に取り組んでいるかといった項目が評価対象です。これらは、DXを組織全体の変革として捉え、経営レベルでの意思決定と実行力を問うものです。
ITシステムの構築に関する指標では、ビジョンを実現するための技術基盤が整備されているか、データをリアルタイムで活用できる環境があるか、既存のレガシーシステムの課題が明確化され対応策が講じられているか、IT投資の配分が適切か、ガバナンス体制が構築されているかといった項目が含まれます。DXの実現には、単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデルの変革を支える柔軟で拡張性の高いシステム基盤が不可欠です。
この二軸評価により、経営戦略とITシステムが乖離することなく、両輪として機能しているかを確認できます。多くの企業では、経営層がビジョンを描いてもIT部門がそれを実現できない、あるいはIT部門が先進技術を導入しても経営や事業部門が活用しきれないといったギャップが生じがちです。DX推進指標は、こうした溝を埋め、経営とITの統合的な推進を促す設計になっています。
DX推進指標を活用する5つのメリット

DX推進の課題が明確になる
DX推進指標の最大のメリットは、自社が抱える課題を具体的に特定できることです。多くの企業では「DXが必要」という認識はあっても、何が問題で何から手をつけるべきかが曖昧なまま進めてしまいがちです。
35項目の診断を通じて、ビジョンの明確さ、経営層のコミットメント、組織体制、人材育成、ITシステムの状況など、多角的な視点から自社の現状が可視化されます。例えば、「経営層はDXの必要性を理解しているが、現場への浸透が不十分」「データ活用の環境は整っているが、それを使いこなす人材が不足している」といった具体的な課題が浮き彫りになります。このように、定性指標の各項目で成熟度レベルを評価することで、どの領域が強みでどこに弱点があるのかが一目瞭然になるのです。
さらに、成熟度の判定理由や根拠、証拠を記載することで、なぜその評価になったのかを客観的に説明できます。これにより、感覚的な判断ではなく、事実に基づいた課題認識が可能になります。
組織全体で共通認識を持てる
DX推進指標を活用する過程で、部門を越えた対話と議論が生まれ、組織全体でDXに対する共通認識が形成されるという大きなメリットがあります。
DXは特定の部門だけで完結するものではなく、経営層、事業部門、IT部門、DX部門など、さまざまな関係者が連携して進める必要があります。しかし、それぞれの立場や専門性の違いから、DXに対する理解や優先順位の認識にズレが生じることも少なくありません。IT部門は技術導入に注目し、事業部門は業務効率化を重視し、経営層はビジネスモデルの変革を求めるといった具合です。
DX推進指標では、経営者がキークエスチョンに回答し、さらに関係者が集まってサブクエスチョンについて議論しながら答える仕組みになっています。この過程で、各部門の現状認識や課題意識が明らかになり、相互理解が深まります。また、評価結果を全社で共有することで、「我々は今どこにいて、どこを目指すのか」という共通のゴールイメージが醸成されます。こうした共通認識があってこそ、部門間の協力がスムーズになり、DX推進の実効性が高まるのです。
他社比較で客観的に現状を把握できる
DX推進指標の自己診断結果をIPAに提出すると、他社の診断結果を統合的に分析したベンチマークレポートを入手できます。これにより、業界内や企業規模別での自社の位置づけを客観的に把握することが可能です。
ベンチマークレポートには、全体平均スコア、業種別平均スコア、企業規模別平均スコア、DX先行企業の特徴などが詳細に記載されています。自社の診断結果と照らし合わせることで、「自社は業界平均よりもIT システムの整備が遅れている」「人材育成については先行企業に近いレベルにある」といった客観的な評価ができます。
また、過去の診断結果も「DX推進ポータル」で確認できるため、前年度と比較してどれだけ成熟度が向上したかを経年で追跡することも可能です。IPAの分析レポートによれば、複数年にわたって継続的にDX推進指標を活用している企業は、そうでない企業に比べて平均スコアが1.06ポイント高いというデータもあります。他社との比較により、自社の立ち位置を正確に認識し、危機感や改善意欲を持つきっかけにもなるのです。
次に取るべきアクションがわかる
DX推進指標は、単なる現状分析にとどまらず、具体的な次のアクションを明確にするという実践的な価値を持っています。
自己診断を通じて課題が明確になり、ベンチマークレポートで他社との差が見えると、「次に何をすべきか」という具体的なアクションが自然と浮かび上がってきます。例えば、「ビジョンの共有」の成熟度が低ければ、まずは経営層が明確なDXビジョンを策定し、全社に発信することが優先課題になります。「人材育成・確保」のスコアが低ければ、DX人材の採用計画や社内研修プログラムの整備が急務だと判断できます。
さらに、DX推進指標の自己診断フォーマットには「アクション」欄が設けられており、各項目の成熟度を向上させるために必要な具体的な取り組みを記載できるようになっています。これにより、診断結果が抽象的な評価で終わることなく、実行可能な施策へと落とし込まれます。経営者と関係者が議論しながらアクションを決定することで、組織全体のコミットメントも高まり、実行力が強化されるのです。
継続的な進捗管理と評価が可能になる
DX推進指標は、一度きりの診断で終わるものではなく、継続的なPDCAサイクルの基準として機能します。年次で定期的に自己診断を実施し、前年度との比較や目標達成度の評価を行うことで、DX推進の進捗を管理できます。
DXは短期間で完了するプロジェクトではなく、中長期的に組織を変革し続ける取り組みです。そのため、施策の実行後にその効果を検証し、必要に応じて方向修正を行いながら進める必要があります。DX推進指標を活用すれば、「昨年レベル1だった項目が今年レベル2に向上した」「当初の3年後目標レベル3を達成できた」といった具体的な進捗が数値で把握できます。
また、定期的な診断を通じて、新たに生じた課題や環境変化にも対応できます。DXを取り巻く技術やビジネス環境は急速に変化するため、昨年は問題なかった領域が今年は課題になることもあります。継続的な診断により、常に最新の状況を反映した評価と改善が可能になり、DX推進の持続性が担保されるのです。
DX推進指標による自己診断の実践手順
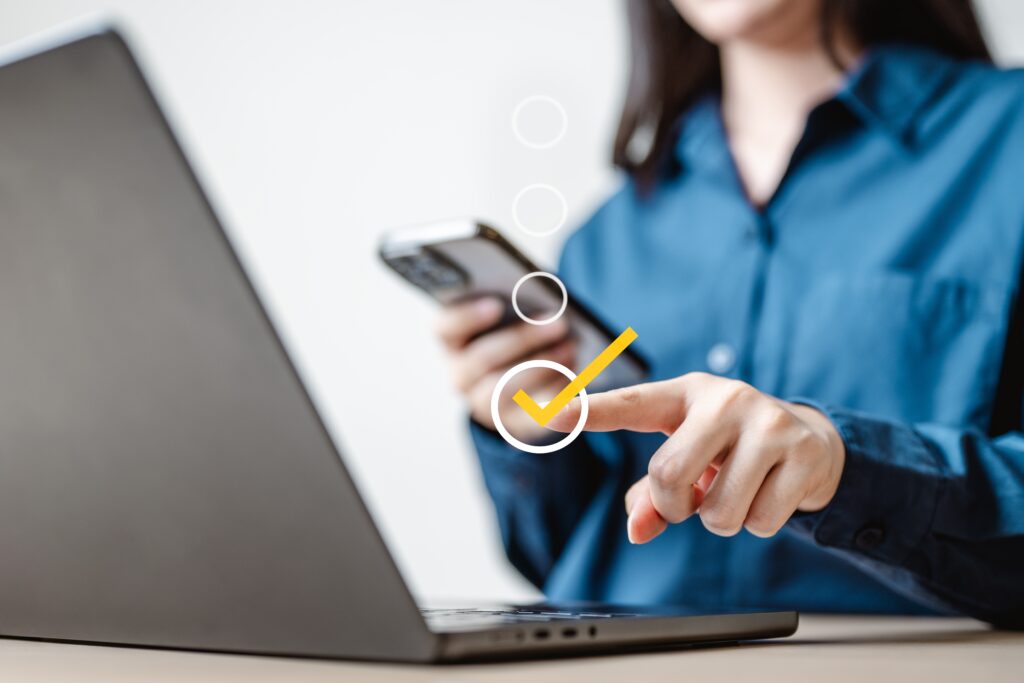
ステップ1:ガイダンスの確認と理解
DX推進指標による自己診断の第一歩は、経済産業省またはIPAの公式Webサイトから「DX推進指標とそのガイダンス」をダウンロードし、内容を十分に理解することです。
このガイダンスは全52ページにわたる詳細な資料で、DX推進指標の策定背景、各指標項目の意味、成熟度レベルの判定基準、活用時の留意点などが網羅的に記載されています。特に重要なのは、各キークエスチョンとサブクエスチョンの意図を正しく理解することです。表面的な質問文だけでなく、その背景にある課題認識や、なぜその項目が重要なのかを把握することで、より本質的な自己診断が可能になります。
まずは経営陣がガイダンスを熟読し、DXの全体像と自己診断の目的を理解します。その上で、各部門の責任者や担当者にも内容を周知し、組織全体でDX推進指標の意義を共有することが重要です。また、自己診断を実施する前に、社員を対象とした意識調査を行い、現場のDXに対する理解度や意見を把握しておくことも有効です。DX推進には一定の反発や抵抗が伴うことも想定されるため、慎重な準備と丁寧なコミュニケーションが求められます。
ステップ2:自己診断フォーマットへの記入
IPAのWebサイトから「DX推進指標自己診断フォーマット」をダウンロードし、35項目について回答を記入します。フォーマットはExcel形式で提供されており、各項目の現在の成熟度レベルと3年後の目標レベルを入力する仕組みになっています。
自己診断は、一人の担当者が単独で回答するのではなく、経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門などの関係者が集まって議論しながら進めることが強く推奨されています。各部門の視点を持ち寄ることで、より多面的で正確な現状認識が可能になります。特に、キークエスチョンについては経営者自らが回答することが重要であり、これによってDX推進に対する経営層のコミットメントが明確になります。
成熟度レベルの判定では、根拠や証拠の提示が推奨されています。例えば、「経営トップのコミットメント」をレベル2と評価した場合、その根拠として社内の中期経営計画やIR資料、プレスリリース、実際に実施した施策の記録などを挙げることで、評価の客観性と説得力が高まります。また、「アクション」欄には、目標レベルを達成するために具体的にどのような施策に取り組むかを記載します。この段階で施策の優先順位や実行スケジュール、担当部署などを明確にしておくと、後のアクション実行がスムーズになります。
ステップ3:IPAへの提出とベンチマーク取得
自己診断フォーマットへの記入が完了したら、IPAが運営する「DX推進ポータル」にアクセスし、診断結果を提出します。提出はWebシステムを通じて行われ、gBizIDというアカウントが必要です。gBizIDを持っていない場合は、事前に作成しておく必要があります。
診断結果を提出すると、IPAから申請管理番号が発行され、メールで通知されます。この番号は今後の問い合わせや過去の診断結果の確認に必要になるため、大切に保管しておきましょう。提出後、IPAは全国の企業から集まった診断結果を統合的に分析し、ベンチマークレポートを作成します。このレポートは提出した企業のみが閲覧でき、一般には公開されません。個々の企業の診断結果が外部に漏れることはないため、安心して正直な評価を提出することができます。
ベンチマークレポートには、全体平均スコア、業種別平均スコア、企業規模別平均スコア、DX先行企業の特徴などが詳細に記載されています。自社の診断結果と照らし合わせることで、業界内での立ち位置や、先行企業と比較してどの領域に差があるのかが明確になります。また、先行企業の具体的な取り組み事例も紹介されているため、自社のアクション検討の参考になります。なお、IPAでは毎年診断結果の分析レポートを公表しており、日本全体のDX推進の動向や課題を把握することもできます。
ステップ4:結果をもとにした関係者での議論
ベンチマークレポートと自己診断結果が揃ったら、経営者、経営幹部、各部門の代表者を集めて、今後のDX推進について具体的な方針と施策を議論します。これがDX推進指標活用の最も重要なステップです。
議論では、まず自社の診断結果を共有し、どの領域が強みでどこに課題があるのかを全員で確認します。次に、ベンチマークレポートをもとに、業界平均や先行企業と比較して自社がどの位置にあるのかを客観的に把握します。そして、優先的に取り組むべき課題を特定し、具体的な施策、実行スケジュール、担当部署、必要なリソース(予算・人材)などを決定していきます。
この議論の過程で重要なのは、部門間の利害対立や認識のズレを乗り越え、全社的な視点でDX推進の方向性を統一することです。例えば、IT部門は最新技術の導入を優先したいかもしれませんが、事業部門は既存業務の効率化を求めるかもしれません。経営層のリーダーシップのもと、こうした異なる視点を統合し、自社にとって最適なDX戦略を策定することが求められます。
方策がまとまれば、経営陣はDXプロジェクトの実施環境を整備し、予算や人材などのリソースを適切に配分します。一方、各部門のDX担当者は、決定された施策を速やかに実行に移します。そして、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて方向修正を行いながら、PDCAサイクルを回していくのです。
DX推進指標とKPI設定の実践

KPIとしてDX推進指標を活用する理由
DX推進指標は、DX推進のKPI(重要業績評価指標)として極めて有効です。KPIとは、目標達成までの各ステップにおける達成度を測定・評価するための指標であり、DXのような長期的なプロジェクトでは特に重要な役割を果たします。
DX推進指標をKPIとして活用する最大の理由は、自社の課題を認識した上で取るべきアクションを明確にできるよう設計されている点です。35項目の定性指標は、多くの日本企業が直面している課題や、解決するために押さえるべき事項を中心に構成されています。したがって、各項目の成熟度を向上させることが、そのままDX推進の進捗につながる仕組みになっているのです。
また、DX推進指標のサブクエスチョンには「挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適したKPIを設定できているか」という項目があります。これは、DX推進においてKPI設定が重要であることを明示しており、指標自体がKPIの必要性を問うている点でもユニークです。経済産業省も、DX推進指標を「多くの日本企業が直面しているDXを巡る課題を指標項目とし、関係者が議論しながら認識を共有し、アクションにつなげていくための気づきの機会を提供するツール」と位置づけており、まさにKPIとしての活用を想定しているのです。
定量指標の具体的な設定方法
DX推進指標の定量指標は、各企業がDXによって実現を目指す目標に合わせて、独自に設定する必要があります。なぜなら、DXの目的は企業ごとに異なり、一律の基準を当てはめることができないためです。
定量指標を設定する際は、まず自社のDXによって達成したい最終目標(KGI:重要目標達成指標)を明確にします。例えば、「3年後に売上を30%増加させる」「顧客満足度を50%向上させる」「業務効率を40%改善する」といった具体的な数値目標です。次に、そのKGIを達成するために必要なプロセスや施策を洗い出し、各プロセスに対してKPIを設定します。
DX推進における定量指標の例としては、以下のようなものが挙げられます。競争力強化に関する指標として、新規顧客獲得数、市場シェア率、新サービスのリリース数などがあります。業務効率化に関する指標では、業務処理時間の短縮率、人的ミスの削減率、自動化された業務の割合などが設定できます。組織・人材に関する指標としては、DX人材の育成数、デジタルスキル研修の受講率、IT部門と事業部門の協働プロジェクト数などが考えられます。ITシステムに関する指標では、レガシーシステムの刷新進捗率、クラウド化率、データ活用基盤の整備状況などが該当します。
重要なのは、ロジックだけで設定するのではなく、実際のデータを重視することです。過去の売上データや業務データを分析し、KGIに最も寄与する要素を特定してKPIとして設定することで、実効性の高い指標になります。
業種・規模別のKPI設定のポイント
業種や企業規模によって、DX推進で優先すべき領域や設定すべきKPIは異なります。自社の特性に合わせた適切なKPI設定が、DX推進の成否を分けるといっても過言ではありません。
製造業の場合、生産プロセスのデジタル化や効率化が主要なテーマになります。そのため、生産ラインの自動化率、IoTセンサーの導入数、予知保全による停止時間の削減率、不良品発生率の低下などがKPIとして設定されることが多いです。また、サプライチェーン全体のデジタル化も重要であり、在庫回転率の向上やリードタイムの短縮なども指標となります。
小売業やサービス業では、顧客接点のデジタル化と顧客データの活用が焦点になります。オンライン売上比率、ECサイトのコンバージョン率、顧客単価の向上、リピート率の改善、デジタルマーケティングのROIなどがKPIの例です。また、店舗とオンラインを統合したオムニチャネル戦略の進捗も重要な指標となります。
中小企業の場合は、限られたリソースの中で効率的にDXを推進する必要があります。そのため、まずは業務効率化や生産性向上に直結するKPIを優先的に設定することが推奨されます。例えば、RPA導入による事務作業の削減時間、ペーパーレス化の進捗率、クラウドツールの導入数と利用率などです。また、外部リソース(フリーランスやコンサルタント)の活用も選択肢となるため、外部人材とのプロジェクト数や成果もKPIに含めることができます。
効果測定とPDCAサイクルの回し方
KPIを設定したら、定期的に測定・評価を行い、PDCAサイクルを継続的に回すことが不可欠です。これにより、DX推進の進捗を管理し、必要に応じて戦略を修正しながら目標達成に近づけます。
まず、各KPIをどのように測定し、どのくらいの頻度で評価するかを決定します。KPIの性質に応じて、週次、月次、四半期ごとなど、適切な測定頻度を設定しましょう。例えば、業務効率化に関するKPIは月次で測定し、中長期的な戦略に関するKPIは四半期ごとに評価するといった具合です。
測定したKPIは、経営層や関係者に報告し、全体での認識共有を図ります。この際、単に数値を報告するだけでなく、なぜその結果になったのか要因を分析し、目標を達成できている指標と達成できていない指標を明確にします。達成できていない指標については、その原因を深掘りし、「デジタルツールの利用率が低い」という課題に対して「ユーザーインターフェースの改善」や「追加トレーニングの実施」といった具体的な対策を立案します。
対策を実行したら、再度KPIを測定し、改善効果を検証します。このPDCAサイクルを継続的に回すことで、DX推進の実効性が高まり、着実に目標に近づいていくのです。また、環境変化や新たな課題が生じた場合は、KPI自体を見直すことも重要です。固定的なKPIにこだわるのではなく、状況に応じて柔軟に調整しながら進めることが、DX推進を成功させる鍵となります。
DX推進指標を効果的に活用する7つのポイント

経営陣が主導して全社で取り組む
DX推進の成否を分ける最も重要な要素は、経営陣が主導的な役割を果たし、全社を巻き込んで取り組むことです。経済産業省の「DX推進指標とそのガイダンス」でも、この点が繰り返し強調されています。
経営陣の主な役割は、リーダーシップの発揮、予算や人材の適切な配分、組織体制や実施環境の整備です。まず、経営トップが明確なDXビジョンを策定し、「なぜDXに取り組むのか」「DXによってどのような価値を創出するのか」「どのような未来を目指すのか」を全社員に対して力強く発信する必要があります。号令をかけるだけでなく、自らが率先してDXプロジェクトに関与し、意思決定を行う姿勢を示すことが不可欠です。
また、DXには一定の投資と人的リソースが必要です。経営陣は、競争領域に資金・人材を大幅にシフトし、レガシーシステムの保守運用コストを抑えながら、新たなデジタル技術やビジネスモデルへの投資を決断しなければなりません。さらに、DX推進に適した組織体制を構築し、各部門の役割を明確化し、部門横断的な協力体制を築くことも経営層の重要な責務です。
DX推進には、既存の業務プロセスや組織文化を変革することが伴うため、現場からの反発や抵抗も予想されます。経営トップは、こうした反対意見に対しても、DXの必要性と現状維持のリスクを丁寧に説明し、説得する覚悟が求められます。
良い点数を目的にしない正しい姿勢
DX推進指標の自己診断では、高いスコアを獲得することが目的ではありません。あくまで現状と課題を正確に把握し、次のアクションにつなげるための「気づきの機会」として活用することが本来の目的です。
定性指標の各項目の成熟度は、組織内での議論を通じて導き出された数値をそのまま受け入れることが重要です。見栄を張って実態よりも高い評価をつけたり、逆に謙遜して過小評価したりすることは、DX推進のスタート地点を誤ることにつながります。自己診断ツールは「テスト」ではなく「アンケート」あるいは「人間ドック」のイメージで、正直かつ客観的に回答することが求められます。
特に、成熟度の判定理由や根拠、証拠を記載する際には、事実に基づいた説明を心がけましょう。「なんとなくこのレベルだろう」という感覚的な判断ではなく、社内の資料や実際に実施した施策の記録を根拠として示すことで、評価の客観性が高まります。そして、評価結果を受け入れ、「ここが弱い」という課題を直視することが、改善への第一歩となるのです。
部門横断的な議論と認識の統一
DX推進指標の自己診断は、一部の経営陣や担当者だけで進めるのではなく、部門を越えた関係者が集まって議論することが極めて重要です。
DXの主な目的は、データやデジタル技術を活用して顧客の視点から新しい価値を創造することです。そのためには、経営の仕組みそのものを変革し、再構築する必要があります。一部の経営陣だけで回答すると、DXの本来のビジョンや目的が現場に伝わらず、結果として手段の目的化(AIを導入すること自体が目的となる)の問題が生じる恐れがあります。逆に、IT部門だけで回答すると、技術的な視点に偏り、ビジネス面での価値創出が見落とされる可能性があります。
したがって、経営者、経営幹部、事業部門、IT部門、DX部門など、部門間の垣根を越えて議論を行うことが不可欠です。各部門の現状認識や課題意識を持ち寄り、相互に理解を深めることで、自社のDX推進に関する共通の認識が築かれます。場合によっては、関係者が集まった議論の前に、それぞれが個別に自己診断を行い、社内での認識の違いを明らかにすることも有効です。認識のズレが可視化されることで、議論の論点が明確になり、より建設的な対話が可能になります。
自社の状況に合わせたカスタマイズ
DX推進指標にある定性指標は、すべての項目でレベル5を目指す必要はありません。自社の事業戦略、経営資源、業界特性に応じて、重点的に強化すべき領域を見極め、現実的な目標設定をすることが推奨されています。
経済産業省の「DX推進指標とそのガイダンス」でも、「基本的には、自社がDXによって伸ばそうとしている定量指標を自ら選択して算出するとともに、例えば3年後に達成を目指す当該指標に関する数値目標を立て、進捗管理を行っていくといった活用方法を想定している」と明記されています。つまり、画一的な基準に従うのではなく、自社の状況に合わせて指標をカスタマイズすることが重要なのです。
例えば、成長戦略として新規事業の創出を重視する企業であれば、「事業への落とし込み」や「ビジョン」に関する指標の成熟度を高めることを優先するでしょう。一方、既存事業の効率化を主眼とする企業であれば、「ITシステムの構築」や「業務プロセスのデジタル化」の指標に注力することになります。定性指標に優先順位をつけ、社内リソースに合わせて目標の成熟度レベルを調整することで、実現可能性の高いDX推進計画が策定できます。
また、DX推進指標はあくまで共通のフォーマットであるため、自社のビジネススタイルや業界特性に応じて表現や項目をカスタマイズすることも有効です。自社に合った言葉や具体例を盛り込むことで、社員全員が理解しやすく、受け入れやすい指標になります。
定期的な診断と継続的な改善
DX推進指標による自己診断は、一度実施して終わりではなく、年次で定期的に行い、継続的な改善につなげることがDX推進を成功させる鍵です。
DXは中長期的に組織を変革し続ける取り組みであり、短期間で完了するプロジェクトではありません。施策を実行した後、その効果を検証し、必要に応じて方向修正を行いながら進める必要があります。年次で自己診断を実施することで、前年度と比較してどの項目の成熟度が向上したか、どの項目が停滞しているかを具体的に把握できます。
IPAの分析レポートによれば、2年、3年と連続してDX推進指標の自己診断を提出している企業は、すべての指標が向上していることがわかっています。また、過去に提出したことのある企業と提出していない企業の現在値の平均(全指標)の差は1.06ポイントであり、継続的にDX推進指標を活用することでDX推進が着実に進展することが実証されています。
定期的な診断を通じて、新たに生じた課題や環境変化にも対応できます。DXを取り巻く技術やビジネス環境は急速に変化するため、昨年は問題なかった領域が今年は課題になることもあります。また、より短期のサイクルで確認しておきたい指標については、マネジメントサイクルに組み込んでおくとより効果的です。継続的な診断と改善のサイクルを回すことで、DX推進の持続性が担保され、組織全体のデジタル成熟度が着実に向上していくのです。
DX推進指標活用時の5つの注意点

高スコア獲得を目的化してしまう
DX推進指標の活用で最もよくある失敗が、良い点数を取ることを目的化してしまうことです。これは本来の目的から大きく逸脱した使い方であり、DX推進の実効性を損なう要因となります。
自己診断は、あくまで現状を正確に把握し、課題を明確にするためのツールです。成熟度レベルの数値そのものに意味があるのではなく、その評価を通じて「何が足りないのか」「次に何をすべきか」という気づきを得ることに価値があります。しかし、組織内で「他社よりも高いスコアを目指そう」「前年よりも良い評価を得よう」といった雰囲気が生まれると、実態よりも良く見せるために評価を操作したり、表面的な施策だけを実施して本質的な変革を怠ったりする危険性があります。
特に注意すべきなのは、経営層がスコアだけを重視し、「なぜその評価になったのか」という根拠や、「評価を向上させるための具体的なアクション」を軽視してしまうケースです。DX推進指標は「テスト」ではなく「アンケート」または「人間ドック」として捉え、正直かつ客観的に現状を評価する姿勢が求められます。
経営陣や担当者だけで進めてしまう
経営層だけの推進や、IT部門・DX部門への丸投げは、DX失敗の大きな原因です。どちらも、DX推進に必要な全社的な取り組みを阻害する行為です。
経営層だけでDXを推進しようとすると、号令はかかるものの、現場への周知や理解が不十分なまま一方的に進められることになります。結果として、現場は混乱し、最悪の場合は反発組織の発生や離職といった事態も起こり得ます。DXは経営層による積極的な行動が重要ですが、それと同時に現場の理解と協力が不可欠です。経営層は、DXの必要性と現状維持のリスクを丁寧に説明し、現場の意見も絶えずヒアリングしながら、部門横断的な協力体制を築く必要があります。
逆に、「IT分野は専門組織に任せればいい」といった理由で、IT部門やベンダーにDX事業そのものを丸投げするケースも問題です。IT部門は技術的な実装を担う重要な役割を持ちますが、ビジネス戦略やビジョンの策定は経営層の責任です。経営層が関与せず、IT部門だけでDXを進めようとすると、技術導入は進んでも経営価値の創出につながらない「手段の目的化」に陥る危険があります。
「DX推進指標とそのガイダンス」でも、経営層のリーダーシップと部門横断的な議論の重要性が何度も注意喚起されています。経営者がリーダーシップを持って各部門を導き、関係者全員が対話しながらDXに取り組む姿勢が、成功への道です。
自己診断だけで取り組みを終えてしまう
自己診断の結果を見て満足し、具体的なアクションに移さないことも、DX失敗の典型的なパターンです。診断結果を具体的な施策にまで落とし込めていない企業は少なくありません。
このケースの原因は、「何が必要かはわかるが、何から始めればいいのかわからない」という状態にあります。自己診断で課題は明確になったものの、それをどう解決すれば良いのか、どの施策を優先すべきか、誰が担当するのか、予算はどう確保するのかといった具体的な実行計画が立てられていないのです。
この問題を解決するには、以下の対策が有効です。まず、同業他社や類似企業のDX事例を参考にすることです。ベンチマークレポートには先行事例が記載されているため、それを参考に自社でも実行可能な施策を検討できます。次に、監査部門による内部監査を実施し、より客観的な視点から改善点を見つけることも有効です。さらに、自社だけでは解決策が見出せない場合は、コンサルティングファームやITベンダーから専門的なアドバイスを受けることも選択肢となります。
重要なのは、診断結果を「終着点」ではなく「出発点」として捉え、必ず具体的なアクションへとつなげることです。自己診断フォーマットの「アクション」欄を活用し、各項目の成熟度を向上させるために必要な施策を明記し、実行スケジュールと担当者を決定しましょう。
一度の実施で満足してしまう
自己診断結果から具体的な施策に落とし込めても、それが一度きりの取り組みで終わってしまうケースも多いです。簡易的なデジタイゼーションやデジタライゼーションだけで満足し、一部の部門の取り組みだけで全社的な変革に至らないパターンです。
DXは決して一度の取り組みだけで完了するものではありません。中長期的に組織を変革し続けるプロセスであり、施策を実行した後にその効果を検証し、絶えず試行と改善を繰り返す体制で臨む必要があります。一度実行した施策の結果はKPIや従業員意識調査など具体的な分析手法で評価し、PDCAサイクルを継続的に回すことが不可欠です。
IPAの分析レポートによれば、2年、3年と連続してDX推進指標の自己診断を提出している企業は、すべての指標が向上していることが実証されています。逆に、一度だけの取り組みで終わってしまった企業は、DXの効果を十分に享受できていないケースが多いのです。
継続的な取り組みを実現するには、経営陣がPDCAサイクルを回し続けるための予算と人的リソースを確保し、年次で定期的に自己診断を実施することを組織の仕組みとして定着させることが重要です。
DX推進そのものを目的にしてしまう
DX推進における最も本質的な誤解が、「手段の目的化」です。デジタル技術やツールの導入そのものが目的になってしまい、本来のゴールである企業価値の向上や市場競争力の強化を見失ってしまうケースです。
DXの究極の目的は、企業価値の向上と市場競争力の強化にあります。デジタル技術の活用は、これらの目標を達成するための非常に効果的な手段ですが、それ自体が目的ではありません。しかし、「AIを導入すること」「RPAを展開すること」「クラウドに移行すること」といった技術導入が目的化してしまうと、本来の目的から逸脱した行動を取ってしまう恐れがあります。
例えば、「AIを使って何かできないか」という発想は、手段先行の典型例です。本来であれば、「顧客にどのような価値を提供するか」「どのような課題を解決するか」というビジョンが先にあり、それを実現するための手段としてAIを選択するという順序が正しいのです。
DX推進指標を活用する際も、指標のスコアを上げることや、デジタル技術を導入することが目的にならないよう注意が必要です。常に「この取り組みは、顧客価値の創出につながっているか」「ビジネスモデルの変革に寄与しているか」「競争優位性を確保できるか」という視点で評価し、本質的な目的を見失わないようにしましょう。
DX推進指標とDX推進ガイドラインの関係

DX推進ガイドラインの概要と位置づけ
DX推進ガイドラインは、経済産業省が2018年12月に策定した、DXを推進するための指針です。DX推進指標と並んで、企業のDX実現を支援する重要な公的資料として位置づけられています。
DX推進ガイドラインは、「DX推進のための経営のあり方、仕組み」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」という二つの主要な項目で構成されています。前者では、企業がDXを推進するための経営戦略や意思決定のあり方について詳しく説明しており、経営層のリーダーシップや組織文化の改革の重要性が強調されています。後者では、DXを実現するためのITシステムの構築方法や、それに必要な体制・仕組み、実行プロセスについて記載されており、システムのブラックボックス化を防ぎ、現場からの抵抗を克服するための具体的な方法が示されています。
このガイドラインを通じて、企業はDXの全体像を理解し、具体的な取り組みを進めることが求められています。DX推進ガイドラインは、「何をすべきか」「どのように進めるべきか」という指針を示すものであり、いわばDXの羅針盤としての役割を果たします。
指標とガイドラインの相互補完関係
DX推進ガイドラインとDX推進指標は、相互に補完し合う関係にあります。ガイドラインが「方向性」を示すものであるのに対し、指標は「現在地の確認」と「進捗管理」を行うツールです。
DX推進ガイドラインは、DXを推進するために必要な経営のあり方やITシステムの構築について、包括的かつ体系的な指針を提供します。しかし、ガイドラインだけでは、自社が現在どの段階にあり、次に何をすべきかが具体的に見えにくいという課題があります。そこで登場するのがDX推進指標です。
DX推進指標は、ガイドラインで示された要件を35項目の診断項目に落とし込み、6段階の成熟度で自己評価できるようにしたものです。つまり、ガイドラインが示す「あるべき姿」に対して、自社がどこまで到達しているかを測定する物差しの役割を果たします。企業はガイドラインを読んでDXの全体像と方向性を理解し、指標を用いて自己診断を行うことで現状と課題を把握し、具体的なアクションを決定できます。
さらに、DX推進指標を用いた自己診断の結果は、ガイドラインの各項目の理解を深めるフィードバックとしても機能します。診断を通じて「なぜこの項目が重要なのか」「どうすれば成熟度を向上できるのか」という問いが生まれ、ガイドラインを再読することでより深い理解が得られるという好循環が生まれます。
両者を組み合わせた実践的な活用法
DX推進ガイドラインとDX推進指標を組み合わせて活用することで、より実効性の高いDX推進が実現します。以下に、具体的な活用ステップを示します。
ステップ1として、まず「DX推進ガイドライン」を熟読し、DXの全体像、必要な経営のあり方、ITシステムの構築方法について理解を深めます。この段階で、経営層はDXのビジョンや方向性を明確にし、組織全体に周知します。
ステップ2では、「DX推進指標とそのガイダンス」を確認し、自己診断の方法と各項目の意味を理解します。そして、「DX推進指標自己診断フォーマット」を用いて、関係者が議論しながら35項目について回答します。この過程で、ガイドラインで学んだ内容が自社の実態とどう対応しているかを具体的に確認できます。
ステップ3では、自己診断結果とベンチマークレポートをもとに、優先的に取り組むべき課題を特定します。その際、ガイドラインに戻り、該当する項目の詳細な説明を参照することで、具体的な施策のヒントを得られます。
ステップ4では、決定した施策を実行し、定期的にDX推進指標で進捗を確認します。年次で自己診断を繰り返し、成熟度の向上を測定しながらPDCAサイクルを回します。必要に応じてガイドラインを参照し、新たな視点や改善策を取り入れながら、継続的にDXを推進していきます。
このように、ガイドラインで方向性を学び、指標で現状を測定し、ガイドラインに戻って具体策を検討するというサイクルを回すことで、理論と実践が統合され、実効性の高いDX推進が可能になるのです。
業種別DX推進指標の活用アプローチ
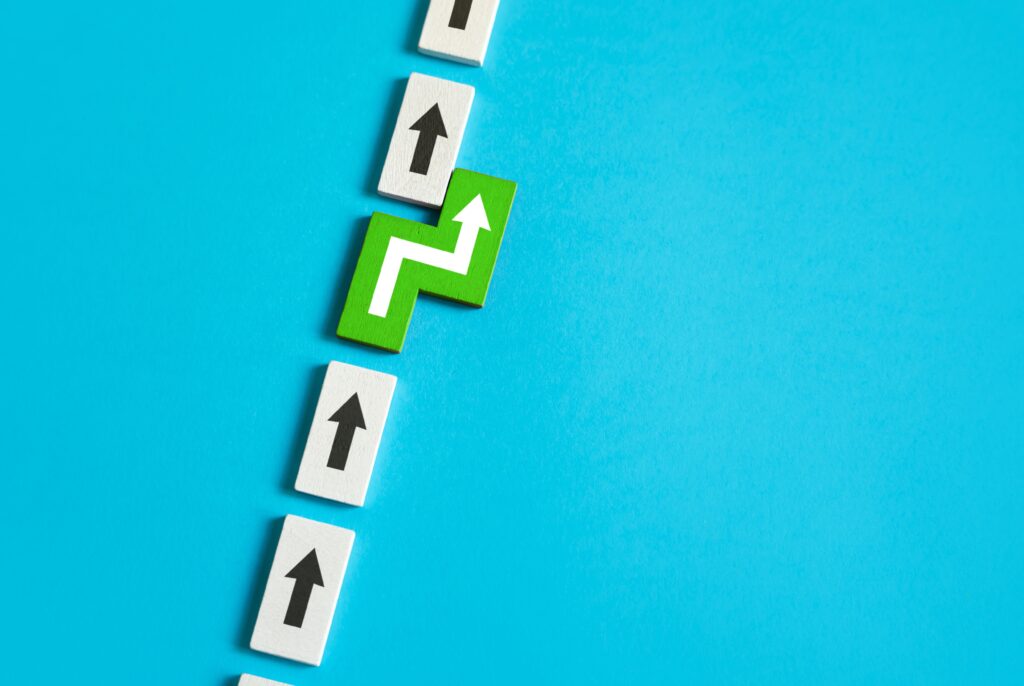
製造業におけるDX推進指標の活用
製造業では、生産プロセスのデジタル化とサプライチェーン全体の最適化がDXの主要テーマとなります。DX推進指標を活用する際も、これらの領域に重点を置いた評価と施策立案が求められます。
製造業のDX推進指標活用では、「ITシステム構築の枠組み」の項目が特に重要です。具体的には、IoTセンサーによるリアルタイムデータ収集の整備状況、AIを用いた予知保全システムの導入、生産ラインの自動化・ロボット化の進捗などを評価します。定量指標としては、生産ラインの稼働率向上、不良品発生率の低減、在庫回転率の改善、リードタイムの短縮などが設定されることが多いです。
また、製造業では、工場内だけでなくサプライチェーン全体のデジタル化も重要な課題です。取引先や物流パートナーとのデータ連携、需要予測の精度向上、調達プロセスの効率化なども、DX推進指標の「事業への落とし込み」や「ビジョン実現の基盤としてのITシステム」の項目で評価すべきポイントです。
物流業界の事例では、DX推進指標を活用して倉庫管理システムの導入状況や配送ルート最適化の進捗度を評価し、アナログな作業が多い領域やデジタル化による効率化が見込める業務を特定することで、優先的に取り組むべき課題を明確化しています。
小売業・サービス業での実践ポイント
小売業やサービス業では、顧客接点のデジタル化と顧客データの活用がDX推進の中核となります。DX推進指標の活用においても、これらの視点を重視した評価が必要です。
小売業・サービス業では、「ビジョン」や「事業への落とし込み」の項目が特に重要です。デジタル技術を活用して顧客にどのような新しい価値を提供するのか、オンラインとオフラインをどう統合するのか、といった戦略的なビジョンが明確になっているかを評価します。定量指標としては、オンライン売上比率、ECサイトのコンバージョン率、顧客単価の向上、リピート率の改善、顧客満足度スコアなどが設定されます。
DX推進指標による自己診断では、顧客データの収集・分析・活用の仕組みが整備されているか、デジタルマーケティングの体制が構築されているか、店舗スタッフがデジタルツールを活用できているか、といった項目を重点的に評価します。また、「人材育成・確保」の項目では、デジタルマーケティングスキルを持つ人材の育成や、データアナリストの確保状況も重要な評価ポイントです。
小売業のケースでは、DX推進指標による評価により、顧客データの活用度が低い点や在庫管理システムの老朽化、デジタルマーケティングのスキル不足といった具体的な弱点が浮かび上がります。これにより、顧客データ分析基盤の構築、在庫管理システムの刷新、デジタルマーケティング人材の育成といった具体的なアクションプランが策定できるのです。
中小企業が押さえるべき活用のコツ
中小企業では、限られたリソースの中で効率的にDXを推進する必要があるため、DX推進指標の活用においても戦略的な優先順位づけが重要です。
中小企業がDX推進指標を活用する際の第一のコツは、すべての項目で高い成熟度を目指すのではなく、自社の経営課題に直結する領域に集中することです。例えば、人手不足が深刻な課題であれば、「業務プロセスのデジタル化」や「RPAの導入」に関連する項目を優先的に強化します。売上拡大が目標であれば、「顧客接点のデジタル化」や「デジタルマーケティング」に関する項目に注力します。
第二のコツは、定量指標を身の丈に合ったものに設定することです。大企業と同じような壮大な目標を掲げるのではなく、「3年後にRPAで月間100時間の業務時間を削減」「デジタルツールの導入で顧客対応時間を30%短縮」といった、実現可能で測定しやすい具体的な指標を設定しましょう。
第三のコツは、外部リソースの積極的な活用です。中小企業では社内にDX人材やIT専門家が不足していることも多いため、コンサルタント、ITベンダー、フリーランスのエンジニアなど、外部の専門家の力を借りることも有効な戦略です。DX推進指標の「人材育成・確保」の項目では、こうした外部リソースの活用状況も評価に含めることができます。
中小企業こそ、DX推進指標を羅針盤として活用し、自社の現状を正確に把握し、限られたリソースを最も効果の高い施策に集中投下することで、着実にDXを前進させることができるのです。
まとめ:DX推進指標で自社のDXを加速させる

DX推進指標は、企業がデジタルトランスフォーメーションを成功させるための強力なツールです。経済産業省が策定したこの自己診断ツールは、35項目の診断項目と6段階の成熟度評価により、自社のDX推進状況を客観的に把握し、次に取るべきアクションを明確にします。
本記事で解説したように、DX推進指標を効果的に活用するには、経営陣が主導して全社で取り組むこと、良い点数を目的にしない正しい姿勢を持つこと、部門横断的な議論で認識を統一すること、自社の状況に合わせてカスタマイズすること、そして定期的な診断と継続的な改善を実践することが重要です。
また、DX推進指標を単なる診断ツールとしてだけでなく、KPIとして活用し、定量指標を適切に設定することで、DX推進の進捗を数値で管理できます。業種や企業規模に応じた活用アプローチを取ることで、より実効性の高いDX推進が実現します。
DX推進は一朝一夕に完了するものではありませんが、DX推進指標という明確な羅針盤を持つことで、迷うことなく着実に前進できます。自己診断を通じて現状を正確に把握し、ベンチマークで他社と比較し、具体的なアクションに落とし込み、PDCAサイクルを回し続けること。これらを実践することで、あなたの企業のDXは必ず成功へと導かれるでしょう。
今こそ、DX推進指標を活用して、自社のデジタル変革を加速させる第一歩を踏み出しましょう。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。
















