DX推進 事例37選~業界別成功事例から学ぶ実践ポイントと組織づくり~


- 製造業から小売、金融、物流、IT、医療、建設、中小企業まで8業種37社の具体的なDX推進成功事例を紹介。トヨタ自動車のマテリアルズ・インフォマティクス、セブン&アイ・ホールディングスのAI配送最適化、りそなホールディングスの生成AI活用など、各社が自社の課題に応じた独自のアプローチで成果を上げています。
- DX推進成功の5つの共通ポイントは、経営層の強いリーダーシップ、明確な目的設定と中長期的な視点、データドリブン経営への転換、DX人材の確保・育成と組織体制の構築、内製化を意識したノウハウ蓄積。これらを実践することで、業種や企業規模を問わず成功確率が高まります。
- DX推進組織の構築では、経営直下型、IT部門拡張型、専門組織型、子会社型の4つのモデルから自社に最適な形態を選択し、戦略策定・技術導入・データ基盤構築・人材育成・業務プロセス改革という5つの役割を明確化することが重要です。
- 現状分析と目標設定→DX戦略の策定と優先順位付け→パイロットプロジェクトの実施→全社展開とPDCAサイクルという段階的なロードマップに基づき、3〜5年の中長期計画で推進することで、リスクを抑えながら着実に成果を積み重ねることができます。
- 2025年最新トレンドとして生成AIがDX推進を加速しており、東京電力エナジーパートナーのChatGPT活用事例やDX銘柄企業の先進的な取り組みが注目されています。中小企業でも月額数千円から導入可能な生成AIツールが増え、DXの民主化が進んでいます。
企業の競争力強化に欠かせないDX推進ですが、「何から始めればよいのか」「自社に合った進め方がわからない」と悩む担当者は少なくありません。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」を目前に控え、レガシーシステムの刷新とデジタル変革は待ったなしの状況です。
本記事では、製造業から小売、金融、物流まで8業種37社のDX推進成功事例を詳しく紹介します。トヨタ自動車のマテリアルズ・インフォマティクス、セブン&アイ・ホールディングスの配送最適化、りそなホールディングスの生成AI活用など、具体的な取り組み内容と成果を解説。さらに組織体制の作り方、失敗事例から学ぶ教訓、2025年最新トレンドまで網羅しています。
自社のDX推進計画策定に役立つ実践的な情報を、ぜひ参考にしてください。
DX推進とは?基本概念と必要性を理解する

DX推進を成功させるためには、まずその本質を正しく理解することが重要です。単なるIT化やデジタルツールの導入ではなく、ビジネスモデルそのものを変革し競争優位性を確立する取り組みがDXの真髄といえます。このセクションでは、DXの定義から必要性まで、基本的な概念を解説します。
DX推進の定義と経済産業省のガイドライン
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データとデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務や組織、プロセス、企業文化までも変革し、競争上の優位性を確立することを指します。経済産業省が2018年に発表した「デジタルガバナンス・コード2.0」では、DXを次のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
この定義から分かるように、DX推進は単にシステムを導入するだけでなく、企業全体の変革を伴う包括的な取り組みです。経済産業省と東京証券取引所は、優れたDX推進を実践している企業を「DX銘柄」として毎年選定し、その取り組み内容を公開しています。2024年には54社が選定され、各業界のモデルケースとして注目されています。
DXとデジタル化(デジタイゼーション・デジタライゼーション)の違い
DXを正しく理解するには、デジタイゼーションやデジタライゼーションとの違いを把握することが大切です。これらは段階的に発展する関係にあり、それぞれ異なる目的と効果を持っています。
デジタイゼーション(Digitization)
デジタイゼーションは、アナログ情報をデジタルデータに変換することを指します。具体的には、紙の書類を電子化してPDF保存する、手書きの帳簿をExcelで管理する、写真や音声をデジタルファイル化するといった取り組みです。情報へのアクセス性を向上させ、保管や検索を効率化することが主な目的となります。ただし、この段階では業務プロセス自体は変わりません。
デジタライゼーション(Digitalization)
デジタライゼーションは、デジタル技術を活用して業務プロセスそのものを変革することです。例えば、電子承認システムの導入で承認フローを自動化する、在庫管理システムで発注を最適化する、顧客データベースを構築してマーケティングを効率化するといった取り組みが該当します。業務の効率化や生産性向上を実現し、付加価値を生み出すプロセス改善がこの段階の特徴です。
デジタルトランスフォーメーション(DX)
DXは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化までも変革し、新たな価値を創造することを意味します。顧客体験の革新、新規事業の創出、業界の常識を覆すようなサービスの提供などが含まれます。ユニクロが「情報製造小売業」への転換を目指す取り組みや、セブン&アイ・ホールディングスがAIで配送を最適化する取り組みは、まさにDXの好例といえるでしょう。
つまり、デジタイゼーションとデジタライゼーションはDXを実現するための基盤であり、これらを積み重ねることで真のデジタル変革が可能になります。
DX推進が求められる3つの背景
日本企業においてDX推進が急務とされる背景には、社会構造の変化と市場環境の激変があります。ここでは主な3つの理由を解説します。
少子高齢化による深刻な人手不足
日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっており、2025年には約7,000万人まで減少すると予測されています。人材確保が困難になる中、限られた人員で生産性を維持・向上させるためには、デジタル技術の活用が不可欠です。AIやRPAによる業務自動化、リモートワークの推進による働き方の多様化など、DX推進は人手不足という構造的課題への有効な解決策となります。
消費者行動とビジネス環境の急激な変化
スマートフォンの普及とEコマースの発展により、消費者の購買行動は劇的に変化しました。商品を購入する前に複数のサイトで価格や口コミを比較し、最適な選択をする消費者が増えています。また、コロナ禍を経て非接触サービスやオンライン化への需要が急増しました。こうした変化に対応できない企業は、顧客を競合他社に奪われるリスクに直面しています。デジタルチャネルでの顧客接点強化やデータ活用による顧客理解の深化は、もはや競争力維持の必須条件です。
既存ビジネスモデルの限界と新規事業創出の必要性
VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる予測困難な時代において、従来のビジネスモデルだけでは持続的な成長が難しくなっています。市場の急激な変化に対応するには、データに基づく迅速な意思決定と、新たな価値を生み出すイノベーションが求められます。DX推進により、顧客データの分析から新たなニーズを発掘し、デジタル技術を活用した新規事業を創出することが可能になります。
2025年の崖とレガシーシステムの課題
経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らしたのが「2025年の崖」という問題です。これは、多くの日本企業が抱える老朽化した基幹システム(レガシーシステム)が、2025年を境に深刻な経営リスクになるという指摘です。
1980年代から1990年代に構築されたシステムは、開発に携わった技術者の定年退職により、仕様や構造を理解する人材が社内から失われつつあります。このブラックボックス化により、システムの保守や改修が困難になり、トラブル発生時の対応が遅れるリスクが高まっています。経済産業省の試算では、このままDX推進が進まない場合、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると指摘されています。
さらに深刻なのは、レガシーシステムがDX推進の妨げになっている点です。古いシステムは新しいデジタル技術との連携が難しく、データの一元管理や活用を阻害します。また、システムの保守運用に多額のIT予算が費やされ、新規投資に回す資金が不足するという悪循環に陥っている企業も少なくありません。
こうした状況を打破するため、多くの企業がレガシーシステムの刷新とクラウド移行を進めています。次のセクションからは、実際にDX推進に成功している企業の具体的な事例を業界別に紹介していきます。
【製造業】DX推進事例8選|デジタル技術で生産性向上

製造業は、グローバル競争の激化や人手不足、原材料高騰といった課題に直面しており、デジタル技術を活用した生産性向上と新たな価値創造が不可欠となっています。経済産業省の「ものづくり白書」でも、エンジニアリングチェーンとサプライチェーンへのデータ活用が重要性を増していると指摘されています。このセクションでは、製造業における先進的なDX推進事例8社を詳しく紹介します。
ブリヂストン|匠の技とデジタルの融合による技能伝承
株式会社ブリヂストンは、タイヤ事業を核とする世界的企業として、熟練技能員の高度な技術を次世代に継承するため「技能伝承システム」を開発しました。航空機用タイヤや鉱山・建設車両用タイヤの製造における匠の技を、カメラやセンサーで計測して可視化し、新人の技能習得を支援する仕組みです。従来は言葉や感覚で伝えられていた微妙な技術を、定量的なデータとして記録・分析することで、効率的な技能伝承を実現しています。
さらにブリヂストンは、蓄積したデータをもとにタイヤ摩耗予測技術を開発し、航空会社と協業して航空機用タイヤ交換の効率化にも取り組みました。予測モデルを活用することで、適切なタイミングでのタイヤ交換が可能となり、コスト削減と安全性向上の両立を達成しています。また、高度設計シミュレーターを活用した鉱山車両用タイヤのカスタマイズなど、顧客ニーズに応じた価値創造も進めています。
これらの取り組みにより、ブリヂストンは単なる製品提供から、データとデジタル技術を活用したソリューション提供へとビジネスモデルを進化させています。リアルである匠の技とデジタルを融合させることで、製造業における人材育成とイノベーションの両立という課題に対する一つの解を示しています。
味の素|スマートファクトリー化とサプライチェーン改革
味の素グループは、社会価値と経済価値の共創を目指す経営基本方針「ASV」のもと、食と健康の課題解決企業として全社的なDX推進に取り組んでいます。特に注力しているのが、デジタル技術を活用した工場のスマートファクトリー化です。包装工程管理システムの開発・導入により、従来紙媒体で記録していた作業をアプリに移行し、稼働データの自動記録を実現しました。
このシステム導入により、管理業務の標準化、リモートでの現場管理、迅速なデータ分析が可能になり、工場運営の効率が大幅に向上しました。さらにサプライチェーン全体のデジタル管理にも着手し、需給予測の精度向上や在庫の最適化を推進しています。リアルタイムでのデータ共有により、市場の変化に素早く対応できる体制を構築しています。
味の素グループは、DX人材の増強も重点KPI(重要業績評価指標)として掲げ、教育と採用による人員増強計画を実行中です。デジタル技術を活用した新事業創出プロジェクトも複数進行しており、製品製造だけでなく、顧客により近い価値提供を目指すビジネス変革を推進しています。
トヨタ自動車|マテリアルズ・インフォマティクスによる材料開発DX
トヨタ自動車株式会社は、自動車業界の大変革期を迎える中、材料の研究・開発に情報科学を活用する「マテリアルズ・インフォマティクス」を導入しました。材料解析クラウドサービス「WAVEBASE」を開発し、マテリアルズ・インフォマティクスをコーディングフリーで使用できる環境を整備しています。これにより、材料開発のスピードが飛躍的に向上しています。
従来、人間が感覚的に理解していた材料特性を定量的なデータに変換し、機械学習に活用できるようにしたことが大きな特徴です。材料のデータを蓄積できるデータベースを構築することで、過去の知見を効率的に活用し、新材料開発の試行錯誤を大幅に削減しました。AIによる予測モデルを活用することで、実験回数を減らしながら最適な材料組成を導き出すことが可能になっています。
トヨタ自動車は、この技術を外部にも提供することを決定しました。社会課題の解決に寄与するという基本理念に基づき、日本の産業競争力強化に貢献したいという考えからです。自社の競争力向上だけでなく、業界全体の発展を見据えたDX推進の姿勢は、オープンイノベーションの好例といえます。
パナソニック|データサイエンスを活用したSCM最適化
パナソニックホールディングス株式会社は、「現場プロセスイノベーション」を主力事業として、サプライチェーンマネジメント(SCM)におけるデータ活用に注力しています。特定領域で発生した問題の原因が、実は別の領域にあるケースも少なくないため、サプライチェーン全体を俯瞰してデータ分析を行う体制を構築しました。
パナソニックは、データ駆動型経営を実現するための統合的なITアーキテクチャを設計し、各工程のデータを一元管理できる基盤を整備しています。AIやテクノロジーを活用して課題領域を特定し、サプライチェーン全体の最適化を図ることで、在庫削減とリードタイム短縮を同時に達成しています。従来は経験と勘に頼っていた需給調整を、データに基づく科学的なアプローチに転換しました。
こうしたSCMのDX推進により、市場の変化に迅速に対応できる柔軟な生産体制を構築しています。需要予測の精度向上により欠品や過剰在庫を削減し、顧客満足度の向上とコスト削減を両立させています。パナソニックのアプローチは、複雑なサプライチェーンを持つ製造業にとって参考になる事例です。
IHI|IoTプラットフォームでライフサイクルビジネスを実現
株式会社IHIは、資源・エネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙の4事業分野を展開する総合重工業企業として、「モノ売り」から顧客の成長や成功を支援するビジネスへの転換を図っています。製品のライフサイクル全体を通じて顧客に価値を提供する「ライフサイクルビジネス」の確立を目指し、IoTプラットフォームの開発に取り組みました。
自社開発のIoTプラットフォームで製品や設備のデータを収集・分析し、顧客情報を共有する「カスタマーサクセスダッシュボード」との連携を進めています。これにより、営業、サービス、技術、製造の各部門が一体となって顧客価値を創出できるビジネスモデルを構築しています。製品を納入した後も、稼働状況をモニタリングして最適なメンテナンスを提案するなど、継続的な関係構築が可能になりました。
さらにIHIグループでは、デジタル化によって事業類型の特性に応じた業務プロセス改革を進めています。研修などを通じてデータ重視の企業文化づくりにも注力し、全社員がデータを活用して意思決定できる組織への変革を推進しています。製造業における「モノからコト」へのビジネス転換の好例といえます。
クボタ|農業機械とICTの融合で食料問題に挑戦
株式会社クボタは、食料、水、環境の領域で顧客価値の最大化を志向するグローバル企業として、農業機械とICTの融合による営農支援システムの開発に取り組んでいます。従来から提供してきた自動運転農機やIoTを活用した水環境分野のソリューションをさらに進化させるため、2020年にマイクロソフトコーポレーションと戦略的提携を発表しました。
この提携により、基幹システムをセキュリティレベルの高いクラウドに移行し、データ集約と分析による製品開発や品質向上を加速させています。農業現場で蓄積される膨大なデータを活用し、AIによる最適な作業提案や故障予測など、新たな価値提供を目指しています。グローバルICT本部を中心に、さまざまな経歴を持つ社員がDXをけん引する体制を構築しました。
クボタが注目するのは、食料、水、環境いずれの領域でも今後問題が深化すると予想される中、DXによるイノベーションで社会課題の解決に貢献することです。単なる機械の販売ではなく、データとデジタル技術を活用したトータルソリューションを提供することで、持続可能な農業の実現を支援しています。
ユニ・チャーム|データ活用で顧客インサイトを発掘
ユニ・チャーム株式会社は、不織布と吸収体の専門メーカーとして、DX導入の主な目的を商品開発、改良点の発見、新分野開拓につながる顧客インサイトの発見の3つに定めています。デジタル技術を活用して開発した新サービスに、保育園向けの紙おむつサブスクリプションサービス「手ぶら登園」があります。保育園の紙おむつ在庫を管理して自動で発注・配送するシステムで、保護者の負担軽減と保育園の業務効率化を実現しました。
さらにユニ・チャームは、離れた場所の様子がわかる「デジタルスクラムシステム」を開発し、顧客とのオンラインミーティングでニーズの吸い上げに活用しています。このシステムを使って留守中のペットの行動を観察することで、従来の市場調査では把握できなかった新しい顧客インサイトの発掘にもつながっています。ペット用品の開発において、実際の使用シーンをデータとして蓄積できることは大きなアドバンテージです。
ユニ・チャームのDX推進は、既存製品の改良だけでなく、まったく新しいビジネスモデルの創出にもつながっています。デジタル技術を活用して顧客との接点を増やし、そこから得られるデータをもとに新たな価値を創造するサイクルを確立しています。製造業における顧客起点のイノベーション創出の好例といえます。
島津製作所|DX人材育成プログラムで全社変革
株式会社島津製作所は、DX推進を中期経営計画の成長基盤強化に必要な要素として位置づけ、「ビジネスDX」と「業務DX」の両輪で取り組みを進めています。ビジネスDXでは顧客への情報・サービス提供の拡充を、業務DXではグローバル情報の一元化による業務のスマート化と事業機会の拡大を目指しています。
これらを成功させるため、島津製作所が最も注力しているのがDX人材の育成です。ITスキルに加え、顧客目線・ユーザー視点で物事を考え、ビジネスモデル変革までをも行うことのできる人材が必要と判断し、全部門を対象とした独自の育成プログラムをブレインパッドとともに構築しました。このプログラムでは、データ活用の基礎から実践的なプロジェクト遂行まで、段階的に学べるカリキュラムを提供しています。
島津製作所が目指すのは「データ×価値創造」の実現です。データ活用の楽しさを全社に広め、各部門の社員が自らデータを活用して業務改善や新規事業開発に取り組める組織文化の醸成に力を入れています。DX推進の成否は人材にかかっているという認識のもと、継続的な育成投資を行うことで、持続可能なDX推進体制を構築しています。
【小売・EC業界】DX推進事例5選|顧客体験を革新

小売・EC業界では、消費者の購買行動の変化とオンライン化の加速により、デジタル技術を活用した顧客体験の革新が競争力の源泉となっています。実店舗とオンラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)戦略や、データ活用による顧客一人ひとりに最適化されたサービス提供が重要性を増しています。このセクションでは、小売・EC業界における先進的なDX推進事例5社を紹介します。
セブン&アイ・ホールディングス|攻めと守りのDXで配送最適化
株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、グループDX推進本部とグループDXソリューション本部の2本部体制で、グループを横断したDXを推進しています。まず「守りのDX」として、セキュリティレベルの高い共通インフラ基盤の構築と各種セキュリティ対策を実施しました。本部内にセキュリティの専門人材を集中させ、本部からグループ各社に機能やアドバイスを提供する体制をとることで、効率的なセキュリティ管理を実現しています。
「攻めのDX」の核となるのが、AIを活用した配送最適化の仕組み「ラストワンマイルDXプラットフォーム」です。拡大し多様化する宅配ニーズに対応し、顧客の利便性を向上させながら、配送効率を高めて社会的課題の解決にも貢献しています。AIが配送ルートを最適化することで、ドライバーの負担軽減とCO2排出削減を実現し、持続可能な物流システムの構築を目指しています。
さらにセブン&アイ・ホールディングスは、グループ共通の7iD会員を重要な資産と位置付け、顧客本位のサービス提供の基盤構築に取り組んでいます。会員データを活用したパーソナライズされた情報提供やポイントプログラムの充実により、顧客エンゲージメントの向上を図っています。グループ全体でのデータ活用により、顧客により良い体験を提供する好循環を生み出しています。
ユニクロ(ファーストリテイリング)|情報製造小売業への変革
株式会社ファーストリテイリングは、ユニクロを展開する企業として、製造小売業から「情報製造小売業」へと業態を変革するため、全社改革「有明プロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの核心は、リアルタイムの販売状況にあわせて出荷する仕組みの構築です。来店客の嗜好や人気のコーディネート、買い手が抱く商品の不満などの情報を集め、開発に役立たせ生産量も決めていく取り組みです。
ファーストリテイリングが目指すのは、「作ったものを売るのではなく、消費者が求めるものを作る」ビジネスモデルです。店舗への無人レジ導入やEコマースと実店舗の融合を実現してきた同社は、デジタル技術を活用して顧客視点での業務改革をおこなう「攻めのIT」を推進しています。RFID(無線タグ)を活用した在庫管理の高度化により、リアルタイムでの在庫把握と補充の自動化を実現しています。
新しいビジネスモデルの構築に向けて、部署を隔てる壁が一切ない有明本部に本社機能を移転させ、デジタル時代にふさわしい企業文化の創造にも取り組んでいます。物理的な空間設計からコミュニケーションの活性化を図り、部門横断でのデータ活用とイノベーション創出を促進する組織づくりを進めています。
ニトリホールディングス|データ活用の内製化で競争力強化
株式会社ニトリホールディングスは、「お、ねだん以上。」のブランドで知られる家具・インテリア小売大手として、データ活用の内製化に注力しています。当初はデータの抽出からブレインパッドが支援していましたが、現在は様々な指標の集計や施策の効果検証まで、通常の業務の中で必要なデータ分析をすべて内製化することに成功しました。
ニトリホールディングスの内製化戦略の特徴は、外部パートナーとの協業を通じてノウハウを蓄積し、段階的に自社で対応できる範囲を広げていった点にあります。初期段階では専門家のサポートを受けながら基礎を固め、徐々に社内人材のスキルを向上させることで、最終的には独力でデータ分析ができる体制を構築しました。この approach により、分析のスピードが向上し、ビジネス判断の迅速化につながっています。
データ活用の内製化により、ニトリホールディングスは市場の変化に素早く対応できる体制を確立しています。顧客の購買データや商品の売れ筋分析をリアルタイムで行い、商品開発や在庫管理に活かすことで、顧客ニーズに的確に応える商品ラインナップを実現しています。内製化による知見の蓄積は、持続的な競争優位性の源泉となっています。
ファミリーマート|ファミペイを起点とした顧客接点強化
株式会社ファミリーマートは、外部から招いたプロ人材のリードによって短期間で立ち上げたスマートフォン決済サービス「ファミペイ」を皮切りに、顧客の利便性向上と店舗業務の省力化につながるDXを推進しています。ファミペイは単なる決済手段ではなく、顧客とのデジタル接点を構築し、購買データを蓄積する重要なプラットフォームとして機能しています。
ファミリーマートは、ファミペイで収集した顧客データを活用し、一人ひとりの購買傾向に応じたクーポンやキャンペーンを配信しています。これにより、顧客満足度の向上と来店頻度の増加を実現しています。また、デジタルチラシの配信や予約機能の追加など、顧客にとって便利な機能を継続的に拡充することで、アプリの利用率向上を図っています。
店舗運営面では、セルフレジの導入拡大やバックオフィス業務のデジタル化により、従業員の負担軽減を進めています。人手不足が深刻化する中、デジタル技術を活用した省力化は不可欠です。ファミリーマートのDX推進は、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現する好例といえます。
資生堂ジャパン|EC×オウンドメディアでパーソナル体験を提供
資生堂ジャパン株式会社は、ECサイトとオウンドメディアを融合させることで、顧客一人ひとりに最適な接客体験を提供するDXを推進しています。美容に関する情報を発信するオウンドメディアと、自社ECサイトを連携させることで、情報収集から購入までシームレスな顧客体験を実現しました。顧客の閲覧履歴や購買データをもとに、パーソナライズされたコンテンツや商品推奨を行っています。
資生堂ジャパンの特徴的な取り組みとして、AIを活用した肌診断サービスや、バーチャルメイクアップ機能があります。スマートフォンのカメラで顔を撮影するだけで、肌の状態を分析して最適なスキンケア商品を提案したり、様々な化粧品を試した仕上がりをバーチャルで確認できたりするサービスです。実店舗に行かなくても、デジタル上で専門的なアドバイスを受けられる体験を提供しています。
こうしたデジタル接客の充実により、資生堂ジャパンはオンラインでも高い顧客満足度を実現しています。実店舗での対面接客の良さを維持しながら、デジタルならではの利便性を加えることで、顧客に新しい価値を提供しています。化粧品業界における顧客体験革新の先進事例として注目されています。
【金融・保険業】DX推進事例5選|フィンテックで業界変革

金融・保険業界は、フィンテックの進歩と異業種からの参入により、デジタル技術を活用した顧客体験の革新と業務効率化が急務となっています。AI、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの先端技術を活用し、従来の金融サービスを刷新する取り組みが加速しています。このセクションでは、金融・保険業界における先進的なDX推進事例5社を紹介します。
りそなホールディングス|内製化とLLM活用で地方創生
株式会社りそなホールディングスは、2020年にDX推進室を立ち上げ、データ活用の内製化を積極的に進めています。特に注目すべきは、大規模言語モデル(LLM)を活用したプロジェクトの推進です。数百時間に及ぶ人事の組織診断の自由記述アンケート集計を、ChatGPTによる分類と自動解析により大幅に効率化し、業務オペレーションの改革を実現しました。従来は人手で行っていた膨大なテキストデータの分類作業を、生成AIが数時間で処理できるようになっています。
りそなホールディングスは、データ利活用施策、人材育成、環境構築を並行して展開することで、包括的なDX推進を実現しています。実務に直結する半年間の育成カリキュラム「データ活用人材育成プログラム」を実施し、専門知識のない多様な事業部からの希望者がデータ活用スキルを習得できる体制を整えました。この取り組みにより、各部署でデータを活用した業務改善が進んでいます。
地方創生への貢献も、りそなホールディングスのDX推進の重要な柱です。地域企業のデジタル化支援や、データを活用した地域経済分析など、金融機関としての知見とデジタル技術を組み合わせた社会貢献活動を展開しています。内製化によって蓄積したノウハウを地域に還元することで、持続可能な地域経済の発展に寄与しています。
静岡銀行|データ利活用と人材育成を並行展開
株式会社静岡銀行は、データ利活用施策、人材育成、環境構築を三位一体で推進することで、実効性の高いDXを実現しています。データ分析基盤の整備と並行して、行員がデータを活用できるスキルを身につけるための教育プログラムを展開し、組織全体のデータリテラシー向上に取り組んでいます。段階的な育成プログラムにより、初心者から上級者まで幅広い層のスキルアップを支援しています。
静岡銀行の特徴的な取り組みとして、顧客データを活用したパーソナライズされた金融商品の提案があります。顧客の属性や取引履歴、ライフイベントなどのデータを分析し、一人ひとりに最適なタイミングで最適な商品を提案する仕組みを構築しました。これにより、顧客満足度の向上と営業効率の改善を同時に達成しています。
さらに静岡銀行は、デジタルチャネルの充実にも注力しています。スマートフォンアプリでの口座開設や各種手続きの簡素化、AI チャットボットによる24時間対応の顧客サポートなど、顧客の利便性を高めるサービスを次々と導入しています。デジタルネイティブ世代のニーズに応えることで、新規顧客の獲得にもつながっています。
ゆうちょ銀行|データ分析専門組織の立ち上げ
株式会社ゆうちょ銀行は、DXの推進に際して、データ活用・分析業務を自走化することが重要であると考え、データ活用と分析の自走化に向けた体制と役割を確立するための分析専門組織を立ち上げました。この組織は、全社のデータ分析ニーズに対応し、各部署のデータ活用を支援する役割を担っています。専門組織を設置することで、データ分析のノウハウが組織内に蓄積され、継続的な改善が可能になっています。
ゆうちょ銀行は、データサイエンスの基礎知識を身につけるための全体学習を推進し、各部署から募ったプロジェクトメンバーが分析テーマを設定するとともに、ブレインパッドからのフィードバックを受けて実践的な学びを深めています。座学だけでなく、実際の業務データを使った演習を取り入れることで、実務に直結するスキルの習得を目指しています。
分析専門組織の活動により、ゆうちょ銀行では顧客セグメント分析に基づくマーケティング施策の高度化や、不正取引検知の精度向上など、具体的な成果が生まれています。データ分析の民主化を進めることで、現場の社員が自らデータを活用して業務改善を提案できる文化が育ちつつあります。
ビューカード|顧客体験と従業員体験の両輪DX
株式会社ビューカードは、JR東日本グループのクレジットカード会社として、DX内製化により顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の向上を同時に実現しています。当初はデータの抽出からブレインパッドが支援していましたが、現在は様々な指標の集計や施策の効果検証まで、通常の業務の中で必要なデータ分析をすべて内製化しています。
ビューカードのDX推進の特徴は、顧客向けサービスの改善と社内業務の効率化を同時に進めている点です。顧客データの分析により、カード会員一人ひとりの利用傾向に応じたキャンペーンやポイント還元施策を展開し、顧客満足度を向上させています。同時に、社内のデータ分析業務を自動化することで、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えています。
内製化により、市場の変化や顧客ニーズの変動に迅速に対応できる体制を構築しました。データ分析のリードタイムが短縮されたことで、PDCAサイクルを高速で回すことが可能になり、施策の効果を素早く検証して改善につなげています。ビューカードのアプローチは、中堅企業における実践的なDX内製化の好例といえます。
クレディセゾン|生成AIで業務変革と顧客体験創出
株式会社クレディセゾンは、ペイメント・ファイナンス事業などを展開する総合金融サービス企業として、生成AIを活用した業務変革や新たな顧客体験の創出を通じて、全社的なDXの実現と組織のイノベーション力向上に取り組んでいます。2024年のDX銘柄選定企業として、先進的な取り組みが評価されています。
クレディセゾンは、生成AIを活用してコールセンター業務の効率化や、顧客からの問い合わせ内容の分析を行っています。AIが過去の対応履歴を学習することで、オペレーターへの回答候補の提示や、よくある質問への自動応答が可能になりました。これにより、顧客の待ち時間短縮とオペレーターの負担軽減を同時に実現しています。
さらにクレディセゾンは、生成AIを活用した新しい顧客体験の創出にも挑戦しています。チャットボットによる対話形式での金融商品の提案や、顧客の状況に応じたパーソナライズされたアドバイスの提供など、従来の金融サービスにはなかった価値を提供しています。生成AIの活用により、24時間365日、一人ひとりに寄り添ったサービスの提供が可能になっています。
【物流・運輸業】DX推進事例5選|2024年問題を乗り越える

物流・運輸業界は、「2024年問題」と呼ばれるドライバーの労働時間規制強化により、デジタル技術を活用した業務効率化と配送最適化が喫緊の課題となっています。グローバル競争の激化を背景に、サプライチェーン全体を最適化するサプライチェーンマネジメントの必要性も高まっています。このセクションでは、物流・運輸業界における先進的なDX推進事例5社を紹介します。
SGホールディングス|物流DXを成長戦略の中核に
SGホールディングスグループは、佐川急便などを擁する物流大手として、2030年ビジョン「新しい物流で、新しい社会を共に育む」の実現に向けて、DXを成長戦略の中核に据えています。2025年のDXグランプリ企業に選定されるなど、業界をリードする取り組みが高く評価されています。物流業務からバックオフィスまで全社的な変革を進め、デジタル技術を活用した新たな価値創造に挑戦しています。
SGホールディングスの特徴的な取り組みとして、AIを活用した配送ルートの最適化や、IoTセンサーによる荷物の状態管理があります。リアルタイムでの配送状況の可視化により、顧客への正確な配達時刻の通知が可能になり、再配達率の削減にもつながっています。また、倉庫内作業の自動化やロボット導入により、人手不足への対応と作業効率の向上を実現しています。
さらにSGホールディングスは、グループ全体でのデータ連携基盤を構築し、サプライチェーン全体の最適化を図っています。荷主企業の在庫情報や販売予測データと連携することで、より効率的な物流計画の立案が可能になりました。物流DXによる社会課題の解決と、持続可能な物流システムの構築を目指す取り組みは、業界全体の模範となっています。
伊藤忠商事|AI自動発注で流通サプライチェーン最適化
伊藤忠商事株式会社は、食品サプライチェーンのDXによる最適化を重要施策と位置づけ、2020年よりグループ会社である日本アクセスとの間で、一部の物流拠点における小売店の販売データ等を活用した需要予測と発注自動化の実証実験を実施しました。人工知能(AI)を活用したメーカー向け自動発注システムの開発により、食品ロスの削減と業務効率化を両立させています。
このシステムは、小売の業務データ(在庫・売上・発注)と卸の業務データ(在庫・入出荷・商品毎の発注ロット)に加え、天候データやカレンダー情報を入力値として機械学習モデルを構築しています。メーカーが要求する発注ロット単位での推奨発注値を算出し、既存の発注システムにデータ転送することで、人の判断を介さない自動発注を実現しました。需要予測の精度向上により、欠品と過剰在庫の両方を削減しています。
伊藤忠商事の取り組みは、食品流通分野におけるデータ活用の先進事例として注目されています。サプライチェーン全体でデータを共有し、AIを活用して最適化を図ることで、業界全体の効率化と持続可能性の向上に貢献しています。今後は対象商品や拠点の拡大を進め、食品流通DXのスタンダードモデルの確立を目指しています。
ヤマト運輸|レコメンド機能でCTRが100倍に向上
ヤマト運輸株式会社は、宅急便の送り状や請求書・納品書などのビジネス向けツールを提供する会員制のポータルサイト「ヤマトビジネスメンバーズ」において、サービスの拡充とインターフェースの刷新を実施しました。サイトリニューアルの際に、顧客の属性や利用履歴に応じて表示するサービスを出し分けるレコメンド機能を盛り込むことで、顧客体験の大幅な向上を実現しています。
ヤマト運輸は、ブレインパッドが提供する自動接客プラットフォーム「Rtoaster」の「ユーザー分析機能」を用いて最適な顧客セグメントの抽出を行いました。その結果、トップページのCTR(クリック率)が導入前の0.01%から1%程度にまで劇的に向上し、約100倍の改善を達成しました。サービス申し込み件数も5倍に向上し、セグメント抽出の方法やレコメンド機能の効果が明確になっています。
この成功により、ヤマト運輸は顧客一人ひとりにふさわしいサービスを提供するというビジョンを実現しつつあります。データ活用により、膨大な数の顧客それぞれに最適な情報を届けることが可能になり、顧客満足度の向上とビジネス成果の創出を両立させています。物流業界におけるデジタルマーケティングの好例といえます。
JR九州|顧客分析基盤刷新でDX戦略を加速
九州旅客鉄道株式会社(JR九州)は、鉄道事業を中心として、駅ビル開発などの不動産業やホテル事業など、九州全域にわたる総合的なまちづくりを推進する事業を展開しています。同社が推進するグループDX戦略においては、ポイントサービス「JRキューポ」を軸に、グループ全体・多様な外部プレイヤーとのデータ連携・データ活用を推進していく方針を掲げています。
従来のシステムではデータ加工・データ抽出が長時間に及ぶことに加え、内製にて顧客分析を行うのが難しいといった課題が顕在化していたため、顧客分析基盤の刷新が行われました。データ処理の実装方法の変更による処理速度の大幅改善に加え、可視化・分析ツールや施策・アクションツールとのシステム連携がよりスムーズになることを目標に設定しました。
ベンダーフリーであるブレインパッドの特徴を活かし、パッケージ型のCDPではなく、高いカスタマイズ性を有し大容量データに対する高速処理が可能な「Snowflake」と「AWS」を連携させました。フレキシブルにスペックを変更できること、データ処理の柔軟性が向上することを担保し、今後も長く使い続けることができる拡張性の高いシステム設計および基盤構築を実現しています。
ソフトバンク|AIでLPガス配送を最適化するRoutify
ソフトバンク株式会社は、社会インフラ課題をデータで解決する新サービス「Routify(ルーティファイ)」を開発しました。LPガス容器の配送を最適化するこのサービスは、LPガス事業者が保有するデータ(検針データ、車両・配送員データなど)と、道路情報や天候などの外部データを活用しています。AIがLPガス容器内の残量を予測することで、その予測に基づいた最適な配送計画・配送ルートを自動で策定可能にしています。
従来、LPガスの配送員は勘や経験によって配送計画やルートを策定していましたが、「Routify」を導入することにより、自動で策定された配送先リストや配送ルートを配送員向けアプリ(ハンディーターミナルやスマホに対応)で確認するだけで、最小限の移動で効率的に配送業務を行うことができます。ガス残量のばらつきが少ない状態で容器を回収できることで、配送回数の削減とCO2排出量の削減も実現しています。
ソフトバンクの「Routify」は、配送員の勘と経験をデータから導き出すという発想の転換により、人手不足に悩む業界の課題解決に貢献しています。熟練配送員のノウハウをデータ化してAIモデルに学習させることで、経験の浅い配送員でも効率的な配送が可能になりました。社会インフラを支える業界のDX推進モデルとして、他業界への横展開も期待されています。
【IT・情報通信業】DX推進事例3選|先進技術で社会課題解決

IT・情報通信業界は、デジタルネイティブな企業が多く、他業界と比較してDX推進が進んでいる分野です。自社で培ったデジタル技術とノウハウを外販する動きも加速しており、日本全体のDX推進を牽引する役割を担っています。このセクションでは、IT・情報通信業界における先進的なDX推進事例3社を紹介します。
ヤフー|マルチ・ビッグデータのプラットフォーム外販
ヤフー株式会社は、検索、ニュース、動画、天気、メール、eコマース、地図など多様なサービスを展開しており、これらのサービスからは顧客の属性データや行動履歴をはじめ、膨大なビッグデータが得られます。こうしたマルチ・ビッグデータを企業や自治体で活用してもらい、日本企業のDX推進に貢献すべくデータソリューション事業を展開しています。
ヤフーの特徴的な取り組みとして、プライバシー保護を前提としながら、顧客データを統合・分析・活用し、顧客とのエンゲージメントを強固にする「Yahoo! Data Xross」(YDX)があります。トレジャーデータが国内外450社以上に提供している顧客データ活用サービス「Treasure Data CDP」内に格納されたデジタル広告やメール配信、アプリプッシュ通知の履歴などの企業が保有する顧客データを、プライバシー保護を最重視した安全な環境で取り扱い、Yahoo! JAPANが保有する購買意向や興味関心などのデータを用いて分析ができます。
YDXにより、企業は自社の顧客データにヤフーの豊富なデータを掛け合わせることで、より精度の高い顧客分析やターゲティングが可能になります。例えば、自社ECサイトの購買データとヤフーの検索データを組み合わせることで、潜在顧客の発掘や効果的なマーケティング施策の立案につながります。ヤフーのデータソリューション事業は、日本企業のマーケティングDXを支える重要なインフラとなっています。
ニフティ|パーソナライゼーションでCTR4倍・CVR2.3倍
ニフティ株式会社は、月間5,300万PV、UU250万人を誇る国内有数のポータルサイト「@niftyトップページ」を運営しています。当時の課題は、「同じ社内でありながら、属性データと行動データが個別管理されている」ことでした。この課題を解決するため、自動Web接客ツール「Rtoaster」を導入し、これらのデータを統合させ、よりパーソナライズされたサービスを提供できるようになりました。
Rtoasterの導入後、CTR(クリック率)は4倍、CVR(コンバージョン率)は2.3倍に増加し、コンテンツ販売の月間売上は10%増加しました。これらの成果は、RtoasterがWebページ内にタグを1つ埋め込むだけで、すぐにコンテンツの出し分けやリターゲティングなどの施策がスタートできるという特性によるものです。ユーザーの属性や行動履歴に基づいて、一人ひとりに最適なコンテンツを表示することで、ユーザーエンゲージメントが大幅に向上しました。
ニフティの事例は、パーソナライゼーションがもたらす具体的な成果を示す好例です。データを統合して顧客を深く理解し、適切なタイミングで適切な情報を提供することで、顧客満足度とビジネス成果の両方を向上させることができます。中堅規模のWebサービス事業者にとって、参考になる取り組みといえます。
トプコン|医食住の3領域でICT×AIソリューション
株式会社トプコンは、精密光学、GNSS(全地球測位システム)、3次元計測、センシング、制御などに独自の高い技術を持っています。それらをベースにIoTとネットワーク技術を活用し、「医食住」3つの事業領域で社会的課題の解決を目指しています。各領域で深刻化する課題に対して、デジタル技術を活用したソリューションを提供しています。
「医」の領域では、高齢化の進展にともなう眼疾患の増加と眼科医の不足に対して、フルオート検査機器とICTの活用による遠隔診断やAI自動診断を実現しました。地方でも都市部と同等の質の高い眼科医療を受けられる環境を整備し、医療格差の解消に貢献しています。「食」の領域では、世界的な食糧不足への懸念に対して、デジタルデータによる営農プロセスの一元管理というソリューションを提供しています。精密農業の実現により、収穫量の増加と環境負荷の低減を同時に達成しています。
「住」の領域では、インフラ需要拡大と建設技能者の不足に対して、ICT自動化施工システムの開発、建設フローのデジタルデータ化で問題解決に貢献しています。建設機械の自動制御により、熟練技能者でなくても高精度な施工が可能になり、人手不足への対応と生産性向上を実現しています。トプコンのDX推進は、社会課題の解決とビジネス成長を両立させる好例です。
【医療・製薬業】DX推進事例3選|健康寿命延伸に貢献

医療・製薬業界は、超高齢社会における健康寿命の延伸と医療費の適正化が重要課題となっており、AIやビッグデータを活用した診断支援と創薬の効率化が加速しています。厚生労働省も「医療DX令和ビジョン2030」を掲げ、全国医療情報プラットフォームや電子カルテの標準化を推進しています。このセクションでは、医療・製薬業界における先進的なDX推進事例3社を紹介します。
昭和大学|マルチモーダルAIで歯科医療の診断精度向上
昭和大学は、健康寿命の延伸を目指し、画像を含めたマルチモーダルAIによる診断支援システムの開発により、医師の診断精度を向上させる取り組みが行われています。画像・テキストなど複数形式のマルチモーダルAIによる検索システムと埋伏歯早期発見システムの開発に取り組み、口腔の写真データから埋伏歯を自動的に抽出する研究を進めています。
従来、埋伏歯(歯茎の中に埋まっている歯)の発見には歯科医師の経験と勘が重要でしたが、マルチモーダルAIを活用することで、経験の浅い歯科医師でも高精度な診断が可能になります。AIが口腔内の画像を解析し、埋伏歯の位置や状態を可視化することで、適切な治療計画の立案を支援します。また、過去の症例データベースと照合することで、類似症例の治療経過を参考にした診断も可能になっています。
このAI活用の先進的な取り組みは、2024年12月に画像認識応用技術の学会「ViEW2024」にてブレインパッドと共同発表が行われ、医療関係者に注目されています。昭和大学の取り組みは、AIによる診断支援が医療の質を向上させ、健康寿命の延伸に貢献する可能性を示しています。今後は他の診療科への横展開も期待されています。
ノバルティスファーマ|各部署にデータ分析エバンジェリストを育成
ノバルティスファーマ株式会社は、2023年にデータ利活用を推進するCustomer Data and Analytics部を立ち上げ、薬剤情報の提供にとどまらず、医療従事者の抱える課題を解決する顧客体験の提供を目指しています。分析系、データ系、人材系の3つの軸で取り組みを進め、組織全体のデータ活用能力の向上を図っています。
特に注目すべきは、人材系の施策「Analytics boot camp(ABC)」です。社内の各部署でデータ分析を担うエバンジェリストを育成するプログラムで、研修、コミュニティ運営、データ分析支援の3つの取り組みを平行して実施しています。この取り組みにより、メンバーが自ら率先して日常業務のデータフローを定義し、データ分析を進める風潮を組織に根付かせることに成功しています。各部署にデータ分析のスキルを持つ人材を配置することで、現場主導のデータ活用が促進されています。
ノバルティスファーマは、分析系の取り組みとして、製品の処方実績に寄与する要因を分析し、アナリティクスユースケースの情報共有を行っています。また、データ系の取り組みでは、クラウドベースのデータ活用プラットフォームの構築、BIツールによる身近なデータ分析環境の整備を進めています。これらの取り組みにより、データに基づく意思決定が組織全体に浸透しつつあります。
第一三共|AI・ビッグデータで創薬プロセスを効率化
第一三共株式会社は、医薬品の研究開発、製造、販売を行うグローバル製薬企業として、デジタル技術を活用した創薬プロセスの効率化やデジタルヘルスケア分野での新たな価値創造に注力しています。AI、ビッグデータ、IoTを活用した創薬プロセスの効率化に取り組み、新薬開発のスピードアップとコスト削減を実現しています。
第一三共は、ビッグデータやAIを用いた治療薬や治療法の最適化研究を推進しています。膨大な臨床データや研究データをAIで解析することで、新薬候補物質の発見や、既存薬の新たな適応症の発見を加速させています。また、患者の疾患管理をサポートするデジタルヘルスケアソリューションの開発にも取り組み、薬剤提供だけでなく、患者の健康管理全体を支援するサービスの展開を進めています。
さらに第一三共は、研究開発、製造、営業などの社内業務プロセス改革へのデジタル技術の活用も進めています。デジタル人材の確保・育成と全社横断的なデジタル推進体制の構築により、組織全体のデジタル化を推進しています。製薬業界において、創薬から患者支援まで一貫したDX推進を実現している好例といえます。
【建設・不動産業】DX推進事例3選|人材不足を技術で解決

建設・不動産業界は、深刻な人材不足と技能継承の課題に直面しており、AIやIoT、ロボット技術を活用した省力化と品質向上が急務となっています。国土交通省も i-Construction を推進し、建設生産プロセス全体のデジタル化を後押ししています。このセクションでは、建設・不動産業界における先進的なDX推進事例3社を紹介します。
大成建設|BIM/CIM・AI・IoT・ロボット活用で生産性向上
大成建設株式会社は、建築・土木工事から開発、エンジニアリングなどを手掛ける総合建設会社として、「経営基盤」「生産プロセス」「サービス・ソリューション」の3つの分野でDX推進に注力しています。経営基盤のDXでは、生産プロセスや社内各部門のデータをつなぐプラットフォームを構築し、AIと連携して活用できる環境を整備しました。全社でデータを共有し活用することで、迅速な意思決定と業務効率化を実現しています。
生産プロセスのDXでは、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)やAI、IoT、ロボットなどを活用し、社内データ集積による技術伝承を進めています。特に注目すべきは、AI画像認識技術を活用したコンクリート打継面評価技術で、品質管理の高度化や省力化を実現しました。従来は熟練技術者が目視で行っていた品質チェックをAIが代替することで、客観的で安定した品質管理が可能になっています。
また、VRを活用した切羽観察システム「T-KIRIHA VR」の導入により、山岳トンネル工事の安全性が向上しました。危険な現場に立ち入ることなく、VR空間で地質状況を確認できるため、技術者の安全確保と正確な判断が両立できます。大成建設のDX推進は、建設業界における人材不足と安全性向上の両課題に対する解決策を示しています。
八千代エンジニヤリング|AIでコンクリート護岸劣化を自動判定
八千代エンジニヤリング株式会社の重要な業務の一つに、河川のコンクリート護岸の点検・改修があります。洪水を始めとした災害対策として設置されているコンクリート護岸は、定期的に点検と改修を必要としますが、従来は人間による目視主体で劣化状況を点検していたため、手間やコストが膨大になっていました。また、劣化状況の判断基準が属人的であり、担当者によってまちまちであることも課題でした。
八千代エンジニヤリングは、ブレインパッドとともに、コンクリート護岸の撮影画像から劣化を検知するアプリケーションを構築しました。ディープラーニングを用いたアルゴリズム(ニューラルネットワークモデル)を実装しており、人手による点検と遜色ない精度を実現することに成功しています。AIによる自動判定により、現場での対応工数を5分の1へ削減できました。
さらに重要なのは、全区間の評価を行うことで人よりも高い精度の定量的な評価が可能になった点です。人間が目視で点検する場合、すべての区間を詳細にチェックすることは時間的・体力的に困難ですが、AIであれば膨大な画像を短時間で高精度に分析できます。八千代エンジニヤリングの取り組みは、社会インフラの維持管理におけるDX活用の好例といえます。
野村不動産ソリューションズ|パーソナライズで顧客体験向上
野村不動産ソリューションズ株式会社は、不動産仲介や不動産コンサルティングを手掛ける企業として、Webサイトのパーソナライズ高度化に取り組んでいます。不動産という高額で重要な買い物において、顧客は膨大な情報の中から自分に合った物件を探し出さなければならず、その労力は相当なものです。この課題を解決するため、BtoC向けマーケティングオートメーション「Probance(プロバンス)」を導入しました。
Probanceの導入により、おすすめ物件以外にもセミナー情報や不動産市場動向、物件の値下げ通知など、顧客ごとによりパーソナライズされた情報の提供を実現しました。顧客の閲覧履歴や検索条件、問い合わせ内容などのデータを分析し、一人ひとりの興味関心に合わせた情報を適切なタイミングで届けることで、顧客満足度の向上と成約率の改善につながっています。
また、野村不動産ソリューションズは、Webサイトに「こだわりハッシュタグランキング」機能を実装し、顧客が重視する条件(駅近、南向き、ペット可など)から物件を探しやすくする工夫も凝らしています。顧客の検索行動データから人気のこだわり条件を可視化し、物件探しの新しい体験を提供しています。不動産業界におけるデジタル技術を活用した顧客体験革新の先進事例です。
【中小企業】DX推進事例5選|規模に応じた実践的アプローチ

中小企業におけるDX推進は、大企業とは異なる制約の中で進める必要があり、限られたリソースで最大の効果を生み出す実践的なアプローチが求められます。経済産業省も「DXセレクション」を通じて中小企業のモデルケースを紹介し、横展開を促進しています。このセクションでは、中小企業における先進的なDX推進事例5社を紹介します。
飲食業A社|AI来客予測で売上5倍・利益50倍を達成
従業員数約40名の老舗飲食店A社は、現在の社長が事業を継承したことを機に、天気や売り上げなどのデータをパソコンに手作業で入力し、データ活用の取り組みを始めました。当初は表計算ソフトでの管理でしたが、徐々にデータ分析の重要性を認識し、専門の人材を獲得して従業員への継続的な教育を実施しました。データドリブン経営への転換により、経験と勘に頼っていた意思決定を、データに基づく科学的なアプローチに変革しています。
A社は自社開発のAIツールを用いて来客数予測や経営データの一覧表示が可能なツールを開発しました。天候、曜日、イベント、過去の来客データなどを機械学習モデルに投入し、精度の高い来客予測を実現しています。この予測をもとに食材の仕入れ量を最適化することで、食品ロスの削減とコスト削減を達成しました。その結果、従来と比較して客単価3.5倍、売り上げ5倍、利益50倍という驚異的な成長を実現しています。
さらにA社は、DXの過程で開発したツールを活用して関連会社を設立し、他の飲食事業者の支援にも取り組んでいます。自社で培ったノウハウを他社に提供することで、業界全体のDX推進に貢献するとともに、新たな収益源の創出にもつながっています。中小企業が独自開発のツールで大きな成果を上げた好例といえます。
サービス業B社|紙業務のクラウド化で業務効率大幅改善
貨物運送や自動車の輸送、機械器具の設置工事を手掛けるB社では、業務の属人化やブラックボックス化が長らく課題でした。特定の社員しか理解していない業務プロセスや、紙ベースで管理されている情報が散在しており、情報共有や業務の標準化が困難な状況でした。この問題に対処するため、IT経営の専門家と協力し、自社の経営ビジョンを明確化し、5年後の実現を目指してDXへの取り組みを進めています。
B社の取り組みの核心は、紙で管理・運用していた業務プロセスをクラウドの運用に切り替え、各業務システムとデータを連携させたことです。受注管理、配車管理、請求管理などのシステムをクラウド上で統合し、リアルタイムでの情報共有を実現しました。これにより、本社と遠隔地の拠点間での情報連携がスムーズになり、意思決定のスピードが向上しています。
さらにB社は、会社全体で業務改革に取り組む体制を構築し、効率化に成功しています。遠隔地の拠点を含めた全社でのデータ共有により、業務の標準化と属人化の解消が進みました。中小企業がIT経営の専門家と協力しながら、段階的にDXを進めた好例であり、限られたリソースでも実効性の高いDX推進が可能であることを示しています。
製造業C社|IT×現場知見の融合チームで課題解決
輸送用機械器具を製造している従業員数約200名のC社は、DXを推進するため、製造現場を熟知するメンバーとITエンジニアからなるチームを組織し、現場の課題解決に取り組みました。製造現場の実情を理解したメンバーとIT技術に精通したメンバーが協力することで、実用性の高いシステム開発が可能になっています。
C社では、製品を製造する部署間での情報連携のミスにより、工程に不具合や誤りが生じるという問題がありました。この課題を克服するために、入力されたデータとサーバー側の情報を照合するシステムを導入し、属人的なエラーを未然に防ぐ措置を講じました。バーコードやRFIDタグを活用した部品管理システムにより、どの部品がどの工程にあるかをリアルタイムで把握できるようになり、工程間の連携ミスが大幅に減少しています。
さらにC社は、製造設備のシステム制御を強化し、不良品の発生を削減しています。また、eラーニングの活用により社員の学習コンテンツを制作し、社内で広く利用しています。重要なのは、現場の経験とIT技術のどちらの知見も活かし、それらを融合させて事業の運営に生かすことです。C社のアプローチは、中小製造業におけるDX推進の実践的なモデルといえます。
サービス業D社|AI外観検査システムを自社開発
配管・油圧・メンテナンス事業を展開する従業員数約30名のD社は、近年の油圧式機器のメンテナンス需要減少を受け、電気駆動式への市場のシフトに応じて、AIを活用した外観検査システムの自社開発に成功し、新たな市場に参入しました。小規模企業でありながら、先端技術を活用した新規事業の創出に挑戦した好例です。
D社が開発したAI外観検査システムは、スマートフォンやMR(Mixed Reality:複合現実)を利用して部品検査が可能で、自社のサービス向上に役立てるとともに、サブスクリプションモデルで他社への販売も行っています。従来は熟練検査員の目視に頼っていた外観検査を、AIが代替することで、検査の客観性と効率性が向上しました。また、MR技術を組み合わせることで、検査結果を現実空間に重ねて表示し、直感的な理解を可能にしています。
開発プロセスの透明化と効率化を図るため、ソフトウェア開発プラットフォームのGitHubを使用し、タイにあるラボと日本との間でのグローバル開発を効率よく進めています。小規模企業でありながら、クラウドツールを活用して国際的な開発体制を構築したことも特筆すべき点です。D社の事例は、中小企業が新技術を活用して新規事業を創出する可能性を示しています。
製造業E社|デジタル拠点でオンライン情報発信
たれやだし、スープの製造メーカーである従業員数約50名のE社は、地域に根付いた食の拠点となることを目指し、キッチンスペースをオープンしました。この拠点には、料理教室や試食会ができるセントラルキッチン、動画やライブの配信に対応したオープンキッチン、商品のスチール撮影が可能なスタジオなど、DXを推進するための設備が備わっています。
E社は、デジタルサイネージやVR/ARなどデジタル技術も備え、オンライン上で情報発信して顧客を増やすことに成功しました。料理教室の様子をライブ配信することで、遠方の顧客も参加できるようになり、顧客接点が大幅に拡大しています。また、商品のレシピ動画をSNSで発信することで、ブランド認知度の向上と新規顧客の獲得につながっています。デジタルとリアルを融合させたハイブリッド型の顧客体験を提供しています。
新型コロナウイルス感染症の蔓延により打撃を受けた飲食事業者に、情報発信や商品開発の支援を行っているのもE社の特徴です。自社の施設とノウハウを地域の飲食事業者に開放し、共同でのプロモーション活動や商品開発を支援することで、地域全体の活性化に貢献しています。中小企業がデジタル技術を活用して地域貢献と事業成長を両立させた好例といえます。
DX推進の成功事例に共通する5つのポイント

これまで紹介してきた37社のDX推進成功事例を分析すると、業種や企業規模を超えて共通する成功要因が浮かび上がってきます。単なるデジタルツールの導入ではなく、組織全体の変革を伴う取り組みとして、計画的かつ継続的に推進していることが成功の鍵となっています。このセクションでは、DX推進を成功させるための5つの重要なポイントを解説します。
経営層がリーダーシップを発揮しトップダウンで推進
成功している企業に共通する最も重要な要素は、経営層が強いリーダーシップを発揮してDX推進を主導していることです。DXは単なるシステム導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化の変革を伴う全社的な取り組みであるため、経営トップのコミットメントが不可欠です。セブン&アイ・ホールディングスやSGホールディングスなど、DXグランプリに選定された企業は、いずれも経営層が明確なビジョンを示し、DXを経営戦略の中核に据えています。
経営層がDX推進の必要性と目標を明確に示すことで、組織全体が同じ方向を向いて取り組むことができます。また、部門間の利害調整や予算配分においても、経営層の強い意志があることで円滑に進みます。トップダウンでの推進により、全社横断的なデータ活用基盤の構築や、部門を超えた業務プロセスの見直しが可能になります。一方で、現場の声を吸い上げる仕組みも重要で、トップダウンとボトムアップを組み合わせたアプローチが理想的です。
経営層の役割は、ビジョンの提示だけでなく、DX推進に必要な人材や予算の確保、推進体制の構築、進捗のモニタリングなど多岐にわたります。ファーストリテイリングが有明本部に物理的な壁のないオフィスを構築したように、企業文化の変革にまで踏み込むことが、真のDX推進には必要です。経営層の本気度が、DX推進の成否を分ける最大の要因といえます。
明確な目的設定と中長期的な視点での取り組み
DX推進に成功している企業は、「なぜDXに取り組むのか」という目的を明確にし、中長期的な視点で計画を立てています。単に「競合がやっているから」「トレンドだから」といった曖昧な理由ではなく、自社が直面している具体的な課題を解決し、将来のビジョンを実現するための手段としてDXを位置づけています。味の素グループのASVやクボタの食料・水・環境問題への取り組みなど、社会課題の解決と自社の成長を結びつけた明確な目的設定が、継続的な推進力となっています。
DXの効果が目に見える形で現れるまでには、一般的に3年から5年程度の期間が必要とされています。短期的な成果を求めすぎると、途中で挫折するリスクが高まります。りそなホールディングスやゆうちょ銀行のように、人材育成と環境構築を並行して進め、段階的に内製化を図るなど、長期的な視点での取り組みが重要です。また、小さな成功体験を積み重ねながら、徐々に対象範囲を拡大していくアプローチも有効です。
目的を明確にする際には、定量的な目標設定も重要です。旭化成の「DX-Challenge 10-10-100」(デジタルプロ人財10倍、データ活用量10倍、増益貢献100億円)のように、具体的な数値目標を設定することで、進捗の測定と評価が可能になります。ただし、すぐに数値化できない定性的な効果(顧客満足度の向上、従業員の働きやすさなど)も重要であり、バランスの取れた目標設定が求められます。
データドリブン経営への転換
成功事例に共通する重要な要素として、経験と勘に基づく意思決定から、データに基づく意思決定へと転換している点が挙げられます。ニトリホールディングスのデータ活用の内製化や、日本たばこ産業のAIによるターゲット抽出など、データを経営判断の中核に据えることで、より客観的で精度の高い意思決定が可能になっています。
データドリブン経営を実現するには、まずデータを収集・蓄積する基盤の整備が必要です。JR九州のように顧客分析基盤を刷新し、高速でのデータ処理を可能にすることで、リアルタイムでの分析と施策展開が実現します。また、部門ごとにサイロ化していたデータを統合し、全社で活用できる環境を整えることも重要です。パナソニックのデータ駆動型経営のためのITアーキテクチャ設計は、その好例といえます。
データドリブン経営において重要なのは、データを活用できる人材の育成です。ノバルティスファーマのように各部署にデータ分析エバンジェリストを配置することで、現場レベルでのデータ活用が促進されます。専門家だけでなく、一般の従業員もデータリテラシーを高め、日常業務の中でデータを活用できるようになることが、組織全体のデータドリブン化につながります。経営層から現場まで、全社でデータを重視する文化の醸成が不可欠です。
DX人材の確保・育成と組織体制の構築
DX推進の成否を分ける重要な要素が、適切な人材の確保・育成と推進体制の構築です。島津製作所のような全部門を対象とした育成プログラムや、静岡銀行の段階的な教育カリキュラムなど、多くの成功企業が人材育成に多大な投資を行っています。DXに必要な人材は、デジタル技術のスキルだけでなく、ビジネス理解力、課題発見・解決能力、変革を推進するマインドセットなど、多面的な能力が求められます。
組織体制の構築においては、専門組織の設置が有効です。大成建設のデジタル戦略推進室のように、社長直轄の専門組織を設置することで、全社横断的なDX推進が可能になります。組織形態としては、経営直下型、IT部門拡張型、専門組織型、子会社型などがありますが、自社の状況やDXの成熟度に応じて最適な形態を選択することが重要です。IHIのように、段階的に体制を見直していくアジャイルなアプローチも有効です。
人材確保においては、社内育成だけでなく、外部人材の活用も重要な選択肢です。ファミリーマートのように外部のプロ人材を招いて短期間でファミペイを立ち上げた事例や、中小企業B社のようにIT経営の専門家と協力した事例など、外部の知見を取り入れることで推進速度を上げることができます。ただし、外部依存だけでは自社にノウハウが蓄積されないため、外部パートナーと協力しながら社内人材を育成するアプローチが理想的です。
内製化を意識したノウハウ蓄積
多くの成功企業に共通するのが、DX推進の内製化を意識している点です。ニトリホールディングスやビューカードのように、当初は外部パートナーの支援を受けながらも、段階的に内製化を進めることで、自社にノウハウが蓄積され、持続的なDX推進が可能になります。内製化により、市場の変化や新たなニーズに迅速に対応できる体制が構築され、競争優位性の源泉となります。
内製化を進める際の重要なポイントは、最初から完全内製化を目指すのではなく、外部パートナーと協力しながら段階的にスキルトランスファーを受けることです。りそなホールディングスのDX推進室のように、専門組織を立ち上げて内製化のコアとなる人材を育成し、そこから全社に展開していくアプローチが効果的です。また、クボタのようにマイクロソフトと戦略的提携を結びながらも、グローバルICT本部を中心に自社での推進体制を構築する例もあります。
内製化の意義は、単なるコスト削減ではなく、ビジネス理解とデジタル技術の融合による価値創造にあります。現場の業務を深く理解している社内人材がデジタルスキルを身につけることで、実務に即した改善提案や新サービスの創出が可能になります。製造業C社のIT×現場知見の融合チームは、この考え方を体現しています。内製化により、継続的な改善と進化が可能な、持続可能なDX推進体制を構築することが、長期的な成功の鍵となります。
DX推進における組織体制の作り方|4つのモデルと役割

DX推進を成功させるためには、適切な組織体制の構築が不可欠です。専門組織を設置し明確な役割と権限を与えることで、全社横断的なDX推進が可能になります。IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の調査でも、DXの成熟度が高い企業ほど専門部署を設置していることが明らかになっています。このセクションでは、DX推進組織の必要性から具体的なモデル、役割、構築のポイントまで解説します。
DX推進組織が必要な理由
既存の部署にDX推進の役割を兼務させるだけでは、日常業務に追われてDXが後回しになりがちです。専門組織を設置することで、DX推進に専念できる環境が整い、推進速度が大幅に向上します。大成建設が2019年に社長直轄の「デジタル戦略推進室」を設置したように、DXに特化した組織を作ることで、全社デジタル戦略の立案から実装まで一貫した推進が可能になります。
DX推進には、既存業務とは異なる視点と専門性が求められます。レガシーシステムの可視化、業務プロセスの抜本的な見直し、新技術の評価と導入、データ活用基盤の構築など、高度な専門知識とプロジェクト管理能力が必要です。これらを既存部署の兼務で対応しようとすると、知識不足や権限の問題で停滞する可能性が高くなります。専門組織であれば、必要なスキルを持つ人材を集中配置し、経営層からの明確な権限委譲も受けやすくなります。
さらに重要なのは、組織変革を推進する役割です。DXは技術導入だけでなく、企業文化や働き方の変革を伴います。島津製作所のデータ活用人材育成プログラムのように、全社的なデジタルリテラシー向上や、データ重視の文化醸成には、専門組織が中心となって推進する必要があります。既存部署では現状維持のバイアスが働きやすいため、変革を推進する独立した組織の存在が重要です。
組織体制の4つのモデル(経営直下型/IT部門拡張型/専門組織型/子会社型)
DX推進組織の体制には、大きく分けて4つのモデルがあります。経営直下型は、経営層の直下にDX推進部門を設置するモデルで、全社横断的な権限を持ち、トップダウンでDXを推進できる利点があります。大成建設のデジタル戦略推進室やセブン&アイ・ホールディングスのグループDX推進本部がこのタイプに該当します。経営戦略と密接に連携でき、部門間の調整も円滑に進みますが、現場との距離が遠くなる懸念もあります。
IT部門拡張型は、既存のIT部門を拡張してDX推進の役割を担わせるモデルです。デジタル技術の専門知識を持つ人材が既に配置されているため、技術面での推進はスムーズです。ただし、IT部門は社内システムの保守運用に追われがちで、ビジネス変革まで踏み込むのが難しい場合があります。顧客向けの新サービス開発など、ビジネス側の視点が必要な領域では、事業部門との密接な連携が不可欠です。
専門組織型は、既存組織から独立した新たなDX専門組織を設置するモデルです。デジタルスキルとビジネス知見の両方を持つ人材を社内外から集め、DX推進に特化したチームを編成します。SGホールディングスのようにDXを成長戦略の中核に据える企業に多く見られます。強力な推進力を持つ一方、既存組織との連携や文化の違いが課題になることもあります。子会社型は、DX推進機能を別会社として独立させるモデルで、より自由度の高い施策展開が可能ですが、親会社との距離感が課題となります。
DX推進組織に求められる5つの役割
DX推進組織の第一の役割は、DX戦略の策定と全社への展開です。経営戦略に基づき、自社が目指すべきDXの方向性を明確にし、具体的なロードマップを作成します。味の素グループがASVの実現に向けてDX戦略を策定したように、社会価値と経済価値の両方を見据えた戦略立案が求められます。また、各部署のDX施策を全社最適の視点で調整し、重複や矛盾を避けることも重要な役割です。
第二の役割は、デジタル技術の導入と活用支援です。AIやIoT、クラウドなど最新技術の動向を調査し、自社への適用可能性を評価します。トヨタ自動車のマテリアルズ・インフォマティクスやりそなホールディングスのLLM活用のように、先端技術を事業に取り入れる際の検証と導入を主導します。また、導入した技術を各部署が効果的に活用できるよう、技術支援や教育も行います。第三の役割は、データ活用基盤の構築と運用です。JR九州の顧客分析基盤刷新のように、全社のデータを統合し活用できるプラットフォームを整備します。
第四の役割は、DX人材の育成です。ノバルティスファーマのAnalytics boot campや静岡銀行の段階的な教育プログラムのように、全社員のデジタルリテラシー向上から専門人材の育成まで、体系的な教育プログラムを企画・実施します。第五の役割は、業務プロセス改革の推進です。既存の業務フローを可視化し、デジタル技術を活用した効率化や自動化を提案します。伊藤忠商事のAI自動発注システムのように、業務プロセスそのものを変革する施策を主導します。これら5つの役割を効果的に果たすことで、全社的なDX推進が加速します。
組織構築の3つのポイント
DX推進組織を構築する際の第一のポイントは、適切な人材の配置です。デジタル技術の専門家だけでなく、ビジネス理解が深く変革マインドを持つ人材、各部署のキーパーソンなど、多様な背景を持つメンバーで構成することが重要です。クボタがグローバルICT本部にさまざまな経歴を持つ社員を集めたように、多様性が組織の推進力を高めます。また、モチベーションの高い人材を選抜し、DX推進に専念できる環境を整えることも重要です。
第二のポイントは、明確な権限と予算の付与です。DX推進には、部門横断的なプロジェクトの推進や、既存業務プロセスの変更を伴うことが多いため、それを実行できる権限が必要です。経営層直下に組織を設置し、明確な権限委譲を行うことで、部門間の調整がスムーズになります。また、システム投資や人材育成に必要な予算を確保し、中長期的な視点で投資できる体制を整えることも不可欠です。旭化成がDX-Challenge 10-10-100で増益貢献100億円を目標に掲げたように、投資対効果を明確にすることも重要です。
第三のポイントは、外部パートナーとの適切な協業体制の構築です。全てを自社だけで進めるのではなく、専門性の高い領域では外部の知見を活用することが効率的です。中小企業B社やD社のように、IT経営の専門家やテクノロジーベンダーと協力しながら推進することで、限られたリソースでも成果を上げることができます。ただし、外部依存にならないよう、協業を通じて社内にノウハウを蓄積する仕組みも重要です。ビューカードのように段階的に内製化を進めることで、持続可能なDX推進体制が構築できます。
DX推進のロードマップ|段階的アプローチで成功に導く

DX推進を成功させるには、明確なロードマップに基づいた段階的なアプローチが重要です。いきなり全社一斉に大規模なDXを始めるのではなく、現状分析から始めてパイロットプロジェクトで検証し、成功事例を積み重ねながら全社展開していく方法が効果的です。このセクションでは、DX推進の各フェーズで取り組むべき内容と、中長期計画の重要性について解説します。
フェーズ1:現状分析と目標設定
DX推進の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。経済産業省が提供する「DX推進指標」を活用して、自社のDX成熟度を評価することから始めましょう。成熟度はレベル0(未着手)からレベル5(グローバル市場におけるデジタル企業)まで6段階で評価され、現在地を把握することで適切な目標設定が可能になります。多くの日本企業の現在値は1.45程度とされており、まずはレベル3(全社戦略に基づく部門横断的推進)を目指すことが推奨されています。
現状分析では、レガシーシステムの状況、既存業務プロセスの課題、データ管理の実態、デジタル人材のスキルレベルなどを詳細に調査します。ブリヂストンが技能伝承の課題を明確化したように、具体的な課題を特定することが重要です。また、競合他社や業界のDX動向も調査し、自社の立ち位置を把握します。こうした分析をもとに、3年後、5年後にどのような姿を目指すのか、具体的かつ測定可能な目標を設定します。ユニクロの「情報製造小売業」への転換のように、ビジョンを明確に言語化することも重要です。
目標設定では、売上やコスト削減などの定量目標だけでなく、顧客満足度の向上や従業員の働きやすさなど定性的な目標も含めることが大切です。また、短期(1年)、中期(3年)、長期(5年)の目標を段階的に設定し、マイルストーンを明確にします。目標は経営層だけで決めるのではなく、現場の意見も取り入れながら、全社で共有できるものにすることで、推進力が高まります。
フェーズ2:DX戦略の策定と優先順位付け
現状分析と目標設定が完了したら、それを実現するための具体的なDX戦略を策定します。どの業務プロセスをどのようにデジタル化するか、どんな新サービスを開発するか、そのために必要なシステムや技術は何かを明確にします。味の素グループがスマートファクトリー化とサプライチェーン改革を両輪で進めたように、複数の施策を組み合わせた包括的な戦略が効果的です。戦略策定では、自社の強みを活かしながら、顧客価値の向上と業務効率化の両方を追求します。
すべての施策を同時に進めるのは現実的ではないため、優先順位付けが重要です。影響度(ビジネスへのインパクト)、実現可能性(技術的・組織的な難易度)、緊急性(市場環境や競合状況)の3軸で評価し、優先的に取り組むべき施策を選定します。ファミリーマートがファミペイから始めて顧客接点を構築したように、まずは成功しやすく効果の高い施策から着手することで、早期に成果を示し社内の理解を得ることができます。優先順位付けでは、Quick Win(短期間で成果が出る施策)を含めることも重要です。
戦略策定では、必要なリソース(人材、予算、時間)も明確にします。IHIがマイクロソフトと戦略的提携を結んだように、外部パートナーとの協業が必要な領域も特定します。また、組織体制やガバナンス、KPI(重要業績評価指標)の設定も行います。パナソニックのデータ駆動型経営のように、進捗を測定し評価できる仕組みを整えることで、PDCAサイクルを回しながら戦略を進化させることができます。戦略は一度決めたら終わりではなく、市場環境の変化に応じて柔軟に見直すことが重要です。
フェーズ3:パイロットプロジェクトの実施
戦略に基づき、まずは小規模なパイロットプロジェクトから始めることが推奨されます。いきなり全社展開するとリスクが大きいため、特定の部門や業務に限定して実証実験を行い、効果を検証します。伊藤忠商事が一部の物流拠点でAI自動発注の実証実験を行ったように、限定的な範囲で試すことで、問題点の早期発見と改善が可能になります。パイロットプロジェクトは、技術的な検証だけでなく、組織や業務プロセスへの影響も確認する重要な機会です。
パイロットプロジェクトでは、明確な成功基準を設定し、データに基づいて効果を測定します。ヤマト運輸がレコメンド機能の導入でCTRが100倍に向上したように、定量的な成果を示すことで、経営層や他部署からの理解と支持を得やすくなります。また、プロジェクトの過程で得られた知見やノウハウを文書化し、次のフェーズに活かせるようにします。失敗から学ぶことも重要で、うまくいかなかった点を分析し改善策を検討します。
パイロットプロジェクトを通じて、DX推進の核となる人材を育成することも重要な目的です。八千代エンジニヤリングがAI画像認識技術を実プロジェクトで活用したように、実践を通じてスキルを習得し、次のプロジェクトのリーダーとなる人材を育てます。また、成功事例を社内に広く共有することで、DXへの関心と理解を高め、全社展開への土台を作ります。パイロットプロジェクトの成功が、DX推進の勢いを生み出す起点となります。
フェーズ4:全社展開とPDCAサイクル
パイロットプロジェクトで成果を確認したら、対象範囲を拡大して全社展開を進めます。ただし、一度にすべての部署に展開するのではなく、段階的に広げていくことが安全です。ニトリホールディングスがデータ分析の内製化を段階的に進めたように、各部署の準備状況に応じて展開のペースを調整します。先行部署の成功事例やノウハウを横展開することで、後続部署はより円滑に導入できます。また、各部署の特性に応じたカスタマイズも必要です。
全社展開では、標準化と柔軟性のバランスが重要です。基本的なシステムやプロセスは全社で統一することで効率化を図りますが、部署ごとの業務特性に応じた調整も許容します。資生堂ジャパンがECとオウンドメディアを融合させたように、複数の施策を統合して相乗効果を生み出す工夫も効果的です。また、展開過程で新たな課題や改善点が見つかることも多いため、柔軟に対応できる体制を維持します。
DX推進は一度完了したら終わりではなく、継続的な改善が必要です。KPIを定期的にモニタリングし、目標に対する進捗を評価します。静岡銀行がデータ利活用施策、人材育成、環境構築を並行展開したように、PDCAサイクルを回しながら、戦略や施策を進化させます。市場環境の変化や新技術の登場に応じて、ロードマップを見直すことも重要です。クボタがマイクロソフトとの提携で計画をアップデートしたように、柔軟な対応が持続的な成功につながります。
3〜5年を見据えた中長期計画の重要性
DXの効果が本格的に現れるまでには、一般的に3年から5年程度の期間が必要とされています。短期的な成果だけを追求すると、表面的なデジタル化に留まり、真のビジネス変革には至りません。日本航空のDXプロジェクトが7年を要したように、大規模な変革には相応の時間がかかることを理解し、中長期的な視点で計画を立てることが重要です。経営層は、短期的な業績へのプレッシャーに負けず、長期的な視点でDX投資を継続する覚悟が求められます。
中長期計画では、技術の進化や市場環境の変化を見据えた柔軟性も必要です。5年前には想定していなかった生成AIのような技術が登場することもあるため、計画を硬直的に固めすぎず、新たな機会に対応できる余地を残しておくことが重要です。りそなホールディングスがLLMプロジェクトを迅速に立ち上げたように、環境変化に応じて計画を進化させる姿勢が求められます。定期的な見直しサイクルを設定し、年に1〜2回は計画を評価して必要な修正を加えます。
中長期計画では、段階的なマイルストーンを設定し、各段階での達成目標を明確にします。旭化成のDX-Challenge 10-10-100のように、3年後、5年後の具体的な数値目標を設定することで、進捗を客観的に評価できます。また、各フェーズでの投資額と期待リターンも明示し、経営判断の材料とします。ただし、すぐに数値化できない文化変革や人材育成の成果も重要であり、定性的な評価も組み合わせた多面的な評価が必要です。長期的な視点での投資と継続的な改善が、DX推進の成功を導きます。
DX推進で直面する4つの課題と対策

DX推進は多くのメリットをもたらす一方で、組織的・技術的・人的な様々な課題に直面します。IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の調査によると、DXに取り組む企業の約4割が「成果が出ていない」と回答しており、課題の克服が成功の鍵を握っています。このセクションでは、多くの企業が直面する4つの主要な課題と、その具体的な対策について解説します。
課題1:全社的な協力体制の構築と部署間調整
DXは特定の部署だけで完結するものではなく、全社横断的な取り組みが必要です。しかし、各部署は通常業務に追われており、DXプロジェクトへの協力を自分事として捉えないケースが多く見られます。また、既存のシステムや業務プロセスに慣れ親しんでいる従業員からは、「今のままで問題ない」「変更する必要性を感じない」といった反発の声も上がります。長谷工コーポレーションの事例でも、新技術の採用が反発を買う可能性が指摘されています。
この課題を克服するには、まず経営層が強いリーダーシップを発揮し、DXの必要性と目標を全社に明確に伝えることが重要です。SGホールディングスが2030年ビジョンを掲げたように、わかりやすいビジョンを示すことで、従業員の理解と共感を得ることができます。また、各部署のキーパーソンをDXプロジェクトに巻き込み、部門を代表する立場で参画してもらうことで、部署内での理解促進と協力体制の構築が進みます。部門間の利害対立が生じた場合は、経営層が調整に入り、全社最適の視点で意思決定を行います。
現場の従業員に対しては、DXによって業務がどう改善されるのか、自分たちにどんなメリットがあるのかを具体的に示すことが効果的です。ビューカードが顧客体験と従業員体験の両輪でDXを進めたように、従業員の働きやすさ向上も重視することで、協力を得やすくなります。また、成功事例を社内で共有し、「DXは自分たちの仕事を楽にしてくれる」という実感を持ってもらうことも重要です。抵抗感を和らげるため、十分な説明と教育の機会を設けることも必要です。
課題2:システム刷新に伴う多額の投資とROI
レガシーシステムの刷新には多額の投資が必要で、DX推進の大きなハードルとなっています。総務省の2021年の調査では、「費用対効果が不明」という回答が約33%に上り、人材不足に次いで多い課題となっています。DXによる効果は「人員を何人削減できる」といった定量的な指標で測りにくく、「より正しい経営判断ができる」「顧客の動向がわかる」といった定性的な効果を求めて導入することが多いため、投資判断が難しいという課題があります。
この課題への対策として、まず小規模なパイロットプロジェクトから始めて具体的な成果を示すことが有効です。伊藤忠商事が一部の拠点で実証実験を行ったように、限定的な投資で効果を検証し、ROI(投資対効果)を明確にしてから全社展開することでリスクを抑えられます。また、クラウドサービスの活用により、初期投資を抑えて段階的に拡張できるアプローチも効果的です。クボタがクラウドに基幹システムを移行したように、従量課金制のクラウドサービスを活用することで、柔軟な投資が可能になります。
投資対効果の評価では、短期的な定量効果だけでなく、中長期的な定性効果も含めた多面的な評価が必要です。旭化成のDX-Challenge 10-10-100のように、複数の指標を組み合わせて総合的に評価する手法が有効です。また、「投資しない場合のリスク」も評価に含めることが重要です。2025年の崖で指摘されているように、DXを推進しない場合の機会損失や競争力低下のリスクを定量化し、投資判断の材料とします。経営層は、短期的な赤字を許容し、中長期的な視点で投資を評価する姿勢が求められます。
課題3:成果が出るまでの時間と経営層のコミットメント
DXの効果が目に見える形で現れるまでには、一般的に3年から5年程度の期間が必要です。この長い期間、継続的に投資と努力を続けることは容易ではなく、途中で方針転換したり、プロジェクトが頓挫したりするケースも少なくありません。特に経営層が交代した場合、新しい経営陣が前任者の方針を継続するとは限らず、DX推進が停滞するリスクがあります。短期的な業績へのプレッシャーも、DX投資を縮小させる要因となります。
この課題を克服するには、経営層の強いコミットメントと、その継続性が不可欠です。ファーストリテイリングの有明プロジェクトのように、経営トップ自らが先頭に立ってDX推進を主導し、その重要性を社内外に発信し続けることが重要です。また、DX戦略を中期経営計画に明確に位置づけ、経営の最重要課題として扱うことで、経営層が変わっても継続性を担保できます。取締役会でDXの進捗を定期的にレビューし、経営層全体でコミットメントを共有することも効果的です。
成果が出るまでの期間を短縮するためには、Quick Win(短期間で成果が出る施策)を含めることが有効です。ヤマト運輸のレコメンド機能のように、数ヶ月で効果が確認できる施策を早期に実施することで、社内の期待感を高め、継続的な推進力を維持できます。また、小さな成功体験を積み重ねながら段階的に拡大していくアプローチにより、長期プロジェクトでもモチベーションを保つことができます。定期的に成果を可視化し、社内に共有することで、DXの価値を実感してもらうことも重要です。
課題4:DX人材不足への対応策
DX推進に必要なデジタルスキルとビジネス理解の両方を持つ人材は希少で、多くの企業が人材不足に悩んでいます。経済産業省の試算では、2025年までにIT人材不足は約43万人に拡大すると予測されており、人材獲得競争は激化しています。社内にDXをリードできる人材がいない場合、外部に全面的に依存することになりますが、それではノウハウが社内に蓄積されず、トラブル発生時に迅速な対応ができないという問題があります。
この課題への対策として、まず社内人材の育成に注力することが重要です。島津製作所やノバルティスファーマのように、体系的な育成プログラムを構築し、継続的に人材を育てることで、中長期的な人材不足を解消できます。全社員を対象としたデジタルリテラシー教育から、専門人材を目指す選抜型の高度なプログラムまで、段階的な育成体系を整備します。また、社内の業務経験者にデジタルスキルを習得してもらうことで、ビジネスとデジタルの両方を理解した人材を育成できます。
外部人材の活用も重要な選択肢です。ファミリーマートがプロ人材を招いてファミペイを立ち上げたように、即戦力となる外部人材を採用することで、推進速度を上げることができます。ただし、外部人材だけに依存するのではなく、中小企業B社のように外部の専門家と協力しながら社内人材を育成するアプローチが理想的です。外部パートナーとの協業を通じてノウハウのトランスファーを受け、段階的に内製化を進めることで、持続可能な体制を構築できます。また、副業人材やフリーランスの活用により、柔軟な人材確保も可能です。
DX推進の失敗事例から学ぶ3つの教訓
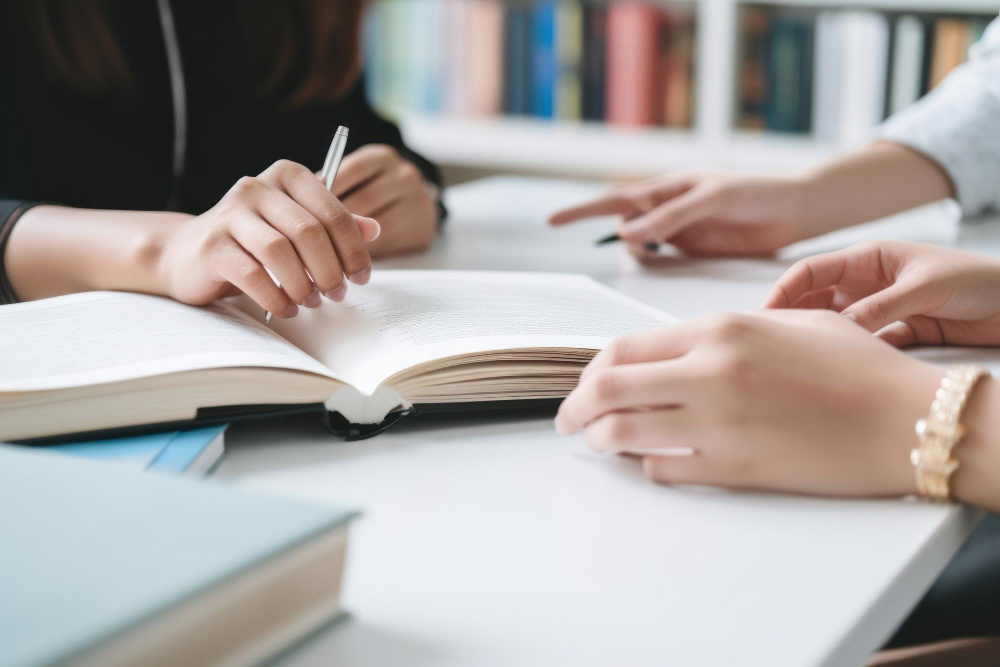
DX推進は成功事例だけでなく、失敗事例からも多くを学ぶことができます。失敗の原因を理解し事前に対策を講じることで、同じ過ちを避けることが可能です。中小企業の失敗事例を中心に、よくある失敗パターンとその教訓を解説します。これらの事例は、企業規模を問わず参考になる重要な示唆を含んでいます。
失敗事例1:機能過多で使いこなせないシステム導入
A社ではデジタルツールを導入する過程で、現場からのすべての意見を取り入れ、フルカスタマイズのシステムを開発しました。各部署の要望を漏れなく盛り込んだ結果、システムは多機能になりましたが、操作が複雑になりすぎ、従業員がうまく使いこなせなくなりました。多額の投資をして開発したシステムが、結果的に現場で活用されず、投資が無駄に終わってしまったのです。現場の声を聞くことは重要ですが、すべての要望を取り入れることが正解とは限りません。
この失敗から得られる教訓は、システムの使いやすさを最優先することです。機能の豊富さよりも、シンプルで直感的に操作できることが重要です。ニフティがRtoasterを選んだのは「手軽さときめ細かさの両方を兼ね備えている」点が評価されたように、使いやすさは導入の重要な判断基準です。要望を整理する際には、「本当に必要な機能」と「あったら便利な機能」を区別し、コア機能に絞り込むことが重要です。また、段階的に機能を追加していくアプローチも有効で、まずは最小限の機能で運用を開始し、使いながら改善していく方法が推奨されます。
システム導入前にプロトタイプやデモ環境で実際に操作してもらい、現場の反応を確認することも重要です。ユーザビリティテストを実施し、操作性に問題がないか事前に検証します。また、導入後の教育やサポート体制を充実させることで、従業員がシステムに習熟するまでの期間を短縮できます。資生堂ジャパンのAI肌診断のように、ユーザーにとって価値があり、使いたくなる仕組みを作ることが、システム活用の鍵となります。
失敗事例2:高機能すぎて業務が停止
B社の事例では、DX推進リーダーが具体的な課題解決のために必要な機能を十分に検討せず、先進的で高機能なシステムを採用しました。最新技術への期待が高まり、必要以上に高度なシステムを導入してしまったのです。この過剰な機能性が原因で、経験の浅い従業員が誤った操作を行い、システムが停止するという事態に至りました。システムの改修と復元作業が必要となり、その間に通常の業務が大きく停滞し、顧客への影響も出てしまいました。
この失敗から学ぶべきは、自社の現状に合ったレベルの技術を選択することの重要性です。最新技術や高機能なシステムが必ずしも最適解とは限りません。中小企業C社が製造現場を熟知するメンバーとITエンジニアのチームで開発を進めたように、現場の実態に即したシステム設計が重要です。技術選定では、「実現したいこと」を明確にしてから適切な技術を選ぶ順序を守り、技術ありきで進めないことが大切です。また、従業員のITリテラシーのレベルも考慮し、段階的にスキルアップを図りながらシステムを高度化していくアプローチが安全です。
システム導入時には、十分なテスト期間を設け、想定されるリスクへの対策を事前に講じることが重要です。八千代エンジニヤリングがAI画像認識を段階的に導入したように、まずは限定的な範囲で試験運用し、問題がないことを確認してから本格展開する方法が推奨されます。また、システム障害が発生した場合の復旧手順や代替手段を事前に準備しておくことで、業務への影響を最小限に抑えられます。高機能なシステムより、安定して動作するシステムを選ぶことが、結果的に業務の継続性を担保します。
失敗事例3:顧客ニーズとのミスマッチで撤退
C社は、他の業者に先駆けて完全キャッシュレスで運営されるテイクアウト専門店を非接触形式で開業しました。DXの先進事例として注目を集めましたが、当時の日本ではまだ現金決済の意識が強く、この先進的なキャッシュレス決済システムは広く受け入れられませんでした。特に高齢者層からは「現金で払えないなら利用しない」という反応が多く、想定していた顧客層を獲得できなかったのです。テイクアウト専門という業態も顧客に浸透せず、店舗は店内飲食への業態転換を余儀なくされました。
業態転換に伴い、改装費や人件費が増大し、経営が困難となり、最終的に閉店へと至りました。この失敗の本質は、業務効率化は達成したものの、顧客や従業員の満足度向上には繋がらなかったことにあります。デジタル技術の先進性だけを追求し、顧客のニーズや市場の成熟度を十分に考慮しなかったことが失敗の原因です。ユニクロが「消費者が求めるものを作る」ビジネスモデルを目指しているように、顧客起点での価値創造が重要です。
この失敗から得られる教訓は、DX推進は顧客価値の向上を最優先すべきということです。内部の業務効率化だけでなく、顧客にとってのメリットを明確にし、それが市場に受け入れられるかを慎重に検証する必要があります。野村不動産ソリューションズがパーソナライズで顧客体験を向上させたように、顧客の視点に立ったDX推進が成功の鍵です。新しい技術やサービスを導入する際には、事前に顧客調査やテストマーケティングを実施し、受容性を確認することが重要です。また、市場の成熟度に合わせて、段階的に新しい仕組みを浸透させていく戦略も有効です。
2025年最新トレンド|生成AIを活用したDX推進事例

2023年のChatGPT登場以降、生成AIは急速に進化し、DX推進の新たな可能性を切り開く技術として注目されています。経済産業省の「DX銘柄2024」でも、生成AI活用を競争優位性確立の基盤としている企業の取り組みが特に評価されています。このセクションでは、2025年最新の生成AI活用事例と、その可能性について解説します。
東京電力エナジーパートナー|ChatGPTでアンケート解析を効率化
東京電力エナジーパートナー株式会社は、2020年にDX推進室を立ち上げ、事業部のデータ活用案件に伴走する体制を構築しています。2023年からは生成AIの活用にも積極的に取り組み、数百時間に及ぶ人事の組織診断の自由記述アンケート集計を、ChatGPTによる分類と自動解析により大幅に効率化しました。従来は人手で数週間かかっていた作業が、生成AIを活用することで数時間で完了するようになり、業務オペレーションの劇的な改革を実現しています。
この取り組みの特徴は、高度なプログラミング知識がなくても、ChatGPTのプロンプトエンジニアリングにより実用的な業務改善が可能になった点です。数千件の自由記述回答をカテゴリ別に自動分類し、傾向分析や要約レポートの作成まで、生成AIが一貫して処理します。コストもほぼゼロで実現でき、投資対効果が極めて高い施策となりました。生成AIの民主化により、専門的なデータサイエンススキルがなくても、現場の担当者が自らデータ活用を推進できる時代が到来しています。
東京電力エナジーパートナーは、実務に直結する半年間の育成カリキュラム「EP Data College」も実施しており、専門知識のない多様な事業部からの希望者がデータ活用スキルを習得しています。生成AIの活用方法も教育プログラムに組み込み、全社的なAIリテラシーの向上を図っています。生成AIを経営効果に変えた同社の取り組みは、中堅企業における実践的な生成AI活用のモデルケースといえます。
経済産業省DX銘柄2024における生成AI活用企業
経済産業省が選定した「DX銘柄2024」では、生成AI技術を活用して競争優位性を確立している企業の取り組みが高く評価されています。クレディセゾンは、生成AIを活用した業務変革や新たな顧客体験の創出を通じて、全社的なDXの実現と組織のイノベーション力向上に取り組んでいます。コールセンター業務での活用やチャットボットによる対話形式の金融商品提案など、顧客接点の強化に生成AIを積極的に導入しています。
ソフトバンクは、「DXグランプリ2025」に選定された企業として、AIを活用した社会インフラ課題の解決に取り組んでいます。LPガス配送最適化サービス「Routify」では、従来の機械学習に加えて生成AIも活用し、配送計画の自動生成精度をさらに向上させています。生成AIによる自然言語処理により、配送員からのフィードバックをシステムに反映させやすくなり、継続的な改善サイクルが加速しています。
旭化成は、研究開発DXにおいて生成AIを活用し、特許情報や論文の分析を効率化しています。膨大な文献情報から関連する研究を抽出し、要約する作業が大幅に効率化され、研究者がより創造的な業務に時間を割けるようになりました。また、マテリアルズ・インフォマティクスにおいても、生成AIを活用した材料特性の予測精度向上に取り組んでいます。DX銘柄企業の多くが、生成AIを単なる業務効率化ツールではなく、新たな価値創造の手段として位置づけています。
生成AIがもたらすDXの新しい可能性
生成AIは、従来のDX推進における様々な障壁を低減する可能性を秘めています。最も大きな変化は、プログラミングスキルがなくても高度なデータ活用が可能になったことです。自然言語で指示を出すだけで、データ分析やレポート作成、コード生成などを実行できるため、DX人材不足という課題の解決につながります。ノバルティスファーマのデータ分析エバンジェリスト育成のように、各部署の担当者が生成AIを活用してデータ分析を行う時代が到来しています。
生成AIは、クリエイティブな業務の支援にも威力を発揮します。資生堂ジャパンのマーケティング部門では、生成AIを活用して商品説明文や広告コピーの案を大量に生成し、人間がその中から最適なものを選択・編集するワークフローを構築しています。ファーストリテイリングでも、商品デザインのアイデア出しに生成AIを活用し、デザイナーの創造性を拡張する取り組みが進んでいます。人間の創造性とAIの生成能力を組み合わせることで、これまでにない価値創造が可能になっています。
顧客接点における生成AI活用も進化しています。クレディセゾンのチャットボットのように、より自然な対話で顧客の課題を理解し、適切な提案を行うサービスが実現しつつあります。ヤマト運輸でも、配送に関する問い合わせに生成AIが対応し、顧客満足度の向上とオペレーターの負担軽減を両立させています。ただし、生成AIには幻覚(ハルシネーション)と呼ばれる誤情報生成のリスクもあるため、人間による確認とAIの出力を組み合わせたハイブリッドアプローチが重要です。
中小企業でも導入可能な生成AIツール
生成AIは大企業だけのものではなく、中小企業でも導入可能なツールが増えています。ChatGPTやGoogle Gemini、Claude などの汎用型生成AIは、月額数千円から利用でき、特別なインフラ投資なしに始められます。飲食業A社のように、従業員数40名程度の企業でも、生成AIを活用して業務効率化を実現しています。自由記述のアンケート分析、議事録の自動要約、メール文案の作成、商品説明文の生成など、様々な業務で活用できます。
業務特化型の生成AIツールも充実してきています。会計業務向けのAI、人事労務向けのAI、マーケティング向けのAIなど、専門領域に特化したツールを活用することで、より実務に即した支援が受けられます。製造業E社がデジタル拠点で情報発信を強化したように、SNS投稿の文案作成やレシピ動画のスクリプト作成に生成AIを活用することで、マーケティング業務の効率化が図れます。また、画像生成AIを活用したビジュアルコンテンツの作成も、中小企業のブランディングに有効です。
生成AI導入で重要なのは、まず小さく始めて効果を確認することです。いきなり全社展開するのではなく、特定の業務や部署で試験導入し、実際の効果とリスクを評価します。東京電力エナジーパートナーのアンケート解析のように、明確な効果が見込める業務から始めることで、社内の理解と支持を得やすくなります。また、生成AIの出力を鵜呑みにせず、人間が確認・編集するプロセスを組み込むことで、品質を担保しながら効率化を実現できます。生成AIは、中小企業のDX推進を加速する強力なツールとなりつつあります。
DX推進のメリット|企業が得られる3つの価値

DX推進は単なるコスト削減や業務効率化にとどまらず、企業の競争力を根本から強化し持続的な成長を実現する重要な取り組みです。多くの成功事例が示すように、適切に推進されたDXは、生産性向上、レガシーシステムからの脱却、新規事業創出という3つの大きな価値をもたらします。このセクションでは、DX推進によって企業が得られる具体的なメリットを解説します。
生産性向上と業務効率化
DX推進による最も直接的なメリットは、生産性の向上と業務効率化です。味の素グループがスマートファクトリー化で実現したように、紙媒体での記録をアプリに移行し稼働データを自動記録することで、管理業務の標準化とリモート管理が可能になります。これにより、従業員は付加価値の高い業務に集中でき、全体的な生産性が向上します。八千代エンジニヤリングのAI画像認識による検査では、現場対応工数を5分の1に削減し、人的リソースをより重要な業務に配分できるようになりました。
業務効率化は、守りのDXと攻めのDXの両面で実現されます。守りのDXでは、RPAによる定型業務の自動化、AIチャットボットによる顧客対応の効率化、クラウドシステムによるリモートワークの実現など、既存業務の効率を高めます。中小企業B社が紙業務をクラウド化したことで、情報共有がスムーズになり意思決定が迅速化した例のように、デジタル化により業務スピードが劇的に向上します。攻めのDXでは、データ活用による需要予測の精度向上、AIによる最適化で付加価値を高めるなど、生み出す価値を大きくすることで生産性を向上させます。
生産性向上の効果は、人手不足への対応としても重要です。日本の生産年齢人口が減少する中、限られた人員で成果を上げるには、デジタル技術の活用が不可欠です。ソフトバンクのRoutifyが配送員の負担を軽減したように、AIやIoTを活用することで、少ない人数でも高い生産性を維持できます。また、リモートワークやフレックスタイムなど、働き方の多様化を実現することで、育児や介護と両立しながら働ける環境を整え、労働参加率の向上にもつながります。DXによる生産性向上は、企業の持続的成長の基盤となります。
レガシーシステムからの脱却
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」の本質は、レガシーシステムが企業成長の足かせとなっているという問題です。1980年代〜1990年代に構築された基幹システムは、技術者の定年退職によりブラックボックス化し、保守運用が困難になっています。2017年時点で日本企業の約8割がレガシーシステムを抱えており、その保守に多額のIT予算が費やされています。この費用を新技術への投資に回すことができれば、イノベーションが加速します。
レガシーシステムからの脱却により、新しいデジタル技術との連携が可能になります。クボタがマイクロソフトと提携し基幹システムをクラウドに移行したことで、データの集約と分析が容易になり、AI活用の基盤が整いました。レガシーシステムでは困難だった部門横断的なデータ活用も、モダンなシステムアーキテクチャであれば実現できます。JR九州の顧客分析基盤刷新により、データ処理速度が大幅に改善し、リアルタイムでの分析と施策展開が可能になった事例は、システム刷新の価値を示しています。
システム刷新は、ビジネスの柔軟性も高めます。市場環境の変化に応じて、迅速にシステムを変更・拡張できることは、競争優位性の源泉となります。クラウドネイティブなシステムであれば、新機能の追加やスケールアップが容易で、ビジネスの成長に合わせてシステムを進化させられます。また、セキュリティ面でも、最新のシステムは高度な脅威への対策が施されており、レガシーシステムと比較して安全性が高まります。セブン&アイ・ホールディングスが共通インフラ基盤を構築したように、セキュアな環境でのDX推進が可能になります。
新規事業創出とビジネスモデル変革
DX推進の最も大きな価値は、新規事業の創出とビジネスモデルの変革です。デジタル技術の進歩により、今まで数値化できなかったデータも含めて、多様なデータが取得できるようになっています。ユニ・チャームがデジタルスクラムシステムで顧客インサイトを発掘し、紙おむつのサブスクリプションサービス「手ぶら登園」という新ビジネスを創出した例は、データ活用が新規事業につながる好例です。従来の製品販売だけでなく、サービス提供やプラットフォームビジネスへと事業を拡張できます。
ビジネスモデルの変革も、DXの重要な成果です。IHIが「モノ売り」から顧客の成功を支援するライフサイクルビジネスへ転換したように、IoTプラットフォームでデータを収集・分析することで、製品納入後も継続的に価値を提供するモデルが実現します。トプコンが医食住の3領域でICT×AIソリューションを提供しているように、単なる機器販売から、顧客の課題を解決するトータルソリューション提供へとビジネスを進化させることができます。こうした変革により、顧客との長期的な関係構築と安定収益の確保が可能になります。
新規事業創出において重要なのは、既存事業で蓄積したデータや顧客基盤を活用することです。ヤフーがマルチ・ビッグデータをプラットフォーム化して外販しているように、自社の強みを他社にも提供することで新たな収益源を生み出せます。中小企業A社が開発したAI来客予測ツールを関連会社を通じて他の飲食事業者に提供している例も、自社のDXノウハウを外販する好例です。DXにより、既存事業の枠を超えた事業機会が広がり、企業の成長可能性が飛躍的に高まります。
まとめ|DX推進事例から学び自社の変革を実現する

本記事では、製造業から小売、金融、物流、IT、医療、建設、中小企業まで、8業種37社のDX推進成功事例を詳しく紹介してきました。トヨタ自動車のマテリアルズ・インフォマティクス、セブン&アイ・ホールディングスのAI配送最適化、りそなホールディングスの生成AI活用など、各社が自社の課題に応じた独自のDXを推進し、具体的な成果を上げています。これらの事例に共通するのは、経営層の強いリーダーシップ、明確な目的設定、データドリブン経営への転換、DX人材の育成、内製化の推進という5つのポイントです。
DX推進は一朝一夕には実現せず、3年から5年の中長期的な取り組みが必要です。現状分析と目標設定から始まり、DX戦略の策定、パイロットプロジェクトでの検証を経て、全社展開とPDCAサイクルを回していく段階的なアプローチが効果的です。組織体制の構築では、経営直下型、IT部門拡張型、専門組織型、子会社型の4つのモデルから、自社の状況に応じて最適な形態を選択します。DX推進組織には、戦略策定、技術導入、データ基盤構築、人材育成、業務プロセス改革という5つの重要な役割があります。
一方で、全社的な協力体制の構築、システム刷新への投資、成果が出るまでの時間、DX人材不足という4つの課題にも直面します。失敗事例から学ぶべき教訓は、機能過多を避けシンプルなシステムを選ぶこと、自社のレベルに合った技術を導入すること、顧客ニーズを最優先することです。2025年の最新トレンドとして、生成AIがDX推進の新たな可能性を切り開いており、東京電力エナジーパートナーのChatGPT活用やDX銘柄企業の先進事例が注目されています。中小企業でも導入可能な生成AIツールが増え、DXの民主化が進んでいます。
DX推進は、生産性向上と業務効率化、レガシーシステムからの脱却、新規事業創出とビジネスモデル変革という3つの大きな価値をもたらします。「2025年の崖」を目前に控え、もはやDXは選択肢ではなく必須の取り組みです。本記事で紹介した37社の事例と実践的なポイントを参考に、自社の状況に合わせたDX推進計画を策定し、着実に実行していくことが重要です。小さな成功体験を積み重ねながら、組織全体のデジタル変革を推進していきましょう。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















