資料作成のコツ~効率的で伝わりやすい資料を作る~

この記事は、3W1HフレームワークやPREP法を基盤にした論理的で分かりやすい資料作成手法を解説しています。
デザインの原則やPowerPoint・Word・Excel活用術、テンプレート・ショートカットによる時短、チーム協働での品質管理のポイントを紹介しています。
さらに、AIツールやクラウド環境を活用した最新の効率化ワークフローまでを網羅し、継続的なスキル向上の重要性を示しています。
資料の作成に3時間以上かけたのに、「で、結局何が言いたいの?」と返ってきた経験はないだろうか。時間をかければ質が上がるわけではない。伝わる資料と伝わらない資料の差は、ほぼ「作り始める前の設計」で決まる。
本記事では、資料作成の根本にある設計思想から、PowerPoint・Word・Excelのツール別の実践テクニック、AIを活用した時短ワークフローまでを順に解説する。どこから読んでも使えるが、初めて読む場合は冒頭から順番に追うことを勧める。
資料作成の基本原則と目的設定

資料作成で最も重要な3W1Hフレームワーク
資料を作り始める前に、4つの問いに答えておく。これを省くと、スライドの中盤で「何を書けばいいか分からない」状態に陥る。
| 問い | 問いかけ | 記入例 |
|---|---|---|
| Why(なぜ) | この資料を作る目的は何か | 経営陣から新製品の開発予算を承認してもらう |
| Whom(誰に) | 誰が読むか、誰が決定権を持つか | 経営陣・財務担当役員(技術的詳細は不要) |
| What(何を) | 伝えるべき核心の情報は何か | 市場ニーズの根拠、投資対効果、競合との差 |
| How(どのように) | 形式・分量・媒体は何が最適か | PowerPoint 10枚以内、口頭説明あり |
この表を埋めるだけで、不要なスライドを作るムダが減る。「この情報、3W1Hのどこに当たるか?」と自問しながら素材を取捨選択すると、資料の密度が上がる。
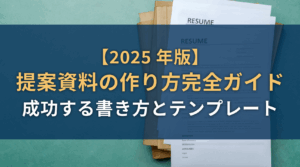
目的を明確にするための具体的手順
「誰に」「何をしてほしいか」を一文で書き出すことから始める。たとえば「財務担当役員に、来期予算として300万円を承認してもらう」のように、対象者と期待する行動と数字をセットにする。この一文が書けない段階で資料に着手すると、後で大幅な作り直しが発生する。
社内向けと社外向けで、資料が担う役割は大きく異なる。
社内向け資料の主な目的
- 意思決定の促進(予算承認・方針決定)
- 情報共有・進捗報告
- 業務マニュアル・手順書
社外向け資料の主な目的
- 営業提案・サービス紹介
- マーケティング・ホワイトペーパー
- 研究・調査結果の発表
目的が複数ある場合は一つに絞る。「提案もしつつ会社紹介もしたい」という欲張りな資料は、結果的にどちらも中途半端になる。
読み手を意識した資料設計の考え方
読み手の立場によって、関心の重心が変わる。
| 対象者 | 最も気にする情報 | 最も気にしない情報 |
|---|---|---|
| 経営層・役員 | 投資対効果、競合優位性、リスク | 技術的な実装詳細 |
| 現場マネージャー | 実行可能性、スケジュール、工数 | 市場全体のマクロ動向 |
| 技術担当者 | 仕様、精度、既存システムとの連携 | 営業的な訴求文言 |
| 外部クライアント | 自社へのメリット、費用感、実績 | 社内の開発プロセス |
この表を念頭に置いて情報を選ぶと、「念のため入れておこう」という蛇足スライドが自然に減る。
効果的な資料構成とストーリー設計

PREP法を活用した論理的構成
伝わる資料の構成はシンプルだ。結論→理由→根拠→結論の順で組む。これがPREP法(Point・Reason・Example・Point)で、スライド全体にもセクション単位にも適用できる。
営業提案書での実例を示す。
Point(結論): 来期の展示会出展を中止し、ウェビナーに切り替えることを提案します。
Reason(理由): 展示会の1リード獲得コストがウェビナーの約4倍になっているためです。
Example(根拠): 昨年の展示会では50リード獲得に150万円かかりましたが、今年実施したウェビナーでは45リードを40万円で獲得できました。
Point(結論): 予算を展示会からウェビナーに移し、浮いた110万円をコンテンツ制作に充当します。
経営陣への提案ではこの構成を最初の3枚以内に収める。忙しい意思決定者は、5枚目まで我慢して読まない。
読み手の関心を引く冒頭の作り方
冒頭の役割は「この資料を最後まで読む価値がある」と思わせることだ。そのために使えるパターンは3つある。
- 課題の提示:「御社と同規模のBtoB企業の担当者が、資料1本に平均6.8時間かけているというデータがあります」のように、読み手が「それ、うちも同じだ」と感じる事実から入る。
- 結論の先出し:「今日ご提案する方法で、現状の作業時間を半分以下にできます」と最初に言い切る。
- 問いかけ:「先月の提案で、いくつ受注できましたか?」のように読み手自身に数字を思い出させる。
目次はページ2か3に入れる。最初のページは課題提示か結論に使う。目次を1ページ目に持ってくる資料は、読む前から「長そう」という印象を与える。
説得力のある結論への導き方
結論ページは「まとめ」ではなく「次のアクション指示」として設計する。「以上が提案内容です」で終わる資料と、「◯月◯日までに方針のご回答をお願いします」で終わる資料では、受け手のアクション率が変わる。
数値の裏付けは意思決定者ほど重視する。ROIの計算、コスト削減額の試算、比較対象との差分を1枚の表にまとめると、口頭説明なしでも判断材料として機能する。また、懸念点を先回りして示す「リスクと対応策」のスライドを1枚入れると、「そのリスクはどうするの?」という質問が来なくなり、会議の時間が短縮される。
デザインで差がつく見やすい資料の作り方

配色ルールと効果的な色使いのテクニック
配色で迷う時間を完全にゼロにする方法がある。3色だけ決めて、それ以外は使わないというルールだ。
| 色の役割 | 使用比率 | 代表的な選択肢 |
|---|---|---|
| ベースカラー | 約70% | 白・ライトグレー |
| メインカラー | 約25% | コーポレートカラー |
| アクセントカラー | 約5% | メインカラーの補色 |
アクセントカラーはCTA(次のアクション)や最重要数値にだけ使う。「強調したい箇所が多い」と感じたら、それはそもそも情報を絞れていないサインだ。
色の心理的効果も頭に入れておく。青系は信頼・安定を想起させるため金融・SaaS系の提案書に向く。緑系は成長・安心感を伝えるため環境・医療系に合う。赤系はアクションを促す力が強いが、多用すると不安感を与える。
フォント選びと文字装飾の統一方法
フォントの選択肢は最初から絞ってよい。日本語資料では以下の3つのどれかを選べば間違いない。
| フォント | 動作環境 | 特徴 |
|---|---|---|
| メイリオ | Windows標準 | 視認性が高く本文に最適 |
| ヒラギノ角ゴ | Mac標準 | クリーンで洗練された印象 |
| 游ゴシック | Win/Mac共通 | 両環境で見た目が崩れない |
文字サイズには明確な階層を作る。タイトルは24pt以上、見出しは18〜20pt、本文は14〜16pt、注釈は10〜12ptを基準にする。この4段階を守ると、情報の重要度が視覚的に伝わる。
太字・色変更・下線は「1スライドに1〜2か所まで」を原則にする。強調が多すぎる資料は「どこが本当に大事なのか」が分からなくなる。
余白と図形配置で生まれるプロフェッショナルな印象
余白は「詰めなかった失敗」ではなく、「意図した設計」だ。ページ四辺に最低1.5cm以上の余白を取り、要素間にも十分な間隔を設けると、読み手の視線が自然に誘導される。
図形配置では4つの原則を使い分ける。
- 整列:全要素を共通のガイドラインに沿って配置する
- 近接:関連する情報はグループ化して近くに置く
- 反復:見出しや矢印などデザイン要素のルールを全ページで統一する
- 対比:重要なメッセージを周囲より大きく・太く・濃く表示する
PowerPointの「ガイド表示」(表示メニュー→ガイド)をオンにして作業すると、目視でのズレが即座に分かる。デザインに自信がない場合は、黄金比や三分割法よりも「全要素がガイド線に揃っているか」だけを確認する方が現実的だ。
PowerPoint・Word・Excelツール別活用術
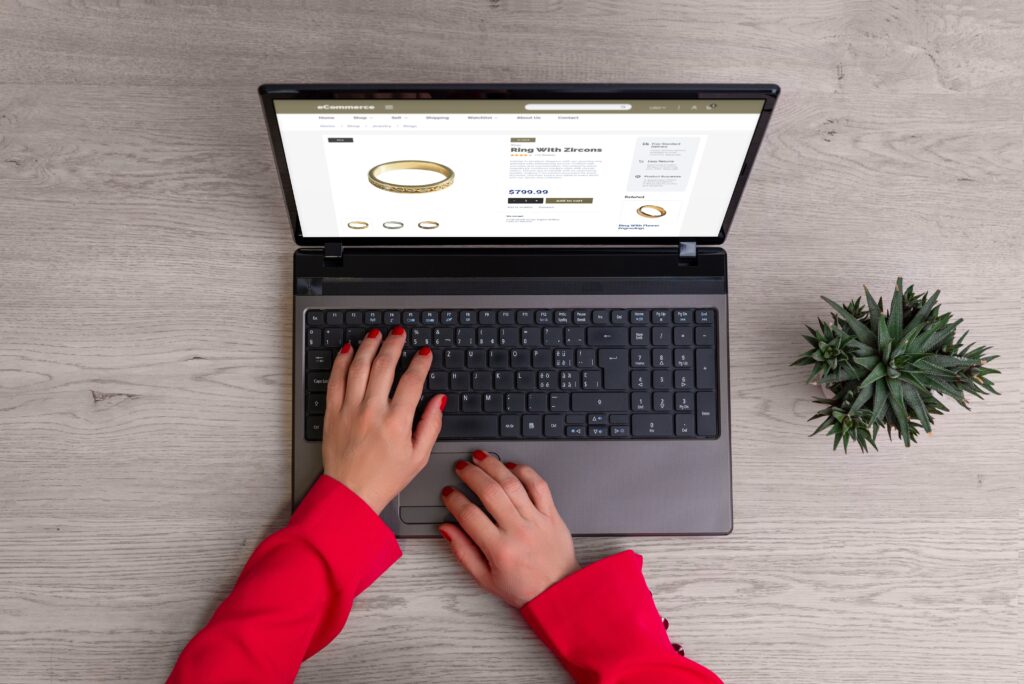
PowerPointで魅力的なプレゼン資料を作るコツ
PowerPointを効率よく使うために、まず「スライドマスター」を設定する。表示メニュー→スライドマスターで開き、フォント・配色・ロゴ位置を一括で登録しておくと、以降のスライドにデザイン設定が自動適用される。資料を作るたびにフォントや色を手動で直す手間がなくなる。
| 機能 | 使い方 | 効果 |
|---|---|---|
| スライドマスター | フォント・配色・ロゴを一括登録 | デザイン統一の自動化 |
| 1スライド1メッセージ | スライドタイトルを「結論文」で書く | 伝達密度が上がる |
| Z・F の法則 | 重要情報を左上に配置 | 視線誘導が自然になる |
| アニメーション制御 | 使うのは段階的開示のみ | 聴衆の集中を維持できる |
「1スライド1メッセージ」を実行するシンプルな確認方法がある。スライドタイトルを見て「だから何?」という問いに答えられなければ、そのタイトルは結論ではない。「市場動向」ではなく「市場は3年で2倍に拡大する」と書く。
アニメーションと遷移効果の適切な使用
アニメーションは、複雑なフローや比較を「順番に見せる」用途に限定する。全スライドに動きを入れると、画面の変化に聴衆の注意が奪われ、話の内容が頭に残らない。遷移効果は「なし」か「フェード(0.3秒)」以外は使わない方が無難だ。
Wordでの読みやすい報告書作成テクニック
Wordでの報告書作成では、最初に「スタイル」を設定してから書き始める。見出し1・見出し2・本文・箇条書きの書式をスタイルとして登録しておくと、後から一括変更できる。フォントを途中で変えたくなっても、スタイルを変更するだけで全箇所に反映される。
| 機能 | 使い方 | 効果 |
|---|---|---|
| アウトライン機能 | 見出しレベルを設定してから書く | 文書構造が崩れない |
| 自動目次 | 参考資料→目次から挿入 | 見出し変更時に自動更新 |
| Excel連携 | グラフを「リンク貼り付け」 | Excelデータ更新が自動反映 |
| スタイル保存 | 書式を登録して再利用 | 次回以降の作業時間を短縮 |
Excelを使った効果的なデータ可視化手法
Excelで最も犯しやすい失敗は「グラフの種類を間違えること」だ。伝えたい内容に合ったグラフを選ぶと、説明なしで数字が伝わる。
| 伝えたいこと | 適切なグラフ | 避けるべきグラフ |
|---|---|---|
| 時系列の変化 | 折れ線グラフ | 棒グラフ |
| 項目間の比較 | 横棒グラフ | 円グラフ |
| 全体に対する割合 | 円・積み上げ棒 | 折れ線グラフ |
| 2変数の相関 | 散布図 | 棒グラフ |
条件付き書式(ホームメニュー→条件付き書式)を使うと、数値の大小を色で自動表示できる。大量データの中から異常値や達成率の高低を視覚的に見つける作業が、関数を書かずにできる。

資料作成スピードを劇的に向上させる時短テクニック

テンプレート活用とマスター機能の効果的利用
テンプレートは「一度作ると、以後ゼロから始めなくて済む資産」だ。よく作る資料の種類(企画書・提案書・報告書・議事録)ごとにテンプレートを1本整備して社内共有しておくと、チーム全体の初動時間が削減される。
テンプレートに最低限組み込むべき要素は次の通りだ。
- 表紙(会社名・ロゴ・日付フィールド)
- 目次ページ
- 本文スライドのレイアウトパターン(テキスト型・図表型・比較型)
- 結論・CTAページ
作ったテンプレートは3ヶ月に一度見直す。使われていないレイアウトを削除し、よく使うパターンを追加する。使いやすいテンプレートは「どのスライドを使えばいいか迷わない」状態が基準だ。
ショートカットキーと自動化機能の活用法
ショートカットキーは「覚えるもの」ではなく「使い続けると自然に覚えるもの」だ。最初から全部習得しようとせず、以下の10個だけを徹底的に使い倒すことから始める。
| ショートカット | 動作 | 特に効く場面 |
|---|---|---|
Ctrl+C / Ctrl+V | コピー・貼り付け | 基本中の基本 |
Ctrl+Z / Ctrl+Y | 元に戻す・やり直し | デザイン調整時 |
Ctrl+Shift+C/V | 書式のコピー・貼り付け | フォント設定の統一 |
Ctrl+G | グループ化(PPT) | 複数要素をまとめて移動 |
F5 | スライドショー開始 | 確認・本番プレゼン |
Ctrl+Shift+矢印 | 整列(PPT) | レイアウト微調整 |
Ctrl+D | 複製 | スライド・図形の量産 |
Alt+Enter | セル内改行(Excel) | 表の見やすさ調整 |
Ctrl+T | 表の挿入(Word) | 素早い表作成 |
Ctrl+Enter | ページ区切り(Word) | 章ごとの改ページ |
WordとPowerPointの「クイックパーツ」機能(挿入メニュー→テキスト→クイックパーツ)に、会社名・免責事項・常用フレーズを登録しておくと、入力の手間がゼロになる。
早期フィードバックで手戻りを防ぐプロセス設計
資料の大幅な作り直しは、ほぼ例外なく「骨子段階でのすり合わせ不足」から起きる。スライドを仕上げた後でフィードバックをもらうと、修正コストが10倍になる。
効率的なレビューサイクルは3段階で設計する。
| フェーズ | タイミング | 確認内容 |
|---|---|---|
| 骨子レビュー | 着手から30分以内 | 3W1Hの方向性・H2の見出し構成 |
| 初稿レビュー | 全体の60〜70%完成時点 | 内容の過不足・論理の流れ |
| 最終レビュー | 完成直前 | 誤字脱字・デザイン統一性・CTA |
骨子レビューは「テキストファイルか箇条書きメモで済ませる」のが正解だ。スライドのデザインを作り込んでからフィードバックをもらうと、「修正が惜しい」という心理が働き、本当に必要な変更に踏み切れなくなる。
チームでの協働資料作成と品質管理

複数人での効率的な資料作成分担方法
チームで資料を作ると質が下がる、というのは役割設計が曖昧なまま始めるからだ。最初に担当範囲を明文化しておくと、重複作業と認識ズレの両方を防げる。
| 役割 | 担当内容 | 向いている人材 |
|---|---|---|
| ディレクター | 全体の品質管理・最終判断 | 資料の目的に精通している人 |
| コンテンツ担当 | 各セクションの原稿作成 | 業務知識が深い人 |
| デザイン担当 | 視覚的統一・図解化 | ツール操作に慣れている人 |
| レビュアー | 読者目線でのチェック | 対象者の立場に近い人 |
分担で重要なのは「担当者が独自判断で変更してよい範囲」を事前に決めることだ。デザインの細部はデザイン担当が決定権を持ち、数値や事実は必ずコンテンツ担当と確認する、というルールを明示しておく。
バージョン管理とフィードバック収集のベストプラクティス
ファイル名のルールを決めていないチームでは、「最新版どれ?」という確認だけで時間が消える。ファイル名は「案件名_資料種別_v1.2_YYYYMMDD」の形式に統一する。
Google DriveやSharePointなどのクラウドプラットフォームを使えば、バージョン管理は自動化できる。ただしクラウドを使う場合も「いつの版が最終承認されたか」を明示するコメントを残す習慣は欠かせない。
フィードバックは「気になったこと」ではなく「こう直す」という形で受け取れるよう、レビュー依頼時に観点を指定する。「内容の抜け・論理の流れ・デザインの統一性」の3つに絞って観点を明示すると、的外れな意見が減る。
品質チェックリストと最終レビューのポイント
最終レビューの前に、以下のチェックリストを使う。
内容チェック
- 3W1Hに基づいた目的が冒頭で示されているか
- 結論が最初と最後のどちらにも登場するか
- 数値・データに出典が明記されているか
- CTA(次のアクション)が明示されているか
デザインチェック
- フォントが全ページで統一されているか
- 使用色が3色以内に収まっているか
- 図表のタイトルと出典が入っているか
- 余白が全ページで一定に保たれているか
最終チェック
- 誤字脱字・固有名詞の表記ゆれがないか
- ページ番号・日付が正しいか
- 資料作成を依頼した相手の期待に応えているか
最終レビューは「資料作成に直接関与していないメンバー」に依頼する。作成者は「書かれていないこと」を無意識に補いながら読むため、抜け漏れを自分では発見しにくい。
継続的改善のためのフィードバック活用
プレゼン後には、提案の結果(承認・否決・保留)と「どのスライドで質問が集中したか」を記録する。質問が多いスライドは情報が不足しているか、論理の飛躍があるサインだ。このデータを次回の資料に反映すると、同じ指摘が繰り返されなくなる。
よくある資料作成の失敗例と改善策

情報過多で読みづらい資料の改善方法
スライドに情報を詰め込む背景にはほぼ例外なく「抜け漏れへの不安」がある。しかし、情報が多いと読み手は要点を探す作業を強いられ、最終的に何も残らない。
改善の手順はシンプルだ。
- 各スライドのタイトルを「結論文(主語+動詞+数値)」で書き直す
- タイトルの結論を支持しない情報を全て削除する
- 削除した情報が必要なら「補足資料」として別ファイルに移す
「補足資料」に移すと決めると、削除に対する心理的抵抗が減る。「消すのではなく移す」という発想で整理を進めると作業が止まらない。
「1スライド1メッセージ」の徹底実践
スライドタイトルを「体言止め」から「文末が動詞の結論文」に変えるだけで、情報の絞り込みが自然に進む。
| 変更前(体言止め) | 変更後(結論文) |
|---|---|
| 市場動向について | 市場は3年で2倍に拡大する |
| 競合比較 | 自社製品は競合3社中コスト最安値 |
| 今後の展開 | Q2から月次ウェビナーを開始する |
タイトルが結論文になると、そのスライドに何を入れるかが自動的に決まる。
デザインの統一性不足を解決するテクニック
複数人で作った資料や、過去の資料を流用した資料でよく起きるのが「フォントが混在している」「スライドごとにレイアウトが違う」という問題だ。
最速の解決策は「スタイルガイドを1ページに作ってチームで共有すること」だ。使用フォント・カラーパレット(HEXコード)・余白設定・見出しのサイズを一覧にしておくと、新しいメンバーが加わっても統一が維持される。
PowerPointの場合、テーマ機能(デザイン→テーマの保存)でチーム共通のテーマファイル(.thmx)を作成し、全員が同じファイルを適用するルールにすると、設定のズレが起きにくい。
目的不明確な資料を生まれ変わらせる手順
「なんか伝わらない気がする」という漠然とした違和感は、ほぼ3W1Hの設計が曖昧なことが原因だ。すでに作った資料が「伝わらない」と感じたら、次の4ステップで立て直す。
- 目的を一文で書く:「誰に、何をしてほしいか」を20字以内で言語化する
- 不要スライドを特定する:目的の一文に直接関係しないスライドに×印をつける
- 冒頭3枚を再設計する:課題提示→結論→根拠の順に並べ直す
- 最終ページにCTAを追加する:「次のステップ」として期限付きのアクションを明示する
この4ステップを実行すると、枚数は減るが伝達力は上がる。
ストーリーテリング手法の活用
「現状の課題→解決策→導入後の姿」という3幕構成は、プレゼンにもホワイトペーパーにも使える。特に「導入後の姿」を具体的な数字で示す(工数が月20時間削減、受注率が15%向上、など)と、読み手がゴールをイメージしやすくなる。
現代の資料作成:AIツールと最新技術の活用

AI支援による効率的な資料作成手法
ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIは、資料作成の「初稿を作る作業」を大幅に速くする。ただし「生成されたものをそのまま使う」と、内容が薄く、AI臭の残る資料になる。AIは「たたき台を作るツール」として使い、仕上げは人間が行うのが正しい役割分担だ。
実務で使えるAI活用のパターンを示す。
| 作業フェーズ | AIの使い方 | 人間がやること |
|---|---|---|
| 骨子設計 | 「3W1H情報を渡してアウトラインを生成させる」 | 抜け漏れの修正・順序の調整 |
| 本文作成 | 「各H2の内容を箇条書きで指示して文章化させる」 | 事実確認・自社固有情報の補完 |
| 表現改善 | 「AI臭を消す指示でリライトさせる」 | トーン調整・専門用語の適正化 |
| 図解化 | 「SlidesAI・Canva AIでビジュアル生成」 | デザイン微調整 |
AIに渡すプロンプトの質が出力の質を決める。「営業部長向けに、来期の広告予算追加申請のアウトラインを作って」より「対象者:経営陣(財務知識あり)、目的:Q2広告予算を200万円追加承認してもらう、前提:昨年の同施策でROI300%達成済み」と情報を構造化して渡す方が、使える出力になる。
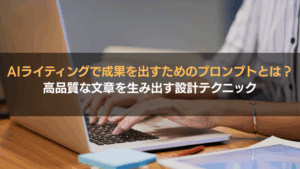
クラウド環境での共同編集とリアルタイム協働
Google Workspace(スライド・ドキュメント・スプレッドシート)とMicrosoft 365の共同編集機能を使うと、複数人が同じファイルを同時に編集できる。「最新版どれ?」問題がほぼ解消される。
編集権限は3段階に分けて管理する。
- 編集権限:プロジェクトリーダー・各セクション担当者
- コメント権限:レビュアー・関係者(内容変更はできないが意見は書ける)
- 閲覧権限:最終承認者・情報共有のみの対象者
非同期作業になる場合(異なる時間帯で作業するメンバーがいる場合)は、コメントで「誰が・何を・いつまでに」確認すべきかを明示する。コメントだけでは漏れやすいため、Slackやチャットと連携してコメント通知を飛ばす設定にしておくと確実だ。
最新ツールを使った資料作成ワークフローの最適化
複数ツールを組み合わせたワークフローを設計すると、繰り返し発生する定型作業が自動化できる。
| 課題 | 解決ツール | 自動化できる内容 |
|---|---|---|
| データ更新のたびに手動で資料を直す | Excel→PowerPoint連携 / Power BI | グラフ・数値の自動反映 |
| 毎月同じフォーマットの報告書を作る | Zapier + Google Slides API | テンプレートへの自動データ挿入 |
| 大量データから異常値を目視確認する | Excel 条件付き書式 / Tableau | 閾値超えの自動ハイライト |
| 完成資料の文章を校正する | Grammarly / 日本語校正AI | 誤字脱字・表記ゆれの自動検出 |
重要なのはツールを増やすことではなく「何の作業時間を削りたいか」を先に決めることだ。目的のないツール導入は管理コストだけが増える。
品質保証の自動化
Grammarlyやテキスト校正くん(日本語)などの文章校正ツールを最終レビュー前に通すと、人間が見落としがちな表記ゆれ・重複表現・句読点の過不足を検出できる。Adobe AcrobatのアクセシビリティチェッカーはPDF化した資料のコントラスト不足や文字サイズの問題も指摘する。これらを通してから人間が最終確認すると、チェックの精度と速度が上がる。
まとめ:継続的な資料作成スキル向上のために

実践的スキル習得のロードマップ
資料作成スキルは「読む」だけでは上がらない。次の順序で実際に手を動かすことが最短ルートだ。
ステップ1(今すぐ): 次に作る資料の3W1Hを一文ずつ紙に書いてから着手する ステップ2(今週中): 既存資料の中で最も伝わっていないと感じるものを選び、PREP法で冒頭3枚を再設計する ステップ3(今月中): チームで使うテンプレートを1本整備し、スライドマスターを設定する ステップ4(3ヶ月後): プレゼン後のフィードバック記録を始め、指摘が集中するスライドのパターンを把握する
スキルが定着するのは「同じ状況で迷わなくなった」と実感したタイミングだ。1本ごとに小さな改善を積み重ねる方が、週末に全部勉強しようとするより確実に上達する。
チーム全体での資料作成力向上
個人のスキルが上がっても、チームの資料品質が揃わなければ対外的な信頼性は上がらない。組織全体での標準化には3つの施策が効く。
- 共通テンプレートの整備と強制適用:「どのテンプレートを使うか」に迷う状態をなくす
- 優れた資料の事例共有:月1回、成功した提案資料を匿名で社内共有する
- 品質チェックリストの運用:提出前に必ず使うルールにする
特に「事例共有」は効果が大きい。「こういう資料で承認が取れた」という実績情報は、研修より早く行動を変える。
今後の技術進歩への対応
AI・クラウド・自動化ツールは今後も進化する。ただし、どれだけツールが変わっても「誰に・何のために・何を伝えるか」という設計思想は変わらない。ツールの習得に時間をかけすぎず、「設計→作成→フィードバック→改善」のサイクルを回すことに集中する方が、長期的に資料作成力は上がる。
資料作成を「外注」する選択肢
ここまで解説したコツを実践しても、「そもそも作る時間がない」「デザインの品質が上げられない」という壁にぶつかることがある。
デボノのサブスクリプション型資料制作サービスでは、一つの資料に10時間以上かかっていた作業が3時間に短縮できた事例がある。 BtoB業界10年以上の知見を持つディレクターと専門デザイナーが、構成設計からデザイン仕上げまでを担う。
社内で作る・外注するの判断基準は、**「この資料に費やす時間の機会コスト」**で考えるとシンプルだ。月に何本も営業資料や提案書を作っているなら、制作を外部に任せてコアな営業活動に集中する方が、売上への貢献度は高くなる。
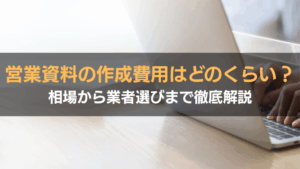
資料作成の品質と速度にお悩みの場合は、まずデボノへのご相談をご検討ください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















