DX推進とは|意味・必要性・実践5ステップと成功のポイントを解説

DX推進は単なるデジタルツール導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化を根本から変革し、競争力を強化する経営戦略である。
DXを成功させるには、現状分析からビジョン策定、体制構築、人材育成、KPI設定、PDCAによる継続改善までの段階的なアプローチが重要。
2025年の崖問題や労働人口減少に対応し、データ活用とテクノロジーによって持続的成長と新たな価値創造を実現することがDX推進の目的。
企業の競争力強化に不可欠となっているDX推進ですが、その本質を正しく理解せずに取り組んでいる企業も少なくありません。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題への対応が急務となる中、DX推進は単なるデジタルツールの導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化を根本から変革する取り組みです。
本記事では、DX推進の基本的な意味から、企業が直面する課題、具体的な推進ステップ、成功のためのKPI設定方法まで、実践的な知識を網羅的に解説します。DX人材の確保・育成方法や成功事例も紹介しますので、これからDXに取り組む方も、推進中の方もぜひ参考にしてください。
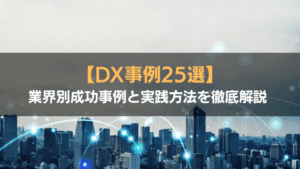
DX推進とは何か

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義
DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化を根本から変革することを指します。経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」では、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
この定義からわかるように、DXの本質は単なる技術導入ではありません。顧客や社会に新たな価値を提供し、市場における競争優位性を獲得することが真の目的です。スウェーデンのウメオ大学エリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した概念が起源とされており、当初は「ITの浸透が人々の暮らしをより良く変化させる」という広い意味で使われていましたが、現在ではビジネス変革の文脈で用いられることが一般的となっています。
DX推進の意味と目的
DX推進とは、企業がDXの実現に向けてあらゆる取り組みを加速させることを意味します。具体的には、デジタル技術の導入、既存システムの改善、業務プロセスの見直し、組織体制の構築など、多岐にわたる活動が含まれます。
経済産業省のデジタルガバナンス・コード3.0によると、DX推進のメリットとして、業務効率や生産性の向上にとどまらず、顧客提供価値の拡大、優秀な人材の獲得、従業員エンゲージメントの向上、創造性人材の育成など、多方面にわたる効果が期待できるとされています。また、サイバーセキュリティ対策を適切に実施することで、企業活動におけるコストや損失を最小化できる点も重要な目的の一つです。
DX推進が目指すもの
DX推進の最終的な目標は、単なる業務改善ではなく、企業全体の変革を通じた持続的な成長基盤の確立にあります。市場環境が急速に変化する現代において、従来のビジネスモデルに固執していては競争力を失うリスクがあります。DX推進によって、変化に柔軟に対応できる組織体制を構築し、新たなビジネスチャンスを創出することが可能になるのです。
DXとIT化・デジタル化の違い
DXを正しく理解するためには、IT化やデジタル化との違いを明確にすることが重要です。これらの用語はしばしば混同されますが、目的と影響範囲が大きく異なります。
IT化との違い
IT化とは、特定の業務にデジタルツールを導入して効率化を図ることを指します。例えば、紙の書類を電子化する、手作業で行っていた計算をExcelで自動化するといった取り組みがIT化に該当します。IT化の目的は既存業務の効率化であり、ビジネスモデル自体の変革を目指すものではありません。一方、DXは組織全体の業務変革によって新たな価値の創出を目指すため、そもそもの目的が異なると言えます。
デジタイゼーション・デジタライゼーションとの関係
デジタイゼーションとデジタライゼーションは、DXに至るまでの段階的なステップとして位置づけられます。デジタイゼーションは個別の業務をデジタル化すること、デジタライゼーションはビジネスプロセス全体をデジタル化することを指します。これらの取り組みを経て、最終的にDXへと到達するという3段階のプロセスが一般的です。
デジタイゼーションの段階では業務標準化や効率化による従業員の負担軽減やコスト削減が実現し、デジタライゼーションの段階ではデータの利活用による業務改善が期待できます。そして最終段階のDXでは、これらの基盤の上に新たなビジネスモデルを構築し、顧客に新しい付加価値を提供することが可能になります。
DX推進が注目される社会的背景
DX推進が多くの企業にとって急務となっている背景には、日本経済が直面する構造的な課題があります。労働力人口の減少、「2025年の崖」と呼ばれるレガシーシステムの老朽化による経済損失リスク、そして新型コロナウイルス感染拡大を契機としたデジタルシフトの加速など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、2024年時点でDXに取り組む企業の割合は73.7%に達しており、2021年度の55.8%から大きく増加しています。この数字は、多くの企業がDX推進の必要性を認識し、実際に行動を起こし始めていることを示しています。しかし同時に、成果が出ていると回答した企業は約6割にとどまっており、取り組みに対して成果がまだ追いついていないケースも多く存在します。
こうした状況の中、企業が競争力を維持し成長を続けるためには、DX推進による社会の変革が不可欠となっているのです。次のセクションでは、なぜDX推進が必要なのか、その具体的な理由を詳しく解説していきます。
なぜDX推進が必要なのか

「2025年の崖」問題への対応
DX推進が急務となっている最大の理由の一つが、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題です。2018年に発表されたDXレポートにおいて、企業がDXを実現できない場合、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があることが指摘されました。この問題の本質は、多くの企業が抱える老朽化したレガシーシステムにあります。
経済産業省の調査によると、日本企業の約80%がレガシーシステムを保有しており、そのうち約70%がDX推進の障壁となっています。2025年には約6割の企業が稼働21年以上のレガシーシステムを抱える見込みであり、これらのシステムは事業部門ごとに構築されて全社横断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズによって複雑化・ブラックボックス化したりしています。
レガシーシステムがもたらすリスク
レガシーシステムの問題は単なる技術的な課題にとどまりません。変化への対応力の欠如により新たなビジネスモデルや市場の変化に迅速に対応できず、部門ごとに分断されたシステムではデータの連携が困難でAIやビッグデータ分析などの先進的な取り組みが阻害されます。さらに、保守・運用コストが膨大となり、新たなデジタル施策への投資余力が削がれてしまうのです。経営者がDXを望んでも、データ活用のために既存システムの問題を解決し、そのためには業務自体の見直しも求められる中、現場サイドの抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題となっています。
競争力強化と市場での優位性確保
近年、世界中のあらゆる市場でデジタル技術による破壊的なイノベーション(デジタルディスラプション)が起きています。これまで市場を牽引してきた企業であっても、突然シェアを奪われてしまうケースが少なくありません。
米国におけるデジタルディスラプションの代表例として、Amazonに代表されるインターネット通販サービスの台頭により大手の小売事業者が経営破綻したケース、Netflixなどのインターネット動画配信サービスが登場したことで大手レンタルビデオ・DVDチェーンが倒産したケースなどが挙げられます。日本企業においても、町の商店や本屋・レコード屋など生活に身近な商売において、デジタル技術を活用して新しいビジネスモデルを展開する新規参入者により、ビジネス環境は大きく変化しています。
グローバル市場での競争
日本企業がグローバル市場で競争力を強化するためには、デジタル技術を活用し既存事業の変革を起こすことが必須となっています。あらゆる産業において、新たなデジタル技術を使ってこれまでにないビジネスモデルを展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起ころうとしている中で、各企業は競争力維持・強化のためにDXをスピーディーに進めていくことが求められているのです。デジタルシフトが進む今日、企業が生き残るためには、デジタル技術によってビジネスモデルに変革をもたらすDX推進が不可欠といえます。
労働人口減少と生産性向上の必要性
日本が直面する深刻な課題の一つが、少子高齢化による労働力人口の減少です。パーソル総合研究所の調査によると、2030年には7,073万人の労働需要に対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、644万人の人手不足となることが明らかになっています。
このような状況下では、既存業務のフローの見直しやテクノロジーの活用によって業務効率化を実現し、一人ひとりの生産性を向上させることが不可欠です。人手不足が社会問題になっている今、DX推進によってデジタル技術を用いた業務に切り替えることで人的コストの削減が可能になります。自動化できる作業はテクノロジーに任せて、その他の業務に人員を割くこともできるのです。
働き方改革の推進
新型コロナウイルス感染拡大を機に、従来のはたらき方や業務プロセスについて課題が浮き彫りになった企業も多いのではないでしょうか。テレワークをはじめ、はたらき方や価値観の多様化が急激に進んだことも、DXを後押しする大きな要素の一つとなっています。コロナ禍は「2025年の崖」問題の深刻さを浮き彫りにするとともに、DX推進の必要性を加速させる触媒となりました。企業は単に目先のデジタル化対応だけでなく、長期的な視点でのレガシーシステム刷新とDX推進の両輪での取り組みが求められています。
急速なテクノロジーの進化への適応
クラウドコンピューティング、AI、IoT、ビッグデータ解析などの先進技術が急速に普及し、企業を取り巻く環境は劇的に変化しています。これらの技術は単独で機能するだけでなく、相互に組み合わせることでより強力なソリューションを生み出します。
例えば、IoTデバイスから収集したデータをクラウド上でAIが解析し、リアルタイムで最適化された業務プロセスを実現するといった統合的な活用が可能になっています。また、技術の民主化により、従来は大企業しか利用できなかった高度な技術が中小企業でも手軽に導入できるようになりました。特に生成AIの登場により、自動生成されるコンテンツのクオリティや分析能力が機械学習や深層学習によって日に日に向上しており、DX推進の取り組みを加速させるとともに、企業文化の変革を実現させるための方法を提供しています。
第四次産業革命の時代
DXが必要とされる背景には、2010年代以降の第四次産業革命が挙げられます。デジタル環境が整備され、デジタルシフトが進み、AIやIoT、ロボティクス、3Dプリンティングなどのテクノロジーを用いて新しい価値を生み出す企業やサービスが登場しました。こうした技術革新のスピードは年々加速しており、従来のビジネスモデルや業務プロセスでは競争力を維持することが困難になっています。企業は継続的な技術導入と業務変革を通じて、変化する市場環境に対応していく必要があります。2025年まで残り少ない中、「崖」から転落せず、デジタル時代の競争を勝ち抜くためには、経営トップのリーダーシップのもと、計画的かつ戦略的なDX推進が不可欠なのです。
DX推進がもたらすメリット

業務効率化と生産性向上
DX推進によって得られる最も直接的なメリットが、業務効率化と生産性の向上です。AIやIoT技術を搭載したシステムや、新しいテクノロジーを備えた設備を導入すれば、業務の自動化・簡略化を実現できます。
従来の手法では人の手が必要だった業務をDXによって自動化すれば、空いたリソースを他業務に回すことも可能です。業務を効率化できると品質にこだわる余裕が生まれるため、製品やサービスの質を向上させられます。データやデジタル技術を使って業務プロセスに変革をもたらすことで、一つの業務に要する時間やコストを削減でき、相対的に生産性の向上につながるのです。
QCD改善への貢献
品質の向上と余分なコストカットを実現すれば、QCD改善にもつながります。QCDとは、Quality(品質)・Cost(コスト)・Delivery(納期)の頭文字を並べたもので、経営戦略における重要な指標です。DX推進は従業員の負担を軽減して業務を効率化できるため、現場に負担をかけずに生産性を向上できることが大きな特徴といえます。また、手作業の業務をツールなどを用いて自動化することで、ヒューマンエラーの削減にも寄与し、全体的な品質向上につながります。
人手不足の解消とコスト削減
少子高齢化によって人手不足が社会問題になっている今、DX推進によってデジタル技術を用いた業務に切り替えることで、人的コストの削減が可能です。自動化できる作業はテクノロジーに任せて、その他の業務に人員を割くこともできます。
特に定型的な業務や繰り返し作業については、RPAツールやAIを活用することで大幅な工数削減が実現できます。例えば、データ入力や集計作業、レポート作成など、これまで多くの時間を要していた業務を自動化すれば、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、限られた人材リソースを最大限に活用し、人手不足という構造的な課題に対応することが可能になるのです。
新たなビジネス価値の創造
DX推進の真の価値は、単なる効率化にとどまらず、新たなビジネスモデルやサービスを創出できる点にあります。デジタル技術を活用することで、これまでにない顧客体験を提供したり、新しい市場を開拓したりすることが可能になります。
蓄積されたデータを分析することで顧客の行動パターンや製品の売上動向を把握し、新製品・サービスの開発や販路拡大などに活かすことができます。例えば、サブスクリプションモデルの導入、プラットフォームビジネスの展開、データを活用した付加価値サービスの提供など、デジタル技術を基盤とした新しいビジネスモデルの構築が可能です。デジタルシフトが進む今日、企業が生き残るためには、デジタル技術によってビジネスモデルに変革をもたらすDX推進が必要不可欠といえます。
競争力の強化
DX推進に取り組むことで競争力を高められ、新規事業の創出にもつながります。デジタルディスラプション(デジタルがもたらす破壊的な改革)により経営破綻した企業や組織も存在していますが、DX推進によって市場での優位性を確保し、持続的な成長を実現できるのです。顧客提供価値の拡大や優秀な人材の獲得など、多方面にわたるさまざまなメリットを享受できる取り組みがDX推進なのです。
働き方改革の実現
DX推進すれば、働き方改革を実現できます。DXによって生産性を向上させれば、従業員の負担を軽減し労働時間を短縮できるのです。従来の手法であれば残業や休日出勤が必要だった業務も、DXで業務効率化すれば限られた時間内で業務を終わらせられます。
コミュニケーションツールや管理システムの導入により、現場で作業しなくても仕事ができる環境の構築も可能です。DXはリモートワークやフレックスタイム制度を促進する施策となるため、多様な働き方の実現につながります。長時間労働を防止し多様な働き方ができる企業へと成長すれば、従業員の定着率が向上し人材不足の課題を解消できます。
従業員満足度の向上
働き方改革を実現したホワイト企業は、求職者から魅力的な職場に見えるものです。働き方改革の実現は定着率向上と採用力の強化にもつながるため、人手不足が課題の企業はDXを推進する価値があります。また、DXを推進していく中で、企業は生産性や従業員エンゲージメントの向上、創造性人材の育成等の恩恵を享受し、結果的に優秀な人材を獲得でき、人的資本経営の実現にもつながるのです。
顧客体験(CX)の向上
DX推進によって、顧客体験(Customer Experience)を大幅に向上させることができます。デジタル技術を活用することで、顧客一人ひとりに最適化されたサービスや製品を提供することが可能になります。
例えば、AIを活用したレコメンデーション機能により顧客の好みに合わせた商品を提案したり、チャットボットによる24時間365日の顧客サポート体制を構築したりすることで、顧客満足度を高められます。また、オムニチャネル戦略を展開することで、オンラインとオフラインをシームレスにつなぎ、顧客にとって利便性の高いサービスを提供できます。新しいテクノロジーを導入することで、顧客体験や顧客満足度の向上が期待でき、企業の業績アップにもつながるのです。
データドリブンな意思決定
DXを推進する過程で蓄積されるデータを分析することで、顧客のニーズや行動パターンをより深く理解できるようになります。この洞察を基にした意思決定により、顧客が本当に求めている価値を提供し、長期的な関係性を構築することが可能になります。データとデジタル技術を活用して顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革することで、競争上の優位性を確立できるのです。
DX推進の3つの領域

プロセスDX(業務プロセスの変革)
DX推進のはじめの一歩となるのが「仕事のやり方を変える」プロセスDXです。従来の業務プロセスにデジタル技術を活用することで、業務効率化や業務改善を実現するために行います。プロセスDXは、DX推進における最も基礎的な段階であり、この取り組みが成功することで次のステップへと進むための土台が築かれます。
プロセスDXの具体的な取り組み例として、業務の現状可視化、業務ナレッジの共有化、業務環境の電子化、業務の自動化、業務の高度化などが挙げられます。例えば、紙の書類をデジタル化してクラウドサービス上に保管することで、情報へのアクセス性が向上し、テレワーク環境でも円滑に業務を進められるようになります。また、RPAツールを導入してデータ入力や集計作業を自動化することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
プロセスDXの効果
プロセスDXを推進することで、業務標準化・効率化による従業員の負担軽減やコスト削減といった効果があらわれ始めます。書類をデジタル化してクラウドサービス上に保管するなど、アナログで行っている業務をデジタル化すると、業務進行が楽になります。ただし、アナログからデジタルへの移行を一気に進めるのは大変です。すぐにデジタル化したい業務、移行の手間が小さい業務から始めてみることをおすすめします。社内全体で取り組むDXの準備段階と言えることもあり、社内で協力して進めることが求められます。
ワークスタイルDX(働き方の変革)
プロセスDXで仕事のやり方を改善した後に着手するのが「はたらき方を変える」ワークスタイルDXです。はたらく環境にデジタル技術を活用することで、時間や場所の制約を減らし、多様なはたらき手を受容し活躍機会を増やします。
ワークスタイルDXの具体的な取り組み例として、テレワークの推進、タレントシェアリング、EX(従業員体験)の向上などが挙げられます。コミュニケーションツールやプロジェクト管理システムを導入することで、オフィスに出社しなくても効率的に業務を進められる環境を整備できます。また、クラウドベースの業務システムを活用することで、場所を問わずに必要な情報にアクセスし、業務を遂行することが可能になります。
柔軟な働き方の実現
ワークスタイルDXを推進することで、従業員は自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を選択できるようになります。育児や介護と仕事を両立させたい従業員、地方に住みながら都市部の企業で働きたい人材など、多様な人材が活躍できる環境を提供することで、優秀な人材の確保と定着につながります。DXはリモートワークやフレックスタイム制度を促進する施策となるため、働き方改革を実現できるのです。組織全体で業務フローや製造プロセスのデジタル化に取り組むことで、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境が整います。
ビジネスDX(事業モデルの変革)
最後に取り組むのが「あたらしい事業を生み出す」ビジネスDXです。新たな事業創造や既存ビジネスモデルの変革を目的として、デジタル技術を活用します。ビジネスDXこそが、DXの本質的な目的である「競争上の優位性の確立」を実現するための取り組みと言えます。
ビジネスDXの具体的な取り組み例として、新規事業の開発、ビジネスモデルの変革などが挙げられます。例えば、製造業が製品販売だけでなくサブスクリプションモデルでサービスを提供したり、小売業がECプラットフォームを構築して新たな販路を開拓したり、データ分析サービスを新規事業として展開したりすることが該当します。顧客に新しい付加価値を提供できるよう、事業やビジネスモデルに変革を起こす段階です。
新たな価値創造
ビジネスDXを推進することで、新しい事業・ビジネスモデルに伴う競争力の強化が期待でき、データ分析による新製品・サービスの開発や販路拡大などを目的とします。蓄積されたデータを基に販路拡大や新商品・サービスの開発に活かすことで、企業は市場での差別化を図り、持続的な成長を実現できます。DXはデジタル化によって顧客に新しい価値を提供することが求められます。DXで社会に何をもたらしたいかを最初に明確にすることで、取り組みを考えやすくなります。個社のDXを超えて、国境・産業・組織等をまたぐデータ連携を行うことで、さらに付加価値を高めることができるのです。
DX推進の具体的なステップ

ステップ1: 現状分析と課題の明確化
DX推進を実現するための最初のステップは、自社のデジタル活用状況や課題を可視化することです。まずはDX推進の現状を把握し、解決すべき課題を整理しましょう。たとえば、現在運用しているシステムをリストアップし、その保守や管理に関わっている従業員の負担がどれくらいか、業務のボトルネックになっているのは何かなどを調査します。
既存のシステムや情報資産だけでなく、従業員の能力や適性といった「ヒト・モノ」の双方の把握が大切です。基幹システムの種類や導入してからの経過年数、活用頻度をデータ化しましょう。データに基づいて改良するべき課題を可視化すれば、導入するべき設備やシステムを把握できます。実務に関する課題は現場の方がより気づきやすいため、ヒアリングを通じての洗い出しも効果的です。
DX推進指標の活用
経済産業省が公表している「DX推進指標」を活用することで、自社のDX進捗状況を客観的に評価できます。DX推進指標は、DX推進のための経営体制(組織体制)とITシステム面の整備状況という2つのカテゴリーから企業のDX状況を評価する点が特徴です。どちらの観点においても、定性指標・定量指標の双方で評価を行います。この指標を用いた自己診断により、自社の現状や具体的な行動、進捗を明確化・共有することが可能になります。現状のDX推進度と課題を可視化することで、目指すべき目標を見つけられます。
ステップ2: DX推進の目的とビジョンの策定
現状把握の次は、DX推進の目的を明確にすることから始めましょう。DX推進はすべての企業が早急に対応すべきことではありますが、目的がはっきりしないままプロジェクトを進めていても関係者に当事者意識が醸成されず、十分な効果が得られなくなってしまいます。
自社のビジネスをどのように変革するためにDX推進を行うのかを明らかにして、関係者全員が共通認識を持つことが大切です。DXはデジタル化によって顧客に新しい価値を提供することが求められます。DXで社会に何をもたらしたいかを最初に明確にすることで、取り組みを考えやすいです。ビジョンを明確にし社内外で共有することが、DX推進成功の第一歩となります。
KGIとKPIの設定
ゴールを明確にすることで、組織全体が共通認識を持ちながらDX推進ができるため、途中で目的を見失うことがありません。そのためにはKGIやKPIといった具体的な数値を掲げるのがおすすめです。KGI(Key Goal Indicator)は売上等、企業が掲げる数値目標を指し、KPI(Key Performance Indicator)はKGIの達成に向けて必要な要素を意味します。KPIの具体例としては、成約率アップや営業チャネルの強化など、売上を上げるために必要となる詳細な活動が挙げられます。KGIやKPIを設定することで具体的な数値がベースになるため、目標の見える化によって作業の進捗具合が分かりやすくなるでしょう。
ステップ3: 全社的な意識共有と体制構築
DX推進の目的を定めたら、次はDX推進の取り組みに必要な人員を揃えて、社内体制を整備します。DX推進は全社に影響するため、さまざまな部門やスペシャリストとの連携が欠かせません。プロジェクトマネージャーをはじめ、エンジニアやプログラマー、デザイナー、データアナリストなど、DX推進にあたって必要なDX人材を確保することが大切です。
DX推進は一部門や一部署が単独で行う部分最適の施策ではなく、企業全体に関わります。全社に向けてDX推進を周知し、理解を得ることが大切です。経営者やマネジメント層のようなトップ層はもちろん、現場の混乱や従業員の不満を解消して協力を得ることが重要です。「経営部門はDX推進を重視しているが、現場は忙しくてそれどころではない」といったケースも多く、企業全体で同じ目線を持つことに課題を感じている企業は少なくないでしょう。
推進体制の構築
DX推進のための体制構築には、経営トップのコミットメントが不可欠です。経営者は、自らのリーダーシップでDX推進を推進していく必要があります。また、DX推進のために各部門の役割を明確にしサポート体制を確立することも重要です。プロジェクトの規模によっては、新たにDX人材を採用することも検討しましょう。従業員を教育し、企業文化を変革することで、全社一丸となってDXに取り組む土台が整います。
ステップ4: DX人材の確保と育成
DX推進には、新たな企業体制の構築に取り組む部署ならびにチームの新設や、DXの知識をもつ人材の確保が必要です。予算を確保し、必要に応じて外部人材の採用や既存社員の育成を行います。
経済産業省によると、2030年には最大で79万人ものIT人材が不足すると言われており、DX人材の獲得競争は激化しています。即戦力を求め、中途採用を検討する企業が多いと思いますが、人材獲得競争が激化しているため、採用だけでなく社内に適任者を探すことも重要です。外部の人材を積極活用している企業が多くなっている一方、プロダクトマネージャーやビジネスデザイナーといったDXを主導するリーダー層は社内の人材を登用する傾向にあります。
内部人材の育成方法
社内の人材を育成すれば、テクノロジーだけでなく自社のビジネスにも精通した、DXを推進する上で心強い戦力となる人材が確保できるようになります。求める人物像を策定し、育成計画を立案した上で、インプットとアウトプットを交えて育成することが重要です。重要なのは「現場を変えるために行う」といった視点を持ち続けることです。実践(=アウトプット)を繰り返すなかで、徐々にデジタル・自動化をベースに業務プロセスを考える癖が身についていき、デジタル思考へと変わっていくことが期待できます。プロジェクト型のワークショップを多く行うなど、座学で終わらないカリキュラムを企画するとよいでしょう。
ステップ5: 優先順位をつけた計画立案
解決すべき課題を抽出し、人材を確保したら、DX推進の優先順位をつけます。DX推進は自社のビジネスへの影響範囲が大きく、一気にすべてを変えるのは難しいと言えます。そのため、着手するタスクの重要度や緊急性などにしたがって優先順位をつけてスケジュールを策定し、計画的に進めていきましょう。
洗い出しにより複数の課題が上がることは珍しくありません。今すぐに改善が必要な業務や、効果がすぐに分かりそうなものから取りかかることがおすすめです。計画の優先順位を定め、目標に期限を設け、スケジュールを明確化し、必要なリソースを把握し、責任者や必要な役割を洗い出すことで、DX推進プロセスへ取り組む意欲を向上させられます。現在の課題と目標達成に向けて必要な要素を可視化して、DX推進プロセスを策定しましょう。
スモールスタートの重要性
DXは組織全体から始めるのではなく、着手しやすい部分から小さな改善を重ねることが大切です。いきなり組織全体でDXを進めると、失敗した際の損失が大きいからです。新たな設備やテクノロジーの導入には高額な費用や手間が発生するため、まずはスモールスタートから始めましょう。特定の工程や部署からDXを推進し、成果が出た場合にはDXを推進する範囲を広げていきます。現在の課題を一つずつ解消していき、組織全体のDXを推進していくことが大切です。
ステップ6: 実行とPDCAサイクルの運用
DX推進は中長期的に取り組む必要があるため、新たな仕組みを運用しながら、都度改善点がないかを点検し、PDCAサイクルを回しましょう。外部環境の変化とともにビジネスのあり方も変容しなければなりません。刷新したシステムが再びレガシー化する可能性もあるため、常にアップデートを図ることが重要です。
PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字を取った品質改善方法です。上記の4プロセスを繰り返すことで、継続的に品質を改善できます。DX推進においても、施策が順当に成果を挙げられているか評価し、現状の課題を解消する施策を立案するために効果的です。KPIを設定して数値で進捗を確認しながらPDCAを回し進めることが重要です。
継続的な改善の仕組み
蓄積したデータを活用することも大切です。システムによってデジタルデータを集計・分析すれば、現状のDX推進度を可視化できます。可視化することで、顧客の行動パターンや製品の売上動向・業務の効率性・設備稼働率など、業績向上につながるデータを分析できます。DXを実現するためには、新しいシステムやテクノロジーを導入するだけでなく、企業に新たな価値を創造しなければなりません。蓄積したデータを活用することで、企業は自社のビジネスや現状を深く理解し、ビジネスチャンスを見つけ出せるのです。DX推進状況を評価し施策を見直すことで、長期的に成果を最大化できます。
DX推進を成功させるKPIの設定と効果測定

KPIとKGIの違い
DX推進を成功に導くためには、適切なKPIを設定して進捗を可視化することが不可欠です。まず、KPIとKGIの違いを正しく理解しておく必要があります。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)は、最終的に達成すべき目標を示す指標です。例えば「2025年までに売上高を20%増加させる」「顧客満足度を30%向上させる」などが該当します。
一方、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、そのKGIを達成するための中間指標であり、プロセスの進捗度を測るものです。目標達成までの各ステップにおいて、達成度合いの計測および評価を正確に行うために存在します。DX推進においては、達成までの各プロセスの達成度合いを客観的に計測するために、KPIが必要不可欠です。KPIがしっかりしていないと、計画通りにプロジェクトが進んでいない場合に気づかずに誤った方向に進んでしまう可能性が高いからです。
KPIの役割
KPIは単なる数字の羅列ではなく、DXの目的と進捗を可視化し、経営層と現場の共通言語となる重要なツールです。KPIを設定することで、DX施策の進捗や成果を数値で把握でき、DXの効果を明確にし必要な調整や改善を実現します。また、経営層と現場が同じ基準で成果を評価するための共通言語となり、施策の優先順位も明確になります。その点、KPIをしっかりと設定しておけば、DX推進の各過程での達成度合いを正確に把握し、目標の達成確率を大きく向上させられます。
DX推進指標の活用方法
経済産業省が公表している「DX推進指標」を活用することで、自社のDX進捗状況を客観的に評価できます。DX推進指標とは、経済産業省が令和元年に公表した指標で、DX推進のための経営のあり方、仕組みに関するものと、DX実現のために基盤となるITシステム構築に関するものの2つに分類されています。それぞれに対し、定量、定性指標について35もの項目が紐づけられています。
DX推進指標は企業が自社の状況と照らし合わせながら質問に回答していくことで、DXの推進状況を点数化しながら見える化し、次の行動へとつなげていくのが目的です。したがって、DX推進指標で高得点をとることは重要ではありません。重要なことは、DX推進指標で自社が弱いと感じた部分へどのように取り組んでいくべきなのか、あるいは取り組む必要はないものではないのかなど、自己分析をすることです。
DX推進指標のメリット
DX推進指標をKPIとして活用するメリットとして、DXの進捗状況について社内で共通認識を持てることが挙げられます。DX推進指標の自己診断では、経営者や経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門など社内の主要な関係者が議論をしながら回答することが想定されています。そのため、DXに対するビジョンや目的などの共通認識を社内で醸成することが可能です。また、自己診断をIPAに提出することで、その自己診断結果を分析した診断結果と全体データとの比較ができるベンチマークを入手できます。それによって現在のDXの達成度合いを数値で確認でき、適切な進捗管理が可能です。自社のレベルが確認できた後、次にどのようにDXを進めていけばよいのかについても「『DX推進指標』とそのガイダンス」にまとめられています。
効果的なKPI設定の5つのポイント
DX推進において効果的なKPIを設定するためには、体系的な手順が重要です。感覚的に指標を決めるのではなく、以下の5つのステップに沿って設定しましょう。
ステップ1: KGIの明確化
まずは、DX推進によって最終的に達成したい目標(KGI)を明確にします。「売上30%増加」「顧客満足度50%向上」「業務効率40%改善」など、具体的な数値目標を設定しましょう。ゴールを明確にすることで、組織全体が共通認識を持ちながらDX推進ができるため、途中で目的を見失うことがありません。
ステップ2: 達成プロセスの洗い出し
KGIを達成するために必要なプロセスや施策を洗い出します。例えば「顧客データ統合」「業務プロセス改革」「デジタル人材育成」など、具体的な取り組みを列挙します。DX推進におけるKPIを設定する前に、まずは現在の業務プロセスを洗い出す必要があります。業務プロセスを徹底的に分析し、デジタル化の対象となるプロセスを明確にします。この分析によって、どの業務をDXするか、どのプロセスが顧客体験を向上させるかが見えてくるでしょう。
ステップ3: SMART原則に基づくKPI設定
洗い出したプロセスごとに、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限付き)に基づいてKPIを設定します。KPIは多くの業種や職種で採用されている指標ですが、DX推進でのKPIの設定は、この原則に従うことで実効性が高まります。従業員全体が分かりやすいような明確な内容を設定するのが重要です。
ステップ4: バランスの取れた指標選択
財務、顧客、業務プロセス、学習と成長という4つの視点からバランスよくKPIを設定しましょう。DX推進指標の中からKPIを選定して、具体的なDXを施策していきましょう。DX推進指標は、あくまでも共通化されたフォーマットであるため、自社のビジネススタイルに応じた内容へのカスタマイズが求められます。自社に合わせたカスタマイズをすることで、KPIの評価がしやすくなり、より正確に現時点の進捗状況を把握できるでしょう。
ステップ5: 定期的な見直しと調整
設定したKPIは固定的なものではなく、評価結果に基づいて柔軟に見直し、改善していくことが重要です。市場環境の変化や技術の進化に応じて、KPIを適宜調整することで、常に最適な指標でDX推進を測定できます。継続的な改善サイクルを回すことで、DX推進の効果を最大化することができるでしょう。
定期的な評価と改善のサイクル
KPIを設定したら、定期的に進捗状況を確認し、目標に対する進捗度を把握することが重要です。進捗が遅れている場合はその原因を分析し、必要に応じて改善策を講じる必要があります。進捗状況の確認を通じて、DXの取り組みを常に最適な状態に保つことができるでしょう。
DX推進の取り組みは可視化することが難しく、KPIを曖昧なまま進めてしまうと、どこにどのような問題があるのか発見できないまま、間違った取り組みを継続してしまうことにもつながります。まずは現状を知ることで、何が足りないのかを把握しながらDXと向き合うことが大切です。ビジネス的視点で何をKPI(重要業績評価指数)とするのかを明確にしておくことで、到達度が可視化されます。曖昧な効果測定にならないためにも、「何で」効果測定を行うのか慎重に決めることがポイントです。
PDCAサイクルの実践
PDCAは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の項目をまとめたサイクルです。PDCAを回すことで、DXの取り組みを継続的に改善する環境が構築できます。PDCAを繰り返すことで、DX推進の取り組みを最適化し、効果を徐々に高めていくことが可能です。PDCAは、業種や職種を問わずにKPIを活用するうえでの基本的で重要なフレームワークです。DX推進状況を評価し、施策を見直すことで、長期的に成果を最大化できます。これらを継続的に実行することで、DXの進捗が数値で把握でき、改善の手を打ちやすくなります。KPIはDXを加速させるための羅針盤です。精度の高い羅針盤を持つことが、DX成功への最短ルートになります。
DX推進を阻む課題と対策

経営層と現場の意識ギャップ
DX推進を阻む企業課題として、社内に危機感が浸透していないことが挙げられます。2022年7月に経済産業省が発表した「DXレポート2.2」によると、DX推進の重要性は浸透しつつある一方で、企業におけるデジタル投資の内訳は、既存ビジネスの維持・運営に約8割が占められている状況が続いています。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」によると、DXの前提となる「将来への危機感」が企業全体になかなか浸透しないこと、変革に対する社内の抵抗が強いことが課題として挙げられています。DXは一部門や一部署が単独で行う部分最適の施策ではなく、企業全体に関わります。「経営部門はDX推進を重視しているが、現場は忙しくてそれどころではない」といったケースも多く、企業全体で同じ目線を持つことに課題を感じている企業は少なくないでしょう。
対策: ビジョンの共有と全社的な取り組み
DX推進を成功させるには、全社員の協力が不可欠です。そのためには、まず経営陣が主導でDX化の重要性とビジョンを明確に示し、それを全社員に共有するといった経営レベルの意識改革が必要です。同時に、各部門間の連携を強化し、現場の従業員にも情報を共有することで、社員一人ひとりに課題意識を持たせるようにしましょう。単にDXを推進すると言っても、どんな理由でDXが必要なのか、DXするとどうなるのかが不透明だと意味がありません。企業としてDXの先にあるビジョンを明確にすることで、はじめて目的意識が芽生えます。まずはビジョンを明確にし、社内外で共有することが重要です。変革しないことで発生する危機を、経営者や現場の人間で共有し、従業員を教育し企業文化を変革することで、全社一丸となってDXに取り組む土台が整います。
DX人材不足への対応策
パーソルホールディングスの調査によると、大手企業の6割、中小企業の4割がDX推進に課題感をもっていることが明らかになりました。取り組みの障壁となっている課題として、最も回答数が多かったのは「推進のためのスキルを持った人材を社内で育成できない」でした。
DXを推進していくためにはデジタル技術に精通した人材だけではなく、業務プロセスを理解し改善できる人材や、抜本的な改革を推進できる人材など、さまざまなスキルをコラボレーションさせる必要があります。しかし、DX人材は獲得競争が激化しており、「予算を確保しているものの採用ができない」「社内でどう育成すればよいのかわからない」といった課題を抱える企業が増えているのが現実です。現在は多くの企業でDX化が進められていることもあり、DX人材が不足しています。
対策: 外部活用と内部育成のバランス
DX人材を獲得する方法は、「採用」と「育成」の2つがあります。人材市場におけるIT通信業界出身者の需要はここ数年で急増し、獲得競争が激化しています。一般的な採用活動のほかに優秀なDX人材を競合他社からスカウトするケースも増えています。IPAの調査によると、外部人材の活用として、先端技術のエンジニアといったシステムの実務を担う業務に外部の人材を積極活用している企業が多くなっています。一方、プロダクトマネージャーやビジネスデザイナーといったDXを主導するリーダー層は社内の人材を登用する傾向にあります。したがって、人材の確保が難しい場合には、DX推進を効率的に進められるDXツールの利用もおすすめです。また、DX人材が適切に評価される環境の構築も重要です。社内の人材を育成すれば、テクノロジーだけでなく自社のビジネスにも精通した、DXを推進する上で心強い戦力となる人材が確保できるようになります。
レガシーシステムからの脱却
長年社内で使われてきた既存システムから刷新する場合の負担が大きく、DX推進が阻まれているケースもよく見られます。これまでの運用で蓄積されてきたデータが多いなどの理由で既存システムに依存していると、新たなシステムにリプレイスすることができず、古いシステムを使い続けざるを得ない状況になりかねません。
レガシーシステムは、メンテナンスコストや運用の属人化が問題視されており、新しい価値観・技術への改革が求められています。レガシーシステムの問題は、DX推進における最大の障壁となっています。変化への対応力の欠如により、レガシーシステムは柔軟性に欠け、新たなビジネスモデルや市場の変化に迅速に対応できません。また、部門ごとに分断されたシステムではデータの連携が困難で、AI・ビッグデータ分析などの先進的な取り組みが阻害されます。保守・運用コストが膨大となり、新たなデジタル施策への投資余力が削がれるという悪循環に陥ります。
対策: 計画的なシステム刷新
DXを実現すれば、老朽化したシステムの刷新を図れるため、レガシーシステムから脱却できます。ただし、一気にすべてのシステムを入れ替えるのではなく、優先順位をつけて段階的に刷新していくことが重要です。特に重要なのは、経営のトップが自社に必要な取り組みを判断する役割を持ち、DX推進に必要な人材を育成し確保することです。DX推進のために各部門の役割を明確にしサポート体制を確立することで、システム刷新をスムーズに進められます。また、クラウドサービスの活用やマイクロサービスアーキテクチャの導入など、柔軟性の高いシステム構成を選択することで、将来的な変化にも対応しやすくなります。
失敗パターンと回避方法
DX推進ができない企業には、いくつかの共通した失敗パターンが存在します。これらのパターンを理解し、事前に対策を講じることが成功への近道となります。
失敗パターン1: ツール導入が目的化
DXは既存の業務にツールを導入してデジタル化することと捉えがちですが、DXの本質は企業を変革していくための一つの手段であり、ツールの導入が目的ではありません。例えば、従来Excelで管理していた勤怠管理にクラウド型ツールを導入したり、給与計算ツールと結び付けたりすることは、業務の効率化を叶えるための「IT化」といえます。一方、DXではその先の競合優位性や生産効率の向上を目指していきます。したがって、ツールを入れた後も、期待した効果に対しどれだけの成果が得られているかを検証しなくてはいけません。「ツールを入れて便利になった」で終わってしまわないよう、目的意識を持って導入しましょう。
失敗パターン2: 従業員の意識改革不足
DX推進ができないもう一つの理由は、従業員の意識改革ができていないためです。明確な目標があってもKPIを設定しても、業務に携わるのは従業員です。その従業員がDX推進を理解し、率先して業務に取り組まないと実現はできないでしょう。すでにKPIを設定していても、一度設定したKPIのことを忘れて目標設定からやり直してみましょう。明確な目標が設定できると、その目標達成に必要なKPIが自然と見えてきます。DXの本質を理解し、全社で取り組む意識を持つことで、失敗を回避できます。
失敗パターン3: 短期的な視点での判断
多くの企業では、DXへの投資を短期的なROIで判断し、長期的な競争力強化の視点が欠如しているケースが見られます。DX推進は中長期的な取り組みであり、すぐに成果が出ないこともあります。しかし、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことで、最終的には大きな成果につながります。短期的な成果にとらわれず、長期的な視点で取り組むことが重要です。
DX人材に求められるスキルと育成方法
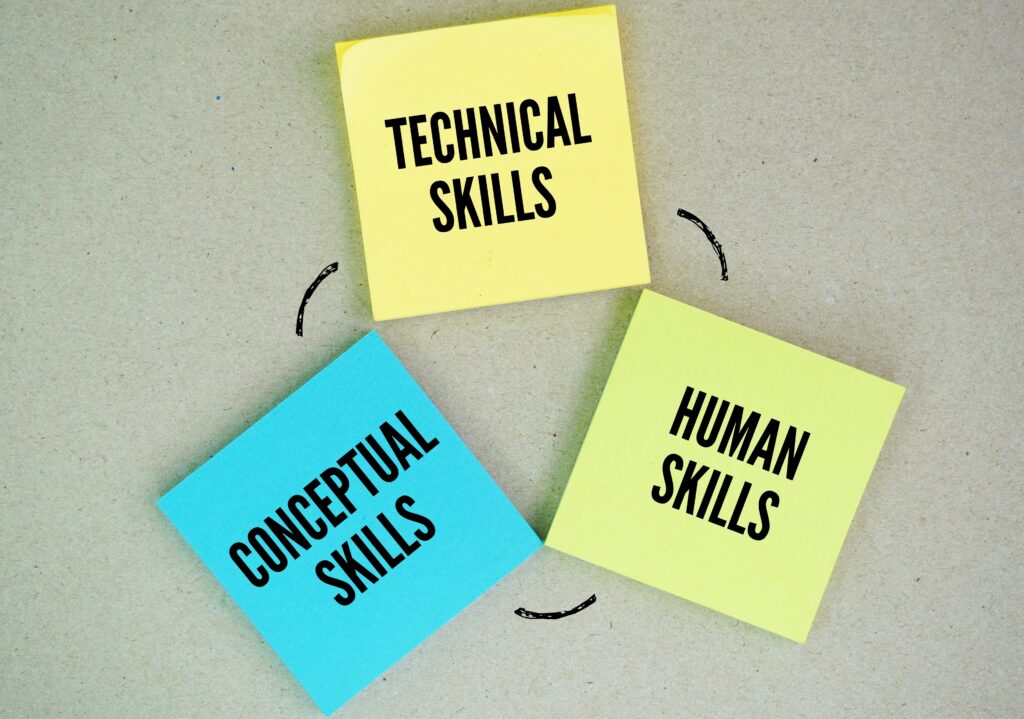
ビジネス変革スキル
DX推進は単なるデジタルツールなどの導入にとどまらず、ビジネスの変革を目的に行われます。従来のビジネスモデルから転換し、新たな販売チャネルを立ち上げるなどの取り組みが考えられるでしょう。そのためDXの推進に関わる人材には、ビジネス戦略の策定・実行をはじめ、ビジネスモデルや業務プロセスの設計、マーケティングやブランディングの理解といった多様なスキルが求められます。
また、顧客提供価値を向上させる上で欠かせない顧客・ユーザー理解も、ビジネス変革のスキルに含まれます。デジタル技術を活用して顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するためには、顧客が何を求めているのかを深く理解する必要があります。市場調査やデータ分析を通じて顧客インサイトを把握し、それをビジネス戦略に反映させる能力が重要です。
データ活用スキル
データ活用のスキルは、DXを推進する人材には不可欠と言えるでしょう。データを正しく理解し、ビジネスにおける意思決定や業務改善に活用できるスキルはもちろん、データ・AIの活用戦略を設計するスキルも必要です。
さらに、データサイエンティストとしての数理統計・多変量解析・データ可視化や、データエンジニアとしてのデータ活用基盤設計など、幅広い専門性が求められます。蓄積されたデータを基に販路拡大や新商品・サービスの開発に活かすためには、データを適切に収集・整理・分析し、そこから有益なインサイトを導き出す能力が必要です。ビッグデータやAIを活用したデータ分析により、これまで見えなかった顧客の行動パターンや市場のトレンドを把握し、ビジネス戦略に活かすことができます。
テクノロジースキル
DX推進におけるテクノロジーのスキルは、主にエンジニアが担うソフトウェア開発を指します。基本的なプログラミングスキルはもちろん、ソフトウェアの設計や開発プロセスの策定、フロントエンドシステムやバックエンドシステムの開発などが当てはまります。
デジタル技術を駆使しながら自社の課題を解決する能力を持った人材は、DX推進の要となる存在と言えるでしょう。クラウドコンピューティング、AI、IoT、ビッグデータ解析などの先進技術に関する知識と実践力が求められます。また、アジャイル開発やDevOpsといった現代的な開発手法についても理解し、実践できることが重要です。技術は日々進化しているため、継続的に学習し、最新の技術動向をキャッチアップする姿勢も必要とされます。
セキュリティスキル
DXにおいて非常に重要なのがセキュリティのマネジメントです。社内の膨大なデータを扱うにあたって、データの流出や不正アクセスなどを防ぐ必要があり、万が一トラブルが起こった場合には企業の社会的信用にも関わるためDX人材に必須のスキルと言えます。
企業の財産とも言えるデータを適切に管理することが、DX推進の基盤となります。サイバーセキュリティ対策は必要不可欠な投資であると捉え、サイバーセキュリティリスクを把握・評価し、対策を実施することで、企業活動におけるコストや損失を最小化できます。また、個人情報保護法やGDPRなどの関連法規制についても理解し、適切なデータガバナンスを実施する能力が求められます。法令等に従い適切なデータの保護措置等を実施し、データを管理・活用すること(データガバナンス)で、取引先等からの信頼性が向上します。
パーソナルスキル
ここまでに挙げたビジネススキルや専門的な技術力はもちろん大切ですが、中長期にわたるDX推進のプロジェクトを進める上ではリーダーシップや適応力といったパーソナルスキルも欠かせません。困難な状況に直面しても柔軟に対処しながら確実にプロジェクトを遂行できるように、プロジェクトメンバー間で連携を図り、問題解決に導くスキルが求められます。
特に重要なのは、変化を恐れず新しいことに挑戦する姿勢です。DX推進は既存の枠組みを変革する取り組みであるため、従来のやり方に固執せず、柔軟に新しいアプローチを試みる姿勢が必要です。また、失敗から学び、改善を続ける粘り強さも重要なパーソナルスキルと言えます。コミュニケーション能力も欠かせません。経営層、現場の従業員、外部のパートナーなど、さまざまなステークホルダーと円滑にコミュニケーションを取り、プロジェクトを前に進める力が求められます。
外部人材の活用と内部育成のバランス
DX人材を確保する方法として、外部からの採用と内部での育成があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の状況に応じて適切なバランスを取ることが重要です。
外部人材の活用
外部人材の活用のメリットは、即戦力となるスキルとノウハウをすぐに獲得できることです。特に、先端技術のエンジニアやデータサイエンティストなど、専門性の高い人材は外部から採用することで、プロジェクトを迅速に立ち上げることができます。採用ターゲットを明確化し、自社の魅力をアピールすることで、優秀な人材を引きつけることが可能です。採用活動を始める前に自社の課題を洗い出し、DX人材に求める役割や必要なスキル、ノウハウを明確にします。採用後に任せたいポジション、必要なスキル、適性を整理し、求める人物像が漠然としているときに陥りがちな、採用後の組織戦略とのミスマッチや選考がスムーズに進まないといった事態を防ぐことができます。
内部人材の育成
内部人材の育成のメリットは、自社のビジネスや文化を理解した上でDXを推進できることです。求める人物像を策定し、育成計画を立案した上で、インプットとアウトプットを交えて育成することが効果的です。求める人物像を策定する方法は2つあります。経営戦略からあるべき人物像を描く方法と、既存プロジェクトのハイパフォーマーのコンピテンシーを抽出する方法です。既存事業の価値向上を目指す、または新規事業でのマネタイズを目指すなどの経営戦略から、組織戦略を描き、あるべき人材像を深堀していく方法があります。また、すでに社内で走っているプロジェクトにおいて高い価値を発揮している従業員がいれば、その従業員が持つスキルやマインド、行動を抽出してみるのも有効です。重要なのは「現場を変えるために行う」といった視点を持ち続けることです。実践(=アウトプット)を繰り返すなかで、徐々にデジタル・自動化をベースに業務プロセスを考える癖が身についていき、デジタル思考へと変わっていくことが期待できます。
DX推進の成功事例

製造業の事例
製造業におけるDX推進の成功事例として、ダイキン工業株式会社の取り組みが挙げられます。ビルや商業施設・病院などにおいては、部屋や設備などの使用状況に応じた空調コントロールが必要です。しかし、設備管理者の人手不足が課題になっているケースも多く、できるだけ効率的で手間のかからない運用や管理が求められていました。
ダイキン工業株式会社が2021年から展開している「DK-Connect」は、空調機をクラウドに接続し、パソコンやスマートフォン・タブレット端末からの監視や制御を可能にします。これによって、顧客ごとに空調管理を効率化し、快適性の向上やエネルギー消費量の削減、管理工数の削減などにつながっています。IoT技術とクラウドサービスを組み合わせることで、遠隔地からでもリアルタイムで空調設備の状態を把握し、最適な制御を実現しています。
製造業DXのポイント
製造業におけるDX推進では、IoTやAIを活用した設備の見える化と最適化が重要なポイントとなります。生産ラインのデータをリアルタイムで収集・分析することで、設備の稼働状況や不良品の発生パターンを把握し、予知保全や品質改善につなげることができます。また、清水建設株式会社の建物OS「DX-Core」のように、建物のシステムや設備の一元管理を実現することで、入居者・建物管理者・オーナーの利便性や業務効率性の向上に役立てることも可能です。従来、建物内に新しいシステムを導入するには、システムや設備を個別に連携する必要があり、時間やコストがかかりがちでしたが、統合的なプラットフォームを構築することでこれらの課題を解決しています。
小売業の事例
小売業におけるDX推進の代表例として、株式会社セブン&アイ・ホールディングスのグループ横断DX推進があります。お客様に豊かな生活体験を提供するため、グループのDXにおける課題解決とともに、グループ共通ID「7iD」の活用をはじめとするさまざまなDX施策を実施しています。
DX戦略としては、DXを「守り」と「攻め」の2つに分け、前者は各種セキュリティ対策と効率化を、後者は新たな顧客価値の創造をテーマとしています。施策の実行にはAIを活用しており、多様化する宅配ニーズに対応して配送を最適化する「ラストワンマイルDXプラットフォーム」の開発を「攻めのDX」施策として行っています。顧客データを統合的に管理し、パーソナライズされたサービスを提供することで、顧客満足度の向上と売上拡大を実現しています。
小売業DXのポイント
小売業におけるDX推進では、顧客接点のデジタル化とデータ活用が鍵となります。オンラインとオフラインをシームレスにつなぐオムニチャネル戦略の展開、顧客データの分析による最適な商品提案、在庫管理の効率化などが重要な要素です。また、ECプラットフォームの構築やモバイルアプリの開発により、顧客との接点を増やし、購買体験の向上を図ることができます。AIを活用したレコメンデーション機能やチャットボットによる顧客サポートなど、テクノロジーを活用した顧客体験の向上も小売業DXの重要なポイントとなっています。
サービス業の事例
サービス業におけるDX推進の事例として、ms&adインシュアランスグループホールディングス株式会社の取り組みが注目されます。交通事故リスクの防止・軽減には、危険箇所の洗い出しや詳しい分析が欠かせません。ms&adインシュアランスグループホールディングスの「交通安全EBPM支援サービス」は、自社の保険サービスの提供によって蓄積されたデータを、事故リスク軽減のために活用するものです。
自動車の走行データをもとに、危険箇所候補の選定、要因分析、対策の提案、効果の検証をワンストップで行うことができます。「交通安全EBPM支援サービス」は自治体の安心・安全なまちづくりに貢献する取り組みとして、2023年の内閣官房主催「冬のDigi田甲子園」で、最高位の内閣総理大臣賞を受賞しています。CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)とDXを組み合わせることで、社会課題の解決と企業価値の向上を同時に実現している好例です。
サービス業DXのポイント
サービス業におけるDX推進では、データを活用した新たな価値創造が重要です。既存のビジネスで蓄積されたデータを分析し、新しいサービスや事業を創出することで、競争優位性を確保できます。また、三菱ケミカルグループ株式会社のように、化学プラントのDXを推進し製造現場の変革を目指す取り組みも見られます。経営の基本方針の一つに「ICT、IoT、人工知能(AI)などの技術を活用しイノベーションを加速させること」を掲げており、社員の自発性を重視しながらDX推進に取り組むことで、全社員に「DXマインド」を浸透させる仕組みを整えました。具体的には、各拠点から自主参加可能なDX推進のための会議や、デジタルツールに関する情報共有プラットフォームによって、成功例と失敗例の共有をしたり、有志による交流会を開催したりして、社員一人ひとりのモチベーションを向上させています。このように、組織文化の変革を伴うDX推進が、サービス業においても重要なポイントとなっています。
まとめ: DX推進を成功に導くために

本記事では、DX推進の基本的な意味から、必要性、具体的な推進ステップ、成功のためのポイントまで、包括的に解説してきました。ここで、DX推進を成功に導くための重要なポイントを改めて整理しましょう。
まず、DX推進とは単なるデジタルツールの導入ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化を根本から変革し、競争上の優位性を確立することです。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題への対応が急務となる中、企業がグローバル市場で競争力を強化するためには、DX推進が不可欠となっています。労働人口の減少や急速なテクノロジーの進化といった外部環境の変化に適応するためにも、DXは避けて通れない経営課題なのです。
DX推進がもたらす価値
DX推進によって企業が得られるメリットは多岐にわたります。業務効率化と生産性向上により、限られたリソースで最大限の成果を生み出すことができます。人手不足の解消とコスト削減を実現しながら、新たなビジネス価値を創造し、市場での競争力を高めることが可能です。また、働き方改革を実現することで従業員満足度を向上させ、優秀な人材の確保と定着にもつながります。顧客体験(CX)の向上により、顧客満足度とロイヤルティを高め、持続的な成長基盤を構築できるのです。
段階的なアプローチの重要性
DX推進には、プロセスDX(業務プロセスの変革)、ワークスタイルDX(働き方の変革)、ビジネスDX(事業モデルの変革)という3つの領域があります。これらを段階的に進めることで、着実に成果を積み上げていくことが重要です。まずは業務のやり方を変えるプロセスDXから始め、次に働き方を変えるワークスタイルDXに取り組み、最終的には新しい事業を生み出すビジネスDXへと発展させていきます。
具体的な推進ステップとしては、現状分析と課題の明確化から始まり、DX推進の目的とビジョンの策定、全社的な意識共有と体制構築、DX人材の確保と育成、優先順位をつけた計画立案、そして実行とPDCAサイクルの運用という6つのステップを踏むことが効果的です。特に重要なのは、いきなり大規模な変革を目指すのではなく、スモールスタートから始めて段階的に範囲を拡大していくアプローチです。
KPI設定と効果測定の重要性
DX推進を成功させるためには、適切なKPIを設定して進捗を可視化することが不可欠です。KGI(最終目標)とKPI(中間指標)の違いを理解し、経済産業省のDX推進指標を活用しながら、自社に適した指標を設定しましょう。SMART原則に基づいたKPI設定により、具体的で測定可能、達成可能、関連性があり、期限付きの目標を掲げることができます。そして、定期的な評価と改善のサイクルを回すことで、DX推進の効果を最大化できます。
課題への対処と人材育成
DX推進を阻む課題としては、経営層と現場の意識ギャップ、DX人材不足、レガシーシステムからの脱却といった問題があります。これらの課題に対しては、ビジョンの共有と全社的な取り組み、外部活用と内部育成のバランス、計画的なシステム刷新といった対策が有効です。また、ツール導入の目的化や従業員の意識改革不足、短期的な視点での判断といった失敗パターンを理解し、事前に回避することが重要です。
DX人材に求められるスキルは、ビジネス変革スキル、データ活用スキル、テクノロジースキル、セキュリティスキル、パーソナルスキルという5つの領域にわたります。外部人材の採用と内部人材の育成を適切に組み合わせながら、自社に必要なDX人材を確保していくことが成功の鍵となります。
成功事例から学ぶ
ダイキン工業の空調機クラウド接続サービス、セブン&アイ・ホールディングスのグループ横断DX推進、ms&adインシュアランスグループの交通安全EBPM支援サービスなど、さまざまな業種における成功事例があります。これらの事例から学べるのは、自社の強みを活かしながらデジタル技術を活用し、顧客や社会に新たな価値を提供することの重要性です。
組織全体での取り組みが成功の鍵
グローバルでDXが加速し、外部環境がめまぐるしく変化していく中、企業が競争力を強化するためにDX推進は不可欠です。会社全体で取り組んでいく意識が必要であり、中長期的な取り組みになります。推進にあたっては、DX人材の不足が多くの企業にとって課題となっていますが、本記事で解説した採用・育成の方法を参考に、一歩ずつ取り組んでいくことが重要です。
DXの本質を理解し、全社で取り組む意識を持つこと、そしてツールの導入そのものが目的にならないよう注意することが成功のポイントです。また、導入後の成果を見直すために効果検証を随時行い、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことが大切です。2025年まで残り少ない中、「崖」から転落せずデジタル時代の競争を勝ち抜くためには、経営トップのリーダーシップのもと、計画的かつ戦略的なDX推進が不可欠なのです。
DX推進は、単なるデジタル化ではなく、企業のビジネスモデルや組織文化を変革する取り組みです。その成否は、適切なKPI設定と継続的な評価・改善のサイクルにかかっています。本記事で紹介した知識とノウハウを活用し、自社のDX推進を成功へと導いてください。変化を恐れず、新しい価値の創造に挑戦することで、持続的な成長を実現できるでしょう。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















