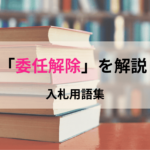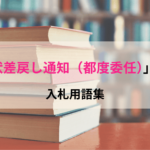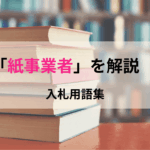三層分離で情報セキュリティを守る – 自治体DX時代の対策と運用ガイド

・三層分離の目的と仕組み
自治体の情報システムを「マイナンバー利用事務系」「LGWAN接続系」「インターネット接続系」の3つに分離し、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを低減する仕組み。個人情報の保護や行政データの安全な運用を目的とし、全国の自治体で導入が進められている。
・三層分離が抱える課題
導入後、業務の効率低下やクラウド活用の制限、テレワークの導入難などの運用上の課題が発生。DX推進が求められる中で、新しい働き方やシステムとの両立が重要になっている。
・DXとセキュリティの両立策
セキュリティを確保しながらDXを進めるため、ゼロトラストの導入やクラウド活用の最適化、人材育成の強化が必要。自治体の業務効率を向上させつつ、サイバー脅威に対抗する体制を整えていくことが課題となる。
自治体の情報セキュリティ対策として、「三層分離」が導入されています。これは、マイナンバー利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系の3つに分けることで、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを低減する仕組みです。しかし、業務効率の低下やクラウド活用の課題、DX推進との両立など、新たな問題も浮上しています。
本記事では、三層分離の基本から現状の課題、DXとセキュリティの両立策まで詳しく解説します。自治体のIT担当者やセキュリティ対策を考える方にとって、実践的な内容となっていますのでぜひご覧ください。
三層分離とは?背景と目的

三層分離の定義と概要
三層分離とは、自治体の情報システムを「マイナンバー利用事務系」「LGWAN接続系」「インターネット接続系」の3つに分離し、情報漏洩リスクを低減するセキュリティ対策の一つです。従来は「基幹系(内部業務)」と「情報系(外部との通信)」の2つに分類されていましたが、2015年の日本年金機構の情報漏洩事件を受け、より高度なセキュリティ体制が求められました。その結果、インターネット接続系を完全に分離することで、機密情報が外部に流出するリスクを抑えつつ、内部業務の効率を向上させることが可能になりました。
三層分離導入の背景
三層分離が導入された背景には、自治体のセキュリティ体制の脆弱性がありました。特に、2015年の年金機構のサイバー攻撃では、内部ネットワークとインターネットが同じ環境にあることで、攻撃者が簡単に機密情報へアクセスできたことが問題視されました。これを受け、総務省は「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」を発表し、全国の自治体に三層分離の導入を義務付けました。
三層分離の目的
三層分離の主な目的は、①機密情報の保護、②行政業務の効率化、③サイバー攻撃への耐性向上です。機密情報を扱う業務を完全に分離し、外部との通信を制限することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。また、職員が適切な環境で業務を行えるようになり、テレワークの普及など新しい働き方にも対応しやすくなります。
三層分離の構成と仕組み

マイナンバー利用事務系
マイナンバー利用事務系は、住民基本台帳、戸籍、税情報、国民健康保険、介護保険など、機密性の高い個人情報を扱う環境です。この系統では、外部ネットワークとの接続を完全に遮断し、データの持ち出しも厳しく制限されます。例えば、二要素認証(ID+生体認証)を導入し、アクセスできる職員を限定するなど、強固なセキュリティ対策が施されています。
LGWAN接続系
LGWAN(Local Government Wide Area Network)は、自治体同士の通信や電子申請に利用されるネットワークです。財務会計、人事給与、庶務事務などの内部業務が行われます。外部との通信を遮断しながらも、自治体間のスムーズな情報共有を可能にする仕組みです。セキュリティ面では、アクセスログ管理や無害化処理が徹底されており、機密情報のやり取りが安全に行われます。
インターネット接続系
インターネット接続系は、職員が外部とコミュニケーションを取るための環境であり、メール送受信や情報検索、自治体HPの管理が主な用途です。サイバー攻撃のリスクが高いため、ファイアウォールやウイルス対策ソフトが強化され、利用端末にはEDR(Endpoint Detection and Response)技術が導入されています。また、自治体ごとに「自治体情報セキュリティクラウド」を構築し、不審なアクセスを常時監視する体制が整えられています。
三層分離の課題と解決策

課題1: 業務効率の低下
三層分離の導入により、職員が業務のたびに異なる端末を使用する必要があり、作業効率の低下が指摘されています。特に、インターネットで取得した情報をLGWAN端末に転送する際の手続きが煩雑になり、業務負担が増加しています。これに対し、「無害化技術」を活用し、特定の情報のみ安全に転送できる仕組みが導入され始めています。
課題2: システム運用コストの増加
三層分離には高度なネットワーク管理が必要であり、自治体にとって運用コストの増加が大きな負担となります。特に小規模自治体では、専任のIT担当者を確保することが困難なため、外部のセキュリティベンダーと連携し、クラウドベースのセキュリティ管理システムを活用するケースが増えています。
課題3: テレワーク環境への対応
コロナ禍を契機にテレワークが普及しましたが、三層分離の環境ではリモートアクセスが制限されるため、在宅勤務の導入が難しいという課題があります。これに対し、「仮想デスクトップ(VDI)」を導入し、LGWAN接続端末に安全にアクセスできる環境を整備することで、業務の柔軟性を確保する動きが進んでいます。
公民連携によるセキュリティ強化

民間企業との協力体制
自治体と民間企業が連携することで、より高度なサイバーセキュリティ対策が可能になります。地方自治体が単独で高度なセキュリティインフラを整備するのは難しいため、民間企業の技術力を活用することで、迅速かつ効果的な対策が実現できます。特に、大手IT企業やセキュリティベンダーとのパートナーシップを結び、最新のセキュリティ技術を導入することが重要です。たとえば、クラウド環境での脆弱性スキャンや、AIを活用したリアルタイムのセキュリティ監視などが挙げられます。また、自治体と企業が共同でセキュリティポリシーを策定し、共通の基準を設けることで、一貫性のある安全対策が可能となります。さらに、インシデント発生時の対応プロトコルを明確にすることで、迅速な対処が可能になります。
最新技術を活用したセキュリティ強化
技術の進化とともに、サイバー攻撃の手法も高度化しており、自治体が最新技術を活用することは不可欠です。例えば、AI(人工知能)を活用したサイバー攻撃検知システムは、異常なネットワークトラフィックや不審なアクセスをリアルタイムで分析し、迅速に対応することができます。また、ブロックチェーン技術を活用することで、データの改ざんを防止し、自治体が扱う公的データの信頼性を向上させることが可能です。加えて、ゼロトラストアーキテクチャを導入することで、ネットワーク内外を問わず、すべてのアクセスを検証し、最小限のアクセス権限のみを付与することでセキュリティを強化できます。これにより、自治体の情報システムがより強固なものとなり、外部からの攻撃に対する耐性が向上します。
セキュリティ教育と意識向上
サイバーセキュリティは技術だけではなく、職員や住民の意識向上も重要な要素です。自治体の職員向けに定期的なセキュリティ研修を実施し、最新の脅威や対策について学ぶ機会を提供することが求められます。例えば、フィッシング詐欺の手口を学び、実際に疑わしいメールを受信した際に適切に対応できるようトレーニングすることが重要です。また、住民向けにもセキュリティ啓発活動を実施し、オンラインでの個人情報の適切な取り扱いや、安全なパスワード管理の方法を周知することが求められます。さらに、自治体の公式ウェブサイトや広報誌を活用し、サイバーセキュリティに関する最新情報を提供することで、地域全体のリスク意識を高めることができます。
住民の協力が必要なセキュリティ対策

住民ができるセキュリティ対策
自治体のセキュリティ対策には、住民一人ひとりの意識向上が欠かせません。例えば、フィッシング詐欺に注意し、怪しいメールやSMSを開かないことが基本的な防衛策となります。また、自治体が提供するオンラインサービスを利用する際には、多要素認証を活用し、パスワードだけでなく、ワンタイムパスコードなどを用いた強固な認証を実施することが推奨されます。さらに、パソコンやスマートフォンのソフトウェアを常に最新の状態に保つことで、既知の脆弱性を突いた攻撃から自身を守ることができます。住民一人ひとりが日常的に実践できるセキュリティ対策を意識することが、自治体全体の安全性向上につながります。
セキュリティ教育の推進
自治体は、住民向けのセキュリティ教育プログラムを提供し、情報リテラシーの向上を図ることが求められます。特に、高齢者やデジタル機器に不慣れな層に対しては、対面型の講習会を開催し、セキュリティの基礎知識をわかりやすく伝えることが有効です。また、学校教育においても、子どもたちがインターネットを安全に利用できるよう、情報モラル教育を充実させることが重要です。さらに、自治体のホームページやSNSを活用し、住民がいつでもアクセスできる形でセキュリティ対策情報を提供することで、日常的に意識を高める仕組みを構築することが求められます。
サイバー犯罪対策への協力
自治体は、住民と連携し、サイバー犯罪の被害を未然に防ぐための取り組みを強化する必要があります。例えば、自治体と警察が協力し、地域のサイバー犯罪に関する情報を迅速に共有し、被害拡大を防ぐ仕組みを整備することが重要です。また、住民が不審なメールやWebサイトを報告できる窓口を設置し、迅速な対応を可能にすることで、被害の発生を抑えることができます。さらに、地域ごとの防犯組織と連携し、サイバーセキュリティの啓発活動を行うことで、住民の意識向上を図ることが可能です。サイバー犯罪は誰もが被害者になる可能性があるため、地域全体で協力し合うことが不可欠です。
自治体DXとセキュリティの両立

DX推進に伴う新たなリスク
自治体におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、新たなセキュリティリスクが生じています。行政手続きのオンライン化、AIやIoTの活用、クラウドシステムの導入が進むことで、従来の三層分離だけでは対応が難しくなっています。例えば、クラウド環境に保存される住民データの管理、オンライン申請システムの不正アクセスリスク、IoTデバイスの脆弱性など、新しい脅威に対応する必要があります。
一方で、DXの推進を優先しすぎると、セキュリティ対策が後回しになる可能性があります。デジタル化とセキュリティは表裏一体であり、利便性の向上とリスク管理を両立することが求められています。自治体がDXを進める際には、**「セキュリティ・バイ・デザイン」**の考え方を取り入れ、システム設計の段階からセキュリティ対策を組み込むことが重要です。
クラウド活用と安全性の確保
DXの一環として、自治体業務のクラウド化が急速に進んでいます。クラウド環境を活用することで、データ共有の効率化、コスト削減、災害時のリスク分散が可能になります。しかし、クラウドに移行することで、従来の三層分離だけでは防ぎきれないリスクも生まれます。たとえば、クラウド環境への不正アクセス、データの暗号化不足、外部委託業者による情報漏洩などが挙げられます。
これらのリスクを軽減するためには、ゼロトラストの考え方を導入し、アクセス管理を強化することが重要です。具体的には、多要素認証(MFA)の導入、データの暗号化、クラウド環境のアクセスログ監視などが挙げられます。また、自治体のセキュリティガイドラインをクラウド環境向けに見直し、適切な管理体制を整えることが不可欠です。
DXとセキュリティを両立するためのアクションプラン
自治体がDXを推進しつつ、セキュリティを強化するためには、具体的なアクションプランの策定が必要です。以下のポイントを押さえることで、DXとセキュリティの両立が可能になります。
- セキュリティの標準化
DXの推進に合わせて、全国の自治体で共通のセキュリティ基準を設定し、ガイドラインを統一することが重要です。 - リスクアセスメントの強化
新しいシステムを導入する前に、リスク評価を徹底し、脆弱性を事前に特定・対策するプロセスを確立します。 - 人材育成と組織体制の強化
IT部門だけでなく、職員全体がセキュリティ意識を持ち、サイバー攻撃に対応できるスキルを習得することが求められます。
これらの施策を実施することで、自治体DXとセキュリティの両立が可能になり、より安全で効率的な行政サービスが実現されます。
今後の課題と展望

高度化するサイバー攻撃への対応
今後、自治体を狙ったサイバー攻撃の高度化が進むと予測されています。特に、ランサムウェア攻撃や標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)などは、自治体の重要なデータを人質にとり、身代金を要求するケースが増えています。これに対応するためには、エンドポイントのセキュリティ強化、ネットワーク監視の自動化、インシデントレスポンスの迅速化が求められます。
また、サイバー攻撃の発生後に適切な対応を行うためには、「サイバー防災訓練」を実施し、自治体の職員が攻撃発生時の対処手順を習得しておくことが重要です。サイバー攻撃は避けられないリスクの一つであり、事前の準備が被害の最小化につながります。
セキュリティ予算と投資の必要性
セキュリティ対策には一定の予算が必要ですが、多くの自治体では予算の確保が課題となっています。特に、小規模自治体ではIT専任者の確保が難しく、外部のセキュリティベンダーに依存せざるを得ないケースが増えています。このため、政府による補助金の活用、共同調達によるコスト削減、クラウドサービスの利用拡大などが今後の重要な施策となります。
また、セキュリティ予算の確保だけでなく、費用対効果を最大化するための戦略的な投資も求められます。具体的には、AIを活用した脅威検知システムの導入、職員向けセキュリティ研修の強化、外部監査の実施など、限られた予算を有効に活用するための工夫が必要です。
自治体間の連携強化と情報共有
サイバーセキュリティの課題は一つの自治体だけで解決できるものではなく、全国規模での連携が不可欠です。現在、多くの自治体が個別にセキュリティ対策を行っていますが、攻撃者はその隙を狙って脆弱な自治体を標的にしています。これを防ぐためには、以下のような取り組みが必要です。
- 自治体間での情報共有プラットフォームの構築
サイバー攻撃の事例や最新の脅威情報を迅速に共有できる仕組みを整え、自治体間の防御力を向上させる。 - 全国統一のセキュリティポリシーの策定
セキュリティの標準化を進め、全国どの自治体でも一定のセキュリティ基準を満たせるような指針を作成する。 - 官民連携の強化
IT企業やセキュリティ専門機関と連携し、最新の技術とノウハウを自治体に導入することで、より強固な防御体制を確立する。
まとめ

自治体の情報セキュリティを強化するために導入された三層分離は、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを軽減する重要な仕組みです。しかし、運用面では業務効率の低下やクラウド活用の制限、DXとの両立といった課題も浮上しています。これらの課題を解決するには、ゼロトラストの導入やアクセス管理の強化、自治体間での情報共有を進めることが不可欠です。
DXが進む中で、セキュリティと利便性を両立するための新たなアプローチが求められています。クラウドの適切な活用やリスクアセスメントの徹底、人材育成の強化など、持続可能なセキュリティ対策を実施することが重要です。自治体、企業、住民が協力し、最新の技術や対策を柔軟に取り入れることで、安全で効率的な行政サービスの実現につなげていくことが求められます。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。