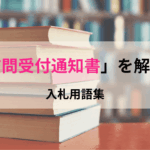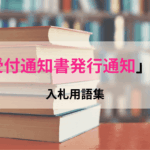プロポーザル方式のガイドラインとは?案件獲得のためのコツを解説
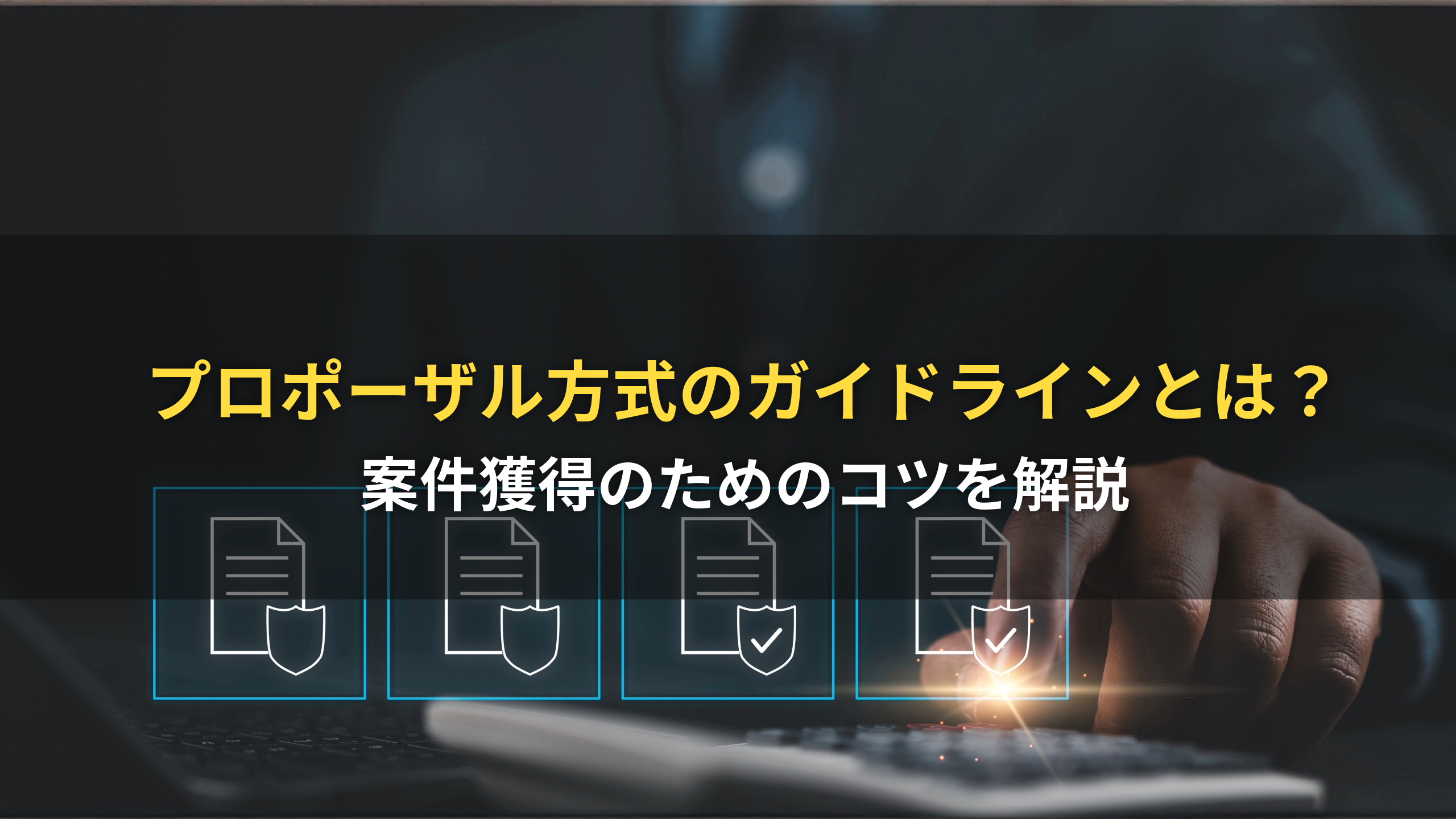
自治体や官公庁の案件を獲得したい企業にとって、プロポーザル方式のガイドラインを正しく理解することは欠かせません。ガイドラインを確認しない場合、「応募資格を満たしていなかった」「提案内容が基準を満たしていなかった」などの理由で受注を逃してしまう可能性があります。
しかし、「ガイドラインの重要性がよくわからない」「どの部分を重点的に確認すればいいのか知りたい」と感じている担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、プロポーザル方式の基本概念を解説し、ガイドラインの役割や確認すべきポイントを詳しく説明します。さらに、案件の受注率を高めるための実践的なコツも紹介します。

1. プロポーザル方式とは何か
- 一般競争入札とは異なり、「提案の質」を重視して受注者を評価する方式
- 高度な専門性や創造性が求められる
2. ガイドラインを確認する重要性
- 自治体ごとに応募資格や審査基準が異なるため、見落としと失格のリスクも
- 対象業務、評価基準、スケジュールなどを事前に把握することが成功の鍵
3. 受注率を高めるための実践的な工夫
- 提案の独自性や実現可能性を明確に示すことで他社と差別化
- 必要に応じて専門家の支援を活用し、短期間で高品質な提案書を作成することも有効
プロポーザル方式のガイドラインとは?
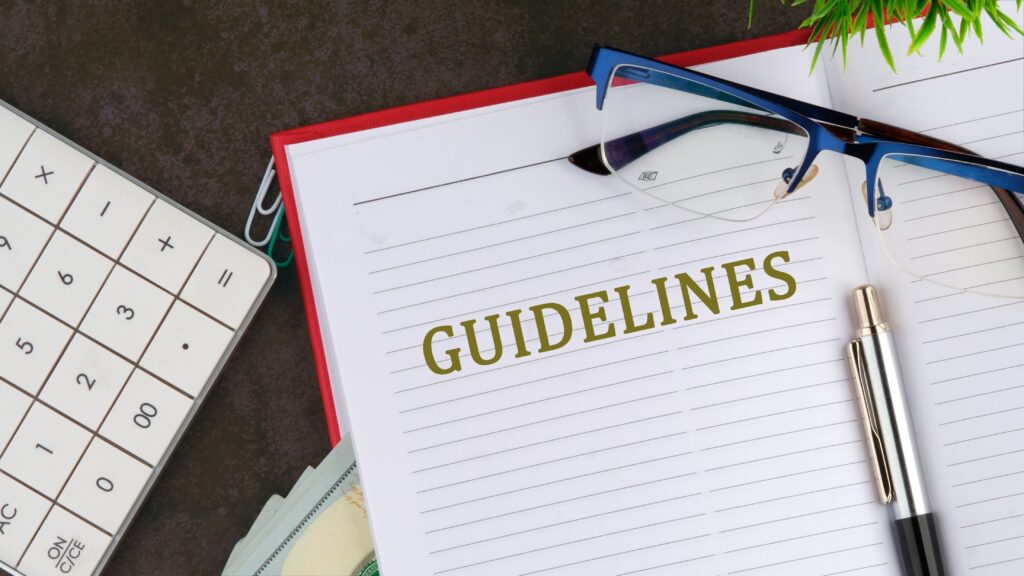
最初に、プロポーザル方式の基本的な仕組みを解説します。また、自治体・官公庁の案件獲得に欠かせないガイドラインの概要や役割についてもみていきましょう。
そもそもプロポーザル方式とは?
プロポーザル方式とは、価格だけでなく提案内容の質や実現可能性、事業者の実績などを総合的に評価し、最も適した受注者を選定する方式です。プロポーザル(proposal)とは「提案」という意味です。
一般競争入札が「価格」を基準とするのに対し、プロポーザル方式では提案の「質」が重視されます。具体的には、業務に対する実施方針、解決策、実施体制、技術力、類似の実績、実現可能性などが評価基準となります。
プロポーザル方式は、一般競争入札に適さない業務が対象となります。例えば、次のようなものが該当します。
<プロポーザル方式が採用される主な業務>
- 高度な知識や豊富な経験が必要とされる業務
(例)各種計画に関する調査分析など
- 専門的な技術力・企画力・開発力・実績・知識が要求される業務
(例)建築設計業務、システム開発・構築など
- 芸術性・創造性・象徴性が必要とされる業務
(例)催事、公演、イベント関連の業務、記念品のデザインなど
なお、プロポーザル方式には、主に公募型・指名型・環境配慮型の3種類があります。
<プロポーザル方式の種類>
- 公募型プロポーザル方式
広く参加者を募集し、多様な提案を受けられる一方、競争が激しくなる傾向がある方式
- 指名型プロポーザル方式
自治体・官公庁などの発注者が特定の事業者を選定し、信頼性を重視する一方、新規参入が難しい方式
- 環境配慮型プロポーザル方式
温室効果ガス削減など環境対策を含む技術提案を評価し、事業者を選定する方式
プロポーザル方式のガイドラインとはルールを定めた指針のこと
プロポーザル方式のガイドラインとは、自治体や官公庁が事業者の選定を行う際に、公平性・透明性を確保するために定めるルールや手続きのことです。
受注を目指す企業側は、ガイドラインを確認することで応募資格を満たし、適切な提案書を作成できます。特に、提案書への記載項目や選定基準、スケジュールなどを正しく把握することが、案件獲得のカギとなります。
ガイドラインを確認すべき理由

企業が自治体・官公庁の案件を獲得するためには、プロポーザル方式のガイドラインを事前に確認することが不可欠です。その理由は、以下の2つに集約されます。
ガイドラインの内容は自治体ごとに異なるため
プロポーザル方式のルールや審査基準は自治体や官公庁ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
自社が要件を満たしていない場合は、そもそもプロポーザル方式の案件に参加できません。
例えば、東京都墨田区のホームページ構築に関する業務委託では、応募資格の項目に「(1)対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。」とあります。
出典:墨田区公式ホームページ構築及び運用保守業務委託プロポーザル実施要領
プロポーザル方式では提案内容の質が重要ですが、その前段階として応募資格や対象業務を把握するためにもガイドラインの中身を正確に理解することが求められます。そうすることで、はじめて競争力のある提案が可能になるのです。
受注の確率を高めるため
ガイドラインに記載されている対象業務や評価基準、評価項目を正しく把握した上で、適切な提案書を作成すると受注確率を高められます。
ガイドラインには自治体や官公庁の意図や審査ポイントが詳細に記載されています。内容を理解して戦略的に提案を行うと、他社よりも有利に評価される可能性が高まるでしょう。
例えば、神奈川県横浜市の公募型プロポーザル方式「横浜未来の文化ビジョン策定支援等業務委託」では、提案内容の項目に「①文化芸術にかかるデータ収集について、次期計画策定につながる具体性のある調査項目の提案がされているか」と記載されています。これは、調査項目の妥当性はもちろん、実効性も評価されるということです。
出典:「横浜未来の文化ビジョン策定支援等業務委託」提案書評価基準
ガイドラインで確認すべき5つのポイント

プロポーザル方式の案件に応募して、実際に受注につなげるためには、ガイドラインの事前チェックが不可欠です。ここでは、特に重要な5つのポイントをみていきましょう。
対象業務
ガイドラインには、当該案件で募集している業務の種類が明記されています。自社のサービスや製品が対象となっているかを確認し、それに適した提案を作成する必要があります。
以下は、東京都墨田区がプロポーザル方式で実施した「墨田区公式ホームページ構築及び運用保守業務委託」の仕様書に記載されている業務内容です。
(1)CMS・システム・サーバ環境の導入・構築・設定(システム導入計画・スケジュールの作成、各ソフトウェア、ハードウェア、サービス等の動作確認テストを含む。)
(2)別紙「CMS 機能要件一覧」に記載されている機能の開発及び各種設定
(3)ホームページの運用設計及びテンプレートの作成
(4)コンテンツの企画立案及び作成
(5)アクセシビリティへの対応
(6)既存システムからのデータ移行
(7)操作・運用等に関するマニュアルの作成
(8)区職員を対象とした操作講習会の実施
(9)ホームページの運用保守
(10)ホームページの稼働維持に係る対応
引用:墨田区公式ホームページ構築及び運用保守業務委託 仕様書
このように、対象業務が詳細に記載されているため、自社がその業務に対して効果的かつ実効性の高い提案ができるかを検討する必要があります。
応募資格
ガイドラインには募集しているプロポーザル方式の案件に参加できる企業の要件が定められています。資格登録の有無、過去の実績などが応募条件となる場合があり、これを満たしていなければ応募できません。
例えば、前述の「横浜未来の文化ビジョン」では、参加資格として所在地や会社規模に制限は設けられていません。一方で、次のように過去の実績が必須となっています。
(2)国または地方自治体において、市町村文化芸術推進基本計画などの文化芸術施策を含む計画の策定またはそれに関連する調査に係る業務の受託実績を有すること。
引用:【公募型プロポーザル方式】 「横浜未来の文化ビジョン(仮称)策定にかかる調査等業務委託」
こうした応募資格も、価格が入札基準となる一般競争入札とは異なる点です。プロポーザル方式の案件では、引用したような過去の類似実績が応募資格に含まれるケースが多くあります。
選定方法
審査が書類審査のみなのか、プレゼンテーションが必要なのかを確認することが重要です。案件によっては、ヒアリングやデモンストレーションが求められる場合もあり、事前の準備が不可欠でしょう。
前述した東京都墨田区の案件では、選定方法として、第1次審査では「応募資格等について書類による審査を行う」としています。
審査に通過した事業者に対して、第2次審査では、企画提案書の書類審査とプレゼンテーションが実施されると記載されています。なお、プレゼンテーション審査では、自治体の担当者によるヒアリングも実施されます。
出典:墨田区公式ホームページ構築及び運用保守業務委託プロポーザル実施要領
選定基準
ガイドラインには、評価基準が詳細に記載されています。実績、事業の進め方、実施体制など、どの項目が重視されるのかを把握し、それに沿った提案を作成することが求められます。
例えば、上越市財務部契約検査課が作成した「プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」には、「評価基準の例示」として、審査項目、審査の視点、配点などが記載されています。
それによると、審査項目には、「類似業務実績」「事業の進め方」「実施体制」があります。類似業務実績に関しては、「類似業務の実績があるか」という視点から審査されます。全体で50点の配点があり、評価によって、0点、10点、30点、50点が加算されます。
上越市の場合、得点方式で事業者を選定する方式の他、各選考委員の評価順位を重視する方式、その2つを併用する方式のいずれかを採用しています。そのため、案件によってどのように受託事業者を特定するかも、事前に確認しておきましょう。
スケジュール
ガイドラインでは、質問書の締切、提案書の締切、審査期間、結果発表までの流れを確認することが重要です。資料提出やプレゼンテーションの準備にかかる時間を考慮し、計画的にスケジュールを立てましょう。
参考までに、長野県東御市の「東御市キャッシュレス決済機能付きセミセルフレジ導入等業務委託」のスケジュールを以下に紹介します。
| 内容 | 日時等 |
| 質問書の締切 | 令和5年4月21日(金) |
| 質問の回答 | 令和5年4月26日(水)市ホームページに掲載 |
| 参加意向申出書締切 | 令和5年5月1日(月) |
| 参加資格確認結果 | 令和5年5月12日(金) |
| 企画提案書等提出期間 | 令和5年5月15日(月)から令和5年5月19日(金)午後5時00分まで |
| ヒアリング審査 | 令和5年5月下旬~6月上旬 詳細は後日連絡 |
| 結果通知・公表 | 令和5年5月下旬~6月上旬 |
参加意向申出書締切から、企画提案書等の提出期限までが3週間程度しかないため、事業者は提案書を効率的に作成できるように、社内で対策を練る必要があるでしょう。
プロポーザル方式の案件を獲得するためのコツ

自治体や官公庁が実施するプロポーザル方式の案件を獲得するためには、以下のコツを押さえることが重要です。ガイドラインを確認することで対策できるコツの他、提案書の質を高めるための施策を講じることも重要になります。
自治体・官公庁のニーズを正確に把握する
プロポーザル方式では、発注者によって、求められる要件や審査基準が異なります。ガイドラインを詳細に分析し、自治体や官公庁が何を重要視しているのかを理解することが重要です。説明会への参加や質疑応答を活用することで、ニーズをより明確に把握し、適切な提案につなげることができます。
H3:独自性のある提案で差別化を図る
競争が激しいプロポーザル方式の案件では、他社と差別化された提案を行うことが不可欠です。自社の強みや実績を活かし、発注者にとってメリットのある独自のアプローチを提示しましょう。
特に、成功事例や過去の実績を具体的に示すことで、信頼性の高い提案が可能になります。また、他社にはない新しい技術やサービスを提案することで、より魅力的な内容にすることができるでしょう。
ただし、独自性を強調するあまり、自治体のニーズから逸脱しないよう注意が必要です。発注者が抱えている課題に対して、明確な解決策を提示することが原則となります。
プレゼンテーション力を高める
提案書の内容が優れていても、プレゼンテーションで十分に伝えられなければ受注の可能性は低くなります。審査員が短時間で提案内容を理解できるよう、わかりやすい構成とビジュアルを活用し、説得力のある説明を行いましょう。
また、想定される質問への回答を事前に準備しておくことで、スムーズな対応が可能になります。さらに、プレゼンテーションを行う担当者の話し方や態度も評価に影響を与える可能性があります。担当者は、簡潔で明確な説明を心がけ、審査員が納得しやすい伝え方を意識しましょう。
実現可能性と具体性を示す
自治体や官公庁は、実際に事業を遂行できる事業者を求めています。そのため、提案内容が実現可能であることを明確に示すのも重要です。スケジュールや必要なリソースを具体的に提示し、リスク対策を説明すると、信頼性の高い提案となります。
ここでも、過去の実績や成功事例を提示するのが有効です。特に、類似した案件で成果を上げた経験があれば、その事例を具体的に紹介することで、提案の信頼性が向上します。発注側も、実績のある事業者に対して安心感を持つため、過去の成功事例をうまく活用することが重要です。
専門家の支援を受ける
競争の激しいプロポーザル方式で勝ち抜くためには、データ分析を活用した提案書の作成や、専門家によるサポートを受けることも有効です。
特に、過去のプロポーザル方式における案件の傾向を分析し、最適な提案内容を導き出すことができる専門企業の支援を受けると、受注の可能性を大きく高められるでしょう。
また、提案書の作成期間は通常3週間程度のため、短期間で質の高い提案を仕上げるのが難しい企業も少なくありません。そうした場合でも、外部の協力会社の知見やノウハウを活用することで、効率的に競争力のある提案書を作成できます。
▼デボノのプロポーザル支援サービスについてはこちらをご覧ください

プロポーザル方式のガイドライン理解には専門家の支援も有効

企業の担当者にとって、ガイドラインは案件獲得のために必ず確認すべき重要な指針です。対象業務、応募資格、選定方法、選定基準、スケジュールなどを正しく理解することで、効果的な提案が可能になります。
さらに、専門家の支援を活用すると、より精度の高い提案書を作成し、受注率を向上させることができます。
案件獲得に悩んでいる企業や、提案書の作成に十分な時間を確保できない担当者は、一度専門家や専門業者に相談してみるのも有効な選択肢です。