AISASとAIDMAの違いとは?デジタル時代のマーケティング戦略への活用ガイド
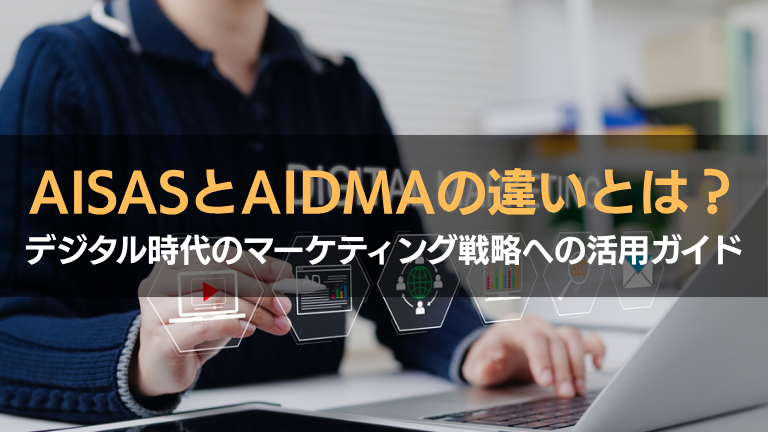
AIDMAとAISASは時代背景に応じた購買モデル
AIDMAは1924年に誕生したマスメディア時代のモデルで「注意→興味→欲求→記憶→行動」、AISASは2004年に電通が提唱したインターネット時代のモデルで「注意→興味→検索→行動→共有」となっており、検索と共有の行動が新たに加わっている。
両者は主導者や適用領域が異なる
AIDMAは企業主導での広範な認知に強みがあり、高額商材やBtoB向け、検討期間の長い商品に適する。一方AISASは消費者主導で検索や共有が軸となり、中低価格帯の商品やECビジネスに適している。
現代ではハイブリッド活用が有効
マーケティング施策では、商材やターゲット特性に応じてAIDMAとAISASを柔軟に使い分けるか、両者を組み合わせることでより高い効果が期待できる。
マーケティング戦略を立てる上で欠かせない「購買行動モデル」。その代表的なものとして知られる「AIDMA(アイドマ)」と「AISAS(アイサス)」は、消費者が商品を認知してから購入に至るまでのプロセスを体系化したフレームワークです。AIDMAは約100年前に誕生した伝統的なモデルであるのに対し、AISASはインターネット時代に適応した比較的新しいモデルです。両者の違いを理解することで、現代の消費者心理をより深く把握し、効果的なマーケティング施策を展開することができます。本記事では、AIDMAとAISASの基本概念から違い、活用方法まで詳しく解説し、自社のマーケティング戦略に活かすためのヒントをご紹介します。

AISASとAIDMAの概要

購買行動モデルとは何か
購買行動モデルとは、消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの心理的・行動的プロセスを段階的に整理したフレームワークです。このモデルを理解することで、各段階に適したマーケティング施策を展開し、効果的に顧客を獲得・維持することができます。
マーケティング戦略において、消費者の購買行動を理解することは非常に重要です。なぜなら、顧客がどのような心理状態にあるのかを把握し、その段階に合わせたアプローチをすることで、コンバージョン率(購入や契約などの成約率)を高めることができるからです。
AIDMAモデルとは
AIDMA(アイドマ)は、1924年にアメリカの広告実務書の著者サミュエル・ローランド・ホールによって提唱された購買行動モデルです。AIDMAという名称は、消費者の心理プロセスを表す以下の5つの英単語の頭文字を取ったものです:
- Attention(注意・注目):商品やサービスの存在に気づく
- Interest(興味・関心):商品やサービスに興味を持つ
- Desire(欲求):商品やサービスが欲しいと思う
- Memory(記憶):商品やサービスのことを記憶に留める
- Action(行動):商品やサービスを購入する
AIDMAは、マスメディアが主流だった時代に生まれたモデルであり、企業から消費者への一方向のコミュニケーションを前提としています。テレビCMや新聞広告などのマス広告が中心だった時代において、消費者の購買行動を理解するための重要なフレームワークとして長く活用されてきました。
AISASモデルとは
AISAS(アイサス)は、2004年に日本の広告代理店・電通によって提唱された購買行動モデルです。インターネットが普及し、消費者が自ら情報を収集したり、体験を共有したりする時代に対応したモデルとして開発されました。AISASという名称は、以下の5つの英単語の頭文字を取ったものです:
- Attention(注意・注目):商品やサービスの存在に気づく
- Interest(興味・関心):商品やサービスに興味を持つ
- Search(検索):商品やサービスについて検索・調査する
- Action(行動):商品やサービスを購入する
- Share(共有):商品やサービスの使用体験を共有する
AISASは、インターネットの普及により消費者が主体的に商品情報を収集し、SNSなどで体験を共有する現代の購買行動を反映したモデルです。企業からの一方的な情報発信だけでなく、消費者同士の情報交換が購買行動に大きな影響を与える点に着目しています。
両モデルの基本的な違い
AIDMAとAISASの最も基本的な違いは、デジタル化時代の消費者行動の変化を反映している点です。具体的には以下の3つの大きな違いがあります:
- 情報収集の主体:AIDMAでは企業から発信される情報を消費者が受け取るのに対し、AISASでは消費者が自ら積極的に情報を検索します。
- 購入前後のプロセス:AIDMAではDesire(欲求)とMemory(記憶)のステップがありますが、AISASではSearch(検索)とShare(共有)に置き換わっています。
- コミュニケーションの方向性:AIDMAは企業から消費者への一方向のコミュニケーションを前提としていますが、AISASは消費者同士の双方向のコミュニケーションも重視しています。
これらの違いは、インターネットやスマートフォンの普及によって、消費者が受動的な情報受信者から能動的な情報収集者・発信者へと変化したことを反映しています。次のセクションでは、それぞれのモデルについてより詳しく解説していきます。
AIDMAモデルの詳細解説
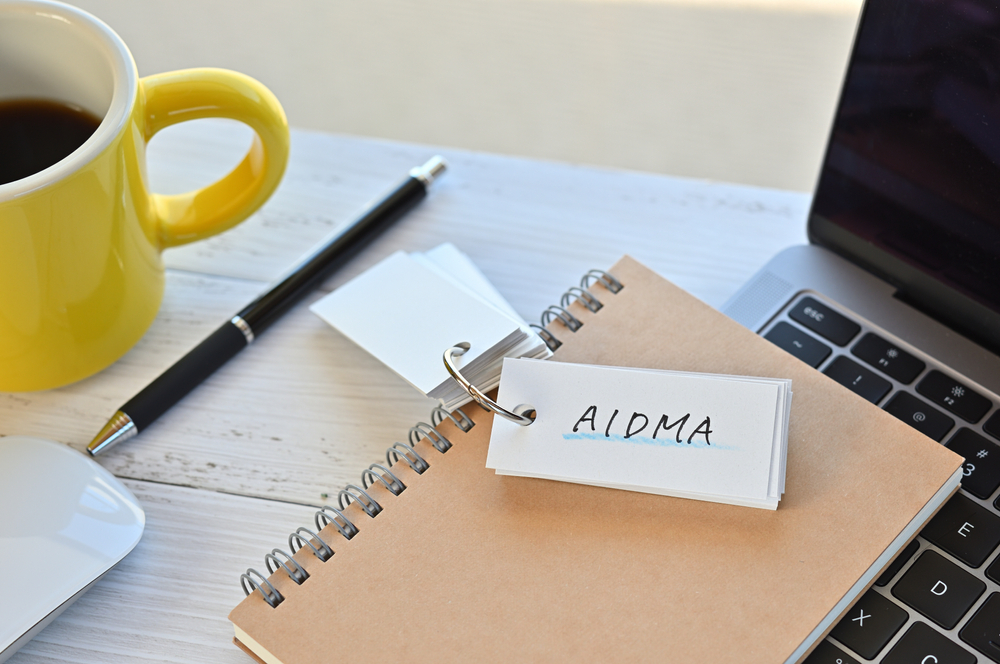
AIDMAモデルは約100年前に誕生しましたが、現代のマーケティングにおいても重要な洞察を提供してくれます。ここでは、AIDMAの各ステップについて詳しく解説し、それぞれの段階で効果的なマーケティング施策について考えていきましょう。
A:Attention(注意・注目)
Attentionは「注意」や「注目」を意味し、消費者が商品やサービスの存在に初めて気づく段階です。この段階は、購買行動の入り口であり、AIDMAモデルの第一段階である「認知段階」に位置づけられます。
消費者の関心を引くために、企業はさまざまな広告媒体を活用します。従来は新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマスメディアが中心でしたが、現代ではWeb広告、SNS広告、YouTubeなどの動画広告、インフルエンサーマーケティングなど、多様な手段が使われています。
Attentionの段階で重要なのは、ターゲットとなる消費者の目に触れる場所に広告を掲出し、印象的なビジュアルやキャッチコピーで注目を集めることです。例えば、人通りの多い場所に設置された大型ビジョンや、テレビの視聴率が高い時間帯に放映されるCM、SNSでの目を引く広告などが効果的です。
I:Interest(興味・関心)
Interestは「興味」や「関心」を意味し、消費者が商品やサービスに対して興味を持つ段階です。この段階はAIDMAモデルの第二段階である「感情段階」の始まりとなります。
Attentionの段階で消費者の目を引きつけた後、次に必要なのは、その商品やサービスがなぜ魅力的なのか、どのような価値を提供するのかを伝えることです。興味を持ってもらうためには、商品の特徴や利点を分かりやすく伝え、消費者の好奇心や関心を刺激することが重要です。
Interestの段階では、商品やサービスに関連した情報を提供するブログ記事、eBook、セミナー、ウェビナーなどのコンテンツマーケティングが効果的です。また、製品の特徴や機能を詳しく説明した紹介動画や、顧客の課題を解決するための情報を提供することで、消費者の関心を高めることができます。
D:Desire(欲求)
Desireは「欲求」や「欲望」を意味し、消費者が商品やサービスを欲しいと思う段階です。この段階もAIDMAモデルの「感情段階」に含まれます。
Interestの段階で興味を持った消費者の購買意欲をさらに高めるためには、その商品やサービスが自分にとって「必要不可欠」であると感じてもらう必要があります。そのためには、商品の魅力をより具体的に伝え、消費者の感情に訴えかけることが重要です。
Desireの段階で効果的な施策としては、製品の無料トライアルやデモの提供、顧客の成功事例(ケーススタディ)の紹介、商品を使用した時の具体的なメリットやベネフィットの説明などがあります。また、「期間限定」「数量限定」といった希少性を強調したり、購入特典を設けたりすることで、購買意欲を刺激することもできます。
M:Memory(記憶)
Memoryは「記憶」を意味し、消費者が商品やサービスのことを覚えておく段階です。この段階はAIDMAモデルの「感情段階」の最終段階になります。
購入に至る過程で、消費者は様々な情報に接し、検討を重ねていきます。特にBtoB取引や高額商品の場合、最終決定までに時間がかかることが多く、その間に商品の存在を忘れられてしまう可能性があります。そのため、消費者の記憶に残るような施策が必要です。
Memoryの段階で効果的なのは、印象的なブランドスローガンやロゴ、キャッチコピーの活用、定期的なリマインドメールの送信、リターゲティング広告の配信などです。また、店舗の場合は、目立つ場所に商品を陳列したり、ポスターを貼ったりすることで、消費者に「思い出してもらう」きっかけを作ることができます。
A:Action(行動)
Actionは「行動」を意味し、消費者が実際に商品やサービスを購入する段階です。この段階はAIDMAモデルの第三段階である「行動段階」に位置づけられます。
消費者が購入に踏み切るには、購入プロセス自体がスムーズで簡単であることが重要です。オンラインショップの場合、使いやすいウェブサイトや複数の決済方法の用意、分かりやすい購入ボタンの設置などが必要です。実店舗の場合は、商品の配置や店内レイアウト、スタッフの接客などが購買行動に影響します。
Actionの段階では、「今すぐ購入」「お問い合わせはこちら」などの明確なコールトゥアクション(行動喚起)を設けることが効果的です。また、購入手続きの簡素化、クーポンや割引の提供、送料無料などの特典も、購入の後押しになります。
3つの段階:認知・感情・行動
AIDMAモデルの5つのステップは、大きく以下の3つの段階に分類することができます:
- 認知段階:Attention(注意・注目)
消費者が商品やサービスの存在を知る段階です。企業からの情報発信が主体となります。 - 感情段階:Interest(興味・関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)
消費者が商品やサービスに対して感情的な反応を示す段階です。興味を持ち、欲しいと思い、記憶に留めます。 - 行動段階:Action(行動)
消費者が実際に購入という行動を起こす段階です。購入を決断し、実行に移します。
このように、AIDMAモデルは消費者の購買行動を認知から感情、そして行動へと段階的に整理しています。各段階に適したマーケティング施策を実施することで、消費者を効果的に購入へと導くことができます。特に、BtoB取引や高額商品など、購入の意思決定に時間がかかる商材では、AIDMAモデルの「Memory(記憶)」の段階が重要になります。
次のセクションでは、インターネット時代に適応したAISASモデルについて詳しく解説していきます。
AISASモデルの詳細解説

AISASモデルは、2004年に電通によって提唱された比較的新しい購買行動モデルです。インターネットが普及し、消費者の行動様式が大きく変化した時代に対応するために開発されました。ここでは、AISASの各ステップについて詳しく解説し、それぞれの段階での効果的なマーケティング施策について考えていきましょう。
A:Attention(注意・注目)
AISASモデルにおけるAttentionは、AIDMAと同様に「注意」や「注目」を意味し、消費者が商品やサービスの存在に初めて気づく段階です。ただし、AISASでは情報接触のチャネルがより多様化しています。
従来のテレビCMや新聞広告などのマスメディアに加えて、ウェブ広告、SNS広告、インフルエンサーマーケティング、動画広告など、デジタルチャネルを通じた認知獲得が重要になっています。特に若年層ではテレビよりもインターネットの利用時間が長いため、デジタル広告の重要性はさらに高まっています。
AISASのAttention段階では、ターゲットユーザーが利用しているデジタルプラットフォームを特定し、そこで効果的に広告を展開することが重要です。例えば、若年層をターゲットにする場合はInstagramやTikTokなどのSNSでの広告が効果的かもしれません。また、検索エンジンで上位表示されるためのSEO対策やリスティング広告も、商品やサービスを認知してもらうための重要な施策です。
I:Interest(興味・関心)
AISASモデルにおけるInterestも、AIDMAと同様に「興味」や「関心」を意味します。ただし、インターネット時代では、興味を持った消費者がすぐに検索行動に移れるという点が大きな違いです。
Attention段階で消費者の目を引いた後、その商品やサービスに対する興味や関心を喚起するコンテンツが重要になります。例えば、魅力的な商品ページ、分かりやすい説明動画、問題解決型のブログ記事などが考えられます。
AISASのInterest段階では、消費者がさらに詳しい情報を得るための「きっかけ」を提供することが重要です。例えば「詳しくはこちら」というリンクや「〇〇について検索」といった行動を促すコールトゥアクションを設けることで、次のSearch段階へスムーズに移行させることができます。
S:Search(検索)- AIDMAとの大きな違い
Searchは「検索」を意味し、AISASモデルの特徴的なステップの一つです。これはAIDMAにはない概念で、インターネットの普及により可能になった消費者の主体的な情報収集行動を表しています。
消費者は興味を持った商品やサービスについて、検索エンジンやSNS、口コミサイトなどを通じて自ら情報を集め、比較検討します。「〇〇 評判」「〇〇 使い方」「〇〇 vs △△」といった検索語句を用いて、商品の詳細や実際の使用感、競合製品との比較などを調べることが一般的になっています。
このSearch段階で重要なのは、消費者が検索したときに適切な情報が見つかるようにすることです。そのためのマーケティング施策としては、以下のようなものが挙げられます:
- SEO対策:検索エンジンで上位表示されるようにWebサイトを最適化する
- コンテンツマーケティング:商品に関する有益な情報を提供するブログ記事や動画を制作する
- 口コミ管理:レビューサイトやSNS上の評判をモニタリングし、必要に応じて対応する
- 比較コンテンツの作成:競合製品との違いを明確に説明するコンテンツを提供する
特に重要なのは、検索結果の上位に自社のコンテンツが表示されるようにすることです。一般的に、多くのユーザーは検索結果の1ページ目しか見ないため、上位表示されることがSearch段階での成功の鍵となります。
A:Action(行動)
AISASモデルにおけるActionも、AIDMAと同様に「行動」を意味し、消費者が実際に商品やサービスを購入する段階です。ただし、AISASでは特にオンラインでの購入行動が重視されています。
インターネット時代では、検索から購入までの動線をシームレスにすることが重要です。例えば、検索結果から商品ページへ、商品ページからカートへ、カートから決済へと、ユーザーがストレスなく進めるようなWebサイト設計が求められます。
AISASのAction段階で効果的なマーケティング施策としては、以下のようなものが挙げられます:
- 使いやすいECサイト設計:分かりやすい商品説明、シンプルな購入フロー、見やすい画像など
- 多様な決済方法:クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、複数の選択肢を用意
- 送料や配送について分かりやすく表示:配送料や納期など、購入の際に気になる情報を明示
- カート放棄対策:カートに商品を入れたまま購入に至らないユーザーへのリマインドメールなど
また、消費者が購入をためらう要因を取り除くことも重要です。例えば、返品・交換の保証、セキュリティへの配慮、明確な価格表示などが考えられます。これらの施策により、検索から購入までの障壁を減らし、コンバージョン率の向上を図ることができます。
S:Share(共有)- AIDMAとの大きな違い
Shareは「共有」や「拡散」を意味し、AISASモデルの最も特徴的なステップの一つです。これもAIDMAにはない概念で、消費者が購入・使用した商品やサービスについて、SNSや口コミサイトなどで自らの体験や感想を発信し、他者と共有する行動を表しています。
消費者は商品を購入・使用した後、その体験を「〇〇を買ってみた」「△△を使ってみた感想」などの形でSNSに投稿したり、レビューサイトに評価を書き込んだりします。こうした口コミは、他の潜在顧客にとって重要な情報源となり、新たなAttention(注目)を生み出すきっかけになります。
このShare段階で重要なのは、消費者の自発的な情報発信を促進することです。そのためのマーケティング施策としては、以下のようなものが挙げられます:
- SNS投稿キャンペーン:商品の写真をハッシュタグ付きで投稿すると特典がもらえるなど
- レビュー促進プログラム:商品のレビューを書いてくれたユーザーにポイントを付与するなど
- ユーザー体験の向上:そもそも共有したくなるような魅力的な商品・サービスを提供する
- アフターフォロー:購入後のサポートや追加情報の提供で顧客満足度を高める
Share段階で消費者による良い口コミが広がれば、それがあらたなユーザーのAttention段階につながり、AISASのサイクルが循環します。このように、AISASモデルは一方向の購買プロセスではなく、ユーザー間で情報が循環する仕組みを表現しています。
以上のように、AISASモデルはインターネット時代の消費者行動を反映した購買行動モデルとして、Search(検索)とShare(共有)という2つの重要な概念を導入しています。特にこの2つのステップは、消費者が受動的な情報受信者から能動的な情報収集者・発信者へと変化したことを示しており、現代のデジタルマーケティングにおいて欠かせない視点となっています。
次のセクションでは、AIDMAとAISASの時代背景や特徴について、より詳しく比較していきます。
AIDMAとAISASの時代背景と特徴の比較

AIDMAとAISASは同じく消費者の購買行動を表すモデルでありながら、それぞれ異なる時代背景や特徴を持っています。この章では両モデルの背景や特徴を比較し、それぞれのモデルが最も効果を発揮する状況について考察します。
時代背景の違い
AIDMAとAISASの最も大きな違いの一つは、それぞれが生まれた時代背景です。
AIDMAの時代背景(1924年)
- マスメディア(新聞、雑誌、ラジオなど)が主要な情報源だった時代
- 企業から消費者への一方向のコミュニケーションが主流
- 消費者自身が商品情報を調べるための手段が限られていた
- 店頭販売が中心で、通信販売は現在ほど一般的ではなかった
- 物質的にそれほど豊かではなく、商品の選択肢も限られていた
AISASの時代背景(2004年)
- インターネットの普及により、情報収集手段が多様化
- 検索エンジンの発達により、消費者が能動的に情報収集できるようになった
- SNSなどのソーシャルメディアを通じて、消費者が情報発信者にもなった
- ECサイトの発展により、オンラインショッピングが一般化
- 商品の選択肢が豊富になり、消費者の選別眼が厳しくなった
この時代背景の違いは、消費者の購買行動に大きな影響を与えています。AIDMAの時代は企業からの情報をもとに消費者が判断する「受動的消費」が中心でしたが、AISASの時代は消費者自身が情報を集め、比較検討する「能動的消費」が主流になっています。
主導者の違い(企業主導 vs 消費者主導)
AIDMAとAISASのもう一つの大きな違いは、購買プロセスを主導するのが誰かという点です。
AIDMA(企業主導型)
- 企業が広告やキャンペーンを通じて消費者の注意を引き、購買行動を誘導する
- 商品情報の流れは企業から消費者への一方向
- 企業が提供する情報が消費者の判断材料の大部分を占める
- 消費者は企業から与えられた情報をもとに購入を決定する
AISAS(消費者主導型)
- 企業の広告は認知のきっかけにすぎず、その後は消費者が主体的に行動する
- 消費者は興味を持った商品について自ら検索して情報を収集する
- 他の消費者の評価や口コミが判断材料として重視される
- 購入後はSNSなどで体験を共有し、また別の消費者の判断に影響を与える
このように、AIDMAでは企業が消費者を導く図式だったのに対し、AISASでは消費者自身が主体的に行動し、時には消費者同士でコミュニケーションを取ることで購買行動が進んでいきます。これはインターネットの普及により、消費者が情報の受け手から主体的な参加者へと変化したことを反映しています。
重視するポイントの違い
AIDMAとAISASでは、マーケティング戦略において重視するポイントも異なります。
AIDMAが重視するポイント
- 広範な認知獲得:マスメディアなどを通じて、できるだけ多くの人に商品を知ってもらうことを重視
- 感情への訴えかけ:欲しいと思わせ、記憶に残るよう感情に訴えるマーケティングを重視
- 購買機会の確保:店頭での目立つ陳列や、購入しやすい環境づくりを重視
AISASが重視するポイント
- 検索での発見率向上:SEO対策やコンテンツマーケティングなど、検索されたときに見つかる施策を重視
- 情報の質と透明性:消費者が自ら調べたときに、納得できる詳細な情報提供を重視
- シェアされやすさ:購入後に口コミされやすい体験や仕掛けを重視
AIDMAでは不特定多数に向けた広告展開によって認知を広げ、AISASではターゲットを絞った広告と詳細な情報提供で検索時の発見率を高めるという違いがあります。また、AIDMAでは記憶に残ることが重要視されるのに対し、AISASでは共有されることが重視されるという違いもあります。
適している商材や業界の違い
AIDMAとAISASは、どちらが優れているというものではなく、商材や業界によって適している方が異なります。
AIDMAが適している商材・業界
- 高額商材:自動車、住宅など、購入までの検討期間が長く複数回の意思決定が必要な商品
- BtoB商材:企業間取引で、複数の関係者が関与し承認プロセスが必要な商品・サービス
- 専門性の高い商材:金融商品や医療サービスなど、専門的な説明が必要な商品・サービス
- 伝統的な業界:歴史や伝統を重視する業界や、高齢者をターゲットとする業界
AISASが適している商材・業界
- 低〜中価格帯の商材:日用品、アパレル、飲食など、比較的気軽に購入できる商品
- BtoC商材:一般消費者向けの商品・サービスで、個人の判断で購入できるもの
- トレンド性の高い商材:流行に敏感な若年層をターゲットとした商品・サービス
- デジタル関連業界:IT製品、アプリ、ゲームなど、デジタルネイティブ世代に訴求する業界
例えば、住宅や自動車のような高額商品では、認知から購入までの期間が長く、比較検討や記憶に残すプロセスが重要になるため、AIDMAモデルが適しています。一方、アパレルや飲食などの比較的低価格な商品では、消費者が検索して情報収集し、購入後に体験を共有するというAISASモデルが効果的です。
ただし、実際のマーケティング戦略では、AIDMAとAISASを厳密に分けるのではなく、商材や顧客層に応じて両方のモデルの要素を組み合わせることも多いです。例えば、高額商材でもオンラインでの検索行動は重要ですし、低価格商品でも記憶に残る広告は効果的です。
次のセクションでは、AIDMAとAISASの共通点とそれぞれのメリットについて考えていきます。
AIDMAとAISASの共通点とメリット
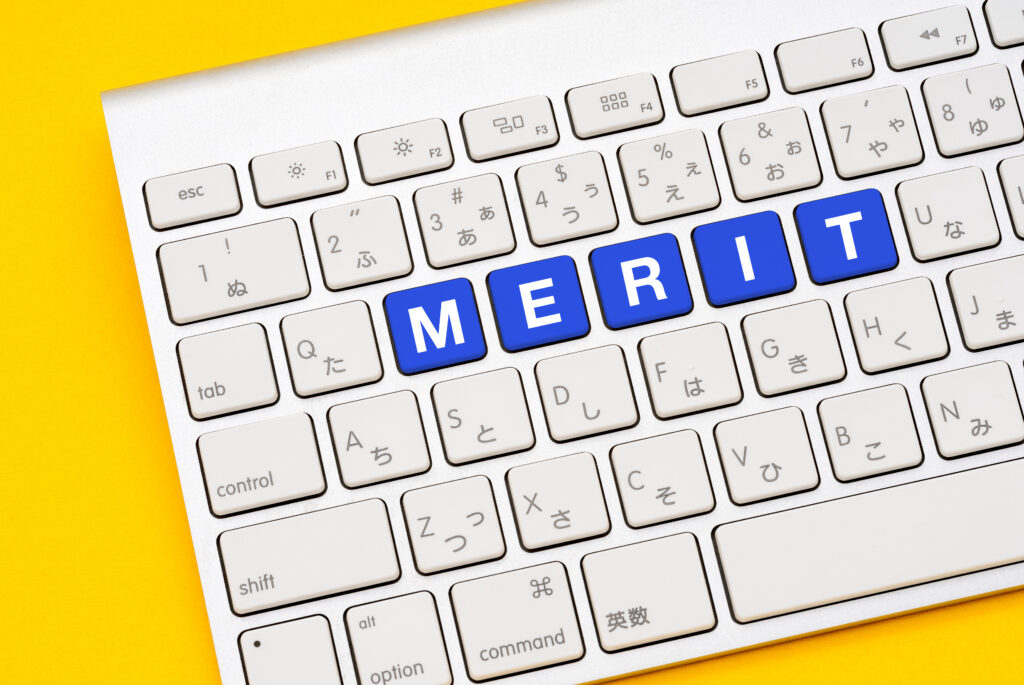
AIDMAとAISASはそれぞれ異なる時代背景で生まれ、異なる特徴を持つモデルですが、「消費者の購買行動を理解し、効果的なマーケティング戦略を立案するためのフレームワーク」という基本的な目的は共通しています。この章では、両モデルの共通点とそれぞれが持つメリットについて考察します。
共通するメリット
AIDMAとAISASには以下のような共通するメリットがあります:
消費者心理の可視化
両モデルともに、消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの心理的・行動的プロセスを視覚化しています。これにより、漠然としていた消費者の購買行動が分かりやすく整理され、マーケターはより客観的に戦略を考えることができます。
例えば、セールスが伸び悩んでいる場合、「そもそも認知されていないのか」「興味は持たれているが欲しいと思われていないのか」「欲しいと思われているが購入行動に至っていないのか」など、問題点を段階ごとに切り分けて考えることができます。
体系的なアプローチの提供
AIDMAもAISASも、消費者の購買行動をステップごとに分けて考えることで、体系的なマーケティングアプローチを可能にします。各ステップに対応した具体的な施策を考えることができるため、「何をすべきか」が明確になります。
例えば、認知段階なら広告や PR、興味・関心段階ならコンテンツマーケティング、購入段階なら決済システムの改善など、それぞれの段階に合わせた施策を体系的に考えることができます。
顧客中心の視点
両モデルとも、企業側の視点ではなく消費者側の視点で購買プロセスを考えるフレームワークです。これにより、「どうやって売るか」ではなく「消費者はどのように購入を決めるのか」という顧客中心のマーケティングが可能になります。
消費者の立場に立って考えることで、消費者のニーズや不満点、障壁などをより深く理解し、それらに対応したマーケティング施策を打ち出すことができます。
マーケティング戦略立案のフレームワーク
AIDMAとAISASは、マーケティング戦略を立案する際の思考フレームワークとして非常に有用です。以下の点において、マーケティング戦略の立案に役立ちます:
ゴール設定とKPI策定
購買行動のどの段階でどれだけの成果を上げたいのかという目標設定に役立ちます。例えば「認知度を30%上げる」「Webサイトへの流入を20%増やす」「購入率を15%向上させる」など、段階ごとに具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することができます。
予算と資源の最適配分
限られた予算や人的資源をどの段階に集中投下すべきかの判断材料になります。例えば、認知度が十分だが購入率が低い場合は、広告費を減らしてWebサイトの使いやすさ改善に予算を振り向けるなど、効率的な資源配分が可能になります。
統合的なマーケティングコミュニケーション
様々なマーケティング施策を購買プロセスの流れに沿って統合することができます。各施策が購買プロセスのどの段階に効果があるのかを明確にし、施策同士の連携を強化することで、一貫したマーケティングコミュニケーションが実現します。
フェーズ別アプローチの実現
AIDMAとAISASの大きなメリットの一つは、消費者の状態(フェーズ)に合わせた最適なアプローチが可能になる点です。
段階別に最適化されたメッセージング
消費者の購買段階に合わせて、発信するメッセージの内容や訴求ポイントを変えることができます。例えば:
- 認知段階では「新しい〇〇が登場!」という新規性を訴求
- 興味段階では「〇〇の特徴はこんなにすごい!」という機能訴求
- 欲求段階では「〇〇を使うとこんなメリットが!」という便益訴求
- 行動段階では「今なら送料無料!」という購入促進訴求
このように、消費者の心理状態に合わせて最適なメッセージを届けることで、コミュニケーションの効果を最大化できます。
適切なチャネル選択
購買段階によって、最適な接触チャネルも変わってきます。AIDMAとAISASのモデルを活用することで、段階に応じた適切なチャネル選択が可能になります。
- 認知段階では広告やPR、SNSなど広く露出できるチャネル
- 興味・検索段階ではWebサイト、ブログ、コンテンツマーケティングなど詳細情報を提供できるチャネル
- 購入段階ではECサイト、店舗など取引を完結できるチャネル
このように、消費者の段階に合わせてチャネルを使い分けることで、効率的なマーケティング活動が実現します。
顧客の心理状態に合わせたコミュニケーション
消費者の心理状態を理解することで、押し売りのような不適切なアプローチを避け、顧客の状況に合わせたコミュニケーションが可能になります。例えば:
- まだ商品を知らない顧客に対して、いきなり「今すぐ購入してください」と言っても効果がない
- すでに購入を検討している顧客に対して、基本的な商品説明だけを繰り返すのは時間の無駄
このように、顧客がどの段階にいるかを理解することで、適切なタイミングで適切なコミュニケーションを取ることができます。
課題の特定と改善
AIDMAとAISASのもう一つの大きなメリットは、マーケティング上の課題を特定し、改善するための視点を提供することです。
ボトルネックの特定
購買プロセスのどの段階で顧客が離脱しているのかを特定することができます。例えば:
- 認知はされているが、興味・関心を持ってもらえていない
- 興味は持たれているが、購入行動につながっていない
- 一度は購入されるが、リピーターになっていない
このように、どの段階でつまずいているのかを明確にすることで、効果的な改善策を打ち出すことができます。
データ分析の枠組み
AIDMAやAISASモデルは、マーケティングデータを分析する際の枠組みとしても役立ちます。各段階ごとに適切なKPIを設定し、データを収集・分析することで、マーケティング施策の効果を客観的に評価することができます。
- 認知段階:広告接触率、認知度調査の結果など
- 興味・検索段階:Webサイト訪問数、滞在時間、検索ボリュームなど
- 購入段階:コンバージョン率、購入率、客単価など
- 共有段階:SNSでの言及数、口コミ件数、レビュー評価など
これらのデータを段階別に分析することで、施策の効果測定や改善ポイントの特定がより明確になります。
継続的な改善サイクル
AIDMAやAISASモデルを活用することで、マーケティング活動のPDCAサイクル(計画-実行-評価-改善)をより体系的に回すことができます。各段階の課題を特定し、改善策を実施し、効果を測定して次の施策に活かすという継続的な改善が可能になります。
例えば、認知度を高めるためにSNS広告を実施し、その結果Webサイトへの流入は増えたものの、購入率が上がらなかった場合、次はWebサイトのコンテンツや購入動線の改善に注力するといった具合に、段階的に課題を解決していくことができます。
このように、AIDMAとAISASはそれぞれ異なる特徴を持ちながらも、マーケティング戦略の立案・実行・改善において共通するメリットを提供しています。どちらが「正しい」というわけではなく、商材や業界、ターゲット顧客に応じて適切なモデルを選択したり、両モデルの要素を組み合わせたりすることが重要です。
次のセクションでは、AISASをさらに発展させた新しい購買行動モデルについて解説します。
インターネット時代の発展型モデル

AISASモデルがインターネット時代の消費者行動を反映したモデルとして登場して以降、デジタル環境の進化やSNSの普及に伴い、さらに新しい購買行動モデルが提唱されています。ここでは、AISASの発展型モデルや、その他の最新の購買行動モデルについて紹介し、それらのデジタルマーケティングにおける活用方法を考察します。
AISCEAS:AISASをさらに発展させたモデル
AISCEAS(アイシーズ)は、AISASモデルをさらに細分化した購買行動モデルです。AISASの「Search(検索)」と「Action(行動)」の間に、「Comparison(比較)」と「Examination(検討)」というステップを追加したモデルです。
AISCEASの各ステップ
- Attention(注意・注目):商品やサービスの存在に気づく
- Interest(興味・関心):商品やサービスに興味を持つ
- Search(検索):商品やサービスについて情報を検索する
- Comparison(比較):複数の商品やサービスを比較する
- Examination(検討):購入するかどうかを深く検討する
- Action(行動):商品やサービスを購入する
- Share(共有):購入体験を他者と共有する
AISCEASモデルは、特に高額商材やBtoB取引など、慎重な購入判断が必要な場面において有効です。消費者はまず複数の選択肢を「比較(Comparison)」し、その後自分のニーズや予算に照らして「検討(Examination)」するというプロセスを経ることが多いためです。
活用方法
AISCEASモデルを活用したマーケティング施策としては、以下のようなものが考えられます:
- 比較段階(Comparison)での施策:
- 自社商品と競合商品を比較した資料の提供
- 比較サイトでの露出強化
- 優位性を明確に示す比較表や図解の作成
- 検討段階(Examination)での施策:
- 詳細な商品仕様や利用ガイドの提供
- 無料トライアルやサンプルの提供
- オンライン相談会やWebセミナーの開催
- 顧客の質問に答えるFAQの充実
比較・検討のプロセスを丁寧にサポートすることで、顧客は安心して購入の意思決定をすることができます。
その他の購買行動モデル(SIPS, DECAX等)
AISASやAISCEAS以外にも、デジタル時代に対応した様々な購買行動モデルが提唱されています。ここでは代表的なモデルをいくつか紹介します。
SIPS(シップス)
SIPSは、電通が2011年に提唱した購買行動モデルで、ソーシャルメディアの時代における消費者行動を表しています。従来のように企業から消費者への一方的な情報提供ではなく、消費者同士の共感や参加を重視したモデルです。
SIPSの各ステップ
- Sympathize(共感する):共感できる価値観や世界観に触れる
- Identify(確認する):実際の商品やサービスの詳細を確認する
- Participate(参加する):商品に関連するコミュニティや活動に参加する
- Share & Spread(共有・拡散する):体験を共有し、拡散する
SIPSモデルの特徴は、「共感」から始まり、「参加」というステップがあることです。これは、単に商品を購入するだけでなく、ブランドの世界観や価値観に共感し、その一部として参加するという消費者の行動を表しています。
DECAX(デキャックス)
DECAXは、電通が2014年に提唱したコンテンツマーケティング時代の購買行動モデルです。「体験」を中心に据え、消費者とブランドの継続的な関係構築を重視しています。
DECAXの各ステップ
- Discovery(発見):コンテンツとの出会い
- Engage(関係構築):コンテンツへの関与
- Check(確認):商品・サービスの詳細確認
- Action(行動):購入などの具体的な行動
- Experience(体験と共有):使用体験の共有
DECAXモデルの特徴は、コンテンツとの「出会い」から始まり、「関係構築」を経て購入に至るプロセスを表している点です。また、購入後の「体験」も重視されています。
その他のモデル
上記以外にも、様々な購買行動モデルが提唱されています:
- AMTUL(アムツール):Aware(認知)、Memory(記憶)、Trial(試用)、Usage(使用)、Loyalty(ブランド構築)
- AIDCA(アイドカ):Attention(注意)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Conviction(確信)、Action(行動)
- AIDCAS(アイドカス):AIDCAにSatisfaction(満足)を加えたモデル
- ARCAS(アルカス):Attention(気づき)、Remind(思い起こし)、Compare(比較)、Action(行動)、Satisfy(満足)
- SAIDCAS(サイドキャス):Search(検索)、Aware(認知)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Conviction(確信)、Action(行動)、Satisfy(満足)
- VASAS(ヴィサス):Viral(口コミ)、Influence(影響)、Sympathy(共感)、Action(行動)、Share(共有)
- ULSSAS(ウルサス):UGC(ユーザー生成コンテンツ)、Like(いいね!)、Search1(SNSでの検索)、Search2(検索エンジンでの検索)、Action(購買)、Spread(拡散)
これらのモデルは、それぞれの時代背景や特定の業界・商材に適応するために開発されたものです。どのモデルが「正しい」というわけではなく、自社の商材やターゲット顧客に合わせて適切なモデルを選択することが重要です。
デジタルマーケティングにおける活用方法
これらの発展型購買行動モデルは、現代のデジタルマーケティングにおいてどのように活用できるでしょうか。
オムニチャネル戦略への応用
消費者はオンラインとオフラインを行き来しながら購買行動を進めることが多くなっています。例えば、店舗で商品を見て(Attention)、スマホで口コミを調べ(Search)、自宅のPCで詳細を確認し(Examination)、再び店舗で購入する(Action)といったように。
発展型購買行動モデルを活用することで、オンラインとオフラインを統合したオムニチャネル戦略を構築することができます。各タッチポイントでどのような体験を提供すべきかを、購買行動のステップに合わせて設計することが可能です。
コンテンツマーケティングの設計
購買行動の各ステップに合わせたコンテンツを作成することで、効果的なコンテンツマーケティングが実現します。
- 認知・興味段階:短い動画や画像など、注目を集めるコンテンツ
- 検索・比較段階:詳細な製品情報、比較表、レビュー記事など
- 検討・購入段階:FAQ、使い方ガイド、購入者の声など
- 共有段階:ユーザー体験を発信しやすい仕組み、ハッシュタグキャンペーンなど
このように、各段階に適したコンテンツを用意することで、消費者の購買行動を効果的にサポートできます。
デジタル広告の最適化
購買行動モデルを活用することで、デジタル広告の配信タイミングや内容を最適化することができます。
- ディスプレイ広告:認知段階での露出を目的とした広告
- 検索連動型広告:検索段階でのアプローチを目的とした広告
- リターゲティング広告:比較・検討段階でのアプローチを目的とした広告
- SNS広告:共有を促進するための広告
それぞれの広告タイプで訴求内容や目的を明確に設定することで、広告効果を高めることができます。
顧客体験(CX)の設計
発展型購買行動モデルは、顧客体験(Customer Experience)設計のフレームワークとしても活用できます。各接点での顧客体験をモデルのステップに沿って設計することで、一貫性のある体験を提供することができます。
例えば、AISCEASモデルを使って、認知から共有までの各ステップでどのような体験を提供するかを具体的に設計できます。特に「比較」や「検討」のステップでどのような体験を提供するかを考えることで、競合との差別化を図ることができます。
データ活用とパーソナライズ
現代のデジタルマーケティングでは、購買行動のどの段階にいるかをデータから判断し、それに応じたパーソナライズされたコミュニケーションが可能になっています。
- Webサイトの閲覧履歴から興味の段階にいると判断して関連コンテンツを表示
- 商品ページの閲覧回数から検討段階にいると判断して詳細情報や比較表を提供
- カート放棄データから購入を迷っていると判断して割引クーポンを送信
このように、発展型購買行動モデルとデータ活用を組み合わせることで、顧客一人ひとりの状態に合わせたアプローチが可能になります。
次のセクションでは、これらの購買行動モデルを実際のマーケティング戦略に活用するための具体的な方法と成功事例について解説します。
実践:購買行動モデルを活用したマーケティング戦略

ここまで、AIDMAとAISASをはじめとする様々な購買行動モデルについて解説してきました。本セクションでは、これらのモデルを実際のマーケティング戦略に落とし込むための実践的な方法について紹介します。
ターゲットユーザーのペルソナ設定
購買行動モデルを効果的に活用するためには、まずターゲットユーザーを明確にする必要があります。ペルソナとは、ターゲットとなる顧客像を具体的な人物像として設定したものです。
ペルソナ設定の重要性
ペルソナを設定することで、以下のようなメリットがあります:
- 抽象的な「顧客」ではなく、具体的な「誰か」をイメージできるようになる
- ターゲットの価値観や行動パターンを共有し、チーム内での認識統一ができる
- マーケティング施策の方向性や優先順位の判断基準になる
効果的なペルソナの作り方
購買行動モデルと連携させるペルソナには、以下の要素を含めると効果的です:
- 基本属性:年齢、性別、職業、家族構成、収入など
- 価値観・ライフスタイル:重視する価値観、日常的な行動パターンなど
- 情報収集行動:よく使うメディアやSNS、情報源など
- 課題・ニーズ:抱えている問題点や満たしたいニーズ
- 購買意思決定要因:購入を決める際に重視するポイント
- 購買行動の特徴:購入前にどのくらい調査するか、オンライン/オフラインどちらで購入するかなど
具体的なペルソナ例
例えば、以下のようなペルソナを設定します:
ペルソナA:30代前半 女性 会社員
佐藤 美香さん(32歳)は大手企業の企画部で働く会社員。独身で都内のワンルームマンションに一人暮らし。年収は500万円程度。仕事が忙しく自分の時間を大切にしている。
情報収集は主にInstagramやTwitterで行い、友人の投稿や流行に敏感。新しいものには興味があるが、購入前にはオンラインでの口コミや評判を必ず調べる慎重派。価格よりも品質や時間短縮などの価値を重視する。
最近の悩みは、忙しさによる自分磨きの時間不足。効率的に美容や健康を維持できる商品・サービスに関心がある。決済はほとんどクレジットカードかスマホ決済を利用。購入後の体験を頻繁にSNSでシェアする。
このようなペルソナを設定することで、AISASなどの購買行動モデルの各ステップでどのようなアプローチが効果的かを具体的に考えることができます。
各ステップに合わせた効果的なアプローチ
ペルソナを設定したら、購買行動モデルの各ステップに合わせた効果的なアプローチを考えていきます。ここではAISASモデルを例に、具体的な施策を紹介します。
Attention(注意)段階のアプローチ
先ほど設定したペルソナ(佐藤美香さん)の場合、以下のようなアプローチが効果的と考えられます:
- Instagram広告:美容や健康に関連するビジュアル重視の広告で認知を獲得
- インフルエンサーマーケティング:佐藤さんが興味を持ちそうなインフルエンサーを起用し、商品を紹介
- 通勤電車内の広告:通勤時に目にする可能性が高い交通広告で認知拡大
この段階では、「時短」「効率」「自分磨き」などの佐藤さんの価値観に訴えかけるメッセージが効果的です。
Interest(興味)段階のアプローチ
佐藤さんが商品に興味を持った場合、以下のようなアプローチが効果的です:
- ブランドストーリーの発信:商品開発の背景や理念など、共感を呼ぶコンテンツ
- SNS公式アカウント:魅力的な商品写真や使用シーンを投稿
- 動画コンテンツ:商品の特徴や使い方を分かりやすく紹介する短い動画
この段階では、「なぜこの商品が佐藤さんの課題解決に役立つのか」という点を明確に伝えることが重要です。
Search(検索)段階のアプローチ
佐藤さんが商品について調べ始めたら、以下のようなアプローチが効果的です:
- SEO対策:「〇〇 効果」「〇〇 口コミ」などの検索キーワードで上位表示を狙う
- 詳細な商品情報:成分、効果、使用方法などを詳しく解説したWebページ
- ユーザーレビュー:実際の使用者の声を集めたレビューページ
- よくある質問:佐藤さんが疑問に思いそうな点をFAQとしてまとめる
この段階では、佐藤さんの疑問や不安を解消する情報を提供することが重要です。
Action(行動)段階のアプローチ
佐藤さんが購入を検討し始めたら、以下のようなアプローチが効果的です:
- 初回割引:購入のハードルを下げる特別価格や初回限定キャンペーン
- 少量サイズ:試しやすい少量タイプや、お試しセットの提供
- 多様な決済方法:クレジットカード、スマホ決済など複数の選択肢
- 簡単な購入プロセス:最小限の入力で完了する購入フォーム
この段階では、「購入する」という行動を起こしやすくするための障壁除去が重要です。
Share(共有)段階のアプローチ
佐藤さんが商品を購入した後は、以下のようなアプローチが効果的です:
- SNS投稿キャンペーン:商品写真を投稿すると特典がもらえるキャンペーン
- ハッシュタグの設定:投稿しやすい専用ハッシュタグの提案
- フォトジェニックな商品パッケージ:SNSに投稿したくなるようなデザイン
- リピート購入特典:次回購入時に使えるクーポンなど
この段階では、佐藤さんの満足度を高め、自発的に情報発信してもらうための仕掛けが重要です。
自社のマーケティングへの応用方法
最後に、購買行動モデルを自社のマーケティングに応用するための具体的なステップを紹介します。
1. 自社商材に適した購買行動モデルの選択
まずは、自社の商材やターゲット顧客に最も適した購買行動モデルを選択します。以下のポイントを考慮しましょう:
- 商品の価格帯(高額商材ならAIDMAやAISCEASなど)
- 購入までの検討期間(短期間ならAISAS、長期間ならAIDMAなど)
- ターゲット顧客の年齢層(若年層ならSIPSやULSSASなど)
- オンライン比率(ECサイト中心ならAISASなど)
必要に応じて、複数のモデルを組み合わせたハイブリッドなアプローチも検討しましょう。
2. 現状の購買行動プロセスの可視化
選択したモデルをもとに、現在の顧客がどのような購買行動をしているかを可視化します:
- 各段階での顧客行動を具体的に書き出す
- 現在のタッチポイントを洗い出す
- 各段階のコンバージョン率やドロップ率を調査する
- ボトルネックや課題点を特定する
可能であれば、実際の顧客インタビューやアンケート調査を行い、リアルな声を収集しましょう。
3. 段階別の施策立案と優先順位づけ
可視化した購買行動プロセスをもとに、各段階での施策を立案します:
- 各段階でのKPIを設定する
- 段階ごとに具体的な施策を複数立案する
- ボトルネックとなっている段階の施策を優先する
- 予算や人的リソースを考慮して優先順位をつける
特に成果への影響が大きい「低hanging fruit(手の届きやすい成果)」から着手することで、早期に効果を実感できます。
4. PDCAサイクルの実施
立案した施策を実行し、継続的に改善していきます:
- 各施策の効果測定の方法を事前に決めておく
- 定期的にデータを分析し、効果を検証する
- 効果の高い施策は拡大し、効果の低い施策は改善または中止する
- 顧客の声やフィードバックを積極的に収集し、施策に反映する
購買行動モデルは固定的なものではなく、顧客の行動変化や市場環境の変化に応じて柔軟に見直すことが重要です。
5. 組織間の連携強化
購買行動モデルを効果的に活用するためには、組織間の連携が欠かせません:
- マーケティング、営業、カスタマーサポートなど部門間での情報共有
- 顧客データの一元管理と活用
- 共通のKPIや目標設定
- 定期的な部門横断ミーティングの実施
特に、オンラインとオフラインの連携が重要な企業では、チャネル間の壁を取り払い、顧客中心のアプローチを実現することが成功の鍵となります。
これらのステップを通じて、購買行動モデルを自社のマーケティング戦略に効果的に取り入れることができます。モデルはあくまでフレームワークであり、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。
次のセクションでは、AIDMAとAISASの使い分けと効果的な活用法についてまとめます。
まとめ:AIDMAとAISASの使い分けと効果的な活用法

本記事では、代表的な購買行動モデルであるAIDMAとAISASについて、その概念から違い、活用方法まで詳しく解説してきました。最後に、両モデルの使い分けと効果的な活用法についてまとめ、マーケティング戦略に活かすためのポイントを整理します。
ビジネスモデルに合わせた使い分け
AIDMAとAISASはどちらが優れているというものではなく、ビジネスモデルや商材の特性に応じて使い分けることが重要です。
AIDMAが適しているケース
- 高額商材:自動車、住宅、高級時計など、購入までに慎重な検討を要する商品
- B2B取引:企業間取引で、複数の決裁者や長い検討期間が必要なケース
- シニア層向け商品:インターネットよりも従来型メディアに接触する機会が多い顧客層
- ブランド構築段階:新規ブランドの認知拡大と記憶に残る施策が必要なケース
- 独自性が高く比較対象が少ない商品:検索や比較よりも記憶に残すことが重要なケース
AIDMAモデルでは特に「Memory(記憶)」の段階が重要であり、長期的な検討プロセスの中で顧客の記憶に残り続けるための施策が鍵となります。
AISASが適しているケース
- 中低価格帯商品:書籍、アパレル、コスメなど、比較的気軽に購入できる商品
- B2C取引:個人の判断で購入でき、検索や口コミの影響を受けやすいケース
- 若年層・デジタルネイティブ層向け商品:インターネットでの情報収集や共有が自然な顧客層
- ECサイト中心のビジネス:オンラインでの検索から購入までの導線が重要なケース
- 比較検討されやすい商品:類似商品が多く、検索や比較が購買判断の鍵となるケース
AISASモデルでは特に「Search(検索)」と「Share(共有)」の段階が重要であり、検索結果での可視性向上と、購入後の共有を促進する施策が鍵となります。
ハイブリッドアプローチ
実際のビジネスでは、AIDMAとAISASの要素を組み合わせたハイブリッドなアプローチが効果的なケースも多くあります。例えば:
- AIDMA+S:従来のAIDMAに「Share(共有)」の要素を加えたアプローチ
- AI+SCE+AS:AISASの「Search」と「Action」の間に「Comparison(比較)」と「Examination(検討)」を加えたAISCEASアプローチ
- オムニチャネル型:オンラインとオフラインの両方のタッチポイントを考慮したアプローチ
自社のビジネスモデルや顧客の特性を分析し、最適なモデルを柔軟に構築することが重要です。
デジタルとリアルの融合におけるポイント
現代の消費者はオンラインとオフラインを行き来しながら購買行動を進めるため、デジタルとリアルの融合が重要なポイントとなります。
オムニチャネル戦略の構築
オンラインとオフラインの双方を統合したオムニチャネル戦略を構築することで、シームレスな顧客体験を提供することができます。
- オンラインからオフラインへの導線:Webサイトでの店舗検索、オンライン予約でのオフライン来店など
- オフラインからオンラインへの導線:店頭でのQRコード提示、デジタルクーポンなど
- 顧客データの統合:オンライン/オフラインの顧客行動データを統合し、パーソナライズされた体験を提供
例えば、化粧品ブランドであれば、オンラインで製品に興味を持った顧客を店舗での無料カウンセリングに誘導し、そこでパーソナライズされた提案を行い、購入後はオンラインでレビュー投稿を促すといった流れが考えられます。
デジタルとリアルの長所を組み合わせる
デジタルとリアルにはそれぞれ長所があるため、それらを効果的に組み合わせることが重要です。
- デジタルの長所:情報量の多さ、検索の容易さ、パーソナライズ、スケーラビリティなど
- リアルの長所:五感での体験、人的接客、即時性、信頼感の醸成など
例えば、家電製品であれば、デジタルで詳細なスペック情報や比較表を提供し、リアル店舗では実際に触れて操作感を確かめられるようにするといった組み合わせが効果的です。
顧客のデジタル成熟度に合わせたアプローチ
顧客のデジタル活用度合いには個人差があるため、顧客のデジタル成熟度に合わせたアプローチも重要です。
- デジタルネイティブ層:SNSやアプリなどデジタル中心のコミュニケーション
- デジタル適応層:デジタルとリアルを使い分けるバランス型のコミュニケーション
- デジタル不慣れ層:リアル中心でデジタルはシンプルに設計したコミュニケーション
顧客のデジタル成熟度によって、AIDMAとAISASの比重を調整することも一つの方法です。
消費者心理を理解したマーケティング施策の重要性
AIDMAやAISASなどの購買行動モデルの本質は、消費者心理を理解し、それに合わせたマーケティング施策を展開することにあります。
購買意思決定プロセスへの寄り添い
消費者が商品やサービスをどのように選び、購入するかという意思決定プロセスに寄り添うことが重要です。
- 問題認識:消費者が問題や欲求を認識するきっかけを提供する
- 情報探索:消費者が必要とする情報を適切なタイミングで提供する
- 代替案評価:比較検討しやすい情報や差別化ポイントを明確に示す
- 購買決定:購入にあたっての不安や障壁を取り除く
- 購買後評価:使用満足度を高め、ポジティブな共有を促進する
各段階での消費者の心理状態を理解し、「押し付け」ではなく「支援」する姿勢でアプローチすることが大切です。
感情的要素と理性的要素のバランス
消費者の購買意思決定には、感情的要素と理性的要素の両方が関わっています。効果的なマーケティングはこの両方にアプローチします。
- 感情的アプローチ:ブランドストーリー、感動的な映像、共感を呼ぶメッセージなど
- 理性的アプローチ:製品の機能や性能、価格優位性、使いやすさなど
AIDMAモデルでは「Desire(欲求)」や「Memory(記憶)」など感情的側面が強く、AISASモデルでは「Search(検索)」など理性的側面が強いとも言えますが、実際にはどちらのモデルでも両方の要素が重要です。
顧客との長期的な関係構築
購買行動モデルは単発の購入だけでなく、顧客との長期的な関係構築にも活用できます。
- カスタマージャーニー全体の設計:初回購入だけでなく、リピート購入や他製品への展開も考慮
- ブランドロイヤルティの醸成:単なる「満足」を超えた「感動」や「共感」を提供
- アドボケート(推奨者)の育成:自発的に商品を推奨してくれるファンを育てる
特にAISASモデルの「Share(共有)」の段階は、新たな「Attention(注意)」を生み出すサイクルとなるため、長期的な関係構築において重要な意味を持ちます。
最後に
AIDMAとAISASをはじめとする購買行動モデルは、マーケティング戦略を考える上での「地図」のようなものです。地図があれば目的地への効率的な道筋が見えますが、実際の道のりは地形や天候によって変わることもあります。同様に、購買行動モデルも基本的な道筋を示すものであり、実際のビジネスでは市場環境や顧客特性に応じて柔軟に調整する必要があります。
重要なのは、「どのモデルが正しいか」ではなく、「自社のビジネスや顧客にとって最適なアプローチは何か」を常に考え、検証し続けることです。消費者の購買行動は時代とともに変化し続けており、マーケティング戦略もそれに合わせて進化させていく必要があります。
AIDMAとAISASの理解を深め、それぞれの特性を活かしながら、自社のマーケティング戦略に最適なアプローチを見つけ出してください。消費者心理に寄り添い、デジタルとリアルを効果的に融合させることで、より効果的なマーケティング活動が実現できるでしょう。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















