カスタマージャーニーマップの作り方とは?5ステップで実践できる手順をわかりやすく解説

カスタマージャーニーマップは顧客視点のプロセス可視化ツール
顧客が商品やサービスに接する際の行動や感情の流れを視覚的に把握するための手法であり、顧客理解を深めるために有効。
目的に応じたマップの種類と正確な設計が成功の鍵
マクロ型・ミクロ型・シナリオ型の3種類から目的に合ったものを選び、明確なゴール・ペルソナ・プロセス設計・データ活用によって効果的に構築する。
マーケティング全体の一貫性強化に貢献
顧客視点で作成し、仮説に頼りすぎず、過度に複雑化しないことが重要。SNSやメールなど複数チャネルにまたがるマーケティング施策の最適化に活用できる。
「顧客の購買行動を可視化したい」「効果的なマーケティング施策を打ちたい」「チーム全体で顧客理解を深めたい」と考えていませんか?そんな課題を解決するのがカスタマージャーニーマップです。本記事では、カスタマージャーニーマップの基本概念から具体的な作成手順、活用方法まで、実践的なノウハウを徹底解説します。3種類のマップから目的に合わせて選べるテンプレート付きで、初心者でも今日から使えるガイドをお届けします。顧客視点で考えるマーケティングを実現し、ビジネス成果を最大化しましょう。
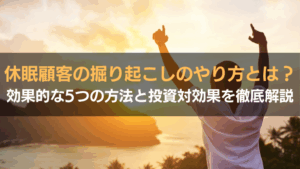
カスタマージャーニーマップとは?基本概念と重要性

カスタマージャーニーマップの定義と本質
カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入・利用し、その後もファンとなって継続利用するまでの「旅(ジャーニー)」を視覚的に表現したものです。顧客の行動、感情、思考、接点(タッチポイント)などを時間軸に沿って整理し、一枚の地図(マップ)として可視化します。
カスタマージャーニーマップの本質は、「顧客体験の全体像を把握する」ことにあります。商品やサービスそのものの価値だけでなく、顧客との接点すべてを通じた体験価値を高めることが、現代のマーケティングでは重要になっています。顧客がどのような行動を取り、何を考え、どのような感情を抱いているのかを理解することで、適切なタイミングで最適なコミュニケーションを取ることができるようになります。
ユーザーの態度変容プロセスを可視化する意義
顧客は商品・サービスを購入するまでに、「知らない」から「知っている」「興味がある」「欲しい」「買いたい」といった心理状態(態度)の変化を経験します。この態度変容プロセスを可視化することには、以下のような意義があります:
- 顧客の購買意思決定プロセスを理解できる
- 各段階での顧客ニーズや課題を特定できる
- 顧客の態度変容を促す適切な施策を検討できる
- 顧客体験上の改善ポイントを発見できる
- 組織全体で顧客視点の共通理解を形成できる
例えば、アパレル商品を購入するユーザーは、SNSで商品を発見した「認知」段階では「かわいい!」「欲しい!」といった漠然とした感情を抱きますが、購入段階に近づくにつれて「自分の体型に合うだろうか」「サイズ感は大丈夫だろうか」といった具体的な不安や疑問を感じるようになります。このように段階によって異なる顧客心理を理解することで、各段階に適したコミュニケーションを設計できるのです。
なぜ今、カスタマージャーニーマップが注目されているのか
カスタマージャーニーマップが近年特に注目されている理由には、以下のような背景があります:
1. 顧客接点の多様化・複雑化:デジタルチャネルの急増により、顧客との接点が複雑化しています。スマートフォン、SNS、EC、実店舗など、多様なタッチポイントを整理し、一貫した顧客体験を提供する必要性が高まっています。
2. 顧客体験(CX)重視の潮流:商品・サービスの機能や価格による差別化が難しくなる中、顧客体験の質が競争優位の源泉として注目されています。優れた顧客体験を設計するためには、まず現状の体験を可視化する必要があります。
3. データ活用の進化:顧客行動データの取得・分析が容易になり、より精緻な顧客理解が可能になっています。これらのデータをカスタマージャーニーマップに組み込むことで、より実効性の高いマーケティング施策を検討できるようになっています。
4. 組織のサイロ化解消の必要性:顧客は部門ごとではなく、企業全体と接しています。マーケティング、販売、カスタマーサポートなどの部門を越えた一貫した顧客体験を提供するために、組織横断的な顧客理解の共有が求められています。
従来のマーケティング手法との違い
カスタマージャーニーマップは、以下の点で従来のマーケティング手法と異なります:
| 従来のマーケティング手法 | カスタマージャーニーマップを活用したマーケティング |
|---|---|
| 企業視点での商品・サービス訴求 | 顧客視点での体験価値の向上 |
| 単発的な広告・プロモーション | 顧客接点全体を通じた一貫したコミュニケーション |
| マーケティングファネルによる一方向的な顧客育成 | 双方向的な関係性構築を含む顧客の旅全体の設計 |
| 部門ごとの最適化 | 組織横断的なカスタマーエクスペリエンスの最適化 |
| 売上・コンバージョンなど結果重視の指標 | 顧客満足度・ロイヤルティなど体験価値を含む総合的評価 |
従来の4P(Product、Price、Place、Promotion)や、マーケティングファネルといったフレームワークも依然として重要ですが、カスタマージャーニーマップはこれらを補完し、より顧客中心のマーケティングを実現するための強力なツールとなっています。
カスタマージャーニーマップを作る4つの目的

カスタマージャーニーマップを作成する目的は、単に「顧客の行動を可視化する」だけではありません。戦略的なマーケティング活動を展開するための基盤として、以下の4つの明確な目的があります。
ユーザー行動の仮説立案:顧客理解の深化
カスタマージャーニーマップの第一の目的は、顧客行動に関する仮説を立てることです。顧客は様々な思考や行動をとるため、すべてを完璧に予測することは不可能です。しかし、データと洞察に基づいた仮説を立てることで、より効果的な施策を検討できるようになります。
例えば、美容サービスを提供する企業の場合、以下のような仮説を立てることができます:
- 「肌トラブルを抱える30代女性は、まず検索エンジンで悩みに関連するキーワードを調べる」
- 「情報収集段階では、専門家の意見や口コミを特に重視する」
- 「購入前に無料サンプルや体験版で効果を確認したいと考える」
このような仮説を立てることで、顧客の行動背景にある思考や感情、課題に気づきやすくなります。デジタルマーケティングの発展により、顧客の行動データを収集・分析することが容易になっているため、より精度の高い仮説立案が可能になっています。
重要なのは、仮説を固定観念としてではなく、検証と改善を繰り返す出発点として捉えることです。実際のデータや顧客フィードバックを継続的に収集し、仮説を検証・修正していくことで、顧客理解をさらに深めていけます。
適切なコミュニケーション施策の設計:最適なタッチポイント戦略
カスタマージャーニーマップの第二の目的は、顧客の状況に応じた適切なコミュニケーション施策を設計することです。顧客が購買プロセスのどの段階にいるかによって、必要とする情報や解決したい課題は異なります。
効果的なコミュニケーション設計では、以下の点を検討する必要があります:
- コンテンツ(何を):特定の心理状態にある顧客に対して、どのような情報・メッセージを提供すべきか
- チャネル(どこで):そのコミュニケーションを実現するために、どのような媒体・接点を活用すべきか
- タイミング(いつ):顧客の意思決定プロセスのどのタイミングで情報を提供すべきか
- 刺激(どのように):どのような形で訴求すれば、次の段階への態度変容を促せるか
例えば、自動車販売の場合、認知段階では車のデザインや特徴的な機能を訴求し、検討段階では他社モデルとの比較情報や試乗体験を提供するといった具合に、段階に応じて最適なコミュニケーションを設計します。
カスタマージャーニーマップを活用することで、顧客の各段階における以下のような情報を可視化できます:
- 顧客の属性や特性
- 顧客が抱える悩みや課題
- 顧客の情報収集方法や接点
- 顧客の意思決定要因
- 購入・利用に至った理由や経緯
これらの情報をもとに、どのような媒体で顧客との接点を作るべきか、どのようなコミュニケーションを取れば態度変容を促せるかを具体的に検討できるようになります。
マーケティング施策の優先順位決定:リソースの効率的配分
どの企業にもマーケティング予算や人的リソースには限りがあります。そのため、取り組むべき施策の優先順位を適切に決め、最大の効果を生み出すことが重要です。カスタマージャーニーマップの第三の目的は、このような優先順位づけを支援することです。
カスタマージャーニーマップでは、顧客行動を俯瞰して見ることができるため、以下のような判断が可能になります:
- どの段階で顧客が最も課題を感じているか(ボトルネックの特定)
- どのタッチポイントが顧客の意思決定に大きな影響を与えているか
- どの施策が顧客体験の向上に最も寄与するか
- どのような改善が競合との差別化に繋がるか
例えば、ECサイトのカスタマージャーニーマップを分析した結果、「商品検討段階で詳細情報が不足している」「購入手続きが複雑で離脱率が高い」という2つの課題が見つかったとします。限られたリソースのなかで、まずどちらに取り組むべきでしょうか。
カスタマージャーニーマップでは、顧客の感情状態やコンバージョン率などのデータも合わせて可視化できるため、「購入手続きの簡素化」が優先度の高い課題だと判断できるかもしれません。このように、顧客視点での優先順位づけを行うことで、効果的なリソース配分が可能になります。
チーム内での共通認識の形成:組織連携の強化
カスタマージャーニーマップの第四の目的は、組織全体で顧客に関する共通認識を形成することです。部門ごとに異なる目標や指標を持っていると、顧客視点での一貫した体験を提供することが難しくなります。
カスタマージャーニーマップを活用することで、以下のような効果が期待できます:
- マーケティング、営業、カスタマーサポートなど部門間の壁を越えた顧客理解の共有
- 顧客視点での問題意識の統一
- 施策の整合性・一貫性の確保
- 部門横断的な協力体制の構築
- 顧客中心の組織文化の醸成
例えば、航空会社A社では、急速な成長に伴い従業員が増加するなかで顧客体験の質を維持するために、カスタマージャーニーマップを活用しました。顧客体験向上チームを組織し、マップを用いて顧客体験の課題を示すとともに、顧客中心の視点を内部化するための研修を実施。協力的でなかった部門も、成果を積み重ねるなかで徐々に協力者が増えていったという事例があります。
特に大規模な組織や、複数の部門が顧客接点に関わる企業では、このような共通認識の形成がきわめて重要です。カスタマージャーニーマップは、単なる分析ツールではなく、組織のコミュニケーションツールとしても大きな価値を発揮します。
次のセクションでは、目的に応じて選べる3つのカスタマージャーニーマップの種類について解説します。どのタイプのマップが自社の目的に最も適しているのかを見極めるポイントを学びましょう。
目的別に選ぶ3つのカスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは一般的に「顧客の行動を可視化したもの」として認識されていますが、実際には目的によって異なる種類があります。自社の課題や状況に合わせて最適なタイプを選ぶことで、より効果的に活用できます。ここでは、代表的な3つの種類について解説します。
マクロ型:マーケティング全体を俯瞰する戦略的マップ
マクロ型カスタマージャーニーマップは、「鳥の目」でマーケティング全体を俯瞰するための戦略的なマップです。このタイプは主に戦略立案フェーズで活用され、商品・サービスのマーケティング全体において、どこに大きな課題が潜んでいるかを把握するのに役立ちます。
特徴:
- マーケティングファネル(AIDMA、AISASなど)に沿った広い視点
- 主要なタッチポイントとKPIの可視化
- マーケティング全体の優先課題の特定
- デジタルマーケティングツール選定の優先順位づけに活用可能
構成要素:
- ファネル:認知、興味・関心、検討、購入、利用、推奨などの段階
- タッチポイント:リアル・デジタルに分けた顧客接点
- コンテンツ・訴求ポイント:各タッチポイントでの訴求内容
- 使用ツール:各タッチポイントで活用している仕組み
- KPI:各段階での主要指標と課題
例えば、ECサイトを運営する企業がマクロ型ジャーニーマップを作成した場合、「認知段階でのリーチ数は十分だが、商品詳細ページから購入ページへの遷移率が低い」という課題が浮かび上がるかもしれません。こうした課題を発見することで、改善すべき優先領域が明確になります。
マクロ型ジャーニーマップは、特に以下のような場合に有効です:
- マーケティング戦略全体を見直したいとき
- 限られたリソースでどこに注力すべきか判断したいとき
- 新規事業のマーケティング計画を立案するとき
- デジタルマーケティングツールの導入を検討するとき
ミクロ型:ユーザー体験の問題点を特定する課題解決型マップ
ミクロ型カスタマージャーニーマップは、「虫の目」で顧客体験の細部を観察するための課題解決型マップです。このタイプも戦略立案フェーズで活用されますが、より詳細な顧客体験に焦点を当て、体験価値を低下させている具体的な問題点(ボトルネック)を特定するのに役立ちます。
特徴:
- 個々の顧客体験に焦点を当てた詳細な視点
- 顧客の感情や体験価値の変化の可視化
- 体験上のボトルネック(期待値を下回る箇所)の特定
- 具体的な改善策検討の基盤
構成要素:
- 時系列:顧客行動の詳細なステップ
- タッチポイント:各ステップでの接点
- 顧客の感情・評価:段階ごとの満足度やNPS(顧客推奨度)
- 期待と実際の体験:顧客が期待していたことと実際の体験のギャップ
- ボトルネック:特に体験価値が低下している箇所
例えば、レストラン経営者がミクロ型ジャーニーマップを作成したとします。「予約は簡単だったが、来店時の駐車場探しが大変で、入店時にはすでに不満を抱えていた」「料理は美味しかったが、会計時の対応が事務的で印象が悪かった」といった具体的な課題を発見できるでしょう。
ミクロ型ジャーニーマップでは、顧客満足度は「体験から期待値を差し引いたもの」と捉えます。つまり、体験が期待を上回れば満足度は高まり、下回れば低下します。特に、顧客の期待値が高い領域で体験が期待を下回ると、大きな不満につながります。
ミクロ型ジャーニーマップは、以下のような場合に特に有効です:
- 顧客体験の改善に取り組みたいとき
- 顧客離脱の原因を特定したいとき
- 新サービス開発のための顧客インサイトを得たいとき
- 競合との差別化ポイントを探りたいとき
シナリオ型:顧客育成シナリオを設計する施策実行型マップ
シナリオ型カスタマージャーニーマップは、実際の施策実行フェーズで活用する実行計画型のマップです。特にMA(マーケティングオートメーション)やCMS(コンテンツ管理システム)などのデジタルマーケティングツールに登録するための、具体的な顧客育成シナリオとして機能します。
特徴:
- 施策実行に直結した実践的な視点
- 顧客育成のための具体的なコミュニケーション計画
- デジタルマーケティングツールへの実装を前提とした設計
- PDCAサイクルを回しながら継続的に最適化
構成要素:
- 時系列:顧客育成の段階
- タッチポイント:顧客とのコミュニケーション接点
- コンテンツ:各段階で提供する情報・メッセージ
- タイミング:コミュニケーションのタイミングや頻度
- 条件分岐:顧客の反応に応じたシナリオの分岐
例えば、BtoBソフトウェア企業がシナリオ型ジャーニーマップを作成した場合、以下のようなシナリオが考えられます:
- ホワイトペーパーをダウンロードした見込み客に、3日後に関連する事例紹介メールを送信
- 事例紹介メールを開封した場合、1週間後にウェビナー案内を送信
- ウェビナーに参加した場合、翌日に製品デモの案内を送信
- 製品デモに参加した場合、営業担当者からの連絡をアクション
このように、顧客の行動や反応に基づいて次のアクションを設計し、段階的に顧客を育成していくシナリオを具体化します。
シナリオ型ジャーニーマップは、以下のような場合に特に有効です:
- MAツールを導入・活用する際
- コンテンツマーケティングの戦略を立案するとき
- パーソナライズされたコミュニケーション計画を策定するとき
- リードナーチャリングの仕組みを構築するとき
目的に合わせた種類の選び方
3つのタイプのカスタマージャーニーマップは、いずれか一つだけを使うのではなく、段階的に組み合わせて活用するのが効果的です。以下のような流れで進めることをおすすめします:
- マクロ型から始める:まず「鳥の目」でマーケティング全体を見渡し、優先的に取り組むべき課題領域を特定します。
- ミクロ型で掘り下げる:優先課題について「虫の目」で詳細に分析し、顧客体験上のボトルネックを特定します。
- シナリオ型で実行計画を立てる:マクロ型・ミクロ型で得られた洞察をもとに、具体的な施策の実行計画を立案します。
組織の状況やリソースによっては、まずはマクロ型から始めて徐々に他のタイプに展開していくアプローチも有効です。重要なのは、単に「カスタマージャーニーマップを作る」という目標ではなく、「何のために作るのか」を明確にすることです。
自社の状況に最適なタイプを選ぶための判断基準として、以下の質問を検討してみてください:
- 現在直面している最大の課題は何か?(全体戦略、顧客体験の改善、施策の実行など)
- マップを活用して具体的に何を達成したいか?
- リソース(時間、人員、予算)の制約は?
- どのようなデータや情報が入手可能か?
- 社内でのマップの活用主体は誰か?
これらの質問に答えることで、自社にとって最適なカスタマージャーニーマップの種類が見えてくるでしょう。
次のセクションでは、カスタマージャーニーマップを作成するための具体的な手順を、5つのステップに分けて解説します。
カスタマージャーニーマップとは?基本概念と重要性

カスタマージャーニーマップの定義と本質
カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入・利用し、その後もファンとなって継続利用するまでの「旅(ジャーニー)」を視覚的に表現したものです。顧客の行動、感情、思考、接点(タッチポイント)などを時間軸に沿って整理し、一枚の地図(マップ)として可視化します。
カスタマージャーニーマップの本質は、「顧客体験の全体像を把握する」ことにあります。商品やサービスそのものの価値だけでなく、顧客との接点すべてを通じた体験価値を高めることが、現代のマーケティングでは重要になっています。顧客がどのような行動を取り、何を考え、どのような感情を抱いているのかを理解することで、適切なタイミングで最適なコミュニケーションを取ることができるようになります。
ユーザーの態度変容プロセスを可視化する意義
顧客は商品・サービスを購入するまでに、「知らない」から「知っている」「興味がある」「欲しい」「買いたい」といった心理状態(態度)の変化を経験します。この態度変容プロセスを可視化することには、以下のような意義があります:
- 顧客の購買意思決定プロセスを理解できる
- 各段階での顧客ニーズや課題を特定できる
- 顧客の態度変容を促す適切な施策を検討できる
- 顧客体験上の改善ポイントを発見できる
- 組織全体で顧客視点の共通理解を形成できる
例えば、アパレル商品を購入するユーザーは、SNSで商品を発見した「認知」段階では「かわいい!」「欲しい!」といった漠然とした感情を抱きますが、購入段階に近づくにつれて「自分の体型に合うだろうか」「サイズ感は大丈夫だろうか」といった具体的な不安や疑問を感じるようになります。このように段階によって異なる顧客心理を理解することで、各段階に適したコミュニケーションを設計できるのです。
なぜ今、カスタマージャーニーマップが注目されているのか
カスタマージャーニーマップが近年特に注目されている理由には、以下のような背景があります:
1. 顧客接点の多様化・複雑化:デジタルチャネルの急増により、顧客との接点が複雑化しています。スマートフォン、SNS、EC、実店舗など、多様なタッチポイントを整理し、一貫した顧客体験を提供する必要性が高まっています。
2. 顧客体験(CX)重視の潮流:商品・サービスの機能や価格による差別化が難しくなる中、顧客体験の質が競争優位の源泉として注目されています。優れた顧客体験を設計するためには、まず現状の体験を可視化する必要があります。
3. データ活用の進化:顧客行動データの取得・分析が容易になり、より精緻な顧客理解が可能になっています。これらのデータをカスタマージャーニーマップに組み込むことで、より実効性の高いマーケティング施策を検討できるようになっています。
4. 組織のサイロ化解消の必要性:顧客は部門ごとではなく、企業全体と接しています。マーケティング、販売、カスタマーサポートなどの部門を越えた一貫した顧客体験を提供するために、組織横断的な顧客理解の共有が求められています。
従来のマーケティング手法との違い
カスタマージャーニーマップは、以下の点で従来のマーケティング手法と異なります:
| 従来のマーケティング手法 | カスタマージャーニーマップを活用したマーケティング |
|---|---|
| 企業視点での商品・サービス訴求 | 顧客視点での体験価値の向上 |
| 単発的な広告・プロモーション | 顧客接点全体を通じた一貫したコミュニケーション |
| マーケティングファネルによる一方向的な顧客育成 | 双方向的な関係性構築を含む顧客の旅全体の設計 |
| 部門ごとの最適化 | 組織横断的なカスタマーエクスペリエンスの最適化 |
| 売上・コンバージョンなど結果重視の指標 | 顧客満足度・ロイヤルティなど体験価値を含む総合的評価 |
従来の4P(Product、Price、Place、Promotion)や、マーケティングファネルといったフレームワークも依然として重要ですが、カスタマージャーニーマップはこれらを補完し、より顧客中心のマーケティングを実現するための強力なツールとなっています。
次のセクションでは、カスタマージャーニーマップを作成する具体的な目的と、それによって得られる効果について詳しく見ていきましょう。
カスタマージャーニーマップを作る4つの目的

カスタマージャーニーマップを作成する目的は、単に「顧客の行動を可視化する」だけではありません。戦略的なマーケティング活動を展開するための基盤として、以下の4つの明確な目的があります。
ユーザー行動の仮説立案:顧客理解の深化
カスタマージャーニーマップの第一の目的は、顧客行動に関する仮説を立てることです。顧客は様々な思考や行動をとるため、すべてを完璧に予測することは不可能です。しかし、データと洞察に基づいた仮説を立てることで、より効果的な施策を検討できるようになります。
例えば、美容サービスを提供する企業の場合、以下のような仮説を立てることができます:
- 「肌トラブルを抱える30代女性は、まず検索エンジンで悩みに関連するキーワードを調べる」
- 「情報収集段階では、専門家の意見や口コミを特に重視する」
- 「購入前に無料サンプルや体験版で効果を確認したいと考える」
このような仮説を立てることで、顧客の行動背景にある思考や感情、課題に気づきやすくなります。デジタルマーケティングの発展により、顧客の行動データを収集・分析することが容易になっているため、より精度の高い仮説立案が可能になっています。
重要なのは、仮説を固定観念としてではなく、検証と改善を繰り返す出発点として捉えることです。実際のデータや顧客フィードバックを継続的に収集し、仮説を検証・修正していくことで、顧客理解をさらに深めていけます。
適切なコミュニケーション施策の設計:最適なタッチポイント戦略
カスタマージャーニーマップの第二の目的は、顧客の状況に応じた適切なコミュニケーション施策を設計することです。顧客が購買プロセスのどの段階にいるかによって、必要とする情報や解決したい課題は異なります。
効果的なコミュニケーション設計では、以下の点を検討する必要があります:
- コンテンツ(何を):特定の心理状態にある顧客に対して、どのような情報・メッセージを提供すべきか
- チャネル(どこで):そのコミュニケーションを実現するために、どのような媒体・接点を活用すべきか
- タイミング(いつ):顧客の意思決定プロセスのどのタイミングで情報を提供すべきか
- 刺激(どのように):どのような形で訴求すれば、次の段階への態度変容を促せるか
例えば、自動車販売の場合、認知段階では車のデザインや特徴的な機能を訴求し、検討段階では他社モデルとの比較情報や試乗体験を提供するといった具合に、段階に応じて最適なコミュニケーションを設計します。
カスタマージャーニーマップを活用することで、顧客の各段階における以下のような情報を可視化できます:
- 顧客の属性や特性
- 顧客が抱える悩みや課題
- 顧客の情報収集方法や接点
- 顧客の意思決定要因
- 購入・利用に至った理由や経緯
これらの情報をもとに、どのような媒体で顧客との接点を作るべきか、どのようなコミュニケーションを取れば態度変容を促せるかを具体的に検討できるようになります。
マーケティング施策の優先順位決定:リソースの効率的配分
どの企業にもマーケティング予算や人的リソースには限りがあります。そのため、取り組むべき施策の優先順位を適切に決め、最大の効果を生み出すことが重要です。カスタマージャーニーマップの第三の目的は、このような優先順位づけを支援することです。
カスタマージャーニーマップでは、顧客行動を俯瞰して見ることができるため、以下のような判断が可能になります:
- どの段階で顧客が最も課題を感じているか(ボトルネックの特定)
- どのタッチポイントが顧客の意思決定に大きな影響を与えているか
- どの施策が顧客体験の向上に最も寄与するか
- どのような改善が競合との差別化に繋がるか
例えば、ECサイトのカスタマージャーニーマップを分析した結果、「商品検討段階で詳細情報が不足している」「購入手続きが複雑で離脱率が高い」という2つの課題が見つかったとします。限られたリソースのなかで、まずどちらに取り組むべきでしょうか。
カスタマージャーニーマップでは、顧客の感情状態やコンバージョン率などのデータも合わせて可視化できるため、「購入手続きの簡素化」が優先度の高い課題だと判断できるかもしれません。このように、顧客視点での優先順位づけを行うことで、効果的なリソース配分が可能になります。
チーム内での共通認識の形成:組織連携の強化
カスタマージャーニーマップの第四の目的は、組織全体で顧客に関する共通認識を形成することです。部門ごとに異なる目標や指標を持っていると、顧客視点での一貫した体験を提供することが難しくなります。
カスタマージャーニーマップを活用することで、以下のような効果が期待できます:
- マーケティング、営業、カスタマーサポートなど部門間の壁を越えた顧客理解の共有
- 顧客視点での問題意識の統一
- 施策の整合性・一貫性の確保
- 部門横断的な協力体制の構築
- 顧客中心の組織文化の醸成
例えば、航空会社A社では、急速な成長に伴い従業員が増加するなかで顧客体験の質を維持するために、カスタマージャーニーマップを活用しました。顧客体験向上チームを組織し、マップを用いて顧客体験の課題を示すとともに、顧客中心の視点を内部化するための研修を実施。協力的でなかった部門も、成果を積み重ねるなかで徐々に協力者が増えていったという事例があります。
特に大規模な組織や、複数の部門が顧客接点に関わる企業では、このような共通認識の形成がきわめて重要です。カスタマージャーニーマップは、単なる分析ツールではなく、組織のコミュニケーションツールとしても大きな価値を発揮します。
次のセクションでは、目的に応じて選べる3つのカスタマージャーニーマップの種類について解説します。どのタイプのマップが自社の目的に最も適しているのかを見極めるポイントを学びましょう。
カスタマージャーニーマップの作成手順:5つのステップ

カスタマージャーニーマップの作成は、一見複雑に思えるかもしれませんが、以下の5つのステップに分けて進めることで、効果的なマップを作成できます。それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
STEP1:明確なゴールを設定する
カスタマージャーニーマップを作成する上で最も重要なのが、明確なゴール設定です。「なぜこのマップを作るのか」「何を達成したいのか」を明確にすることで、適切な範囲と詳細度でマップを作成できます。
ゴール設定のポイント:
- マップ作成の目的(課題特定、コミュニケーション設計、組織共有など)
- 対象とする商品・サービス
- 対象とする顧客の旅の範囲(いつからいつまで)
- マップを活用する具体的なシーン
例えば、「新規顧客の獲得からリピート購入してくれるロイヤルカスタマーになるまで」をゴールにする場合、数年単位の長期的なジャーニーを描くことになります。一方、「キャンペーンからの会員登録促進」のように短期的なゴールの場合は、数日や数時間単位のジャーニーになることもあります。
また、「売上向上」のような一般的な目標だけでなく、「SNS上でのUGC(ユーザー生成コンテンツ)増加」「Webサイトからの問い合わせ増加」など、具体的なゴールを設定することで、より明確なジャーニーマップが作成できます。
ゴール設定の段階で関係者を巻き込み、合意形成を図ることも重要です。マップ作成の意義を共有し、期待値を揃えておくことで、後工程での協力を得やすくなります。
STEP2:ターゲットユーザー(ペルソナ)を定義する
カスタマージャーニーマップはペルソナごとに作成します。顧客像があいまいだと、実際の顧客行動とかけ離れたマップになりかねません。具体的なペルソナを設定し、リアルな顧客像をもとにマップを描いていきましょう。
ペルソナ設定のポイント:
- 基本属性(年齢、性別、職業、家族構成など)
- 価値観や考え方(何を重視するか、どんな判断基準を持つか)
- 行動特性(情報収集の方法、意思決定のプロセスなど)
- 課題や悩み(解決したいことは何か)
- 目標や理想(実現したい状態は何か)
可能であれば、既存顧客へのインタビューや調査データをもとにペルソナを設定することをおすすめします。実在の顧客の声を反映させることで、より現実的なジャーニーマップを作成できます。
例えば、アパレルECサイトのペルソナ例:
佐藤 美咲(28歳・会社員)
大手企業の営業部で働く独身女性。月収35万円。都内のワンルームマンションで一人暮らし。
価値観:忙しい仕事の合間に自分磨きを大切にしている。流行には敏感だが、価格と品質のバランスを重視。
行動特性:InstagramやTikTokで日常的にファッション情報を収集。購入前には必ず口コミをチェックする慎重派。
課題:仕事が忙しく店舗に行く時間がない。オンラインで購入したいが、サイズ感や着心地が不安。
目標:自分らしいファッションを手軽に見つけ、周囲から「センスがいい」と言われたい。
ただし、ペルソナ設定に過度にこだわりすぎて実作業が進まなくなるのは避けましょう。まずは暫定的なペルソナで作業を進め、データや洞察が増えるにつれて精緻化していくアプローチも有効です。
また、複数のペルソナを設定する場合は、優先順位をつけることも重要です。すべてのペルソナに対応しようとすると焦点がぼやけてしまうため、最も重要なペルソナから順に対応していくことをおすすめします。
STEP3:プロセス(時間軸)のステップを設計する
カスタマージャーニーマップの横軸となる時間軸のステップを設計します。顧客がどのような段階を経て最終的なゴールに到達するのかを整理しましょう。
ステップ設計のポイント:
- 顧客の認知からゴールまでの一連の流れを時系列で整理
- 各ステップの粒度を揃える
- 必要に応じてAIDMAやAISASなどの既存フレームワークを参考に
- 業界や商品・サービス特性に応じたカスタマイズ
一般的なECサイトであれば、「認知→興味・関心→検討→購入→利用→再購入・推奨」といったステップが考えられます。BtoBサービスであれば、「認知→情報収集→比較検討→トライアル→契約検討→契約→導入→活用→更新」など、より詳細なステップが必要かもしれません。
重要なのは、自社の商品・サービスに合わせたステップ設計をすることです。例えば、高額な商品であれば「比較検討」のステップをより詳細に分解したり、サブスクリプションサービスであれば「継続利用」や「アップグレード」のステップを追加したりするなど、柔軟に調整しましょう。
各ステップの定義を明確にしておくことも大切です。例えば、「検討」と「比較」の違い、「利用」と「活用」の違いなど、チーム内で共通認識を持っておくことで、マップ作成の効率が上がります。
STEP4:各ステップにおける行動・タッチポイントを整理する
ステップごとに、ペルソナがどのような行動を取り、どのようなタッチポイント(接点)と接しているかを整理します。この段階で、顧客と企業の接点を網羅的に把握することが重要です。
行動・タッチポイント整理のポイント:
- 各ステップでペルソナが取りうる行動をリストアップ
- オンライン・オフライン両方のタッチポイントを考慮
- 自社の直接的なタッチポイントだけでなく、第三者経由の接点も含める
- 顧客調査や営業担当者へのヒアリングで情報を補完
例えば、スマートフォンを購入する顧客の「検討」ステップでは、以下のような行動とタッチポイントが考えられます:
| 顧客行動 | タッチポイント |
|---|---|
| 製品スペックを調べる | 自社サイトの製品ページ、比較サイト、レビューサイト |
| 実機を確認する | 実店舗、家電量販店 |
| 価格を比較する | 価格比較サイト、ECサイト、チラシ |
| 口コミを確認する | SNS、レビューサイト、知人からの評判 |
| 質問・相談をする | 店舗スタッフ、カスタマーサポート、Q&Aサイト |
売り手の視点だけでは気づけないタッチポイントも多くあります。例えば、商品購入前に「友人・知人に相談する」「SNSで評判を調べる」といった行動は、企業の直接的なコントロール下にはありませんが、購買意思決定に大きな影響を与えることがあります。
このような網羅的なタッチポイントの把握には、顧客アンケートやインタビュー、ウェブサイトの行動ログ分析、営業担当者へのヒアリングなど、多角的な情報収集が有効です。
STEP5:ユーザーの感情・体験・課題を可視化してマッピングする
最後に、各ステップにおけるペルソナの感情、体験、課題を可視化し、マップとして統合します。この段階で顧客視点に立ち、彼らの内面を理解することが重要です。
感情・体験・課題の可視化ポイント:
- 各行動・タッチポイントにおける感情状態(期待、満足、不安、混乱など)
- 顧客が考えていること、疑問に思っていること
- 障壁や課題となっていること
- 顧客にとっての理想的な体験は何か
- 現状の体験と理想とのギャップ
感情状態は、数値スケール(例:-3〜+3)やエモーショングラフ(波線で感情の起伏を表現)で視覚化すると、直感的に理解しやすくなります。また、顧客の声を想定した「セリフ」や「思考」を吹き出しで表現する方法も効果的です。
例えば、レストラン予約サービスの「予約」ステップでは:
感情:初めは期待感(+2)だが、予約画面の複雑さに戸惑い(-1)を感じる
思考:「人気店に予約できるかな?」→「入力項目が多くて面倒…」→「本当に予約できたか不安…」
課題:予約フォームが複雑で、入力に時間がかかる。予約完了後の確認メールが分かりにくい。
理想:シンプルな操作で短時間に予約でき、明確な確認情報がすぐに届く体験。
このように顧客の内面を可視化することで、単なる行動の羅列ではなく、より深い顧客理解に基づいたマップが完成します。
最終的に、これらの要素を統合して一枚のマップにまとめます。マップは必ずしも複雑である必要はなく、目的に応じて必要な情報を盛り込むことが重要です。完成したマップは、関係者と共有し、改善のためのディスカッションのベースとして活用しましょう。
また、各ステップにおけるKPI(重要業績評価指標)を設定することも有効です。例えば、「認知」ステップでは広告接触率や認知度、「検討」ステップではウェブサイト滞在時間や資料請求数、「購入」ステップではコンバージョン率などを設定し、改善の目標と進捗を測る指標として活用できます。
次のセクションでは、データを活用した精度の高いカスタマージャーニーマップの作り方について解説します。定量・定性データをどのように収集・分析し、マップに反映させるかを学びましょう。
データを活用した精度の高いカスタマージャーニーマップの作り方

カスタマージャーニーマップの精度と有効性を高めるためには、主観的な想像や仮説だけでなく、実際のデータに基づいた分析が不可欠です。このセクションでは、既存データの活用法から新たなデータ収集まで、データドリブンなカスタマージャーニーマップ作成の方法を解説します。
既存データ(GA4、CRMデータ)の効果的な活用法
多くの企業では、すでに様々な顧客データが蓄積されています。これらの既存データを効果的に活用することで、カスタマージャーニーマップの精度を大幅に向上させることができます。
GA4(Google Analytics 4)の活用:
- ユーザーフロー分析:ユーザーがウェブサイト内でどのように行動しているかを可視化し、一般的な閲覧パターンを把握できます。
- 離脱率分析:どのページや段階で顧客が離脱しているかを分析し、改善すべきボトルネックを特定できます。
- コンバージョンパス分析:購入や問い合わせなどのコンバージョンに至るまでの代表的な経路を把握できます。
- セグメント分析:ユーザーの属性や行動パターンによってセグメントを分け、それぞれの特性を把握できます。
- イベント分析:特定のボタンクリックやフォーム入力などのユーザーインタラクションを測定し、詳細な行動パターンを把握できます。
GA4の分析データは、カスタマージャーニーマップの「行動」「タッチポイント」部分を作成する際に特に役立ちます。例えば、「商品ページ→カート追加→購入ページ→離脱」というパターンが多いことが分かれば、購入ページに何らかの障壁があると推測できます。
CRMデータの活用:
- 顧客属性データ:年齢、性別、地域などの基本情報からペルソナ設定の精度を高められます。
- 購買履歴データ:購入頻度、金額、商品カテゴリなどから顧客の好みや行動パターンを把握できます。
- 問い合わせ履歴:よくある質問や問い合わせ内容から、顧客の課題や疑問点を特定できます。
- NPS(顧客推奨度)データ:顧客満足度の高低と、その理由から改善ポイントを見つけられます。
- 顧客のライフタイムバリュー:顧客の長期的な価値を把握し、重点的に改善すべき顧客層を特定できます。
CRMデータは、特に既存顧客の「感情」「課題」「ニーズ」を推測する際に有効です。例えば、「初回購入後3ヶ月以内に2回目の購入がない顧客は離脱している」という傾向が見られれば、初回購入後のフォローアップに課題があると考えられます。
定量・定性データの収集と分析方法
既存データだけでは把握しきれない部分を補うために、新たなデータを収集することも重要です。定量データと定性データを組み合わせることで、より立体的な顧客理解が可能になります。
定量データの収集方法:
- 顧客アンケート調査:大規模なサンプルから傾向を把握するのに適しています。例えば、「当社の商品をどのように知りましたか?」「購入を決めた最も大きな理由は何ですか?」といった質問が有効です。
- A/Bテスト:異なるデザインや機能を比較し、どちらがより良い結果をもたらすかを測定します。ランディングページや購入フローの最適化に役立ちます。
- ヒートマップ分析:ウェブサイト上でのユーザーの視線や行動を可視化し、どの要素に注目しているかを把握できます。
- コンバージョンファネル分析:各ステップでのコンバージョン率を測定し、ドロップオフが多い箇所を特定します。
- SNS分析:自社に関する言及や評判をソーシャルリスニングツールで分析し、顧客の声を定量的に把握します。
定性データの収集方法:
- ユーザーインタビュー:少数の顧客と深く対話し、行動の背景にある動機や感情を理解します。「なぜそう思ったのですか?」といった掘り下げ質問が有効です。
- フォーカスグループ:複数の顧客を集めてディスカッションを行い、多様な視点を収集します。
- カスタマーサポート担当者へのヒアリング:日常的に顧客と接している社員から、よくある質問や困りごとを聞き出します。
- ユーザーテスト:実際の製品やサービスを使ってもらい、その過程で感じたことや考えたことを語ってもらいます。
- レビュー・口コミ分析:自社や競合の製品・サービスに関するレビューを質的に分析し、共通のテーマや感情を抽出します。
これらのデータ収集方法を組み合わせることで、「何が起きているか(定量)」と「なぜそれが起きているか(定性)」の両面を理解できます。例えば、アンケートで「購入ページからの離脱率が高い」ことが分かったら、ユーザーインタビューで「配送料が表示されて驚いた」という理由を発見できるかもしれません。
データドリブンなカスタマージャーニーマップ作成の実践ポイント
収集したデータを効果的にカスタマージャーニーマップに反映させるための実践ポイントを紹介します。
1. ジャーニーの各段階でのKPIを設定する
段階ごとに測定可能な指標を設定し、データで進捗を追跡できるようにします。
| ジャーニー段階 | KPI例 |
|---|---|
| 認知 | 広告到達率、ブランド認知度、SNSでの言及数 |
| 興味・関心 | サイト訪問数、ページ滞在時間、動画視聴率 |
| 検討 | 商品ページPV数、カタログ請求数、比較ページ閲覧率 |
| 購入 | コンバージョン率、平均購入額、カート放棄率 |
| 利用 | アクティブユーザー率、機能利用率、サポート問い合わせ数 |
| 推奨 | NPS、リピート率、SNSでの推奨投稿数 |
2. データの可視化ツールを活用する
複雑なデータを理解しやすく表現するために、可視化ツールを活用します。
- PowerBI、Tableau、Google Data StudioなどのBIツール
- Figma、Miro、Mural などの協働ビジュアルツール
- 専用のカスタマージャーニーマップ作成ツール(UXPressia、Smaplyなど)
3. セグメント別のジャーニーを分析する
顧客は均一ではありません。データに基づいて重要なセグメントを特定し、セグメント別のジャーニーマップを作成することで、よりターゲットに適した施策を検討できます。
- デモグラフィック(年齢、性別、地域など)によるセグメント
- 行動パターン(購入頻度、利用頻度など)によるセグメント
- 流入経路(検索、SNS、紹介など)によるセグメント
- 顧客ステータス(新規、リピーター、休眠など)によるセグメント
4. データに基づいてペルソナを精緻化する
初期のペルソナ設定は仮説に基づくことが多いですが、データ収集・分析を進めるにつれて、より実態に即したペルソナに更新していきます。
- 実際の顧客属性データからペルソナの基本情報を更新
- アンケートやインタビューから得られた価値観や行動特性を反映
- 複数の典型的なパターンを見つけ、複数のペルソナに分岐させる
5. 定期的なデータ更新とマップの見直しを行う
カスタマージャーニーは固定的なものではなく、市場環境や顧客行動の変化に応じて変化します。定期的にデータを更新し、マップを見直す仕組みを作りましょう。
- 四半期または半期ごとにデータを更新
- 新たなトレンドや行動パターンの変化を監視
- 施策実施後の効果測定結果をマップに反映
ユーザーインタビューとアンケート設計のコツ
カスタマージャーニーマップ作成において、特に重要な定性・定量データである「ユーザーインタビュー」と「アンケート」の効果的な設計・実施のコツを紹介します。
ユーザーインタビューの設計と実施のコツ:
- 適切な対象者を選定する:ターゲットペルソナに近い実在の顧客を選び、多様性にも配慮します。
- オープンエンドな質問を用意する:「はい/いいえ」で答えられる質問ではなく、「どのように感じましたか?」「なぜそう思いましたか?」などの質問で深堀りします。
- 実際の体験を思い出してもらう:「一般的にどうしますか?」ではなく、「最後に購入したときはどうでしたか?」と具体的な経験を聞きます。
- 行動と感情の両方を聞く:「何をしましたか?」だけでなく、「その時どう感じましたか?」と感情面も聞きます。
- 非誘導的な質問を心がける:「使いにくかったですか?」ではなく「使用感はいかがでしたか?」など、中立的な質問をします。
- 沈黙を恐れない:間を与えることで、相手が考えをまとめ、より深い回答を得られることがあります。
ユーザーインタビューの質問例:
- 「この商品を知ったきっかけは何でしたか?」
- 「購入を検討し始めた理由を教えてください」
- 「情報収集はどのように行いましたか?」
- 「購入を決めた決め手は何でしたか?」
- 「購入プロセスで困ったことはありましたか?」
- 「商品を使用してみた感想を教えてください」
- 「他の人にこの商品を勧めますか?その理由は?」
アンケート設計のコツ:
- 明確な目的を設定する:何を知りたいのかを明確にし、それに直結する質問だけを含めます。
- 簡潔で分かりやすい質問を作る:専門用語や複雑な表現を避け、誰でも理解できる言葉を使います。
- 回答選択肢を網羅的に用意する:予想される回答をカバーし、必要に応じて「その他」の自由記述欄も設けます。
- バイアスのかかる質問を避ける:「素晴らしい新機能をどう思いますか?」ではなく「新機能についてどう思いますか?」といった中立的な表現を使います。
- 論理的な質問順序にする:一般的な質問から具体的な質問へ、時系列に沿うなど、回答者が答えやすい流れを作ります。
- 適切な長さに抑える:回答率を維持するためにも、5〜10分で完了できる長さを目安にします。
カスタマージャーニーマップのためのアンケート質問例:
- 「当社の製品をどのように知りましたか?」(選択式)
- 「購入前にどのような情報を調べましたか?」(複数選択可)
- 「購入を決断する際に最も重視した要素は何ですか?」(選択式)
- 「購入プロセスの満足度を1〜5で評価してください」(評価スケール)
- 「商品使用時に困ったことがあれば教えてください」(自由記述)
- 「当社の製品・サービスで改善してほしい点は何ですか?」(自由記述)
データに基づいたカスタマージャーニーマップは、単なる想像や希望的観測ではなく、実際の顧客行動と感情に基づいた強力なツールとなります。継続的にデータを収集・分析し、マップを更新していくことで、より精度の高い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になるでしょう。
次のセクションでは、実践で使えるテンプレートとフォーマットを紹介します。目的や業種に応じた最適なテンプレートの選び方を学びましょう。
実践で使えるテンプレートとフォーマット

カスタマージャーニーマップを効率的に作成するには、適切なテンプレートやフォーマットを活用することが重要です。このセクションでは、基本的なテンプレート構成から目的別・業種別のカスタマイズ方法まで、実践ですぐに使えるフォーマットについて解説します。
基本的なテンプレートの構成要素
カスタマージャーニーマップの基本構造は、横軸に時間経過(ステージ)、縦軸に顧客の行動や感情などの要素を配置する表形式が一般的です。効果的なマップには、以下の要素が含まれていることが望ましいでしょう。
基本的なテンプレート構成要素:
- ペルソナ情報:マップの上部にペルソナの基本情報や画像を配置し、誰のジャーニーを描いているかを明確にします。
- ステージ(フェーズ):横軸に配置する時間軸で、一般的には「認知」「興味・関心」「検討」「購入」「利用」「推奨」などのステップを設定します。
- 行動:各ステージで顧客が取る具体的な行動を記述します。
- タッチポイント:顧客が接する接点(チャネル、媒体、場所など)を列挙します。
- 感情/体験:各ステージでの顧客の感情状態や体験価値を示します。感情曲線やスコアリングで可視化するとよいでしょう。
- 思考/発言:顧客が考えていることや言っていることを記述します。吹き出しで表現すると効果的です。
- 課題/痛点:各ステージで顧客が感じる障壁や不満点を示します。
- 機会/改善案:特定された課題に対する解決策や改善案を記入します。
- KPI/指標:各ステージの目標や測定指標を設定します。
- 担当部門/責任者:各タッチポイントや施策の担当部署を明確にします。
これらすべての要素を一度に盛り込むと複雑になりすぎる場合もあります。目的に応じて必要な要素を選び、シンプルかつ実用的なマップを作成することが重要です。
以下は、基本的なカスタマージャーニーマップのテンプレート例です:
| 認知 | 興味・関心 | 検討 | 購入 | 利用 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行動 | |||||
| 〇〇を検索する | ウェブサイトを閲覧する | 商品を比較する | 購入手続きをする | 商品を使用する | SNSで体験を共有する |
| タッチポイント | |||||
| 検索エンジン SNS広告 | ウェブサイト SNSアカウント | 商品ページ レビューサイト | ECサイト カスタマーサポート | 商品 マニュアル | SNS 口コミサイト |
| 感情 | |||||
| 興味 (+1) | 期待 (+2) | 不安/期待 (±0) | 緊張 (-1) | 満足 (+2) | 喜び (+3) |
| 課題/痛点 | |||||
| 情報が見つかりにくい | 詳細情報が不足している | 比較が難しい | 支払い方法が限られている | 使い方が分かりにくい | 共有しやすい機能がない |
| 改善案 | |||||
| SEO強化 広告出稿 | コンテンツ充実 UX改善 | 比較表の作成 レビュー強化 | 決済方法の追加 プロセス簡略化 | マニュアル改善 サポート強化 | シェア機能追加 レビュー促進 |
目的別テンプレートの選び方と活用法
先に説明した3つのタイプのカスタマージャーニーマップ(マクロ型、ミクロ型、シナリオ型)に応じて、最適なテンプレートも異なります。目的に合わせたテンプレートの選び方と活用法を紹介します。
マクロ型(戦略立案用)テンプレート:
マクロ型は全体像を把握する目的のため、詳細よりも俯瞰性を重視します。
- 特徴:広範な視点、シンプルな構造、主要KPIの可視化
- 主要構成要素:ステージ、主要タッチポイント、KPI、課題、機会
- 活用法:経営層や跨部門のミーティングでの利用、戦略的優先順位の決定に活用
マクロ型テンプレートでは、数値データを効果的に活用し、ステージごとのKPIやコンバージョン率を視覚的に示すことで、戦略上のボトルネックを明確にします。例えば、認知段階から興味段階へのコンバージョン率が低い場合、広告コピーやランディングページの改善が必要だと判断できます。
ミクロ型(顧客体験分析用)テンプレート:
ミクロ型は顧客体験の詳細な理解を目的とするため、感情や思考のような定性的要素を重視します。
- 特徴:詳細な行動フロー、感情曲線の可視化、具体的な顧客の声
- 主要構成要素:詳細なステップ、感情スコア、具体的な思考/発言、課題、理想体験
- 活用法:UX/UI改善、顧客接点の品質向上、カスタマーサポート改善に活用
ミクロ型テンプレートでは、感情曲線(顧客の感情の起伏をグラフ化したもの)を中心に配置し、各ポイントでの具体的な思考や発言を吹き出しで表現するとより直感的です。「期待と現実のギャップ」を明示することで、改善すべきポイントが明確になります。
シナリオ型(施策実行用)テンプレート:
シナリオ型は具体的な施策実行を目的とするため、アクションプランの要素を含みます。
- 特徴:時系列に沿った具体的なアクション、ツールやチャネルの明示、コンテンツ計画
- 主要構成要素:ステージ、タッチポイント、具体的なメッセージ/コンテンツ、タイミング、担当者
- 活用法:MAツールのシナリオ設定、コンテンツカレンダー作成、施策の実行管理
シナリオ型テンプレートでは、「いつ、どのチャネルで、どんなメッセージを、どのような条件で」送るかを具体的に記載します。例えば、「資料ダウンロード後3日経過・未連絡の場合、事例紹介メールを送信」といった具体的なアクションプランを時系列で整理します。
業種・業界別のカスタマイズポイント
カスタマージャーニーマップは業種や業態によってカスタマイズすることで、より効果的に活用できます。主要な業種別のカスタマイズポイントを紹介します。
EC・小売業向けカスタマイズポイント:
- ステージ設定:「商品発見」「カート追加」「チェックアウト」「配送待ち」「受け取り」「使用」などの詳細なステップを設定
- 重要指標:カート放棄率、平均購入額、リピート率、返品率などの指標を追加
- 特有の課題:「サイズ感がわからない」「配送状況が不明」などECに特有の課題を重点的に記載
- オムニチャネル対応:オンラインとオフライン(実店舗)の接点を統合的に可視化
BtoBサービス向けカスタマイズポイント:
- 長期的な時間軸:「認知」から「契約」までに数ヶ月〜1年以上かかることを考慮した長期的な視点
- 複数関係者の視点:決裁者、利用者、インフルエンサーなど複数の関係者のジャーニーを並行して表現
- 営業活動の詳細化:「提案」「見積」「交渉」「契約」などの詳細なステップを追加
- 顧客成功指標:導入後の活用度、追加契約率、更新率などの長期的な成功指標を追加
サブスクリプションサービス向けカスタマイズポイント:
- 継続利用フェーズの重視:「初期設定」「習熟」「活用」「更新検討」など利用段階の詳細化
- 解約理由の分析:解約検討時の課題や理由を詳細に分析する項目を追加
- アップセル/クロスセルポイント:追加機能や上位プランへの移行を促す適切なタイミングを表示
- エンゲージメント指標:継続率、機能利用率、顧客生涯価値(LTV)などの指標を追加
金融サービス向けカスタマイズポイント:
- 信頼構築プロセス:金融サービス特有の「信頼獲得」段階を詳細化
- コンプライアンス要素:法的要件や規制に関連する顧客体験要素を追加
- 長期的な関係性:口座開設後の長期的な利用シーンや節目(ライフイベント)を含める
- セキュリティ体験:本人確認や認証など、セキュリティに関わる体験を詳細に分析
テンプレートの活用例
具体的なテンプレート活用例として、アパレルECサイトを想定したカスタマージャーニーマップの一部を紹介します。
アパレルECサイトのカスタマージャーニーマップ(ミクロ型)例:
ペルソナ:佐藤美咲(28歳・会社員)
| 商品検索 | 商品詳細確認 | 購入決定 |
|---|---|---|
| 行動 | ||
| ・インスタで見たアイテムを検索 ・カテゴリーページをブラウズ ・検索フィルターを使用 | ・商品画像をすべて確認 ・サイズ表を確認 ・レビューとコーディネート例をチェック | ・サイズを選択 ・在庫確認 ・カートに追加 ・チェックアウト |
| タッチポイント | ||
| ・Instagram ・検索エンジン ・ECサイトトップページ ・カテゴリーページ | ・商品詳細ページ ・サイズガイドページ ・顧客レビューセクション ・コーディネート例 | ・サイズ選択UI ・カートページ ・チェックアウトページ ・注文確認メール |
| 感情 | ||
| 期待(+2)→ 少し混乱(±0) | 興味(+1)→ 不安(-1)→ 期待(+2) | 迷い(-1)→ 決断(+1)→ 達成感(+2) |
| 思考/発言 | ||
| 「インスタで見たあのワンピース、どこで売ってるんだろう」 「カテゴリーが多すぎて迷うな…」 | 「実際に着た感じはどうなんだろう?」 「私の体型に合うサイズはどれだろう?」 「このレビュアーと似た体型だから参考になる!」 | 「Mサイズで大丈夫かな…」 「今注文すれば週末のパーティに間に合うかな」 「やっぱり買っちゃおう!」 |
| 課題/痛点 | ||
| ・検索機能が弱い ・フィルターオプションが分かりにくい ・商品数が多すぎて目的のものを見つけづらい | ・着用イメージが湧きにくい ・サイズ表が分かりにくい ・レビューが少ない | ・サイズ選択に不安が残る ・配送日数が明確でない ・クーポン適用の手順が複雑 |
| 改善案 | ||
| ・画像検索機能の追加 ・フィルターUIの改善 ・人気アイテムのハイライト表示 | ・360度画像の追加 ・体型別サイズガイドの導入 ・インフルエンサーレビューの強化 | ・サイズ選択補助ツールの導入 ・配送日シミュレーターの追加 ・クーポン自動適用機能 |
| KPI | ||
| ・検索からの商品ページ遷移率 ・平均ページ滞在時間 ・ページ離脱率 | ・詳細ページから商品追加率 ・サイズガイド閲覧率 ・レビュークリック数 | ・カート追加から購入完了率 ・カート放棄率 ・クーポン利用率 |
このように、具体的なステップごとに顧客の行動、感情、思考などを詳細に可視化することで、改善すべきポイントが明確になります。例えば、上記の例では「商品詳細確認」段階での「サイズ表が分かりにくい」という課題に対して、「体型別サイズガイドの導入」という改善案が提案されています。
テンプレートを活用する際は、自社の状況に合わせて必要な要素を選び、適切にカスタマイズすることが重要です。最初から完璧を目指すのではなく、まずはシンプルな形でスタートし、徐々に精緻化していくアプローチも効果的です。
次のセクションでは、カスタマージャーニーマップ作成時の注意点と失敗例について解説します。よくある落とし穴を避け、より効果的なマップを作成するためのポイントを学びましょう。
カスタマージャーニーマップ作成時の注意点と失敗例
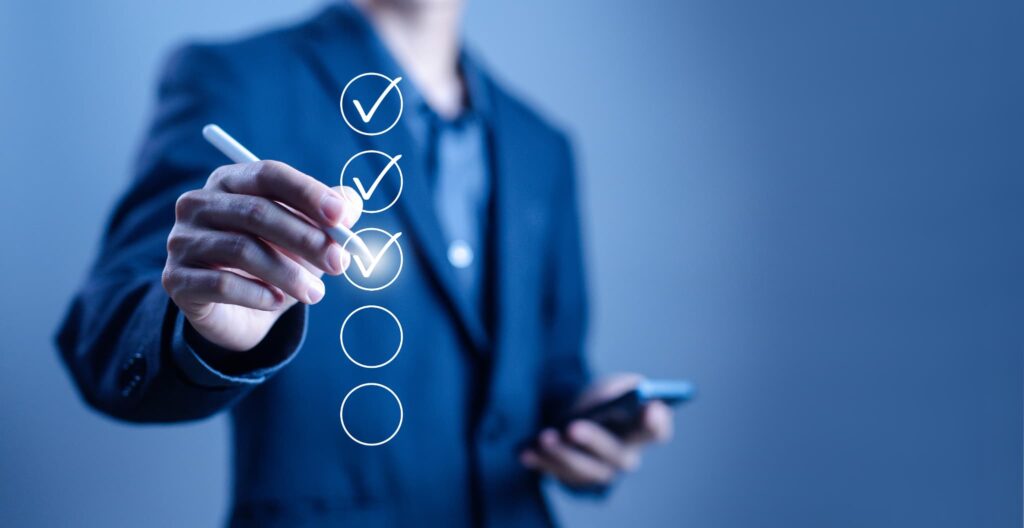
カスタマージャーニーマップは強力なツールですが、作成方法や活用方法を誤ると期待した効果を得られないだけでなく、誤った方向へのマーケティング施策につながることもあります。このセクションでは、カスタマージャーニーマップ作成時によくある注意点と失敗例、そしてそれらを回避するためのポイントを解説します。
企業視点ではなくユーザー視点で作成する
カスタマージャーニーマップ作成における最も根本的な注意点は、企業視点ではなくユーザー視点で作成することです。この視点の転換ができていないマップは、本来の目的を果たせません。
失敗例:
- 企業の希望を顧客の行動として描く:「SNSで商品を知り、すぐに公式サイトに訪問して詳細を確認し、迷わず購入する」といった、企業側の理想的なストーリーを描いてしまう
- 企業内部のプロセスをベースにする:「リード獲得→ナーチャリング→案件化→受注」といった営業プロセスをそのまま顧客ジャーニーとして扱う
- 自社チャネルだけに注目する:自社のウェブサイトやSNS、店舗などの接点だけを考慮し、比較サイトや口コミサイト、友人からの推薦など第三者経由の接点を無視する
改善ポイント:
- 顧客調査を必ず実施する:実際の顧客インタビューやアンケート、行動データを基にマップを作成する
- 「What」だけでなく「Why」を考える:行動の背景にある動機や感情、価値観を理解する
- 複数の情報源を活用する:アナリティクスデータ、カスタマーサポートの声、営業担当者のフィードバック、SNSでの言及など多角的な情報を集める
- 顧客目線のチェックを入れる:可能であれば、実際の顧客にマップを見てもらい、現実と乖離していないか確認する
USA.govのカスタマージャーニーマップ作成事例では、既存サイトのユーザー行動データだけでなく、顧客満足度調査やGoogle検索結果、他の公的機関のウェブサイトのアクセス状況など、多角的なデータを活用してジャーニーを描き出しました。結果として、本当の顧客ニーズに基づいたサイト改善につながりました。
過度に詳細に作り込みすぎない:シンプルさの重要性
カスタマージャーニーマップは詳細であるほど良いというわけではありません。過度に詳細に作り込みすぎると、かえって全体像が見えなくなったり、作成・更新の負担が大きくなりすぎたりする問題があります。
失敗例:
- あらゆる可能性を網羅しようとする:すべての顧客タイプ、すべての行動パターン、すべての例外ケースを1つのマップに詰め込もうとする
- 細かすぎるセグメントを作る:「20代前半・独身・都市部在住・年収400万円台・趣味は写真」といった極めて狭いセグメントを多数設定し、それぞれに詳細なマップを作成する
- 過剰な情報を盛り込む:マップに過剰に多くの指標や情報を詰め込み、何が重要なのか分からなくなる
改善ポイント:
- 目的に応じた詳細度に調整する:戦略検討なら俯瞰的に、特定の接点改善なら詳細に、といった具合に目的に合わせる
- 代表的なジャーニーに焦点を当てる:すべてのケースではなく、最も典型的・頻度の高いジャーニーを優先的に描く
- 段階的に精緻化する:シンプルなマップから始め、必要に応じて徐々に詳細化していく
- マップを階層化する:全体像を示す上位マップと、特定の段階に絞った詳細マップを分けて作成する
効果的なカスタマージャーニーマップでは、「木を見て森を見ず」にならないよう、適切な粒度でバランスを取ることが重要です。例えば、航空会社A社のカスタマージャーニーマップでは、すべての顧客接点を詳細に描くのではなく、顧客体験に大きな影響を与える主要なタッチポイントに焦点を当て、改善に取り組みました。
データや調査に基づかない仮説に頼らない
カスタマージャーニーマップが真に価値あるものになるには、主観的な仮説だけでなく、実際のデータや調査に基づいて作成する必要があります。エビデンスなしのマップは、間違った方向への投資につながりかねません。
失敗例:
- 担当者の個人的な体験を一般化する:「私だったらこうする」という自分自身の行動や好みをターゲット顧客に投影してしまう
- 社内の常識を前提にする:「皆知っているはず」「当然こうするだろう」という社内の常識や思い込みでジャーニーを描く
- データがないからと言って仮説だけで進める:「まずは作ってみよう」と根拠のない仮説だけでマップを作成し、そのまま施策に落とし込んでしまう
改善ポイント:
- 定量・定性データを組み合わせる:アナリティクスデータとユーザーインタビューなど、複数の情報源を活用する
- 仮説と検証のサイクルを回す:初期仮説は持ちつつも、継続的にデータで検証・修正していく
- 顧客の声を直接取り入れる:インタビュー、アンケート、レビュー分析などで顧客の生の声を収集する
- 仮説を明示的に区別する:マップ上でデータに基づく部分と仮説ベースの部分を明確に区別する
例えば、ある金融サービス企業では、自社アプリの利用状況データとユーザーインタビューを組み合わせて、顧客がどの段階でアプリを利用し、どのような課題を感じているかを詳細に分析しました。その結果、「簡単に利用できる」と思われていたお知らせ機能が実際には複雑で使いにくいと感じられていることが判明し、UI改善につながりました。
KPIを設定しない・見直さない問題と対策
カスタマージャーニーマップを作っただけでは価値は生まれません。マップを基にした改善活動を測定・評価するためのKPIが不可欠です。また、KPIを設定しても定期的に見直さなければ、環境変化に対応できなくなります。
失敗例:
- KPIなしでマップを完成と考える:「マップを作ること」自体が目的になり、成果指標を設定しない
- ビジネス成果に紐づかないKPIを設定する:「SNSフォロワー数」などの表面的な指標だけを重視し、売上や顧客満足度などの本質的な指標との関連を考えない
- 一度設定したKPIを見直さない:環境変化やユーザー行動の変化にもかかわらず、過去に設定したKPIをそのまま使い続ける
改善ポイント:
- 各ステージに適切なKPIを設定する:認知段階なら認知度や到達率、検討段階なら滞在時間やページ遷移率など、段階ごとに適切な指標を選ぶ
- 短期・中期・長期の指標をバランスよく設定する:即時的な反応(クリック率など)だけでなく、中長期的な成果(リピート率、LTVなど)も測定する
- 指標間の関連性を理解する:例えば「ページ滞在時間の増加」が最終的に「コンバージョン率の向上」にどうつながるかを整理する
- 定期的にKPIをレビュー・更新する:少なくとも年に一度はKPIの妥当性を見直し、必要に応じて更新する
効果的なKPI設定の例として、あるBtoB企業では、顧客ジャーニーの各段階に応じて以下のような指標を設定しました:
| ジャーニー段階 | KPI | 測定方法 |
|---|---|---|
| 認知 | ・ターゲット業界での認知率 ・専門メディアでの言及数 | ・市場調査 ・メディアモニタリング |
| 興味・関心 | ・ウェブサイト訪問数 ・資料ダウンロード数 | ・Googleアナリティクス ・MAツールデータ |
| 検討 | ・製品デモ申込率 ・見積もり依頼数 | ・CRMデータ ・営業活動記録 |
| 購入 | ・商談成約率 ・初期契約額 | ・販売データ ・CRMレポート |
| 利用 | ・アクティブ利用率 ・サポート問い合わせ数 | ・利用データ ・サポートチケット分析 |
| 推奨 | ・NPS(推奨度) ・アップセル・クロスセル率 | ・顧客アンケート ・購入データ分析 |
こうした体系的なKPI設定により、ジャーニー全体の健全性を測定し、改善すべき箇所を特定することができます。
作って終わりにしない:継続的な更新の重要性
カスタマージャーニーマップは一度作って終わりではなく、継続的に更新・改善していくことが不可欠です。市場環境や顧客行動の変化に伴い、ジャーニーも変化していくためです。
失敗例:
- 作成して安心してしまう:大がかりなワークショップでマップを作成した後、そのまま放置してしまう
- 古いマップを基に施策を継続する:数年前に作成したマップをそのまま現在の施策立案に使用する
- 更新の仕組みがない:誰がいつどのようにマップを更新するのか、責任と手順が明確になっていない
改善ポイント:
- 定期的な見直しサイクルを設定する:少なくとも半年〜1年ごとに全体を見直し、必要に応じて更新する
- 継続的なデータ収集の仕組みを作る:顧客の声やデータを継続的に収集し、ジャーニーの変化を監視する
- 環境変化に応じて柔軟に修正する:新技術の普及、競合動向、規制変更などの大きな環境変化があった場合は臨時で見直す
- マップの管理責任者を明確にする:誰がマップを管理し、更新プロセスを主導するかを明確にする
航空会社A社の事例では、顧客体験向上チームが定期的にカスタマージャーニーマップを見直し、環境の変化(モバイル利用の増加など)に合わせて更新しています。こうした継続的な取り組みにより、急速な成長にもかかわらず、顧客体験の質を維持することに成功しています。
カスタマージャーニーマップを真に価値あるツールとして活用するには、これらの注意点を踏まえ、ユーザー視点で、適切な詳細度で、データに基づき、明確なKPIを設定し、継続的に更新していくことが重要です。これらのポイントを押さえることで、マップが「作って終わり」の資料ではなく、顧客理解と体験向上のための生きたツールとなるでしょう。
次のセクションでは、完成したカスタマージャーニーマップを実際のマーケティング活動にどのように活かしていくか、具体的な活用方法について解説します。
カスタマージャーニーマップの効果的な活用方法

カスタマージャーニーマップを作成したら、次はそれを実際のマーケティング活動にどう活かすかが重要です。このセクションでは、カスタマージャーニーマップを様々なマーケティング施策に効果的に活用するための具体的な方法を解説します。
コンテンツマーケティングへの活用:段階に応じたコンテンツ設計
コンテンツマーケティングの成功には、顧客の各段階に応じた適切なコンテンツを提供することが不可欠です。カスタマージャーニーマップを活用することで、より効果的なコンテンツ戦略を立案できます。
カスタマージャーニーマップを活用したコンテンツマーケティング:
- ジャーニー段階別のコンテンツニーズを特定する
- 認知段階:顧客の課題や悩みに関する基本的な情報
- 興味・関心段階:解決策のオプションや概要知識
- 検討段階:詳細な情報、比較検討に役立つ情報
- 購入段階:最終的な不安を解消する情報
- 利用段階:活用方法や応用例に関する情報
- 推奨段階:成功体験を共有しやすいコンテンツ
- コンテンツタイプをジャーニー段階に合わせる
- 認知段階:ブログ記事、ソーシャルメディア投稿、インフォグラフィック
- 興味・関心段階:解説動画、入門ガイド、初級ウェビナー
- 検討段階:詳細な比較表、事例研究、デモ動画
- 購入段階:FAQ、顧客レビュー、購入ガイド
- 利用段階:チュートリアル、活用ガイド、ハウツー記事
- 推奨段階:成功事例、共有しやすいインフォグラフィック、UGC
- コンテンツギャップを特定し、優先順位をつける
- ジャーニーマップ上で顧客のニーズが高いが、既存コンテンツが弱い部分を特定
- 特に顧客の感情が不安定な段階や、決定的なタッチポイントを優先
- KPIが低い段階のコンテンツ強化に注力
- コンテンツの連続性を確保する
- コンテンツ間の自然な流れを設計(記事の最後に次に読むべきコンテンツへの誘導など)
- ジャーニー段階の移行を促すCTAの設置
- コンテンツ間の一貫したメッセージとトーンの維持
活用例:スキンケアブランドのコンテンツマーケティング
あるスキンケアブランドでは、カスタマージャーニーマップから「多くの顧客がスキンケア製品選びに悩んでおり、自分の肌質に合った製品を見つけられない」という課題を発見しました。そこで、ジャーニー段階別に以下のようなコンテンツを展開しました:
- 認知段階:「あなたの肌質を理解しよう」というブログ記事シリーズ
- 興味・関心段階:「60秒で分かる肌質診断ツール」の提供
- 検討段階:「肌質別おすすめスキンケアルーティン」の詳細ガイド
- 購入段階:「よくある質問と専門家の回答」や「購入者のビフォーアフター写真」
- 利用段階:「最大効果を得るための正しい使い方」解説動画
- 推奨段階:「あなたのビフォーアフターを共有しよう」キャンペーン
このように段階に応じたコンテンツを提供することで、顧客の悩みを段階的に解消し、購入への移行をスムーズにすることができます。
SNSマーケティングへの活用:適切なプラットフォーム選択と発信内容
SNSマーケティングでは、適切なプラットフォーム選択と各段階に合わせた発信内容が重要です。カスタマージャーニーマップは、こうした戦略立案に大きく役立ちます。
カスタマージャーニーマップを活用したSNSマーケティング:
- ターゲット顧客が利用するSNSプラットフォームを特定する
- ジャーニーマップから顧客の情報収集行動を分析
- 各段階で顧客が頻繁に利用するSNSプラットフォームを特定
- プラットフォームごとの役割を明確化(例:Instagramは認知獲得、Twitterはカスタマーサポートなど)
- ジャーニー段階に合わせたSNSコンテンツを設計する
- 認知段階:エンターテイメント性の高い投稿、トレンド関連コンテンツ
- 興味・関心段階:教育的コンテンツ、ブランドストーリー
- 検討段階:製品機能紹介、UGCの共有
- 購入段階:限定オファー、購入方法案内
- 利用段階:活用のヒント、トラブルシューティング
- 推奨段階:ハッシュタグキャンペーン、ユーザー体験の共有促進
- SNS上での顧客インタラクションを設計する
- 顧客からの質問や不満に対する迅速な対応方針
- コミュニティ育成のためのインタラクション計画
- インフルエンサーとのコラボレーション戦略
- SNS広告をジャーニー段階に合わせて最適化する
- リターゲティング広告でジャーニーを進めるための設計
- 各段階に応じた広告クリエイティブとメッセージの調整
- コンバージョンポイントの設定(認知段階ならサイト訪問、検討段階なら資料ダウンロードなど)
活用例:スポーツブランドのSNSマーケティング
あるスポーツブランドでは、カスタマージャーニーマップから「顧客は購入前に製品を実際に使っている様子を確認したい」という洞察を得ました。そこで、SNSマーケティングを次のように最適化しました:
- Instagram:影響力のあるアスリートが製品を実際に使用している様子を紹介する動画コンテンツ(認知・興味段階)
- TikTok:製品を使ったチャレンジ企画で、実用性と楽しさを訴求(興味・検討段階)
- YouTube:製品の詳細レビューや性能検証の長尺動画(検討段階)
- Twitter:リアルタイムの質問対応とフラッシュセール告知(検討・購入段階)
- Facebook:ユーザーコミュニティでの使用方法やカスタマイズ例の共有(利用・推奨段階)
このように、ジャーニー段階ごとに最適なプラットフォームと内容を設計することで、顧客をスムーズに次の段階へと導くことができます。
メールマーケティングへの活用:シナリオに基づいた最適配信
メールマーケティングは、顧客との直接的なコミュニケーションチャネルとして非常に重要です。カスタマージャーニーマップを活用することで、より効果的なメール施策を展開できます。
カスタマージャーニーマップを活用したメールマーケティング:
- 段階別のメールシナリオを設計する
- メールアドレス獲得時点でのジャーニー段階を特定
- 各段階に応じた一連のメールシーケンスを設計
- 行動に基づいた分岐シナリオの設計(例:メールを開封した場合と未開封の場合で異なるフォローアップ)
- メールの内容と頻度を最適化する
- ジャーニー段階に応じたメール内容の調整(例:認知段階では教育的内容、検討段階では比較情報など)
- 顧客の行動パターンや時間帯に合わせた配信タイミングの調整
- パーソナライズ要素の追加(名前、過去の行動、興味関心など)
- 行動トリガーに基づくタイムリーなメール配信
- カート放棄時の自動フォローメール
- 製品閲覧後の関連情報メール
- 購入後の使い方ガイドメール
- 定期的な利用がない場合の再アクティベーションメール
- メール効果測定とシナリオの継続的改善
- 開封率、クリック率、コンバージョン率などの指標監視
- A/Bテストによる継続的な最適化
- 顧客フィードバックに基づくコンテンツ改善
活用例:SaaSプロダクトのメールマーケティング
あるSaaS企業では、カスタマージャーニーマップから「無料トライアル中のユーザーが機能の使い方を十分に理解できておらず、有料版への移行が進まない」という課題を発見しました。そこで、次のようなメールシナリオを設計しました:
- トライアル開始直後:「30日間トライアルの始め方」基本ガイド
- 3日後:「あなたがまだ試していない主要機能」の紹介
- 7日後:実際の使用状況に基づいたパーソナライズドヒント
- 14日後:「他のユーザーはこう活用している」成功事例の紹介
- 20日後:「有料版でさらに活用できる機能」の案内
- 25日後:「トライアル終了まであと5日」移行促進メール
- トライアル終了後3日:「トライアル延長オファー」または「限定割引」の案内
このように、顧客のジャーニー段階と行動に合わせてメールを最適化することで、コンバージョン率を大幅に向上させることができました。
デジタルマーケティングツール選定への活用:必要ツールの優先順位づけ
デジタルマーケティングツールは多種多様で、すべてを導入するのは現実的ではありません。カスタマージャーニーマップを活用することで、最も効果的なツール選定と投資の優先順位づけができます。
カスタマージャーニーマップを活用したツール選定:
- ジャーニー上の課題とボトルネックを特定する
- コンバージョン率が低い段階や顧客満足度が低い接点を特定
- 手動で行われている非効率なプロセスを特定
- データ収集や分析が不十分な領域を特定
- 課題解決に必要なツール機能を明確にする
- 認知段階の課題なら、SEOツールやソーシャルリスニングツールなど
- 検討段階の課題なら、パーソナライゼーションツールやチャットボットなど
- 購入段階の課題なら、カート最適化ツールや決済システムなど
- 利用段階の課題なら、カスタマーサポートツールやナレッジベースなど
- ツール間の連携と統合を考慮する
- データの一元管理と顧客の一元的な把握が可能か
- 既存システムとの互換性や連携のしやすさ
- 複数チャネルをまたいだ顧客体験の一貫性を確保できるか
- ROIと優先順位を検討する
- 最も大きな課題解決につながるツールを優先
- 導入コストと期待される効果のバランスを評価
- 段階的な導入計画を立案
活用例:オムニチャネル小売業のツール選定
ある小売企業では、カスタマージャーニーマップから「オンラインで検討した商品を実店舗で購入したいが、在庫状況が不明」という顧客の課題を発見しました。そこで、次のようなツール選定を行いました:
- 優先課題:オンラインと実店舗の在庫情報の統合と顧客への可視化
- 必要機能:リアルタイム在庫管理、店舗別在庫表示、予約・取り置き機能
- 選定ツール:統合型在庫管理システムとウェブサイト連携モジュール
- 次のステップ:顧客行動データ分析のためのCRMシステム拡張
このように、カスタマージャーニーマップから特定された優先課題に基づいてツールを選定することで、限られた予算でも最大の効果を得ることができます。
CXマネジメントとの連携:顧客体験価値の最大化
カスタマージャーニーマップは、より広範なCX(カスタマーエクスペリエンス)マネジメントの一部として活用することで、顧客体験価値を最大化できます。
カスタマージャーニーマップとCXマネジメントの連携:
- 体験と期待値のギャップを特定する
- 顧客が各接点で期待する体験と実際の体験のギャップを分析
- 特に顧客の期待値が高い領域での体験向上に注力
- 競合と比較した体験価値の差別化ポイントを特定
- 組織横断的なCX改善体制を構築する
- ジャーニーマップを組織共通の言語として活用
- 部門を越えた体験改善チームの編成
- 各タッチポイントの責任部署と連携方法の明確化
- 体験品質のモニタリングと測定の仕組みを整える
- NPS(顧客推奨度)や顧客満足度などの体験指標の継続測定
- VOC(顧客の声)プログラムの実施
- 体験データと業績データの関連性分析
- 継続的な体験改善サイクルを回す
- 定期的な体験評価と課題の優先順位づけ
- 改善施策の実施と効果測定
- 顧客の期待値の変化に応じたジャーニーマップの更新
活用例:通信サービス企業のCXマネジメント
ある通信サービス企業では、カスタマージャーニーマップを活用したCXマネジメントを次のように実施しました:
- ジャーニーマップからの洞察:「契約手続きの複雑さ」と「料金プラン変更時の混乱」が主要な課題として特定
- 組織横断チーム編成:販売、カスタマーサポート、製品開発、ITの各部門からメンバーを集めたCX改善チームを結成
- 改善施策実施:契約手続きの簡素化、セルフサービスポータルの改善、料金プラン説明資料の刷新
- 効果測定:NPS上昇、問い合わせ数減少、契約完了率向上などの成果を確認
- 継続的改善:四半期ごとのジャーニーマップレビューと新たな課題への対応
このように、カスタマージャーニーマップをCXマネジメントの中核に据えることで、断片的な改善ではなく、顧客体験全体を一貫して向上させることができます。
カスタマージャーニーマップは、コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、メールマーケティング、ツール選定、CXマネジメントなど、多様なマーケティング活動に活用できる汎用的なツールです。重要なのは、単なる「絵」として終わらせず、具体的な施策立案と実行、そして継続的な改善のサイクルにつなげていくことです。
次のセクションでは、実際の企業がカスタマージャーニーマップをどのように活用して成功したのか、具体的な事例から学びましょう。
成功事例に学ぶ:実践企業のケーススタディ

理論を理解することも大切ですが、実際の企業がカスタマージャーニーマップをどのように活用して成果を上げたのかを知ることで、より具体的な実践のヒントを得ることができます。このセクションでは、さまざまな業界の企業によるカスタマージャーニーマップ活用の成功事例を紹介します。
USA.govの事例:UX改善とコンバージョン向上
USA.govは米国の電子政府サイトで、市民に対して政府サービスや情報への入り口となる重要なポータルです。しかし、多様な情報とサービスを提供するため、ユーザーが必要な情報を見つけにくいという課題を抱えていました。
課題:
- 膨大な情報量の中から市民が求める情報を効率的に提供する必要がある
- 多様なバックグラウンドを持つ利用者に対応する必要がある
- ウェブサイトのデザインとナビゲーションが複雑で分かりにくい
- コールセンターへの問い合わせが多く、効率化が求められている
カスタマージャーニーマップの活用プロセス:
- データ収集と分析
- 既存サイトの利用データ分析(人口統計、利用デバイス、アクセスページなど)
- 顧客満足度に関する調査データの収集
- Googleの検索結果や他の公的機関サイトの分析
- コールセンターへの問い合わせ内容の分析
- ワークショップの実施
- USA.govの運営メンバーによる4回のワークショップセッション
- 「顧客と関わる人やシステム」「対話をサポートする人やシステム」「顧客の態度や感情、ニーズ」「最良/最悪の顧客体験」について議論
- タイプの異なる複数のペルソナに対するジャーニーマップを作成
- 改善策の立案と優先順位づけ
- ワークショップを通じて110個の改善案を抽出
- 実現可能性とインパクトの観点から優先順位づけ
- 短期・中期・長期の実行計画を策定
実施した改善策:
- コンタクトセンターの自動応答メニューの簡素化と再構成
- ウェブサイトの検索機能と情報アーキテクチャの最適化
- モバイルユーザー向けのUI/UX改善
- よく検索される情報へのアクセス経路の簡略化
- 専門用語を分かりやすい言葉に置き換えるコンテンツ改善
成果:
- ウェブサイトのユーザビリティスコアの向上
- コールセンターへの問い合わせ数の減少(月間6,000件以上の削減)
- ユーザーの検索成功率の向上(15%改善)
- モバイルユーザーのセッション継続時間の増加
- 利用者満足度の向上
継続的な取り組み:
USA.govでは、この成功体験から学び、新規プロジェクトにおいてはペルソナとカスタマージャーニーマップの作成を標準プロセスとして組み込むようになりました。また、定期的に利用者データを分析し、ジャーニーマップを更新する仕組みも構築しています。
この事例からの学び:公共サービスのような複雑な情報提供においても、カスタマージャーニーマップを活用することで、利用者視点での改善点を明確にし、効果的な優先順位づけが可能になります。特に、多様なユーザーに対応する必要がある場合は、複数のペルソナに基づくジャーニーマップを作成することが有効です。
小売業での活用事例:オムニチャネル戦略の強化
ある大手アパレル小売チェーンは、オンラインと実店舗の連携強化によるオムニチャネル戦略の推進を目指していましたが、チャネル間の断絶が顧客体験を損なっているという課題を抱えていました。
課題:
- オンラインと実店舗の在庫情報や価格の不一致
- チャネルをまたいだ購買プロセスでの顧客体験の断絶
- 顧客データがチャネルごとに分断され、一元的な顧客理解ができない
- オンラインで検討した商品を店舗で購入したいというニーズへの対応不足
カスタマージャーニーマップの活用プロセス:
- マルチチャネル顧客行動の調査
- 店舗とオンラインの両方を利用する顧客への詳細インタビュー
- 購買前の調査行動から購入後のサポートまでの詳細なプロセス分析
- チャネル間の移動がどのような状況で発生するかの特定
- オムニチャネルジャーニーマップの作成
- オンラインから店舗、店舗からオンラインなど複数のパターンを可視化
- 各チャネル移行時のフリクション(障壁)ポイントを特定
- 理想的なオムニチャネル体験の設計
- 部門横断的な改善計画の立案
- eコマース部門、店舗運営、IT、マーケティング部門が参加するワークショップ
- チャネル間の一貫性確保のための施策立案
- システム統合とプロセス改善の優先順位づけ
実施した施策:
- 統合型在庫管理システムの導入によるリアルタイム在庫情報の共有
- オンラインで検討した商品を店舗で簡単に見つけられる「店舗内商品検索アプリ」の開発
- オンラインで購入した商品の店舗返品サービスの導入
- 統合顧客データプラットフォームによるチャネル横断的な顧客理解の実現
- 店舗スタッフがオンラインでの顧客行動履歴を確認できるシステムの導入
成果:
- オンラインと店舗を併用する顧客の購入額が平均20%増加
- 店舗来店前のオンライン調査を行う顧客の転換率向上
- 顧客満足度と再訪問率の改善
- 店舗スタッフとeコマース部門の協力関係の強化
- 返品率の低下とカスタマーサポートコストの削減
継続的な取り組み:
この小売チェーンでは、カスタマージャーニーマップを「生きた文書」として継続的に更新し、新たなテクノロジー(AR試着、モバイル決済など)の導入検討にも活用しています。また、定期的な顧客調査を通じて、ジャーニーマップの妥当性を検証しています。
この事例からの学び:オムニチャネル環境では、チャネルをまたいだ顧客行動を包括的に把握することが極めて重要です。カスタマージャーニーマップを活用することで、チャネル間の断絶ポイントを特定し、シームレスな顧客体験を設計することができます。また、部門間の協力を促進する効果も大きいといえます。
BtoB企業での活用ポイント:長期的な顧客関係構築
ある法人向けITソリューション企業は、複雑で長期間に及ぶ購買プロセスの中で、効果的な顧客育成とエンゲージメント維持に課題を抱えていました。
課題:
- 最初の問い合わせから契約締結までに平均6〜9ヶ月かかる長期的な購買プロセス
- 購買意思決定に複数の関係者(決裁者、利用者、技術評価者など)が関与
- 各段階での適切な情報提供と次のステップへの誘導の難しさ
- 契約後の顧客活性化と拡販機会の特定
カスタマージャーニーマップの活用プロセス:
- 複数の関係者視点を含むジャーニー分析
- 決裁者、実際の利用者、技術評価者など複数のペルソナ設定
- 各ペルソナの情報ニーズと意思決定基準の特定
- 契約前〜契約後までの長期的なジャーニーマッピング
- 段階別・役割別のコンテンツとコミュニケーション設計
- 各購買段階と役割に応じた最適なコンテンツの特定
- 意思決定プロセスの各段階での懸念事項と解消方法の整理
- 顧客育成シナリオの詳細設計
- 営業・マーケティング連携の強化
- リードスコアリングとハンドオフタイミングの最適化
- 営業活動の各段階での適切なサポート体制構築
- 顧客情報の一元管理と共有体制の整備
実施した施策:
- 役割別・段階別のコンテンツハブの構築(決裁者向け、技術評価者向け、利用者向け)
- 行動トリガーに基づく自動化されたリードナーチャリングプログラムの導入
- 営業担当者向けの「顧客ジャーニーステージ別営業ガイド」の作成
- 顧客成功プログラムの体系化と契約後の継続的エンゲージメント設計
- アカウントベースドマーケティング(ABM)アプローチの導入
成果:
- 営業サイクルの15%短縮
- マーケティングから営業へのリード転換率向上
- 提案成約率の20%改善
- 既存顧客からの追加サービス導入率向上
- 顧客満足度と契約更新率の改善
BtoB企業でのカスタマージャーニーマップ活用の特徴と留意点:
- 複数の関係者を考慮する
- 意思決定に関わる複数の役割(決裁者、利用者、評価者など)を理解する
- 役割ごとの情報ニーズや懸念点を別々に分析する
- 各役割の相互影響関係を考慮する
- 長期的なタイムスパンを考慮する
- 数ヶ月〜数年にわたる長期的なジャーニーを設計する
- 「離脱→再接触」といった非線形なパターンも考慮する
- 各段階での適切なタイミングとペースを見極める
- 営業プロセスとの連携を強化する
- マーケティングと営業の連携ポイントを明確にする
- 営業担当者が活用しやすいジャーニーマップを作成する
- 顧客接点データの共有と活用の仕組みを構築する
- 契約後のジャーニーも重視する
- 導入支援、活用促進、アップセル・クロスセルまでの一貫したジャーニーを設計する
- 顧客成功(カスタマーサクセス)の視点を取り入れる
- 長期的な関係構築とライフタイムバリュー向上を目指す
この事例からの学び:BtoB企業のカスタマージャーニーマップでは、複数の意思決定者の視点を考慮し、長期的な関係構築を視野に入れることが重要です。特に、営業プロセスとの連携、契約後の顧客体験まで含めた包括的なアプローチが効果的です。また、役割別・段階別に最適化されたコンテンツとコミュニケーション設計が成功のカギとなります。
これらの事例が示すように、カスタマージャーニーマップは様々な業界や目的に合わせて柔軟に活用できるツールです。重要なのは、自社の状況や課題に合わせてアプローチをカスタマイズし、継続的な改善サイクルを回していくことです。これらの成功事例から学び、自社の顧客体験向上に活かしていきましょう。
次のセクションでは、これまでの内容を総括し、効果的なカスタマージャーニーマップ作成と活用のための重要ポイントをまとめます。
まとめ:効果的なカスタマージャーニーマップ作成のポイント

ここまで、カスタマージャーニーマップの基本概念から作成方法、活用法、成功事例まで詳しく解説してきました。このセクションでは、これまでの内容を総括し、効果的なカスタマージャーニーマップを作成・活用するための重要ポイントをまとめます。
カスタマージャーニーマップ作成の重要ポイント総括
カスタマージャーニーマップは、単なる図表ではなく、顧客理解と体験向上のための強力なツールです。効果的なマップ作成と活用のために、以下の重要ポイントを押さえておきましょう。
- 明確な目的を持つ
- 「なぜマップを作るのか」「何を達成したいのか」を明確にする
- 目的に応じて適切なタイプ(マクロ型、ミクロ型、シナリオ型)を選ぶ
- 単に「作ること」が目的にならないよう注意する
- 顧客視点で考える
- 企業視点ではなく、徹底して顧客の立場で考える
- 実際の顧客データや声に基づいてマップを作成する
- 顧客の行動だけでなく、感情や動機も理解する
- 適切なペルソナを設定する
- 具体的かつ現実的なペルソナを設定する
- ターゲット市場の規模や価値も考慮する
- BtoBの場合は複数の意思決定者を考慮する
- データと洞察を組み合わせる
- 定量データ(アクセス解析、購買データなど)と定性データ(インタビュー、レビューなど)を組み合わせる
- 仮説と検証のサイクルを回す
- 継続的にデータを収集・分析する仕組みを構築する
- シンプルかつ実用的に保つ
- すべての可能性を網羅しようとせず、最も重要な要素に焦点を当てる
- 目的に応じた適切な詳細度を設定する
- 実際に活用できる形式と内容にする
- チーム全体で共有・活用する
- 部門を越えた共通理解のツールとして活用する
- 関係者全員がアクセスしやすい形で管理する
- 定期的にワークショップなどでマップを見直す機会を設ける
- 継続的に更新・改善する
- 市場環境や顧客行動の変化に合わせて定期的に更新する
- 施策の効果を測定し、マップにフィードバックする
- 「生きた文書」として進化させ続ける
- 具体的な行動につなげる
- マップから得られた洞察を具体的な施策に落とし込む
- 優先順位をつけて実行計画を立てる
- 効果測定の指標(KPI)を設定する
継続的な改善のためのチェックリスト
カスタマージャーニーマップは作って終わりではなく、継続的に改善していくことが重要です。以下のチェックリストを活用して、定期的にマップの有効性を評価し、改善していきましょう。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 目的の妥当性 | ・マップの目的は現在も有効か ・新たな目的や課題が発生していないか |
| ペルソナの適切性 | ・ペルソナは実際の顧客像と一致しているか ・新たなペルソナの追加が必要ではないか |
| ジャーニーの網羅性 | ・重要なタッチポイントが抜け落ちていないか ・新たなチャネルや接点が発生していないか |
| データの最新性 | ・最新のデータが反映されているか ・新たなデータソースの追加が必要ではないか |
| 顧客行動の変化 | ・顧客の行動パターンに変化がないか ・技術やトレンドの変化による影響はないか |
| KPIの達成状況 | ・設定したKPIは達成されているか ・KPI自体の見直しが必要ではないか |
| 改善施策の進捗 | ・計画した改善施策は実行されているか ・効果が出ている施策と出ていない施策はどれか |
| 組織内の活用状況 | ・関係者全員がマップを活用しているか ・マップの理解と活用を促進する必要はないか |
| 競合環境の変化 | ・競合の顧客体験に変化がないか ・自社の差別化ポイントは維持できているか |
これらのチェック項目を少なくとも四半期または半年ごとに確認し、必要に応じてマップを更新していきましょう。また、大きな環境変化(新技術の普及、競合の動き、規制変更など)があった場合は、臨時でレビューすることも重要です。
次のステップ:実践に向けて
カスタマージャーニーマップの作成と活用に向けた、具体的な次のステップを紹介します。以下の手順に従って、実践に移していきましょう。
- 目的と範囲の明確化
- マップ作成の具体的な目的を文書化する
- 対象とする商品・サービス、顧客セグメントを決定する
- 作成するマップのタイプ(マクロ型、ミクロ型、シナリオ型)を選択する
- 推進体制の構築
- マップ作成・活用の責任者を決める
- 関連部門からのメンバーを集めたチームを編成する
- 経営層の理解と支援を取り付ける
- データ収集計画の立案
- 既存データの棚卸しを行う
- 追加で必要なデータとその収集方法を決定する
- 顧客インタビューやアンケートの計画を立てる
- ワークショップの実施
- 関係者を集めたワークショップを企画する
- ペルソナ設定、ジャーニーマッピング、課題の特定などを実施する
- 部門間の認識すり合わせと合意形成を図る
- マップの作成と共有
- ワークショップの結果をもとにマップを作成する
- 関係者からのフィードバックを収集し、改善する
- 組織全体で参照・活用できる形で共有する
- 施策の立案と実行
- マップから得られた洞察をもとに改善施策を立案する
- 施策の優先順位づけと実行計画を作成する
- KPIを設定し、効果測定の仕組みを整える
- 継続的な改善サイクルの構築
- 定期的なレビューと更新のスケジュールを決める
- データ収集と分析の継続的な仕組みを整える
- 成功事例と学びを組織内で共有する体制を作る
これらのステップは、組織の規模や状況に合わせて調整してください。小規模な組織では、よりシンプルなプロセスから始めることも有効です。重要なのは、完璧を目指して先延ばしにするのではなく、まずは小さく始めて、徐々に改善していく姿勢です。
カスタマージャーニーマップは、顧客理解を深め、顧客体験を向上させるための非常に効果的なツールです。しかし、それ自体が目的ではなく、あくまでも顧客中心の組織文化と施策を実現するための手段であることを忘れないでください。
顧客の声に耳を傾け、顧客視点で考え、継続的に改善していく姿勢こそが、真の顧客体験向上につながります。カスタマージャーニーマップを活用して、顧客との長期的な信頼関係を構築し、ビジネスの持続的な成長を実現していきましょう。
最後に
本記事では、カスタマージャーニーマップの基本概念から作成方法、活用法、成功事例まで幅広く解説してきました。カスタマージャーニーマップは、顧客の行動や感情を可視化することで、顧客理解を深め、最適な体験を設計するための強力なツールです。
デジタル化の進展により顧客接点が多様化し、顧客体験の重要性が高まる中、カスタマージャーニーマップの価値はますます大きくなっています。正しい方法で作成・活用することで、顧客満足度の向上、顧客ロイヤルティの強化、ビジネス成果の向上につなげることができるでしょう。
ぜひ本記事の内容を参考に、自社のカスタマージャーニーマップ作成に取り組んでみてください。顧客視点で考え、データに基づき、継続的に改善していくプロセスが、真の顧客中心のビジネスへの第一歩となるはずです。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















