オーバーツーリズムの現状と対策:持続可能な観光地づくりの鍵とは?
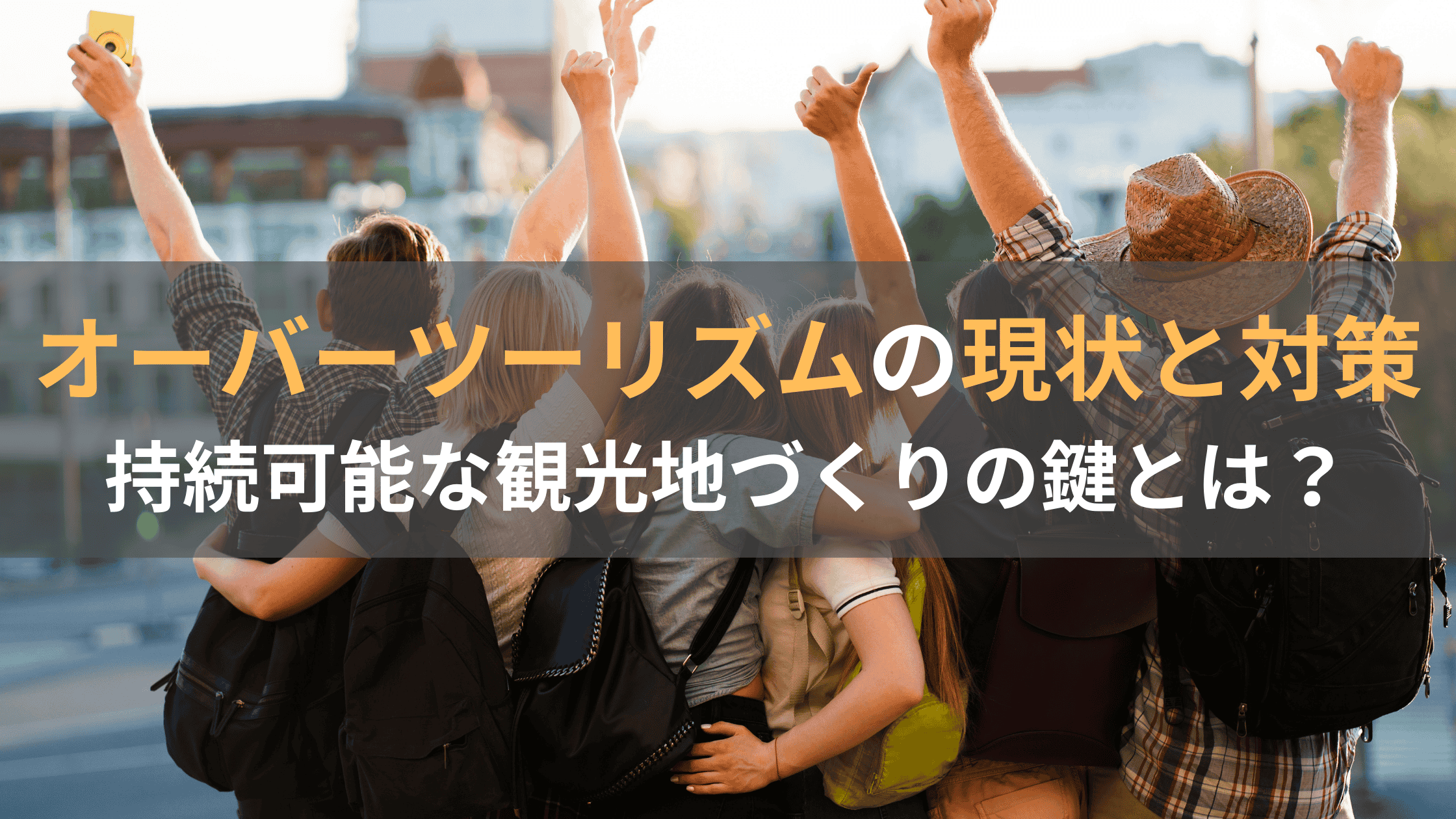
・オーバーツーリズムの現状と課題
観光客の過剰な集中により、住民の生活環境や観光資源が悪化。京都や鎌倉など日本各地で問題が再燃し、SNSやLCCの発展が観光地への集中を加速させている。
・各国・自治体の対策
観光客の分散や規制を強化。日本の観光庁は「持続可能な観光推進事業」を実施し、ベネチアでは入場料導入、京都では早朝拝観などの対策を実施。デジタル技術を活用した管理も進む。
・持続可能な観光の方向性
観光客数の増加より「滞在時間の延長と質の向上」を重視。地域主体の観光ビジョンや観光税導入、環境負荷軽減策を推進し、データを活用した改善を継続することが重要。
観光客の過度な集中により、地域住民の生活環境や観光体験の質が脅かされる「オーバーツーリズム」。コロナ禍からの回復に伴い、2024年から再び各地で顕在化しつつあるこの課題に、国内外の観光地が様々な対策を講じています。特に日本では、観光庁が「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」を本格始動させ、地域主体の取り組みを支援しています。本記事では、オーバーツーリズムの原因と影響を整理し、国内外の成功事例と最新支援制度を紹介しながら、観光と地域社会が共存できる持続可能な観光地づくりのためのフレームワークを解説します。
オーバーツーリズムとは:定義と現状

オーバーツーリズムの基本概念と定義
オーバーツーリズムとは、特定の観光地に観光客が過度に集中することで、地域住民の生活環境や観光客自身の観光体験に悪影響を与える現象です。2015年頃にアメリカの観光メディア「skift」が使い始めた造語で、日本語では「観光公害」とも呼ばれます。交通渋滞や騒音、ゴミ問題といった直接的な問題から、家賃高騰や地域住民向け商店の減少など長期的な影響まで含みます。
日本国内の現状と課題
日本では京都市、鎌倉市、白川村、宮島などでオーバーツーリズムが顕在化しています。京都では公共交通機関の混雑や舞妓さんの無断撮影問題、鎌倉市では観光客のゴミ問題や混雑が課題となっています。コロナ禍で一時沈静化していた問題も、2023年には訪日外国人旅行者数が2507万人まで回復し、2024年第1四半期にはパンデミック前の97%に達したことで再び顕在化しつつあります。
世界各国の状況と比較
世界的にはベネチア、バルセロナ、アムステルダムなどでオーバーツーリズムが深刻化しています。ベネチアではクルーズ船による一時的な人口集中や民泊増加による住民追い出し、バルセロナでは家賃高騰や生活環境悪化が問題となっています。アジアではバリ島やプーケットで水資源枯渇や環境破壊、南北アメリカではマチュピチュやイエローストーン国立公園で文化遺産・自然環境への負荷が懸念されています。どの地域も観光収入の経済的利益と地域環境保全のバランスが課題です。
オーバーツーリズムが発生する主な原因

観光市場の拡大とインバウンド需要
世界的な観光市場の急速な拡大がオーバーツーリズムの主因です。2019年には世界全体で14.7億人の国際観光客数を記録し、2010年から約1.5倍に成長しました。日本では2003年に521万人だった訪日外国人観光客が2019年には3188万人へと約6倍に増加。政策的な後押しもあり、一部の人気観光地への観光客集中が加速しています。
交通手段の多様化と旅行コストの低下
LCC(格安航空会社)の台頭により、海外旅行のハードルが大幅に下がりました。日本でもLCCが国内線旅客の15%、国際線の20%を占めています。また、ビザ要件の緩和も旅行を容易にし、現在では71の国・地域に対して短期滞在ビザが免除されています。これらの要因が観光客の増加と人気観光地への集中をもたらしています。
SNSの発達と情報拡散の影響
SNSの普及(世界のSNS利用者数は2022年時点で45.9億人)により、観光地情報の拡散方法が変化しました。「インスタ映え」を意識した投稿が観光客の行動に影響し、特定スポットへの集中を引き起こしています。また、一部の観光客はSNSでの「いいね」獲得のために危険な場所や立入禁止区域に侵入するなど、マナー違反も問題となっています。
民泊などの新たな宿泊形態の台頭
世界的に普及した「民泊」サービスは新たな宿泊選択肢を提供する一方、住宅地に観光客が入り込むことで騒音問題や治安不安を生んでいます。日本では2018年の住宅宿泊事業法施行により、住居専用地域でも一定条件下で民泊営業が可能になり、従来は観光客が滞在しなかった住宅地にも新たな課題が生じています。
観光政策と地域社会のミスマッチ
多くの国や自治体は経済効果を期待し観光客数の量的拡大を目標としてきました。日本でも「1千万人」達成後さらに目標を引き上げ、観光のマイナス面への対策が不十分なまま量的拡大を追求してきた側面があります。インフラ整備や規制導入の遅れも問題を悪化させました。近年は量より質を重視する観光政策への転換が進みつつあります。
オーバーツーリズムがもたらす影響と課題

地域住民の生活環境への直接的影響
オーバーツーリズムの最も顕著な問題は地域住民の日常生活への影響です。公共交通機関の混雑や道路渋滞、観光客による深夜の騒音や早朝のスーツケース音、ゴミのポイ捨てなどが住民の生活環境を悪化させています。鎌倉市などでは観光客が住宅地に立ち入り写真撮影するプライバシー侵害も問題となっており、地域住民の観光に対する反感を生む原因となっています。
観光資源の劣化と持続可能性の危機
観光の対象となる文化遺産や自然環境も過度な観光圧力によって損なわれる危険性があります。寺社仏閣や伝統的街並みは本来、宗教施設や居住空間であり「観光のため」のものではありません。観光客の集中はこれらの資源に物理的負荷をかけるだけでなく、宗教施設の静寂さや伝統的街並みの風情など本質的価値を損なう「価値の逆説」を生じさせるリスクがあります。
地域経済と産業構造への長期的影響
観光客増加に伴い、地域住民向け店舗が観光客向け店舗に置き換わり、地域の個性が失われる「商店街の画一化」が進行します。さらに地域外資本の参入で観光収益の地域外流出も起こります。観光に過度に依存した経済構造は外的要因に弱く、2020年のコロナ禍では観光依存度の高い地域が大きな経済的打撃を受けました。地域経済の多様性喪失はリスクへの脆弱性を高めます。
地域文化・アイデンティティの変容
観光客の嗜好に合わせて地域文化や伝統が変質する「文化の商品化」も重要課題です。本来、地域文化や祭りは住民のアイデンティティ表現ですが、観光客向けに簡略化・定型化されることで本質的価値が失われる恐れがあります。また、地域の「テーマパーク化」は住民の地域への愛着や誇りを損ない、地域住民の流出やコミュニティ崩壊につながりかねない問題です。
環境負荷の増大と生態系への影響
観光客増加はエネルギー消費、水資源の過剰利用、廃棄物増加、CO2排出など環境への負荷を増大させます。特に水資源乏しい地域では観光施設の大量水消費が地下水位低下を招き、農業や生活用水にも影響します。沖縄県西表島では世界自然遺産登録に伴う観光客増で希少生態系への負荷が懸念され、プーケットなどではサンゴ礁損傷や海洋ゴミ増加が問題となっています。環境への配慮を欠いた観光開発は、結果として観光資源そのものを破壊しかねません。
持続可能な観光に向けた対策フレームワーク

観光客のマネジメント戦略
オーバーツーリズム対策の第一の柱は観光客の流れをコントロールするマネジメント戦略です。中心となるのが観光客の時間的・空間的分散を図る取り組みです。京都市では朝観光推奨や清水寺の早朝特別拝観実施、複数ルート提案や新たな観光スポット開発などで集中緩和を図っています。また、地域のルールや文化背景を多言語で伝えるマナー啓発も重要ですが、禁止事項羅列ではなくポジティブな表現で観光客の協力を促す工夫が必要です。
産業・事業者のマネジメント方針
観光産業や事業者へのマネジメントもオーバーツーリズム対策の重要要素です。法制度や条例による規制(民泊営業日数制限、区域制限など)、都市計画法や建築基準法の活用(銀座のカプセルホテル規制など)、地域合意に基づく自主ルール(金沢東茶屋街の「金沢ゆかりの物品」販売制限など)を組み合わせることで、地域の個性や魅力を保全し観光地としての価値を維持できます。
地域主導型の観光ビジョン構築
対策の根幹は地域主体で観光将来像を描き、実現に向けて取り組む姿勢です。観光振興を通じて目指す地域像や望ましい観光のあり方について、関係者間で合意形成することが重要です。西表島では環境容量を踏まえた具体的数値目標(年間33万人・1日1,200人上限)を設定。また地域の食材・工芸品活用促進や地元事業者連携強化など、観光収益の地域内循環の仕組みづくりも重要です。
デジタル技術の活用と革新的アプローチ
AI、IoT、ビッグデータ解析などの先端技術活用はオーバーツーリズム対策に新たな可能性をもたらします。鎌倉市の「鎌倉観光混雑マップ」や京都市の「京都観光Navi」などのアプリは混雑状況をリアルタイム可視化し、観光客の分散と満足度向上に貢献しています。また、VR/ARなどを活用した新たな観光体験創出も、物理的観光圧力軽減と体験多様化・質向上を実現する革新的アプローチとして期待されています。
国際基準と持続可能な観光指標
持続可能な観光地づくりには国際的基準や指標活用も有効です。UNWTO(国連世界観光機関)の持続可能な観光の定義や、GSTC(持続可能な観光地のためのグローバル基準)などの国際的フレームワークが参考になります。日本でも観光庁が2020年に「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」を公表。これらの指標活用で体系的な持続可能な観光地づくりが可能になり、国際認証取得による観光地ブランディングにもつながります。
最新支援制度:観光庁の持続可能な観光推進事業2025

事業概要と背景(オーバーツーリズム未然防止・抑制)
観光庁は2025年度の「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」の公募を開始しました(2025年2月17日〜3月14日12:00受付)。この事業は観光客の過度な混雑問題に対し、地域主体の具体的取り組みを総合的に支援するもので、観光客受入と住民生活の質確保の両立を目指します。対象は既に課題が発生している地域だけでなく、今後問題発生が想定される地域も含まれています。観光庁は2018年の「持続可能な観光推進本部」設置、2020年の「日本版持続可能な観光ガイドライン」公表に続き、本事業で地域主体の実践的取り組みをさらに後押しします。
「地域一体型」支援の詳細と申請要件
2025年度支援事業の「地域一体型」は、地方公共団体またはDMO(観光地域づくり法人)が申請主体となる事業を対象とします。前年度の「先駆モデル地域型」からDMOも申請主体に加わった点が変更点です。最大の特徴は地域関係者による協議の場の設置と協議に基づく対策計画策定を要件としている点で、申請主体を中心とした協議会設置または地域住民を含む関係者との個別協議実施が必要です。対策計画策定と実施には事務局による伴走支援も提供され、補助上限額は8000万円です。
「実証・個別型」支援の内容と活用方法
もう一つの類型「実証・個別型」は前年度の「一般型」に相当し、地方公共団体、DMOまたは民間事業者などが実施する具体的取り組みを支援します。包括的な協議プロセスや計画策定は必須ではなく、より柔軟で機動的な取り組みが対象です。受入環境整備・増強、需要管理、需要平準化、マナー違反防止・抑制、地域住民と協働した観光振興といった課題タイプのうち一つまたは複数に係る取り組みが対象となり、補助率は対象経費の1/2、補助上限額は5000万円です。
効果的な申請書作成と審査のポイント
採択を目指す上で重要なのが効果的な申請書作成です。「地域一体型」では協議の場における多様な関係者(特に地域住民)の参画と、単年度事業ではなく継続的な議論・連携体制が評価されます。両類型共通の審査ポイントは、現状把握の適切さ、具体的で効果的な計画性、適切なKGI・KPI設定、実施体制の適切さと実現可能性です。特に定量的データに基づく現状分析と課題抽出、測定可能な成果指標設定が高く評価されます。
採択後の実施体制と成果最大化のコツ
事業成功の鍵は効果的な実施体制構築とPDCAサイクルに基づく継続的改善です。関係者の役割分担明確化と定期的進捗管理、協議会などを活用した情報共有・意思決定プロセス確立が重要です。収集データを活用した定期的なKPI進捗評価と計画の柔軟な修正も必要です。補助事業終了後の継続性も視野に、観光税や入場料など独自の財源確保、地域内多様な主体による自律的推進体制構築を検討すべきです。事業は交付決定以後に着手し2026年2月27日12:00までに完了が必要で、事前準備と効率的なスケジュール構築も成功の重要要素です。
オーバーツーリズム対策の実践ステップ

現状分析と課題の明確化手法
オーバーツーリズム対策の第一歩は地域の現状把握と課題明確化です。観光客の実態把握(訪問時期・時間帯、滞在時間、訪問場所、移動手段、消費行動など)を観光統計、モバイル位置情報、交通機関利用データなどから多角的に行います。同時に地域への影響評価として、経済効果(雇用創出、所得増加)、環境負荷(ゴミ量、水使用量、騒音レベル)、社会的影響(住民生活満足度、家賃動向)を定量的に把握し、特に住民アンケート・ヒアリングを通じて実際の影響や懸念を詳細に調査します。これらのデータをSWOT分析などで体系的に整理し、オーバーツーリズムの段階と最優先課題を特定します。観光客だけでなく地域住民、事業者、行政など多様な視点を取り入れることが重要です。
多様な関係者を巻き込む協議体制の構築
効果的なオーバーツーリズム対策には多様な関係者が参画する協議体制構築が不可欠です。行政や観光事業者だけでなく、地域住民、交通事業者、商工業者、文化財管理者、環境保全団体など幅広いステークホルダーを巻き込みます。参加者は観光の影響を受ける地域全体をカバーし、年齢層や職業、居住地域の偏りがないよう配慮します。協議の場は公式協議会だけでなく、ワークショップ、タウンミーティング、オンライン討論など多様な形式を組み合わせ、透明性確保のために議事録公開や進捗状況の定期報告も行います。観光振興派と規制強化派の利害対立や短期的経済利益と長期的地域持続性のバランスなど、対立意見調整には客観的データや専門家知見を活用した建設的議論が重要です。最終的に地域全体で共有できるビジョンと目標を設定し、役割分担と協力体制を構築することを目指します。
効果的な対策計画の立案プロセス
現状分析と多様な関係者による協議をもとに具体的対策計画を立案します。まず基本方針と目標を明確に設定し、「観光と地域生活の調和」「観光の質的向上と経済効果最大化」など持続可能な観光地づくりの視点を含む複合的目標を定めます。次に具体的施策を観光客マネジメント、産業・事業者マネジメント、地域主導型ビジョン構築、デジタル技術活用などの枠組みに沿って多角的に検討します。効果の大きさ、実現可能性、コスト、実施期間を評価し、短期的「クイックウィン」と中長期的取り組みを区分けした優先順位をつけます。各施策の実施主体、スケジュール、必要予算、財源確保方法を具体的に定めた実行計画を策定し、関係者の役割分担と責任の所在を明確にします。また感染症流行や自然災害、国際情勢変化などの不確実性に対応できる柔軟性を持たせ、複数シナリオを想定した計画づくりも重要です。
KPIの設定とモニタリングシステムの確立
オーバーツーリズム対策の効果測定と継続的改善には適切なKPI設定とモニタリングシステム確立が不可欠です。目標(KGI)を明確にした上で、その達成度を測る具体的指標を選定します。観光客の分散状況(時間帯別混雑度、エリア別観光客数比率)、観光の質(満足度、リピート率、滞在時間、消費額)、地域社会への影響(住民生活満足度、騒音・ゴミ苦情件数、住宅価格動向)、経済効果(消費額、地域内調達率、雇用数)、環境への影響(CO2排出量、水使用量、廃棄物量)など多面的指標を組み合わせます。これらを定期測定するモニタリングシステムを確立し、統計調査に加えビッグデータやIoT技術を活用したリアルタイムモニタリングも取り入れます。結果は定期的に関係者間で共有し、施策効果検証と改善に活用します。また、混雑状況のリアルタイム可視化や環境負荷の変化を図示するなど、結果を地域住民や観光客にわかりやすく公開することで、取り組みの透明性向上と協力獲得にもつながります。
PDCAサイクルによる継続的改善
オーバーツーリズム対策は一度実施して終わりではなく、環境変化や施策効果を踏まえて継続的に改善することが重要です。Plan(計画)段階では現状分析、協議体制構築、対策計画立案を行います。Do(実行)段階では関係者間の連携と役割分担を明確にし、円滑な実施体制で計画を実行します。Check(評価)段階ではKPIに基づいて効果を測定・分析し、定量的データと定性的フィードバックから多角的評価を行います。特に想定通りの効果が得られなかった施策はその原因を深く分析します。Act(改善)段階では評価結果をもとに次のアクションを決定し、効果の高い施策は強化・拡大、不十分な施策は見直し改善します。状況変化で目標自体の見直しが必要な場合もあります。このPDCAサイクルを定期的(年度ごとなど)に繰り返すことで、変化する状況に柔軟に対応しながらより効果的な対策を実現できます。観光は季節変動や社会経済状況の影響を受けやすいため、固定的計画ではなく継続的改善プロセスが成功の鍵です。
自治体・DMOのためのオーバーツーリズム対策ロードマップ

地域の観光キャパシティ評価の方法
オーバーツーリズム対策の出発点は「観光キャパシティ(収容力)」の多角的評価です。物理的側面(観光スポットの空間的制約、交通・宿泊インフラの容量)、環境的側面(水資源・廃棄物処理能力と観光負荷の関係)、社会的側面(住民の観光に対する許容度、生活への影響度)、経済的側面(観光依存度、収益の地域内循環率)から総合的に判断します。これらをもとに「1日あたりの推奨観光客数」「特定スポットの収容可能人数」など、具体的な指標を設定し活用します。
住民参加型の観光マネジメント組織構築
持続可能な観光地づくりには、多様なステークホルダーが参画する観光マネジメント組織が不可欠です。観光事業者や行政だけでなく、地域住民、商工業者、教育機関など幅広い関係者を巻き込み、情報公開と公正な意思決定プロセスを確保します。この組織が観光計画策定、対策実施、ルール作りなどの中核を担い、観光と地域生活の調和を図ります。財源は観光税・入場料の一部、会費、補助金、自主事業収入など多様な財源を組み合わせることが望ましいでしょう。
観光客の行動変容を促す効果的アプローチ
観光客の自発的な協力を引き出すには、行動経済学の「ナッジ」手法が効果的です。社会的規範を伝えるメッセージや混雑情報の可視化提供で、望ましい行動を促します。旅行前からの地域ルール・文化背景の多言語での情報提供も重要です。体験設計では地域住民との交流や環境保全活動参加など「責任ある観光」要素を取り入れ、オフピーク時訪問への割引など経済的インセンティブも活用します。コミュニケーションでは禁止・規制よりも、地域文化・環境尊重で得られるポジティブな体験を強調することが効果的です。
地域ブランディングと質の高い観光体験設計
オーバーツーリズム対策は単なる観光客数制限ではなく、質の高い観光体験提供への転換です。地域の独自性(歴史、自然、文化など)を明確化し、その価値観や魅力に共感する「望ましい観光客層」をターゲットにします。単に「見る」観光から五感を使って「体験する」観光へと進化させ、滞在時間延長や消費単価向上を図ります。ARやVRなどデジタル技術を活用した新たな体験創出も、観光の質的向上に有効です。
持続可能な財源確保の仕組みづくり
継続的な取り組みには安定的な財源確保が不可欠です。観光税・入域料の導入、これまで無料だった観光資源の適切な有料化、官民連携による資金調達(ネーミングライツ、クラウドファンディング、企業版ふるさと納税など)、組織自体の収益事業(物販、体験プログラム運営など)を組み合わせます。財源確保の仕組みは、観光収益が地域全体に広く還元される設計にすることで、持続可能な観光への地域の支持と協力を得られます。
まとめ:持続可能な観光地づくりのこれから

オーバーツーリズム対策の核心は、地域主導・住民参加の原則に基づく多様なステークホルダーの共有ビジョン形成にあります。観光客分散、産業規制、観光税導入、デジタル技術活用などの多角的アプローチを組み合わせ、単なる観光客数増加から滞在時間延長や消費額向上など質重視への転換が求められています。これらの取り組みにはデータに基づくモニタリングと外的ショックへの回復力構築の長期的視点が不可欠です。
今後の観光トレンドとしては、個人の興味関心に基づく多様な体験を求める個別化・パーソナライズ化の進展、環境・社会配慮型観光への関心拡大、VR/ARなどによるデジタルとリアルの融合体験、ワーケーションなど地域に溶け込む長期滞在型観光の増加、そして様々なリスクへの対応力が観光地選択の重要要素となっています。
実践ステップとしては、短期的(3〜6ヶ月)な現状把握と協議体制構築、中期的(6ヶ月〜1年)な観光ビジョン策定と分散施策実施、長期的(1〜3年)な地域ブランディング戦略展開と条例制定など、段階的アプローチが効果的です。オーバーツーリズム対策は単なる観光客数制限ではなく、地域と観光の共存共栄を実現する包括的アプローチです。2025年、観光庁の支援事業を活用しながら、各地域が持続可能な観光地づくりに向けた一歩を踏み出す好機といえるでしょう。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















