デジタルマーケティング企業20選|失敗しない選び方と費用相場を徹底解説


- デジタルマーケティング企業は、戦略立案から実行、効果測定まで一気通貫でサポートし、急速に変化する顧客行動への対応や専門人材不足を解決します
- 企業選びでは、自社の目標とのマッチング度、実績と専門性、費用対効果、企業規模に応じた支援タイプ、サポート体制の5つの基準が重要です
- 目的別に厳選した20社を紹介し、総合力の大手企業からSEO・広告・SNS・データ分析に強い企業、中小企業向けまで幅広く網羅しています
- 費用相場は施策によって異なり、SEO対策は月額10万円から50万円、広告運用は広告費の15%から20%が手数料の目安となります
- 契約前のチェックリスト活用と、目標設定の明確化、丸投げの回避、定期的なコミュニケーションが成功の鍵となります
この記事では、デジタルマーケティング企業を選ぶ際に実際に使える判断基準を整理したうえで、目的別のおすすめ20社・費用相場・よくある失敗パターンと回避策を具体的に解説します。「いい企業を選んだはずなのに成果が出ない」という状況を防ぐために、契約前に確認すべきことも含めて網羅しています。
デジタルマーケティング企業とは?2025年の最新動向

デジタルマーケティング支援企業の役割と提供価値
デジタルマーケティング企業とは、デジタル技術とデータを使って企業のマーケティング活動を包括的に支援する専門会社です。単なる広告代理店との大きな違いは、戦略立案から施策実行・効果測定・改善提案まで一貫して担う点にあります。
具体的なサービスとしては、SEO対策やコンテンツマーケティング、リスティング広告・SNS広告の運用、マーケティングオートメーション(MA)ツールの導入支援、データ分析に基づく戦略設計など多岐にわたります。これらを社内で一から整えようとすると、人材採用・育成・ツール整備に1年以上かかるケースも珍しくありません。支援企業を活用すれば、各領域の専門家チームに即日アクセスできる点が最大の利点です。
また、デジタルマーケティングの支援を続ける中で自社にもノウハウが蓄積されていくため、将来的な内製化への布石にもなります。
Webマーケティングとの違いと包括的アプローチ
Webマーケティングとデジタルマーケティングは混同されやすいですが、対象範囲が異なります。Webマーケティングはサイトやオンライン施策に特化した概念です。デジタルマーケティングはその上位概念で、デジタルサイネージ・IoTデバイス・実店舗のデジタル接点など、あらゆるデジタルチャネルを統合的に扱います。
実務上の強みは、オンラインとオフラインをまたいだ顧客体験の設計です。オンライン広告で興味を持った顧客を実店舗に誘導し、購買データを次のオンライン施策に還元する、といったループを回せるようになります。顧客データの統合管理によってカスタマージャーニー全体が可視化され、各タッチポイントでの施策精度が上がります。
2025年注目のトレンド:AI活用と統合型マーケティング
2024年の国内デジタルマーケティング市場規模は3,672億円で、2025年は前年比14.1%増の4,190億円に達する見込み Dreamnewsです(矢野経済研究所調べ)。市場拡大の主な背景は、AIを活用したツールの多機能化と、それに伴う導入企業の広がりにあります。
2025年の現場で起きている変化で特に大きいのは、生成AIの業務組み込みです。広告クリエイティブの自動生成、コンテンツ制作の高速化、顧客対応の自動化など、これまで人手をかけていた工程がAIで代替されつつあります。施策の実行スピードが上がった分、「何を・誰に・どう届けるか」という戦略判断の精度がより問われるようになっています。
もう一つの大きな変化はプライバシー規制への対応です。サードパーティクッキーの廃止に向けた動きが続く中、自社で収集したファーストパーティデータをどう活用するかが企業の競争力を左右します。支援企業を選ぶ際、この領域の対応力を確認することが重要な判断基準の一つになっています。

デジタルマーケティング企業が必要とされる3つの理由

急速に変化する顧客行動への対応
スマートフォンが普及し、消費者は常時オンラインで情報収集しています。SNSの口コミ、短尺動画、ライブコマースなど、顧客の購買に影響するチャネルはここ数年で大幅に増えました。こうした変化を追い続けながら自社で施策を回すのは、専任チームを抱える大企業でも難しい状況です。
デジタルマーケティング企業は複数社の支援を通じて最新の消費者行動を常時観測しており、「今どのチャネルに投資すべきか」という判断を根拠を持って提示できます。Z世代向けのTikTok施策、シニア層向けのLINE活用など、ターゲットセグメントによってアプローチが異なる設計を、内製と比べて短期間で実装できる点が実務上の強みです。
専門人材不足とノウハウの獲得
デジタルマーケティングに必要なスキルセットは広範です。SEOの技術的知識、広告運用のノウハウ、データ分析、コンテンツ制作、MAツールの操作など、一人の担当者が全領域を習得するのは現実的ではありません。しかもこれらのスキルは常にアップデートが必要で、キャッチアップだけで相当な時間を要します。
自社でデジタルマーケティング部門を立ち上げる場合、採用から実戦力になるまで最低でも半年から1年はかかります。その間、競合他社との差が開くリスクも無視できません。支援企業を活用すれば、SEO・広告・データ分析それぞれの専門家チームに即日アクセスでき、過去の成功・失敗から蓄積されたノウハウを最初から利用できます。
費用対効果の最大化とリスク軽減
知識や経験が不足した状態でデジタルマーケティングを始めると、無駄なコストが積み上がります。効果の薄い広告への継続的な出稿、SEO効果の出ないコンテンツの大量制作、ツール導入後の活用不足——こうした失敗は自社運用でよく見られます。
デジタルマーケティング企業はデータに基づいたアプローチで投資配分を最適化します。広告運用ではA/Bテストを繰り返してCPA(顧客獲得単価)を下げ、成果の出ているチャネルに予算を集中させます。リスク管理の面では、Googleのアルゴリズム変更・SNSの炎上・プライバシー規制への対応など、事前に察知して対策を打てる体制があります。
失敗しない企業選びの5つの基準

自社の目標・課題とのマッチング度
まず決めるべきは「何を達成したいか」です。新規顧客の獲得、既存顧客のリピート率向上、ブランド認知の拡大では、適した支援企業が変わります。目標が曖昧なまま発注すると、成果の判断基準そのものがなくなり、「なんとなく続ける」か「なんとなく解約する」かしかなくなります。
目標を決めたら、その企業が自社の業界・事業モデルに精通しているかを確認します。BtoBとBtoCでは求められる施策が異なり、EC事業と店舗ビジネスでもアプローチは変わります。自社と似た業種・規模の支援実績があれば、業界固有の課題に対して具体的な提案が期待できます。
支援範囲の確認も欠かせません。戦略立案のみか、実行まで含めるか、内製化支援もセットか。社内にある程度リソースがあればコンサルティング特化の企業が合いますし、人手不足で実作業を任せたいなら実行支援に強い企業を選ぶべきです。
実績と専門性の適切な評価方法
「導入企業数〇〇社」「売上〇〇億円」といった表面的な数字よりも、具体的な成果内容を確認することが重要です。「リード獲得数が3ヶ月で2.5倍になった」「CPAが40%改善した」「オーガニック検索流入が6ヶ月で150%増加した」といった数値が示されている事例は、実力の判断材料として信頼できます。
GoogleのPremier PartnerやYahoo!マーケティングソリューションの上位パートナー認定など、プラットフォーム側の公式認定も参考になります。ただし認定の有無だけでなく、実際に担当するメンバーの経験年数・チーム体制・使用ツールまで確認することで、より実態に近い評価ができます。
費用対効果を見極める予算設定
費用体系はサービスによって大きく異なります。戦略コンサルティングは月額10〜100万円以上、広告運用代行は広告費の20%程度、SEO対策は月額10〜50万円、コンテンツ制作は1記事3〜10万円程度が目安です。
予算を設定する際は、初期費用と月額費用を合算した年間総額で考えます。月額30万円のサービスであれば年間360万円、初期費用30万円を加えると初年度は390万円の投資になります。最低契約期間が設定されている場合が多いため、この計算は必須です。
初めて外注する場合は、まず単一施策(例:SEOのみ)を3〜6ヶ月試し、成果を確認してから追加施策を依頼するというステップアプローチが失敗を減らします。
企業規模別の最適な支援会社タイプ
スタートアップ・小規模企業には、柔軟な対応と費用効率に優れた中小規模のマーケティング会社や特定領域の専門企業が適しています。予算の制約が厳しい分、優先施策に集中投資できる提案力を重視してください。
中堅企業は複数チャネルを横断した施策が必要になるため、SEO・広告・SNSを横断して対応できる企業が向いています。社内マーケターとの協業がスムーズかどうかも重要な選定基準です。
大企業は、複雑な組織構造・承認プロセスへの対応力と豊富な実績が求められます。電通デジタルやサイバーエージェントなどの大手は最低契約金額が高めに設定されているケースが多いため、予算規模とのバランスも確認が必要です。医療・不動産・金融など規制が厳しい業界では、企業規模に関わらず業界特化の支援企業を選ぶほうが現実的なケースもあります。
サポート体制とコミュニケーション品質
デジタルマーケティングはPDCAを繰り返す性質上、担当者とのコミュニケーション品質が成果に直結します。週次または隔週の定例ミーティング、月次での詳細レポート提出——この程度の頻度が確保されているかを、契約前に確認してください。
専任担当者制かチーム体制かも確認すべきポイントです。専任制は自社理解が深まる反面、担当者の力量に依存するリスクがあります。チーム体制は各領域の専門家が関わる分、施策の質は安定しますが、窓口が複数になる可能性があります。
問い合わせへの返答が24時間以内にあるか、提案内容の具体性、質問への理解度——これらは初回商談の段階で既に確認できます。契約前のやり取りが雑な企業は、契約後も同じです。
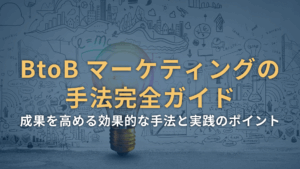
【目的別】厳選デジタルマーケティング企業20社

まず、20社の全体像を一覧表で確認してください。その後、各カテゴリの詳細を解説します。 <!– image: デジタルマーケティング企業20社比較表 / alt: デジタルマーケティング企業20社の目的別比較表 –>
| 企業名 | 得意領域 | 対象規模 | 費用感 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 電通デジタル | 総合・DX推進 | 大企業 | 高め | グループデータ活用・組織変革まで対応 |
| サイバーエージェント | 動画・SNS広告 | 中〜大 | 中〜高 | ABEMAデータ活用・クリエイティブ強い |
| アイレップ | 運用型広告・統合マーケ | 中〜大 | 中〜高 | Google Premier Partner 最優秀賞受賞 |
| オプト | 広告×AI | 中〜大 | 中 | 生成AI活用ツール「CRAIS」独自開発 |
| トランスコスモス | 総合・オフライン連携 | 中〜大 | 中 | 3,000社超の実績・32カ国展開 |
| ウィルゲート | SEO・コンテンツ | 中小〜中堅 | 中 | 自社SEOツール「TACT SEO」提供 |
| ナイル | SEO・コンテンツ | 中小〜中堅 | 中 | 複数自社メディア運営の実践知識 |
| MOLTS | コンテンツ・データ分析 | 中小〜中堅 | 中 | 数値重視・リード獲得実績豊富 |
| D2C R | 広告・データ | 中〜大 | 中 | ドコモデータ活用・効果測定に強み |
| DAC | 広告・海外展開 | 中〜大 | 中〜高 | アジア圏のグローバル展開対応 |
| アドウェイズ | アフィリエイト・SNS | 中〜大 | 中 | アジアでのグローバル展開対応 |
| スパイスボックス | SNS・インサイト分析 | 中〜大 | 中 | 1,000万超SNSユーザーデータ保有 |
| ガイアックス | SNS運用・炎上対策 | 中小〜大 | 中 | SNS運用代行10年・1,000社超実績 |
| メンバーズ | SNS・デジタルクリエイティブ | 中〜大 | 中 | 複数SNS一括運用・クリエイティブ強 |
| マクロミル | 市場調査・データ分析 | 中〜大 | 中〜高 | 国内最大級パネル・90カ国対応 |
| Speee | MAツール・DX | 中〜大 | 中 | 自社メディアで培った実践データ活用 |
| グローバルウェイ | MA・Salesforce連携 | 中〜大 | 中 | Salesforce Expert認定・MA導入特化 |
| LIG | コンテンツ・デザイン | 中小・スタートアップ | 低〜中 | Webデザイン受賞歴・コスト効率高 |
| ベーシック | BtoB・MA・Web制作 | 中小〜中堅 | 低〜中 | 自社ツール「ferret One」提供 |
| インフォバーン | コンテンツ・ブランディング | 中小・スタートアップ | 低〜中 | 出版ルーツの編集力・コンテンツ品質高 |
総合力で選ぶ大手企業5選
株式会社電通デジタル
電通グループの膨大な広告データと独自フレームワーク「People Driven Marketing」を組み合わせた、個人単位でのマーケティング実現が強みです。戦略立案から実行・運用まで一貫しており、組織変革やDX推進を含む大規模プロジェクトの実績が豊富です。初期費用は高めですが、確実な成果が求められる大企業向けの選択肢として国内トップクラスの実力を持ちます。
こんな企業に向いている: 年商50億円以上・社内に専任マーケチームがあり、DXも含めた包括的な変革を求める大企業
株式会社サイバーエージェント
ABEMA運営で蓄積した動画コンテンツとユーザーデータを広告施策に活かせる点が他社にない強みです。GoogleやYahoo!から最高ランクの認定を受けており、特にBtoC企業の新規顧客獲得施策での実績が豊富です。クリエイティブ制作から広告配信まで内製できる体制が整っています。
こんな企業に向いている: 動画・SNS広告に注力したい・BtoC消費財・サービス業
株式会社アイレップ
博報堂DYグループとして、Google Premier Partner Awardsで国内最優秀賞を複数回受賞しています。運用型広告とSEM領域の専門性が特に高く、データに基づいた高精度な広告運用とPDCAに特化した専門チームによる継続的な改善が特徴です。中堅企業から大企業まで対応しています。
こんな企業に向いている: 広告ROIを徹底改善したい・検索広告・ディスプレイ広告の運用を任せたい中〜大企業
株式会社オプト
インターネット広告代理事業を基盤に、生成AIを使った広告クリエイティブ制作ツール「CRAIS for Text」を自社開発するなど、最新テクノロジーの実装速度が速い企業です。データを活かした広告戦略とマーケティング分析の組み合わせが強みで、AI活用に前向きな企業との相性が良い選択肢です。
こんな企業に向いている: AI活用を前提にマーケ効率を上げたい・デジタル全チャネル対応が必要な中〜大企業
トランスコスモス株式会社
3,000社超の取引実績と32カ国展開のグローバル体制を持ちます。デジタルマーケティングにBPO(業務プロセスアウトソーシング)やコールセンター事業を組み合わせられる点が他社にない強みで、オンライン・オフラインを統合した顧客接点管理が必要な企業に適しています。
こんな企業に向いている: カスタマーサポートとマーケティングを統合管理したい・アジア展開を見越した施策が必要な企業
SEO・コンテンツマーケティングに強い企業3選
株式会社ウィルゲート
自社開発のSEOツール「TACT SEO」を提供しており、キーワード調査から検索上位表示のための分析・改善提案まで自社ツールで完結できます。戦略支援・実行支援・分析支援の3ラインで企業フェーズに応じた支援が可能で、継続的なコンテンツ制作にも対応しています。
こんな企業に向いている: オーガニック流入を体系的に伸ばしたい・自社ツールを使いながら支援も受けたい中小〜中堅企業
ナイル株式会社
複数の自社メディア運営で蓄積した実践的なSEOノウハウが強みです。戦略策定からコンテンツ制作まで一貫対応し、ターゲット・コンセプト設計の段階から丁寧に関与します。運用後の分析と改善提案も継続して行うため、中長期で着実にオーガニック流入を積み上げたい企業に向いています。
こんな企業に向いている: コンテンツマーケティングを本格化させたい・質の高い記事制作と戦略を両立させたい中小〜中堅企業
株式会社MOLTS
コンテンツマーケティングとデータ分析の組み合わせに強く、数値に基づいた成果創出にこだわる社風です。複数の企業でリード獲得数を数倍に増加させた成功事例があり、データ計測基盤の構築から支援します。「やってみる」ではなく「成果を出す」ことを前提に動ける企業との相性が良い選択肢です。
こんな企業に向いている: リード獲得数の具体的な改善を求めるBtoB企業・データドリブンな施策運用を重視する中小〜中堅企業
広告運用に強い企業3選
株式会社D2C R
NTTドコモと電通の共同出資で、ドコモが保有するデータを活用したリサーチ・ビッグデータ分析が得意です。SNSや屋外広告など複数媒体のコミュニケーション戦略立案から効果測定まで対応し、GA4などの計測ツール活用サポートも手厚く、広告運用の内製経験が少ない企業でも安心して任せられます。
こんな企業に向いている: 初めて本格的な広告運用に取り組む・若年層向けのデジタル広告施策を強化したい中〜大企業
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(DAC)
国内外のインターネット広告企業とのネットワークを持ち、マスメディアとデジタルメディアを横断した投資効果最大化の提案が得意です。アジア圏での現地企業パートナーシップを活かしたグローバルなプロモーション戦略にも対応しており、海外展開を視野に入れた広告施策が必要な企業に適しています。
こんな企業に向いている: マスとデジタルを統合したプロモーションが必要・アジア圏への海外展開を検討している中〜大企業
株式会社アドウェイズ
アフィリエイト広告を中心に、ライブコマース・SNSマーケティングまで包括的に対応します。アジアを中心にグローバル展開しており、SmartNews Ads パートナー・Twitter認定パートナーなど各種プラットフォームの公式認定も取得。アプリ開発との相乗効果も強みで、モバイルファーストの施策展開に向いています。
こんな企業に向いている: アフィリエイト広告を活用したい・アジア市場への展開を見据えた広告施策が必要な企業
SNSマーケティングに強い企業3選
株式会社スパイスボックス
博報堂グループとして、1,000万人超のSNSユーザープロファイリングデータを保有しています。データに基づいたインサイト起点のマーケティング推進が強みで、エンゲージメントを高めるコンテンツ戦略の設計から広告運用まで一貫対応します。TikTok・Instagramなどでの若年層向け施策の実績が豊富です。
こんな企業に向いている: 若年層・Z世代へのブランドコミュニケーションを強化したいBtoC企業
ガイアックス株式会社
SNS運用代行歴10年以上・累計1,000社超の支援実績を誇り、炎上リスク対策や危機管理サポートが充実している点が特徴です。戦略設計・運用・内製化支援・コンサルティングまで幅広くカバーし、コンバージョン獲得まで見据えた支援を行います。BtoB企業のSNS活用支援実績も持つ、実績重視の選択肢です。
こんな企業に向いている: SNS運用を初めて本格化させたい・炎上リスクを最小化しながら安定した運用を求める企業
株式会社メンバーズ
Facebook・Instagram・X(旧Twitter)・YouTubeなど複数のSNSを一括依頼できます。専門性の高いデジタルクリエイターによる専任チームを組成し、SNS立ち上げから運用・分析・改善提案まで対応します。デジタルクリエイティブに強みがあり、企業Webサイトの構築・運用との連携も可能です。
こんな企業に向いている: 複数SNSをまとめて一社に任せたい・クリエイティブ品質を落とさず運用したい中〜大企業
データ分析・マーケティングオートメーションに強い企業3選
株式会社マクロミル
国内最大級のパネルを保有する業界首位のマーケティングリサーチ会社です。オンラインアンケートから対面インタビューまで多様な調査手法に対応し、90カ国以上の海外調査も可能です。施策の根拠となる顧客・市場理解を深めるフェーズ、つまり「何をやるか決める前の調査」で特に力を発揮します。
こんな企業に向いている: 新商品・新規事業の市場検証をしたい・施策の前提となる顧客理解が不足している中〜大企業
株式会社Speee
自社で運営する「イエウール」(不動産査定)や「ケアスル介護」などのサービスから得た実践データを活用したマーケティング支援が強みです。マーケティングインテリジェンスとDXを軸に据え、データプラットフォームを東南アジア圏でも展開しています。自社サービスで実証済みのノウハウを移植できる点が差別化ポイントです。
こんな企業に向いている: データドリブンなマーケティング基盤を構築したい・グローバル展開も見据えた中〜大企業
株式会社グローバルウェイ
MAツール・SFAツールの導入支援から基盤構築・業務プロセス改善まで一貫対応します。Salesforce Partner NavigatorのIntegration/MuleSoft領域で最上位のExpert認定を取得しており、Salesforceを中核に据えたMA導入・活用支援での技術力は国内トップクラスです。人材紹介も提供しており、技術と人材の両面でDXを支援できます。
こんな企業に向いている: Salesforceを活用したMAの本格導入を検討している・CRM/SFAとマーケティング施策を連携させたい中〜大企業
中小企業・スタートアップ向け企業3選
株式会社LIG
毎年Webデザインアワードを受賞するクリエイティブ品質の高さが武器で、オウンドメディア運営・SEO対策・コンテンツ制作を組み合わせたブランド力向上に定評があります。フィリピン・ベトナムの海外拠点を活用したWeb・アプリ開発により、コストを抑えながら質の高い制作物を求める企業の選択肢になります。
こんな企業に向いている: ブランディングとSEOを同時に強化したい・コストを抑えながら品質にこだわりたい中小企業・スタートアップ
株式会社ベーシック
自社開発のCMS&マーケティングツール「ferret One」を基軸に、BtoBマーケティング全般を支援します。LP制作・メールマーケティング・コンテンツ制作の自動化で工数とコストを削減でき、国内最大級のWebマーケティングメディア「ferret」の運営から得た実践知識も支援に活かされます。
こんな企業に向いている: BtoBのリード獲得体制を整えたい・マーケティングツールの導入と運用支援をセットで受けたい中小〜中堅企業
株式会社インフォバーン
出版事業からスタートした背景を持ち、コンテンツ制作の編集力とデザイン力が強みです。オウンドメディア主体のマーケティング支援・サービスデザイン・人材支援を手がけ、ユーザーニーズを踏まえたサイト設計と質の高いコンテンツ制作を組み合わせた支援を行います。
こんな企業に向いている: コンテンツ品質を重視したブランディングを目指すスタートアップ・クリエイティブな発信で差別化したい企業

デジタルマーケティング支援の費用相場完全ガイド

サービス内容別の費用目安一覧
費用はサービスの種類と自社の規模・フェーズによって大きく変わります。まず全体の相場観を把握し、その上で自社の予算と照らし合わせてください。
| サービス種別 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戦略コンサルティング | 月額10〜100万円以上 | スタートアップ向け簡易型:月10〜20万円、大企業向け包括型:月50万円〜 |
| SEO対策(内部対策のみ) | 月額10〜30万円 | 固定型が主流。成果報酬型は1KW達成時1〜10万円 |
| SEO対策(外部対策込み) | 月額20〜50万円 | 長期的には固定型のほうが総額を抑えやすいケースが多い |
| 広告運用代行 | 広告費の15〜20%が手数料 | 最低手数料あり。広告費100万円なら手数料15〜20万円が目安 |
| コンテンツ制作 | 1記事3〜10万円 | 専門性・文字数・SEO設計の有無によって変動 |
| SNS運用代行 | 月額10〜50万円 | 運用チャネル数・投稿頻度・広告運用の有無により変動 |
| MAツール導入支援 | 初期50〜300万円+月額10〜50万円 | ツール費用は別途発生 |
初期費用と月額費用の構成要素
デジタルマーケティング支援は初期費用と月額費用の両方が発生します。初期費用には、アカウント設定・初期戦略立案・ツール導入・初回コンテンツ制作などが含まれ、合計で10〜50万円が一般的です。大規模プロジェクトでは100万円を超えることもあります。
月額費用は運用管理・レポート作成・定例ミーティング・改善分析などを含みます。年間総額で計算する習慣をつけてください。月額30万円のサービスは年間360万円の投資であり、初期費用30万円を合計すると初年度は390万円になります。
最低契約期間は3〜6ヶ月が一般的です。途中解約が可能でも解約手数料が発生するケースがあるため、契約前に必ず確認してください。成果が出始めた段階で施策を拡大する場合、追加費用が生じることも念頭に置いておきましょう。
成果報酬型と固定報酬型のメリット・デメリット
成果報酬型は、設定した目標を達成した場合のみ費用が発生する体系です。初期投資を抑えたいスタートアップや、初めてデジタルマーケティングに取り組む企業に向いています。一方、成果報酬型は単価が高く設定されるケースが多く、長期的には固定型よりも総額が高くなりがちです。また「何を成果とするか」の定義が曖昧だと後でトラブルになるため、契約時に成果指標を明確に数値で定めることが前提条件です。
固定報酬型は毎月一定額を支払う体系で、費用の予測がしやすく予算管理が容易です。支援企業も短期成果に縛られず中長期の施策を提案しやすいため、SEOやコンテンツマーケティングといった積み上げ型の施策との相性が良いです。成果が出ていない期間も費用は発生し続けるため、定期的な成果評価と契約内容の見直しが重要になります。
実際には、初期フェーズを固定型で基盤を構築し、軌道に乗ってきた段階で一部を成果報酬型に移行するハイブリッド型の契約も増えています。
契約前に必読!失敗パターンと対策

よくある失敗事例3パターン
失敗パターン1:目標設定が曖昧なまま契約する
最も多い失敗です。「売上を上げたい」「認知度を高めたい」だけでは、支援企業も適切な施策を設計できず、成果の判断基準も生まれません。3ヶ月後に「期待した成果が出ていない」と感じても、何が問題だったか特定できない状況に陥ります。
対策は単純で、契約前に具体的なKPIを数値で設定することです。「3ヶ月でWebからの問い合わせを月10件から30件に増やす」「6ヶ月でオーガニック検索流入を50%増やす」という形で、指標・目標値・達成期限の3つを決めてから発注してください。
失敗パターン2:自社の実態を正確に伝えない
見栄を張って実際より大きな予算を伝えたり、社内の協力体制が整っていないのに整っているように話したりすると、実現不可能な施策を提案されます。その結果、途中で予算が足りなくなったり、社内調整が進まずに施策が止まったりします。
初回ヒアリングでは、予算の上限・社内リソースの実態・過去の施策と結果・意思決定プロセスを包み隠さず共有してください。実態を正直に伝えた上で「できること」を提案する支援企業が、長期的に良いパートナーになります。
失敗パターン3:丸投げしてしまう
支援企業に任せきりにすると、施策の質が落ちます。自社商品・サービスの深い理解、顧客インサイトの共有、タイムリーな意思決定は、支援企業だけでは補えません。定例ミーティングへの不参加・情報提供の遅れが積み重なると、施策は形式的なものになっていきます。
定期的なコミュニケーション(週次または隔週の進捗確認、月次の詳細レビュー)を確保し、自社から積極的に情報を提供する姿勢が成果を左右します。
契約前に確認すべき10項目チェックリスト
契約前に以下の10項目を確認してください。
- 成果目標とKPIが数値で明示されているか(指標・目標値・達成期限の3点セット)
- サービスの対応範囲と除外事項が明確か(どこから追加費用になるか)
- 担当者の経験年数と実際に関わるチーム構成(可能なら事前に担当者と面談)
- レポーティングの頻度・内容・ミーティングの設定サイクル
- 最低契約期間と途中解約の条件・費用
- 初期費用・月額費用の内訳と隠れたコストの有無
- 使用ツール・プラットフォームのライセンス費用の負担先
- 成果が出なかった場合の対応方針(改善策の提案義務、契約見直しの可否)
- 競合他社との同時契約の有無(利益相反リスク)
- 制作物・データの知的財産権の帰属(契約終了後も自社で使えるか)
トラブル回避のための契約条項のポイント
契約書で特に確認すべき点を押さえておきます。
業務範囲は具体的に記載してもらうことが前提です。「デジタルマーケティング支援」という抽象的な表現ではなく、「月4本のSEO記事制作・各記事3,000字以上・キーワード選定を含む」という形で成果物の要件を明記します。
成果の定義と測定方法も契約書に落とします。何をもって成果とするか、どのツールで測定するか、目標未達の場合の対応をあらかじめ合意しておくことでトラブルを防げます。
機密保持条項も欠かせません。顧客データ・事業戦略の取り扱い方法、第三者への開示制限、契約終了後のデータ削除について明記します。解除条項については、解約可能な条件・手続き・必要な通知期間(一般的に1〜3ヶ月前の書面通知)を確認し、遅延損害金や残期間費用の清算ルールも把握しておきます。
成功企業に学ぶ効果的な活用法

BtoB企業の成功事例
人材派遣・人材紹介を展開する株式会社ウィルオブ・ワークは、テレアポ中心のアウトバウンド営業からオウンドメディア施策へと軸足を移しました。当初はPV数を追うだけの施策に陥っていましたが、デジタルマーケティング企業の支援を受けて「リード獲得数」を成果指標として明確に定義し直しました。
戦略転換後、成果につながらないコンテンツを一斉に削除し、本質的な価値提供に集中した結果、月4〜5件だった問い合わせは2021年から翌年にかけて月130件前後まで増加し、26〜32倍の成長を達成しました。オウンドメディア経由で数億円を超える売上を生み出しています。
この事例から見えるのは二点です。表面的な指標ではなく事業成長に直結する指標を設定すること、そして成果につながらないコンテンツを削除する判断を迷わず下すことです。支援企業の専門知識を活かしながら、自社が判断・実行に関与する姿勢が大きな差を生みました。
BtoC企業のROI改善事例
ECサイト運営企業が前年割れの売上を立て直した事例です。まず各施策が売上にどう貢献しているかを可視化する計測基盤を構築し、投資対効果を数値で把握できる状態を作りました。分析の結果、新規ユーザー獲得の強化が売上回復の鍵であることが判明しました。
SNS広告・リスティング広告の予算配分を見直して成果の高いチャネルに集中させ、従来手をつけていなかったLINE公式アカウントのプッシュ通知を活用して既存顧客の再購入を促進しました。広告クリエイティブのA/Bテストも継続して実施し、最終的に売上は前年比110%まで回復しました。
データに基づいて既存施策を見直し、新チャネルにも踏み込んだ点がポイントです。感覚ではなく数値で判断し、PDCAを高速で回し続けることで確実に改善できることを示しています。
成果を最大化する協業のコツ
定期コミュニケーションの確保が最優先です。 施策開始から3ヶ月間は特に細かな調整が必要になるため、週次または隔週での進捗確認を設定してください。
次に、自社が持つ情報を惜しみなく提供することです。顧客からの問い合わせ内容、営業現場で得たインサイト、商品・サービスの開発背景——支援企業が持ち得ない一次情報こそが、施策の精度を上げます。情報を出し惜しみすると、外部から観察できる範囲での提案しか返ってきません。
意思決定のスピードも成果を左右します。デジタルマーケティングは環境変化が早いため、社内承認プロセスを簡素化し、担当者に一定の裁量を持たせることで施策実行のタイムラグを減らせます。
SEOやコンテンツマーケティングは3〜6ヶ月単位で積み上がる性質の施策です。短期で判断せず、データが蓄積される中で改善を続ける姿勢が必要です。支援期間中に社内にノウハウを蓄積しておくことも忘れないでください。定期的な勉強会の開催や施策ドキュメントの整備を依頼することで、将来的な内製化への道筋が見えてきます。
よくある質問(FAQ)

発注のタイミングはいつがベスト?
次のいずれかに当てはまれば、すぐに動くべき段階です。社内リソースが不足していてマーケティングまで手が回らない、施策を実施しているのに期待した成果が出ていない、新規事業のローンチや新商品の発売など重要なタイミングが迫っている——こうした状況では、専門家に介入してもらうことで意思決定の質が上がります。
逆に「何から始めればいいか全くわからない」という段階も、発注を検討すべきサインです。市場分析と戦略立案から支援してもらうことで、無駄な先行投資を防げます。予算が確保できたら早めに相談を開始し、準備期間を設けた上で施策を開始することが成果への最短ルートです。
複数社への相見積もりは必要?
3〜5社への相見積もりを強く推奨します。複数社を比較することで費用の相場感が掴め、提案内容の質の違いも把握できます。依頼する際はすべての企業に同じ条件を提示してください。自社の現状・目標・予算・期待する成果を統一した情報として伝えることで、提案内容を公平に比較できます。
単純に価格だけで判断しないことが重要です。提案の具体性・過去実績・担当者との相性・サポート体制を総合的に評価してください。評価シートを作成し、項目ごとに点数をつけると判断が明確になります。
成果が出るまでどのくらいかかる?
施策の種類によって期間は大きく異なります。リスティング広告やSNS広告は開始から1ヶ月程度で初期成果が見え始め、最適化には2〜3ヶ月かかります。SEO対策は4〜6ヶ月で検索順位の上昇が始まり、流入が本格的に増えるまでに6ヶ月〜1年が目安です。コンテンツマーケティングも同様に、半年〜1年の中長期的な積み上げが前提になります。
短期間で成果を求めるなら運用型広告から始め、中長期の集客基盤を作るならSEO・コンテンツと組み合わせる設計が現実的です。いずれの施策も、初期データを収集しながらPDCAを回すことが成果につながります。
契約期間はどう設定すべき?
最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月〜1年の契約期間を設定してください。デジタルマーケティングは効果が出るまでに一定期間が必要で、短期で契約を打ち切ると本来得られたはずの成果を手放すことになります。
初めて支援企業と組む場合は、3ヶ月のトライアル期間で相性を確かめてから本契約に移行する方法も有効です。長期契約には費用面での優遇が付くケースが多く、支援企業も中長期の視点で戦略を立てやすくなります。ただし、成果が出ない場合や方向性を変えたい場合に備えて、柔軟な見直し条項と解約条項を契約書に盛り込んでください。
途中解約は可能?
多くの場合、最低契約期間内の解約には制限があります。残期間分の費用を請求されるか、解約手数料が発生するケースが一般的です。最低契約期間(3〜6ヶ月が多い)を過ぎれば、1〜3ヶ月前の書面通知によって解約できる企業がほとんどです。
進行中のプロジェクトがある場合は完了まで継続が求められることもあります。初期費用は原則返金されません。トラブルを避けるには、解約条件と費用の清算方法を契約前に詳細に確認し、契約書に明記してもらうことが唯一の確実な対策です。
まとめ:自社に最適なデジタルマーケティング企業の選び方

企業選びの3ステップ
ステップ1:自社の課題と目標を数値で定義する
現在の課題(流入が少ない、リードが取れない、広告CPAが高いなど)を整理し、「3ヶ月後にどの数値をどの程度改善したいか」を具体化します。予算規模・社内リソース・意思決定プロセスも同時に把握しておきます。ここが曖昧なまま動き出すと、すべての判断が後手に回ります。
ステップ2:目標と業界に合った企業を3〜5社に絞り、比較する
本記事の比較表と各社の紹介を参考に、自社の目標・業界に強みを持つ企業をリストアップします。各社に問い合わせ、提案内容・過去実績・費用・サポート体制を評価シートで比較してください。担当者と実際に面談し、相性とコミュニケーションの質を確かめることが、最終判断で最も重要なインプットになります。
ステップ3:契約時にチェックリストを使い、KPIと条件を明文化する
本記事の「契約前に確認すべき10項目チェックリスト」を活用し、KPI・業務範囲・費用内訳・解約条件・知的財産権の帰属を契約書に明記してもらいます。キックオフミーティングで目標と役割分担を再確認し、コミュニケーションの頻度と方法を具体的に決めることで、立ち上がりのロスを最小化できます。
長期的な成功のためのパートナーシップ構築
デジタルマーケティングで継続的な成果を上げるには、発注者と受注者の関係ではなく、共通の目標に向かって動くパートナーとして支援企業と向き合うことが必要です。定期ミーティングでは成果確認だけでなく、市場動向や競合の動きを共有し、戦略を柔軟に調整していく姿勢が重要です。
支援期間中に社内にノウハウを蓄積しておくことも欠かせません。施策ドキュメントの整備・定期的な勉強会の開催を依頼しておくことで、将来的な内製化の基盤が生まれます。完全な内製化が難しい場合でも、基本的な知識を持つことで支援企業とのディスカッションが深まり、施策の質が向上します。
信頼関係の構築が長期的なパートナーシップの根幹です。約束した情報提供を確実に行い、決定事項は迅速に実行し、問題が生じたら早期に共有する——この誠実なコミュニケーションが積み重なることで、リスクを取った挑戦的な施策も実施しやすくなります。
次のアクションプラン
- 自社の課題・現状マーケ施策・予算・目標をドキュメントにまとめる
- 本記事の比較表から自社の目標・業界に合いそうな企業を3〜5社選定する
- 各社の公式サイトで事例と実績を確認し、問い合わせを行う(多くの企業が無料の初回相談を提供しています)
- 提案を受けた後、評価シートで比較し最終選定する
- 契約時に「10項目チェックリスト」で条件を確認・明文化する
デジタルマーケティングは継続的な改善の積み重ねで成果が出る領域です。最初から完璧な状態を目指す必要はありません。小さく始め、データを蓄積しながら投資規模を拡大していく進め方が、最終的に最も大きなROIをもたらします。
自社に最適なパートナー企業選びについて相談したい場合は、debono.jpにお気軽にご相談ください。貴社の課題・目標をヒアリングした上で、最適な進め方をご提案します。

※本記事の企業情報は2025年10月時点の公開情報に基づいています。各社のサービス内容・費用・体制は変更される場合があります。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

















